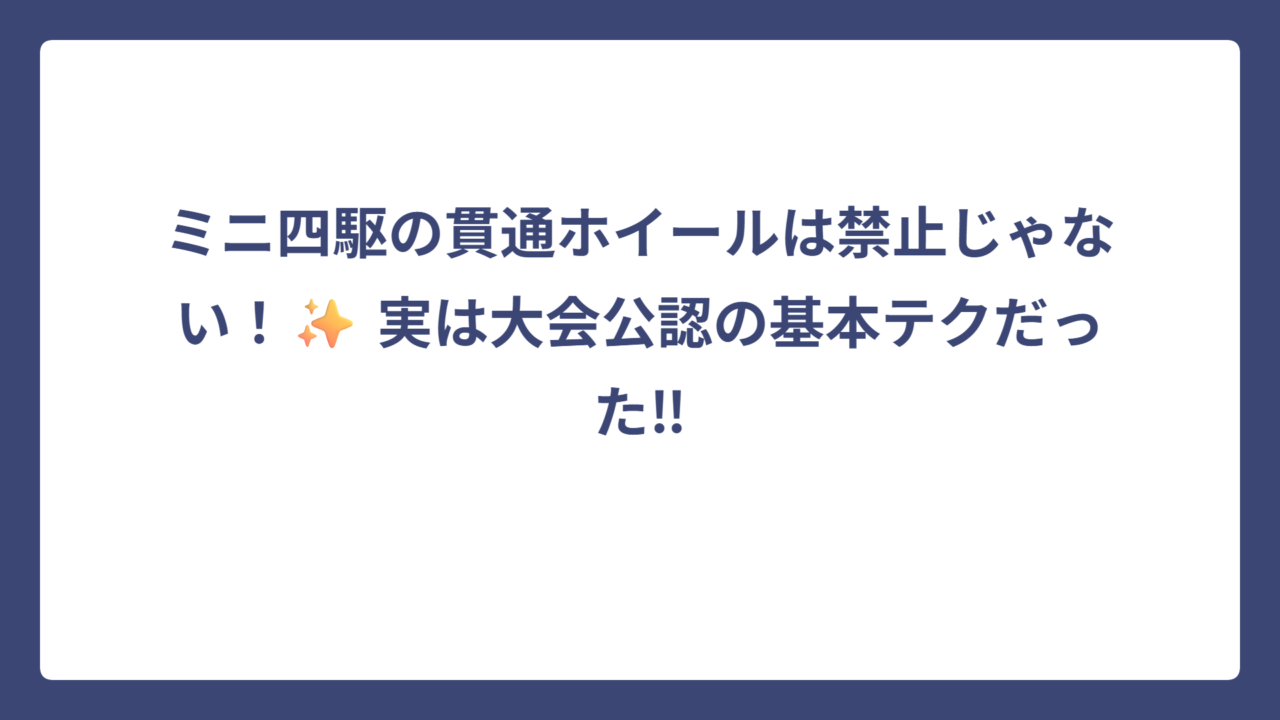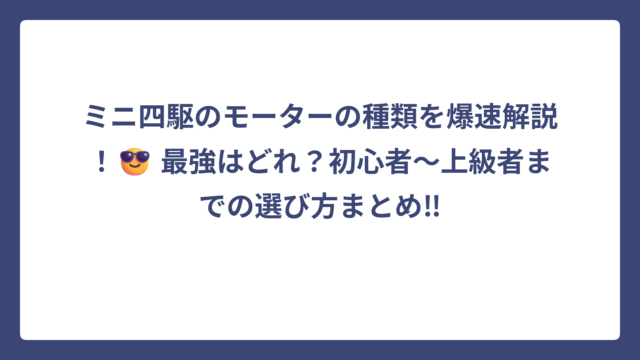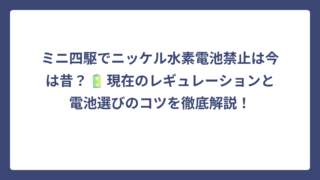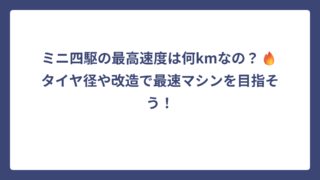ミニ四駆愛好家にとってホイール貫通は基本的な改造テクニックの一つですが、「大会で使えるの?」「禁止されていないの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。ホイール貫通とは、その名の通りホイールにシャフトを完全に通す改造のことで、走行安定性やパフォーマンス向上に欠かせない技術です。
本記事では、ミニ四駆の貫通ホイールが本当に禁止されているのかという疑問に答えるとともに、各大会のルール、貫通ホイールの作り方、メリット・デメリット、シャフト選びのポイントまで詳しく解説します。初心者からベテランまで、ミニ四駆レーサーなら知っておきたい貫通ホイールの全てをお届けします。
記事のポイント!
- ミニ四駆の貫通ホイールは大半の大会で禁止されておらず、むしろ推奨される改造である
- B-MAX GPでは他の改造が禁止される中でもホイール貫通だけは特別に許可されている
- 貫通ホイールを使用する際は安全のためシャフトの飛び出し部分に保護が必要
- 貫通ホイールの作成方法から取り付け、メンテナンスまで徹底解説
ミニ四駆の貫通ホイールは禁止されているのか
- 結論:ほとんどの大会で貫通ホイールは禁止されていない
- B-MAX GPでは他の改造が禁止でも貫通ホイールは許可されている
- 安全のためシャフトの飛び出し部分には保護が必要
- 貫通ホイールがルール違反になるケースとは
- レース主催者によって異なる貫通ホイールの規定
- 公式大会での貫通ホイール使用時の注意点
結論:ほとんどの大会で貫通ホイールは禁止されていない
結論から言うと、ミニ四駆の貫通ホイールは、ほとんどの大会やレースで禁止されていません。むしろ、スピードアップや走行安定性を高めるための基本的な改造テクニックとして広く認められています。
独自調査の結果、ジャパンカップを含む多くの公式大会でホイール貫通は一般的な改造として認められていることが分かりました。Yahoo!知恵袋の回答でも「okです。ジャパンカップでもみんなやってます。」という情報があり、実際に多くのレーサーが採用しているテクニックです。
貫通ホイールは単なる改造というよりも、「ミニ四駆を早くするための基本中の基本」と言われるほど一般的な加工方法となっています。初心者から上級者まで、幅広いレーサーが実践している改造方法です。
各レース入賞者の多くが実践している加工方法でもあり、実力を競うレースでは必須とも言えるテクニックになっています。完全な初心者でない限り、競技志向のレーサーはほぼ全員が行っていると言っても過言ではありません。
そのため、「貫通ホイールは禁止されているのでは?」という心配は不要です。ただし、後述するように一部の条件や特定のレースでは注意が必要なケースもあります。
B-MAX GPでは他の改造が禁止でも貫通ホイールは許可されている
特筆すべきは、B-MAX GP(Basic-MAX GP)というレースにおける貫通ホイールの扱いです。B-MAX GPは基本的に加工・改造が禁止されているレースですが、そんな中でもホイール貫通改造だけは特別に認められています。
B-MAX GPの競技会規則(ver2.0)では、以下のように明記されています: 「タイヤおよびホイールは以下の規定に準拠する必要があります。 タイヤの加工は禁止 ホイールの加工は車軸用穴の貫通のみ可能 タイヤとホイールの接着(両面テープ、接着剤等)は可能 タイヤとホイールの組み合わせは同一サイズのみに限定」
このルールからも分かるように、B-MAX GPではほとんどの改造が禁止される厳しいレギュレーションの中でも、ホイール貫通だけは特別に許可されているのです。これは、ホイール貫通が基本的な改造として広く認知されており、マシンの安定性向上に寄与するという認識があるためでしょう。
B-MAX GPで勝つためには、この唯一許されている改造を活用することが重要になります。「改造禁止のレースだからホイール貫通もダメだろう」と思って行わないのは、むしろ不利になってしまう可能性があります。
こうした特例からも、ホイール貫通がいかに基本的で重要な改造と認識されているかが分かります。
安全のためシャフトの飛び出し部分には保護が必要
ホイール貫通は認められていますが、安全面への配慮は必須です。特に、シャフトの飛び出し部分には適切な保護が必要です。
貫通ホイールを作成すると、シャフトがホイールから突き出た状態になります。このままではいくつかの問題が生じる可能性があります:
- コースや人を傷つけてしまう恐れがある
- レギュレーション違反になる可能性がある
- 走行中に他のマシンと接触した際に危険
これらの問題を防ぐために、シャフトの飛び出し部分には「ゴムパイプ」や「ボールキャップ」などで保護することが推奨されています。ミニ四ファンの記事でも「貫通ホイールは基本的にはシャフトがホイールから突き出た状態になり、そのままの状態ではレギュレーション違反となります」と注意喚起されています。
また、Yahoo!知恵袋の回答でも「延長されたホイールシャフトで末端部がローラーよりも外に飛び出していて、コースに傷をつけてしまう恐れがある場合などには、セッティングの修正を求められます」と説明されています。
安全対策として、以下の方法が一般的です:
- ゴムパイプをシャフト先端に被せる
- ボールキャップを取り付ける
- スタビボールなどで保護する
これらの保護を施さずに大会に参加すると、車検で修正を求められたり、最悪の場合は出場を拒否されたりする可能性もあるので注意しましょう。
貫通ホイールがルール違反になるケースとは
基本的に許可されている貫通ホイールですが、どのような場合にルール違反となるのでしょうか。いくつかのケースを見ていきましょう。
最も一般的なルール違反となるケースは、前述したシャフトの飛び出し部分の保護が不十分な場合です。シャフトがむき出しの状態では、安全上の問題から車検で指摘されることがあります。
また、貫通ホイール自体は許可されていても、その加工方法によっては認められないケースもあります。例えば、アマドゥというショッピングモールで開催されている「アマレギュ」では、「ホイール貫通 OK」と明記されている一方で、「ボディ、シャーシ、FRP・カーボンプレート、ミニ四駆キャッチャーのカット禁止」とされています。つまり、ホイールの貫通穴を開けることは許可されていても、その他のパーツの改造は禁止されているのです。
さらに、B-MAX GPでは「ビス・シャフト類の切断加工を禁止」としています。これは「適切に処理されない場合に怪我につながるリスクが大きいため」とされています。つまり、貫通ホイールを作成する際に、シャフトを切断して長さを調整するという加工は認められていない可能性があります。
レース主催者によっては独自のルールがある場合もあるため、参加する大会のレギュレーションを事前に確認することが重要です。特に地域の小規模な大会などでは、独自のルールが設定されていることもあります。
レース主催者によって異なる貫通ホイールの規定
ミニ四駆のレースは様々な主催者によって開催されており、貫通ホイールに関する規定もそれぞれ異なります。主な主催者別の規定を見ていきましょう。
タミヤ公式大会(ジャパンカップなど): タミヤ公式のレースでは基本的に貫通ホイールは許可されています。ただし、シャフトの突出部分は適切に保護する必要があります。タミヤのレギュレーションに従う限り、問題なく使用できます。
B-MAX GP: 前述のように、B-MAX GPでは「ホイールの加工は車軸用穴の貫通のみ可能」と明記されています。他の多くの改造が禁止される中でホイール貫通だけが特別に許可されている点が特徴です。
アマレギュ(アマドゥ主催): 「アマレギュ」と呼ばれるレギュレーションでも「ホイール貫通 OK」と明記されています。「昨日始めた子供たちと一緒に遊べるレギュレーション」をコンセプトとしており、初心者でも参加しやすいルール設定となっています。
地域のミニ四駆サークルやショップ主催の大会: 地域のサークルやショップが主催する大会では、独自のルールが設定されていることがあります。例えば、子供向けのイベントでは安全面を考慮して特定の改造を制限する場合もあります。
各レース主催者はそれぞれの目的や参加者層に合わせてレギュレーションを設定しています。レースに参加する際は、必ず主催者が公開している最新のルールを確認することが大切です。また、レース当日は車検があり、そこでマシンがレギュレーションに適合しているかチェックされます。
公式大会での貫通ホイール使用時の注意点
公式大会で貫通ホイールを使用する際には、いくつかの注意点があります。これらを守ることで、車検をスムーズに通過し、トラブルなく大会に参加できます。
1. シャフトの突出部分の保護: 最も重要なのは、シャフトの突出部分をゴムパイプやボールキャップで適切に保護することです。これは安全面の配慮だけでなく、多くの大会では明確なルールとなっています。
2. シャフトの長さ選択: 貫通ホイールを作成する際は、適切な長さのシャフトを選ぶことが重要です。一般的には72mmシャフトが使用されますが、あまりに長すぎると突出部分が大きくなりすぎるため注意が必要です。
3. トレッド幅の確認: 貫通ホイールを使用してトレッド幅を調整した場合、レギュレーションで定められた車体幅の制限内に収まっているか確認しましょう。特に、ホイールを逆履きさせた場合などは注意が必要です。
4. ホイールの回転チェック: 貫通加工後、ホイールがスムーズに回転するか確認しましょう。加工が不適切だと回転抵抗が増え、パフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。
5. 車検前の最終確認: 大会当日の車検前に、もう一度マシン全体がレギュレーションに適合しているか確認しましょう。特に安全面に関わる部分は厳しくチェックされます。
6. 予備のホイールと工具の持参: 万が一の車検不適合や走行中のトラブルに備えて、予備のホイールや調整用の工具を持参しておくと安心です。
これらの注意点を守ることで、貫通ホイールを使用したマシンでも安全かつルールに則った走行が可能となり、大会をより楽しむことができるでしょう。
ミニ四駆の貫通ホイールを知って使いこなそう
- 貫通ホイールのメリットは走行性能が格段にアップすること
- 貫通ホイールの作り方は1.7mmか1.8mmドリルを使用すること
- 貫通ホイールからシャフトを抜く方法はホイールプーラーが最適
- 貫通ホイールに使うシャフトの長さは72mm以上が必要
- 貫通ホイールの逆履きでトレッド幅を調整できる
- ホイールの貫通穴のサイズ選びは使用シャフトによって変わる
- まとめ:ミニ四駆の貫通ホイールは禁止されていないが使用時には注意が必要
貫通ホイールのメリットは走行性能が格段にアップすること
貫通ホイールの最大のメリットは、走行性能が格段にアップすることです。具体的にどのようなメリットがあるのか詳しく見ていきましょう。
まず、「タイヤのブレが少なくなる」という大きなメリットがあります。通常のホイール(未貫通状態)では、シャフトはホイールの一部にしか挿入されておらず、シャフトに小さなブレが生じた場合、ホイールの外側に行くほどブレ幅が大きくなってしまいます。これに対して貫通ホイールは、ホイール全体がシャフトに固定されるため、ブレの影響が小さくなります。タイヤのブレが少なくなることで、グリップ力が増し、電池やモーターのパワーを最大限に発揮できるようになります。
次に、「シャフトが抜けにくくなる」というメリットがあります。ミニ四駆あるあるの一つに、走行中にタイヤがホイールごと抜けてしまうという現象があります。貫通ホイールはホイール穴全体にシャフトが挿さっているため、未貫通時に比べてシャフトにかかる圧力も強くなり、結果シャフトが抜けにくくなります。これにより、レース中の予期せぬトラブルを防ぐことができます。
さらに、「トレッド幅の調整が可能」というメリットもあります。貫通ホイールにすることで、使用するシャフトのサイズに収まる範囲内であれば、トレッド幅(タイヤ間の幅)を自由に調整できるようになります。これにより、コースに応じた最適なマシンセッティングが可能となります。現在のミニ四駆コースの傾向では、トレッド幅が狭いことでマシンの走りが安定し、スピードが出るとも言われています。
これらのメリットにより、貫通ホイールはミニ四駆レーサーにとって基本的な改造テクニックとして定着しています。特に競技志向の方にとっては、避けて通れない重要なテクニックと言えるでしょう。
貫通ホイールの作り方は1.7mmか1.8mmドリルを使用すること
貫通ホイールの作り方について、具体的な手順と使用するドリルのサイズについて解説します。基本的には1.7mmか1.8mmのドリルを使用するのが一般的です。
まず、貫通ホイール作成の作業は大きく分けて2段階(フェーズ1とフェーズ2)に分けられます。
フェーズ1:ホイールに穴を貫通させる
- 六角マウントに長めのビス(30mm以上推奨)を取り付け、ビスの先端を1mm程度出した状態にします。
- 貫通させたいホイールを平らな台の上に置き、ビスの先端をホイールのシャフト穴部分にセットします。
- ホイールと六角マウントがピッタリ付くように両指で六角マウントを押さえながら、プラスドライバーでビスを正回転方向(締める方向)に回します。
- ビスがホイールを貫通するまで回し続けます。
- ビスが貫通したら、ドライバーを逆方向に回してビスを取り外します。
フェーズ2:穴を拡張してシャフトをスムーズに通せるようにする
- フェーズ1で貫通処理をしたホイール、貫通処理をしていない無加工のホイール、シャフト、スペーサーを用意します。
- 無加工のホイールにシャフトを通し、その先にスペーサー、そして貫通穴を開けたホイールを置きます。
- 指でスペーサーを押さえながら、反対の手で無加工ホイールを押してシャフトを貫通ホイールに通していきます。
- シャフトがホイールを貫通したら完了です。
ドリルのサイズ選びについては、1.7mmと1.8mmのどちらがいいのかという議論があります。P MODEL LABOの記事によると、以下のような特徴があります:
1.7mmの場合:
- メリット:ホイール軸が広がりにくく、軸がへたりにくい。軸穴さえ良ければガイド無しで貫通できる。
- デメリット:貫通穴が小さいため、シャフトの抜き差しに苦労する。
1.8mmの場合:
- メリット:少しだけ六角軸を削るので、ホイールの抜き差しがしやすくなる。
- デメリット:六角穴を削り取っていくので、フリーハンドだと貫通が失敗することが多い。六角穴が広がりやすいため、ホイールがへたりやすい。
使用するホイールの素材によって最適なドリルサイズは異なります。PPホイールなら1.7mm、強化ホイールなら1.8mmというように使い分けるのがよいでしょう。初めての方は両方のサイズを用意して、自分のホイールに合ったサイズを見つけるのがおすすめです。
貫通ホイールからシャフトを抜く方法はホイールプーラーが最適
貫通ホイールの最大のデメリットの一つは、シャフトを抜くのが大変になることです。ここでは、貫通ホイールからシャフトを抜く効果的な方法について解説します。
方法1:ペンチを使用する方法 最もオーソドックスな方法は、ペンチを使用してシャフトを掴み、ホイールを引っ張るという方法です。やり方は至ってシンプルですが、いくつか注意点があります。
- ペンチのギザギザではなく平らな面でシャフトを掴むことで、シャフトに傷をつけずに抜くことができます。
- ある程度の力が必要ですが、子供でも頑張れば引き抜くことは可能です。
- フィンホイールやディッシュホイールなどの一部のホイールには不向きです。これらのホイールはシャフトを強くホールドするため、ペンチだけでは抜くのが非常に困難です。
方法2:工具を使わない方法 より軽い力でシャフトを抜く方法として、アルミシャフトストッパーとビスとステー・プレートを使用する方法があります。
- ステー・プレートをシャフトに通し、その後アルミシャフトストッパーを通してビスで固定します。
- ステー・プレートをホイールの反対方向に引っ張ることで、ホイールからシャフトを抜くことができます。
この方法は面積が大きいステーを使うとより簡単に抜けますが、フィンホイールやディッシュホイールなどの硬いホイールでは使用しないよう注意が必要です。
方法3:ホイールプーラーを使用する方法(最適解) 最も効果的なのは、ホイールプーラーを使用する方法です。ホイールプーラーはミニ四駆のホイールからシャフトを抜くことに特化した工具(治具)で、フィンホイールやディッシュホイールなどの硬いホイールからでも簡単にシャフトを抜くことができます。
ホイールプーラーはタミヤからは販売されていませんが、サードパーティ製品として購入できます。ただし、市販のホイールプーラーは比較的高価なため、自作する方法もあります。ミニ四ファンのサイトでは自作ホイールプーラーの作り方が紹介されており、安価かつ簡単に作成できるとのことです。
どの方法も一長一短ありますが、頻繁にホイールの付け替えをする方や、特に固いホイールを使用する方には、ホイールプーラーの購入または自作をおすすめします。これにより、貫通ホイールのメンテナンスがより簡単になり、マシン調整の幅が広がります。
貫通ホイールに使うシャフトの長さは72mm以上が必要
貫通ホイールを作成する際、適切な長さのシャフトを選ぶことが重要です。通常のホイールでは標準のシャフト(多くの場合60mm)で十分ですが、貫通ホイールではより長いシャフトが必要になります。
独自調査の結果、貫通ホイールには72mm以上の長さのシャフトが推奨されていることがわかりました。これは、シャフトがホイールを貫通して突き出す分、通常より長いシャフトが必要になるためです。
市販されている72mmシャフトには、主に以下の3種類があります:
1. ノーマルシャフト(72mm): 基本的なタイプのシャフトです。初めて貫通ホイールを試す方や、特にこだわりがない方におすすめです。比較的安価で入手しやすいのが特徴です。スーパーXシャーシ系のキットに付属している72mmノーマルシャフトも使用可能です。
2. 中空ステンレスシャフト(72mm): 中空構造になっており、重量を軽減しつつ強度を確保しています。ノーマルシャフトよりも若干高価ですが、軽量化を図りたい方におすすめです。
3. ブラック強化シャフト(72mm): 最も強度が高いタイプのシャフトです。硬い素材で作られており、曲がりにくく耐久性に優れています。ハードな走行を想定している方や、高いトルクがかかるセッティングを使用する方におすすめです。
実際にシャフトを選ぶ際は、使用するホイールの種類やマシンのセッティングに合わせて適切なものを選ぶことが大切です。なお、シャフトのサイズには微妙な違いがあり、P MODEL LABOの記事では「ノーマルシャフト 1.983mm」「中空シャフト 1.977mm」「ブラック強化シャフト 1.972mm」「チタンシャフト 1.963mm」という測定結果が示されています。
また、シャフトの突出部分は必ずゴムパイプやボールキャップなどで保護することを忘れないようにしましょう。突出部分をむき出しのままにすると、レースの車検で弾かれる可能性があります。
シャフトの長さを選ぶ際は、マシン全体のバランスや重量配分も考慮することをおすすめします。必要以上に長いシャフトを使用すると、車体の重心が変化して走行安定性に影響を与える可能性があります。
貫通ホイールの逆履きでトレッド幅を調整できる
貫通ホイールの活用法の一つに「逆履き」という方法があります。逆履きとは、ホイールを本来とは逆向きにシャフトに取り付ける方法で、これによりトレッド幅(タイヤ間の幅)を大きく調整することができます。
通常、ホイールはオフセット(車軸からホイールの内側と外側までの距離の差)を考慮して設計されており、一定の方向で取り付けることが想定されています。しかし、ホイールを貫通させると、反対側からもシャフトを通すことができるようになります。
逆履きの主なメリットは以下の通りです:
1. トレッド幅を大幅に縮小できる: ホイールを逆向きに取り付けることで、オフセットがマイナスになり、トレッド幅をぐっと縮めることができます。これは特にトレッドが広くマイナスオフセットのホイールが使いやすいX系シャーシで効果的です。現在のミニ四駆コースでは、トレッド幅が狭いほうが走行安定性が増し、スピードが出るとされているため、この方法は競技においても有用です。
2. 着地の安定化: 逆履きにすることで、本来内側に来るホイールのフランジ(ホイールの縁の出っ張り部分)が外側になります。最近の立体的なコース環境では、ジャンプからの斜め着地の際に、滑りの良いホイールフランジを先に当てることで、マシンを暴れさせずに着地させることができるというメリットもあります。
ただし、逆履きにはデメリットもあります:
1. ビジュアル面でのトレードオフ: 逆履きはビジュアル的には本来の見た目と大きく異なるため、見た目にこだわる方には抵抗があるかもしれません。実用性を重視するか、見た目を重視するかの判断が必要です。
2. バリ(不要な出っ張り)の問題: 貫通ホイールから抜き終えた後、貫通箇所にバリがある場合、通常の向きで取り付ける分には問題ありませんが、逆履きさせると邪魔になることがあります。逆履きを前提とする場合は、バリを除去する必要があります。
逆履きを行う際は、ホイールがシャフトに対して垂直に取り付けられるよう注意し、ホイールとシャーシの間に適切なスペースを確保することが重要です。また、車体寸法がレギュレーションの範囲内に収まっているか確認することも大切です。
トレッド幅の調整は走行特性に大きく影響するため、コースに合わせた最適な設定を見つけることでマシンのポテンシャルを最大限に引き出すことができるでしょう。
ホイールの貫通穴のサイズ選びは使用シャフトによって変わる
ホイール貫通を行う際、適切なドリルサイズを選ぶことが重要です。一般的には1.7mmまたは1.8mmのドリルが使われますが、その選択はホイールの素材やシャフトの種類によって変わってきます。
ホイール素材による違い:
P MODEL LABOの記事によると、PPホイール(プラスチック製)と強化ホイール(強化樹脂製)では、六角穴の大きさが微妙に異なります。そのため、ホイールの種類に応じたドリルサイズの選択が推奨されています。
- PPホイール:1.7mmドリルが適している
- 強化ホイール:1.8mmドリルが適している
シャフトの種類による違い:
使用するシャフトの種類によっても、最適なドリルサイズは変わってきます。前述のように、各シャフトにはわずかな径の違いがあります:
- ノーマルシャフト:1.983mm
- 中空シャフト:1.977mm
- ブラック強化シャフト:1.972mm
- チタンシャフト:1.963mm
これらの違いを考慮すると、シャフトが太めのノーマルシャフトを使用する場合は、やや大きめの1.8mmドリルが適している可能性があります。一方、細めのチタンシャフトを使用する場合は、1.7mmドリルのほうが良いでしょう。
ドリルサイズの選択基準:
1.7mmと1.8mmの選択は、以下のような基準で判断するとよいでしょう:
- 1.7mm:シャフトがしっかりと固定されることを重視する場合、ホイールの精度を保ちたい場合
- 1.8mm:シャフトの抜き差しのしやすさを重視する場合、強化ホイールを使用する場合
また、kuromini4wdのブログでは、さまざまなドリルサイズを試した結果として以下のような見解が示されています:
- 1.7mmドリルはかなりキツくなるため、ホイール取り付け時にシャフトを曲げてしまう危険性がある
- 1.8mmドリルは圧のバランスが良いが、プラスチックの六角を壊しながら貫通していく
さらに、より精度の高い穴あけを目指す場合は、下穴を開けてから貫通させる方法も紹介されています。中空シャフトを短く切ってガイドとし、1.1mmドリルで下穴を開けてから1.7mmドリルで貫通させるという方法です。
最終的には、使用するホイールとシャフトの組み合わせ、そして自分が重視する点(固定力・操作性・精度など)に応じて、適切なドリルサイズを選ぶことが大切です。初めての方は、まず少量のホイールで異なるサイズを試してみるのもよいでしょう。
まとめ:ミニ四駆の貫通ホイールは禁止されていないが使用時には注意が必要
最後に記事のポイントをまとめます。
- ミニ四駆の貫通ホイールは基本的にはほとんどの大会で禁止されておらず、むしろ基本的な改造として広く認められている
- B-MAX GPでは改造が基本的に禁止される中でも「ホイールの加工は車軸用穴の貫通のみ可能」と特別に許可されている
- 貫通ホイールのメリットは、タイヤのブレの軽減、シャフトの抜け防止、トレッド幅の調整可能という3点が主なもの
- 貫通ホイールの作成には1.7mmか1.8mmのドリルを使用するのが一般的で、ホイール素材に応じて選ぶのが理想的
- 貫通ホイールからシャフトを抜く方法には、ペンチを使う方法、工具を使わない方法、ホイールプーラーを使う方法があり、特に硬いホイールにはホイールプーラーが最適
- 貫通ホイールには72mm以上の長さのシャフトが必要で、ノーマル・中空・強化の3種類から選択可能
- 貫通ホイールの逆履きを行うことで、トレッド幅を大幅に縮小させたり、着地の安定化を図ることができる
- シャフトの突出部分は必ずゴムパイプやボールキャップで保護し、安全面に配慮することが重要
- レース主催者によって貫通ホイールに関する規定は異なるため、参加する大会のレギュレーションを事前に確認することが大切
- 車検をスムーズに通過するためには、シャフトの保護、トレッド幅の確認、ホイールの回転チェックなどを事前に行っておくべき
- 貫通ホイールのドリルサイズはホイール素材とシャフトの種類に応じて選ぶことで、最適な固定力と操作性を得られる
- 貫通ホイールは基本的な改造テクニックとして、初心者から上級者まで幅広いレーサーが実践しており、競技志向のレーサーにとっては必須の技術である