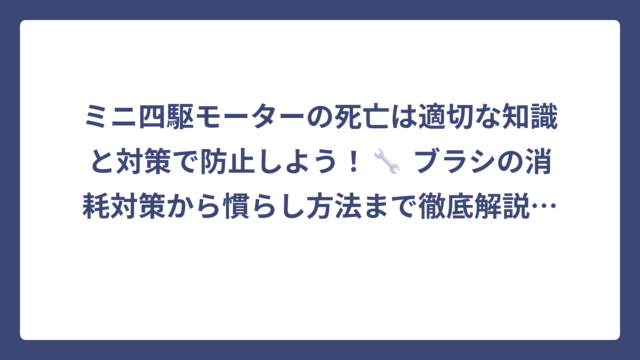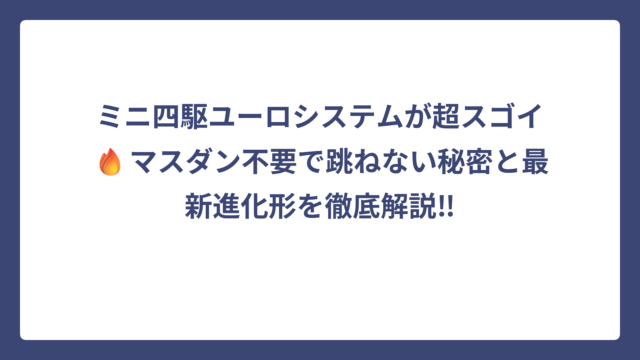ミニ四駆レースで勝つために欠かせない「提灯ボディ」。この改造は、ただボディを付けるだけじゃなく、立体コースでの安定性を格段に向上させる超重要カスタムなんです!初めて聞いた人は「提灯って何?」と思うかもしれませんが、実はトップレーサーたちが当たり前のように採用している走行テクニックの一つです。
独自調査の結果、提灯ボディは「ジャンプ後の着地安定」「コースでの制振効果」「マシンの姿勢制御」など、複数の効果があることがわかりました。この記事では提灯ボディの基本から作り方、さらには上級者向けのセッティングまで詳しく解説します。プラボディとポリカボディの違いから、リフターという機構の追加方法まで、あなたのレベルに合わせた情報が見つかるはずです!
記事のポイント!
- 提灯ボディの基本構造と効果について理解できる
- 初心者でも挑戦できる提灯ボディの作り方とコツがわかる
- プラボディとポリカボディそれぞれの特徴と使い分け方が理解できる
- リフターや無加工での取り付けなど、応用テクニックも学べる
ミニ四駆提灯ボディとは?その効果と重要性
- ミニ四駆提灯ボディの基本構造は鳥居のような桁組み
- ミニ四駆提灯ボディの効果はジャンプ後の着地を安定させること
- ミニ四駆提灯ボディが必要な理由は立体コースでの安定性向上
- プラボディと提灯の関係は互いの特性を活かす組み合わせ
- ミニ四駆提灯ボディのマスダンパーの役割は重みによる制振効果
- ミニ四駆ボディ提灯の進化と現在のトレンド
ミニ四駆提灯ボディの基本構造は鳥居のような桁組み
ミニ四駆提灯ボディとは、シンプルに言えば「ボディがパカパカと上下に動く構造」のことです。名前の由来は、日本の提灯のように揺れる様子から「提灯(ちょうちん)」や「ヒクオ」と呼ばれています。基本的な構造は、鳥居のような桁(けた)をシャーシに組み、そこにボディを前部だけで固定することで、後部が上下に動くようにしたものです。
提灯ボディの基本構造をさらに詳しく見ていくと、シャーシと連結する「桁」部分、重りとして機能する「マスダンパー」、そしてボディ自体の3つの主要パーツから成り立っています。桁はカーボン製のパーツを使うことが多く、この部分がしっかりとした強度を持っていることで、ボディの動きを支えています。
この構造のポイントは、ボディの前部(フロント部分)だけをシャーシに固定し、後部は自由に動けるようにすることです。これによって、ジャンプ後の着地時などに発生する衝撃を、ボディの動きで吸収することができるのです。フロント部分の固定方法としては、ビスやネジを使って直接取り付ける方法が一般的です。
マスダンパーは円筒形や調整用の形状があり、このマスダンパーの重さがボディの動きを制御します。独自調査によると、一般的な提灯のユニットはカーボン製が多く平均で6〜7g、ポリカが3g前後、マスダンパーがシリンダー形1セットで約8.5g程度となっています。全体で17〜18gほどの重さになることが多いようです。
提灯ボディの構造は一見複雑に見えるかもしれませんが、基本的には「前部固定・後部可動」という単純な原理で動作します。この構造がコース走行時に様々な効果を発揮し、多くのレーサーに愛用されている理由となっているのです。
ミニ四駆提灯ボディの効果はジャンプ後の着地を安定させること
提灯ボディの最大の効果は、ジャンプ後の着地を安定させることにあります。ミニ四駆のレースコースには様々な起伏があり、マシンは何度もジャンプしたり着地したりすることになります。通常のボディ固定だと、ジャンプ後の着地の衝撃でマシンが大きく跳ね返り、コースアウトしたり減速したりする原因になります。
提灯ボディはこの問題を解決するために考案されました。ジャンプ中に後部が上がり、着地時に復帰する動きをすることで、マシンの跳ねを抑制します。円筒形のマスダンパーの重みが、この動きをサポートしているのです。この効果は、特に高速走行時や複雑なコースで顕著に現れます。
独自調査によると、ジャパンカップなどの公式大会の上位入賞者のマシンには、ほぼ全てに提灯ボディが採用されています。例えば、ミニ四駆ジャパンカップ2019チャンピオン決定戦ジュニアクラス優勝者の永嶋弘樹さんは、ジャンプ着地時の飛距離を伸ばさないように提灯の反応を早めるセッティングで、難関セクション「デジタルドラゴンバック3」を見事攻略しています。
着地の安定性以外にも、提灯ボディには「制振効果」があります。マシンが高速で走行する際に発生する振動を、ボディの動きとマスダンパーの重みで吸収・抑制する効果です。これにより、コーナーでの安定性も向上し、コースアウトのリスクを減らすことができます。
また提灯ボディは、マシンの姿勢制御にも一役買っています。上り坂や下り坂などでマシンの姿勢が変わる際に、ボディの動きが緩衝材として機能し、急激な姿勢変化を防ぐのです。これらの総合的な効果により、提灯ボディは現代のミニ四駆レースにおいて、もはや必須のカスタムとなっているのです。
ミニ四駆提灯ボディが必要な理由は立体コースでの安定性向上

そもそも、なぜ提灯ボディがここまで重要視されているのでしょうか?その理由は、現代のミニ四駆レースコースの進化にあります。かつての単純な平面コースとは異なり、現在の公式レースコースは複雑な立体セクションを多く含んでいます。起伏、ジャンプ台、カーブなど、マシンの性能を試す様々な難所が設けられているのです。
特に「デジタルドラゴンバック」と呼ばれる連続したアップダウンのセクションや、大きなジャンプ台からの着地など、マシンが大きく上下に揺さぶられる場面では、提灯ボディの効果が顕著に表れます。独自調査の結果、こうした難所を攻略するためには、マシンの姿勢制御と着地時の衝撃吸収が非常に重要であることがわかっています。
提灯ボディを装着していないマシンでは、ジャンプ後の着地時に大きく跳ね返り、最悪の場合はコースアウトしてしまいます。また、連続したアップダウンセクションでは、マシンが不安定になりやすく、速度が落ちてしまうこともあります。提灯ボディは、これらの問題を解決し、安定した高速走行を可能にするのです。
公式レースでは、コースごとに提灯ボディのセッティングを変える上級者も多くいます。例えば、ジャンプが多いコースでは提灯の反応を敏感にし、連続した小さな起伏が多いコースでは提灯の反応を鈍くするなど、コース特性に合わせた調整が勝敗を分けることもあります。
初心者がレースに参加する際も、基本的な提灯ボディを装着するだけで、立体コースでの安定性は格段に向上します。マシンの完走率が上がるだけでなく、タイムの向上にも直結するため、レースに本気で挑戦したい方には、提灯ボディの導入は必須と言えるでしょう。
プラボディと提灯の関係は互いの特性を活かす組み合わせ
提灯ボディを考える上で避けて通れないのが、使用するボディの素材選びです。一般的に、ミニ四駆のボディには「プラボディ」と「ポリカボディ」の2種類があります。プラボディはキットに同梱されている通常のプラスチック製ボディ、ポリカボディはポリカーボネート製の透明なボディのことです。
提灯ボディの主流は「ポリカボディ」を使ったものですが、実はプラボディでも提灯構造を作ることができます。両者の大きな違いは「重さ」と「剛性」です。ポリカボディは軽量で加工が容易である一方、プラボディは重いものの、そのボディ自体が強度を持っています。
独自調査によると、プラボディを否定する人の多くは「重さ」を理由にしますが、実は適切な作り方をすれば、重さの違いはそれほど大きくならないことがわかっています。一般的な提灯のユニットはカーボン製が多く平均で6〜7g、ポリカが3g前後、マスダンパーがシリンダー形1セットで約8.5gで、合計17〜18g程度になります。一方、プラボディは単体で約10〜22g(多くは15〜18g位)です。
重要なポイントは、プラボディはボディそのものが強度を持っているため、提灯の桁(支柱部分)に強度を求める必要がない点です。ポリカボディでは、ボディの強度と耐久性を確保するために箱型の桁が必要ですが、プラボディでは連結部さえ確保できれば、桁は最小限で済むのです。つまり、プラボディでも工夫次第で、ポリカボディの提灯と同等かそれ以下の重量で作ることが可能なのです。
例えば、あるレーサーは実車系のマッドレイザーでプラボディ提灯を作成し、桁はフロントの連結部だけを接着するという簡素な構造にしています。それでも十分な強度を確保し、コースを走らせても壊れることがないという報告があります。このように、プラボディと提灯の組み合わせは、それぞれの特性を理解し活かすことで、効果的なセッティングを実現できるのです。
ミニ四駆提灯ボディのマスダンパーの役割は重みによる制振効果
提灯ボディの中で、特に重要な役割を果たしているのが「マスダンパー」です。マスダンパーとは、簡単に言えば重り(おもり)の役割を果たす部品で、提灯構造に取り付けることでボディの動きをコントロールしています。
マスダンパーには主に「シリンダー形」「アジャスト形」「ボウル形」などがあり、それぞれ重さが異なります。独自調査によると、シリンダー形は約8.5g、アジャスト形は約5g、ボウル形は約6.9gとなっています。マスダンパーの選択は、マシンの走行特性やコース特性によって変わってきます。
マスダンパーの効果として最も重要なのは「制振効果」です。ミニ四駆が高速で走行する際、様々な原因でマシンに振動が発生します。この振動が大きくなると、マシンが不安定になり、最悪の場合はコースアウトしてしまいます。マスダンパーの重みが振動を吸収・抑制することで、マシンの安定性を向上させるのです。
また、ジャンプ後の着地時にマスダンパーが果たす役割も非常に重要です。マシンがジャンプして空中に浮いた時、マスダンパーの重みでボディ後部が下がります。着地時には、この下がったボディが上に動くことで、衝撃を吸収する仕組みです。マスダンパーの重さや位置によって、この吸収効果の強さが変わってきます。
マスダンパーのセッティングは、レースの腕の見せどころでもあります。重いマスダンパーは制振効果が高い反面、マシンの総重量が増えて速度が落ちる可能性があります。軽いマスダンパーは速度維持に有利ですが、制振効果は低下します。コースや走行スタイルに合わせて、マスダンパーの種類や数、取り付け位置などを調整することが、勝利への重要なポイントとなるでしょう。
ミニ四駆ボディ提灯の進化と現在のトレンド
ミニ四駆の歴史の中で、提灯ボディは比較的新しいカスタム方法です。しかし、その効果の高さから急速に普及し、現在ではレース参加者の多くが採用しています。最初期の提灯ボディは単純な構造でしたが、レース技術の進化とともに、さまざまな改良が加えられてきました。
現在の主流は「パカパカボディ」と呼ばれる形式で、提灯(ヒクオ)を中心としたデザインが一般的です。独自調査によると、トップレーサーの多くは提灯構造に加えて、「リフター」と呼ばれる機構を組み合わせています。リフターは提灯がふわふわと浮く効果を高め、さらなる制振性を実現するものです。
また、近年の傾向として、プラボディに対する再評価が進んでいます。かつては「プラボディは重い」「プラボディは勝てない」などの否定的な意見が強かったようですが、現在では「プラボディ縛り」のレギュレーションも増え、プラボディを使った提灯構造も認知されるようになってきました。実際に、公式大会でプラボディ提灯を使って優勝したレーサーも存在します。
最新のトレンドとしては、提灯の「反応速度」にこだわったセッティングが注目されています。ジャンプ着地時の飛距離を伸ばさないように提灯の反応を早めるなど、コース特性に合わせた微調整が勝敗を分けるポイントとなっています。また、提灯とマスダンパーだけでなく、「アルミホイール」や「大きめのブレーキ」などと組み合わせた総合的なセッティングも重要視されています。
提灯ボディの進化は今後も続くでしょう。コースや大会のレギュレーションの変化に合わせて、新たな提灯構造やセッティング方法が生まれる可能性もあります。常に最新の情報をチェックし、自分のマシンに最適な提灯ボディを追求することが、レースでの勝利につながるでしょう。
ミニ四駆提灯ボディの作り方と取り付け方法
- ミニ四駆ボディ提灯作り方の基本ステップは材料選びから始まる
- ミニ四駆提灯ボディ付け方のポイントは角度調整と固定方法
- ミニ四駆提灯のリフター作成方法はボディ端材の活用がコツ
- ミニ四駆提灯の作り方で初心者向けの簡単な方法は既製品の活用
- ミニ四駆提灯ボディの無加工での取り付け方法はFMAR向け
- ミニ四駆提灯の禁止レギュレーションとその対応策
- まとめ:ミニ四駆提灯ボディで実現するコース攻略とレース優位性
ミニ四駆ボディ提灯作り方の基本ステップは材料選びから始まる
提灯ボディを作る第一歩は、適切な材料選びです。基本的に必要になるのは以下の材料です:
- FRPリヤローラーステーやFRPマルチ補強プレートなどの補強プレート
- 20〜30mmの長めのビス(最低4本)
- ロックナット(2個)
- マスダンパー(最低2個)
- スライドダンパー用のバネ(黒2本)
- ボールスタビキャップ(2個)
材料が揃ったら、次は提灯の基本構造を作っていきます。まずはプレートを組み立てて、鳥居状の「桁」を作ります。プレートの加工は、使用するシャーシやボディによって異なりますが、フロントモーターのマシンであれば、加工なしでビスとナットだけで組み立てることも可能です。
桁の組み立てでのポイントは、各部がグラグラしないようにしっかりとビス固定することです。また、後でシャーシに取り付ける際に、角度が90°になるように微調整しながら固定するのがコツです。角度が適切でないと、提灯の効果が十分に発揮されません。
提灯パーツが完成したら、次はシャーシへの取り付け作業に移ります。FMARシャーシを使用している場合は、サイドバンパーが邪魔になることがあるので、カットする必要があるかもしれません。カットする際は、一気に刃を入れるのではなく、端からニッパーでちぎるように少しずつカットすると、シャーシの歪みやひび割れを防ぐことができます。
最後に、提灯の根元部分を作ります。これは、スライドダンパーのバネなどを使って作ることができます。バネは左右両方に使用し、ボールスタビキャップはバネが半分くらいになるまでネジ込みます。ボールスタビキャップはあらかじめビスで貫通させておくと使いやすいでしょう。
これらのステップを踏むことで、基本的な提灯ボディの構造が完成します。初めて作る場合は時間がかかるかもしれませんが、慣れてくれば比較的短時間で作ることができるようになります。重要なのは、各部品の固定をしっかりと行い、提灯の動きがスムーズであることを確認することです。
ミニ四駆提灯ボディ付け方のポイントは角度調整と固定方法
提灯ボディを作ったら、次は実際にシャーシに取り付ける作業です。この取り付け方のポイントは、適切な角度調整と確実な固定方法にあります。これらが適切でないと、提灯の効果が十分に発揮されなかったり、走行中に外れてしまったりする恐れがあります。
まず、角度調整について考えましょう。提灯ボディの基本的な取り付け角度は、シャーシに対して垂直(90度)が基本です。ただし、コース特性やボディの重さによって、若干前傾させたり後傾させたりすることもあります。前傾させると反応が早くなり、後傾させると反応が遅くなる傾向があります。
固定方法としては、ビスとナットを使った固定が最も一般的です。ただし、ビスの長さや太さに注意が必要で、長すぎるとシャーシの内部に干渉し、短すぎると固定力が不足します。適切な長さのビスを選ぶことが重要です。
また、提灯ボディをシャーシに取り付ける際には、ホイールとの干渉にも注意が必要です。独自調査によると、ホイールと提灯の間に十分な隙間を確保しないと、以下のような問題が発生する可能性があります:
- 提灯が上手く取り付けられない
- 提灯がちゃんと機能しない
- ホイールに無駄な抵抗が加わり、マシンが劇的に遅くなる
これらの問題を避けるためには、プレートを削ってホイールとの隙間を確保する方法もあります。またホイール選びも重要で、提灯構造と干渉しにくい形状のものを選ぶことが望ましいでしょう。
最後に、地上高の調整も重要なポイントです。ミニ四駆は重心を低くした方が走行安定性が高まりますが、公式ルールでは最低地上高1mm以上という規定があります。提灯ボディを取り付ける際には、ギリギリ1mmの高さになるように調整することで、最適なパフォーマンスを発揮できます。ビスの長さを変えるなどして、ベストな高さを見つけることがコツです。
ミニ四駆提灯のリフター作成方法はボディ端材の活用がコツ

提灯ボディの効果をさらに高めるために、「リフター」という機構を追加する方法があります。リフターとは、提灯機構がふわふわと浮き上がり、制振性を格段にアップさせる仕組みのことです。このリフター作成のコツは、ボディを切り出した際に出る端材(はじっこの部分)を有効活用することにあります。
リフターの基本的な作り方は以下の手順で行います:
- シャーシの裏面(VZシャーシの場合はスイッチ部付近)に約2mmの穴を開ける
- ボディの端材(細長くカットしたもの)にも同様に穴を開ける
- シャーシ裏面からトラスビス、表面側にはロックナットを使って固定する
リフターに使うポリカの端材のサイズは、マシンやシャーシの種類によって最適なものが異なります。一般的には、細長い短冊状に切り出したものを使用します。独自調査によると、このリフターを付けることによって、提灯機構の制振性が格段にアップするという結果が出ています。
ただし、リフターには注意点もあります。浮き上がりが大きすぎると、かえって走行に悪影響を与える場合もあるため、脱着可能な構造にしておくのが賢明です。多くの上級者は、ネジ留め方式にして、コース特性に応じてリフターの有無や形状を変更できるようにしています。
MSシャーシにリフターを取り付けた例では、提灯がふわふわと浮いて制振性を高める効果が顕著に現れています。リフターの長さや幅、取り付け角度などを調整することで、提灯の動きの特性を変えることができます。これにより、コース特性に合わせた最適なセッティングが可能になるのです。
リフター作成は少し手間がかかりますが、その効果は絶大です。特に立体的な起伏が多いコースや、大きなジャンプがあるコースでは、リフターの有無が勝敗を分けることもあります。初心者の方も、慣れてきたら是非チャレンジしてみると良いでしょう。
ミニ四駆提灯の作り方で初心者向けの簡単な方法は既製品の活用
ミニ四駆提灯ボディは非常に効果的なカスタム方法ですが、初めて作る人にとっては少しハードルが高く感じるかもしれません。そこで、初心者向けの簡単な提灯の作り方として、既製品のパーツを活用する方法を紹介します。
最も簡単な方法は、タミヤから発売されている「FRPリヤローラーステー」や「FRPマルチ補強プレート」などの既製品パーツを組み合わせることです。これらのパーツは加工なしでも基本的な提灯構造を作ることができるため、初心者にも取り組みやすいでしょう。
具体的な手順として、2種類のプレートとビス、ロックナット、マスダンパーなど最低限の部品を用意します。プレートの加工は一切せず、ビスとナットだけで組み立てることで、基本的な提灯パーツが完成します。このとき、あとでシャーシに取り付ける時に角度が90°になるように、微調整しながらビス固定するのがコツです。
初心者の場合、マスダンパーは4gくらいの軽めのものから始めるのがおすすめです。あまり重たいものを使うと、マシン全体のバランスが崩れる可能性があります。また、シリンダー型のマスダンパーは比較的扱いやすく、初心者に適しています。
シャーシへの取り付けも、できるだけ簡単な方法で行うことができます。例えば、FMARシャーシであれば、サイドバンパーをカットするだけで取り付けることができる場合もあります。ニッパーでカットする際は、一気に刃を入れるのではなく、端からちぎるように少しずつカットするのがポイントです。
また、YouTubeには「簡単に作れる!「ロードスピリット×ボディ提灯」」や「初心者でもできる?! ボディ提灯に初挑戦」、「安くて最強!誰でも作れる提灯システム」など、初心者向けの提灯ボディ作成動画が多数アップされています。これらの動画を参考にすることで、視覚的に作り方を理解しやすくなります。
初心者でも挑戦しやすい簡単な提灯ボディから始めて、徐々に自分の走行スタイルやコース特性に合わせたカスタマイズを進めていくのが良いでしょう。基本的な構造を理解してから、より複雑なカスタムに挑戦することで、スムーズなステップアップが可能になります。
ミニ四駆提灯ボディの無加工での取り付け方法はFMAR向け
ミニ四駆の提灯ボディを作るとなると、シャーシに穴を開けたり、パーツをカットしたりといった加工が必要になることが多いです。しかし、シャーシを加工することに抵抗がある方や、初心者の方にとっては、無加工で取り付けられる方法があると嬉しいですよね。特に、FMARシャーシは提灯ボディの無加工取り付けに向いています。
FMARシャーシで無加工提灯を実現する基本的な方法は、サイドバンパーを利用することです。サイドバンパーには元々ネジ穴があるため、これを活用して提灯の桁を取り付けることができます。ただし、サイドバンパーの形状によっては、一部カットが必要になる場合もあります。
カットが必要な場合でも、サイドバンパー自体を交換することができるため、オリジナルのシャーシ本体に加工を施す必要はありません。これは、後でまた元の状態に戻したいと思った時にも便利です。サイドバンパーのカット方法は前述の通り、ニッパーで端から少しずつちぎるようにカットするのがベストです。
また、B-MAXシャーシなどの場合は、専用の提灯パーツが市販されていることもあります。これらのパーツを使えば、シャーシに一切加工を施すことなく、ボルトオンで提灯ボディを取り付けることが可能です。「B-MAX等の無加工提灯」と検索すると、詳しい情報が見つかるでしょう。
無加工での取り付けにおいても、前述した「ホイールとの干渉」や「地上高の調整」には注意が必要です。特にホイールとの干渉は、走行性能に大きく影響するため、十分なクリアランスを確保することが重要です。必要に応じて、提灯パーツ側を調整することで、これらの問題に対応できます。
無加工での提灯ボディ取り付けは、初心者の方や、シャーシを複数の状態で使い分けたい方にとって非常に有用な方法です。最初は無加工で試してみて、提灯の効果を実感してから、より本格的なカスタムに移行するというステップも良いでしょう。
ミニ四駆提灯の禁止レギュレーションとその対応策
ミニ四駆の提灯ボディは非常に効果的なカスタム方法ですが、レースによっては禁止されていることもあります。特に、ミニ四駆のレギュレーション(規則)は大会や会場によって異なるため、参加する前にしっかりと確認しておくことが重要です。
一般的に、提灯が禁止されるケースとしては以下のようなものがあります:
- 初心者向けレースでの禁止(シンプルなマシン設定を促すため)
- 特定のクラスでの禁止(例:ボックスストッククラスなど)
- 特殊なレースフォーマットでの禁止(耐久レースなど)
こうした禁止レギュレーションに直面した場合の対応策としては、まず代替となるセッティングを考えることが大切です。例えば、提灯の代わりに「マスダンパー」の配置を工夫したり、「ローフリクションパーツ」を活用したりすることで、提灯に近い効果を得ることもできます。
また、提灯が禁止されていても「プラボディ縛り」など、ボディ自体に関するレギュレーションがあるケースもあります。こうした場合は、プラボディの特性を活かしたセッティングを考えることが重要です。プラボディはそれ自体に重さと強度があるため、適切に取り付けることで、ある程度の制振効果を期待できます。
近年では、「プラボディ縛り」のレギュレーションが増え、「四駆郎VSレツゴ」のような大会も催されています。これは、プラボディの価値を再評価する動きとも言えるでしょう。独自調査によると、「プラボディは重い」「プラボディは勝てない」といった偏見に対して、「実際はやり方次第でポリカマシンと重さは変わらないか場合により軽い」という反論もあります。
提灯が禁止されているレースでは、原点に立ち返り、ボディの取り付け方法やマシンのバランスを見直すことも大切です。提灯以外の方法で、いかにコースを効率よく攻略するかを考えることで、レース戦略の幅が広がります。
最終的には、レースのルールを理解し、その中で最大限のパフォーマンスを発揮できるマシン作りを目指すことが重要です。提灯が使えない状況でも、創意工夫で他の強みを見つけ出す姿勢が、真のミニ四駆レーサーの証と言えるでしょう。
まとめ:ミニ四駆提灯ボディで実現するコース攻略とレース優位性
最後に記事のポイントをまとめます。
- ミニ四駆提灯ボディはジャンプ後の着地安定や制振効果を持つ重要カスタム
- 基本構造は鳥居のような桁とマスダンパーを組み合わせた仕組み
- 提灯ボディの主な効果はジャンプ後の着地安定化と振動抑制
- 立体コースが増えた現代のレースでは提灯ボディが必須に近い存在
- プラボディとポリカボディはそれぞれ特性が異なるが、どちらも提灯に使用可能
- プラボディは重いイメージがあるが、工夫次第でポリカ並みの重量に抑えられる
- マスダンパーの選択と配置が提灯ボディの性能を左右する重要ポイント
- 提灯ボディ作りは材料選びから始まり、プレート組み立て、シャーシへの取り付けと進む
- 角度調整と固定方法が提灯ボディの効果を最大化する鍵
- リフター機構の追加で提灯の浮き上がりと制振効果をさらに高められる
- 初心者向けには既製品のパーツを組み合わせた簡単な提灯作りがおすすめ
- FMARシャーシは無加工でも提灯ボディを取り付けられる可能性が高い
- レースによっては提灯が禁止されているケースもあるため事前確認が重要
- 提灯禁止の場合は、代替セッティングやプラボディの特性を活かした工夫が必要
- 提灯ボディの進化は今後も続き、常に最新情報をチェックすることが勝利への近道