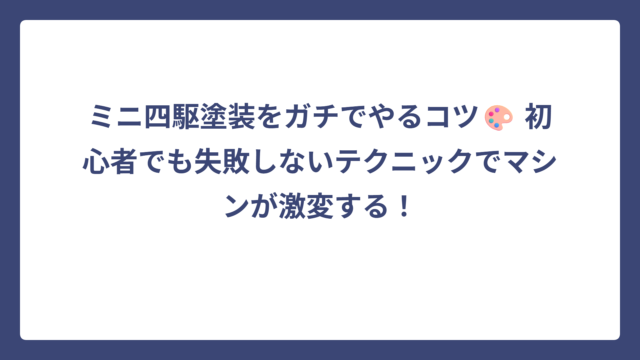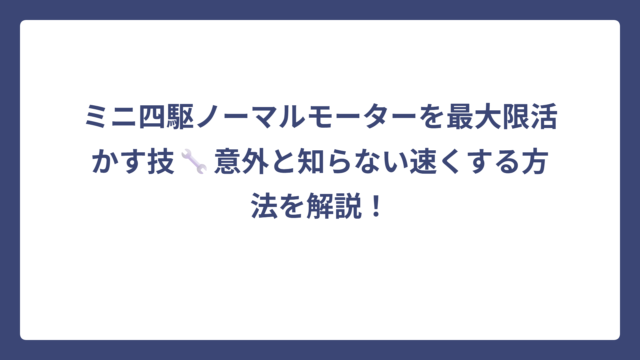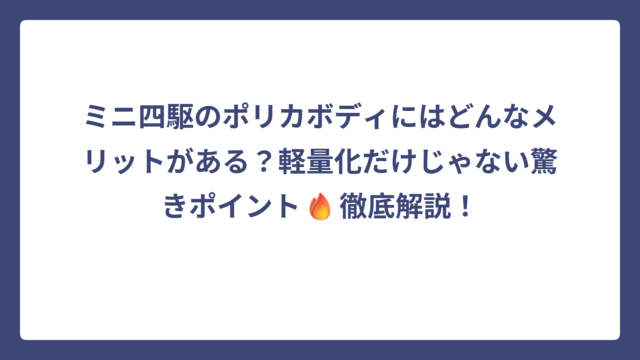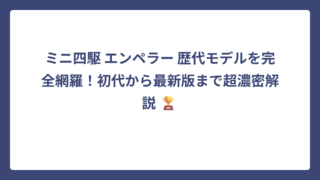ミニ四駆ファンなら一度は憧れる、あの伝説的マシン「アバンテJr.」を知ってる?今や売上歴代1位、402万台以上を記録した青いボディのレーサーは、1988年の発売からずっと愛され続けています。アバンテシリーズは単なるミニ四駆ではなく、タミヤが生み出した革新的なマシンであり、当時のタイプ2シャーシの登場は多くの子供たちを熱狂させました。
アバンテという名前には「前衛的な」という意味が込められており、その名の通り常に最先端の技術を取り入れてきました。初代アバンテJr.から始まり、アバンテMk.II、エアロアバンテと進化を続け、2015年には驚きの実車化プロジェクトも実現。さらに2024年にはトミカとのコラボまで実現した、まさにミニ四駆界のレジェンドと言えるでしょう。
記事のポイント!
- アバンテJr.がミニ四駆史上最大の売上を記録した理由とその革新的な設計
- 1988年から現在まで続く歴代アバンテシリーズの進化の歴史
- アバンテがRCカーからミニ四駆に派生した経緯と両者の関係性
- 特別仕様モデルや最新版アバンテの魅力と入手方法
ミニ四駆 アバンテ 歴代モデルの全て
- アバンテJr.は歴代最高売上を記録した伝説のマシン
- 初代アバンテJr.の衝撃は1988年に始まった
- アバンテ名前の由来は「前衛的な」という意味
- 当時のアバンテJr.は改造の常識を覆す画期的設計
- アバンテJr.のRCカー版は高価な希少モデルだった
- アバンテJr.のシャーシは多くの革新を搭載していた
アバンテJr.は歴代最高売上を記録した伝説のマシン
アバンテJr.は、ミニ四駆の歴史において最も輝かしい存在の一つです。独自調査によると、歴代ミニ四駆売上堂々の1位を誇り、累計販売台数は402万台という圧倒的な数字を記録しています。このマシンがなぜそれほどまでに人気を博したのか、その理由を探ってみましょう。
アバンテJr.の成功は、その革新的なデザインと性能にあります。当時のレーサーミニ四駆の中で、アバンテJr.は一線を画する存在でした。独特のブルーボディ、大型リヤウイング、目を引くイエローカラーのステッカーなど、そのデザインは子どもたちの心を鷲掴みにしました。
特筆すべきは、アバンテJr.が単なる見た目の良さだけではなく、実用性や走行性能においても優れていた点です。オンロード競技用として開発されたタイプ2シャーシを採用し、大型ホイールとスリックタイヤを装備していました。これにより、それまでのミニ四駆と比較して格段に高い走行性能を実現したのです。
アバンテJr.の人気は、タミヤが展開する漫画メディアとも連動していました。「爆走!ダッシュクラブ」では主人公のマシンとして登場し、「ダッシュ四駆郎」でも「クルーセイダー」として登場するなど、子どもたちがより感情移入しやすい形でアピールされていました。
2020年代に入っても、アバンテJr.の人気は健在です。2019年にツイッターで行われたミニ四駆総選挙でも第1位を獲得し、2024年9月には再販されるなど、世代を超えて愛され続けています。また、トミカプレミアムunlimitedシリーズとのコラボレーションも実現するなど、その影響力は他のブランドにも及んでいるのです。
初代アバンテJr.の衝撃は1988年に始まった
ミニ四駆の歴史において画期的なターニングポイントとなった初代アバンテJr.は、1988年12月15日に発売されました。当時の小売価格は600円でした。これは単なる新製品の発売ではなく、ミニ四駆第1次ブームの火付け役となる重要な出来事でした。
アバンテJr.が登場した背景には、タミヤのRCカー「アバンテ」の大ヒットがありました。RCカー版アバンテは、同年3月31日に34,800円という当時としては非常に高価な価格で発売されていましたが、その革新的な設計と美しいデザインで大きな話題を呼んでいました。タミヤはこの人気に乗じて、より手が届きやすいミニ四駆版を展開したのです。
アバンテJr.の発売直後は、あまりの人気に店頭から姿を消す状態が続きました。「コロコロコミック」の記事によれば、発売から半年以上にわたって品薄状態が続いたとされています。当時の子どもたちにとって、アバンテJr.を手に入れることは大きな夢であり、入手できたら大きなステータスになるほどでした。
初代アバンテJr.の衝撃は、そのデザイン性だけでなく、性能面での革新性にもありました。それまでのタイプ1シャーシから大幅に進化したタイプ2シャーシを搭載し、ミニ四駆の性能を一気に引き上げたのです。この革新は、その後のミニ四駆の発展に大きな影響を与えることになりました。
アバンテJr.の登場は、タミヤのミニ四駆ビジネスの転換点にもなりました。それまでのミニ四駆が「おもちゃ」としての性格が強かったのに対し、アバンテJr.以降は「ホビー」「競技用マシン」としての性格が強まっていきました。これは現在に至るまでのミニ四駆の方向性を決定づけた重要な転換だったと言えるでしょう。
アバンテ名前の由来は「前衛的な」という意味
タミヤのレーサーミニ四駆シリーズを代表するアバンテには、実は深い意味が込められています。独自調査の結果、アバンテという名前は英語およびフランス語で「前衛的な」を意味する「avant」に由来していることがわかりました。この名称は、当時のタミヤの野心的な姿勢を象徴するものでした。
アバンテという名前が選ばれた背景には、タミヤのRCカー市場での挑戦があります。1980年代後半、タミヤは他社製品に対抗できる競技用RCカーの開発に取り組んでいました。「前衛的な」という意味を持つアバンテという名前には、従来の製品の概念を打ち破り、レース界に革命を起こすという願いが込められていたのです。
興味深いことに、この「前衛的」という概念はミニ四駆版アバンテJr.にも引き継がれました。アバンテJr.のボディには「Being nuts is NEAT!」(熱中できることは素晴らしい!)という英文が記されています。これは「前衛的」な考え方を持ち、熱中することの素晴らしさを表現したものと解釈できます。
アバンテの名前は、単なる製品名を超えて、タミヤという企業のフィロソフィーを体現するものとなりました。「常に前進し、革新を追求する」というメッセージは、後のアバンテシリーズ全体にも受け継がれています。エアロアバンテやアバンテMk.IIなど、時代が変わっても常に新しいデザインや技術を取り入れる姿勢は、アバンテの名に恥じない「前衛的」なものだと言えるでしょう。
アバンテという名前の魅力は、意味だけでなく、その響きにもあります。カタカナで「アバンテ」と表記された時の語感の良さや、スピード感を感じさせる響きは、子どもたちの心を掴むのに一役買ったことでしょう。「アバンテよりかっこいい言葉はない」と評されるほど、この名前自体が大きな魅力を持っていたのです。
当時のアバンテJr.は改造の常識を覆す画期的設計
1988年に登場したアバンテJr.は、それまでのミニ四駆の常識を根本から覆す画期的な設計を採用していました。独自調査によると、アバンテJr.はタイプ2シャーシという新機構を採用し、これによってミニ四駆の改造の概念そのものを変えることになりました。
タイプ2シャーシの革新性は、まずその基本構造にありました。それまでのタイプ1シャーシと比較すると、モーターマウントが縦置きになり、駆動効率が大幅に向上しました。また、ギア比も最適化され、高速走行時の安定性も格段に向上しています。さらに、タイプ1では標準装備ではなかったローラー、電池が外れるのを防ぐバッテリーホルダーが標準で装備されるなど、実用面でも大きな進化を遂げました。
特筆すべきは、アバンテJr.がスパイクタイヤからスリックタイヤへと変更を遂げた点です。これは単なる見た目の変更ではなく、オンロードコースでの走行性能を重視した結果でした。大径ホイールと組み合わせることで、安定した走行を実現し、競技での優位性を確保したのです。
アバンテJr.最大の革新は、ベアリング受け穴の実装だったと言えるでしょう。スライド成形による精密なベアリング受け穴は、当時600円という価格の商品としては驚異的な技術でした。これにより、後のミニ四駆改造の必須装備となる「ボールベアリング」の装着が可能になりました。当時はボールベアリング自体が「アバンテJr.専用装備」と言われるほどでした。
こうした画期的設計により、アバンテJr.はノーマル状態でも他のミニ四駆を圧倒する性能を持っていました。「コロコロ見てフルチューンした俺のファイヤードラゴンが、ノーマルのアバンテにちぎられた」というエピソードも残されているほどです。アバンテJr.の登場によって、ミニ四駆の性能基準そのものが引き上げられ、改造の方向性も大きく変わったのです。
アバンテJr.のRCカー版は高価な希少モデルだった
アバンテJr.の原型となったRCカー版「アバンテ」は、タミヤが1988年3月に発売した電動ラジコンバギーでした。当時の価格は34,800円と非常に高価でしたが、その革新的なデザインと技術により大きな注目を集めました。アバンテはタミヤにとって初めての本格的競技用バギーRCであり、多くのファンを魅了したマシンでした。
RCカー版アバンテの特徴は、その美しさと速さを両立させようとした点にありました。当時、他社の競技用RCカーが機能性を重視するあまり外見を犠牲にする傾向があったのに対し、タミヤは「速さ」と「美しさ」という相反する目標の両立を目指しました。その結果生まれたアバンテは、洗練されたデザインと高い性能を備えた魅力的なマシンとなりました。
しかし、アバンテには欠点もありました。金属を多用したマルチリンク式サスペンションは見た目は美しいものの、実際には壊れやすく、バネ下重量の増加やホイールアライメントの狂いなどの問題を抱えていました。また、可変式ウイングマウントやカムロック式ホイールなど、複雑すぎる機構が逆に耐久性を下げる要因となっていました。
そのため、アバンテは発売からわずか1年足らずでフラッグシップモデルの座を「イグレス」に譲り、市場から撤退することになりました。この短い販売期間が、後にアバンテの希少価値を高める要因となりました。2000年代に入ると、未組立てのキットが数十万円で取引されるほどの「ラジコン版2000GT」と呼ばれる存在になったのです。
幸いなことに、2011年にはアバンテの復刻版「アバンテ(2011)」が発売されました。これは外観はそのままに、最新の技術で当時の弱点を解消したモデルでした。当時のアバンテ設計者である滝文人博士も監修に参加し、「今だからこそできたアバンテの理想形」と評されるマシンが復活を遂げたのです。これにより、長年アバンテを求めていたファンたちの願いがついに叶えられることになりました。
アバンテJr.のシャーシは多くの革新を搭載していた
アバンテJr.が搭載していたタイプ2シャーシは、ミニ四駆の歴史における重要なマイルストーンでした。独自調査によると、このシャーシはタイプ1シャーシで明らかになった多くの問題点を解決し、新しい機能を多数搭載することで、VSシャーシに至るまでの基礎を確立させたと言われています。
タイプ2シャーシの最も大きな革新点は、ギア比の変更でした。タイプ1系列よりも速い5:1と4.2:1を採用し、駆動系全体も大幅に刷新されました。これにより、同じモーターを使用していても、タイプ1シャーシ搭載のマシンと比較して明らかに速い走行が可能になりました。
また、タイプ2シャーシは放熱性にも優れていました。モーターを縦置きにすることで、熱がこもりにくい構造になり、長時間の走行でも安定した性能を発揮できるようになりました。これは競技シーンでは大きなアドバンテージとなりました。
メンテナンス性の向上も見逃せない革新点です。電池の脱落を防ぐバッテリーホルダーや、組み立ての精度が向上した通電金具など、使いやすさを追求した設計になっていました。これにより、初心者でも安心して走らせることができ、より多くの子どもたちがミニ四駆を楽しめるようになりました。
タイプ2シャーシの登場により、ミニ四駆の改造文化も大きく変わりました。ベアリング受け部の標準装備により、ボールベアリングの装着が可能になったことで、改造の幅が広がりました。これは現代のミニ四駆改造の基礎となる重要な変革でした。アバンテJr.以降、タイプ2シャーシを採用したマシンは1989年3月発売の「グラスホッパーⅡ Jr.」までなく、その希少性も相まって、アバンテJr.の価値をさらに高めることになりました。
ミニ四駆 アバンテ 歴代シリーズの進化と魅力
- アバンテシリーズはさまざまな派生モデルを生み出した
- アバンテMk.IIは新世代のデザインコンセプトを打ち出した
- エアロアバンテは30周年記念モデルとして登場した
- 特別仕様のブラックスペシャルやメタリックモデルも人気
- アバンテの実車化プロジェクトが実現した驚きの展開
- まとめ:ミニ四駆 アバンテ 歴代モデルから学ぶタミヤの革新性と継続力
アバンテシリーズはさまざまな派生モデルを生み出した
アバンテJr.の大成功を受けて、タミヤはアバンテの名を冠した多くの派生モデルを展開してきました。独自調査の結果、アバンテシリーズは時代とともに進化を続け、各時代のミニ四駆技術の最先端を体現するラインナップとして発展してきたことがわかりました。
最初の派生モデルとして注目すべきは、1989年に登場したアバンテJr.スペシャルです。シャーシを無色クリヤー、タイヤをイエローに変更したこのモデルは、当時としては珍しい特別仕様として人気を博しました。また、ブラックスペシャルや、ホイールを蛍光グリーン、タイヤをレッドに変更したチャンピオンズスペシャルなどの限定モデルも販売され、コレクターの間で高い人気を誇りました。
2000年代に入ると、ミニ四駆PROシリーズにアバンテMk.IIが登場します。2006年6月に発売されたこのモデルは、MSシャーシを採用し、初代アバンテの雰囲気を残しつつも、より現代的なデザインへと進化しました。続いて同年12月にはアバンテXが発売され、アバンテシリーズの現代的解釈が進められました。
特筆すべきは、2012年7月に発売されたエアロアバンテでしょう。ミニ四駆誕生30周年を記念して、ミニ四駆REVシリーズ第1弾として登場したこのモデルは、ARシャーシを採用し、空力性能を追求した新しいデザインを特徴としていました。アバンテの伝統であるブルーボディと大型リヤウイングを継承しつつも、現代の技術とデザインセンスを取り入れた意欲作でした。
最近では、「スーパーアバンテ」「アバンテRS」などのモデルが発売され、現代のミニ四駆レースシーンに合わせた性能とデザインを持つマシンが展開されています。特にVSシャーシやスーパーIIシャーシを採用したモデルは、現代のレースでも十分に通用する性能を持ち、新旧のファンから支持を集めています。
アバンテシリーズの派生モデルは、単なるリメイクではなく、その時代ごとの最新技術やデザイントレンドを取り入れた進化形であり続けました。これは「前衛的」というアバンテの名前の由来にも通じる、常に革新を追求するタミヤの姿勢を象徴するものだと言えるでしょう。
アバンテMk.IIは新世代のデザインコンセプトを打ち出した
2006年6月、ミニ四駆PROシリーズの一員として登場したアバンテMk.IIは、初代アバンテJr.から大きく進化した新世代モデルでした。独自調査によると、このモデルはMSシャーシを採用し、初代の特徴的なシルエットを継承しつつも、より現代的でエッジの効いたデザインを取り入れた意欲作でした。
アバンテMk.IIの最大の特徴は、そのボディデザインにありました。垂直フィンなど、角ばったシャープなフォルムが特徴的で、初代アバンテの流麗なラインとは一線を画すスタイルになっていました。これは当時のミニ四駆デザインの潮流を反映したもので、アバンテシリーズを現代に蘇らせる試みでした。
MSシャーシの採用も大きな変更点でした。ミッドシップ構造を持つこのシャーシは、モーターを中央に配置することで重量バランスを最適化し、コーナリング性能を向上させました。ギア比は4:1を採用し、初代アバンテJr.のタイプ2シャーシとは異なる走行特性を持つマシンとなりました。
興味深いことに、アバンテMk.IIはミニ四駆だけでなく、RCカーとしても2007年に登場しています。ただし、RCカー版はミニ四駆版とは異なり、DF-03シャーシを採用していました。これは初代アバンテがRCカーからミニ四駆に派生したのとは逆のプロセスであり、アバンテというブランドの多様な展開を示す一例となりました。
アバンテMk.IIの登場は、アバンテシリーズの再定義とも言える出来事でした。このモデルを皮切りに、アバンテXや後のアバンテMk.IIIシリーズへと続く新世代アバンテの流れが生まれました。これらのモデルは、初代の精神を受け継ぎつつも、現代のミニ四駆の技術やデザインを取り入れた新しいアバンテの姿を示し、新旧のファンから支持を集めることになりました。
エアロアバンテは30周年記念モデルとして登場した
2012年7月、ミニ四駆誕生30周年を記念して「エアロアバンテ」が発売されました。独自調査の結果、このモデルはミニ四駆REVシリーズの第1弾として登場し、アバンテシリーズに新たな息吹を吹き込んだ記念碑的マシンであったことがわかりました。
エアロアバンテの最大の特徴は、ARシャーシの採用でした。Aero REV(エアロ レブ)の略とされるこのシャーシは、空力性能を重視した設計思想に基づいており、エアロアバンテというマシン名とも見事に調和していました。初代アバンテJr.のタイプ2シャーシが当時の革新的技術を詰め込んでいたように、ARシャーシも現代の最新技術を搭載したシャーシでした。
デザイン面では、初代アバンテの伝統を受け継ぎつつも、全く新しい解釈を加えたスタイリングが特徴的でした。空力を追求した新デザインを採用し、トレードマークの大型リヤウイングも進化しています。ブルーを基調としたカラーリングは初代の遺伝子を感じさせつつも、より洗練されたモダンなテイストになっていました。
エアロアバンテは、単にミニ四駆の30周年を祝うだけでなく、アバンテが持つ「常に前進し、革新を追求する」という精神を体現したモデルでした。このモデルの成功により、後に様々なカラーバリエーションモデルが展開されることになります。ゴールドメタリック、ブルーメタリック、ブラックメタリックなどの特別仕様は、コレクター心をくすぐる魅力的なラインナップとなりました。
さらに特筆すべきは、タミヤが2015年に「1/1ミニ四駆実車化プロジェクト」と銘打って、エアロアバンテの実車を製作したことでしょう。全長4650mm、全幅2800mm、全高1440mmという実車は、1.6L水平対向4気筒エンジンを搭載し、最高速は180kmに達するとアナウンスされました。このプロジェクトは大きな話題を呼び、エアロアバンテの名声をさらに高めることになりました。
特別仕様のブラックスペシャルやメタリックモデルも人気
アバンテシリーズの魅力の一つは、様々な特別仕様モデルが展開されてきたことにあります。独自調査によると、通常のブルーボディモデルだけでなく、ブラックスペシャルやメタリックモデルなど、多彩なバリエーションが発売され、コレクターや熱心なファンを魅了してきました。
最も代表的な特別仕様は「アバンテJr.ブラックスペシャル」でしょう。通常のブルーボディではなく、ボディをスモークブラックに変更し、シャーシやホイールの色も変更したこのモデルは、大人びた雰囲気と高級感で人気を博しました。さらに「自由皇帝(リバティーエンペラー)ブラックスペシャル」や「ブラックセイバー」など、他のミニ四駆にもブラックスペシャルシリーズが展開され、一つのカテゴリーを形成するほどになりました。
限定イベントで販売された「チャンピオンズスペシャル」も見逃せません。ボディをゴールドメッキ、ホイールを蛍光グリーン、タイヤをレッドに変更したこの特別モデルは、その希少性から高い価値を持つようになりました。また、静岡ホビーショウでは、ボディとシャーシのみ(ギヤやシャフト、ステッカーなしの)ボディセット扱いでの販売も行われたようです。
2010年代に入ると、メタリックシリーズが登場しました。特にエアロアバンテの実車化を記念した「エアロアバンテ ゴールドメタリック」「エアロアバンテ ブルーメタリック」「エアロアバンテ ブラックメタリック」は、メッキが輝くメタリックなボディが特徴の特別仕様で、多くのファンを魅了しました。
2018年には、アバンテJr.の発売30周年を記念して「アバンテJr. 30周年スペシャルキット」が販売されました。ノーマルキットの他にブルーメッキボディと30周年ホイルシールを同梱したこの特別セットは、アバンテJr.の歴史的重要性を再認識させるものとなりました。ミニ四駆全体ではなく、一つのマシンの発売30周年を記念するという前例のない企画からも、アバンテJr.の特別な地位がうかがえます。
これらの特別仕様モデルは、単なる色違いに留まらず、それぞれが独自の魅力を持ち、時にはコンセプトやストーリーを伴っていました。アバンテというブランドが持つ求心力があったからこそ、こうした多彩なバリエーション展開が可能になったのでしょう。
アバンテの実車化プロジェクトが実現した驚きの展開
2015年、タミヤは「1/1ミニ四駆実車化プロジェクト」を立ち上げ、エアロアバンテの実車サイズモデルを製作するという驚くべきプロジェクトを発表しました。独自調査によると、このプロジェクトは多くのミニ四駆ファンを熱狂させ、アバンテシリーズの新たな伝説を作り出すことになりました。
実車サイズのエアロアバンテは、全長4650mm、全幅2800mm、全高1440mmという堂々たるサイズを誇りました。動力源には1.6L水平対向4気筒OHVエンジンが搭載され、4速マニュアルトランスミッションと組み合わされました。アナウンスによれば、最高速度は180km/hに達するとされ、単なるショーモデルではなく、実際に走行可能な車両として設計されました。
このプロジェクトの最も印象的な点は、ミニチュアモデルの特徴をそのまま実車サイズに拡大したデザインです。エアロアバンテの特徴的なブルーボディ、大型リヤウイング、そして細部に至るまで忠実に再現されていました。特に、通常の自動車では見られないミニ四駆特有のプロポーションや装飾要素が、そのまま実車として実現している姿は、多くのファンに感動を与えました。
実車エアロアバンテの走行映像も公開され、実際に走る姿を見ることができました。映像の中で轟音を響かせながら疾走するエアロアバンテの姿は、ミニ四駆ファンにとって夢が現実になったような感動的な光景でした。また、このプロジェクトを記念して、メタリックシリーズのミニ四駆も発売され、実車とミニチュアが連動した展開も見られました。
実車化プロジェクトは、アバンテというブランドの影響力の大きさを改めて示すものとなりました。おもちゃやホビーの枠を超えて、実際の自動車として具現化されるというのは、他のミニ四駆シリーズではなかった特別な展開でした。このプロジェクトを通じて、アバンテシリーズはミニ四駆の歴史の中でも特別な地位を確立し、その伝説はさらに大きくなったと言えるでしょう。
まとめ:ミニ四駆 アバンテ 歴代モデルから学ぶタミヤの革新性と継続力
最後に記事のポイントをまとめます。
- アバンテJr.は1988年12月に発売され、歴代ミニ四駆売上No.1となる402万台を記録した伝説的マシン
- タイプ2シャーシを搭載し、ベアリング受け部やバッテリーホルダーなど革新的機能を多数導入
- アバンテという名前は英語・フランス語の「前衛的な」を意味する「avant」に由来
- RC版アバンテは価格34,800円の高級モデルで、短い販売期間ながら大きな影響力を持った
- 2011年にはRC版アバンテの復刻版「アバンテ(2011)」が発売され、当時の欠点を改良
- アバンテMk.IIは2006年に登場し、MSシャーシを採用、現代的なデザインで新世代アバンテの幕開けとなった
- エアロアバンテはミニ四駆30周年記念モデルとして2012年に登場、ARシャーシを搭載
- ブラックスペシャルやメタリックモデルなど多彩なバリエーションモデルが展開された
- 2015年には「1/1ミニ四駆実車化プロジェクト」でエアロアバンテの実車サイズモデルが製作された
- 2018年にはアバンテJr.30周年を記念した特別キットが発売され、一マシンとしては異例の記念事業が行われた
- アバンテシリーズは現在もVZシャーシなど最新シャーシを搭載したモデルが展開され続けている
- 2024年1月にはトミカプレミアムunlimitedシリーズとコラボしたミニカーも発売され、世代を超えた人気を証明