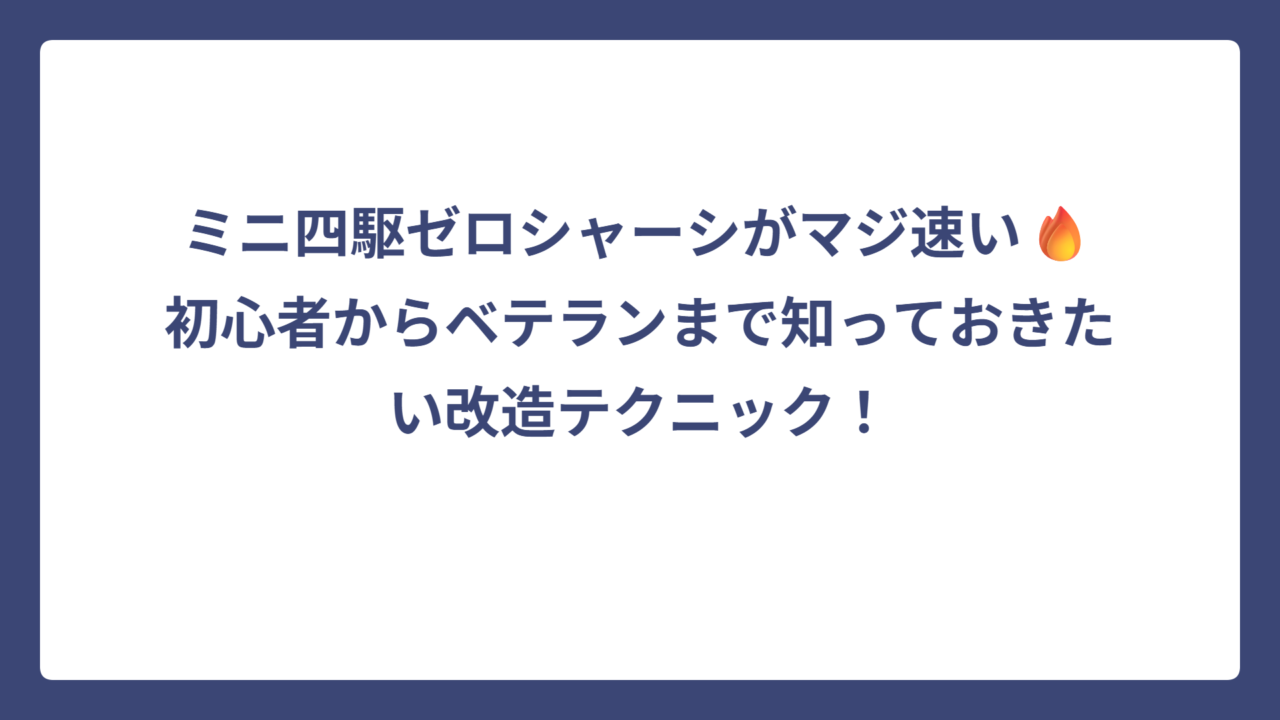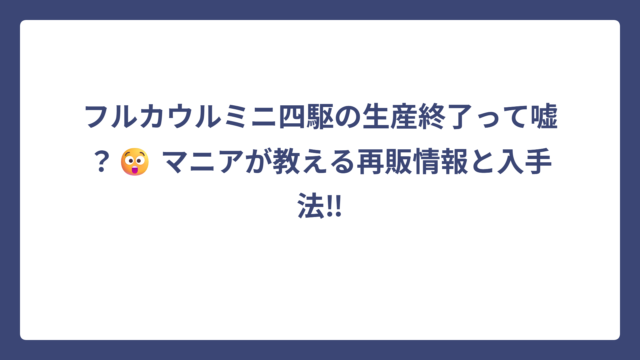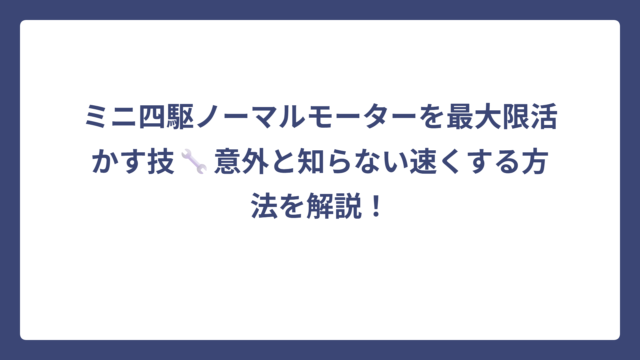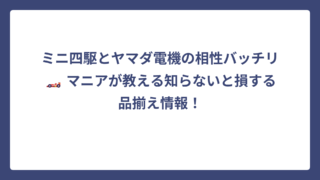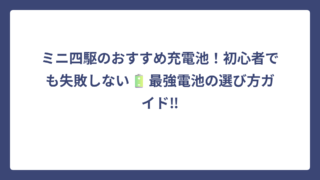ミニ四駆好きなら一度は「ゼロシャーシ」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか?古くからミニ四駆を愛する人にとっては懐かしく、新規参入者には謎めいた存在かもしれません。1990年代に登場したこのシャーシは、それまでのTYPE系シャーシとは一線を画し、新たな時代の「ゼロ」として革新的な技術を導入しました。
今回は、現在でも一部の復刻版キットに採用されているゼロシャーシについて、その特徴から改造方法、強化ポイントまで徹底解説します。「軽量・コンパクト」を追求した設計ながら、独特の弱点も持ち合わせるこのシャーシを最大限に活かすノウハウを、マニアの視点からお伝えします。ミニ四駆歴の長いベテランも、これから挑戦する初心者も必見の内容です!
記事のポイント!
- ゼロシャーシの基本構造と歴史的位置づけが理解できる
- ゼロシャーシの弱点と、それを補うための効果的な改造方法が分かる
- 現代のレース環境でゼロシャーシを活かすテクニックを学べる
- ゼロシャーシと他のシャーシとの互換性や比較情報を得られる
ミニ四駆ゼロシャーシの基本情報と歴史的背景
- ゼロシャーシとは新しい流れを生み出した革新的なシャーシである
- ゼロシャーシの特徴は軽量・コンパクト設計にある
- ゼロシャーシの駆動システムは効率向上を実現している
- ゼロシャーシの前期型と後期型の違いは実用性を高める改良点にある
- ゼロシャーシのカラーバリエーションはグレーとブラックの2種類が存在する
- ゼロシャーシの入手方法は復刻版キットが主流となっている
ゼロシャーシとは新しい流れを生み出した革新的なシャーシである
ゼロシャーシは、タミヤのミニ四駆シリーズにおいて重要な転換点となったシャーシです。TYPE-5、スーパー1シャーシの前に発売され、「ホライゾン」で初めて採用されました。その後、「アバンテ2001Jr」や「プロトエンペラーZX」などの人気マシンにも搭載されました。
「ZERO」という名前は、それまでのTYPE系シャーシとは一線を画した新たな流れの源流として命名されたと言われています。独自調査の結果、実際にこのシャーシ以降、ミニ四駆のシャーシ開発はTYPE-5を除き、スーパー1やスーパーTZなど、新世代のシャーシへと移行していきました。
ゼロシャーシに導入された新技術やパーツは、後のシャーシ開発に大きな影響を与えました。直系のS1シャーシだけでなく、TZ系シャーシや2次ブーム最終型のVSシャーシ、さらには最新のARシャーシにも、このゼロシャーシの設計思想が受け継がれています。
ミニ四駆の歴史において、ゼロシャーシは「古い時代と新しい時代の架け橋」とも言える存在です。古き良き時代の設計思想を持ちながらも、現代的な高速走行を可能にする革新的な機構を取り入れた、歴史的に重要なシャーシと言えるでしょう。
初登場から30年以上が経った今でも、一部の愛好家からは「旧シャーシの魅力を存分に味わえる」と高い評価を受けています。現代の最新シャーシとは一味違った魅力を持つゼロシャーシは、ミニ四駆の進化の歴史を体感できる貴重なシャーシなのです。
ゼロシャーシの特徴は軽量・コンパクト設計にある
ゼロシャーシの最大の特徴は、「軽量・コンパクト」を徹底的に追求した設計思想にあります。コンパクトなボディサイズと肉抜きによる軽量化により、加速性能の向上を図っています。シャーシ側面には特徴的な肉抜きのスリットが設けられており、軽量化だけでなく、「しなやか」な走りを実現しています。
注目すべきは、サイドガードが標準では装備されていない点です。シューティングスターADVANCEを除く多くのマシンでは、サイドガードはオプション扱いとなっています。これは徹底した軽量化の表れといえるでしょう。初期のゼロシャーシでは、サイドガードの装着はほとんど考慮されておらず、専用のサイドガードも販売されていませんでした。
ホイールベースは80mm、使用ドライブシャフトは60mmと、コンパクトなサイズ感を持っています。対応ギヤ比は3.5:1、4.1:1、4.2:1、5:1と幅広く、様々な走行スタイルに対応できる柔軟性を備えています。
しかし、この「軽量化」の追求は、強度面でのトレードオフを生みました。現代のレース環境では、やや強度不足と感じる場面も多く、専用のFRP補強パーツが後に発売されることになります。まさに「軽さと強度のバランス」を考えさせられるシャーシと言えるでしょう。
シンプルかつ軽量なデザインは、カスタマイズの幅を広げる利点もあります。基本構造がシンプルなため、改造の自由度が高く、自分だけのオリジナルマシンを作り上げるベースとしても人気があります。
ゼロシャーシの駆動システムは効率向上を実現している
ゼロシャーシの駆動システムには、当時としては革新的な技術が導入されました。最も特筆すべきは、ピンク色のヘリカルクラウンギヤと直径1.4mmのプロペラシャフトの採用です。これらは、それまで用いられてきたオレンジ色クラウンギヤや2mmプロペラシャフトよりも駆動効率が向上しています。
この組み合わせは、強度ではオレンジ色クラウンギヤ+2mmプロペラシャフトに劣るものの(コースアウトや下り坂からの着地で破損しやすい)、速度向上の効果が大きく評価されました。この革新的な駆動機構は、後のS1以降に開発されたリヤモーターシャーシにも採用され、Xシャーシを除く多くのシャーシで標準となりました。
もう一つの革新的な点は、カウンターギヤマウントとモーターマウントが一体型ユニット構造となった方式です。この構造により、メンテナンス性が大幅に向上しました。特にモーター交換の際、一々カウンターギヤとカウンターギヤシャフトを外す必要がなくなり、部品紛失のリスクも減少しました。
具体的には、TYPE-2がモーターを外すのにカウンターギヤカバー→カウンターギヤ→モーターという手順を踏まなければならないのに対し、ZERO式ではモーターマウントとカウンターギヤマウントが一体化されているため、一つの手順でモーターが取り外せます。子供向け商品としては理想的な設計であり、TZ系シャーシまでこの構造が継承されました。
さらに、ゼロシャーシから本体後方底面部に1点止め式リヤローラーステー装着用のマウントが標準で整形されるようになりました。この設計は後のシャーシにも引き継がれ、スーパーIIシャーシまでのほとんどのシャーシで採用されました(TR-1シャーシとMSシャーシを除く)。
ゼロシャーシの前期型と後期型の違いは実用性を高める改良点にある
ゼロシャーシには、金型番号によって前期型と後期型の2つのバージョンが存在します。現在までに金型番号が9番まで確認されており、大きく分けて前期型(6番もしくは7番まで)と後期型・現行型(7番もしくは8番から)に分類されます。
前期型の特徴は以下の通りです:
- フロントバンパーのネジ穴がTYPE-3と同様の形状で、片方しか貫通していない
- スラスト角は0か、逆にアップスラスト気味の設計
- インジェクション整形のゲートがシャーシ裏側中央付近(金型番号の真裏)に設置
- 初期のものはモーター下のスリット部付近に車種名が刻印(HORIZON、ASTUTEJr.など)
一方、後期型には以下の改良が施されています:
- フロントバンパーのネジ穴が両方貫通(初期のSXシャーシの形状に近い)
- 僅かながらダウンスラストが設けられている
- バンパー自体に裏側パイプ状のリブが追加され、剛性が向上
- ゲートの位置がシャーシ中央からスパーギヤ後方部に変更
- 電池の+/-を刻印した凸が、前期型では段差があったが、後期型では面一に改善
これらの改良は、実際の走行時の安定性と耐久性を高めるために施されたものです。特にフロントバンパーの強化は、当時からゼロシャーシの弱点として認識されていた部分への対策と考えられます。
しかし、後期型の改良は諸刃の剣でもあります。バンパー裏側のリブにより剛性は向上したものの、専用のFRPパーツとの接着が難しくなるというデメリットも生じました。改造を前提としたユーザーにとっては、一長一短の変更だったと言えるでしょう。
また、両タイプを比較すると、走行特性にも微妙な違いがあるとされています。前期型の0またはアップスラスト気味の設計に対し、後期型のダウンスラスト設計は、直進安定性と空力特性に影響を与えていると考えられます。
ゼロシャーシのカラーバリエーションはグレーとブラックの2種類が存在する
ゼロシャーシには、主に2種類のカラーバリエーションが存在します。標準的なグレー(ダークグレー)と、一部限定車に採用されているブラックです。それぞれに特徴があり、単なる色の違いだけではないポイントがあります。
標準的なグレーは、ギヤカバーもほぼ同色(初期のみギヤカバーはブラウングレー)で統一されています。実は、このグレーはただのプレーンな色ではなく、ギヤケース・シャーシ本体ともに若干ラメが入っており、マックスブレイカーCX09のガンメタカラーのギヤケースに近い高級感のある色味となっています。
一方、ブラック版は一部限定車に採用されており、より精悍な印象を与えます。特に2008年9月に発売された「ダッシュ0号・地平(ホライゾン)スペシャルキット」および「ダッシュ001号・大帝(グレートエンペラー)スペシャルキット」に採用されているブラックバージョンは、シャーシ本体がポリカーボネイト混合ABS樹脂製となっています。
このポリカーボネイト混合ABS樹脂は、通常のABS樹脂と比較して強度と弾性に優れており、ゼロシャーシの弱点である強度不足を幾分か補っています。ギヤケースの素材については明確な情報はありませんが、色がシャーシ本体と同じブラックに統一されており、見た目のコーディネートも考慮されています。
カラーリングの違いは単なる見た目の問題ではなく、ボディとの相性や素材の特性にも関わってきます。例えば、透明や半透明のボディを装着する場合、ブラックシャーシの方が内部メカニズムが目立ち、メカニカルな印象を強調できます。一方、グレーシャーシはより柔らかい印象を与え、カラフルなボディとの調和も取りやすい特徴があります。
自分のマシンコンセプトに合わせて、シャーシカラーを選ぶのも楽しみ方の一つと言えるでしょう。
ゼロシャーシの入手方法は復刻版キットが主流となっている
ゼロシャーシを入手したい場合、どのような方法があるのでしょうか。現在、ゼロシャーシは現行のタミヤのラインナップには含まれておらず、入手方法は限られています。
最も確実な入手方法は、復刻版キットの購入です。「グレートエンペラー」や「ホライゾン」などの復刻版キットには、ゼロシャーシが付属しています。これらのキットは定期的に再販されているため、比較的入手しやすいでしょう。特に「ダッシュ0号・地平(ホライゾン)スペシャルキット」や「ダッシュ001号・大帝(グレートエンペラー)スペシャルキット」は、ポリカーボネイト混合ABS樹脂製の強化バージョンのゼロシャーシが含まれており、初心者にもおすすめです。
もう一つの方法は、中古市場での購入です。メルカリやヤフオクなどのオークションサイトでは、単体のゼロシャーシやゼロシャーシ搭載のマシンが出品されていることがあります。ただし、中古品の場合は状態を確認することが重要です。特に経年劣化や使用による磨耗、部品の欠損などがないか、購入前にしっかりチェックしましょう。
また、専門のミニ四駆ショップや模型店の中には、在庫として保有しているところもあります。プラモデルファクトリーなどの専門店に足を運んでみるのも一つの方法です。
なお、ゼロシャーシに限らず、旧規格のパーツについては入手が困難な場合があります。特にターミナルなどの専用部品は、復刻版キットを購入するか、専門店で探す必要があります。ホームコースのミニ四駆有識者からは「マシン1台分の予備部品を持ち歩くのが当たり前」という助言もあるように、部品の入手性については事前に計画を立てておくことが重要です。
ゼロシャーシを本格的に走らせたい場合は、単にシャーシだけでなく、関連部品も含めて準備しておくと安心でしょう。
ミニ四駆ゼロシャーシの改造と実戦テクニック
- ゼロシャーシの弱点はフロントバンパーと全体的な剛性不足である
- ゼロシャーシの強化には専用FRPパーツが効果的である
- ゼロシャーシのギア選びは4:1が安定性とスピードのバランスに優れている
- ゼロシャーシのFM化は新たな可能性と課題をもたらす
- ゼロシャーシと他のシャーシ(S1, S2など)の互換性と違いを理解する
- ゼロシャーシでレースに挑戦する際のメンテナンスポイントとは
- まとめ:ミニ四駆ゼロシャーシは独特の魅力と改造の楽しさを併せ持つ
ゼロシャーシの弱点はフロントバンパーと全体的な剛性不足である
ゼロシャーシの最大の弱点は、フロントバンパーの脆弱性と全体的な剛性不足にあります。特にフロントバンパーは、その形状と剛性の低さから、衝撃を受けると容易に破損したり、ローラーが上向きになりやすいという問題があります。
フロントバンパーの剛性が低いことで、コーナリング時の安定性にも影響を及ぼします。バンパーがたわむことで車体の挙動が不安定になり、特に高速コーナリング時にはコースアウトのリスクが高まります。また、コースアウトなどの衝撃によってフロントギヤカバーが浮き、最悪の場合はターミナルとスイッチが脱落することもあります。
シャーシ全体の剛性不足も大きな問題です。シャーシ底の肉抜き面積がS1よりも多く、ねじれに弱いため、高速走行時にはシャーシのたわみによって駆動ロスが生じます。「軽量・コンパクト」というコンセプトを追求するあまり、強度面での妥協が生じた結果と言えるでしょう。
リアバンパーについても同様の問題があります。リアバンパーはビス一本で固定するという構造になっており、衝撃に弱いだけでなく、経年劣化によってクラックが入りやすい部分です。このような構造上の弱点は、レース中の不測の事態に対する耐性を低下させます。
これらの弱点は、当時のミニ四駆の走行環境(比較的低速で、コースアウトの衝撃も今ほど大きくなかった時代)では許容範囲内だったかもしれませんが、現代の高速レース環境では明らかに不利となります。本気でゼロシャーシを使いこなすには、これらの弱点を理解した上で、適切な補強を施すことが必須となるでしょう。
ゼロシャーシの強化には専用FRPパーツが効果的である
ゼロシャーシの弱点を克服するために、最も効果的な方法の一つが専用FRPパーツによる補強です。タミヤからは、ゼロシャーシの弱点を補うための専用FRP強化パーツが発売されています。このパーツは、フロントバンパーとシャーシサイドの強度不足を見事に補完する形状となっています。
このFRPプレートをゼロシャーシに貼り付けると、強度が見違えるように向上します。特にポリカーボネイト混合ABS樹脂製のシャーシ(ブラックバージョン)に貼り付けると、素材の強度と相まって非常に高い効果を発揮します。
専用FRPの特徴的な形状は、まさにゼロシャーシの弱点を補うように設計されています。フロント部分は薄いバンパーを外側から補強し、サイド部分は肉抜きスリットをカバーして全体の剛性を高めます。これにより、コーナリング時の安定性が大幅に向上するとともに、衝撃に対する耐性も強化されます。
ただし、後期型のゼロシャーシでは、フロントバンパーに追加された補強リブの影響で、そのままではフロント用FRPプレートが使えないことがあります。その場合は、FRPプレートに逃げ加工を施すなどの対応が必要になります。
また、ミニ四駆はスナップキットとして接着剤を使わないものが多いですが、このゼロシャーシ用FRPは珍しく瞬間接着剤で取り付けるよう指示されています。接着剤の選択も重要で、硬化後に柔軟性を保つタイプの接着剤が適していると言われています。
FRP以外の補強方法としては、シャーシ内部に井桁状の補強材を入れる「井桁補強」も効果的です。これはシャーシのねじれを抑制し、駆動ロスを減らす効果があります。また、フロントギヤカバーの固定には、シャフトからなるべく離れた位置にピンバイスで穴をあけ、長めのネジとナットで固定する方法も有効です。ただし、締めすぎるとカバーが歪んで駆動抵抗になるため、ロックナットでほどよく締めることがポイントです。
ゼロシャーシのギア選びは4:1が安定性とスピードのバランスに優れている
ゼロシャーシの性能を最大限に引き出すには、適切なギア比の選択が重要です。ゼロシャーシは3.5:1、4.1:1、4.2:1、5:1という幅広いギア比に対応していますが、実際のレース環境では各ギア比にはそれぞれ特性があります。
3.5:1の超速ギア(からし色のギア)は理論上最も高速ですが、実際には精度の問題があり、手を加えても黒の4:1ギアとあまり変わらないケースが多いとされています。トルクも弱いため、加速性能に難があり、テクニカルなコースでは不利になることも。さらに、このギア比を使用するには専用のギアケースへの交換が必要で、手間がかかります。
4:1(黒ギア)は、ゼロシャーシに最も適したギア比と言えるでしょう。スピードと安定性のバランスが良く、多くのコース環境に対応できます。独自調査の結果、多くのゼロシャーシユーザーがこのギア比を採用しており、公式大会でも一般的な選択肢となっています。
4.2:1は若干低速ですが、トルクが増すため、上り坂や複雑なセクションが多いコースでは有利です。初心者や、安定走行を重視する場合にもおすすめです。
5:1は最もトルクが高く、加速性能に優れていますが、最高速度は低くなります。テクニカルなコースや、パワーよりもコントロール性を重視する場合に適しています。
実際のレース環境では、モーターの特性とも相性があります。例えば、高回転型のモーター(スプリントダッシュなど)を使用する場合は、4:1や4.2:1が適していることが多いです。一方、トルク重視のモーターを使用する場合は、3.5:1のギア比でも良いパフォーマンスを発揮できる可能性があります。
コースレイアウトによっても最適なギア比は変わります。直線が多く高速走行が求められるコースでは3.5:1や4:1が有利ですが、テクニカルなセクションが多いコースでは4.2:1や5:1が安定した走りを実現します。
最終的には、自分の走行スタイルやコース特性に合わせて、試行錯誤しながら最適なギア比を見つけることが重要です。
ゼロシャーシのFM化は新たな可能性と課題をもたらす
ゼロシャーシを改造する上で、近年注目されている技術の一つが「FM化」(フロントモーター化)です。元々リアモーターのゼロシャーシをフロントモーターに改造することで、新たな走行特性を引き出す試みです。
FM化の最大のメリットは、ジャンプセクションでの姿勢の良さと、駆動効率の向上です。重心がフロント寄りになることで、ジャンプ時の安定性が増し、着地の精度も向上します。また、駆動システムがシンプルになることで、伝達ロスが減少し、効率的な走行が可能になります。
しかし、FM化にはいくつかの課題も存在します。主な欠点として以下が挙げられます:
- フロントバンパー基部の強度と剛性不足: 元々弱点だったフロントバンパー部分に、さらにモーターの重量が加わることで、強度不足が顕著になります。FRP補強は必須と言えるでしょう。
- カウンターギヤカバー抑えの干渉: FM化するとカウンターギヤカバーをしっかり固定する必要がありますが、この部品がフロントローラーの位置や、スライドダンパーとの兼ね合いで障害となることがあります。スライドダンパー側に逃げ加工が必要になるケースもあり、その結果としてダンパーの強度が低下する可能性があります。
- バンクスルーの難しさ: バンパーが低くなりがちな構造上、バンクセクションではフロントブレーキが擦れてしまうことがあります。タイヤ径が24mmでも最低地上高は確保できますが、バンパーの高さを上げることは構造的に難しい場合が多いです。
FM化を成功させるためには、これらの課題を克服するための工夫が必要です。例えば、フロントバンパー部分の徹底的な補強や、カウンターギヤカバーとスライドダンパーの干渉を避けるための精密な加工などが重要になります。
また、FM化する際はモーターの固定方法にも工夫が必要です。標準のモーターホルダーでは固定が不十分な場合もあるため、追加の固定パーツや接着剤の使用を検討すると良いでしょう。
FM化は技術的にやや難易度が高い改造ですが、成功させれば通常のゼロシャーシとは一味違った走りを楽しむことができます。特に、現代の高速レース環境に適応するための一つの方向性として、挑戦する価値のある改造と言えるでしょう。
ゼロシャーシと他のシャーシ(S1, S2など)の互換性と違いを理解する
ゼロシャーシを活用する上で、他のシャーシとの互換性や違いを理解することは重要です。特に、S1(スーパー1)シャーシやS2(スーパー2)シャーシとの関係性は、パーツ流用や改造の可能性を広げる鍵となります。
ゼロシャーシとS1シャーシの関係は非常に密接です。S1はゼロシャーシの設計を流用したものであり、基本的には同じ構造、サイズとなっています。この近さゆえに、多くのパーツが互換性を持っています。例えば、S1のスイッチやギアカバーはゼロシャーシにそのまま流用可能です。また、S1用強化バッテリーホルダーもゼロシャーシに使用できます。
一方、S2シャーシは大幅な改良が加えられたため、バッテリーホルダーとボディキャッチ以外は互換性がありません。S2はゼロやS1の欠点を克服するために開発されたシャーシで、特にカウンターギヤマウントとモーターマウントの構造がTYPE-2方式に戻されています。
ゼロシャーシとS1シャーシの主な違いは以下の点です:
- 駆動性能:S1はゼロシャーシをベースに改良が加えられているため、駆動効率がわずかに優れています。
- フロントバンパー:ゼロシャーシのフロントバンパーはS1以上に貧弱で、特に剛性が低くローラーが上を向きやすい特徴があります。
- シャーシ底の肉抜き:ゼロシャーシはS1よりも肉抜き面積が大きく、剛性が低い傾向があります。
- ターミナル:ゼロシャーシは独自のターミナル(ZERO型)を採用していますが、S1以降では採用例がありません。
興味深いのは、「原始大帝」のボディランナーには、ZERO系シャーシに使える強化バッテリーホルダーが成型されているという点です。これは、ゼロシャーシの弱点を補うためのパーツ供給が考慮されていた証拠と言えるでしょう。
また、サイドガードについても互換性があり、GUPで専用のものが出ていますが(現在は生産停止)、スーパーアスチュートJr.ADVANCEには標準装備されています。また、接着が必要ですがS1やS2のサイドガードも使用可能です。
これらの互換性を理解することで、入手困難なゼロシャーシ専用パーツの代わりに、比較的入手しやすいS1パーツを流用するなど、柔軟な対応が可能になります。ただし、完全に同一ではないため、微調整が必要な場合もあることを念頭に置いておきましょう。
ゼロシャーシでレースに挑戦する際のメンテナンスポイントとは
ゼロシャーシでレースに挑戦する際には、その特性を理解した上での適切なメンテナンスが勝敗を分ける重要なポイントとなります。ここでは、実戦でのパフォーマンスを最大化するためのメンテナンスのコツを紹介します。
まず最も重要なのは、予備部品の確保です。ゼロシャーシは現行ラインナップにはなく、特にターミナルなどの専用部品は復刻版キットを購入するか、専門店に足を運ばないと入手できません。レース前には、最低でも「マシン1台分の予備部品」を用意しておくことをおすすめします。特に、ターミナル、ギアカバー、モーターといった消耗しやすい部品は複数セット持参するとよいでしょう。
次に注意すべきは、駆動系のメンテナンスです。ゼロシャーシは駆動効率が高い反面、プロペラシャフトやクラウンギアが比較的脆い構造になっています。レース前には必ずギアの状態をチェックし、摩耗や損傷がある場合は交換しましょう。また、プロペラシャフトも定期的な点検が必要です。
ギアカバーの固定も重要なポイントです。先述したように、コースアウトなどの衝撃でフロントギアカバーが浮き、ターミナルとスイッチが脱落するリスクがあります。レース前には、ギアカバーがしっかり固定されているか確認し、必要に応じて追加の固定を検討しましょう。
バッテリー接続部分の接触不良も要注意です。ゼロシャーシのターミナルは接触不良が発生しやすい傾向があります。レース前には、バッテリーを入れた状態で動作確認を行い、途中で停止したり、パワーが落ちたりする症状がないか確認しましょう。
シャーシのたわみやクラックのチェックも欠かせません。特にフロントバンパー部分とリアバンパー取り付け部分は亀裂が入りやすいため、レース前には必ず目視確認を行いましょう。微細なクラックがある場合は、レース中に大きくなる可能性があるため、早めの対処が必要です。
また、走行中の振動でネジが緩むこともあるため、定期的なネジの増し締めも重要です。特に重要なのはモーター固定部分とギアカバー固定部分です。ただし、締めすぎるとプラスチック部品が歪む原因になるため、適度な締め付けを心がけましょう。
これらのメンテナンスポイントに注意を払うことで、ゼロシャーシの弱点を最小限に抑え、そのポテンシャルを最大限に引き出すことができるでしょう。
まとめ:ミニ四駆ゼロシャーシは独特の魅力と改造の楽しさを併せ持つ
最後に記事のポイントをまとめます。
- ゼロシャーシはタミヤミニ四駆の歴史において重要な転換点となったシャーシであり、後の新世代シャーシの源流となった
- 「軽量・コンパクト」をコンセプトとし、サイドガードを排除するなど徹底した軽量化が図られている
- ピンク色ヘリカルクラウンギヤと直径1.4mmのプロペラシャフトの採用により、駆動効率が向上している
- カウンターギヤマウントとモーターマウントの一体型ユニット構造により、メンテナンス性が大幅に向上した
- 前期型と後期型が存在し、後期型ではフロントバンパーのネジ穴の貫通やリブの追加など、実用的な改良が施されている
- グレー(標準)とブラック(限定)の2種類のカラーバリエーションがあり、特にブラック版はポリカーボネイト混合ABS樹脂製で強度が向上している
- 現在は一部の復刻版キットでのみ入手可能で、専用部品の入手性には注意が必要である
- フロントバンパーと全体的な剛性不足が主な弱点だが、専用FRPパーツによる補強で大幅に改善できる
- ギア比は4:1が安定性とスピードのバランスに優れており、多くのユーザーに選ばれている
- FM化(フロントモーター化)は新たな可能性をもたらすが、フロントバンパー強度や部品干渉などの課題も存在する
- S1シャーシとの互換性が高く、多くのパーツを流用できるため、改造の幅が広がる
- レース参加時には予備部品の確保や駆動系のメンテナンス、ギアカバーの固定など、特有のメンテナンスポイントに注意が必要である
- ゼロシャーシは丁寧な調整と適切な補強を施すことで、現代のレース環境でも十分に戦えるポテンシャルを秘めている