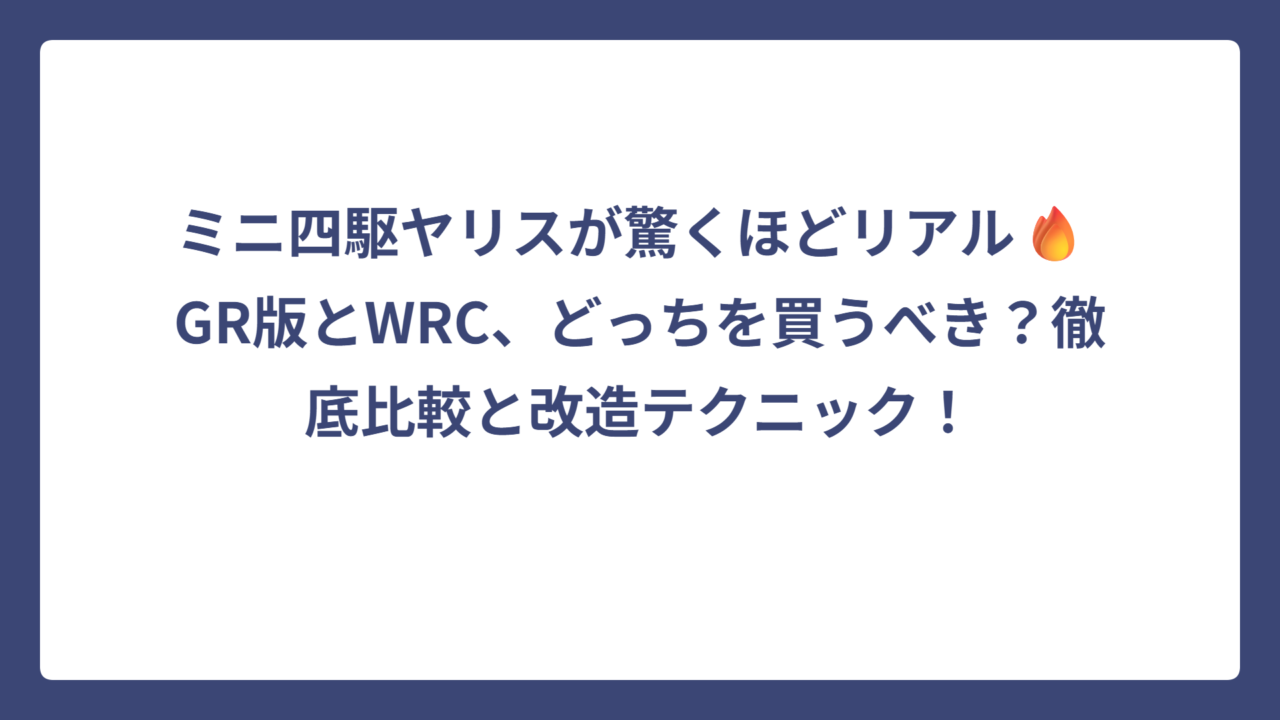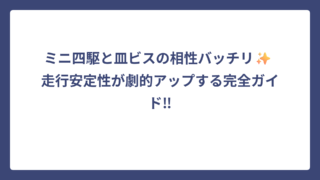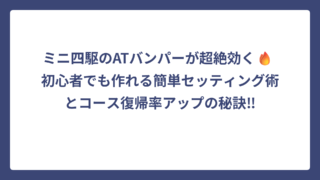ミニ四駆といえば子供の頃の思い出としてだけでなく、大人になってからも楽しめる奥深いホビーとして根強い人気がありますよね。そんなミニ四駆の世界に、トヨタの人気モデル「ヤリス」が登場し、コレクターやミニ四駆ファンの間で話題になっています。特にWRCバージョンとGRバージョンという2つのタイプが発売されており、それぞれ異なるシャーシと特徴を持っています。
この記事では、「ミニ四駆ヤリス」の基本情報から種類の違い、そして実際のカスタム方法まで詳しく解説します。リアルなラリーカーを再現したWRC版と、スポーティーな市販車GR版の魅力を徹底比較!さらに、パーツ交換や塗装のテクニックなど、あなたのミニ四駆ライフをレベルアップさせる情報が満載です。初心者からベテランまで、ミニ四駆ヤリスの魅力を存分に味わいましょう!
記事のポイント!
- ミニ四駆ヤリスには「GR版(VZシャーシ)」と「WRC版(MAシャーシ)」の2種類がある
- それぞれの特徴や価格、組み立て方法の違いが分かる
- タイヤ交換やベアリング交換などの基本的な改造方法を学べる
- 塗装やステッカー貼りのコツと、カスタマイズのアイデアが分かる
ミニ四駆ヤリスの基本情報と種類
- ミニ四駆ヤリスには2種類のモデルが存在する
- ミニ四駆ヤリスのGR版はVZシャーシを採用している
- ミニ四駆ヤリスWRCはMAシャーシで空力性能を追求している
- ミニ四駆ヤリスの価格は800円から1,300円程度である
- ミニ四駆ヤリスのボディはホワイトが基本カラーである
- ミニ四駆ヤリスの組み立ては接着剤不要で初心者でも簡単
ミニ四駆ヤリスには2種類のモデルが存在する
ミニ四駆ヤリスは、実はタイプが2種類あることをご存知でしょうか?タミヤから発売されているヤリスのミニ四駆には明確に異なる2つのバージョンが存在します。
1つ目は「トヨタ GR ヤリス (VZシャーシ)」で、タミヤのレーサーミニ四駆シリーズ No.97として2020年8月に発売されました。このモデルは市販されているスポーツ4WD車「GRヤリス」をベースにしたものです。
2つ目は「トヨタ ガズーレーシング WRT/ヤリス WRC (MAシャーシ)」で、タミヤのミニ四駆PROシリーズ No.54として2019年7月に発売されました。こちらはFIA世界ラリー選手権を戦うために開発されたラリーカーバージョンです。
このように、普通の市販車をベースにしたモデルと、レース仕様車をベースにしたモデルという2つの選択肢があり、それぞれファンの好みに合わせて選ぶことができます。見た目だけでなく、採用しているシャーシも異なるため、走りの特性も違ってきます。
コレクション目的なら両方揃えるのも良いですし、走行性能重視なら自分の好みに合った方を選ぶのも良いでしょう。また、改造やカスタムを楽しみたい方は、それぞれのモデルの特性を理解した上で選ぶことをおすすめします。
ミニ四駆ヤリスのGR版はVZシャーシを採用している
トヨタ GR ヤリス (ITEM 18097)は、VZシャーシを採用したミニ四駆です。このシャーシの「VZ」とは特定の意味を持つ略語ではありませんが、「VS」シャーシの性能を磨き上げた進化版と考えると分かりやすいでしょう。
VZシャーシの特徴として、軽量・コンパクト・ショートホイールベースであることが挙げられます。小回り性能に優れており、メンテナンス性も高いのがポイントです。また、VSシャーシから進化した点として、バンパー、リヤステー基部、プロペラシャフト軸受けなどの強度がアップしている点が挙げられます。
シャーシのカラーはグレイで統一されており、ホイールはブラックのフィンタイプを採用しています。小径ローハイトタイヤを装着することで、実車感も満点に仕上がっています。
完成時のサイズは全長158mm、全幅98mm、全高49mmとなっており、コンパクトながらも迫力あるスタイルが魅力です。3ドアハッチバックスタイルの大型のラジエターグリルやワイドに張り出したリヤフェンダー、ルーフ後端のスポイラーなど、WRC活動で培った技術を注ぎ込んで開発された実車GRヤリスの特徴をリアルに再現しています。
また、シャフトの軸受けには摩擦抵抗の少ないPOM樹脂製の620プラベアリングを採用し、ギヤ比は3.5:1をセットしています。これにより高性能な走りが楽しめるだけでなく、ディスプレイモデルとしても存在感を放ちます。
ミニ四駆ヤリスWRCはMAシャーシで空力性能を追求している
トヨタ ガズーレーシング WRT/ヤリス WRC(ITEM 18654)は、MAシャーシを採用したミニ四駆PROシリーズの一つです。この「MA」とは、Midship AERO(ミドシップエアロ)の略で、その名の通り駆動効率と空力性能を追求したシャーシとなっています。
MAシャーシは、ダブルシャフトモーターを車体中央に搭載したミドシップレイアウトの「MSシャーシ」と、走行中の気流(エアロ)を特に意識してデザインされた「ARシャーシ」の優れた特徴を1台のシャーシにまとめあげた設計です。3.5:1のギヤ比を採用し、6個の低摩擦樹脂ローラーやリヤスキッドバーも標準装備するなど、走行性能も徹底的に磨き上げられています。
WRCヤリス版の特徴は、実車のラリーカーさながらの空力を追求したデザインにあります。エッジが立った前後のオーバーフェンダー、フロント両サイドのカナード、リヤフェンダー後部の大型エアアウトレットなど、ダイナミックなフォルムを実感たっぷりにモデル化しています。特に2段タイプの大型リヤウイングは見どころの一つです。
ボディカラーはホワイトで、レッドとブラックをあしらったアグレッシブなグラフィックやスポンサーロゴはステッカーで再現できます。シャーシ本体とAパーツはブラックで統一され、シルバーのディッシュタイプホイールにブラックの小径ローハイトタイヤを装着しているのも特徴的です。
完成時のサイズは全長156mm、全幅97mm、全高44〜49mmで、一体型のモノコック構造の採用により組み立てやすさやメンテナンス性も向上しています。初心者からベテランレーサーまで幅広く対応できるシャーシデザインとなっています。
ミニ四駆ヤリスの価格は800円から1,300円程度である
ミニ四駆ヤリスの価格帯について詳しく見ていきましょう。価格は販売店や時期によって変動がありますが、基本的な相場を把握しておくと購入の参考になります。
トヨタ GR ヤリス(VZシャーシ)は、Amazonや楽天などのオンラインショップでは809円〜1,210円程度で販売されています。一方、タミヤの公式オンラインストア「TAMIYA SHOP ONLINE」では1,210円(税込)で販売されています。
トヨタ ガズーレーシング WRT/ヤリス WRC(MAシャーシ)は、オンラインショップでは882円〜1,320円程度、タミヤ公式オンラインストアでは1,320円(税込)での販売となっています。
興味深いのは、WRC版の方がGR版より若干高めの価格設定になっている点です。これはWRC版がミニ四駆PROシリーズに属し、より高性能なMAシャーシを採用していることや、複雑なデザインのパーツが多いことなどが理由として考えられます。
また、ミニ四駆を走らせるためには本体以外にも単3形電池が2本必要ですので、こちらも別途購入する必要があります。タミヤからは「パワーチャンプRX」などの専用電池も販売されており、こちらは396円(税込)程度です。
さらに、改造やカスタマイズを楽しむ場合は追加のパーツ代も考慮しておく必要があります。ベアリングやタイヤ、ホイール、モーターなど、基本的な改造パーツだけでも数千円程度かかることもあります。
価格面では比較的手頃なホビーであり、初期投資としてはリーズナブルといえますが、改造にハマると追加費用がかさむ可能性もありますので、予算計画を立てる際には注意が必要です。
ミニ四駆ヤリスのボディはホワイトが基本カラーである
ミニ四駆ヤリスのボディカラーは、GR版もWRC版も基本的にはホワイトが採用されています。このホワイトボディには重要な理由があります。
まず、ホワイトはステッカーの映えるカラーです。両モデルともに複雑なカラーリングやグラフィックはステッカーで再現するようになっており、ホワイトベースだからこそ、ステッカーの色が鮮やかに映えるのです。WRC版では特に、レッドとブラックをあしらったアグレッシブなグラフィックやスポンサーロゴのステッカーが多数用意されています。
また、ホワイトは塗装する際にも下地として優れています。カスタムペイントを楽しみたい方にとって、ホワイトボディは様々なカラーに塗り替えやすいという利点があります。ブログレビューなどでも、ホワイトをベースに黒の部分塗装を施して、よりリアルな見た目にカスタマイズしている例が多く見られます。
GR版のボディには、ウインドウやライト類、ルーフのカーボンパターンなどを表現するメタリック調のステッカーが付属しています。これらをホワイトボディに貼ることで、スポーティーでアグレッシブな実車の雰囲気をそのまま再現できるようになっています。
WRC版に関しては、リヤウイングやボンネットのアウトレット部分など、一部パーツに塗装が必要な箇所があります。レビューの中には「塗装が必要とは…」という声もありますが、これらの部分を塗装することで、よりリアルな仕上がりになります。マットブラックでの塗装が人気のようです。
ボディカラーはカスタマイズの自由度を高めるためのキャンバスと考えると良いでしょう。自分だけのオリジナルカラーを施すも良し、ステッカーだけで仕上げるも良し、ホワイトボディは様々な可能性を秘めています。
ミニ四駆ヤリスの組み立ては接着剤不要で初心者でも簡単
ミニ四駆ヤリスは、接着剤を使わずに組み立てられるように設計されています。これは初心者にとって大きなメリットといえるでしょう。
GR版(VZシャーシ)は、はめ込みとビス止めで組み立てられるようになっています。つまり、パーツ同士をカチッとはめ込んだり、小さなネジで固定したりするだけで組み立てができるのです。これにより、接着剤を使う際の失敗(接着剤のはみ出しやパーツの接着位置のズレなど)を心配する必要がありません。
WRC版(MAシャーシ)も同様に、接着剤不要のはめ込み式を採用しています。モノコック構造の一体型シャーシを採用することで、組み立てやすさやメンテナンス性も向上しています。
組み立てに必要な時間は、慣れていない方でも1〜2時間程度で完成させることができるでしょう。ただし、ステッカー貼りには時間と根気が必要です。特にWRC版はステッカーの量が多く、レビューにも「すさまじいシール攻撃」「永遠とシール貼り続けて…」という声があります。ステッカーを丁寧に貼るためには、綿棒などを使って位置を調整しながら貼ると良いようです。
また、一部のパーツには塗装が必要な箇所もあります。特にWRC版のリヤウイングやボンネットのアウトレット部分などは、塗装することでよりリアルな仕上がりになります。塗装は必須ではありませんが、見た目の完成度を高めたい方は挑戦してみるのも良いでしょう。
組み立てに必要な道具は基本的にドライバーだけです。塗装する場合は別途塗料やマスキングテープなどが必要になりますが、ステッカーだけで仕上げる場合は特別な道具は不要です。このように、特別な技術や道具がなくても組み立てられるのが、ミニ四駆ヤリスの魅力の一つといえるでしょう。
ミニ四駆ヤリスのカスタムと改造テクニック
- ミニ四駆ヤリス改造の第一歩はタイヤとホイールの交換
- ミニ四駆ヤリスのベアリング交換でスムーズな走行を実現
- ミニ四駆ヤリスの塗装はマットブラックが人気でかっこいい
- ミニ四駆ヤリスWRCのステッカー貼りは複雑だが魅力的
- ミニ四駆ヤリスのカスタムはシャーシ強化も重要
- ミニ四駆ヤリスのレビューから分かる魅力と注意点
- まとめ:ミニ四駆ヤリスはカスタム性に優れたコレクション価値も高いモデルである
ミニ四駆ヤリス改造の第一歩はタイヤとホイールの交換
ミニ四駆ヤリスのカスタマイズを始めるならば、最初に取り組みやすいのがタイヤとホイールの交換です。この改造は見た目と性能の両方を向上させる効果があります。
まず、タイヤの交換について考えてみましょう。ミニ四駆ヤリスの標準装備は小径ローハイトタイヤですが、これをスーパーハードタイヤなどに変更することで走行特性が変わります。ブログ記事によれば、タイヤにプリントがしてあるとよりスポーティーな印象になるようです。
「タイヤにプリントがしてあると映える。ペラタイヤを考えたが、プリントが消えるのが嫌なのでやめておくことにした。」という記述があることから、見た目も重視されていることがわかります。
次にホイールの交換です。標準のホイールをワンウェイホイールに交換することで、走行性能だけでなく見た目の印象も大きく変わります。ワンウェイホイールは、一方向にだけ回転する特殊なホイールで、加速性能の向上や直進安定性の向上が期待できます。
「ワンウェイホイールも第一ブーム世代にはロマンだ。普通のホイールでは得られ難いドキドキ感がある。」という感想からも、単なる性能向上だけでなく、ホビーとしての楽しさを高める要素といえるでしょう。
また、「実車でもそうだが、ホイール選びに失敗するとマシンはダサくなる。ミニ四駆も奥が深い。」という記述があるように、ホイール選びはマシン全体の印象を左右する重要なポイントです。
タイヤとホイールの交換は比較的簡単な改造でありながら、見た目と性能の両面で大きな変化が得られる点が魅力です。特にミニ四駆ヤリスのような実車をモデルにした車種では、実車感を高めるためのホイール選びが楽しみの一つとなります。
初めての改造に挑戦する方にとっても、タイヤとホイールの交換は失敗が少なく、達成感を得やすい改造といえるでしょう。
ミニ四駆ヤリスのベアリング交換でスムーズな走行を実現
ミニ四駆ヤリスの走行性能を向上させる上で、ベアリング交換は非常に効果的な改造方法です。標準のプラスチック製軸受けをベアリングに交換することで、摩擦抵抗が大幅に減少し、スムーズな回転と優れた走行性能を実現できます。
標準のVZシャーシやMAシャーシにも、すでにPOM樹脂製の620プラベアリングなど高性能なパーツが使用されていますが、これを金属製のベアリングに交換することで、さらなる性能向上が期待できます。ブログ記事によれば、「ベアリングはロマンなので、必ず装着しなくてはイケナイ。これだけで第一ブームの頃ならマシンが1台買える高級品だ。」と述べられており、パフォーマンス向上だけでなく、ミニ四駆愛好家にとっては特別な意味を持つパーツであることがわかります。
ベアリング交換の代表的な箇所としては、以下のポイントが挙げられます:
- シャフト軸受け: プロペラシャフトが通る部分のベアリング交換により、駆動効率が向上します。ブログ記事では620ベアリングが使用されています。
- ギア部分: 「更にギヤにもベアリング。タイプシャーシの頃には確かギヤにはベアリングが無かったような気がする。ロマンが加速する。」という記述があるように、ギア部分にもベアリングを装着することで、動力伝達の効率が向上します。
- ホイール部分: ホイールの回転部分にもベアリングを使用することで、より滑らかな走行が実現できます。
また、シャフト自体も「ステンレス中空シャフト。かなり軽い上に精度が高い。」というように、標準のものから軽量・高精度なものに交換することで、さらなる性能向上が期待できます。
ベアリング交換の効果は、加速性能の向上、最高速度の向上、バッテリー消費の効率化など多岐にわたります。特にコーナリング時の安定性が増し、コースアウトのリスクが減少するというメリットも大きいでしょう。
ただし、ベアリングは比較的高価なパーツであり、複数箇所を交換するとコストがかさむ点には注意が必要です。初心者の方は、まずはシャフト軸受けなど効果の大きい部分から交換を始めるのがおすすめです。
ミニ四駆ヤリスの塗装はマットブラックが人気でかっこいい
ミニ四駆ヤリスの塗装は、カスタマイズの楽しみの一つです。特にマットブラックでの塗装が人気で、クールでカッコいい印象に仕上がります。
ブログ記事によれば、「塗装は成型色を活かした部分塗装だ。さらばホワイトボディ。」とあるように、全体を塗り替えるのではなく、特定の部分だけを塗装することで、メリハリのあるデザインに仕上げることができます。
特にWRC版では、リヤウイングやリヤウィンドウ部などの塗装が必要となる部分があります。「D3パーツ、リヤウイング部。こちらは全塗装のため、ダボ軸のみマスキングした。楽勝。」「続いてD2、リヤウィンドウ部。塗り分け超面倒い。」という記述からも、塗装の難易度は部位によって異なることがわかります。
マスキング(塗りたくない部分を保護する作業)は塗装において非常に重要なプロセスです。ブログ記事では、「とりあえず少ない知恵を絞ってマスキング開始。リヤウイングに貼って。ウイングの下部分に合わせてカット。」という工程が紹介されています。丁寧なマスキングにより、きれいな塗り分けが可能となります。
マットブラックを選ぶ理由としては、「組んでみるとカッコ悪くなった。シールを貼らないと変なバランスだ。しかし、マットブラックの風合いはカッコいい。」という感想があるように、落ち着いた高級感が出せる点が挙げられます。特にラリーカーやスポーツカーをモチーフにしたミニ四駆では、マットブラックが車の力強さや精悍さを引き立てる効果があります。
塗装の時間帯については、「朝の5時から塗装。」という記述があります。塗装は静かな環境で集中して行いたい作業であり、早朝の静かな時間帯が適しているという例と言えるでしょう。
塗装後の仕上がりについては、「マスキングを剥がしてみると、微修正する箇所が少々。不器用なワタクシにしてはキレイな仕上がりだ。」とあるように、多少の修正が必要になることも想定しておくと良いでしょう。
ミニ四駆ヤリスの塗装は、初心者にはやや難易度が高い作業ですが、その分完成したときの達成感は大きく、唯一無二のオリジナルマシンを作り上げる喜びを味わうことができます。
ミニ四駆ヤリスWRCのステッカー貼りは複雑だが魅力的
ミニ四駆ヤリスWRC版の大きな特徴の一つが、豊富なステッカーです。このステッカー貼りは一見すると手間のかかる作業に思えますが、完成したときの満足感は格別です。
ブログ記事には「すさまじいシール攻撃」「永遠とシール貼り続けて…」という表現があるように、WRC版のステッカーの量は相当なものです。特にラリーカーならではの複雑なスポンサーロゴやカラーリングを再現するためには、多くのステッカーが必要となります。
レッドとブラックをあしらったアグレッシブなグラフィックは、ステッカーを丁寧に貼ることで見事に再現されます。「ホワイトのABS樹脂製ボディに貼り付けるだけで、複雑なカラーリングが手軽に仕上がります。」とあるように、塗装が難しい複雑なデザインもステッカーなら比較的簡単に再現できる利点があります。
ステッカー貼りのコツとしては、「シールの位置合わせも綿棒を使ってキッチンにフィットさせることができる」という記述があります。ステッカーを貼る際は、まず大まかな位置を決めてから少しずつ調整していき、最後に綿棒などで気泡を押し出しながら密着させると綺麗に仕上がります。
また、レビューには「シールを貼って仕上げた状態。リヤーウイングの塗装をしなくても、レーシーなカラーリングはステッカーでリアルに再現できる」という記述もあり、ステッカーだけでもかなりリアルな仕上がりになることが分かります。
一方で、「孫のため購入しましたが、ステッカーが細かく、老眼が悪化しました」というレビューもあるように、細かい作業が苦手な方や視力に自信のない方にとっては、やや難易度の高い作業と言えるかもしれません。
GR版のステッカーについても、「ウインドウやライト、フロントグリルなどのステッカー付き」とあり、車の細部を表現するためのステッカーが用意されています。特にウインドウやライト類、ルーフのカーボンパターンなどを表現するメタリック調のステッカーが特徴的です。
完成後のマシンは「だが、でもこの後、コースでブンブン走らせました」とあるように、飾るだけでなく実際に走らせることで、さらに楽しみが広がります。ただし、走行させるとステッカーがはがれやすいという指摘もあるため、「クリアーでコーティングしました」という対策を取っている例もあります。
ミニ四駆ヤリスのカスタムはシャーシ強化も重要
ミニ四駆ヤリスをより高性能に、より長持ちさせるためには、シャーシ強化も重要なカスタマイズポイントです。シャーシは車の骨格となる部分であり、ここをいかに強化・最適化するかで走行性能やマシンの寿命が大きく変わってきます。
VZシャーシを採用したGR版の特徴として、「バンパー、リヤステー基部、プロペラシャフト軸受けなどの強度をアップ。衝撃を吸収する適度な”しなり”もポイント」とあります。この「しなり」は走行中の衝撃を吸収し、マシンの安定性を向上させる重要な要素です。
シャーシのカスタマイズオプションとして、「リヤローラーステーに加えてフロントバンパーも分割が可能。セッティングの自由度も大幅に向上」という特徴があります。これは走行コースや走行スタイルに合わせて、フロントとリアのセッティングを細かく調整できることを意味します。
一方、MAシャーシを採用したWRC版は、「一体型のモノコック構造の採用で、組み立てやすさやメンテナンス性もさらに向上」という特徴があります。モノコック構造は強度と軽量化を両立させる設計で、高い耐久性が期待できます。
実際のカスタム例としては、「VZ用のファーストトライパーツセットを付ける時にそのままだと前後干渉しボディを載せられないのでリアが特にボディかステーを削るなど加工が必要です」というレビューがあります。これは、追加パーツを装着する際に生じる干渉問題への対処法として参考になります。
また、シャーシ強化と合わせて考えたいのが重量バランスの最適化です。「ステンレス中空シャフト。かなり軽い上に精度が高い」という記述があるように、単に強化するだけでなく、重量増加を抑えながら強度と精度を向上させることがポイントです。
さらに、「リヤスキッドバーやサイドステーも標準装備」という点も、シャーシの保護と強化に貢献する要素です。これらのパーツはコースの壁面との接触から車体を保護し、安定した走行をサポートします。
シャーシのカスタマイズは、見た目の変化は少ないものの、走行性能や耐久性に直結する重要な要素です。特にミニ四駆を長く楽しみたい方や、競技志向の強い方は、シャーシの特性を理解した上で、適切な強化・最適化を検討することをおすすめします。
ミニ四駆ヤリスのレビューから分かる魅力と注意点
実際に購入した方々のレビューからは、ミニ四駆ヤリスの魅力や使用時の注意点が見えてきます。以下、主なポイントをまとめてみましょう。
まず、デザイン面での評価は非常に高く、「めちゃくちゃかっこいい!」「本物みたいにカッコいい!!」といった声が多数見られます。特にWRC版については「複雑な形状のリアウイングやフェンダーなどがしっかり再現されていて赤と黒のカラーリングやロゴもステッカーを貼るだけで再現できるので良くできてると思います」という評価があります。
組み立てのしやすさについても、「作りやすかったです」「手軽にWRCマシンが手に入る」といった好意的な意見が見られます。「少ない部品点数でしっかりイメージを再現しています」という声もあり、パーツ数を抑えながらもリアル感を損なわない設計が評価されています。
しかし、いくつかの注意点も挙げられています。特にWRC版については「リヤウイングや、ボンネットのアウトレット等々、塗装が必要です」という指摘があります。「一部塗装が必要な事に文句を言ってる人がいますが、定価1000円ちょっとの物なんだから我慢しろよ…」という擁護する声もありますが、初心者にとっては予想外の手間になる可能性があります。
走行性能については、「ミニ四駆のコース試走ではルーブを周る事が出来ず、いやはや、カスタマイズしないととてもとても勝てないなあと思った」という声があります。これは標準状態では競技での性能が十分でなく、カスタマイズが必要なことを示唆しています。
また、「ボディ形状のせいか駆動音がこもったような感じになります」という特有の音に関する指摘もあります。これは車体形状に起因する特性であり、必ずしも欠点とは言えませんが、購入前に知っておくと良いポイントです。
使用シーンについては、「ローラーを取り外して飾ることも出来てディスプレイとしてもとてもいい」という声があるように、走行させるだけでなくディスプレイモデルとしての価値も高く評価されています。「痛車にしました」というレビューもあり、アニメキャラクターなどのデカールを貼る「痛車」カスタムの素材としても人気があるようです。
親子でのコミュニケーションツールとしての価値も見逃せません。「子供へのプレゼントにミニ四駆を購入し、さっそく作って遊んでいます。ミニ四駆レース場にも出向き遊んでおります。子供は大満足しています」という声は、ミニ四駆が世代を超えた楽しみを提供していることを示しています。
これらのレビューから、ミニ四駆ヤリスはデザイン性と組み立てのしやすさが魅力である一方、競技で使用する場合はカスタマイズが必須であること、一部塗装が必要な点には注意が必要であることがわかります。
まとめ:ミニ四駆ヤリスはカスタム性に優れたコレクション価値も高いモデルである
最後に記事のポイントをまとめます。
- ミニ四駆ヤリスには「GR版(VZシャーシ)」と「WRC版(MAシャーシ)」の2種類があり、それぞれ特徴が異なる
- GR版は市販車をベースにしたスポーティな外観で、軽量・コンパクトなVZシャーシを採用している
- WRC版はラリーカーをモデルにした迫力あるデザインで、駆動効率に優れたMAシャーシを搭載している
- 価格は800円〜1,300円程度で、WRC版が若干高い傾向にある
- 両モデルともにホワイトボディが基本で、ステッカーでカラーリングを再現する仕様になっている
- 組み立ては接着剤不要のはめ込み式で、初心者でも比較的簡単に完成させられる
- カスタムの第一歩としてタイヤとホイールの交換が効果的で、見た目と性能の両方が向上する
- ベアリング交換によって摩擦抵抗が減少し、スムーズな走行が実現できる
- 塗装はマットブラックが人気で、特にWRC版ではリヤウイングなど一部の塗装が必要な部分がある
- WRC版のステッカー貼りは複雑だが、丁寧に貼ることでリアルなラリーカーの雰囲気を再現できる
- シャーシ強化はカスタムの重要なポイントで、走行性能や耐久性の向上に直結する
- 購入者のレビューでは、デザイン性の高さと組み立てやすさが評価されている一方、競技使用にはカスタムが必須という声もある
- ディスプレイモデルとしての価値も高く、「痛車」カスタムの素材としても人気がある
- 親子で楽しめるコミュニケーションツールとしての価値も持っている
- 両モデルともにカスタム性に優れており、個性的なマシンを作り上げる楽しさがある