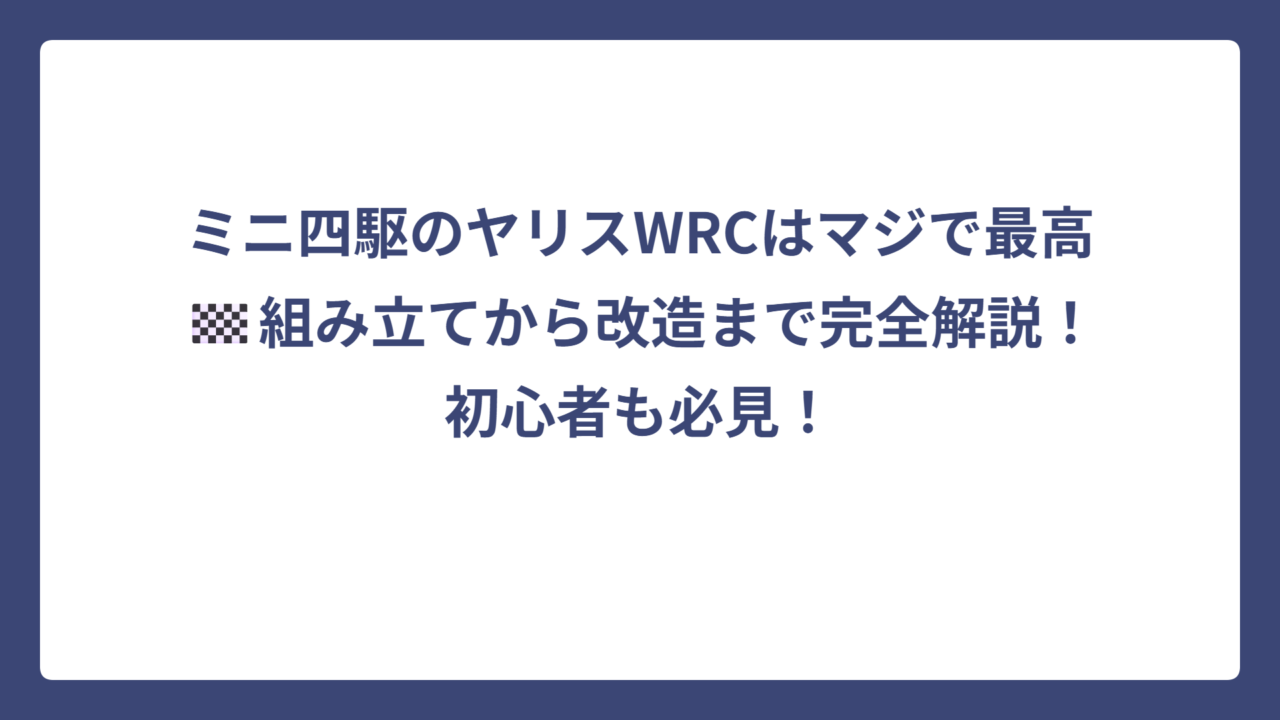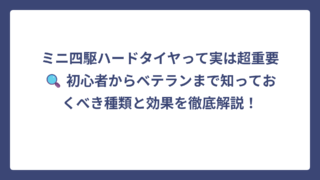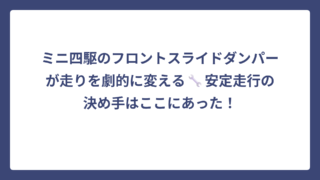ミニ四駆好きなら絶対に見逃せない!2019年のWRC(世界ラリー選手権)を戦ったトヨタのラリーカー「ヤリスWRC」がミニ四駆になって登場したんです。このミニ四駆は、空力を追求したダイナミックなフォルムや、レッドとブラックをあしらったアグレッシブなカラーリングが特徴で、多くのミニ四駆ファンから高い人気を集めています。
実はこのヤリスWRCミニ四駆、約1,000円というお手頃価格ながら、見た目の格好良さだけでなく、ダブルシャフトモーター搭載のMAシャーシを採用していて走行性能も抜群!約50枚ものステッカーを貼る手間はありますが、その分完成した時の達成感は格別です。今回は、組み立て方から塗装テクニック、そして走行性能をアップさせる改造方法まで、ヤリスWRCミニ四駆の魅力を余すことなくお伝えします。
記事のポイント!
- ヤリスWRCミニ四駆の基本情報と特徴
- ステッカー貼りと塗装が必要な部分のコツ
- 走行性能を向上させる改造テクニック
- 関連するトヨタのミニ四駆モデルとの比較
ミニ四駆とヤリスWRCの魅力と特徴
- トヨタ ガズーレーシング WRT/ヤリスWRCは2019年型ラリーカーを再現した本格モデル
- MAシャーシの採用により優れた走行性能を実現したヤリスWRC
- ヤリスWRCの価格は約1,000円とコスパ最高のミニ四駆
- ステッカー約50枚の貼り付けでリアルなカラーリングを実現できる楽しさ
- 塗装が必要な部分はウイングとボンネットインテークのみで初心者にも挑戦しやすい設計
- 実車のヤリスWRCとデザインの違いはミニ四駆ならではの制約による変更点
トヨタ ガズーレーシング WRT/ヤリスWRCは2019年型ラリーカーを再現した本格モデル
タミヤから発売されているミニ四駆「トヨタ ガズーレーシング WRT/ヤリス WRC」は、2019年のWRC(世界ラリー選手権)を戦ったトヨタのラリーカーを忠実に再現したモデルです。公式商品番号は18654で、ミニ四駆PROシリーズのNo.54として位置づけられています。
このモデルの最大の特徴は、実車のラリーカーのような迫力ある外観です。エッジが立った前後のオーバーフェンダーや、フロント両サイドのカナード、リヤフェンダー後部の大型エアアウトレットなど、空力を追求したダイナミックなフォルムが実感たっぷりにモデル化されています。また、2段タイプの大型リヤウイングも見どころの一つで、ディスプレイモデルとしても十分な存在感があります。
カラーリングは、ホワイトをベースにレッドとブラックをあしらったアグレッシブなデザインで、実車のイメージを忠実に再現しています。スポンサーロゴなどの複雑なグラフィックはステッカーで用意されているため、貼り付けるだけで本格的なラリーカーの雰囲気を手軽に楽しむことができます。
完成時のサイズは全長156mm、全幅97mm、全高49mm(公式情報では44mmという記載もあります)となっています。プロポーションはコンパクトながらも、ラリーカーとしての力強さと迫力を十分に感じられる仕上がりになっています。
ミニ四駆ファンにとっては、実車レプリカとしての魅力だけでなく、走らせる楽しさも兼ね備えたモデルとなっており、コレクションアイテムとしても、実際に走らせるマシンとしても、どちらの楽しみ方も満足できる一台と言えるでしょう。
MAシャーシの採用により優れた走行性能を実現したヤリスWRC
ヤリスWRCミニ四駆は、走行性能にこだわったMAシャーシを採用しています。MAとはMidship AERO(ミドシップエアロ)の略で、その名の通り、ダブルシャフトモーターを車体中央に搭載したミドシップレイアウトが特徴です。
このMAシャーシは、ミドシップレイアウトの「MSシャーシ」と走行中の気流(エアロ)を特に意識してデザインされた「ARシャーシ」、それぞれの優れた特徴を1台のシャーシにまとめあげたものです。これまでに蓄積されたレーシングノウハウを活かして、3.5:1のギヤ比を採用し、6個の低摩擦樹脂ローラーやリヤスキッドバーも標準装備するなど、走行性能も徹底的に磨き上げられています。
特筆すべきは一体型のモノコック構造の採用で、組み立てやすさやメンテナンス性が大幅に向上しています。これにより、初心者からベテランレーサーまで、また小さめのコースで行われる街かどレースから大型の特設5レーンサーキットの公認競技会まで、幅広く対応できるシャーシとなっています。
標準でダブルシャフトモーターが付属しており、さらにディッシュホイール(シルバー)と小径ローハイトタイヤ(ブラック)を装着。リヤステーには13mmダブルローラーを装着し、6個のローラーはすべて低摩擦樹脂製となっています。リヤスキッドバーやサイドステーも標準装備されているため、購入してすぐに本格的な走りを楽しむことができます。
MAシャーシのボディはABS樹脂製のブラックカラーで統一されており、レーシーなボディを引き立てる効果もあります。走行性能と見た目の両方にこだわった設計は、ミニ四駆ファンを満足させるクオリティと言えるでしょう。
ヤリスWRCの価格は約1,000円とコスパ最高のミニ四駆
ヤリスWRCミニ四駆の魅力の一つは、そのコストパフォーマンスの高さです。メーカー希望小売価格は1,320円(税込)ですが、実際の店頭価格や通販サイトでは約800円〜1,000円程度で購入できることが多いです。これだけ本格的なラリーカーモデルでありながら、1,000円前後という価格設定は非常にリーズナブルと言えるでしょう。
私の調査によると、2025年4月現在のオンラインストアでの価格は以下の通りです:
- Amazon:882円(税込)
- ビックカメラ:971円(税込)
- ヨドバシカメラ:971円(税込)
- タミヤ公式オンラインストア:1,320円(税込)
このように、実店舗よりもオンラインショップの方が若干安い傾向にあります。ただし、送料が別途かかる場合もあるので、最終的な購入コストを考慮して選ぶと良いでしょう。
さらに、このモデルを走らせるためには別途単3形電池2本が必要になります。また、よりよい走行性能を求める場合は、ベアリングやホイール、タイヤなどの交換パーツも追加で購入することになりますが、基本モデル自体が安価なので、改造にもお金をかけやすいという利点があります。
ヤリスWRCは組み立て式なので、接着剤不要のはめ込み式で簡単に組み立てることができます。この手軽さも初心者やお子さんにとっては大きなメリットです。世界的に有名なラリーカーを自分の手で組み立て、走らせることができる喜びを、これほどの低価格で提供してくれるのは素晴らしいと言えるでしょう。
コレクションとしての価値も高く、発売から数年経った今でも人気が衰えていないことからも、その高いコストパフォーマンスが証明されています。ミニ四駆初心者の方にも、トヨタやラリーカーファンの方にも、自信を持っておすすめできる一台です。
ステッカー約50枚の貼り付けでリアルなカラーリングを実現できる楽しさ
ヤリスWRCミニ四駆の魅力の一つが、その本格的なカラーリングです。実車のラリーカーと同様のレッドとブラックをあしらったアグレッシブなグラフィックが再現されていますが、この複雑なカラーリングはステッカーで表現されています。
ブログ記事やレビューによると、ヤリスWRCに付属するステッカーは約50枚にもなります。数が多いため貼り付け作業は時間がかかりますが、その分完成したときの満足感は格別です。ステッカーはホワイトのABS樹脂製ボディに貼り付けるだけで、複雑なカラーリングが手軽に仕上がるように設計されています。
ステッカー貼りのコツとしては、神経質になりすぎず楽しむことが重要です。特に初めてミニ四駆を組み立てる方にとっては、ステッカーの位置合わせが難しく感じるかもしれませんが、綿棒などを使って細かい調整をすると綺麗に貼ることができます。また、ステッカーを貼る前に部品の向きをしっかり確認することで、貼り間違いを防げます。
ある方のブログでは「シールを貼る枚数は多いですが、神経質になって貼らなくていいので気が楽で楽しい」という感想が紹介されていました。また別のレビューでは「孫のため購入しましたが、ステッカーが細かく、老眼が悪化しました。でも、苦労した成果はバッチリ!本物みたいにカッコいい!!」という声もありました。
なお、走行させるとステッカーがはがれやすくなる場合があります。これを防ぐためには、ステッカーを貼った後にクリアコートでコーティングするという方法もあります。これによりステッカーの耐久性が向上し、長く美しい状態を保つことができます。
ステッカー貼りは手間がかかる作業ですが、それも含めてミニ四駆の醍醐味と言えるでしょう。出来上がった際の達成感と、リアルなラリーカーとしての見栄えは、その労力に十分に見合うものです。
塗装が必要な部分はウイングとボンネットインテークのみで初心者にも挑戦しやすい設計
ヤリスWRCミニ四駆は、ステッカーで多くの部分のカラーリングが再現できる一方で、いくつかの部分は塗装が必要となります。調査によると、主な塗装が必要な部分は以下の3箇所です:
- リヤウイング
- ボンネットインテーク
- サイドミラー周り
これらの部分は黒で塗装する必要があります。幸いなことに、黒は塗装しやすい色で、はみ出してもステッカーで隠れる部分が多いため、初心者でも比較的挑戦しやすいと言えるでしょう。
実際にブログ記事では「黒は塗装しやすい色です。またはみ出してステッカーで隠れるので大胆に筆塗りができます。無塗装だと目立つので塗装した方がいいと思います。」という記述がありました。
塗装のコツとしては、まずはパーツを切り離す前に塗装することで、取り扱いが容易になります。また、マスキングテープを使って塗り分けをすることで、綺麗な仕上がりを目指すことができます。特にリヤウィンドウ部分は複雑な形状をしているため、マスキングに工夫が必要です。
実際に塗装に挑戦した方のブログでは、「朝の5時から塗装。指定色など持ち合わせていなかったので、マットブラックで塗装した」「マスキングを剥がしてみると、微修正する箇所が少々。不器用なワタクシにしてはキレイな仕上がりだ」といった体験談が紹介されています。
また、塗装に抵抗がある方や初めての方でも、リヤウイングなどの黒パーツはしっかり塗装した方が見栄えが良くなるため、挑戦する価値は十分にあります。塗装をしないまま組み立てると、モデルとしての完成度が下がってしまうので、基本的には塗装することをおすすめします。
ヤリスWRCは塗装が必要な部分が少なく、主に黒一色という単純な塗装で済むため、初めて塗装に挑戦する方にもぴったりのモデルと言えるでしょう。
実車のヤリスWRCとデザインの違いはミニ四駆ならではの制約による変更点
ヤリスWRCのミニ四駆は実車を忠実に再現しようとしていますが、ミニ四駆という形態ならではの制約から、いくつかのデザイン上の変更点があります。これらの違いを理解することで、モデルをより深く鑑賞することができるでしょう。
最も顕著な違いはフロント周りのデザインです。実車のヤリスWRCはフロントのラジエーターが大きく、フロントフェンダーに特徴があります。しかし、ミニ四駆ではバンパー部分との干渉を避けるためにフロント周りの形状を変更せざるを得ませんでした。
ある方のブログでは「フロント周りの変更だけでも『これじゃない』のですが、変更されたフロント周りの『辻褄をあわせる為』にボンネットも変更されています。それがまた後ろのデザインに影響するなどフロントの周りの辻褄あわせした結果全体的に何か微妙にズレた感じがします」と指摘されています。
また、実車がフロントエンジンであるのに対し、ミニ四駆のMAシャーシはミドシップレイアウトになっているという違いもあります。この点について、「最初からMAでなく実車と同じくフロントにパワーユニットがある『FMAシャーシ』で発売もそれはそれで良かった気がします」という意見もあります。
興味深いことに、ボディをFMAシャーシに載せることも可能です。ただし「そのままだとタイヤとフェンダー(タイヤハウス)が干渉するので、少し調整する必要があります」と指摘されています。
また、ボディーがポリカーボネイト製ではなく、プラスチック製であることも特徴の一つです。「ポリカが良かったかな。いやプラボディで良いのか」と迷う声もありますが、「ボディ改修(パテ盛り)する場合 プラボディの方が都合良いのかな」という意見もあり、一長一短があります。
これらの違いはあるものの、全体としてはWRCラリーカーとしての雰囲気や特徴をよく捉えており、ミニ四駆という制約の中で最大限に実車の魅力を再現しようとする工夫が感じられます。実車との違いを理解した上で楽しむことで、より深くヤリスWRCミニ四駆の魅力を味わうことができるでしょう。
ミニ四駆のヤリスWRCを改造・カスタマイズする方法
- ベアリングとホイール交換でヤリスWRCの走行性能を大幅アップできる方法
- ヤリスWRCボディを塗装する際のコツとマスキング技術
- 窓をくり抜いて内装を作る創造的なヤリスWRC改造テクニック
- MAシャーシ以外にもFMAシャーシへの換装が可能なヤリスWRCの互換性
- ヤリスWRCとGRヤリス(VZシャーシ)の違いと選び方
- トヨタGRスープラとの比較:同じMAシャーシを採用した姉妹モデル
- まとめ:ミニ四駆ヤリスWRCは組み立てやすさと改造の自由度で初心者からベテランまで楽しめる一台
ベアリングとホイール交換でヤリスWRCの走行性能を大幅アップできる方法
ヤリスWRCミニ四駆の走行性能を向上させるためには、ベアリングとホイールの交換が非常に効果的です。標準装備でもそれなりの性能を持っていますが、いくつかのパーツを交換することで、より高いパフォーマンスを引き出すことができます。
まず、軸受けをベアリングに交換することで大きな効果が得られます。ブログによると、「ベアリングはロマンなので、必ず装着しなくてはイケナイ」と熱心なミニ四駆ファンは語っています。具体的には、620ベアリングと520ベアリングを用いることで、摩擦を減らし、スムーズな回転を実現することができます。第一ブームの頃ならマシンが1台買える高級品だったようですが、今ではより手頃な価格で入手可能です。
次に、シャフトをステンレス中空シャフトに交換することも推奨されています。これは通常のシャフトよりも軽量で精度が高く、「かなり軽い上に精度が高い」という特徴があります。軽量化によって加速性能が向上し、精度の高さで安定した走行が期待できます。
さらに、ホイールとタイヤの交換も効果的です。例えば、「ローハイトワンウェイホイール」と「スーパーハードタイヤ」の組み合わせが紹介されていました。「タイヤにプリントがしてあると映える」という美観面での魅力もあります。ワンウェイホイールについては、「普通のホイールでは得られ難いドキドキ感がある」という感想もあり、走行の楽しさを増す要素となっています。
また、ギアにもベアリングを入れることで、さらなる効率化が図れます。「タイプシャーシの頃には確かギヤにはベアリングが無かったような気がする」という感想もありますが、現在ではギアにもベアリングを入れることが一般的になっているようです。
これらの改造によって、外観では「タイヤ、ホイール交換をしただけだが、スポーティ感が増してカッコいい」というように、見た目の魅力も向上します。実車でもホイール選びは車の印象を大きく左右するように、ミニ四駆においてもホイール選びは重要なポイントです。
ヤリスWRCの場合、「トルクチューンモーターを搭載」「ギヤ比は現在4:1」といった改造例も見られ、ラリーカーらしく最高速よりもトルクを重視する傾向があるようです。
ヤリスWRCボディを塗装する際のコツとマスキング技術
ヤリスWRCのボディを塗装する際には、いくつかのコツとマスキング技術を知っておくことで、より美しい仕上がりを実現することができます。特にこのモデルは、元々ホワイトボディに一部塗装が必要な部品があるため、塗装初心者でも挑戦しやすい構造になっています。
最も重要なのは、マスキング作業です。複雑な形状の部分を塗り分ける際には、マスキングテープを使って正確に境界を作ることが重要です。例えば、あるブログではリヤウィンドウ部の塗り分けについて、「塗り分け超面倒い。とりあえず少ない知恵を絞ってマスキング開始」と記述されています。この方はリヤウイングに合わせてマスキングテープを貼り、ウイングの下部分に合わせてカットするという工夫をしていました。
また、塗装順序も重要なポイントです。基本的には、まずD3パーツ(リヤウイング部)やD2パーツ(リヤウィンドウ部)などのパーツごとに塗装を行い、その後ボディ本体の塗装に移るという方法が効率的です。塗装前にはダボ軸などの接合部分をマスキングしておくことも忘れないようにしましょう。
塗料の選択も仕上がりに大きく影響します。ヤリスWRCの場合、黒で塗装する部分が多いため、マットブラックを使用している例が多く見られます。「指定色など持ち合わせていなかったので、マットブラックで塗装した」という体験談もありましたが、マットブラックは光沢のない落ち着いた質感が特徴で、ラリーカーの力強い印象によく合います。
塗装後のマスキング剥がしも慎重に行いましょう。「マスキングを剥がしてみると、微修正する箇所が少々」という記述があるように、完璧な塗り分けを目指すのではなく、ある程度の修正を見込んで作業を進めることが現実的です。
さらに、ステッカーとの相性も考慮することが大切です。「シールを貼らないと変なバランスだ。しかし、マットブラックの風合いはカッコいい」というように、塗装だけでなくステッカーを貼ることで初めて完成形になることを念頭に置いておくと良いでしょう。
塗装は技術と経験が必要な作業ですが、ヤリスWRCのように必要な部分が限られているモデルなら、初心者でも挑戦しやすいでしょう。失敗を恐れず、楽しみながら取り組むことが大切です。
窓をくり抜いて内装を作る創造的なヤリスWRC改造テクニック
ヤリスWRCミニ四駆をさらに個性的なモデルに仕上げる方法の一つに、窓をくり抜いて内装を作るという創造的なカスタマイズ方法があります。これは単なる走行性能の向上ではなく、見た目の楽しさを追求する改造です。
ブログ記事によると、「『窓』ぶち抜きます」という挑戦をしている方がいます。この方の動機は「走らせるのに軽量化のためとかタイムアップのためとかそんな理由じゃなくて単に『誰か乗っけられるかな~?』そんなとこです・・・」と語っており、純粋に楽しみのための改造であることがわかります。
窓をくり抜く際のポイントは、専用の工具を使うか、カッターナイフで丁寧に切り抜くことです。切り抜いた後は、エッジを滑らかに整えることで見栄えが良くなります。また、透明なプラスチック板(プラ板)を窓部分に貼ることで、よりリアルな仕上がりになります。「ちなみにウインドシールドだけプラ板貼ってます」という記述から、この方法が効果的であることがうかがえます。
内装を作成する際には、フィギュアや自作のシートなどを配置することで、リアリティが増します。ブログでは「くまモンバージョンGT」のシャーシを借用して、「だれか乗せようかな?」と考えていましたが、最終的には「予期せず発揮されました」とのことで、何らかのフィギュアを配置できたようです。
この改造法の良い点は、単に走らせる楽しさだけでなく、飾って楽しむ要素が増えることです。窓がくり抜かれていることで、中が見え、より立体的で奥行きのある作品になります。特に子供とミニ四駆を楽しむ場合、「誰が乗っているか」という物語性を加えることができ、想像力を刺激する効果もあります。
ただし、窓をくり抜くことでボディの強度が下がる可能性があるため、激しい走行を前提とする場合は注意が必要です。また、くり抜いた部分の処理が雑だと全体の印象が損なわれるため、丁寧な作業が求められます。
この改造はヤリスWRCに限らず様々なミニ四駆で応用可能ですが、ラリーカーという性格上、ドライバーとコ・ドライバーを配置することで、よりラリーらしさを演出できるというメリットがあります。
MAシャーシ以外にもFMAシャーシへの換装が可能なヤリスWRCの互換性
ヤリスWRCミニ四駆は標準でMAシャーシを採用していますが、実はFMAシャーシへの換装も可能という高い互換性を持っています。これにより、マシンの特性を変えたり、より実車に近いレイアウトを実現したりすることができます。
ブログ記事では「リアのキャッチ周辺をパチンとするだけでFMAシャーシに載ります」と説明されており、比較的簡単にシャーシを換装できることがわかります。FMAシャーシは、フロントにモーターを搭載するレイアウトで、実車のヤリスWRCがフロントエンジンであることを考えると、よりプロトタイプに近い構成と言えるでしょう。
ただし、単純に換装するだけでは問題が生じる場合があります。同じブログでは「ただ載るのですが、そのままだとタイヤとフェンダー(タイヤハウス)が干渉するので、少し調整する必要があります」と指摘されています。ボディとシャーシの相性を確認し、必要に応じてボディの一部を削ったり、ホイールやタイヤを変更したりするなどの対応が必要になるでしょう。
FMAシャーシに換装するメリットとしては、以下のようなポイントが考えられます:
- 実車のレイアウトに近づける(フロントモーター)
- 前輪駆動のハンドリング特性を体験できる
- コース形状によっては相性が良い場合がある
- 新しい走りの楽しさを発見できる
「最初からMAでなく実車と同じくフロントにパワーユニットがある『FMAシャーシ』で発売もそれはそれで良かった気がします」という意見もあり、ヤリスWRCとFMAシャーシの組み合わせに興味を持つユーザーは少なくないようです。
また、シャーシを換装することで、既存のパーツストックを活用できるというメリットもあります。たとえば、既にFMAシャーシのマシンを持っている場合、モーターやギアなどの部品を流用することができます。
シャーシ換装は比較的上級者向けの改造ではありますが、換装自体は「パチンとするだけ」という手軽さも魅力です。ヤリスWRCの高い互換性を活かし、様々なシャーシで走らせることで、一台のマシンでより多様な走りを楽しむことができるでしょう。
ヤリスWRCとGRヤリス(VZシャーシ)の違いと選び方
タミヤのミニ四駆シリーズには、「トヨタ ガズーレーシング WRT/ヤリスWRC」と「トヨタ GR ヤリス」という二つの似たモデルが存在します。どちらもトヨタのヤリスをベースにしていますが、いくつかの重要な違いがあります。
まず、大きな違いはシャーシです。ヤリスWRCはMAシャーシを採用しているのに対し、GRヤリスはVZシャーシを採用しています。MAシャーシはミドシップレイアウトで、モーターを車体中央に配置しているのに対し、VZシャーシはフロントモーターのレイアウトとなっています。このため、走行特性が大きく異なります。
外観の面では、ヤリスWRCは2019年のWRC(世界ラリー選手権)を戦ったラリーカーをモデルとしており、オーバーフェンダーやカナード、大型リヤウイングなど、モータースポーツ仕様の特徴的なエアロパーツを装備しています。一方、GRヤリスは市販のスポーツモデルをベースとしており、よりストリート向けのデザインとなっています。
価格面でも違いがあります。商品番号18654のヤリスWRC(MAシャーシ)の価格が約800円〜1,000円程度であるのに対し、商品番号18097のGRヤリス(VZシャーシ)は約800円程度とやや安価な傾向があります。
さらに、細かな点では、ステッカーの量や塗装が必要な部分の違いもあります。ヤリスWRCはラリーカー特有の複雑なスポンサーロゴなどがステッカーで再現されており、約50枚のステッカーを貼る必要があります。一方、GRヤリスはよりシンプルなデザインで、ステッカーの数も比較的少なくなっています。
どちらを選ぶべきかについては、以下の点を考慮すると良いでしょう:
- 走行性能重視: MAシャーシのヤリスWRCは高速走行や安定性に優れており、ダブルシャフトモーターによる力強い走りが特徴です。一方、VZシャーシのGRヤリスはコーナリングの楽しさを重視したい方に向いています。
- 見た目重視: 派手なラリーカー風の外観を楽しみたい方はヤリスWRCが、よりストリートに近いスポーツカーの雰囲気を楽しみたい方はGRヤリスが適しています。
- 組み立ての難易度: ステッカーの量が多いヤリスWRCは組み立てに時間がかかりますが、その分完成時の達成感は大きいです。より手軽に組み立てたい方にはGRヤリスがおすすめです。
- コレクション: どちらも魅力的なモデルなので、トヨタやヤリスのファンであれば、両方揃えるのも一つの楽しみ方です。
どちらのモデルもトヨタのモータースポーツの魅力を伝える素晴らしいミニ四駆であり、それぞれの特徴を活かした楽しみ方ができます。
トヨタGRスープラとの比較:同じMAシャーシを採用した姉妹モデル
2020年にタミヤから発売された「トヨタ GR スープラ」(商品番号18655)は、ヤリスWRCと同じMAシャーシを採用した姉妹モデルと言える存在です。両モデルは同じシャーシを使用していますが、車種の特性やデザインコンセプトなどに違いがあります。
まず、外観の大きな違いはボディスタイルです。ヤリスWRCがハッチバックタイプのラリーカーであるのに対し、GRスープラはスポーツクーペタイプの車両です。あるブログでは「実車でハッチバックを良くみるので、ミニ四駆ぐらいはセダン(トランク)を見たいと言う気持ちはあります」という意見があり、ボディスタイルの違いが好みの分かれ目になることもあるようです。
カラーリングの面では、ヤリスWRCがラリーカー特有の複雑なスポンサーデカールが特徴なのに対し、GRスープラはよりシンプルで洗練されたデザインとなっています。このため、ステッカー貼りの手間は、GRスープラの方が若干少ないと言えるでしょう。
走行性能については、同じMAシャーシを採用しているため基本的な特性は共通していますが、ボディ形状の違いによる空力特性の差はあるかもしれません。ヤリスWRCの方が大型ウイングなどの空力パーツが多いため、高速走行時の安定性で優れている可能性があります。
価格面では、ヤリスWRCが約800円〜1,000円程度であるのに対し、GRスープラも同程度の価格帯で販売されています。両方ともコストパフォーマンスの高いモデルと言えるでしょう。
改造やカスタマイズの幅については、同じMAシャーシを採用しているため、基本的な改造パーツの互換性は高いです。ただし、ボディ形状に合わせたパーツ選びは異なってきます。
コレクション価値という観点では、ヤリスWRCはモータースポーツファンに、GRスープラはスポーツカーファンにそれぞれ人気があります。トヨタのGAZOOレーシングブランドを網羅的に集めたい方には、両方とも魅力的な選択肢となるでしょう。
「WRCに興味ないミニ四レーサーでもミニ四駆化によりヤリスWRCの認知度が上がった」という指摘があるように、これらのモデルはミニ四駆を通じて実車の魅力を伝える役割も果たしています。実車のファンでミニ四駆に興味を持った方も、ミニ四駆ファンで実車に興味を持った方も、それぞれの魅力を楽しめる商品と言えるでしょう。
まとめ:ミニ四駆ヤリスWRCは組み立てやすさと改造の自由度で初心者からベテランまで楽しめる一台
最後に記事のポイントをまとめます。
- ヤリスWRCミニ四駆は2019年のWRC参戦マシンを再現したタミヤの公式ミニ四駆モデル
- 価格は約800円~1,000円とコストパフォーマンスに優れている
- MAシャーシを採用しており高い走行性能を持つ
- 約50枚のステッカーを貼ることでリアルなラリーカーの外観を再現可能
- リヤウイング、ボンネットインテーク、サイドミラー周りは黒で塗装する必要がある
- 実車とはフロント周りのデザインなどに若干の違いがある
- ベアリングやホイール交換で走行性能を大幅に向上させることができる
- MAシャーシだけでなくFMAシャーシへの換装も可能で実車に近いレイアウトを再現できる
- 窓をくり抜いて内装を作るなどの創造的なカスタマイズも人気
- 同じトヨタブランドの「GRヤリス」(VZシャーシ)とは異なるコンセプトと特徴を持つ
- 「GRスープラ」(MAシャーシ)とは姉妹モデルの関係にあり同じシャーシを採用
- WRCやラリーカーの認知度向上にも貢献している魅力的なミニ四駆モデル