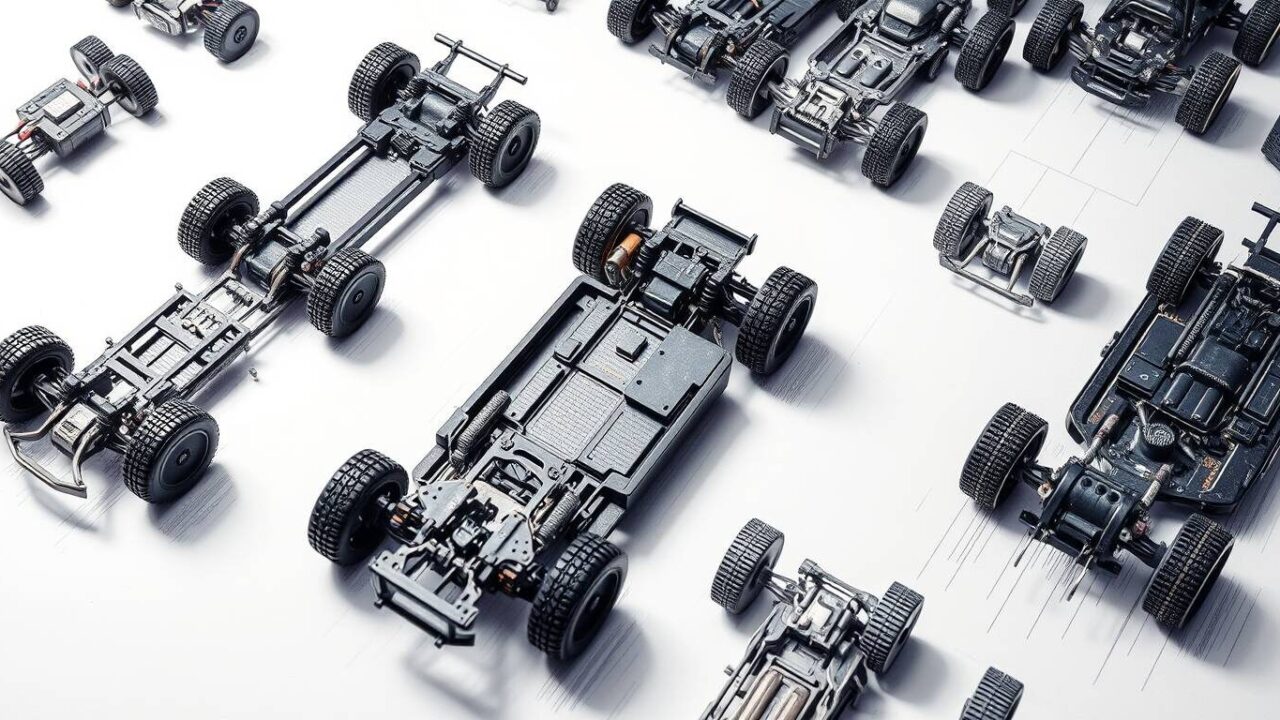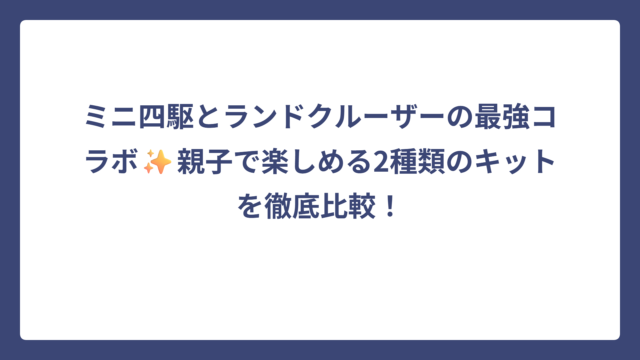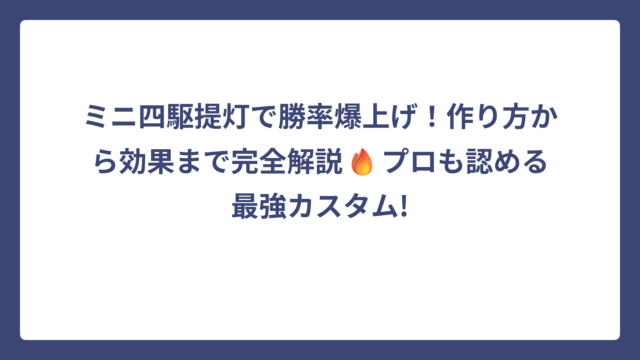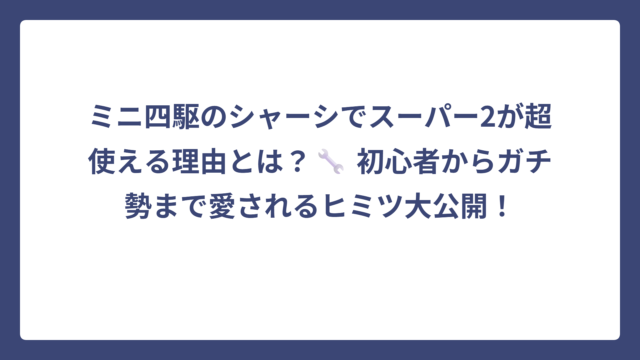ミニ四駆のスライドダンパー(スラダン)は、コースの壁に衝突した際の衝撃を吸収し、安定した走行を実現するための重要なパーツです。市販品も販売されていますが、自作することで自分のマシンやコースに最適なスラダンを作ることができます。
本記事では、スラダンの基本的な役割から、ATスラダンや左右独立スラダンなどの様々なタイプの作り方、そして効果的な調整方法まで詳しく解説します。必要な材料や工具、製作手順からよくある失敗とその対策まで網羅的に紹介するので、初心者から上級者まで役立つ内容となっています。
記事のポイント!
- スライドダンパーの役割と効果、種類別の特徴について学べる
- 初心者でも作れるATスラダンから上級者向けの左右独立スラダンまで詳細な作り方を知ることができる
- スラダン製作に必要な材料や工具の選び方、準備方法が分かる
- スライドダンパーの調整方法や失敗しないコツを習得できる
ミニ四駆スラダン作り方の基本と効果
- スライドダンパーの役割はコース走行の安定性向上
- 市販のスライドダンパーと自作の違いは製作難易度と調整幅
- 自作スラダンに必要な材料はFRPやカーボンステーが基本
- 工具の準備はリューターとドリルが必須アイテム
- スラダンを作る前に知っておくべき3つのポイント
- 左右独立式と一体型の違いは衝撃吸収の仕組み
スライドダンパーの役割はコース走行の安定性向上
スライドダンパー(スラダン)は、ミニ四駆がコースを走行する際に壁に衝突したときの衝撃を吸収し、マシンの安定性を向上させる重要なパーツです。通常、フロントバンパーに取り付けられ、左右にスライドする機構によって衝撃を和らげます。
スラダンがない状態でコースの壁に衝突すると、その衝撃でマシンが大きく跳ね返されたり、コースアウトしたりする可能性があります。スラダンがあれば、衝突時の衝撃がスプリングによって吸収され、マシンは安定した走行を続けることができます。
特にコーナリング時や高速走行時には、スラダンの効果が顕著に現れます。壁との接触が避けられない場面でも、マシンの速度を大幅に落とすことなく走行を継続できるのです。
公式大会などの上級者はほとんどがスラダンを装備しており、それだけスラダンがミニ四駆のパフォーマンスに与える影響が大きいことを示しています。スラダンの装着は、「速く走る」だけでなく「安定して走る」ための重要な要素なのです。
さらに、スラダンの効果は単なる衝撃吸収だけではありません。コースのセクションに応じた最適なセッティングによって、さらに走行性能を引き出すことも可能です。初心者から上級者まで、スラダンの効果を体感することで、ミニ四駆の走りが格段に向上するでしょう。
市販のスライドダンパーと自作の違いは製作難易度と調整幅
ミニ四駆のスライドダンパーには、市販品と自作品があります。それぞれに特徴があるので、自分のニーズに合わせて選択するとよいでしょう。
市販のスライドダンパーの最大の利点は、すぐに使用できる手軽さです。タミヤから販売されているフロントワイドスライドダンパーやカーボンスライドダンパーなどは、パッケージを開けてシャーシに取り付けるだけで基本的な機能を発揮します。初心者や時間のない方には、この手軽さが大きな魅力となります。
一方、自作スラダンの魅力は、自分のマシンや走行スタイルに合わせたカスタマイズが可能な点です。スライドの硬さ、可動域、スラスト角など、細かな調整が自由にできます。また、市販品にはない左右独立式など、より高度な機構も実現できます。特に、競技志向の強い方には、この調整幅の広さが大きなメリットになります。
製作難易度については、市販品が圧倒的に簡単である一方、自作は工具や技術が必要になります。しかし、基本的な工具さえあれば、独自調査の結果、初心者でも比較的簡単に製作できるタイプのスラダンもあります。
コスト面では、市販品は手軽ですが、自作の場合は既に持っているパーツを流用できるため、場合によってはコストを抑えることも可能です。また、一度工具を揃えれば、複数のスラダンを作ることもできるため、長期的にはコスト効率が良くなることもあります。
自作スラダンは、失敗を重ねながら自分だけの最適解を見つける楽しさもあります。ミニ四駆の理解を深める良い機会にもなるでしょう。どちらを選ぶにしても、自分の目的や環境に合わせた選択が大切です。
自作スラダンに必要な材料はFRPやカーボンステーが基本

自作スラダンを作るには、いくつかの基本的な材料が必要です。主要な材料と、それぞれの役割を紹介します。
まず、スラダンの本体となるステー材には、FRP(ガラス繊維強化プラスチック)またはカーボン製のステーが使われます。特に「カーボンマルチワイドリヤステー」や「FRPマルチワイドリヤステー」が多く使用されます。これらは適度な強度と弾性を持ち、加工もしやすいため、スラダンの材料として最適です。
カーボン製は軽量で強度が高いですが、価格が高く、加工が難しい傾向があります。一方、FRP製は比較的安価で加工しやすいですが、強度はやや劣ります。初心者の方は、まずはFRP製から始めるのがおすすめです。
スプリングは、スラダンの中核となる部品です。タミヤから販売されている「ミニ四駆PROスライドダンパースプリングセット」などが使われます。スプリングの硬さによって、スラダンの特性が大きく変わるため、複数の硬さのものを用意しておくとよいでしょう。一般的には、黒(柔らかい)、青(中間)、銀(硬め)、金(最も硬い)などの種類があります。
また、スライド機構を作るためのビス、ナット、スペーサー、ワッシャーなども必要です。特に、2mmのトラスビスとロックナットは、スラダンの組み立てに欠かせません。
その他、既製品のスライドダンパーパーツを利用する場合は、「フロントワイドスライドダンパー」の上蓋やアルミプレートを使用することで、製作が容易になります。アルミプレートは加工時の型枠としても活用できます。
フロント提灯(ローラー)を取り付ける場合は、それに適した径のパイプやブッシュも必要になります。
これらの材料は、ミニ四駆専門店やオンラインショップなどで入手可能です。全て揃えると少し費用がかかりますが、一度購入すれば複数のスラダンを作ることができます。
工具の準備はリューターとドリルが必須アイテム
自作スラダンを製作するには、いくつかの工具が必須になります。適切な工具を用意することで、正確かつ効率的に作業を進めることができます。
最も重要な工具は電動リューターです。リューターを使用することで、カーボンやFRPステーの精密な加工が可能になります。特にスライドレールやスプリングスペースを作るための穴拡張作業には、欠かせない工具です。リューター用のビットは、円筒形や先端が細いものなど、複数のタイプを用意しておくとよいでしょう。
リューターがない場合は、ドリルとヤスリで代用することも可能ですが、作業効率と精度が大幅に落ちてしまうため、本格的にスラダンを作る予定があるなら、リューターへの投資を検討する価値があります。
ドリルもまた必須アイテムです。3mmドリルを使って既存のビス穴を拡張したり、新たに穴を開けたりする作業に使用します。ハンドドリルでも可能ですが、電動ドリルがあるとより効率的に作業できます。
小さめの棒ヤスリは、スプリングスペースの角を整えるなど、リューターでは難しい細かな加工に役立ちます。特に四角形のスプリングスペースを作る際には、角を直角に仕上げるために棒ヤスリは不可欠です。
その他、ニッパー、ピンセット、ドライバー(プラスドライバーとボックスドライバー)なども基本的な作業に必要です。また、パーツの固定にはマスキングテープやマルチテープなどの補助工具も役立ちます。
グリスやスキッドシールを使用する場合は、ミニ四駆用のオイルペンなども準備しておくとよいでしょう。これらを使用することで、スラダンのスムーズな動作を実現できます。
これらの工具はミニ四駆の改造全般に役立つものなので、一度揃えておけば様々な場面で活用できます。初めは基本的な工具だけを揃え、徐々に必要に応じて追加していくのもよいでしょう。
スラダンを作る前に知っておくべき3つのポイント
スライドダンパーを自作する前に、いくつか重要なポイントを押さえておくことで、失敗を防ぎ、効率的に製作を進めることができます。
1つ目のポイントは、「目的に合ったスラダンのタイプを選ぶ」ことです。ATスラダン、左右独立スラダン、一体型スラダンなど、様々なタイプがあります。コースレイアウトや自分の走行スタイルに合わせて、最適なタイプを選びましょう。例えば、複雑なコーナーが多いコースでは左右独立式が有利ですが、製作難易度も高くなります。初心者の方は、まずはATスラダンや一体型から始めるのがおすすめです。
2つ目のポイントは、「適切な素材選び」です。特にステー材は重要で、カーボン製は軽量で強度が高い一方、加工が難しいという特徴があります。FRP製は加工しやすいですが、強度はやや劣ります。初めてスラダンを作る場合は、加工のしやすさを優先してFRP製を選ぶとよいでしょう。また、強度を確保するために、複数枚のステーを重ねて使用する方法もあります。
3つ目のポイントは、「加工精度を重視する」ことです。スライドレールの幅やスプリングスペースの大きさなど、細かな部分の精度がスラダンの性能に大きく影響します。一度削りすぎると修正が難しいので、「少しずつ削って確認する」という慎重な姿勢が重要です。特に、スライドレールの削りすぎは、バンパーのガタつきの原因になるので注意が必要です。
また、製作前にはシャーシとの干渉や取り付け方法も確認しておきましょう。シャーシの種類によって最適なスラダンの形状が異なる場合があります。例えば、VZシャーシとMA・MSシャーシでは、バンパーの位置が異なるため、干渉箇所のカット具合も変わってきます。
これらのポイントを押さえた上で計画的に作業を進めれば、初心者でも満足のいくスラダンを作ることができるでしょう。失敗を恐れずに、少しずつ挑戦してみてください。
左右独立式と一体型の違いは衝撃吸収の仕組み
ミニ四駆のスライドダンパーには、大きく分けて「左右独立式」と「一体型」の2つのタイプがあります。それぞれの特徴と違いを理解することで、自分のマシンに最適なスラダンを選択できます。
一体型スラダンは、バンパー全体が左右に動く仕組みです。構造がシンプルで製作も比較的容易なため、初心者にもおすすめです。衝撃を受けると、バンパー全体がスライドして衝撃を吸収します。中央のスプリングが衝撃を受け止め、バンパー全体が動くため、左右どちらからの衝撃も同様に吸収できます。ただし、左右両方から同時に衝撃を受けた場合は、十分な効果を発揮できないことがあります。
一方、左右独立式スラダンは、左右のバンパーが独立して動く仕組みです。左右それぞれにスプリングを設置するため、片側だけが衝撃を受けても効果的に吸収できます。複雑なコーナーが連続するコースや、左右から交互に衝撃を受けるような状況で特に効果を発揮します。また、左右で異なる硬さのスプリングを使用することで、コースの特性に合わせた細かい調整も可能です。
製作難易度は左右独立式の方が高く、特に軸の加工やスプリングの配置などに技術が必要です。しかし、走行安定性という点では左右独立式の方が優れていることが多いです。
左右独立式の中にも様々なバリエーションがあり、「2軸タイプ」と「1軸タイプ」などがあります。2軸タイプは安定性が高い一方、1軸タイプは軽量化が図れるというメリットがあります。
また、純正のスラダンを改造して左右独立式にすることも可能です。これは、完全な自作よりも簡単な方法として、中級者におすすめの方法です。
コース特性や自分の技術レベルを考慮して、最適なタイプを選択するとよいでしょう。初めてスラダンを作る場合は、一体型から始めて、徐々に左右独立式にチャレンジするという方法もおすすめです。
ミニ四駆スラダン作り方の実践ガイド
- ATスラダンの作り方は既存パーツの組み合わせが簡単
- 左右独立スラダンの作り方はカーボンステーの加工がポイント
- 純正スラダンを改造する方法はビス穴の拡張から始める
- スラダンの調整方法はスプリングの硬さとビスの締め具合
- スラダン作りでよくある失敗は削りすぎと締めすぎ
- スムーズな動きを実現するコツはグリスとスキッドシールの活用
- まとめ:ミニ四駆スラダン作り方のポイントは素材選びと精密な加工
ATスラダンの作り方は既存パーツの組み合わせが簡単
ATスラダン(ATスライドダンパー)は、市販パーツを組み合わせることで比較的簡単に作ることができるスライドダンパーです。初心者の方にもおすすめの作り方を紹介します。
まず必要なパーツは、フロントワイドスライドダンパー、カーボンマルチワイドリヤステーまたはFRPマルチワイドリヤステー、そしてカーボンマルチ強化プレートです。これらのパーツは比較的入手しやすく、ミニ四駆専門店やネット通販で購入できます。
作り方の手順は以下のとおりです:
- カーボンマルチワイドリヤステーを使って、スライドレールとスプリングスペースを作ります。既存のビス穴をリューターで拡張し、スライドレールとスプリングスペースを形成します。スライドアルミプレート(フロントワイドスライドダンパーに付属)を型枠として使うと、正確な加工が可能です。
- スライドレールは、アルミプレートの形に合わせて削りますが、カーボンマルチステーの強度を保つために、外側は必要以上に削らないよう注意します。特に表面ばかり見ているとカーボンマルチステーの削れ具合に気付かないので、裏面も確認しながら慎重に削りましょう。
- スプリングスペースは四角形に削り、スプリングがきれいに収まるようにします。リューターで削った後、棒ヤスリで四隅を角ばった状態に整えます。スプリングを実際に入れてみて、綺麗に収まるかチェックしましょう。
- シャーシやローラーとの干渉を避けるため、バンパーの上部や下部を適宜カットします。シャーシの種類によって干渉箇所が異なるので、実際にシャーシに取り付けながら確認するとよいでしょう。VZシャーシ用のバンパーは全体的に後ろ寄りなので、MA・MSシャーシ用より多く削る必要があります。
- 上蓋(フロントワイドスライドダンパーに付属)も同様に、干渉箇所をカットします。必要に応じて、スプリングスペースの底上げも行います。底上げには、ミニ四駆キャッチャーの端材などが利用できます。
- 最後に、バンパー、上蓋、カーボンマルチ強化プレートをビスとロックナットで結合させます。このとき、ロックナットの締め具合に注意し、スライドがスムーズに動くように調整します。締めすぎるとスライドしなくなり、緩すぎるとバンパーがガタつくので、適切な締め具合を見つけることが重要です。
ATスラダンは、比較的シンプルな構造でありながら効果的な衝撃吸収が可能です。初めてスラダンを自作する方は、まずはこのATスラダンから挑戦してみるとよいでしょう。
左右独立スラダンの作り方はカーボンステーの加工がポイント
左右独立スラダンは、左右のバンパーが独立して動く高性能なスライドダンパーです。製作難易度はやや高いですが、その効果は絶大です。ここでは、カーボンステーを使った左右独立スラダンの作り方を解説します。
まず必要な材料は、3mmカーボンリヤステー、マルチプレート、スプリング、真鍮スペーサー(3.6mm程度)、ビス、ナットなどです。工具はリューターやボール盤(またはドリル)、エンドミル、ヤスリが必要です。
製作手順の概要は以下の通りです:
- 3mmカーボンリヤステーを左右にカットし、それぞれをスライド部分として使用します。19mmローラーを使用する場合は、それに合わせてカットサイズを調整します。
- カーボンステーに1.5mm程度の深さで溝を作ります。この溝にマルチプレートが通るようにします。この工程は精密な作業が必要で、ボール盤やエンドミルを使うと良いでしょう。水平に削ることが重要なので、工具のセッティングには注意が必要です。
- 溝を作った後、軸用の穴を開けます。この穴を通して、左右のステーが独立して動く仕組みを作ります。「ボール盤の力を借りてなんとか1.5mmの深さで、マルチプレート幅の溝をつくれました」という体験談もあるように、この作業は難易度が高いです。
- 真鍮スペーサーを3.6mmになるようにヤスリで削り、これを軸として使用します。軸となるパーツの精度がスムーズな動きの鍵となります。
- マルチプレートを半分に切り、重ねてビス留めします。そして、軸用の穴を外側に約5mm拡張し、真鍮スペーサーがスムーズに動くように調整します。穴の幅は3.2mm程度が適切です。
- バネを引っ掛けるための凸型を作り、各パーツを組み立てます。組み立てる際は、パーツが動きを妨げないように注意しましょう。
- シャーシに組み付けて動作確認を行い、必要に応じて調整します。実際に壁に押し当てて、左右のバンパーが独立してスムーズに動くかをチェックします。
左右独立スラダンの作成で特に重要なのは、軸とマルチプレートの加工精度です。削りすぎると動きがぶれてしまい、削りが足りないとスムーズに動かないので、少しずつ慎重に加工することがポイントです。「3mmカーボンに1.5mmの溝を作ること思いついた人すごいな。軸だけで支えるよりガタツキが軽減できてそう」という評価もあるように、アイデア次第で性能が大きく変わります。
また、左右独立スラダンはガタつきやすいので、組み立て時の各部品の固定にも注意が必要です。特に、ビスとナットの締め具合は、動きを阻害しない程度にしっかりと固定することが重要です。
左右独立スラダンは製作難易度は高いですが、完成すれば複雑なコースでも安定した走行が可能になります。技術を磨きながら、自分だけの最適なスラダンを作り上げましょう。
純正スラダンを改造する方法はビス穴の拡張から始める

市販の純正スライドダンパーを改造して、より高性能なスラダンを作る方法を紹介します。既製品をベースにすることで、一から作るよりも手軽に自分好みのスラダンが完成します。
純正スラダンの改造で最も一般的な方法は、「左右独立式に変更する」というものです。タミヤの純正スライドダンパーは一体型が多いため、これを左右独立式に改造することで、より効果的な衝撃吸収が可能になります。
改造の第一歩は、ビス穴の拡張です。純正スラダンのビス穴をリューターやドリルで拡張し、スライドレールを形成します。このとき、左右それぞれが独立して動くように、中央部分を残して左右のビス穴を別々に拡張することがポイントです。
純正カーボンスラダンを使った簡易独立スラダンの作り方としては、以下の手順があります:
- スライドダンパーのスプリングを左右に分けて設置できるよう、中央部分にスペーサーを追加します。このスペーサーがスプリングの動きを分けるポイントとなります。
- スプリングの配置を変更し、左右それぞれにスプリングを設置します。これにより、左右のバンパーが独立して動作するようになります。スプリングの硬さも、左右で変えることができます。
- 必要に応じて、スプリングの硬さを調整します。左右で異なる硬さのスプリングを使うことも可能です。例えば、コース特性に合わせて、右側は硬め、左側は柔らかめにするなどの調整ができます。
- 上蓋の形状を変更し、左右独立の動きに対応させます。場合によっては、上蓋を新たに自作することも検討します。干渉箇所を適切にカットすることが重要です。
既製品を改造する際の注意点として、強度の低下に気をつける必要があります。ビス穴を拡張しすぎると、ステーの強度が大幅に低下する可能性があります。適度な拡張にとどめ、必要に応じて補強を行いましょう。例えば、FRPステーを追加で重ねるなどの方法が考えられます。
また、改造後は必ず動作確認を行い、スムーズに動くかどうかチェックします。動きが悪い場合は、ビス穴の形状や各部品の固定方法を見直しましょう。特に、ロックナットの締め具合は重要なポイントです。
こうした改造は、ジャパンカップ2017オープンクラスで優勝した選手も実践しているテクニックです。実際に公式大会でも既製品カーボンスライドダンパーを使用して優勝する例が多くあります。純正スラダンの改造は、全くのゼロから作るよりも手軽に始められるため、スラダン自作の入門としてもおすすめです。
スラダンの調整方法はスプリングの硬さとビスの締め具合
スライドダンパーを製作した後、その性能を最大限に引き出すためには適切な調整が不可欠です。ここでは、スラダンの調整方法について詳しく解説します。
スラダンの調整で最も重要なのは「スプリングの硬さ」と「ビスの締め具合」です。これらを調整することで、コースの特性やマシンの走行スタイルに合わせた最適なセッティングが可能になります。
まず、スプリングの硬さについては、タミヤから販売されているスライドダンパースプリングセットに含まれる異なる硬さのスプリングを使い分けることができます。スプリングの色で硬さが区別されており、一般的には黒(最も柔らかい)、青(中間)、銀(硬め)、金(最も硬い)などがあります。
コースの特性に応じたスプリング選びのポイントは以下の通りです:
- 高速コーナーが多いコース:硬めのスプリング(銀や金)を使用すると、高速時の安定性が向上します
- テクニカルなコース:柔らかめのスプリング(黒や青)を選ぶと、細かな衝撃も吸収できます
- 左右からの衝撃が不均等なコース:左右独立式スラダンの場合、左右で異なる硬さのスプリングを使用することで対応できます
次に、ビスの締め具合も重要な調整ポイントです。ロックナットの締め具合によって、スライドの滑らかさや反発力が変わります。締めすぎるとスライドが固くなりすぎて動かなくなり、緩すぎるとバンパー全体がガタついてしまいます。
理想的な締め具合は、バンパーがしっかり固定されていながらも、スムーズにスライドする状態です。これを見つけるには、少しずつ調整しながら実際に動作を確認することが大切です。「バンパーの各パーツがしっかり固定されつつもバンパーがスムーズにスライドする硬さでロックナットを締めていきましょう」というアドバイスが参考になります。
また、スライドの可動範囲も調整可能です。スプリングの中にスペーサーを入れることで、最大可動域を制限できます。スペーサーが長いほど可動域は狭くなります。昨今のトレンドでは、可動域を比較的狭めに設定するケースが多いようです。「スライド可動を柔らかめにしたいなら黒スプリング・硬めにしたいないなら銀スプリングと使い分けて、更に微調整したいということであれば スライドダンパー2スプリングセット を別途購入してスプリングを交換していきます」という方法も効果的です。
スラダンの調整は、実際にコースで走らせながら微調整を重ねることで、最適なセッティングを見つけていくのが理想的です。マシンの挙動を観察しながら、少しずつ調整していきましょう。
これらの調整を丁寧に行うことで、スライドダンパーの性能を最大限に引き出し、安定した走行を実現することができます。
スラダン作りでよくある失敗は削りすぎと締めすぎ
スライドダンパー製作の過程では、いくつかよくある失敗ポイントがあります。これらを事前に知っておくことで、失敗を回避し、より良いスラダンを作ることができます。
最も多い失敗は「ステーの削りすぎ」です。特にスライドレールを作る際、既存のビス穴を拡張していくのですが、リューターなどの工具を使って削っていると、ついつい削りすぎてしまうことがあります。削りすぎると以下の問題が生じます:
- ステーの強度が大幅に低下し、走行中に破損する恐れがある
- スライド機構にガタが生じ、正確な動作ができなくなる
- 必要以上にスライド可動域が広がり、制御が難しくなる
「削っているとカーボンマルチステーの強度が落ちてしまうので以下の画像のように強度が落ちない程度のところで止めておきましょう」というアドバイスがあるように、削りすぎには特に注意が必要です。
削りすぎを防ぐためには、少しずつ慎重に削り、こまめに確認することが重要です。また、リューターの回転速度を調整し、低速で削ることでコントロールしやすくなります。初めは削り足りないくらいの方が安全です。後から少しずつ削り足すことはできますが、削りすぎてしまった場合は修正が難しいからです。
次によくある失敗は「ロックナットの締めすぎ」です。スラダンの各パーツをビスとロックナットで結合する際、しっかり固定しようとするあまり、ナットを強く締めすぎてしまうことがあります。締めすぎると以下の問題が発生します:
- スライド機構が動かなくなる
- バンパーが固定されてしまい、スラダンとしての機能を失う
- パーツに過度な力がかかり、変形や破損の原因になる
「ロックナットをきつく締めすぎるとバンパーが完全に固定されてスライド可動しなくなります」という指摘の通り、適切な締め具合を見つけることが重要です。
締め具合は、バンパーがガタつかない程度でありながら、スムーズにスライドする状態が理想です。少しずつ締めながら動作を確認することが大切です。
その他の失敗としては、「スプリングスペースの形状不良」があります。スプリングスペースが小さすぎると、スプリングが入らない、または圧縮されて動きが悪くなります。大きすぎると、スプリングが安定せず、効果的に機能しません。スプリングを実際に入れてみて確認することが大切です。
また、「シャーシやタイヤとの干渉」も見落としがちなポイントです。スラダンを取り付けた際に、シャーシやタイヤと干渉すると、正常に機能しないだけでなく、走行中の抵抗になります。実際にシャーシに取り付けて、干渉箇所を確認することが重要です。「シャーシの種類によって最適なスラダンの形状が異なる場合があります」という点も覚えておきましょう。
これらの失敗ポイントを意識しながら、慎重に作業を進めることで、失敗を最小限に抑え、満足のいくスラダンを作ることができるでしょう。
スムーズな動きを実現するコツはグリスとスキッドシールの活用
スライドダンパーをせっかく作っても、その動きがスムーズでなければ、本来の性能を発揮できません。ここでは、スラダンの動きをよりスムーズにするためのコツを紹介します。
まず最も効果的なのは「グリスの活用」です。スライドダンパーの摺動部分(こすれ合う部分)にグリスを塗ることで、摩擦を減らし、スムーズな動きを実現できます。具体的には以下の箇所にグリスを塗ります:
- カーボンマルチステーの表面と裏面
- 上蓋の裏面(カーボンマルチステーと接触する部分)
- マルチプレートの表面(カーボンマルチステーと接触する部分)
グリスの塗布量は少量で十分です。塗りすぎると余分なグリスが周囲に付着し、ホコリを吸着するなどの問題が生じる可能性があります。「塗る量も少量で構わないので、最初はほんのわずかに塗ってみてそれでもスライド可動がスムーズにいかないようであれば更に少し追加して調整していきましょう」というアドバイスは参考になります。
ミニ四駆専用のオイルペンを使えば、ピンポイントで適量を塗布できるので便利です。オイルペンの先端は極細の筆ペンとなっており、狙った箇所にピンポイントで塗布することができます。
次に効果的なのは「スキッドシールの活用」です。スキッドシールは、滑り性能を向上させるためのシール状のパーツで、これをカーボンマルチステーや上蓋、マルチプレートの接触面に貼ることで、摩擦を大幅に減らすことができます。
スキッドシールを貼る手順は以下のとおりです:
- 必要なサイズ(約2.5cm × 1cm)にスキッドシールをカット
- カーボンマルチステーの表面と裏面の摺動部分に貼り付け
- はみ出た部分は切り取り、バンパーの形状に合わせる
また、「ブレーキステーのビス穴拡張」も動作をスムーズにするコツの一つです。ブレーキステーのビス穴を拡張することで、ATバンパーをブレーキステーに装着したままロックナットの締め具合を調整できるようになります。これにより、取り外しと再取り付けを繰り返すことなく、理想的な締め具合を見つけることができます。
さらに、「動作確認の徹底」も重要です。実際に壁に押し付けてスライド動作を確認し、戻りがスムーズかどうかチェックします。特に、「押した時はスムーズにいくものの戻りがスムーズではない」という症状は頻繁に発生します。この場合、ロックナットの締め具合やグリスの塗布状況を見直しましょう。
「仮に走行中にATスラダンが押したまま戻ってこなければ、走行が不安定になったり速度減に繋がることもあります」という指摘があるように、戻りの動作も重要です。適切な調整で、押す動作と戻る動作の両方がスムーズになるようにしましょう。
これらのコツを実践することで、スライドダンパーの動きがより洗練され、コース走行時の安定性と速度が向上します。少しの手間をかけることで、スラダンの性能を最大限に引き出しましょう。
まとめ:ミニ四駆スラダン作り方のポイントは素材選びと精密な加工
最後に記事のポイントをまとめます。
- スライドダンパーはコース走行の安定性を向上させる重要なパーツである
- 自作スラダンの魅力は自分のマシンに最適なカスタマイズが可能な点である
- 素材選びはスラダン作りの基本であり、カーボンやFRPステーが主に使われる
- リューターやドリルといった工具の準備が自作スラダンには不可欠である
- スラダンには左右独立式と一体型があり、それぞれに特徴と利点がある
- ATスラダンは既存パーツの組み合わせで比較的簡単に作ることができる
- 左右独立スラダンはカーボンステーの精密な加工がポイントとなる
- 純正スラダンの改造はビス穴の拡張から始める方法が一般的である
- スプリングの硬さとビスの締め具合がスラダンの調整における重要要素である
- ステーの削りすぎとロックナットの締めすぎはスラダン作りでよくある失敗である
- グリスとスキッドシールの活用でスラダンの動きをスムーズにできる
- スラダン製作においては加工精度が重要であり、少しずつ慎重に作業を進めることが成功の鍵である
- コースの特性に合わせたスラダンのセッティングが走行性能を最大化する
- 一度作ったスラダンでも微調整を繰り返すことでより良い性能を引き出せる