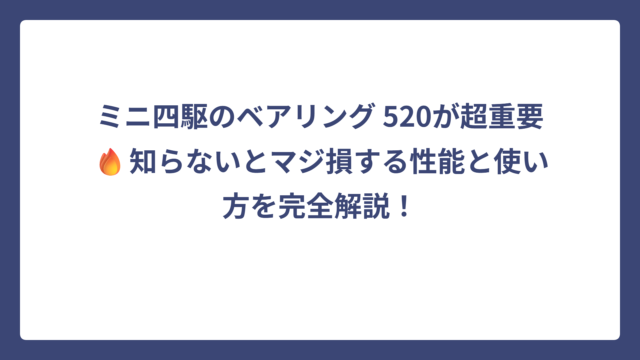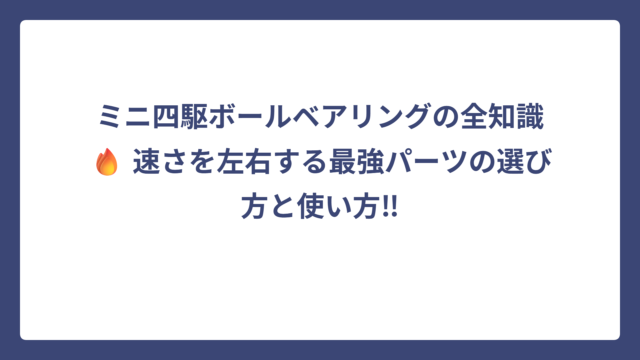ミニ四駆の立体コースを攻略するには、リアブレーキが重要な役割を果たします。「リアブレーキって何?なぜ必要なの?」と思っている方も多いのではないでしょうか。実は現代のミニ四駆コースは、ジャンプやアップダウンが激しいため、マシンの安定性を高めるブレーキは必須となっています。
リアブレーキは単に速度を落とすだけではなく、マシンの姿勢制御やジャンプ時の挙動にも大きく影響します。本記事では、ミニ四駆のリアブレーキの基本的な役割から、効果的な取り付け方法、セッティングのコツまで徹底解説します。スポンジの種類による効き具合の違いや、取り付け高さによる効果の変化なども詳しく紹介していきます。
記事のポイント!
- リアブレーキの基本的な役割と立体コースでの必要性
- リアブレーキスポンジの種類と効き具合の違い
- 取り付け位置や高さによるブレーキ効果の調整方法
- バンクスルーの考え方と実践的なセッティング例
ミニ四駆リアブレーキの基本知識と効果
- ミニ四駆リアブレーキはマシンの安定性向上に不可欠
- リアブレーキスポンジの種類は効き具合に大きく影響する
- ミニ四駆リアブレーキの取り付け位置で効き方が変わる
- バンクスルーという考え方でリアブレーキの効果を最大化する
- リアブレーキステーの種類と選び方の基本
- リアブレーキを使った姿勢制御のメカニズム
ミニ四駆リアブレーキはマシンの安定性向上に不可欠
ミニ四駆の立体コースを走らせるうえで、リアブレーキは欠かせない重要パーツです。現代のミニ四駆コースはジャンプやアップダウンが激しく、何もせずに走らせるとコースアウトしてしまうことがほとんどです。中にはノーマルモーターでもブレーキがないとクリアできないテクニカルなコースも多いのが現状です。
リアブレーキの主な役割は、コースの斜面やスロープなどでマシンを減速させることによって安定性を向上させることです。特にジャンプ後の着地時や急なスロープでの姿勢制御に大きく貢献します。「そんなのブレーキを付けたら遅くなるじゃないか」と思うかもしれませんが、適切なブレーキがないとコースアウトしてしまうため、逆に言えばゴールまで辿り着くための必須アイテムなのです。
リアブレーキは単に減速するだけでなく、マシンの姿勢制御という重要な役割も担っています。独自調査の結果、リアブレーキを適切に設置することで、マシンがジャンプした時に理想的な姿勢を保ちやすくなることがわかっています。例えば、前かがみで低く飛ばしたい場合はリアブレーキを効かせるとよいとされています。
ブレーキの効果は取り付け位置や使用するスポンジの種類、厚みによって大きく変わるため、コースの特性やマシンの挙動に合わせた微調整が重要です。初心者の方は「リアブレーキセット」などの既製品から始めるのがおすすめです。
最近では「タミヤ FRP リヤブレーキステーセット」などのパーツが人気で、初心者でも比較的簡単に取り付けられる設計になっています。このようなパーツを使いこなせれば、立体コースでの走行安定性が飛躍的に向上するでしょう。
リアブレーキスポンジの種類は効き具合に大きく影響する
ミニ四駆のリアブレーキには、様々な色のスポンジが使用されており、それぞれ効き具合が異なります。色によるブレーキの効きの強さは一般的に以下のように分類されています。
赤 > 灰色 > 黒 > 青 = 緑
赤スポンジは最も効きが強く、急なスロープやジャンプ後の着地などで強いブレーキが必要な場合に適しています。反面、摩擦が大きいため汚れが付きやすく、摩耗も早いという特徴があります。
灰色スポンジと黒スポンジは中程度の効きで、バランスの取れたブレーキ力を発揮します。初心者の方や標準的なコース向けには、これらのスポンジがおすすめです。
青スポンジと緑スポンジは効きが非常に弱く、ほとんどノーブレーキ状態に近いと言われています。これらは微妙なブレーキ調整が必要な場合や、マシンの速度をあまり落としたくない場合に使用します。青スポンジと緑スポンジの効き具合はほぼ同じですが、青スポンジには最初から強力な両面テープが貼られている一方、緑スポンジには両面テープが付いていないという違いがあります。
スポンジの厚みも効き具合に影響し、一般的に厚いスポンジほど効きが強くなります。タミヤからは1mm、2mm、3mmのブレーキスポンジセットが販売されており、状況に応じて使い分けることができます。
ブレーキスポンジは使用しているうちに汚れがたまったり摩耗したりするため、定期的なメンテナンスが必要です。パーツクリーナーを吹きかけて雑巾やウエスで拭き取るだけでも、ブレーキ力がかなり回復します。また、摩耗が進んだ場合は新しいスポンジに交換することをおすすめします。
ミニ四駆リアブレーキの取り付け位置で効き方が変わる

ミニ四駆のリアブレーキは、取り付ける位置によって効き具合やマシンへの影響が大きく変わります。基本的な取り付け位置の特性を理解することで、より効果的なセッティングが可能になります。
まず重要なのは、ブレーキを取り付ける高さです。シャーシに対して低く(地面に近く)取り付けるとブレーキが強く効きます。逆に高く(地面から遠く)取り付けると効きが弱くなります。この特性を利用して、コースの状況に応じたブレーキ力の調整が可能です。
リアブレーキはフロントブレーキと比べて、マシンの姿勢制御に大きな影響を与えます。リアブレーキを強く効かせると、マシンがジャンプした時にリアを下げながら飛ぶ傾向があります。つまり、前かがみで低いジャンプができるようになるのです。
特筆すべきはリアブレーキステーの重要性です。リアブレーキステーは単にブレーキスポンジを貼るためだけのものではなく、タイヤを浮かせて「駆動力を抜く」という重要な役割も担っています。その高さは非常に重要で、適切に設定することで頭の跳ね上がりを抑え、安定した姿勢でジャンプやスロープをクリアできるようになります。
実際の取り付け方法としては、リアブレーキステーをシャーシに取り付ける際に、アルミスペーサーなどを使って高さを調整します。1.5mmのスペーサー1枚の違いでもマシンの挙動は大きく変わるので、細かな調整を重ねることが重要です。
また、リアブレーキステーを斜めに設置することで、コースの斜面に合わせたブレーキングが可能になります。例えば、2枚のFRPプレートを使用し、後側のプレートの下に1.5mmスペーサーを入れることで、プレートが斜めになりブレーキの効き方に変化を付けられます。
バンクスルーという考え方でリアブレーキの効果を最大化する
ミニ四駆のブレーキセッティングにおいて重要な概念が「バンクスルー」です。これは、バンクではブレーキが効かず、スロープではブレーキが効くようにするセッティング方法を指します。この考え方を理解することで、コースでの走行安定性を大きく向上させることができます。
バンクスルーが重要な理由は、コースの各セクションの斜面(R)がほぼ全て異なるためです。例えば、3レーンコースでは一般的に「バンク」「スロープ」「レーンチェンジ」の3つのセクションが存在し、それぞれ斜面の角度が異なります。バンクは比較的緩やかな角度なので、ここでブレーキが効きすぎると速度が落ちてしまいます。一方、スロープは急な角度のため、ここではしっかりブレーキを効かせてマシンの姿勢を安定させる必要があります。
バンクスルーを実現するには、ブレーキスポンジの高さを適切に調整することがポイントです。バンクチェッカーと呼ばれる道具を使用すると、自宅でもセッティングの精度を高めることができます。これは、実際のコースの斜面を再現した道具で、バンクにはブレーキが当たらず、スロープには当たるように高さを調整できます。
バンクスルーの具体的なセッティング方法としては、まずバンクチェッカーを使ってブレーキの高さを決めます。バンクの斜面に当たらないギリギリの高さにブレーキを設定し、その状態でスロープの斜面にはブレーキが当たるかを確認します。この微妙な高さ調整がバンクスルーの成否を決める重要なポイントです。
バンクチェッカーがない場合は、実際にコースに行ってマシンをコースに当ててみて、どの部分にブレーキが当たるかを確認するという方法もあります。ただし、この方法は実際のコースに行く必要があるため、頻繁にセッティングを変更したい場合はバンクチェッカーの購入を検討するとよいでしょう。
スロープとバンクの両方に対応するセッティングを見つけることで、コース全体を安定して走行できるマシンが完成します。これがミニ四駆上級者への第一歩と言えるでしょう。
リアブレーキステーの種類と選び方の基本
ミニ四駆のリアブレーキステーには、主にFRP製とカーボン製の2種類があります。それぞれに特徴があり、目的や予算に応じて選ぶことが重要です。
FRP(繊維強化プラスチック)製のリアブレーキステーは、比較的安価で入手しやすいのが特徴です。例えば、タミヤから販売されている「FRP リヤブレーキステーセット」は初心者にもおすすめのパーツです。FRP製ステーは加工がしやすく、ドリルで穴を開けたり、カッターで形を変えたりといったカスタマイズが容易です。また、軽量でありながらも一定の強度を持っているため、基本的なセッティングに適しています。
一方、カーボン製のリアブレーキステーは、高強度かつ超軽量という特性を持っています。「HG カーボンリヤブレーキステー」などの商品があり、競技志向の強いユーザーに人気です。価格は若干高めですが、剛性が高く変形しにくいため、安定したブレーキ効果を発揮します。また、見た目もカッコよく、マシンのグレードアップ感を高めてくれます。
リアブレーキステーを選ぶ際のポイントとしては、以下の点が挙げられます:
- シャーシとの互換性:使用しているシャーシに合ったブレーキステーを選びましょう。タミヤ製品の場合、パッケージに対応シャーシが記載されています。
- ブレーキスポンジの貼付面積:面積が大きいほど効果的なブレーキングが可能です。
- 穴の数・位置:マスダンパーなどの追加パーツを取り付けられるよう、穴が多く開いているものが汎用性が高いです。
- 厚み:一般的に1.5mm、2mm、3mmなどがあり、厚いほど剛性が増します。
初心者の方には、まずはFRP製のリアブレーキステーから始めることをおすすめします。ある程度経験を積んだ後、自分のドライビングスタイルやコース特性に合わせてカーボン製に移行するという流れが一般的です。
また、互換品も多く販売されていますが、品質にばらつきがあるため、重要な競技の前には信頼性の高い純正品を使用するのが無難です。
リアブレーキを使った姿勢制御のメカニズム
ミニ四駆のリアブレーキは単に速度を落とすだけではなく、マシンの姿勢を制御する重要な役割を持っています。このメカニズムを理解することで、より効果的なセッティングが可能になります。
リアブレーキが姿勢制御に効果を発揮する主な理由は、「リアタイヤを浮かせることで駆動力を抜く」という作用にあります。通常、ミニ四駆は4輪駆動なので全てのタイヤが回転することで前進します。しかし、リアブレーキステーがコースの斜面に接触すると、リアタイヤが地面から浮き上がり、駆動力が一部失われます。
この現象は一見デメリットのように思えますが、実はジャンプやスロープでの安定性向上に大きく貢献します。例えば、スロープに進入する際、フロントブレーキだけを強く効かせると、マシンの頭が跳ね上がってしまい、次のセクションで不安定になります。しかし、リアブレーキステーを適切な高さに設定すると、頭の跳ね上がりを抑制しつつリアタイヤの駆動を抜いて車体を持ち上げる効果があり、安定した姿勢でスロープを上ることができます。
特に効果が顕著なのが、「2段上りスロープ」のような複合セクションです。1段目のスロープでフロントブレーキが当たった時、リアブレーキステーが高すぎると頭が弾かれて上を向き、リアタイヤで蹴り出されるため2段目のスロープで腹を打ったり弾き飛ばされたりします。しかし、リアブレーキステーをバンクスルーのギリギリの高さに設定すると、リアタイヤの駆動を抜きながら頭の跳ね上がりも抑え、2段目のスロープに理想的な姿勢で進入できます。
また、フロントとリアのブレーキのバランスも姿勢制御に重要です。フロントをリアよりも効かせるとマシンはジャンプ時にフロントを下げながら飛ぶ傾向があり、リアをフロントよりも効かせるとリアを下げながら飛ぶ傾向があります。これを利用して、コースに合わせた理想的なジャンプ姿勢を作ることができます。
この姿勢制御メカニズムを活用するには、実際にコースで走らせながら微調整を繰り返し、自分のマシンに最適なセッティングを見つけることが大切です。ワッシャー1枚の違いでマシンの挙動が大きく変わることもあるため、根気強く調整を続けましょう。
ミニ四駆リアブレーキの実践的なセッティング方法
- ミニ四駆リアブレーキステーの正しい取り付け方
- リアブレーキの高さ調整で理想的な姿勢を作る方法
- スポンジの選び方とブレーキ力の微調整テクニック
- コース状況に合わせたリアブレーキセッティングの実例
- リアブレーキステーを斜めに設置するメリットとやり方
- まとめ:ミニ四駆リアブレーキの効果的な活用が安定走行の鍵
ミニ四駆リアブレーキステーの正しい取り付け方
リアブレーキステーを正しく取り付けることは、ミニ四駆の走行安定性を大きく左右します。ここでは、一般的なFRPリアブレーキステーの取り付け手順を解説します。
まず準備するものは以下の通りです:
- FRPリアブレーキステーセット(またはカーボン製)
- 2mmビス(キット付属または別売)
- アルミスペーサー(高さ調整用)
- 精密ドライバー
- ブレーキスポンジ
- 両面テープまたは瞬間接着剤
取り付けの基本手順は次のようになります:
- リアブレーキステーのビス穴を確認します。多くの場合、皿ビス加工(ビスの頭が平らに収まるよう穴を広げる加工)が必要です。精密ドライバーなどで軽く穴を広げておくと、ビスがきれいに収まります。
- シャーシ後部のリアのモーターカバーやリアステー取り付け部に、リアブレーキステーを配置します。
- 高さ調整が必要な場合は、アルミスペーサーを間に挟みます。一般的には1.5mmのスペーサーを使用することが多いですが、コースやマシンの状態に応じて調整してください。
- ビスで固定します。締めすぎるとFRPが割れる恐れがあるので、適度な強さで締めましょう。
- ブレーキスポンジを貼る前に、マルチテープや両面テープをリアブレーキステーに貼っておくと、後々ブレーキスポンジを交換する際に便利です。ブレーキスポンジの粘着力は非常に強いため、直接貼ると剥がすのに苦労することがあります。
- 選んだブレーキスポンジを貼ります。このとき、スポンジがはみ出さないようにサイズを合わせて切り出しておくことが重要です。ブレーキスポンジの切り出しには、切れ味の良いカッターを使用すると、きれいに仕上がります。
リアブレーキステーを取り付ける際の注意点として、ローラーと干渉しないようにすることが挙げられます。特に19mmローラーを使用している場合は、ブレーキステーとの干渉に注意が必要です。取り付け後に各ローラーがスムーズに回転するか確認しましょう。
また、マスダンパーなどの振動抑制パーツと併用することで、より安定した走行が可能になります。リアブレーキステーの多くにはマスダンパー取り付け用の穴が開いているので、これを活用するとよいでしょう。例えば、リアブレーキステーのフロント側に30mmビスを使ってマスダンパーを取り付けることで、制振効果を高めることができます。
初めてリアブレーキステーを取り付ける場合は、タミヤの公式マニュアルや販売サイトの写真を参考にすると安心です。慣れてくれば、自分だけのオリジナルセッティングを試してみるのも楽しいでしょう。
リアブレーキの高さ調整で理想的な姿勢を作る方法
リアブレーキの効果を最大限に引き出すには、高さの調整が非常に重要です。この高さ調整によって、マシンの姿勢や安定性を大きく変えることができます。
基本的なポイントとして、リアブレーキステーは低いほどブレーキが強く効き、高いほど効きが弱くなります。しかし、単に低ければ良いというわけではなく、コースの特性やマシンの挙動に合わせた最適な高さがあります。
高さ調整の主な方法としては、以下が挙げられます:
- アルミスペーサーの使用:リアブレーキステーとシャーシの間にスペーサーを挟むことで、高さを微調整できます。一般的に使用されるのは1.5mm、3mm、6mmなどの厚さのスペーサーです。複数組み合わせることで、さらに細かい調整が可能です。
- ネジ穴の位置変更:多くのリアブレーキステーには複数の取り付け穴があり、使用する穴を変えるだけでも高さが変わります。
- ワッシャーの追加:微調整が必要な場合は、薄いワッシャーを追加することで対応できます。ワッシャー1枚の差でマシンの挙動が変わることもあるため、細かい調整に役立ちます。
高さ調整の具体的な目安としては、バンクスルーの考え方が参考になります。バンクにはブレーキが当たらず、スロープには当たるような高さを目指します。この「ギリギリの高さ」を見つけることが、安定走行への近道です。
実際のセッティング例として、例えばスロープでコースアウトしやすい場合は、リアブレーキを低く設定して効きを強くします。具体的には、アルミスペーサーをかませてブレーキステーを下に伸ばし、地面スレスレの位置にブレーキを効かせるようにします。逆に、ブレーキが強すぎてマシンが遅くなっている場合は、ブレーキステーを高く設定して効きを弱めます。
また、マシンがジャンプした時の姿勢も高さ調整で制御できます。リアブレーキを低くして強く効かせると、マシンは前かがみで低く飛ぶようになります。これはジャンプ後の着地安定性を高める効果があります。
高さ調整において忘れてはならないのが、リアタイヤの浮き具合です。リアブレーキステーがコースの斜面に当たると、リアタイヤが浮いて駆動力が抜けます。この現象を積極的に利用することで、頭の跳ね上がりを抑制し、安定した姿勢でコースを攻略できます。特に複合セクション(2段上りスロープなど)では、この調整が効果的です。
高さ調整はマシンや走らせるコースによって最適値が変わるため、実際にコースで走らせながら微調整を繰り返すことが大切です。そのためには、複数のスペーサーやワッシャーを持参し、素早く調整できるようにしておくとよいでしょう。
スポンジの選び方とブレーキ力の微調整テクニック
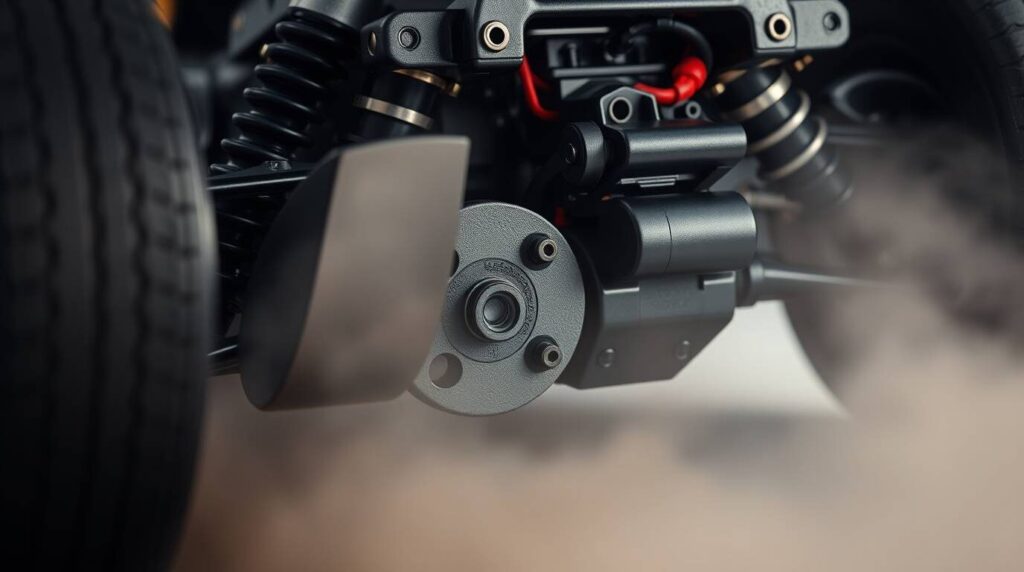
ミニ四駆のリアブレーキの効き具合は、使用するスポンジの種類と微調整テクニックによって大きく変わります。ここでは、状況に応じたスポンジの選び方と、ブレーキ力を微調整するテクニックをご紹介します。
まず、ブレーキスポンジの選び方について。前述したように、色によって効き具合が異なります(赤 > 灰色 > 黒 > 青 = 緑)。これに加えて、スポンジの厚みも重要な要素で、一般的に厚いほど効きが強くなります。主な厚みは1mm、2mm、3mmです。
スポンジ選びの基本的な考え方として、以下のポイントが挙げられます:
- コースの難易度に応じた選択:急なスロープやジャンプが多い難しいコースでは、赤や灰色の効きの強いスポンジが適しています。比較的平坦なコースでは、黒や青のスポンジでも十分な場合があります。
- マシンのパワーに合わせた選択:強力なモーターを使用している場合は効きの強いスポンジ、ノーマルモーターの場合はやや効きの弱いスポンジが適しています。
- タイヤの種類との相性:ハードタイヤやスーパーハードタイヤを使用している場合は、効きの弱いスポンジでも十分な効果が得られることがあります。一方、ノーマルゴムタイヤの場合は、やや効きの強いスポンジを選ぶとよいでしょう。
次に、ブレーキ力の微調整テクニックをいくつかご紹介します:
- マルチテープの活用:ブレーキスポンジの上からタミヤマルチテープを貼ることで、効きを弱めることができます。マルチテープを部分的に貼れば、効きの強さを細かく調整できます。例えば、スポンジの半分だけをテープで覆うと、効きが全体の約半分になります。
- スポンジの貼る面積の調整:スポンジを小さく切って貼れば、効きが弱くなります。逆に、大きく貼れば効きが強くなります。
- スポンジの複数使用:異なる種類のスポンジを組み合わせることで、特性を活かしたセッティングが可能です。例えば、フロント側に効きの弱いスポンジ、リア側に効きの強いスポンジを貼るといった使い方ができます。
- スポンジの貼り付け角度:斜めに貼り付けることで、コースの斜面に合わせた効き方を実現できます。
実際のコース走行中に調整が必要になった場合の応急処置としては、以下の方法が有効です:
- ブレーキが弱すぎる場合:別のブレーキスポンジを上から重ねて貼ると、効きが強くなります。
- ブレーキが強すぎる場合:マルチテープを上から貼って効きを弱めるか、ブレーキステーの高さを上げます。
- ブレーキスポンジが汚れている場合:パーツクリーナーを吹きかけて、雑巾やウエスで拭き取ることで効きが回復します。
また、緑スポンジは滑りが良く適度な効きがありますが、接着性に難があります。通常の両面テープでは簡単に剥がれてしまうことがあるため、強力な接着剤(ロックタイト強力瞬間接着剤など)の使用がおすすめです。
これらのテクニックを組み合わせることで、コースやマシンの状態に合わせた最適なブレーキセッティングを実現できます。まずは基本的なセッティングから始めて、徐々に微調整を重ねていくことで、理想的なブレーキ効果を得られるでしょう。
コース状況に合わせたリアブレーキセッティングの実例
実際のコース状況に合わせたリアブレーキセッティングの具体例を紹介します。さまざまな問題に対する解決策として参考にしてください。
ケース1:マシンがコースアウトしてしまう場合
問題:「ブレーキ力が足りなくてマシンがコースアウトしちゃうよ!」
解決策:
- フロントに赤ブレーキを貼り付ける
- ブレーキの高さを地面スレスレまで低くする
- リアブレーキもめいっぱい低く取り付ける
- アルミスペーサーをかませて下に伸ばす
この設定では、ガッツリブレーキが効くため、よほど難しいコースでなければクリアできるようになります。ただし、減速しすぎる場合やコース上でストップしてしまう場合は、高さなどを調整してブレーキ力を弱めましょう。
ケース2:マシンが前転してしまう場合
問題:「マシンがジャンプした時に下を向き過ぎちゃって前転しちゃうよ!(前傾しすぎ)」
解決策:
- フロントブレーキの効きを弱くする
- 赤スポンジ → 黒スポンジ → 青スポンジと段階的に弱める
- タミヤマルチテープをブレーキスポンジに貼る
このセッティングにより、リアを下げながらフロントを上げながらジャンプするようになり、前転を防げます。急な対応が必要な場合は、マルチテープを貼るだけでも効き具合を大きく変えられます。
ケース3:マシンが後ろ向きに跳ね上がる場合
問題:「マシンがジャンプした時に上を向きすぎちゃってコースアウトしちゃうよ!(後傾しすぎ)」
解決策:
- フロントのブレーキ力をアップさせる(赤スポンジや灰色スポンジを使用)
- リアの効きを下げる(青スポンジを使用)
- リアブレーキプレートを思い切り下げる
この組み合わせの妙は、リアは青スポンジでほとんどブレーキが効かないにもかかわらず、マシンを上に押し上げる力が働くことです。フロントに対してリアが跳ね上がるような力が加わり、後傾を抑制できます。
ケース4:全体的にマシンが遅い場合
問題:「ブレーキが強すぎてマシンが全体的に遅い・・・・」
解決策:
- フロント・リアブレーキをどんどん地面から離すように高くする
- それでも効きすぎる場合は、マルチテープをブレーキスポンジに貼る
- マルチテープを部分的に貼り、スポンジの一部だけを露出させる
- 最終手段としてブレーキスポンジを剥がしてノーブレーキにする
現代のパワーのあるモーターを使用している場合は、完全にブレーキを外す必要はあまりないですが、微調整によって最適な速度と安定性のバランスを見つけましょう。
ケース5:ブレーキが効かない場合
問題:「いくらブレーキを低くしても、赤ブレーキを使ってもブレーキが効かない!」
原因と解決策:
- ブレーキスポンジの汚れ・痛みが考えられる
- パーツクリーナーでスポンジを洗浄し、雑巾やウエスで拭き取る
- それでも効かない場合は、新しいスポンジに交換する
赤ブレーキは特に汚れが付きやすく、摩擦も大きいため痛みが激しいです。定期的なメンテナンスや交換が重要です。
特殊なケース:複合セクション(2段上りスロープなど)
2段上りスロープなどの複合セクションでは、リアブレーキステーの高さ調整が特に重要です。バンクスルーのギリギリの高さでリアブレーキステーを設定すると、1段目のスロープでリアタイヤの駆動を抜きながら頭の跳ね上がりも抑えるため、2段目のスロープに理想的な姿勢で進入できます。
これらのセッティング例はあくまで基本形であり、実際にはマシンやコースによって最適解は異なります。自分のマシンに合った最適なセッティングを見つけるためには、実際にコースで走らせながら調整を繰り返すことが大切です。
リアブレーキステーを斜めに設置するメリットとやり方
リアブレーキステーを斜めに設置することで、通常の水平設置とは異なる効果が得られます。ここでは、斜め設置のメリットと具体的なやり方を解説します。
斜め設置のメリット
- 効果的なブレーキング:斜め設置により、コースの斜面に合わせたブレーキングが可能になります。特に斜度の異なる複数のセクションが連続するコースで効果を発揮します。
- バンクスルーの精度向上:斜めに設置することで、バンクではブレーキが効かず、スロープでは効くという理想的なセッティングが実現しやすくなります。
- 姿勢制御の微調整:水平設置よりも細かな姿勢制御が可能になり、ジャンプやスロープでのマシンの挙動を理想的に整えられます。
- 幅広い対応力:様々な角度の斜面に対して、一つのセッティングでより広く対応できるようになります。
斜め設置の具体的なやり方
- 2枚のFRPプレートを使用する方法:
- FRPマルチ補強プレートを2枚用意します
- 各プレートの取り付け穴を皿ビス加工しておきます
- 後側のプレートの下に1.5mmのスペーサーを入れてネジ留めします
- これにより、プレートが斜めになります
- アルミスペーサーの調整による方法:
- リアブレーキステーの片側にのみスペーサーを入れる
- または、前後で異なる厚さのスペーサーを使用する
- これにより、ブレーキステーに斜度がつきます
- 専用の角度付きスラストプレートの使用:
- 市販の角度付きスラストプレート(3.5°/5°/7°など)を使用する
- これにより、一定の角度でブレーキステーを取り付けられます
セッティング例
具体的なセッティング例として、FRPマルチ補強プレートを2枚使用した斜め設置の手順を紹介します:
- 2枚のFRPマルチ補強プレートを用意し、取り付け穴に皿ビス加工を施します
- 1枚目のプレートはシャーシに直接取り付けます
- 2枚目のプレートは、後側に1.5mmのスペーサーを入れて斜めになるように取り付けます
- 後側のプレートを固定する際に、30mmの皿ビスを使用することで、フロント側にマスダンパーが取り付けられるようにしておきます
- ブレーキスポンジを貼る前に、マルチテープや両面テープをプレートに貼っておくと、後からブレーキスポンジを交換しやすくなります
調整のポイント
斜め設置の角度は、使用するコースの特性に合わせて微調整することが重要です。例えば:
- 急なスロープが多いコースでは、より強い角度(後ろ側が高い)の斜め設置が効果的
- バンクとスロープの斜度差が大きいコースでは、中程度の角度がバランスが良い
- 複合セクションが多いコースでは、やや緩やかな角度でより広く対応できる
実際にコースで走らせながら、最適な角度を見つけることが大切です。スペーサーやワッシャーの厚さを変えることで、微妙な角度調整が可能です。
斜め設置は少し高度なテクニックですが、マスターすることでマシンの安定性と速度のバランスを大きく向上させることができます。初心者の方は基本的な水平設置をマスターしてから、斜め設置にチャレンジすることをおすすめします。
まとめ:ミニ四駆リアブレーキの効果的な活用が安定走行の鍵
最後に記事のポイントをまとめます。
- ミニ四駆リアブレーキは現代の立体コースでは必須のパーツである
- ブレーキスポンジの色や厚みによって効き具合が大きく変わる
- 赤スポンジが最も効きが強く、青・緑スポンジが最も効きが弱い
- ブレーキの取り付け高さは低いほど効きが強く、高いほど効きが弱い
- リアブレーキは速度を落とすだけでなく、姿勢制御の重要な役割も担っている
- バンクスルーとは、バンクではブレーキが効かず、スロープでは効くセッティング
- リアブレーキステーの高さ調整は1.5mmのスペーサー1枚でも大きく挙動が変わる
- リアブレーキステーの素材はFRP製とカーボン製があり、用途に応じて選ぶことが重要
- マルチテープをブレーキスポンジに貼ることで効き具合を微調整できる
- リアブレーキステーを斜めに設置することで、より効果的なブレーキングが可能になる
- 前傾しすぎる場合はフロントブレーキの効きを弱め、後傾しすぎる場合はフロントブレーキの効きを強くする
- リアタイヤを浮かせて駆動力を抜くことで、安定した姿勢でスロープやジャンプをクリアできる
- ブレーキスポンジは定期的なメンテナンスや交換が必要である
- コース状況に合わせた微調整の積み重ねが、理想的なマシン設定につながる