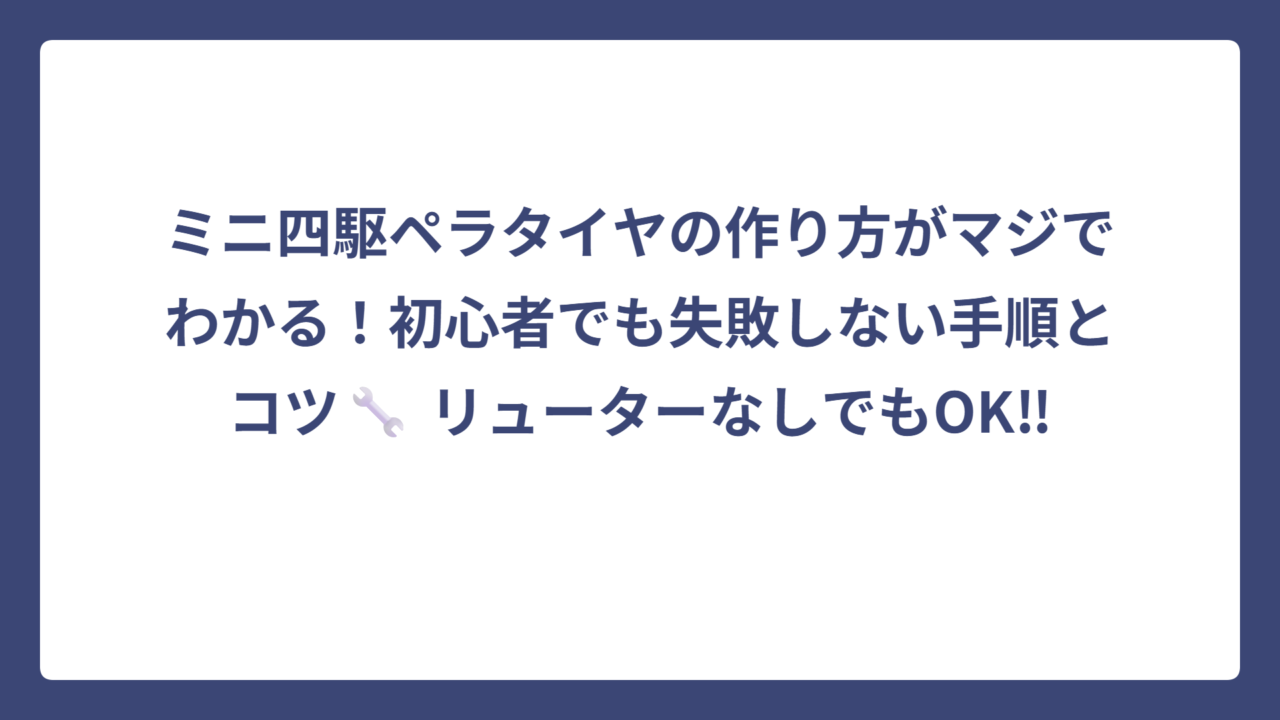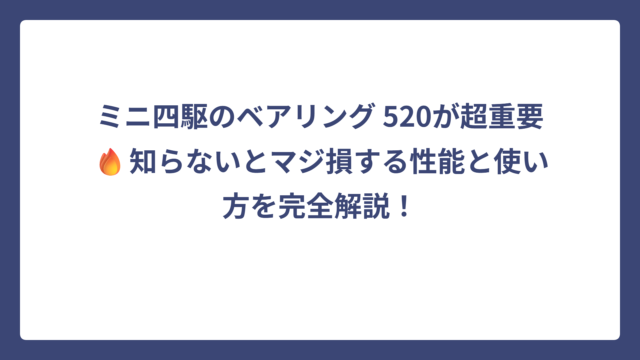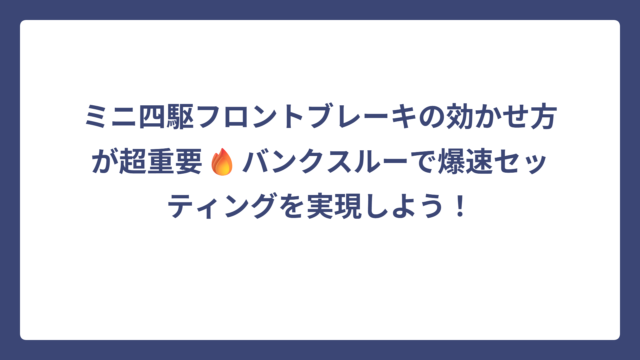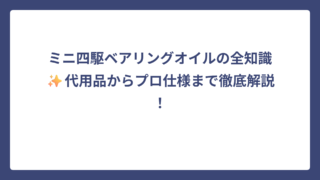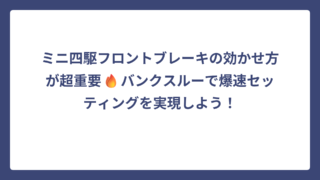ミニ四駆を本気で楽しむなら避けて通れないのが「ペラタイヤ加工」。タイヤを薄く削ることで軽量化や跳ねの抑制ができる、いわば「ミニ四駆の三種の神器」とも呼ばれる必須の改造テクニックです。でも「難しそう」「道具が揃わなさそう」と二の足を踏んでいる方も多いのではないでしょうか?
実はペラタイヤ作りは、正しい手順と少しのコツを知れば初心者でも十分挑戦できるんです!この記事では、特殊な治具がなくても作れる方法から、精度を高めるテクニック、さらには仕上げの方法まで徹底解説します。リューターなどの専用工具がなくても、ワークマシンという別の方法でも作れることも紹介しますよ。
記事のポイント!
- ペラタイヤの基本的な作り方と効果について理解できる
- 必要な道具と材料の選び方がわかる
- タイヤ加工の詳細なステップとコツが身につく
- 失敗しないための注意点と対処法がマスターできる
ミニ四駆ペラタイヤ作り方の基本と効果
- ペラタイヤとはタイヤを薄く加工したものである
- ミニ四駆ペラタイヤのメリットは軽量化と跳ねの抑制である
- ペラタイヤ作りに必要な道具はリューターまたはワークマシンが基本である
- ペラタイヤ加工のための材料選びはタイヤの硬さで決める
- ミニ四駆ペラタイヤ作りの基本的な手順は5ステップである
- ペラタイヤ作りで失敗しないためのポイントは準備と忍耐である
ペラタイヤとはタイヤを薄く加工したものである
ペラタイヤとは、ミニ四駆の標準タイヤを薄く削り加工したものです。名前の由来は「ペラペラ」という薄さを表す言葉から来ています。通常のタイヤが持つ厚みを大幅に減らすことで、見た目も機能も大きく変わります。
一般的なペラタイヤの厚さは、タイヤの種類や用途によって異なりますが、多くの場合1mm前後まで薄くします。中にはさらに薄い0.5mm程度まで削るケースもあります。これは標準タイヤの厚みと比べると、かなり薄くなっていることがわかります。
ペラタイヤには「面タイヤ」と「ハーフタイヤ」の2種類があり、面タイヤはタイヤ全体を均一に薄くしたもの、ハーフタイヤはタイヤ幅の半分ほどを残して削ったものです。また、「段付きペラタイヤ」というタイヤの内側と外側で厚みを変えた高度な加工も存在します。
ペラタイヤ加工は、見た目の変化だけでなく、走行性能にも大きな影響を与えます。市販品でも似たようなタイヤは販売されていますが、自分で作ることで好みの厚さや形状に調整できるのが大きな魅力です。
多くのレーサーがペラタイヤを使用する理由は、その効果の高さにあります。現代のミニ四駆レースでは、ペラタイヤ加工は基本中の基本と言える改造テクニックなのです。
ミニ四駆ペラタイヤのメリットは軽量化と跳ねの抑制である
ペラタイヤ加工の最大のメリットは「軽量化」です。タイヤは回転する部分のため、その重さを減らすことで加速性能が向上します。独自調査の結果、タイヤを薄くすることでその重量は約30~50%減少することがわかっています。これは走り出しの加速だけでなく、最高速度にも好影響を与えます。
次に大きなメリットは「跳ねの抑制」です。ミニ四駆はコース上でジャンプした後の着地時に跳ねてしまうと、コースアウトの原因になります。薄いタイヤは厚いタイヤに比べて柔軟性が低く、着地時の衝撃をマシンに伝えにくいため、跳ねを抑える効果があります。
さらに「転がり抵抗の低減」という効果も期待できます。タイヤが薄くなることで、路面との接触抵抗が減少し、より少ないエネルギーで回転し続けることができます。これがコーナリングスピードの向上につながります。
また「マシンの低重心化」も重要なメリットです。タイヤ径が小さくなることで、マシン全体の重心位置が下がり、コーナリング時の安定性が増します。特に立体コースが主流の現代のレースでは、この低重心化の効果は非常に大きいです。
これらのメリットを総合すると、ペラタイヤはマシンの動きをより速く、より安定させる効果があると言えます。ただし、タイヤが薄すぎるとホイールに負担がかかるというデメリットもあるため、適切な厚さに仕上げることが重要です。
ペラタイヤ作りに必要な道具はリューターまたはワークマシンが基本である
ペラタイヤを作るための道具には、大きく分けて「リューター方式」と「ワークマシン方式」の2つがあります。どちらを選ぶかで準備するものが少し変わってきます。
リューターとは小型の電動工具で、高速回転するビットやチャックにホイールを取り付け、タイヤを削る方法です。一般的には「プロクソン」や「タミヤのハンディリューター」などが使われます。リューターの利点は電池交換などの手間がなく、高速回転でスピーディーに加工できることです。ただし、専用チャックが必要だったり、パワーが強すぎてブレやすいという欠点もあります。
一方、ワークマシンとは、余っているミニ四駆のシャーシにモーターを搭載し、それを利用してタイヤを回転させながら削る方法です。始めやすいのがこのワークマシン方式で、通常のミニ四駆パーツさえあれば準備できます。実走に近い回転数で加工できるので面が出しやすく、シャフトを2点で支えるため回転のブレも少ないのが特徴です。ただし、モーターや電池の交換が必要というデメリットがあります。
どちらの方式でもさらに以下の道具が必要になります:
- デジタルノギス(タイヤ径の計測用)
- ヤスリ(粗目と細目の2種類)
- デザインナイフ(タイヤを大きく削る場合)
- パーツクリーナー(タイヤの仕上げと冷却用)
- メラミンスポンジ(タイヤ表面の仕上げ用)
- 防塵ボックス(削りカスの飛散防止)
これらの道具はホビーショップやホームセンターで揃えることができます。特にデジタルノギスは精度の高いペラタイヤを作るために必須のアイテムです。ノギスがなければ0.1mm単位の調整が困難になるので、できれば用意しておきましょう。
ペラタイヤ加工のための材料選びはタイヤの硬さで決める
ペラタイヤ加工に適したタイヤを選ぶことは、成功の第一歩です。タイヤの種類によって削りやすさや仕上がりの質が大きく変わってきます。
タイヤの削りやすさは、硬さによって大きく異なります。独自調査によると、削りやすさは「ハード→スーパーハード→ローフリクション→ノーマル→縮みタイヤ」の順になっています。特に縮みタイヤは非常に削りにくいので、初めての加工には向いていません。
初心者におすすめなのは「ローフリクションローハイトタイヤ」です。適度な硬さで削りやすく、仕上がりも綺麗になりやすいタイヤです。また、「スーパーハードタイヤ」も削りやすく、精度の高いペラタイヤが作りやすいという特徴があります。
タイヤのサイズも重要なポイントです。初心者は「ローハイトタイヤ」から始めるのがおすすめです。このタイヤは名前の通り高さが低く、車高を下げる効果があるため、現代のミニ四駆レースで最も使われているタイプです。ペラタイヤにした後の目標径は、大体24mm前後が一般的です。
また、使用するホイールの選択も重要です。カーボン強化ホイールなどの高強度タイプを選ぶと、薄く削ったタイヤの負荷に耐えることができます。ホイールの精度もペラタイヤの出来を左右するので、極端にブレているものは避けた方が良いでしょう。
タイヤとホイールのセット品を購入する場合は、「〇〇タイヤ&カーボン強化〇〇スポークホイール」のような商品がおすすめです。これならタイヤとホイールの相性も保証されています。
ミニ四駆ペラタイヤ作りの基本的な手順は5ステップである
ペラタイヤ作りの基本的な手順は5つのステップで構成されます。ここでは全体の流れを把握するために、各ステップの概要を説明します。
ステップ1:ホイールの準備 まずホイールを「貫通」させます。これは、ホイールの中心に1.7〜1.8mmのドリルで穴を開ける作業です。この工程でホイールにシャフトをしっかり通せるようになり、加工時のブレを防止できます。また、ホイールの形をヤスリで整え、テーパー(傾斜)を取り除いておくと、より精度の高いペラタイヤが作れます。
ステップ2:タイヤとホイールの接着 次にタイヤをホイールに固定します。単に嵌めただけでは加工中にタイヤが外れてしまう可能性があるので、両面テープや接着剤(シアノン、ボンドなど)でしっかり固定します。PPホイールを使用する場合は、プライマーを吹いておくとより強固に接着できます。
ステップ3:タイヤの荒削り リューターかワークマシンにホイールをセットし、タイヤを回転させながら削ります。荒削りの方法は主に2つあります。1つ目はデザインナイフを使って縦横に切り込みを入れる方法、2つ目はヤスリを使って少しずつ削る方法です。目標のタイヤ径より0.5〜1.0mm大きい状態まで削るのが目安です。
ステップ4:仕上げ削り 目の細かいヤスリ(600番以上)を使って、目標のタイヤ径まで慎重に削ります。頻繁にノギスで測定しながら、タイヤ全周の径が均一になるように調整します。深く削りすぎないよう、こまめに計測することが重要です。
ステップ5:表面の仕上げ 最後にタイヤ表面をパーツクリーナーを染み込ませたメラミンスポンジで磨きます。これにより、削りカスを取り除き、表面を滑らかに仕上げることができます。回転させながら表面を拭くと、効率よく綺麗に仕上がります。
これら5つのステップを順番に丁寧に行うことで、精度の高いペラタイヤを作ることができます。特に初心者は一気に作業を進めようとせず、各ステップでしっかり確認しながら進めることが大切です。
ペラタイヤ作りで失敗しないためのポイントは準備と忍耐である
ペラタイヤ作りでよくある失敗と、それを回避するためのポイントを紹介します。ペラタイヤ加工は根気のいる作業ですが、以下のポイントを押さえれば初心者でも成功率を高めることができます。
1. 十分な準備をする 作業前に必要な道具と材料をすべて揃えておきましょう。特にデジタルノギスは必須です。また、削りカスが飛び散るため、防塵ボックスや新聞紙などで作業場所を保護することも重要です。怪我防止のため、保護メガネやマスクの着用も検討しましょう。
2. 焦らず少しずつ削る 一度に深く削ろうとすると失敗の原因になります。特にデザインナイフを使う場合は、一気に切り込まず、何段階かに分けて少しずつ切り進めましょう。「急がば回れ」の精神で、ゆっくり確実に進めることが成功の秘訣です。
3. タイヤの熱に注意する タイヤを長時間削り続けると、摩擦熱でタイヤが溶けてしまうことがあります。特にノーマルタイプのタイヤは溶けやすいので注意が必要です。1分程度削ったら一度冷却時間を設けたり、パーツクリーナーでタイヤを冷やしながら作業すると良いでしょう。
4. 定期的に測定する 削り作業中は頻繁にノギスでタイヤ径を測定してください。しかも一箇所だけでなく、複数の場所で測定することで、タイヤ全体の均一性を確認しましょう。理想的には±0.1mm以内の誤差に収めることを目指します。
5. 失敗を恐れない 最初から完璧なペラタイヤを作ることは難しいものです。何本か失敗しながら、自分なりのコツをつかんでいくのが一般的です。失敗したタイヤも、練習の一環と考えて、次回に活かしましょう。
6. 作業時間を確保する ペラタイヤ作りは時間のかかる作業です。特に初めての場合は、1本作るのに30分以上かかることもあります。時間に余裕を持って取り組むことで、焦りによるミスを防ぐことができます。
多くの上級者も最初は失敗を繰り返しながら技術を身につけてきました。重要なのは「地道に、丁寧に、忍耐強く」という姿勢です。数をこなすことで自然とコツがつかめるようになり、徐々に精度の高いペラタイヤが作れるようになっていきます。
ミニ四駆ペラタイヤ作り方の詳細ステップ
- ホイールの準備と貫通作業はペラタイヤの精度を左右する
- タイヤとホイールの接着はシアノンやボンドが効果的である
- タイヤの荒削りはデザインナイフやヤスリで行うことが基本である
- タイヤが溶ける問題はパーツクリーナーで解決できる
- 目標径までの仕上げは細かいヤスリとノギスが必須である
- ペラタイヤの表面仕上げはパーツクリーナーとメラミンスポンジが効果的である
- まとめ:ミニ四駆ペラタイヤ作り方は根気と精度が勝負のカギである
ホイールの準備と貫通作業はペラタイヤの精度を左右する
ペラタイヤ作りの第一歩は、ホイールの準備です。この工程がペラタイヤ全体の精度を大きく左右するため、丁寧に行うことが重要です。
まず最初に行うのが「ホイール貫通」です。ホイール貫通とは、ホイールの中心に穴を開け、シャフトが完全に通るようにする作業です。通常のホイールは中心に浅い穴しかないため、このままでは加工時にホイールがブレてしまいます。1.7〜1.8mmのドリルビットを使って、ホイールを完全に貫通させましょう。
貫通作業の際は、ドリルをまっすぐに入れることが重要です。斜めに穴を開けてしまうと、回転時のブレの原因になります。標準ギヤなどを軸にかぶせてガイド代わりにすると、まっすぐに穴を開けやすくなります。
次に行うのが「ホイールの成形」です。ミニ四駆のホイールはプラスチック製品の特性上、わずかにテーパー状(縁に向かって径が大きくなる形状)になっています。このままタイヤを接着すると、タイヤも均一に削れなくなるため、リューターやワークマシンにホイールをセットし、ヤスリなどでホイールの径を均一にしておきます。
ホイールの選別も重要なポイントです。あまりにブレの大きいホイールを使うと、いくら丁寧に加工してもペラタイヤがブレてしまいます。特に4輪すべてを同じ精度にしたい場合は、事前にホイールの選別をしておくとよいでしょう。とはいえ、あまり神経質になりすぎる必要はなく、極端にブレているホイール以外は問題ないケースが多いです。
ホイール貫通に専用治具を使う方法もあります。「ホイールピアッサー」や「ヒートインサーター」などの専用工具を使えば、より精度高く簡単に貫通作業ができます。ただし、これらは必須ではなく、上記の方法でも十分に精度の高い貫通が可能です。
タイヤとホイールの接着はシアノンやボンドが効果的である
ホイールの準備が終わったら、次はタイヤとホイールをしっかり接着する工程です。この工程を丁寧に行わないと、加工中にタイヤがホイールから外れたり、歪みが生じたりする原因になります。
接着方法には主に「両面テープ」と「接着剤」の2種類があります。両面テープを使う場合は、ブレーキなどにも使われる強力粘着タイプがおすすめです。タイヤを回転させた時の遠心力でテープが伸びることがあるため、接着剤ほどの固定力はありませんが、手軽に使える利点があります。
接着剤を使う場合は、「シアノン」のような低粘度の瞬間接着剤や、「ボンドウルトラ多用途S・U」などのPPにも接着できるタイプの接着剤が効果的です。流し込みがしやすく、硬化までに時間があるシアノンは特におすすめです。
PPホイール(プラスチックホイール)を使用する場合は、接着前に「タミヤ ナイロン・PP用プライマー」を吹いておくと接着効果が高まります。プライマーはプラスチックの表面処理剤で、接着剤が効きにくい素材でも強固に接着できるようにする効果があります。
接着の手順は以下のとおりです:
- ホイールの接着面を清掃する
- 必要に応じてプライマーを吹き、乾かす
- 接着剤をホイールのリム部分に均等に塗布する
- タイヤをホイールに押し込む
- 接着剤が乾く前にリューターやワークマシンに取り付けて回転させる
最後の工程が重要で、接着剤が乾く前にタイヤを回転させることで、遠心力により接着剤が均等に広がり、より強固に接着できます。特に瞬間接着剤の場合は、外側に飛び出しやすいので、この方法が効果的です。
接着後は完全に乾くまで最低でも数時間、できれば1日程度放置すると良いでしょう。急いで加工を始めると、接着が不完全なまま作業することになり、タイヤが外れる原因になります。
タイヤの荒削りはデザインナイフやヤスリで行うことが基本である
タイヤとホイールの接着が完了したら、いよいよタイヤの削り加工に入ります。最初に行うのは「荒削り」と呼ばれる工程で、タイヤを大まかに目標径に近づける作業です。
荒削りには主に3つの方法があります:
- デザインナイフでカットする方法
- 粗目のヤスリで削る方法
- ペラタイヤ専用の治具を使う方法
最も基本的なのはヤスリを使った方法です。ワークマシンやリューターにタイヤをセットし、回転させながら粗目のヤスリをタイヤに当てて少しずつ削っていきます。この方法は時間はかかりますが、失敗が少なく初心者にも取り組みやすい方法です。
より早く削りたい場合は、デザインナイフを使う方法があります。まずタイヤの上からナイフを入れて円周に沿って切り込みを入れ、次にタイヤの側面からナイフを入れて少しずつ切り離していきます。一度に深く切りすぎるとタイヤの回転が止まってしまうので、数回に分けて徐々に切り進めるのがコツです。
デザインナイフを使う際のポイントとして、刃に水やパーツクリーナーをつけると切れ味が良くなります。また土台となるプレートを用意し、そこにナイフを置くことで安定した切り込みを入れることができます。
ペラタイヤ専用の治具(ペラクルカッターなど)を使う方法もあります。これらはタイヤをセットするだけで簡単に荒削りができる便利な工具ですが、別途購入が必要になります。
どの方法を選ぶにしても、荒削りの目標は最終的なタイヤ径より0.5〜1.0mm大きい状態にすることです。例えば最終的に24.0mmのタイヤを目指すなら、荒削りでは24.5〜25.0mmくらいまで削ります。これは後工程の仕上げ削りで微調整するための余裕を持たせるためです。
荒削りの段階では完璧を求めず、大まかに形を整えることを意識しましょう。この段階で時間をかけすぎると、集中力が続かなくなり、後の工程で失敗する原因にもなります。
タイヤが溶ける問題はパーツクリーナーで解決できる
ペラタイヤ加工中によく遭遇する問題の一つが「タイヤが溶ける」現象です。特にノーマルタイプやソフトタイプのタイヤは、ヤスリを長時間当て続けると摩擦熱によってタイヤが溶け、ベトベトになってしまうことがあります。これは精度の高いペラタイヤを作る上での大きな障害になります。
タイヤが溶ける原因は主に2つあります。1つはタイヤ自体が熱で溶けてしまうケース、もう1つはヤスリについた削りカスが熱で溶けてタイヤに付着するケースです。前者の場合は修復が難しいですが、後者であればパーツクリーナーでの清掃で対応できます。
タイヤが溶けるのを防ぐための対策は以下のとおりです:
1. 削る時間を区切る 一度に長時間削るのではなく、1分程度削ったら一度冷却時間を設けましょう。この「削る→冷ます→削る」のサイクルを繰り返すことで、タイヤの温度上昇を防ぐことができます。
2. パーツクリーナーで冷却する 削る途中でタイヤにパーツクリーナーを吹きかけると、冷却効果があります。パーツクリーナーは揮発性が高く、蒸発する際に熱を奪うため、効果的にタイヤを冷やすことができます。スポイトなどを使ってこまめに吹きかけると良いでしょう。
3. ハードタイプのタイヤを使用する タイヤの種類によって溶けやすさが異なります。一般的にハードタイプやスーパーハードタイプのタイヤは熱に強く、溶けにくい傾向があります。初心者はこれらのタイヤから始めると失敗が少なくて済みます。
4. ヤスリの圧力を調整する ヤスリをタイヤに強く押し付けすぎると、摩擦熱が増して溶けやすくなります。「当たるか当たらないか」くらいの軽い力でヤスリを当て、ゆっくりと削ることが重要です。
万が一タイヤがベトベトになってしまった場合の対処法ですが、これが削りカスの付着によるものであれば、パーツクリーナーを染み込ませた布やキムワイプでタイヤを拭くことで改善できます。キッチンペーパーでも代用可能です。何度か拭き取ることでベトベト感が消えれば回復の兆しです。
ただし、タイヤ自体が溶けてしまった場合は、残念ながら修復は難しいので、その部分を避けて使うか、新しいタイヤで作り直す必要があります。
目標径までの仕上げは細かいヤスリとノギスが必須である
荒削りが終わったら、次は「仕上げ削り」の工程に移ります。この工程では、荒削りで大まかに形を整えたタイヤを、目標のタイヤ径まで精密に削り込んでいきます。ここでの作業精度がペラタイヤの出来映えを大きく左右するため、じっくりと時間をかけて行うことが重要です。
仕上げ削りには、600〜1000番程度の細かい目のヤスリを使用します。粗い目のヤスリで削ると表面が荒れてしまうため、目の細かいヤスリでゆっくりと削ることがポイントです。一部のレーサーはさらに細かい1500番や2000番のヤスリも使用していますが、これはタイヤ表面の滑り具合に影響するので、使用するコースの特性に合わせて選ぶと良いでしょう。
デジタルノギスを使った頻繁な測定がこの工程の鍵となります。単に1箇所だけを測るのではなく、タイヤの3〜4箇所で測定することで、タイヤ全周の均一性を確認します。理想的には全周のタイヤ径の誤差が±0.05mm以内に収まることを目指しましょう。ただし神経質になりすぎる必要はなく、実用上は±0.1mm程度の誤差であれば問題ないケースが多いです。
測定と削りを繰り返す際のポイントとして、目標の径よりも少し大きい段階から特に慎重に作業することが挙げられます。0.1mmでも削りすぎると、修正が効かなくなってしまいます。「急がば回れ」の精神で、少しずつ削りながら頻繁に測定するのが成功の秘訣です。
目標のタイヤ径は、使用目的やセッティングによって異なります。一般的な目安としては以下のようになります:
- 小径タイヤ:22.0〜23.0mm
- ローハイトタイヤ:23.5〜24.5mm
- 大径タイヤ:26.0〜27.0mm
また、前後で異なるタイヤ径にすることもあります。例えば、前輪を23.8mm、後輪を24.0mmにするなど、わずかな差をつけることで走行特性を調整することもできます。
仕上げ削りの過程でも、タイヤの熱には十分注意してください。細かい目のヤスリでも長時間削り続けると熱が発生します。前述のように、こまめに冷却しながら作業を進めることが重要です。
ペラタイヤの表面仕上げはパーツクリーナーとメラミンスポンジが効果的である
目標のタイヤ径まで削れたら、最後に「表面仕上げ」の工程に移ります。この工程は見た目だけでなく、タイヤの性能にも影響する重要なステップです。
表面仕上げでは、主にパーツクリーナーとメラミンスポンジ(激落ちくんなど)を使用します。まずパーツクリーナーをメラミンスポンジに染み込ませ、タイヤを回転させながら表面を軽く擦ります。これにより、削り作業で付着した細かな削りカスが除去され、タイヤ表面が滑らかになります。
この仕上げによってタイヤ表面に微細な変化が生じ、コースとの接地感や摩擦係数に影響を与えます。表面が粗いとグリップ力は増しますが、摩擦抵抗も大きくなります。逆に表面が滑らかであれば、摩擦抵抗は減りますが、グリップ力も低下する傾向があります。
理想的なタイヤ表面の仕上がりは、回転させながら指で触ったときに「吸い付くような感覚」が得られる状態です。この状態は、適度なグリップ力と低い摩擦抵抗のバランスが取れている証です。
ただし、表面の仕上げ方は使用するコースの特性やセッティングによっても変わってきます。例えば以下のような使い分けが考えられます:
- 滑りやすいコース:やや粗めの仕上げでグリップ力を確保
- 摩擦の大きいコース:滑らかな仕上げで摩擦抵抗を低減
- 高速サーキット:より滑らかな仕上げで最高速を重視
- テクニカルコース:程よい粗さで操作性を重視
タイヤ表面の仕上げ具合によって走りの特性が変わるため、複数のタイヤを用意して走行テストを行い、最適な仕上げを見つけることも上級者には一般的です。
さらに細かいコツとして、タイヤ表面に微細な「みぞ」を付けるレーサーもいます。横みぞを付けるとコーナリング性能が向上し、縦みぞを付けると直線での安定性が増すと言われています。これはかなり高度なテクニックで、効果の程度も環境によって変わるため、経験を積んだ後に試してみると良いでしょう。
最後に、完成したペラタイヤは保管方法にも注意が必要です。長期間放置するとタイヤが変形したり、表面の状態が変化したりすることがあります。使用しない時は平らな場所に置き、直射日光を避けて保管することをおすすめします。
まとめ:ミニ四駆ペラタイヤ作り方は根気と精度が勝負のカギである
最後に記事のポイントをまとめます。
- ペラタイヤとはミニ四駆のタイヤを薄く削り加工したもので、軽量化や跳ねの抑制に効果がある
- ペラタイヤ作りには主にリューター方式とワークマシン方式の2種類があり、どちらも一長一短がある
- 必要な道具はリューターかワークマシン、ヤスリ、デザインナイフ、ノギス、パーツクリーナーが基本
- ハードタイプやスーパーハードタイプのタイヤは削りやすく、初心者におすすめである
- ホイール貫通と成形はペラタイヤの精度を左右する重要な準備工程である
- タイヤとホイールはしっかり接着することで、加工中の外れや歪みを防止できる
- 荒削りはデザインナイフやヤスリで行い、目標径よりも0.5〜1.0mm大きい状態を目指す
- タイヤが溶ける問題はパーツクリーナーでの冷却や、削る時間を区切ることで防止できる
- 目標径までの仕上げは細かいヤスリを使い、ノギスで頻繁に測定しながら慎重に行う
- 表面仕上げはパーツクリーナーとメラミンスポンジを使い、用途に合わせた表面状態に調整する
- 初心者は一気に作業を進めず、各工程で確認しながら焦らずに作業することが大切である
- ペラタイヤ作りは練習あるのみで、失敗を恐れず数をこなすことでコツがつかめるようになる