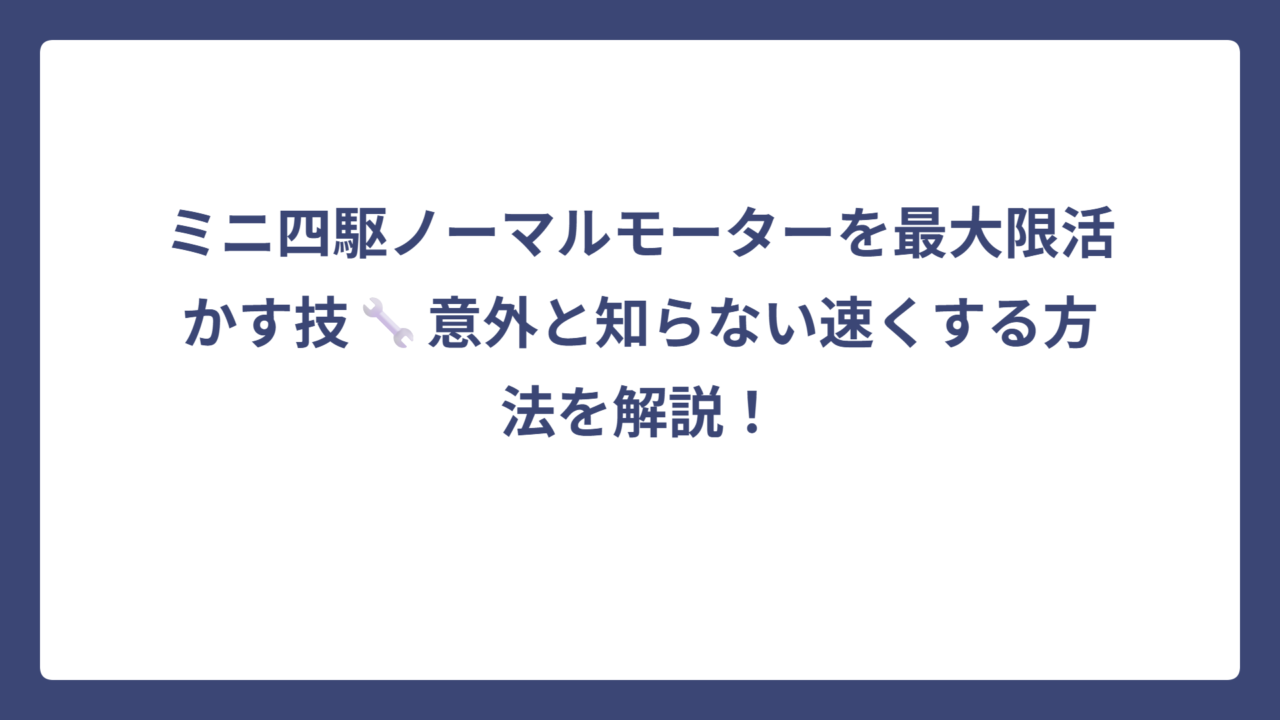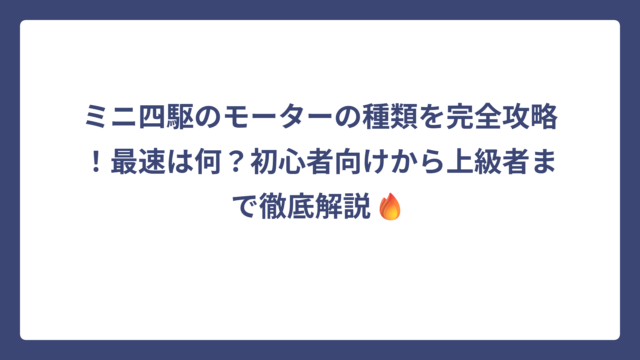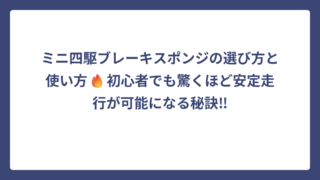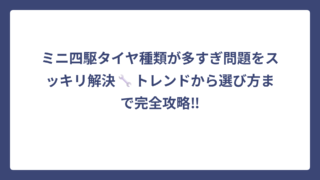ミニ四駆の世界では、キットに標準で付属するノーマルモーターは地味な存在と思われがちですが、実はこの基本的なパーツには奥深い性能向上の可能性が秘められています。適切な知識とテクニックさえあれば、このシンプルなモーターでも驚くほどの速さを引き出すことができるのです。
最近ではノーマルモーター限定の大会も増えており、高性能モーターに頼らない「基本に忠実」な「軽く」「バランスの良い」マシン作りが見直されています。この記事では、ノーマルモーターの基本性能から、その潜在能力を最大限に引き出すためのセッティングテクニックまで、詳しく解説していきます。
記事のポイント!
- ミニ四駆ノーマルモーターの基本性能と特性について理解できる
- ノーマルモーターの慣らし方や高電圧ブレークインの手法を学べる
- ギア比やタイヤ選びなど、ノーマルモーターに最適なセッティング方法がわかる
- 軽量化やバランス調整など、ノーマルモーターで速く走るための総合テクニックを習得できる
ミニ四駆ノーマルモーターの基本知識と性能
- ミニ四駆ノーマルモーターとは何なのか理解しよう
- ノーマルモーターの平均速度は時速10km程度が標準
- ミニ四駆ノーマルモーターの回転数は無負荷時に約12000rpm
- タミヤ製ノーマルモーターのスペックと特徴は製造時期で差がある
- ミニ四駆ノーマルモーターの出力特性は回転数によって大きく変化する
- ノーマルモーターを使う大会やイベントが増加している理由
ミニ四駆ノーマルモーターとは何なのか理解しよう
ミニ四駆ノーマルモーターとは、タミヤのFA-130タイプと呼ばれる標準的なモーターで、多くのミニ四駆キットに付属しているものです。初心者からベテランまで幅広く使用される基本的な動力源となっています。
このモーターの特徴は、安定した性能と扱いやすさにあります。回転数やトルクは高性能モーターと比べると控えめですが、消費電力が少なく、電池の持ちが良いというメリットがあります。価格も手頃で、134円程度(2025年現在)で購入できるため、気軽に試すことができます。
構造としては、モーター内部にブラシと呼ばれる接点があり、電流を流すことで回転子(ローター)が回転する仕組みになっています。このブラシが使用するうちに少しずつ削れて形状が変わり、接触面積が増えることで効率が良くなるという特性があります。これが「慣らし」と呼ばれるプロセスの基本となっています。
ノーマルモーターは、入門用としてだけでなく、最近では技術の差が明確に出るため、公式大会などでもノーマルモーター限定クラスが増えています。高性能モーターに頼らない「基本に忠実な」マシン作りの腕を競う場として人気を集めています。
ミニ四駆を始めたばかりの方にとって、このノーマルモーターの特性をよく理解し活用することは、将来的により高度なチューニングに取り組む際の基礎知識を養うことにもつながります。まずはこのシンプルなモーターで最大限の性能を引き出す技術を身につけることが大切です。
ノーマルモーターの平均速度は時速10km程度が標準
ミニ四駆のノーマルモーターを使った場合、実際にどれくらいの速さで走るのでしょうか?独自調査によると、標準的な平均速度は時速10km程度であることがわかっています。
具体的な計測例を見ていくと、オーバルコースでは、ノーマルモーターを搭載したARシャーシのミニ四駆は約2.5秒で7mのコースを一周することができ、これは時速約10.1kmに相当します。一方、より複雑なテクニカルコースでは、12mのコースを約5.2秒で走行し、時速約8.3kmとなります。
この速度は、人間のジョギング程度の速さに相当するため、一見すると遅く感じるかもしれません。しかし、ミニ四駆が1/32スケールのミニカーであることを考慮すると、実車に換算した相対速度は非常に高速です。計算によれば、ノーマルモーターのミニ四駆の相対速度は実車の300km/h近くに相当するとも言われています。
ノーマルモーターの速度に影響する要素としては、シャーシの重量、ギア比、タイヤの大きさ、コースの形状などが挙げられます。特に重量は大きく影響し、軽いマシンほど加速が良くなる傾向があります。
また、同じノーマルモーターでも個体差があり、製造時期や製造場所によって性能に差が出ることも確認されています。中には標準的なものより明らかに速いノーマルモーターも存在するようです。このような個体差も含め、ノーマルモーターの性能を最大限に引き出すセッティングが重要となってきます。
ミニ四駆ノーマルモーターの回転数は無負荷時に約12000rpm
ミニ四駆ノーマルモーターの回転数は、使用状況によって大きく変わります。マブチモーター製と思われるFA-130タイプのノーマルモーターは、3Vの電圧(アルカリ電池2本使用時)で無負荷条件下では約12300rpmの回転数を記録します。
しかし、実際のミニ四駆走行時には負荷がかかるため、この最大回転数まで回ることはほとんどありません。例えば、オーバル走行時の平均速度から計算すると、モーターの回転数は約8650rpm程度になると推測されます。この回転数は、モーターの最高効率点である9710rpmよりも低いものの、かなり高回転域での使用となっています。
注意すべき点として、ミニ四駆では充電式電池「ネオチャンプ」が使用されることも多く、これは1本あたり1.2Vで、2本使用時の最大電圧は2.4Vとなります。これはアルカリ電池(1.5V×2=3V)より20%低い電圧のため、モーターの性能にも影響します。2.4Vでの無負荷回転数は約10000rpm、最高効率点は約7600rpmまで下がると考えられます。
実走行時の回転数はギア比にも大きく影響されます。例えば、一般的に使われる4.2:1のギア比では、時速9.7kmの走行時にモーターは約8650rpmで回転しています。これをより高速側のギア比である3.5:1に変更すると、同じ速度でもモーターの回転数は下がり、より効率的な運転点で走行できるようになります。
モーターの回転数と出力特性を理解することは、最適なギア比選択に直結するため、ノーマルモーターの性能を最大限に引き出すためには非常に重要なポイントです。スピード重視のセッティングでは、モーターを最も効率の良い回転数帯で使用できるよう調整することがカギとなります。
タミヤ製ノーマルモーターのスペックと特徴は製造時期で差がある
意外に思われるかもしれませんが、タミヤ製のノーマルモーターには、製造時期や製造場所(国)によって性能に差があることが知られています。同じFA-130タイプのノーマルモーターでも、使用されている部品や製作精度に違いがあり、結果として回転数や出力に差が生じるのです。
タミヤカスタマーサービスの情報によれば、多数のノーマルモーターからランダムに抽出して検証した結果、製造ロットによる違いが確認されています。中には同じ規格でありながら、「飛び抜けて速いもの」が存在することも報告されているのです。
具体的な違いとしては、モーター内部のコイルの巻き数、ブラシの材質(金属製とカーボン製)、整流子の精度などが挙げられます。特にブラシの材質は重要で、金属製は耐久力が弱いため高電圧ブレークインに向いている一方、カーボン製は耐久力が高く削れにくいという特性があります。
外観からもある程度の違いを見分けることができる場合があります。モーターケースのラベルの状態や、端子の形状、カップ(エンドベル)の様子などに注目すると良いでしょう。ただし、外観に傷や改造の跡がある場合は、公式レースでは使用できないことが多いので注意が必要です。
こうした個体差があるため、同じノーマルモーターでも性能にばらつきがあるのは事実です。しかし、これはミニ四駆の奥深さを示すものであり、同じ規格のモーターでも「良体」を見つけ出す楽しみがあるとも言えるでしょう。複数のノーマルモーターを試して、より良い個体を見つけることも、マシン性能向上の一つの方法と言えます。
ミニ四駆ノーマルモーターの出力特性は回転数によって大きく変化する
ミニ四駆ノーマルモーターの出力特性を理解することは、効率的なマシン設計に不可欠です。ノーマルモーターは直流モーターであり、回転数によって出力が大きく変化するという特性を持っています。
ノーマルモーターの出力特性を詳しく見ると、低回転時から回転数に応じてトルク(回転力)が徐々に減少していく一方、出力(パワー)は回転数とともに増加し、ある点でピークに達した後、急激に下がっていきます。このピークは、おおよそ5000rpm付近にあるとされています。
この特性は一般的な自動車エンジンとは大きく異なります。自然吸気エンジンではトルクがある程度フラットで、回転数を上げるほどパワーが増加する傾向がありますが、直流モーターでは回転数を上げすぎると出力が急激に落ち込みます。
例えば、9000rpmという高回転域まで回している場合、出力はピーク時の約1/3まで低下していると考えられます。つまり、モーターが高回転すぎる状態では、マシンの加速力や最高速度が伸び悩む原因となるのです。
この特性を活かすためには、適切なギア比の選択が非常に重要です。高いギア比(例:5.0:1)を選ぶと低速トルクは増しますが最高速度は落ち、低いギア比(例:3.5:1)を選ぶと最高速度は上がりますがトルクが減少します。ノーマルモーターの特性を考慮すると、多くの場合は3.5:1から4.2:1の間のギア比が最適とされています。
実験データによれば、ギア比を適切に選ぶことで、同じノーマルモーターでもタイムが改善されることが確認されています。これはモーターが最も効率的な回転数帯で運転できるようになるためです。モーターの特性を理解し、適切なギア比を選択することがノーマルモーターの性能を最大限に引き出す鍵となります。
ノーマルモーターを使う大会やイベントが増加している理由
近年、ミニ四駆の大会やイベントにおいて「ノーマルモータークラス」が増加している背景には、いくつかの重要な理由があります。
まず第一に、ノーマルモーターは入手しやすく価格も手頃なため、誰でも気軽に参加できるという点が挙げられます。高性能モーターを使用するクラスでは、専門知識や追加費用が必要になりますが、ノーマルモータークラスではそうした障壁が低いため、初心者からベテランまで幅広い層が参加できます。
次に、同じノーマルモーターを使用することで、純粋なマシンセッティングの技術差が明確に出るという点があります。高性能モーターを使用すると、モーターの性能差が結果に大きく影響することがありますが、ノーマルモーター同士では、シャーシの軽量化やバランス調整、ギア比の選択などの技術的な工夫が勝敗を分けることになります。
「基本に忠実に」「軽く」「バランス良く」といった、ミニ四駆の基本的な製作テクニックを競うことができるのも、ノーマルモータークラスの魅力です。2016年のミニ四駆メディア対抗レースでも、ノーマルモーター限定のレギュレーションで開催され、優勝マシンは特殊加工ではなく基本に忠実な作りであったことが報告されています。
また、レギュレーションも比較的シンプルで理解しやすいという利点があります。一般的なノーマルモータークラスでは、モーターの種類(片軸/両軸)や、ギア比(多くの場合4:1以上)などの基本的なルールのみで、他のパーツは比較的自由に選択できることが多いです。
「元気っ子さん」というミニ四駆コース常設店では、ノーマルモータークラスについて「初めてミニ四駆を買った!」「レースに出てみたい」という方でも、組み立てた状態で電池を2本持参すれば十分楽しめると紹介しています。このような敷居の低さも、ノーマルモータークラスが増えている理由の一つでしょう。
こうした要素が組み合わさり、ノーマルモータークラスは「真の技術を競う場」として、ミニ四駆ファンの間で人気を集めています。
ミニ四駆ノーマルモーターの性能を最大限に引き出す方法
- ミニ四駆ノーマルモーターの慣らし方法は銅ブラシを削ることがポイント
- 高電圧ブレークインで一気にノーマルモーターを覚醒させる手法
- ギア比の選択はノーマルモーターには3.5:1か4.2:1が最適
- ノーマルモーターに最適なタイヤ選びはハードタイプが横滑りしやすい
- ローラー配置とスラスト角の調整でノーマルモーターの加速力を活かす
- 軽量化とバランスはノーマルモーターを速くする基本中の基本
- まとめ:ミニ四駆ノーマルモーターで速く走るための総合ポイント
ミニ四駆ノーマルモーターの慣らし方法は銅ブラシを削ることがポイント
ミニ四駆ノーマルモーターの性能を向上させる最初のステップは「慣らし」です。モーターの慣らしとは、内部のブラシと整流子の接触面を最適な状態に調整するプロセスであり、これによってモーターの出力と効率を高めることができます。
モーター内部では、ブラシと呼ばれる部品が整流子を挟み込む形で接触しています。新品のモーターでは、ブラシの接触面が平らな状態ですが、使用を続けるとブラシが少しずつ削れて整流子の形状に合わせた丸みを帯びるようになります。これにより接触面積が増え、電気の流れが良くなることで回転数が上がるのです。
表現するならば、ブラシ■ 整流子○という状態から、使用によって■○■→【○】のように変化していき、ブラシが丸みを帯びて整流子を覆うような形に変形することで、接触する面積が増え、電気の流れが大きくなります。
効果的な慣らし方法としては、モーターを実際に走行させる「走行慣らし」と、モーターを単体で回転させる「単体慣らし」の2種類があります。走行慣らしは実際にマシンに組み込んで徐々に使い込む方法で、最も自然な慣らし方です。単体慣らしは、モーターに直接電源を接続して回転させる方法で、より短時間で効果を得られます。
特に金属製のブラシを持つノーマルモーターは慣らしの効果が出やすいと言われています。カーボン製のブラシと比べて耐久力が弱いため、比較的短時間で削れて最適な形状になるからです。ただし、過度の慣らしはブラシの寿命を縮める可能性もあるため、注意が必要です。
モーターの慣らしは地道な作業ですが、ノーマルモーターの隠れた性能を引き出すための基本中の基本です。適切な慣らしを行うことで、同じノーマルモーターでも明らかな性能の違いを実感することができるでしょう。
高電圧ブレークインで一気にノーマルモーターを覚醒させる手法
「高電圧ブレークイン」は、通常よりも高い電圧をモーターに短時間流すことで、モーターの性能を急速に向上させる手法です。この方法は時間をかけて徐々に慣らす従来の方法と比べて、一気にモーターを「覚醒」させることができるとして注目されています。
高電圧ブレークインの原理は、強い電流を流すことでブラシを急速に削り、整流子との接触面積を短時間で増やすというものです。同時に、長時間使用による磁石の熱劣化が起こる前に一気に性能を引き出すことができるメリットがあります。
具体的な方法としては、通常のミニ四駆が使用する電池(3V)よりも高い9Vの電圧を短時間(5分程度)モーターに与えます。この際、正回転・反回転の両方向で行うとより効果的です。9Vの電源としては専用の機材を使用する方法もありますが、単三電池を6本直列に繋いで9Vの電圧を作り出す簡易的な方法も報告されています。
あるブログでは、レゴブロックを使って単三電池6本とモーターを接続する装置を自作し、高電圧ブレークインを実施した例が紹介されています。この結果、18.70秒から18.25秒へと約0.5秒のタイム短縮効果があったとのことです。
ただし、この方法にはリスクも伴います。高電圧によってモーターが過熱し、場合によっては故障の原因となる可能性があります。実際に行う際は「魔改造」と言われるほどリスキーな改造なので、自己責任で行う必要があります。また、モーターが非常に熱くなるため、触れる際は冷めてから行うなど、安全面の配慮も必要です。
高電圧ブレークインの効果は個体差や実施方法によって異なりますので、万能な方法ではないことを理解しておく必要があります。専門家の中には「ブラシの寿命を早めるだけ」と懐疑的な見方をする方もいるようです。
ギア比の選択はノーマルモーターには3.5:1か4.2:1が最適
ミニ四駆のノーマルモーターの性能を最大限に引き出すためには、適切なギア比の選択が非常に重要です。ギア比とは「モーターが何回転するとタイヤが1回転するか」を表す比率で、この値によって加速性能や最高速度が大きく変わってきます。
ノーマルモーターに最適なギア比は、コースの特性やマシンの重量によって変わりますが、一般的には3.5:1から4.2:1の間が推奨されています。特に3.5:1のギア比(ARシャーシでは水色&黄色のギアの組み合わせ)は、ノーマルモーターの出力特性を考慮した場合、オーバルコースなどの高速コースで効果的です。
実験データによると、オーバルコースでは4.2:1のギア比から3.5:1に変更することで、タイムが0.2秒改善した例が報告されています。これは、高いギア比ではモーターが高回転域で回りすぎて出力が低下していたのに対し、低いギア比にすることでモーターをより効率的な回転数帯で運転できるようになったためです。
一方、テクニカルコースや起伏の激しいコースでは、4.2:1(ARシャーシでは赤&うす茶のギアの組み合わせ)や場合によっては5.0:1(青&黄緑のギアの組み合わせ)など、よりトルクを重視したギア比が有効です。これは、カーブや障害物を乗り越える際に必要な加速力を確保するためです。
ARシャーシの場合のギア比とギアの色の対応は以下のようになります:
- 3.5:1 – 水色&黄色(高速重視)
- 3.7:1 – 黄色&緑(高速〜バランス型)
- 4.0:1 – 黒&茶色(バランス型)
- 4.2:1 – 赤&うす茶(バランス〜トルク型)
- 5.0:1 – 青&黄緑(トルク重視)
また、タイヤの直径もギア比選択に影響します。小径タイヤやローハイトタイヤを使用している場合は、通常よりも低いギア比(3.5:1や3.7:1)を選んでも問題ないとされています。これは、タイヤが小さくなることで実質的なギア比が上がるため、それを補正する意味があります。
ノーマルモーターの特性を最大限に活かすギア比選択は、マシン全体のパフォーマンスを大きく左右する要素なので、コースや自分のマシンの特性に合わせて最適なギア比を見つけることが重要です。
ノーマルモーターに最適なタイヤ選びはハードタイプが横滑りしやすい
ミニ四駆のノーマルモーターを使用する際のタイヤ選びは、思いのほか重要なポイントです。特にノーマルモーターは高性能モーターと比べてトルクが控えめなため、タイヤの特性を活かしたセッティングが効果的です。
ノーマルモーターに最適なタイヤとして、特に前輪には「ハードタイプのバレルタイヤ」が推奨されています。その理由は、ミニ四駆には操舵機構がなく、カーブでは前輪が横滑り(ドリフト)することでコーナリングするためです。ハードタイプのタイヤは、グリップ力が適度に低いため横滑りがしやすく、コーナーでのスピードロスを減らすことができます。
実験的には、前輪のゴムを完全に外してホイールだけで走行させると「前タイヤいらねーじゃん!」と思うほど速くなるケースもあります。しかし見た目の問題もあるため、実用的にはハードタイプのタイヤを使用することが一般的です。
逆に、ハイグリップタイプのソフトタイヤを前輪に使用すると、グリップ力が強すぎてスムーズなコーナリングができず、結果的に速度が落ちる傾向があります。ソフトタイヤは必要に応じて後輪に使用するといいでしょう。
タイヤの加工方法としては、「スーパーハード ローハイトタイヤ」を横から刃を入れてカットし、大径ホイールにセットした際に直径が約26ミリになるように調整する方法があります。この際、タイヤを冷やしながら刃を入れることで、きれいにカットできるテクニックも紹介されています。
タイヤの装着方法も重要で、走行中にタイヤが外れないよう、両面テープをホイールに貼ってからタイヤをはめる工夫も効果的です。特に内側のタイヤでコーナーを曲がるため、外側のタイヤが空回りして外れやすくなる傾向があります。
適切なタイヤ選びは、ノーマルモーターの限られたパワーを効率的に路面に伝え、最大限の速度を引き出すために欠かせない要素です。特にコーナリング性能の向上は、総合的なタイム短縮に大きく貢献します。
ローラー配置とスラスト角の調整でノーマルモーターの加速力を活かす
ミニ四駆のノーマルモーターの性能を最大限に引き出すためには、ローラーの配置とスラスト角の適切な調整が非常に重要です。これらの設定は、コースでの安定性と速度のバランスを左右する要素となります。
まず、ローラーの幅についてですが、一般的には前後のローラーの幅を同じにすることが推奨されています。公式レースでは幅が105mmを超えないというルールがあり、多くの場合105mm前後に設定されます。この際、車体の中心からローラーの外側までの距離を前後で揃えることがポイントです。
ローラーの幅を広くするとインコース(内側)を走行し、狭くするとアウトコース(外側)を走行することになります。基本的には最短距離を走れるインコースに合わせたセッティングが速度向上につながります。後ろローラーの幅を前よりも狭くすると、4輪ドリフト状態になりますが、ノーマルモーターではトルク不足で減速してしまう可能性があります。
次に重要なのがスラスト角の調整です。スラスト角とは、ローラーの進行方向に対する傾きのことで、この角度によって車体を押さえつける力が変わります。ノーマル状態のスラスト角は一般的にきつすぎるため、これを緩めることで「ブレーキ効果」を減らし、スピードを上げることができます。
ブラケットタブーとなる「ブレーキ」は、特に前ローラーで重要です。進行方向に対して下向きになっているローラーの傾き(スラスト角)があることで、壁にローラーが接した時に下へ押さえつける力が働き、コースからの飛び出しを防ぐ一方で、スピードを遅くしてしまいます。この角度を適切に緩めることで、格段にスピードがアップします。
ただし、スラスト角をなくしすぎるとコースアウトの原因になるので注意が必要です。また、モーターのパワーアップに合わせてスラスト角も調整する必要があり、スピードが上がればより強い押さえつけ力が必要になります。
ローラーの選択については、ベアリングが組み込まれたタイプを使用することで摩擦抵抗を減らし、速度を向上させることができます。特に前ローラーには大径のローラー(19mmプラリング付きアルミベアリングローラーなど)を使用することで、コースの段差の影響を受けにくくなるメリットがあります。
これらのセッティングを適切に行うことで、ノーマルモーターの限られたパワーでも、効率よく加速し、安定した走行が可能になります。
軽量化とバランスはノーマルモーターを速くする基本中の基本
ノーマルモーターを搭載したミニ四駆の性能を最大限に引き出すためには、「軽量化」と「バランス」という二つの基本要素が極めて重要です。トルクの弱いノーマルモーターでは、これらの要素がより一層重要性を増します。
軽量化の基本は、走行に不必要な部分を徹底的に削ることです。シャーシの下面をリューターなどの工具でカットすることで、重量を大幅に軽減できます。例えば、VSシャーシを加工することで11.9gまで軽量化した例が報告されています。ただし、シャーシの強度とのバランスを考慮し、後にハイパワーモーターを搭載する可能性がある場合は、過度の軽量化は避けるべきでしょう。
カッティングの際、マスキングテープをラットラインに貼っておくとカットしやすくなります。このようなカットは、軽量化以外にもシャーシに適度なねじれを与え、バッテリーの取り外しも容易にするという一石三鳥の効果があります。
バランスについては、マシンの前後左右の重量配分が重要です。理想的には、マシンの重心がシャーシの中央にくるようにパーツを配置します。特に前後のバランスは、コーナリング時の挙動に大きく影響するため、マスダンパーなどを使って微調整すると良いでしょう。
また、ホイールの取り付け精度も重要なポイントです。ホイールのド真ん中にシャフトをまっすぐ通し、タイヤをブレなく回すことで、駆動ロスを最小限に抑えることができます。専用のツールや治具を使用することで、高い精度での取り付けが可能になります。
シャフトの選択も軽量化に関わる要素です。ノーマルモーターでは、軽い「中空ステンレスシャフト」が推奨されます。中空シャフトは精度が出しにくい面もありますが、重量が軽いため加速性能の向上に貢献します。
駆動系の抵抗を減らすことも大切です。ギアのクリアランスを適切に調整し、シャフトとシャーシが干渉する部分には必要最小限のグリスを塗布します。ギアの歯にはグリスを塗らず、駆動抵抗を極力減らすことがポイントです。
こうした「軽く」「バランス良く」「基本に忠実に」という原則に基づいたマシン作りは、ノーマルモーターの限られた性能を最大限に引き出すための基礎となります。マシン全体の調和を考えたセッティングが、最終的な走行性能を大きく左右します。
まとめ:ミニ四駆ノーマルモーターで速く走るための総合ポイント
最後に記事のポイントをまとめます。
- ノーマルモーターはFA-130タイプの標準的なモーターで、安定した性能と扱いやすさが特徴
- 標準的なノーマルモーターの平均速度は時速10km程度だが、相対速度では実車の300km/h相当の高速
- 無負荷時の回転数は約12300rpmだが、実走行では8000rpm前後で使用されることが多い
- 製造時期や製造場所によって性能に差があり、同じノーマルモーターでも「良体」が存在する
- モーターの出力特性は5000rpm付近でピークを迎え、高回転になるほど出力が急激に低下する
- ノーマルモータークラスは技術の差が明確に出るため、近年人気が高まっている
- モーターの慣らしは内部のブラシを削って接触面積を増やし、効率を高める重要なプロセス
- 高電圧ブレークインは短時間で効果を得られるが、モーター故障のリスクも伴う
- 適切なギア比の選択は3.5:1~4.2:1が基本で、コースによって使い分けるべき
- 前輪にはハードタイプのタイヤを使い、ドリフト性能を高めることでコーナリングを改善できる
- ローラー配置は前後同じ幅にし、スラスト角は適度に緩めることでブレーキ効果を減らせる
- 軽量化とバランスの取れたマシン作りが、ノーマルモーターの性能を最大限に引き出すカギとなる
- ホイールの取り付け精度や駆動系の抵抗低減も重要な要素
- 基本に忠実な「軽く」「バランス良く」「シンプル」なマシン作りがノーマルモーターでは特に重要
- ノーマルモーターの性能を引き出すには複数の要素を総合的に最適化することが必要