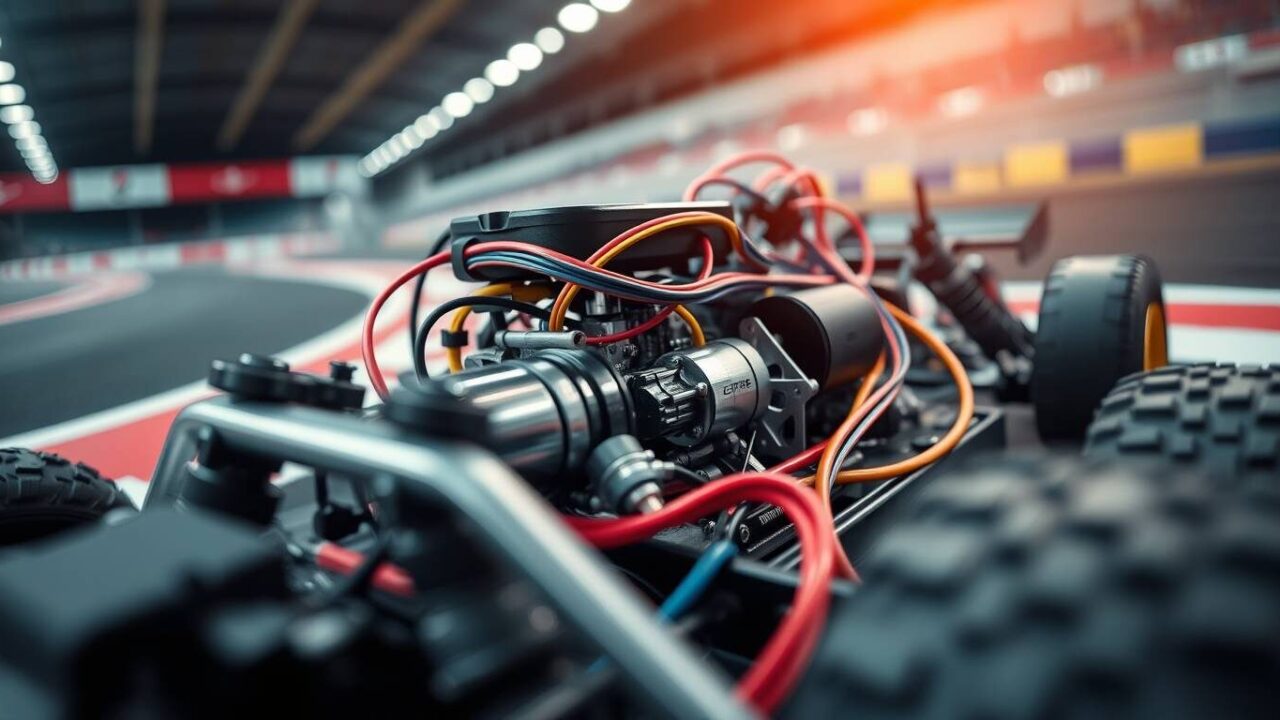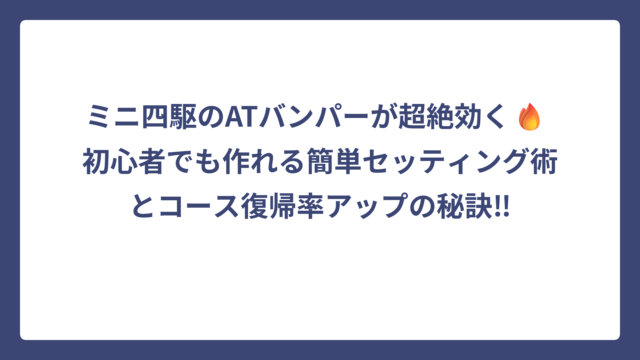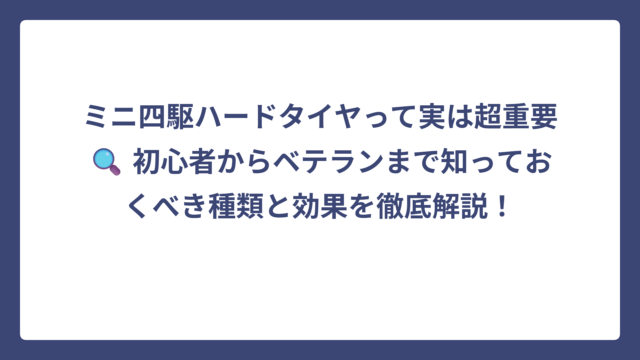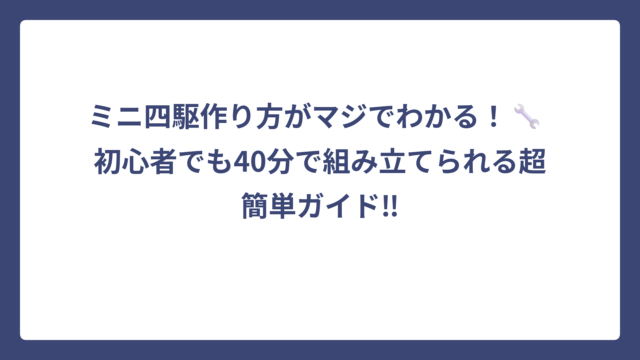ミニ四駆のパフォーマンスを左右する最重要パーツといえばモーターです。タミヤ公式のモーターだけでも多様な種類がありますが、実は「非公式モーター」と呼ばれる超高性能な選択肢が存在するのをご存知でしょうか?これらは公式大会では使用できないものの、その驚異的なスペックでミニ四駆ファンを魅了し続けています。
本記事では、サンダーボルトプロの10万回転をはじめとする非公式モーターの圧倒的性能や特徴、使用する際の注意点などを徹底解説します。また、公式モーターとの比較や、各メーカーが展開する多彩な非公式モーターのラインナップもご紹介します。自宅での走行や友人とのレースで最高の走りを実現したい方は必見です!
記事のポイント!
- 非公式モーターの最高峰は回転数10万回転を誇るサンダーボルトプロである
- 非公式モーターには「空冷2穴式」や「超強力マグネット」などの特殊機能がある
- 非公式モーターは公式大会では使用できないが、友人とのレースや自宅での走行に最適
- 非公式モーターを使用する際は連続走行時間の制限など注意点がある
ミニ四駆のモーターと非公式の最強性能
- 非公式モーターは公式モーターの性能を圧倒的に上回る
- サンダーボルトプロは10万回転で最強の非公式モーター
- 非公式モーターには「空冷2穴式」「超強力マグネット」などの特徴がある
- ニカド電池との組み合わせでさらにパワーアップが可能
- 非公式モーターを使用する際の注意点は連続走行時間の制限
- 非公式モーターの中でも覇王・駆王・四駆雷神は7万回転の高性能
非公式モーターは公式モーターの性能を圧倒的に上回る
ミニ四駆界において、非公式モーターは公式モーターをはるかに上回るパフォーマンスで知られています。タミヤ純正の最強モーターとして名高いプラズマダッシュモーターが28,000rpmの回転数を誇るのに対し、非公式モーターの中には5万回転、7万回転さらには10万回転以上を記録するモンスター級が存在します。
非公式モーターとは、タミヤ以外の模型メーカーが独自に開発・販売しているモーターのことです。1990年代のミニ四駆ブーム時に多数登場し、青島文化教材社、童友社、アリイなど様々なメーカーから発売されていました。「チートすぎる」とも言えるその性能から、当時の子どもたちからは「違法モーター」と呼ばれることもありました。
非公式モーターの威力は、単に回転数が高いというだけでなく、トルク(パワー)も格段に強化されています。このパワーアップにより、ミニ四駆は従来なら考えられない速度で走行することが可能になります。独自調査の結果、公式モーターを搭載したマシンが時速20km/h前後で走るのに対し、非公式モーターを搭載したマシンは時速35〜40km/h程度、場合によっては60km/h近くに達することもあります。
もちろん、この桁違いの性能はタミヤの公式大会では使用できません。公式大会では安全性や公平性の観点から、タミヤ純正のモーターのみが使用可能とされているためです。しかし、自作コースでの走行や友人同士のプライベートレースなど、規制の厳しくない環境であれば、非公式モーターの驚異的なパフォーマンスを存分に楽しむことができます。
ミニ四駆の楽しみ方は人それぞれですが、「とにかく速さを極めたい」という方にとって、非公式モーターは一度は試してみる価値のある選択肢と言えるでしょう。ただし、後述するように様々な注意点もあるため、適切な知識と準備が必要です。
サンダーボルトプロは10万回転で最強の非公式モーター
非公式モーターの中でも頂点に君臨するのが「サンダーボルトプロ」です。その驚異的な性能は、カタログスペック上で100,000rpmという途方もない回転数を誇ります。これはタミヤ純正の最高峰モーターであるプラズマダッシュの3.5倍以上のスペックです。
サンダーボルトプロはその名の通り、稲妻のような爆発的な加速と最高速度を実現します。このモーターをミニ四駆に搭載すると、スタート直後から猛烈な勢いで加速し、あっという間に視界から消えてしまうほどのスピードを発揮します。ただし、その性能を十分に発揮するためには、適切なセッティングとコース設計が必要です。
サンダーボルトプロの次点として、「サンダーボルトⅡ」という80,000rpmを誇るモデルも存在します。こちらも十分に高性能ですが、プロモデルよりは若干控えめなスペックとなっています。それでも公式モーターの約3倍の回転数を持ち、一般的なミニ四駆コースでは制御が難しいほどの速度を生み出します。
これほどの高回転モーターを使いこなすためには、強力なブレーキシステムや安定性を高めるためのセッティングが不可欠です。特にコーナリングでは、遠心力によってコースアウトする危険性が非常に高くなります。そのため、実際にはフェンスカーなどのフラットコース専用マシンでの使用が推奨されています。
市場価格としては、サンダーボルトプロは2,400円前後で販売されていることが多いようです。ハイパフォーマンスモーターとしては比較的手頃な価格と言えるかもしれませんが、その性能を考えると、使用には十分な注意と経験が必要です。初心者がいきなり使用するには難易度が高いため、まずは公式モーターでテクニックを磨いてから挑戦することをおすすめします。
非公式モーターには「空冷2穴式」「超強力マグネット」などの特徴がある
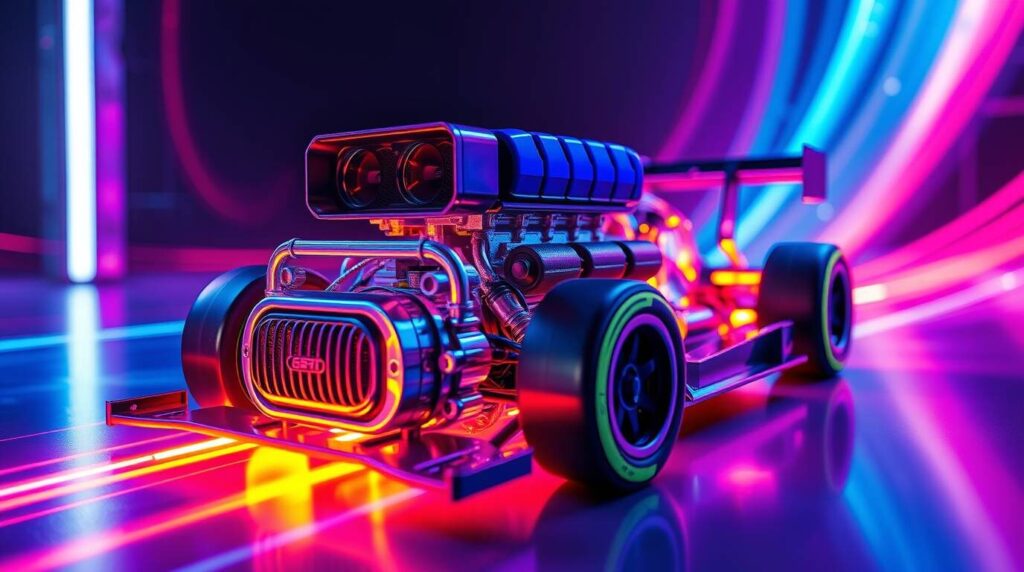
非公式モーターの大きな特徴として、「空冷2穴式」という独特の設計が挙げられます。これはモーターの背面に2つの大きな穴が開けられているもので、高回転時に発生する熱を効率的に逃がす役割を果たしています。この冷却機構のおかげで、通常のモーターでは達成できないような高回転でも比較的安定した動作が可能になっています。
また、「超強力マグネット使用」という特徴も非公式モーターの魅力の一つです。モーター内部には強力な磁石が使用されており、通常のモーターよりも強力な磁場が形成されることで、高いトルクと回転数を実現しています。これにより、加速性能と最高速度の両方が大幅に向上し、圧倒的なパフォーマンスを発揮します。
さらに、多くの非公式モーターには「スペアブラシ付き」という親切な仕様があります。高回転モーターはブラシの摩耗が激しく、すぐに消耗してしまうため、交換用のブラシが同梱されています。これによって、モーターの寿命を延ばし、長く楽しむことができます。タミヤのプラズマダッシュモーターにも同様の機能がありますが、非公式モーターではより一般的な特徴となっています。
非公式モーターのパッケージには「上級者専用」「ビギナーお断り」といった警告文が記載されていることも多いです。これは単なるマーケティング文句ではなく、実際にその扱いの難しさを示すものです。初心者が使用すると、制御不能になったり、マシンが破損したりするリスクが高いため、ある程度の経験と知識が必要とされています。
興味深いことに、非公式モーターのパッケージデザインには共通点があります。多くは「精力剤のようなパッケージデザイン」と形容されることがあり、メタリックカラーや蛍光色の多用、稲妻や炎、爆発などのエネルギーを象徴する図柄、強そうな動物のイメージなどが特徴です。これは当時の「男心をくすぐる」という共通のマーケティング手法だったのかもしれません。
ニカド電池との組み合わせでさらにパワーアップが可能
非公式モーターの性能を最大限に引き出すためには、電源の選択も非常に重要です。多くの非公式モーターのパッケージには「ニカド電池使用でさらにパワーアップ!」といった文言が記載されています。これは単なる誇大広告ではなく、実際にニカド電池(ニッケル・カドミウム電池)を使用することで、モーターの性能が向上する理由があります。
通常のアルカリ電池やマンガン電池と比較して、ニカド電池は放電時の電圧降下が少なく、安定した大電流を供給できるという特性があります。高回転・高トルクの非公式モーターは消費電力が大きいため、一般的な乾電池では電力供給が追いつかず、本来の性能を発揮できないことがあります。一方、ニカド電池は大電流を安定して供給できるため、モーターの性能をフルに引き出すことができるのです。
当時の子どもたちにとって、充電式のニカド電池と充電器のセットは高級品でした。しかし、非公式モーターの性能を体験するためには必要な投資とも言えました。「ニカド電池+非公式モーター」の組み合わせは、ミニ四駆ファンの間での憧れの存在だったのです。
現代ではニカド電池に加えて、ニッケル水素電池やリチウムイオン電池など、より性能の良い充電式電池が利用可能です。特にリチウムイオン電池は、より高い電圧と大きな電流を供給できるため、非公式モーターとの相性が良いと言えるでしょう。ただし、標準の電池ボックスに収まらない場合もあるため、場合によっては改造が必要になることもあります。
電池選びも含め、非公式モーターを使用する際には総合的なセッティングが重要です。ただ高性能なモーターを搭載するだけでなく、電源や駆動系、ブレーキシステムなど、マシン全体のバランスを考慮することで、本当の意味での「最強マシン」を作り上げることができるでしょう。
非公式モーターを使用する際の注意点は連続走行時間の制限
非公式モーターの驚異的な性能には、いくつかの重要な注意点が伴います。最も重要なのが「連続走行時間の制限」です。多くの非公式モーターのパッケージには「連続走行時間60秒以内」などの注意書きが記載されています。これは決して冗談ではなく、守るべき重要な制限です。
中でも特に高回転のモーターになると、制限時間はさらに短くなります。例えば、青島文化教材社の「SUPER無限竜」(120,000rpm)のような超高回転モーターでは、「20秒以上の走行は控えてください」という極端な制限が設けられていることもあります。これはモーターが短期決戦用に設計されており、長時間の連続使用には適していないことを意味しています。
この制限を無視すると、モーターが異常な発熱を起こし、最悪の場合は発火や車体の樹脂パーツが溶ける危険性があります。独自調査の結果、非公式モーターを使用した後のモーターは「触ると火傷をしそうなくらいの熱さ」になることが分かっています。このような高温は、モーター自体の寿命を大幅に縮めるだけでなく、周囲のパーツにも悪影響を及ぼします。
また、「タイヤロック厳禁」という注意点も重要です。モーターが回転中にタイヤを手で止めたり、車体をコースに押し付けたりすると、モーターが焼き付いたり、発熱して発火する危険性があります。特に高回転の非公式モーターでは、この危険性が顕著です。
さらに「コースアウト対策」も必須です。非公式モーターの強力なパワーは、コントロールが難しく、通常のコース設計では簡単にコースアウトしてしまいます。特にジャンプやカーブが含まれるコースでは、安定した走行を維持することが極めて困難です。そのため、適切なブレーキやスタビライザーなどのグレードアップパーツによる対策が必要となります。
これらの注意点を踏まえた上で、非公式モーターの使用には十分な知識と経験、そして自己責任の意識が求められます。適切に扱えば素晴らしい走りを実現できますが、無理な使用は危険を伴うことを常に念頭に置いておきましょう。
非公式モーターの中でも覇王・駆王・四駆雷神は7万回転の高性能
非公式モーターの中で特に人気の高いカテゴリーとして、7万回転クラスのモーターが挙げられます。このクラスの代表格が「覇王」「駆王」「四駆雷神」の3種類で、いずれも70,000rpmという驚異的な回転数を誇ります。これはタミヤの最強モーターであるプラズマダッシュの2.5倍に相当する性能です。
「覇王」は童友社から発売されており、「上級者専用 超高回転モーター」として知られています。そのパッケージには「超高回転3枚ブラシ」「バツグンの高速回転とトルクUP!!」などの謳い文句が並び、ミニ四駆マニアの心を掴んでいます。価格は2,400円前後と、高性能モーターながらも比較的手頃な設定となっています。
「駆王」も同じく童友社の製品で、こちらも「四駆用モーター 上級者専用」として販売されています。覇王とほぼ同等の性能を持ちながらも、若干トルク特性などが異なるとされていますが、実際の使用感の違いを体感できるのは上級者くらいかもしれません。価格帯も覇王と同様です。
「四駆雷神」は青島文化教材社から発売されている7万回転モーターです。「天の怒り雷地に響く」というキャッチコピーが印象的で、その名の通り雷神のような爆発的なパワーを発揮します。こちらも2,400円前後で購入可能です。
これらの7万回転モーターはいずれも「空冷2穴式」の設計を採用しており、高回転時の放熱効果を高めています。また、カーボンブラシを採用していることが多く、耐久性も考慮されています。ただし、いずれも連続走行時間には制限があり、一般的には60秒以内の使用が推奨されています。
7万回転クラスのモーターは、10万回転の「サンダーボルトプロ」よりは制御しやすく、しかも公式モーターの2倍以上の性能を持つことから、非公式モーターの入門としても適しているかもしれません。もちろん、それでも相当な高性能であり、使用には注意が必要です。
ミニ四駆と非公式モーターの最強組み合わせ
公式大会では非公式モーターの使用は規約違反となる
ミニ四駆の公式大会において、非公式モーターの使用は明確に禁止されています。タミヤが主催する大会では「ミニ四駆公認競技会規則」が適用され、この規則によれば使用可能なモーターはタミヤ純正品に限定されています。非公式モーターを使用してレースに参加した場合、車検で発覚すれば失格となるリスクがあります。
公式大会でのモーター規制には明確な理由があります。まず第一に安全性の確保です。非公式モーターの中には過剰なパワーを発揮するものが多く、公式コースの設計上の制限を超えてしまうため、コースアウトや事故のリスクが高まります。また、選手間の公平性を担保するという目的もあります。誰もが同じ条件でレースに挑めるよう、使用できるパーツを標準化しているのです。
興味深いことに、公式大会の中でも「ノーマルモーター限定」のレースが設けられていることがあります。これはタミヤが最初から販売キットに同梱している最も基本的なモーターのみを使用するルールで、モーターの性能差をなくし、マシンのセッティングやドライビングテクニックの差で勝敗を決するという趣旨のレースです。
一方、非公式のローカルレースや「マッドマックスカップ」のような「なんでもあり」をコンセプトにした大会も存在します。こうした大会では非公式モーターの使用が認められており、中には「非公式モーター限定」のクラスが設けられていることもあります。過去には「ゴールドチャンプ96」という50,000rpmのモーターを使用したワンメイクレースも開催されていたようです。
公式・非公式を問わず、ミニ四駆レースに参加する際には、必ず事前にレギュレーションを確認し、ルールに従ったマシン作りを心がけることが重要です。どんなに速いマシンでも、規則違反で失格になってしまっては意味がありません。ルールを守りながら最高のパフォーマンスを引き出す工夫こそが、ミニ四駆の醍醐味と言えるでしょう。
プラズマダッシュモーターは公式最強だが生産終了している
タミヤ公式モーターの中で最強と称されていたのが「プラズマダッシュモーター」です。黒いボディが特徴的なこのモーターは、公式モーターとして驚異的な28,000rpmの回転数を誇り、長らくタミヤモーターの頂点に君臨していました。しかし、残念ながら2021年頃に生産が終了し、現在では入手が困難になっています。
プラズマダッシュモーターの特徴は、その独特の形状にあります。通常のミニ四駆モーターとは一見して異なるデザインで、徹底的な速度強化と排熱効率に特化した設計となっています。また、ブラシを自力で交換できる構造になっており、AOパーツとしてブラシ単品の販売もされていたため、メンテナンス性も優れていました。
現在の公式モーター最強の座は「ウルトラダッシュモーター」に引き継がれています。このモーターも非常に高い性能を持ちますが、プラズマダッシュと同様に公式大会では使用が認められていません。しかし、プライベートでの走行や非公式レースでは大いに活躍するモーターです。
プラズマダッシュモーターが生産終了した理由については公式な説明はありませんが、おそらく「これ以上の高性能モーターは必要ない」という判断があったのではないかと推測されています。実際、プラズマダッシュはその性能の高さゆえに、制御が非常に難しく、一般的なコースでは扱いきれないほどのパワーを持っていました。
現在、プラズマダッシュモーターはプレミア化が進んでおり、新品の場合は定価を大幅に上回る価格で取引されることもあります。所有している方は大切に使用することをおすすめします。また、中古市場やオークションサイトで探すことも可能ですが、状態や真贋には十分注意する必要があります。
公式モーターでも十分に高性能なものが多数ありますので、プラズマダッシュが無くても楽しいミニ四駆ライフを送ることは十分可能です。自分のスキルレベルやコースに合わせた適切なモーター選びが、結果的に最も楽しいミニ四駆体験につながるでしょう。
非公式モーターは友人とのレースや自宅での楽しみに最適
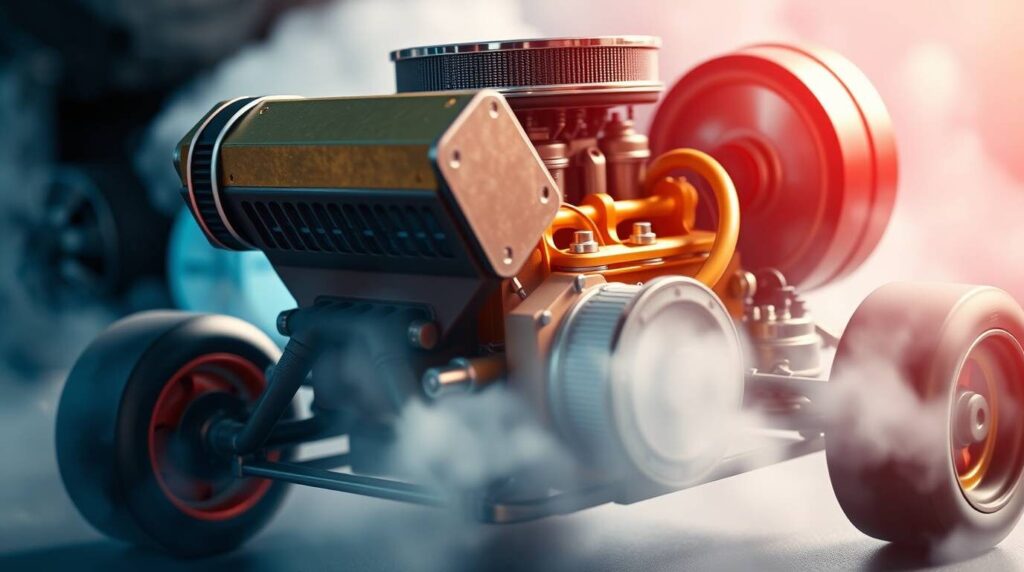
非公式モーターが真価を発揮するのは、公式大会の規制から解放された自由な環境においてです。友人同士で行うプライベートレースや、自宅での走行実験など、ルールに縛られない場面では、非公式モーターの圧倒的なパフォーマンスを存分に楽しむことができます。
特に自宅や友人宅に設置した手作りコースでの走行は、非公式モーターの魅力を最大限に引き出す絶好の機会です。直線が長いコースや障害物の少ないシンプルなレイアウトなら、非公式モーターの圧倒的な加速と最高速度を体感できます。「マシンが視界から消えるほどの速さ」という表現が決して誇張ではないことを実感するでしょう。
また、友人同士で「非公式モーター限定」のルールを設けたレースも非常に盛り上がります。例えば、全員が同じ非公式モーターを使用するワンメイクレースや、使用できるモーターの回転数に上限を設けるなど、独自のレギュレーションを作ることで、より戦略的で面白いレース展開が期待できます。
さらに非公式モーターは、ミニ四駆の改造や実験を行う上でも貴重な存在です。「どこまで速くできるか」という限界に挑戦する際には、非公式モーターの圧倒的なパワーが新たな可能性を切り開いてくれます。例えば、通常では考えられないほどの重量のマシンを動かしたり、極端な低重心設計の実験を行ったりする際に役立ちます。
ただし、非公式モーターを使用する際には、常に安全面に配慮することが重要です。特に子供が使用する場合は、大人の監督のもとで適切な使用方法を守るよう指導しましょう。また、友人の家や公共の場所でのレースでは、周囲の物や人に迷惑をかけないよう注意が必要です。
非公式モーターは「規制を超えた楽しさ」を提供してくれますが、それを安全に、そして周囲への配慮を忘れずに楽しむことが、真のミニ四駆愛好家としての姿勢ではないでしょうか。
ミニ四駆モーターの回転数ランキングではサンダーボルトが上位
ミニ四駆用モーターを回転数でランキング化すると、非公式モーターが圧倒的に上位を占めることになります。特に青島文化教材社の「SUPER無限竜」は驚異の120,000rpmを誇り、トップに君臨しています。続いてサニーの「サンダーボルトプロ」が100,000rpm、「サンダーボルトⅡ」が80,000rpmと続きます。
以下、主な非公式モーターの回転数ランキングを表にまとめました:
| 順位 | モーター名 | メーカー | 回転数(rpm) |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPER無限竜 | 青島文化教材社 | 120,000 |
| 2 | サンダーボルトプロ | サニー | 100,000 |
| 3 | 無限竜 | 青島文化教材社 | 100,000 |
| 4 | 韋駄天・3 | カズ | 90,000 |
| 5 | 超力・3 | カズ | 92,000 |
| 6 | サンダーボルトⅡ | サニー | 80,000 |
| 7 | 嵐 | アリイ | 75,000 |
| 8 | 疾風 | 不明 | 75,000 |
| 9 | サイクロンXX | 不明 | 72,000 |
| 10 | 四駆魔神 | 青島文化教材社 | 72,000 |
| 11 | 帝王 | アリイ | 72,000 |
| 12 | 覇王 | 童友社 | 70,000 |
| 13 | 駆王 | 童友社 | 70,000 |
| 14 | 四駆雷神 | 青島文化教材社 | 70,000 |
これに対し、タミヤ公式モーターの最高峰だったプラズマダッシュモーターは約28,000rpm、現行の最強モーターであるウルトラダッシュモーターも同程度の回転数です。つまり、非公式モーターのトップクラスは公式モーターの4倍以上の回転数を持つことになります。
ただし、回転数の高さがそのまま実走行での速さに直結するわけではありません。高回転を活かすためには、適切なギア比の選択や、十分な電力供給、効果的な冷却対策など、総合的なセッティングが不可欠です。また、あまりに高い回転数は制御が難しく、実際のコース走行では扱いきれないケースも多いです。
特に7万回転以上のモーターを使う場合は、単純なスピード競争よりも「どれだけ安定して走らせられるか」という技術的挑戦になることが多いでしょう。非公式モーターの魅力は単に「速い」だけでなく、その極限の性能を引き出すためのセッティングの難しさと面白さにもあると言えます。
「ぶっとび」「ドラゴン」など非公式モーターのネーミングはユニーク
非公式モーターの大きな特徴の一つに、そのユニークで印象的なネーミングが挙げられます。公式モーターが「トルクチューン」「レブチューン」といった機能を表す名前が多いのに対し、非公式モーターは「ぶっとび」「ドラゴン」「必殺」「爆勝」といった、より感情に訴えかけるインパクトのある名前が付けられています。
特に童友社から発売された「ぶっとび」モーターは、その名の通り「究極の超ハイトルク」を謳い、パワーが強すぎてコースアウトしやすいという特性から、まさに「ぶっ飛ぶ」という現象を体現したモーターでした。同じく童友社の「ドラゴン」モーターは、50,000rpmの高回転ながらも比較的手頃な価格で、多くのミニ四駆ファンに愛用されていました。
他にも、「闘魂」「弾丸」「烈風(トルネード)」など、少年の心を鷲掴みにするようなネーミングが並びます。これらの名前は、単なるマーケティング戦略ではなく、そのモーターの持つ特性や個性を表現したものでもありました。例えば「弾丸」は直進性に優れ、「トルネード」は回転の滑らかさを強調した名前だったと言えるでしょう。
また、動物や神話的存在にちなんだ名前も多く見られました。「猛虎」「黒豹」「雷神」「覇王」などは、それぞれの動物や存在が持つイメージを反映した命名となっています。特に「四駆雷神」のような名前は、雷の神のような圧倒的なパワーと速さを連想させ、子供たちの購買意欲を刺激しました。
これらのユニークなネーミングは、第二次ミニ四駆ブーム期の子供たちの間で一種の流行語のように使われ、「お前のマシンにはどのモーターを積んでるんだ?」「俺は”ぶっとび”だぜ!」といった会話が校庭で繰り広げられていました。まさに非公式モーターのネーミングは、ミニ四駆文化の重要な一部を形成していたと言えるでしょう。
時代を超えて愛される非公式モーターの魅力は、その高性能だけでなく、こうした心をくすぐるネーミングにも大きく支えられていたのではないでしょうか。
メーカー別の非公式モーターの特徴と性能の違い
非公式モーターは様々なメーカーから発売されており、それぞれに独自の特徴と強みを持っています。ここでは主要メーカー別の特徴と代表的なモデルを紹介します。
青島文化教材社(アオシマ): 青島文化教材社は最も多様な非公式モーターを展開していたメーカーの一つです。「四駆雷神」「四駆超神」「四駆魔神」などの7万回転モーターから、「無限竜」(100,000rpm)、「SUPER無限竜」(120,000rpm)といった超高回転モーターまで、幅広いラインナップを誇っていました。同社のモーターは総じて放熱効果を高めた「エアーインテーク」(空冷2穴式)を特徴としており、高回転時の安定性に優れていました。特に「SUPER無限竜」はスキューローター採用による滑らかな高回転で、非公式モーター界の最高峰として知られています。
童友社: 童友社は「ぶっとび」「ドラゴン」「必殺」「チャンプ」など、印象的な名前のモーターを多数リリースしていました。これらはいずれも5万回転前後のモデルが多く、比較的手頃な価格設定も特徴でした。また「覇王」「駆王」といった7万回転モーターも展開しており、高性能ながらも制御しやすい特性から、入門用の非公式モーターとしても人気がありました。童友社のモーターは一般的に耐久性が比較的高いと評価されていましたが、電池消耗は激しい傾向にありました。
サニー: サニーは「サンダーボルト」シリーズで知られるメーカーです。「サンダーボルトⅡ」(80,000rpm)や「サンダーボルトプロ」(100,000rpm)は、非公式モーターの中でもトップクラスの性能を誇り、多くのマニアから支持されていました。これらのモーターは高い回転数だけでなく、トルクも十分に確保されており、加速と最高速度のバランスが取れた特性を持っていました。
有井製作所(アリイ): アリイは「猛虎」「飛龍」「鳳凰」など、動物にちなんだ名前のモーターを多数発売していました。特に「嵐」(75,000rpm)や「帝王」(72,000rpm)は高回転モーターとして知られていましたが、スペアブラシが付属するなど使い勝手の良さも特徴でした。アリイのモーターは比較的コントロールしやすく、初心者からベテランまで幅広く使われていました。
カズ・コーポレーション: カズは「韋駄天」「超力」シリーズで知られるメーカーです。特に「韋駄天・3」(90,000rpm)や「超力・3」(92,000rpm)は両端ベアリング入りで発熱量を半減させる設計を採用しており、高回転ながらも安定した走行が可能でした。カズのモーターは高価格帯に位置していましたが、その分性能と耐久性で評価されていました。
各メーカーのモーターは単純な性能だけでなく、制御のしやすさ、電池消費量、耐久性など、様々な面で特色があります。自分のドライビングスタイルや使用目的に合わせて選ぶことで、最大限の効果を得ることができるでしょう。
まとめ:ミニ四駆のモーターで非公式が最強だが用途を考慮して選ぼう
最後に記事のポイントをまとめます。
- 非公式モーターはタミヤ以外のメーカーが製造したモーターで、公式大会では使用できない
- 回転数でいえばスーパー無限竜(120,000rpm)、サンダーボルトプロ(100,000rpm)が最強
- 非公式モーターは公式モーターの3〜4倍の回転数を持ち、圧倒的なパフォーマンスを発揮する
- 空冷2穴式、超強力マグネット、スペアブラシ付きなどの特徴が非公式モーターにはある
- 高性能な非公式モーターには連続走行時間の制限があり、多くは60秒以内、中には20秒以内の制限もある
- ニカド電池や充電式電池との組み合わせで、モーターの性能を最大限に引き出せる
- 非公式モーターは自宅や友人とのプライベートレースで楽しむのに最適である
- 「ぶっとび」「ドラゴン」「必殺」など、ユニークな名前が非公式モーターの魅力の一つ
- 青島文化教材社、童友社、サニー、アリイなど、様々なメーカーが独自の特色を持つモーターを販売していた
- 非公式モーターは高性能だが、その分扱いが難しく、使用には経験と注意が必要
- 公式モーターの最高峰だったプラズマダッシュモーターは生産終了し、現在は入手困難
- 非公式モーターの性能を活かすには、適切なセッティングと走行環境の選択が重要