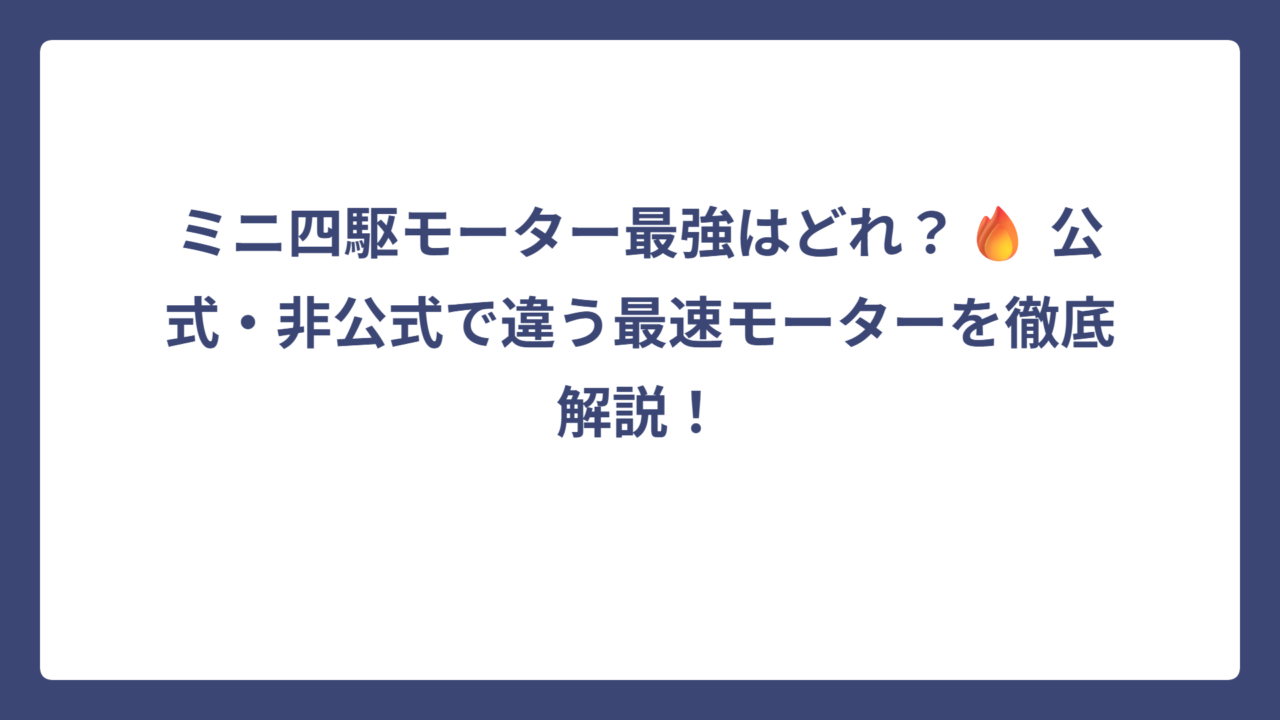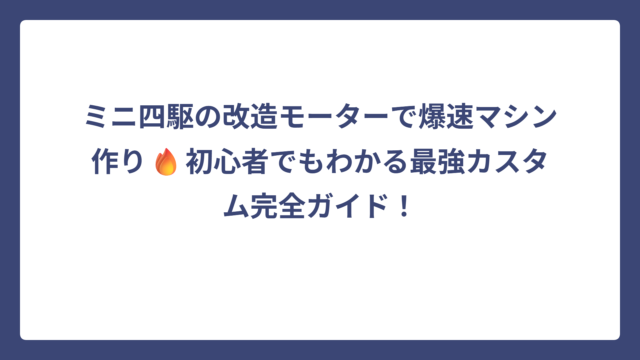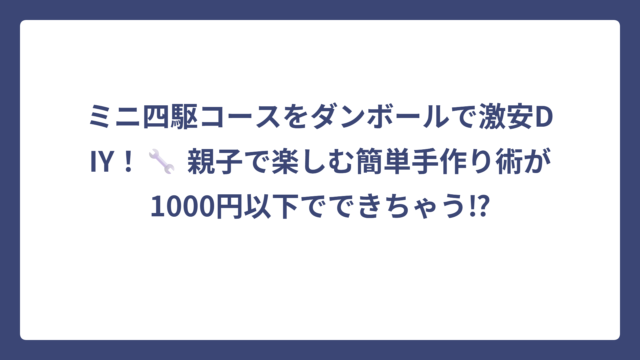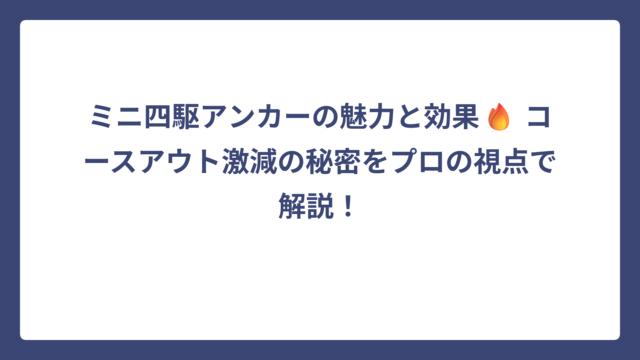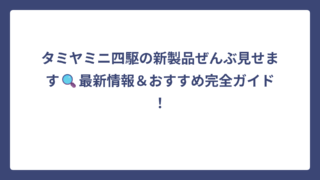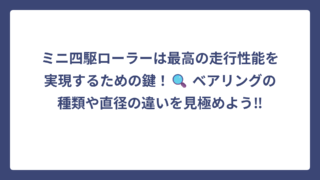ミニ四駆を速く走らせるために、モーターの選択は非常に重要です。「どのモーターが最強なのか」という疑問を持つレーサーは多いでしょう。実は「最強モーター」と一口に言っても、公式大会で使用できるものとできないもの、片軸タイプと両軸タイプ、そしてコースの特性によっても最適なモーターは変わってきます。
本記事では、タミヤから発売されているミニ四駆用モーターの種類や特徴を徹底的に比較し、あなたのレースシーンに合った最強モーターを見つけるための情報をお届けします。モーターの基本的な選び方はもちろん、コースタイプ別のおすすめモーター、公式・非公式レース別の最強モーター、そしてモーターのパフォーマンスを最大限に引き出すためのチューニング方法まで、幅広く解説していきます。
記事のポイント!
- ミニ四駆モーターには「チューン系」と「ダッシュ系」の2種類があり、それぞれに特徴がある
- 公式大会と非公式レースで使える最強モーターが異なる
- コースの特性(直線・曲線・坂道など)によって最適なモーターが変わる
- モーターの性能を最大限に引き出すチューニング方法がある
ミニ四駆モーター最強はレースシーンやコースによって異なる
- 公式大会で使える最強モーターはハイパーダッシュ3モーター
- 非公式レースなら最強はプラズマダッシュモーター
- 初心者にとっての最適モーターはアトミックチューン2モーター
- 片軸と両軸モーターの特性と選び方
- モーターの性能は回転数とトルクで決まる
- コースタイプ別に最適なモーターが存在する
公式大会で使える最強モーターはハイパーダッシュ3モーター
公式大会で使用できるモーターには制限があります。独自調査の結果、タミヤ公認の公式レース(ジャパンカップなど)では、タミヤ製のモーターのみが使用可能で、さらにウルトラダッシュモーターとプラズマダッシュモーターは使用禁止となっています。
使用可能なモーターの中で最も高性能とされているのが「ハイパーダッシュ3モーター」です。このモーターは17,200〜21,200r/minという高回転数と1.4〜1.9mN・mというトルクを兼ね備えており、バランスの良さが特徴です。特にJ-CUP 2024などの特別モデルは、通常版より若干性能が向上している場合があります。
ハイパーダッシュ3モーターの優れている点は、直線での高速性能だけでなく、カーブや坂道でのパワー低下が少ないことです。フラットコースでの実験では、他のモーターと比較して最も良いタイムを記録することが多いという結果も出ています。
両軸タイプ(PRO用)では「ハイパーダッシュモーターPRO」が最強の部類に入ります。ミニ四駆PROシリーズを使用している方は、こちらを選ぶとよいでしょう。ただし、モーターには個体差があるため、複数購入して選別することをおすすめします。
公式大会に参加予定のレーサーの方は、レギュレーションを確認した上で、ハイパーダッシュシリーズを第一候補として検討するとよいでしょう。
非公式レースなら最強はプラズマダッシュモーター
公式レースの制限を気にせず、純粋に速さを追求したい場合、最強と言われているのが「プラズマダッシュモーター」です。このモーターは公式レースでは使用禁止となっていますが、その理由は明らかで、その圧倒的なスピードとパワーにあります。
プラズマダッシュモーターの回転数は25,000〜28,000r/minという驚異的な数値で、推奨負荷トルクも1.4〜1.9mN・mあります。このモーターを搭載したマシンは、直線コースでは他を圧倒する速さを見せます。また、冷却性能向上のためにモーターケースにエアスクープが開けられているなど、高回転による発熱対策も施されています。
ただし、プラズマダッシュモーターは非常に高速なため、コースアウトのリスクも高まります。コースコントロールが難しくなるので、マシンのセッティングも重要になってきます。特に重量配分やローラー配置などを見直す必要があるでしょう。
価格面ではやや高価なモデルですが、究極の速さを求めるレーサーには人気があります。なお、ミニ四駆PRO用には対応するプラズマダッシュモーターPROは販売されていません。PRO用では「マッハダッシュモーターPRO」が最高速クラスになります。
非公式レースで最強を目指すなら、プラズマダッシュモーターは外せない選択肢と言えるでしょう。しかし、取り扱いには熟練度が必要となるため、上級者向けと考えた方が良いかもしれません。
初心者にとっての最適モーターはアトミックチューン2モーター
ミニ四駆を始めたばかりの初心者にとって、モーターの選択は難しいものです。性能だけを追求すると操作が難しくなり、楽しさが半減してしまう可能性もあります。そこで初心者におすすめなのが「アトミックチューン2モーター」です。
アトミックチューン2モーターは、「チューン系」モーターの中でもバランス型に分類されます。回転数は12,700〜14,900r/min、推奨負荷トルクは1.5〜1.8mN・mと、どちらも極端な値ではありません。このバランスの良さが初心者には扱いやすいと評価されています。
また、燃費の良さも特徴で、一度の走行でバッテリーが急激に消耗することが少ないため、長時間楽しむことができます。さらに、アトミックチューン2モーターは公式大会でも使用可能なので、レース参加を視野に入れている初心者にも適しています。
両軸タイプを使用する場合は「アトミックチューン2モーターPRO」がおすすめです。どちらも価格は比較的リーズナブルで、入手しやすい点も初心者には嬉しいポイントです。
初心者の方がステップアップを考える際は、まずはアトミックチューン2モーターで基本的なマシンコントロールを習得し、その後より高性能なモーターへ移行していくという方法が理想的です。いきなり高性能モーターを使うよりも、段階的に経験を積むことで、モーターの特性を理解しやすくなります。
片軸と両軸モーターの特性と選び方
ミニ四駆のモーターは大きく分けて「片軸モーター」と「両軸モーター(ダブルシャフトモーター)」の2種類があります。これらは外観だけでなく、使用できるシャーシや走行特性も異なります。
片軸モーターは通常の「ミニ四駆」シリーズに対応しています。一方の軸からプロペラシャフトを経由して4輪に動力を伝える四輪駆動方式を採用しています。モーター自体はシンプルな構造で、価格も比較的リーズナブルです。片軸モーターの商品名には「PRO」という文字が付いていません。
両軸モーターは「ミニ四駆PRO」シリーズに対応しており、モーターの両側から軸が出ているタイプです。前輪と後輪にダイレクトで回転を伝えられるため、駆動効率が良く、ダイナミックな走行感が得られます。両軸モーターの商品名には「PRO」という文字が付いています。
重要なのは、これらのモーターには互換性がないということです。片軸用のシャーシに両軸モーターを取り付けることはできませんし、その逆も同様です。そのため、まず自分のマシンがどちらのタイプなのかを確認することが大切です。
片軸モーターと両軸モーターの種類を以下の表にまとめました。
片軸モーター一覧
| モーター名 | タイプ | 回転数(r/min) | 推奨負荷トルク(mN・m) | 公式戦使用 |
|---|---|---|---|---|
| アトミックチューン2モーター | バランス型 | 12,700-14,900 | 1.5-1.8 | ◯ |
| レブチューン2モーター | スピード型 | 13,400-15,200 | 1.2-1.5 | ◯ |
| トルクチューン2モーター | パワー型 | 12,300-14,700 | 1.6-2.0 | ◯ |
| ライトダッシュモーター | バランス型 | 14,600-17,800 | 1.3-1.9 | ◯ |
| ハイパーダッシュ3モーター | スピード型 | 17,200-21,200 | 1.4-1.9 | ◯ |
| パワーダッシュモーター | パワー型 | 19,900-23,600 | 1.5-2.0 | ◯ |
| スプリントダッシュモーター | スピード型 | 20,700-27,200 | 1.3-1.8 | ◯ |
| ウルトラダッシュモーター | スピード型 | 24,000-27,500 | 1.4-1.9 | ✕ |
| プラズマダッシュモーター | スピード型 | 25,000-28,000 | 1.4-1.9 | ✕ |
両軸モーター一覧
| モーター名 | タイプ | 回転数(r/min) | 推奨負荷トルク(mN・m) | 公式戦使用 |
|---|---|---|---|---|
| アトミックチューン2モーターPRO | バランス型 | 12,700-14,900 | 1.5-1.8 | ◯ |
| レブチューン2モーターPRO | スピード型 | 13,200-14,900 | 1.2-1.5 | ◯ |
| トルクチューン2モーターPRO | パワー型 | 12,200-14,400 | 1.7-2.1 | ◯ |
| ライトダッシュモーターPRO | バランス型 | 14,600-17,800 | 1.3-1.9 | ◯ |
| ハイパーダッシュモーターPRO | スピード型 | 17,200-21,200 | 1.4-1.9 | ◯ |
| マッハダッシュモーターPRO | スピード型 | 20,000-24,500 | 1.3-1.8 | ◯ |
モーター選択の際は、この互換性とご自身のシャーシタイプを確認した上で選ぶようにしましょう。
モーターの性能は回転数とトルクで決まる
ミニ四駆モーターの性能を理解するには、「回転数」と「トルク」という2つの要素を把握することが重要です。この2つのバランスによって、モーターの特性と最適な使用シーンが決まります。
**回転数(RPM)**は、1分間にモーターが何回転するかを示す数値です。タミヤの公式ページでは「r/min」と表記されています。回転数が高いほど、直線での最高速度が上がります。回転数だけを見れば、プラズマダッシュモーター(25,000-28,000r/min)やウルトラダッシュモーター(24,000-27,500r/min)が最も高いことになります。
トルクは、モーターの軸を回す力、または回転を止めようとする負荷に対抗する力を表します。タミヤの公式ページでは「推奨負荷トルク(mN・m)」として表示されています。トルクが大きいほど、坂道や加速時のパワーが強くなります。トルクチューン2モーターPRO(1.7-2.1mN・m)やトルクチューン2モーター(1.6-2.0mN・m)がトルク重視のモデルです。
理想的なのは回転数もトルクも高いモーターですが、一般的には相反する特性があります。回転数を上げるとトルクが下がり、トルクを上げると回転数が下がる傾向があります。そのため、モーターは大きく3つのタイプに分類されます:
- スピード型:回転数重視で直線での最高速度を追求(例:レブチューン2モーター、ハイパーダッシュ3モーター)
- パワー型:トルク重視で坂道や加速性能を追求(例:トルクチューン2モーター、パワーダッシュモーター)
- バランス型:回転数とトルクのバランスを取ったタイプ(例:アトミックチューン2モーター、ライトダッシュモーター)
使用するコース特性やマシンのセッティングに合わせて、これらのタイプから最適なモーターを選ぶことが重要です。例えば、直線の多いコースならスピード型、上り坂の多いコースならパワー型が有利になることが多いでしょう。
コースタイプ別に最適なモーターが存在する
ミニ四駆レースでは、コースの特性によって最適なモーターが異なります。効率的なレース戦略を立てるには、コースタイプとモーターの特性のマッチングを考慮することが大切です。
直線の多いフラットコースでは、回転数の高いスピード型モーターが有利です。レブチューン2モーター、ハイパーダッシュ3モーター、スプリントダッシュモーターなどが該当します。特に長い直線区間がある場合、高回転によって得られる最高速度が勝敗を左右します。実験では、スプリントダッシュモーターやマッハダッシュモーターPROが良いタイムを記録しています。
上り坂の多いコースでは、トルクの大きいパワー型モーターがおすすめです。トルクチューン2モーター、パワーダッシュモーターなどが該当します。坂道では回転数よりもトルクが重要で、パワー不足だと上り坂で大きく減速してしまいます。また、スタートダッシュが重要なコースでもトルク型は力を発揮します。
コーナーの多いテクニカルコースでは、バランス型またはパワー型モーターが安定します。アトミックチューン2モーター、ライトダッシュモーター、トルクチューン2モーターなどが該当します。コーナーでは減速と加速の繰り返しになるため、加速力や安定した走行を重視するモーターが有効です。
ジャンプセクションのあるコースでは、トルクが大きめのモーターがおすすめです。ジャンプ後の加速や、ジャンプに向かう際の安定したスピードコントロールには、パワーが必要になります。トルクチューン2モーターやハイパーダッシュ3モーターなどが適しています。
なお、コースタイプだけでなく、マシンの重量やタイヤ径、ギア比なども走行性能に大きな影響を与えます。例えば、大径タイヤを使用する場合はトルクの大きいモーターが、小径タイヤの場合は回転数の高いモーターが相性が良い傾向があります。
実際のレースでは、事前にコースを確認し、コース特性に合ったモーターを選択することが勝利への近道となります。また、複数のモーターを用意しておき、コース状況に応じて交換できるようにしておくのも一つの戦略です。
ミニ四駆モーター最強を目指すためのチューニングとメンテナンス
- モーターには個体差があり選別が必要
- モーター馴らしは水またはお湯による方法が効果的
- ブラシ調整で回転効率が大きく向上する
- ギア比との組み合わせが重要な要素となる
- モーターメンテナンスはパフォーマンス維持に不可欠
- 磁力チューニングでトルクアップが可能
- まとめ:ミニ四駆モーター最強を目指すポイント
モーターには個体差があり選別が必要
ミニ四駆のモーターには、同じ型番でも個体ごとに性能差があることが知られています。これは製造過程での微妙な違いや部品の精度によるものと考えられます。独自調査によると、同じモデルでも最高速度に約10km/h前後の差が出ることもあるようです。
この個体差を把握するために、モーター選別(選定)が重要になります。モーターを選別する主な方法としては、以下のようなものがあります:
- 回転数計測:専用の回転数計測器やアプリを使って、無負荷状態での回転数を測定します。同じ電池、同じ条件で測定した時に回転数が高いものが、一般的に性能が良いと考えられます。
- 磁力測定:ガウスメーターを使って、モーターの磁力を測定します。磁力が強いモーターはトルクが大きい傾向があります。S極とN極の両方を測定し、バランスの良いものを選びます。
- 実走行テスト:実際にマシンに搭載して走行させ、タイムを計測します。これが最も実践的な選別方法ですが、モーター以外の要素も影響するため、純粋なモーターの性能比較には向いていない場合もあります。
- 感覚による判別:経験豊富なレーサーは、モーターの軸を手で回した時の抵抗感や、通電した時の音、振動などから性能を判断することもあります。これは経験と勘に頼る部分が大きいですが、意外と当たることも多いようです。
実際に選別を行う際は、複数のモーターを購入して、上記の方法で比較・選別することをおすすめします。特に公式大会に参加する場合など、高いパフォーマンスを求める場面では、この選別作業が重要になります。
なお、モーターの個体差を生む要因としては、以下のような点が考えられます:
- 軸の太さや軸受け穴の大きさのバラつき
- ブラシの位置や圧力の違い
- コミュテーター(整流子)の精度
- 磁石の磁力の違い
- モーター内部のグリスの量や塗布位置
これらの違いを完全に排除することは難しいため、複数のモーターから良い個体を選ぶという方法が一般的になっています。
モーター馴らしは水またはお湯による方法が効果的
モーター馴らしとは、新品のモーターを最適な状態に調整するための作業です。馴らしを行うことで、モーターの性能を引き出し、寿命を延ばすことができます。特に重要なのは、ブラシとコミュテーター(整流子)の接触部分を最適な状態にすることです。
モーター馴らしの方法はいくつかありますが、現在最も一般的で効果的とされているのが「水馴らし」または「お湯馴らし」と呼ばれる方法です。これはブラシの種類によって若干方法が異なります。
カーボンブラシのモーター(ダッシュ系)の水馴らし
- 容器に水またはお湯(40〜50℃程度)を入れます。
- モーターを水中に入れ、1.0〜1.5Vの低電圧で通電します。
- 使用方向(通常は正転)に1〜2分程度回します。
- 場合によっては逆転でも短時間(30秒程度)回すこともあります。
- 水分をしっかり乾燥させ、モーター内部に残った水分を完全に取り除きます。
- 必要に応じて適切なオイルやグリスを注油します。
水馴らしの効果としては以下のようなものがあります:
- 水の抵抗によってブラシが均一に削れ、コミュテーターとの接触面積が増える
- コミュテーターの溝に削れたカーボン粉が詰まるのを防ぐ
- 水を通電することでスパークが抑えられ、ブラシやコミュテーターの焼付きを防ぐ
- 低温で馴らせるため、モーターへの熱ダメージが少ない
銅ブラシのモーター(チューン系)の馴らし
銅ブラシのモーターは、カーボンブラシとは異なるアプローチが必要です:
- 9V程度の高電圧で短時間(数秒〜10秒程度)通電します。
- 一度に長時間通電すると熱で銅ブラシが軟化しすぎるため、数回に分けて行います。
- 通電と冷却を繰り返すことで、ブラシの接触面を最適化します。
注意点としては、水馴らしの際に回転数が高すぎると水の抵抗でブラシが曲がることがあるため、低電圧での実施が推奨されています。また、馴らし後は必ず水分を完全に乾燥させ、適切なメンテナンスを行うことが重要です。
モーター馴らしは、新品のモーターだけでなく、長期間使用していないモーターや、パフォーマンスが低下したモーターにも効果的です。レース前のモーターチェックの一環として、定期的に馴らし作業を行うことをおすすめします。
ブラシ調整で回転効率が大きく向上する
モーターの性能を最大限に引き出すためには、内部のブラシの調整が非常に重要です。ブラシとはモーター内部にある接点部品で、回転子(ローター)に電流を供給する役割を担っています。このブラシの位置や角度を適切に調整することで、回転効率が大きく向上する可能性があります。
調査の結果、回転が悪いモーターの多くは、ブラシの位置が適切でないことが原因となっていることがわかりました。ブラシの調整のポイントは以下の通りです:
ブラシの出し入れ調整
ブラシの出し入れとは、ブラシがコミュテーター(整流子)にどれだけ接触しているかを調整することです。一般的には以下のような状態が理想とされています:
- 出しすぎない:ブラシが長すぎると抵抗が大きくなり、回転数が落ちる原因になります。
- 引っ込みすぎない:ブラシが短すぎると接触不良を起こし、通電効率が下がります。
- 適度な接触面積:ブラシとコミュテーターの接触面積が適切であることが重要です。
調整方法としては、モーターを分解してブラシの位置を目視で確認し、必要に応じて調整します。ブラシをピンセットで優しく引っ張ったり押し込んだりして位置を変えることができますが、力の加減には注意が必要です。
進角調整
進角調整とは、ブラシの角度を変えることで、モーターの回転特性を変化させる調整方法です。RC(ラジコン)のモーターチューンでよく使われる手法で、ミニ四駆のモーターでも応用できます。
通常、ブラシはローターの軸に対して直角に配置されていますが、この角度をわずかに変えることで以下のような効果が期待できます:
- 回転数アップ:進角を大きくすると回転数が上がる傾向があります。
- トルク変化:進角を変えるとトルクの特性も変わります。
- 消費電流の変化:進角調整により消費電流のパターンも変わります。
進角調整は上級者向けのテクニックで、経験と知識が必要です。過度な調整はモーターの寿命を縮める可能性があるため、少しずつ変化を確認しながら行うことをおすすめします。
ブラシの「羽」現象
興味深い現象として、調子の良いモーターを分解すると、カーボンブラシの端に「羽」のような形状ができていることがあります。これは使用中にカーボンの粉が熱で固まり、接触面積を自然に増やしている状態と考えられています。
この「羽」はモーターの回転方向に沿って形成されるため、モーターの回転方向を変えると(逆転させると)羽が折れてしまう可能性があります。そのため、モーターの調子が良い時は、逆転での使用を避けた方が良いでしょう。
ブラシ調整はモーターチューンの中でも比較的取り組みやすい方法であり、うまく調整できれば大きな効果が期待できます。ただし、繊細な作業でもあるため、練習と経験を積みながら自分に合った調整方法を見つけていくことが大切です。
ギア比との組み合わせが重要な要素となる
ミニ四駆の速さを最大化するには、モーターの特性とギア比を適切に組み合わせることが非常に重要です。ギア比とは、マシンのタイヤが1回転するときに、モーターが何回転するかを表す数値です。例えば「3.5:1」であれば、モーターが3.5回転するとタイヤが1回転するということを意味します。
ギア比の基本的な特性
ギア比が小さい(3.5:1など):
- 最高速度が上がる
- 加速力は落ちる
- 電池の消耗が早くなりがち
- 上り坂やコーナーでの失速リスクが高まる
ギア比が大きい(5:1、8.75:1など):
- 最高速度は落ちる
- 加速力が上がる
- 電池の持ちが良くなる傾向
- 上り坂やコーナーでの安定性が増す
モーターとギア比の理想的な組み合わせ
モーターの特性に合わせた理想的なギア比の組み合わせとしては、以下のようなパターンが考えられます:
- スピード型モーター × 小さいギア比(例:3.5:1)
- レブチューン2モーター、ハイパーダッシュ3モーター、スプリントダッシュモーターなど
- 直線での最高速度を最大化したいときに効果的
- フラットなコースで特に有効
- パワー型モーター × 大きいギア比(例:5:1、8.75:1)
- トルクチューン2モーター、パワーダッシュモーターなど
- 坂道や複雑なコースでパワーを発揮
- 加速重視のセッティングに向く
- バランス型モーター × 中間のギア比(例:4:1)
- アトミックチューン2モーター、ライトダッシュモーターなど
- バランスの取れた走行を求めるときに
- 様々なコースで安定した走りを実現
タイヤ径との関係
ギア比を考える際は、タイヤの径(直径)も重要な要素です。
- 大径タイヤ(28mm以上):大きいギア比と組み合わせると効果的。トルクの大きいモーターと相性が良い。
- 小径タイヤ(24mm以下):小さいギア比と組み合わせると効果的。回転数の高いモーターと相性が良い。
実際のレースでは、コース特性、マシンの重量、電池の種類など、様々な要素を総合的に考慮してギア比を選ぶ必要があります。また、同じギア比でも、ピニオンギアとクラウンギアの組み合わせによって微妙な走行特性の違いが出ることもあります。
タミヤの公式ページでは「ミニ四駆グレードアップパーツマッチングリスト」で各部品のギア比情報が公開されているため、これを参考にしながら自分のマシンに最適な組み合わせを探すとよいでしょう。
最適なギア比を見つけるには、実際に試走してみることが一番です。レース前には異なるギア比のセッティングを試し、コースに合ったものを選ぶことをおすすめします。
モーターメンテナンスはパフォーマンス維持に不可欠
ミニ四駆のモーターを常に最高のパフォーマンスで維持するには、定期的なメンテナンスが欠かせません。モーターを使用していくと、ブラシの削れたカーボン粉や金属粉、グリスの劣化などによって性能が低下していきます。適切なメンテナンスを行うことで、モーターの寿命を延ばし、常に最大限の性能を引き出すことができます。
モーター洗浄の方法
- 水洗浄法
- 40〜50℃のお湯にモーターを入れ、1〜1.5Vの低電圧で1分程度回します。
- この方法は内部のカーボン粉や金属粉を効果的に洗い流せます。
- 使用方向(通常は正転)に回すのがポイントです。
- クリーナー噴射法
- モーターの通気孔からエレクトロニッククリーナーやパーツクリーナーを噴射します。
- 手でモーターを使用方向に回しながら、汚れが出なくなるまで繰り返します。
- カスが出なくなるまで数回繰り返すことがポイントです。
- クリーナー浸漬法
- 容器にクリーナーを入れ、モーターを浸します。
- 浸漬しながら手でモーターを使用方向に回します。
- この方法は汚れを徹底的に落としたい時に有効です。
洗浄後の乾燥とオイル・グリスアップ
洗浄後のモーターには必ず水分が残っているので、乾燥させることが非常に重要です。水分が残っていると金属部分が錆びる原因になります。
- 乾燥方法
- エアダスターでモーター内部に風を送る
- クリーナーを大量噴射して水分を押し流す
- 自然乾燥させる(時間がかかるため、レース直前は避ける)
- オイル・グリスアップ 乾燥後は適切な部位に適量のオイルやグリスを注油します。
- 軸と軸受けの摩擦部分:不通電グリスまたはオイル
- 金属通電部:通電性グリスまたはオイル(コンタクトスプレーなど)
- 粘度が高い→持続効果が長いが抵抗も大きい
- 粘度が低い→持続効果は短いが抵抗が少ない
メンテナンスの頻度
メンテナンスの頻度は使用状況によって異なりますが、以下のタイミングが目安になります:
- レースの前後
- 性能の低下を感じた時
- 長期間使用していないモーターを使う前
- 約5〜10レース毎
また、モーターのラベルがクリーナーによって剥がれることがありますが、厚めの粘着テープの粘着部をクリーナーで溶かして塗れば再度貼り付けることができます。
モーターメンテナンスは面倒に感じるかもしれませんが、ミニ四駆の性能を最大限に引き出すための重要な作業です。特に公式大会など、真剣にレースに臨む際には欠かせない工程と言えるでしょう。
定期的なメンテナンスを習慣化することで、モーターのトラブルを未然に防ぎ、常に良好なコンディションでレースに臨むことができます。
磁力チューニングでトルクアップが可能
より高度なモーターチューニング方法として、「磁力チューン」と呼ばれる手法があります。これはモーターの磁力を強化することでトルクを向上させる方法です。磁力チューンはやや専門的な知識と技術が必要となりますが、正しく行えばモーターの性能向上に大きく貢献します。
磁力チューンの基本原理
ミニ四駆のモーターには、両側に永久磁石が配置されています。これらの磁石の磁力が強いほど、理論上はトルクが大きくなります。磁力チューンでは、以下のような方法で磁力を強化します:
- 外部磁石による着磁:ネオジム磁石などの強力な磁石を使い、モーターの永久磁石を着磁(磁力を強める)する方法。
- モーター磁石の間隔調整:モーターの外殻を微妙に変形させ、磁石とローター(回転子)の間隔を狭める方法。
着磁による磁力チューンの実践方法
着磁を行う際には、以下の点に注意する必要があります:
- 適切な磁石の選択:ネオジム磁石の中でも、S極とN極がはっきりと分かれている「高さ方向に極が分かれている」タイプを使用します。安価な多極磁石は磁力が乱れるため不適切です。
- 磁極の方向に注意:モーターの磁石と同じ極性になるように着磁します。間違った方向で着磁すると逆に磁力が弱まることがあります。
- 着磁時間:一般的には5〜10分程度磁石を当てておきます。長すぎる着磁は必ずしも効果が高まるわけではありません。
実験によると、正しく着磁することで磁力(ガウス値)が数ポイント上昇し、マシンの速度が1〜2km/h向上することがあります。ただし、着磁によって回転数が若干下がることもあります。
モーター磁石の間隔調整(モーター潰し)
いわゆる「モーター潰し」と呼ばれる手法です。これはモーターケースを軽く変形させ、磁石とローターの間隔を狭めることでトルクを向上させる方法です。
- 調整方法:モーターを万力などで非常に微妙な力加減で挟み、形状をわずかに変化させます。
- 注意点:磁石間の実際の隙間はわずか0.29mm程度しかなく、ローター回転時のブレも考慮すると、実際に調整可能な幅は0.08〜0.18mm程度と非常に狭いです。これ以上狭めるとローターと磁石が接触して摩擦が生じ、逆に性能が低下します。
この方法は非常に繊細な作業であり、やり過ぎるとモーターを破損する恐れがあります。経験者のアドバイスを受けながら、徐々に技術を習得することをお勧めします。
磁力チューンの効果と注意点
磁力チューンの効果としては、以下のようなものがあります:
- トルクの向上(特に低回転時の力強さが増す)
- 加速性能の向上
- セクション後の立ち上がりが良くなる
一方で、以下のような注意点もあります:
- 回転数が下がる可能性がある
- 不適切な着磁は逆効果になりうる
- ネオジム磁石は非常に強力なため、取り扱いに注意が必要
- 電子機器に近づけると故障の原因になることがある
磁力チューンは上級者向けの手法ですが、正しく行えばマシンのパフォーマンス向上に貢献します。特に坂道の多いコースやテクニカルコースでは、トルクアップの効果が実感できるでしょう。
まとめ:ミニ四駆モーター最強を目指すポイント
最後に記事のポイントをまとめます。
- ミニ四駆の最強モーターは用途によって異なり、公式大会ではハイパーダッシュ3モーター、非公式レースではプラズマダッシュモーターが最強クラス
- モーターは「チューン系」と「ダッシュ系」の2種類に大別され、さらに片軸と両軸(PRO)の形状がある
- スピード型、パワー型、バランス型の3つのタイプがあり、コース特性に合わせて選択する必要がある
- 直線の多いコースにはスピード型、坂道の多いコースにはパワー型が適している
- 初心者にはバランス型のアトミックチューン2モーターが扱いやすい
- モーターの性能は個体差があるため、複数購入して選別するのが理想的
- モーター馴らしは水またはお湯を使った方法が効果的で、性能を引き出せる
- ブラシの調整で回転効率が大きく向上し、進角調整は上級者向けのテクニック
- モーターとギア比の組み合わせが重要で、スピード型には小さいギア比、パワー型には大きいギア比が適している
- 定期的なモーターメンテナンスがパフォーマンス維持には不可欠
- 磁力チューンでトルクアップが可能だが、専門知識と慎重な作業が必要
- 最強のモーターは一つではなく、コース条件やレースシーン、個人の走行スタイルに合わせて最適なものを選ぶことが大切