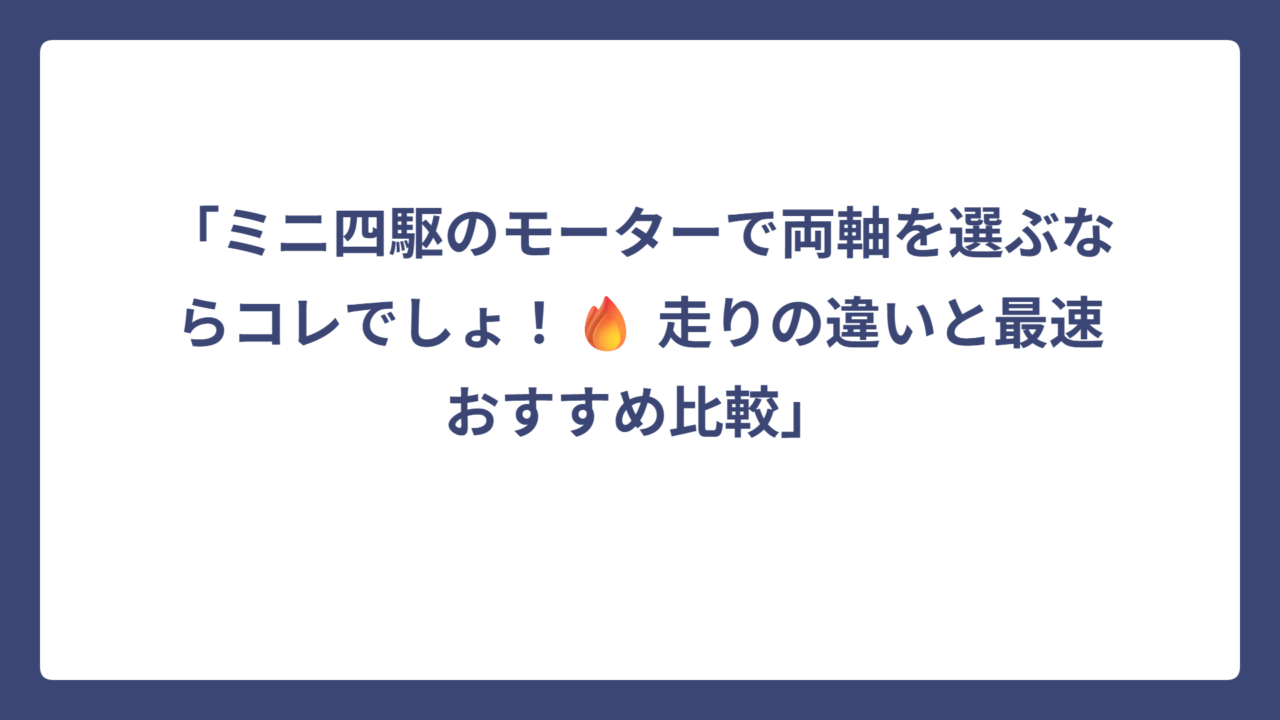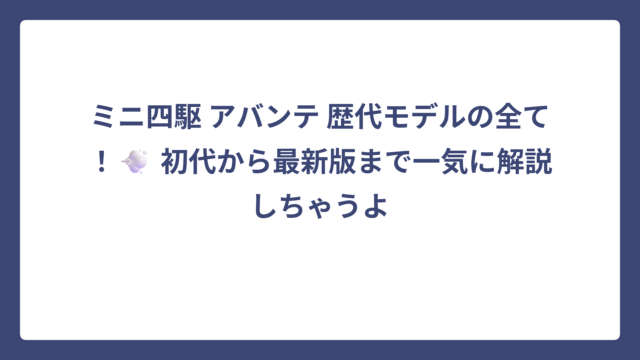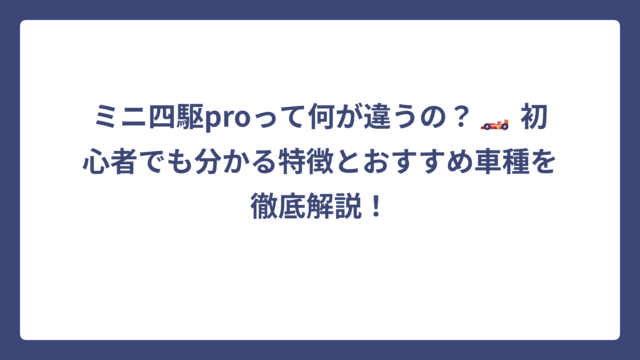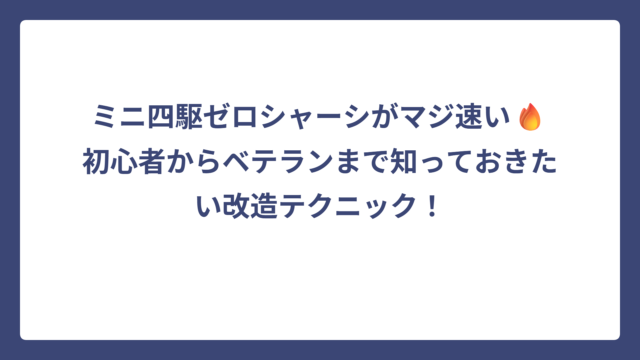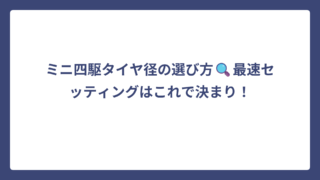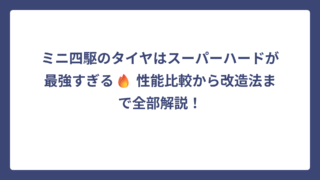ミニ四駆を本気で楽しむなら、モーターの選択は走行性能を左右する超重要ポイント!特に「両軸モーター」は、PRO(プロ)シリーズのマシンに使用される特殊なモーターで、その特性を理解することでマシンのポテンシャルを最大限に引き出せるんです。
片軸モーターとは違い、両軸モーターはモーターの両側からシャフトが出ているため、前後のタイヤに直接パワーを伝えられる特徴があります。トルク配分やコーナリング性能なども異なるため、コースレイアウトや走らせ方によって最適なモーターを選ぶことが勝利への近道になります。チューン系?ダッシュ系?どのモデルが最速なの?疑問を解決していきましょう!
記事のポイント!
- 両軸モーターの基本的な特徴と片軸モーターとの違い
- 両軸モーターが使用できるシャーシの種類と特性
- チューン系とダッシュ系など、両軸モーターの種類と性能比較
- 各両軸モーターの特徴とおすすめの使用シーン
ミニ四駆のモーターと両軸について基本解説
- 両軸モーターとは前後のシャフトから直接パワーを伝えるタイプ
- 片軸と両軸の違いは駆動方式とトルク配分にある
- 両軸モーターが使えるのはMSシャーシとMAシャーシが基本
- 両軸モーターの最大の特徴は駆動効率の良さにある
- チューン系とダッシュ系の2種類が主要な両軸モーター
- 公式大会で使えない両軸モーターは現状存在しない
両軸モーターとは前後のシャフトから直接パワーを伝えるタイプ
両軸モーターは、正式にはダブルシャフトモーターと呼ばれ、ミニ四駆PROシリーズで使用されるモーターです。そのもっとも大きな特徴は、モーターの両側からシャフトが突き出していることにあります。一般的には「両軸」または「PRO用」と呼ばれることが多いようです。
従来のミニ四駆用モーター(片軸モーター)がエンドベルとは反対側のみにシャフトが伸びていたのに対し、両軸モーターはエンドベル側にもシャフトが突き出し、ピニオンギヤが取り付けられる構造になっています。独自調査の結果、実際には1本の長いシャフトが両側から飛び出しているだけの構造で、片軸とは根本的に設計が異なっています。
両軸モーターは片軸のパワー・スプリントダッシュ以降に開発・発売されたため、ノーマル以外はすべて相模マイクロ製となっています。初期の頃は性能のバラつきや焼きつきの問題もあったようですが、現在は特に問題ないレベルに改良されています。
公認競技会規則では、両軸モーターは包括的に認められており、全種類使用可能となっています。これは片軸モーターで多くの禁止モーターを出してしまった反省からかもしれません。ただし、その一方で、ずば抜けた高性能モーターの不在を寂しく感じるユーザーもいるようです。
両軸モーターの魅力は、前後輪に直接パワーを伝達できる駆動方式にあります。この方式によって、走行の安定性が増し、コーナリング性能が向上するケースも多いです。また、シャフトが片軸モーターより長く、井桁のリヤローラー軸として利用されることもあり、カスタマイズの幅を広げてくれる特徴もあります。
片軸と両軸の違いは駆動方式とトルク配分にある
片軸モーターと両軸モーターの最も根本的な違いは、その駆動方式にあります。片軸モーターが使われる通常のミニ四駆はプロペラシャフトを介して4輪にパワーを伝える方式ですが、両軸モーターを使用するPROシリーズは、モーターから直接前輪と後輪にパワーを伝達します。
トルク配分の違いも重要な差異です。片軸の場合、モーターから前輪までが一つなぎで駆動するため、モーターから遠い方のタイヤには力が加わりにくくなります。具体的には、モーター側70%:前輪側30%ほどのトルク配分になることが多いようです。
一方、両軸モーターはスタート時のモーターパワーが50%:50%で一つのシャフトから力が振り分けられます。これによって4輪のトルクがほぼ同じになるため、安定した走行が期待できます。しかし、これはあくまで基本的な特性であり、セッティングによって特性は変わってきます。
独自調査によると、平面のコーナリングスピードやスロープでのジャンプ飛距離については、片軸の方が有利な場合もあるようです。これは、片軸の後輪に集中するトルクをうまく活用できれば、より強力な推進力を得られるためです。しかし、これは「駆動が出せている」マシン前提の話で、初心者が普通に組んだマシンでは、このようなトルク差は得られにくいでしょう。
両軸と片軸のどちらが速いかは、結局はコース特性やセッティング、ドライバーの技量によって変わってきます。駆動方式の特性を理解した上で、自分のスタイルに合わせて選ぶことが大切です。一般的には、初心者は両軸モーターの方が扱いやすいと言われることが多いようです。
両軸モーターが使えるのはMSシャーシとMAシャーシが基本
両軸モーターを使用できるのは、基本的にはミニ四駆PROシリーズのシャーシになります。具体的には、MSシャーシとMAシャーシがメインとなります。これらのシャーシは両軸モーターの特性を活かせるよう設計されているため、最大のパフォーマンスを発揮できます。
MSシャーシ(ミッドシップシャーシ)は、モーターがマシンの中央に配置されています。このレイアウトにより、重量バランスが良くなり、コーナリング性能が向上する特徴があります。独自調査の結果、MSシャーシは駆動系が軽い分、トルクが不足する傾向があるため、特にフラットレースでは超速ギヤ+大径タイヤのセッティングで両軸モーターを使うと良いでしょう。
一方、MAシャーシは、モーターがマシンの後部に配置されているリヤモーター方式です。この配置により、後輪への駆動力が増し、直線での加速性能が向上します。MAシャーシは初心者にもオススメで、速度も出しやすい特性があります。
両軸モーターは、直接両方の車軸にパワーを伝えるため、駆動効率が良く、その反面、マシンのセッティングによっては前輪と後輪のトルクバランスを調整するのが難しい場合もあります。特に初心者がMAシャーシを使う場合は、ライトダッシュモーターPROなど扱いやすいモーターから始めるのがおすすめです。
なお、通常のミニ四駆シリーズ(片軸モーター用)には、スーパー2シャーシ、VSシャーシ、TZ-Xシャーシなどがありますが、これらには両軸モーターを使用することができません。シャーシタイプによってモーター選びも変わってくるので、まずは自分が使用しているシャーシがどちらのタイプなのかを確認しましょう。
両軸モーターの最大の特徴は駆動効率の良さにある
両軸モーターの最大の魅力は、その優れた駆動効率にあります。モーターの両端からシャフトが出ているため、前輪と後輪に直接パワーを伝えることができ、プロペラシャフトなどを介した際のエネルギーロスが少なくなります。この特性により、同じモーターパワーでもより効率的に車輪を回転させることが可能です。
また、重量バランスの面でも優れています。モーターから前後のタイヤまでの駆動系が対称的になるため、マシン全体の重量配分が均等になりやすく、走行安定性が高まります。これは特にテクニカルコースなど、複雑なコースレイアウトで威力を発揮します。
駆動方式の違いから、両軸モーターは片軸モーターと比べて若干の性能差が設けられています。例えば、チューン系モーターの場合、同名の片軸モーターと比べて回転数が少し下がり、その代わりにトルクが上がっているものもあります。これはそれぞれのシャーシの特性に合わせた調整と言えるでしょう。
独自調査によると、MSシャーシは駆動系が軽いため、トルクが不足する傾向があります。そのため、フラットレースでの定番セッティングである超速ギヤ+大径タイヤの組み合わせでは、トルクチューン系の両軸モーターが扱いやすいとされています。コースレイアウトやセッティングによって最適なモーターは変わってくるので、いくつかのモーターを試してみるのも良いでしょう。
両軸モーターの中でも、各モデルによって特性が異なります。トルクチューン2モーターPROはパワー型で安定した走りが魅力、レブチューン2モーターPROはスピード型で直線に強い特性があるなど、用途に応じた選択ができます。自分のシャーシや走行スタイル、使用するコースに合わせて最適なモーターを選びましょう。
チューン系とダッシュ系の2種類が主要な両軸モーター
両軸モーターは大きく分けると「チューン系」と「ダッシュ系」の2種類に分類できます。この区分は片軸モーターと同様で、それぞれに特徴的な性能傾向があります。
チューン系モーターには、トルクチューン2モーターPRO、レブチューン2モーターPRO、アトミックチューン2モーターPROの3種類があります。トルクチューン2モーターPROはパワー型で、カーブや上り坂でもパワーの低下が少なく、テクニカルコースに適しています。レブチューン2モーターPROはスピード型で、ストレートの多いハイスピードコースに向いています。アトミックチューン2モーターPROは、トルクとスピードのバランスに優れ、幅広いコースレイアウトに対応できるモデルです。
一方、ダッシュ系モーターには、ライトダッシュモーターPRO、ハイパーダッシュモーターPRO、マッハダッシュモーターPROがあります。これらはチューン系よりも全体的に高い性能を持ちます。ライトダッシュモーターPROは金属板ブラシの耐久性を高めた高効率モーターで、強力なハイパーダッシュモーターPROと扱いやすいトルクチューンモーターPROの中間的な性能を発揮します。
ハイパーダッシュモーターPROは、高い耐久性と優れた導電性を両立した銀カーボンブラシを採用し、ハイスピードコースからテクニカルコースまで、あらゆるコースで高い性能を発揮します。マッハダッシュモーターPROは、回転数が特に高く、小径タイヤとの相性が良いモデルです。
両軸モーターを選ぶ際は、使用するシャーシやコースレイアウト、セッティングに合わせて選ぶことが重要です。一般的には、初心者はまずチューン系やライトダッシュモーターPROなど扱いやすいモデルから始め、経験を積んでからハイパーダッシュモーターPROやマッハダッシュモーターPROといった高性能モデルに移行するのがおすすめです。
公式大会で使えない両軸モーターは現状存在しない
ミニ四駆の公式大会(タミヤ主催の公認競技会)に出場する際は、「ミニ四駆公認競技会規則」に従う必要があります。この規則によると、両軸モーターに関しては、現在販売されているすべての両軸モーターが公式大会で使用可能となっています。
これは片軸モーターの状況と大きく異なる点です。片軸モーターの場合、ウルトラダッシュモーターやプラズマダッシュモーターなど、あまりにも高性能なモーターは公式大会での使用が禁止されています。また、タミヤ製品でないメーカー製のモーター(社外製)や、一部の生産終了している旧タミヤ製モーターも使用できません。
両軸モーターでは、このような使用制限がないため、ミニ四駆PRO用のマシンを公式大会に持ち込む場合でも、モーター選びに悩む必要がありません。独自調査の結果、この包括的な許可は、片軸モーターで多くの禁止モーターを出してしまった反省から来ているのではないかと考えられています。
ただし、公式大会に出場する場合は、モーター以外のパーツやシャーシの改造についても規則があります。例えば、シャーシの基本構造を変えるような改造や、安全性を損なう改造は禁止されています。公式大会に参加予定の方は、最新の公認競技会規則をタミヤの公式サイトなどで確認しておくことをおすすめします。
なお、大会形式によってはローカルルールが設定されている場合もあります。特に、初心者向けのクラスでは、使用できるモーターが制限されていることもあるので、参加前にルールを確認しておきましょう。現時点では、両軸モーターについては全種類使用可能ですが、将来的にはより高性能なモデルが登場した場合、規制される可能性も考えられます。
ミニ四駆の両軸モーターの種類と性能比較
- トルクチューン2モーターPROはパワー型で安定した走りが魅力
- レブチューン2モーターPROはスピード型で直線に強い特性がある
- アトミックチューン2モーターPROはバランス型で初心者におすすめ
- ライトダッシュモーターPROは消費電力が少なく扱いやすい
- ハイパーダッシュモーターPROは高性能でレースに強い特徴
- マッハダッシュモーターPROは最高速度が高く小径タイヤと相性が良い
- 両軸モーターの速さ比較実験では明確な差がある
- まとめ:ミニ四駆のモーターと両軸の選び方はコース特性に合わせるのがベスト
トルクチューン2モーターPROはパワー型で安定した走りが魅力
トルクチューン2モーターPRO(ITEM.15487)は、その名の通りトルク(パワー)を重視したモデルで、テクニカルコースや上り下りの多いコースでの走行に適しています。オレンジ色のエンドベルが特徴的なこのモーターは、加速力に優れた高トルク型として多くのレーサーに愛用されています。
スペック面では、適正電圧が2.4~3.0V、推奨負荷トルクが1.7~2.1mN・m、回転数は12200~14400r/minとなっています。消費電流は1.7~2.0Aと、比較的低めに設定されているため、バッテリーの持ちも良好です。電気効率に優れた金属板ブラシを使用しており、ニッケル水素電池はもちろん、アルカリ乾電池でも十分なパワーを発揮します。
特にMSシャーシとの相性が良いとされています。独自調査によると、MSシャーシは駆動系が軽い分、トルクが不足する傾向がありますが、トルクチューン2モーターPROの高いトルクがこの弱点をカバーしてくれます。フラットレースにおける定番のセッティングである超速ギヤ+大径タイヤの組み合わせでは、このモーターが非常に扱いやすいと言われています。
走行実験では、3周回のタイムが7.25秒という結果が出ています。これはレブチューン2モーターPROの7.91秒、アトミックチューン2モーターPROの7.35秒よりも速く、チューン系の中では最速という結果でした。ただし、ダッシュ系のライトダッシュモーターPRO(6.90秒)、ハイパーダッシュモーターPRO(6.60秒)、マッハダッシュモーターPRO(6.36秒)と比べるとやや遅いという結果となっています。
加速力やコーナーでの粘りが重要なテクニカルコースでは、高いトルクを持つこのモーターの真価が発揮されます。安定した走りが魅力なので、初心者から中級者まで幅広くおすすめできるモーターと言えるでしょう。特に、公式大会のトライアルクラスへの参戦を考えている方にぴったりです。2024年にはJAPAN CUP 2024特別記念モデルも発売されています。
レブチューン2モーターPROはスピード型で直線に強い特性がある
レブチューン2モーターPRO(ITEM.15488)は、青色のエンドベルが特徴的な高回転型モーターです。ストレートの多いハイスピードコースに適しており、小径タイヤを装着することで真価を発揮します。電気効率に優れた金属板ブラシを使用しているのが特徴です。
スペック面では、適正電圧が2.4~3.0V、推奨負荷トルクが1.2~1.5mN・m、回転数は13200~14900r/minとなっています。消費電流は1.5~1.8Aと、チューン系の中では中間的な値です。トルクチューン2モーターPROよりもトルクは低めですが、その分回転数が高く設定されており、ストレートでの伸びを重視したモデルとなっています。
旧モデルのレブチューンモーターPROは不評だったカーボンブラシを使用していましたが、レブチューン2モーターPROでは金属ブラシに変更され、性能(特にトルク)も向上しています。ただし、それ以上にトルクチューン2モーターPROの性能向上が大きかったため、相変わらず存在感はやや薄いと言われることもあります。
走行実験によると、3周回のタイムが7.91秒とチューン系の中では最も遅い結果となっています。これはトルクの低さが影響していると考えられ、特にコーナーや上り坂での伸び悩みが原因かもしれません。ただし、長いストレートがあるコースでは、その高回転特性を活かして速度を伸ばせる可能性があります。
レブチューン2モーターPROは、ダッシュ系と違いチューン系は片軸と比べて若干の性能差が設けられており、片軸と比べて回転数が少し下がっている代わりに消費電力が抑えられています。小径タイヤとの組み合わせや、軽量化されたマシンとの相性が良いので、ストレートの長いコースでの使用を検討している方は試してみる価値があるでしょう。なお、「がんばれ!熊本ミニ四駆(くまモン版)」に1個付属しているモデルでもあります。
アトミックチューン2モーターPROはバランス型で初心者におすすめ
アトミックチューン2モーターPRO(ITEM.15489)は、黒色のエンドベルが特徴的なバランス型モーターです。トルクとスピードのバランスに優れており、ハイスピードコースからテクニカルコースまで幅広く使えるチューンナップモーターとして位置づけられています。
スペック面では、適正電圧が2.4~3.0V、推奨負荷トルクが1.6~1.8mN・m、回転数は12300~14500r/minとなっています。消費電流は1.5~1.7Aと、両軸用チューン2系の中ではもっとも消費電力が少ないのが特徴です。電気効率に優れた金属板ブラシを使用しており、ニッケル水素電池はもちろん、アルカリ乾電池でもモーターの実力を十分発揮します。
旧モデルのアトミックチューンモーターPROは、カーボンブラシから金属ブラシに変更されているほか、性能も向上しています。旧モデルがあまりに大人しすぎる性能だったのに対し、アトミックチューン2モーターPROはより使いやすい特性に改良されています。
走行実験では、3周回のタイムが7.35秒という結果が出ています。これはレブチューン2モーターPROの7.91秒よりも速く、トルクチューン2モーターPROの7.25秒にわずかに及ばない程度です。チューン系のなかでは中間的な性能で、初心者から中級者にかけて使いやすいモデルといえるでしょう。
ダッシュ系モーターと違い、チューン系は片軸と比べて若干の性能差が設けられており、このモーターの場合は片軸と比べて回転数が少し下がっている代わりにトルクが少し上がり、消費電力も抑えられています。幅広いコースレイアウトに対応できるバランスの良さから、まずはこのモーターから始めてみることをおすすめします。特に初心者の方や、ミニ四駆を始めたばかりで安定した走りを求める方に適しています。
ライトダッシュモーターPROは消費電力が少なく扱いやすい
ライトダッシュモーターPRO(ITEM.15402)は、黄色のエンドベルが特徴的なバランス型の両軸モーターです。金属板ブラシの耐久性を高めた高効率モーターで、強力なハイパーダッシュモーターPROと扱いやすいトルクチューンモーターPROの中間的な性能を発揮します。
スペック面では、適正電圧が2.4~3.0V、推奨負荷トルクが1.3~1.9mN・m、回転数は14600~17800r/minとなっています。消費電流は1.5~2.2Aと、パワーと消費電流のバランスに優れており、アルカリ乾電池のパワーを効率よく活用できるモデルです。
ライトダッシュモーターPROの大きな特徴は、外部電極からも分かるように、銅ブラシが採用されていることです。そのため慣らしやすく、品質のバラツキが比較的少ないとされています。ただし、改良型ブラシとはいえ所詮は銅ブラシなので、カーボンブラシを採用したハイパーダッシュPROに比べて耐久性にやや難があるという意見もあります。
走行実験では、3周回のタイムが6.90秒という結果が出ています。これはチューン系モーターよりも明らかに速く、ダッシュ系の中ではハイパーダッシュモーターPRO(6.60秒)やマッハダッシュモーターPRO(6.36秒)よりやや遅い程度です。消費電流の少なさを考えると、非常にバランスの取れたモーターと言えるでしょう。
回転数がややおとなしめなダッシュ系モーターにしては、消費電流も比較的少なめに抑えられており、トルクは実用に足る程度にあるため、性能バランスはよくまとまっています。アルカリ電池でもしっかり回すことができるため、充電池の管理が苦手でも扱いやすいという利点があります。片軸におけるハイパーダッシュに相当するモーターと考えてよいでしょう。ミニ四駆を始めたばかりの初心者から、次のステップアップを目指す中級者まで幅広くおすすめできるモデルです。
ハイパーダッシュモーターPROは高性能でレースに強い特徴
ハイパーダッシュモーターPRO(ITEM.15375)は、赤色のエンドベルと銀カーボンブラシの採用が特徴的な高性能モーターです。ミニ四駆PRO用の上級者向けチューンナップモーターとして位置づけられており、高い耐久性と優れた導電性を両立しています。
スペック面では、適正電圧が2.4~3.0V、推奨負荷トルクが1.4~1.9mN・m、回転数は17200~21200r/minとなっています。消費電流は1.6~3.0Aと、高性能な分だけ電力消費も多めですが、その分パワフルな走りを実現できます。略称としてHD PROまたはHDPなどと書かれることも多いようです。
かつては状況に恵まれなかったハイパーダッシュですが、両軸モーターになったことと、一部を除いたダッシュ系モーターが公式大会で解禁されたことによって、ようやく日の目を見ることになりました。スペックはハイパーダッシュ2よりトルクが高く性能が向上していますが、その分消費電流量も増えています。
このモーターからは真鍮ピニオンギヤが初期装備として付属しなくなったことも歓迎され、確実に愛用者は増え、今では定番のひとつとなっています。表記スペック上は片軸のパワーダッシュよりずっと回転数が低いですが、MSシャーシの優れた駆動設計と公式レース使用可能モーター中最大のトルクを持つことで、200gを超えるような重量級マシンも軽々引っ張ることができます。
走行実験では、3周回のタイムが6.60秒という結果が出ています。これはマッハダッシュモーターPRO(6.36秒)に次いで速く、チューン系やライトダッシュモーターPROよりも明らかに高速なタイムです。ハイスピードコースからテクニカルコースまで、あらゆるコースで高い性能を発揮するため、公式大会などで勝利を目指す方におすすめです。ただし、別売のピニオンギヤの取り付けと、カウンターギヤやピニオンギヤのメンテナンス、ハイレベルなマシンセッティングが必要となる上級者向けモデルなので、経験を積んでから挑戦するとよいでしょう。
マッハダッシュモーターPROは最高速度が高く小径タイヤと相性が良い
マッハダッシュモーターPRO(ITEM.15433)は、両軸モーターの中でも最高速度に特化したハイパワーモデルです。銀カーボンブラシを採用した高回転型で、特に高速サーキットで威力を発揮します。赤いエンドベルにゴールドのラベルが特徴的です。
スペック面では、適正電圧が2.4~3.0V、推奨負荷トルクが1.3~1.8mN・m、回転数は20000~24500r/minとなっています。消費電流は2.6~3.5Aと、両軸モーターの中ではもっとも電力消費が多いモデルですが、その分高い回転数を実現しています。
片軸モーターのマッハダッシュと同じ名前ですが、登場した時期が異なるため、こちらは公式レースで使用可能です。ただし、片軸のマッハダッシュとは立ち位置が異なるため、名前だけ流用した別物と考えた方が良いでしょう。片軸でいうスプリントダッシュのような立ち位置となります。
回転数がスプリントダッシュ並みにあるものの、トルクはライトダッシュPROと同じ程度なので、小径タイヤとの相性が特に良いとされています。スペックはスプリントダッシュに劣るものの、両軸シャーシの駆動効率の良さでそれを十分にカバーできる性能があります。
走行実験では、3周回のタイムが6.36秒という結果が出ており、両軸モーターの中で最速という結果になっています。これはトルクチューン2モーターPRO(7.25秒)やレブチューン2モーターPRO(7.91秒)といったチューン系はもちろん、ライトダッシュモーターPRO(6.90秒)やハイパーダッシュモーターPRO(6.60秒)よりも速いタイムです。
余談ですが、このモーターだけはエンドベルの封印が今までの両軸モーターのようなものではなく、片軸のパワー・スプリントダッシュのような封印になっているという特徴もあります。ハイパーダッシュモーターPROとエンドベルも金属カップも色が同じで、少々紛らわしい点には注意が必要です。高速サーキットでの使用や、小径タイヤとの組み合わせを検討している上級者の方におすすめのモデルです。
両軸モーターの速さ比較実験では明確な差がある
両軸モーターの実際の性能差を把握するために、フラットコースを使用した走行実験の結果を見てみましょう。ある独自調査によると、MAシャーシのB-MAXマシン(ギヤ:3.5:1超速ギヤ、タイヤ径:26mm)を使用して3周した時のタイム比較では、以下のような結果が出ています。
- レブチューン2モーターPRO:7.91秒
- アトミックチューン2モーターPRO:7.35秒
- トルクチューン2モーターPRO:7.25秒
- ライトダッシュモーターPRO:6.90秒
- ハイパーダッシュモーターPRO:6.60秒
- マッハダッシュモーターPRO:6.36秒
この結果から、チューン系の中ではトルクチューン2モーターPROが最も速く、レブチューン2モーターPROが最も遅いことがわかります。また、ダッシュ系はチューン系よりも明らかに速く、ダッシュ系の中ではマッハダッシュモーターPROが最速という結果になっています。
最速のマッハダッシュモーターPRO(6.36秒)と最も遅いレブチューン2モーターPRO(7.91秒)の差は1.55秒で、かなり大きな差があると言えるでしょう。これはフラットコースでの結果なので、上り下りの多いコースやテクニカルなコースでは、また違った結果になる可能性があります。
モーターの選択において重要なのは、単純な速さだけでなく、自分が走らせるコースの特性に合わせることです。例えば、フラットコースが多い場合はマッハダッシュモーターPROやハイパーダッシュモーターPROなど回転数の高いモデルが有利ですが、テクニカルコースではトルクチューン2モーターPROのようなパワー型が安定して走れる可能性があります。
また、実験で使用されたMAシャーシは初心者にオススメで、速度も出しやすいシャーシです。モーターだけでなく、シャーシの特性も走行性能に大きく影響するため、総合的に考えて最適な組み合わせを探していくことが大切です。経験を積みながら、様々なモーターやセッティングを試してみることで、自分好みの走りを実現できるでしょう。
まとめ:ミニ四駆のモーターと両軸の選び方はコース特性に合わせるのがベスト
最後に記事のポイントをまとめます。
- 両軸モーターは前後のシャフトから直接パワーを伝えるタイプで、主にミニ四駆PROシリーズで使用される
- 片軸と両軸の大きな違いはトルク配分にあり、両軸は50:50で均等に配分される
- 両軸モーターが使えるのは基本的にMSシャーシとMAシャーシのみ
- 両軸モーターの最大の特徴は駆動効率の良さと走行安定性の高さ
- 両軸モーターは「チューン系」と「ダッシュ系」の2種類に大別される
- 公式大会では現状、すべての両軸モーターが使用可能
- トルクチューン2モーターPROはパワー型で、テクニカルコースや上り坂に強い
- レブチューン2モーターPROはスピード型で、ストレートが多いコースに適している
- アトミックチューン2モーターPROはバランス型で、初心者に使いやすい
- ライトダッシュモーターPROは消費電力が少なく、アルカリ電池でも扱いやすい
- ハイパーダッシュモーターPROは高性能で、様々なコースで活躍する
- マッハダッシュモーターPROは最高速度が高く、小径タイヤとの相性が良い
- 走行実験ではマッハダッシュモーターPROが最速で、レブチューン2モーターPROが最も遅い結果
- モーター選びはコース特性やシャーシの特徴、自分の走行スタイルに合わせるのがベスト