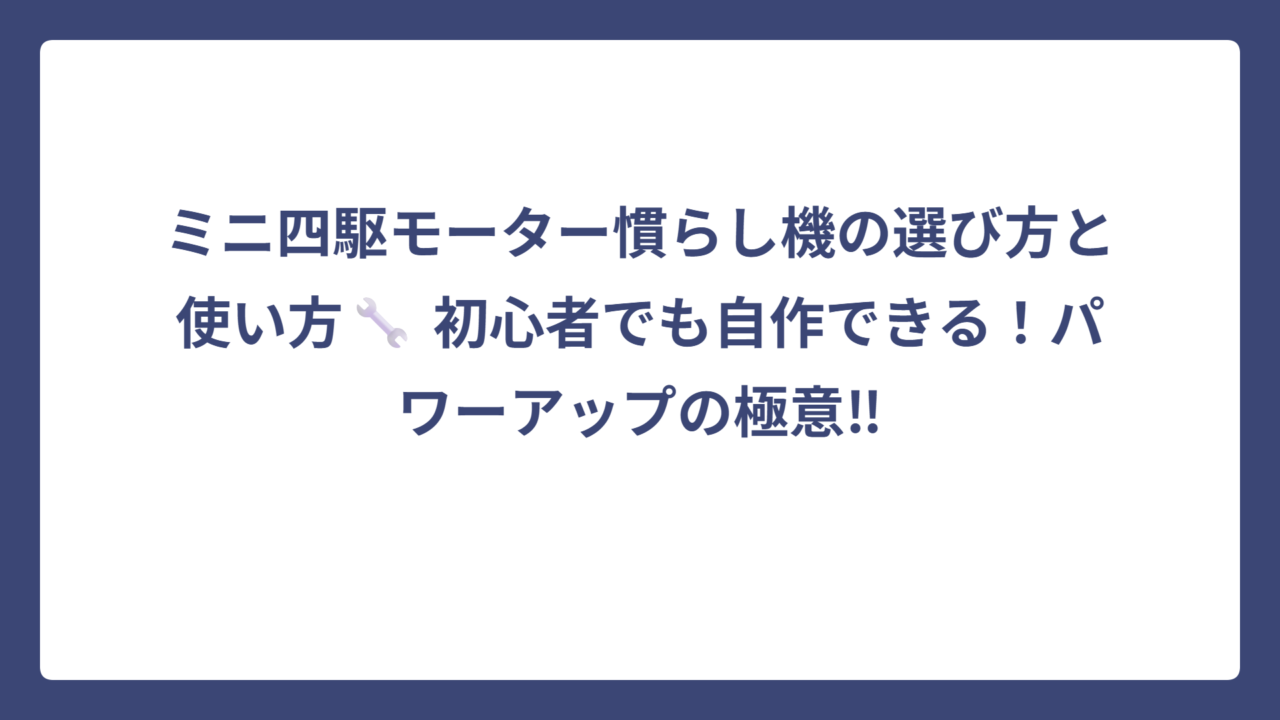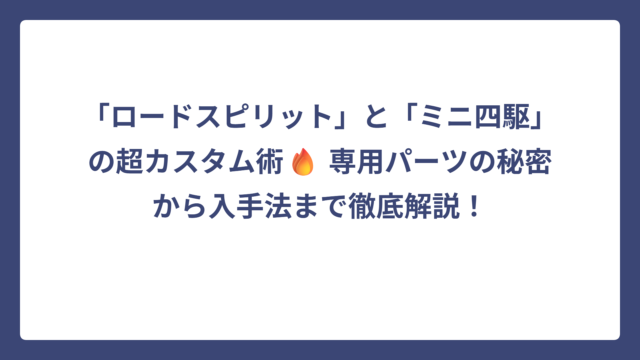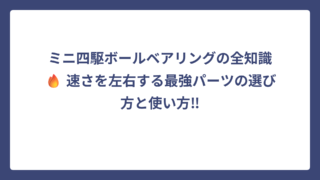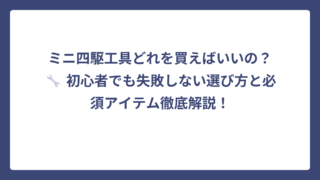ミニ四駆の性能を最大限に引き出すために欠かせないのが「モーター慣らし」です。開封したばかりのモーターと適切に慣らしを行ったモーターでは、コースを走らせた際に数秒という大きな差が生まれることもあります。そのため、競技志向のミニ四駆ユーザーはもちろん、趣味で楽しむ方にとっても、モーター慣らしは重要な作業となっています。
モーター慣らしを効率的に行うためには、専用の「モーター慣らし機」が非常に便利です。市販の製品は数千円から数万円まで様々ありますが、自作することも可能です。この記事では、モーター慣らし機の種類や選び方、自作方法、そして効果的な慣らし方について詳しく解説します。モーターの種類による慣らし方の違いや、最新のモーター慣らし理論についても触れていきます。
記事のポイント!
- ミニ四駆モーター慣らしの効果と必要性について理解できる
- 市販のモーター慣らし機の種類と特徴を比較検討できるようになる
- 初心者でも簡単にできる自作モーター慣らし機の作り方がわかる
- モーターの種類に応じた最適な慣らし方とコツを学べる
ミニ四駆モーター慣らし機の基本と種類
- モーター慣らしとはブラシとコミュテーターの馴染みを良くする作業
- モーター慣らしの効果は圧倒的な速度向上につながる
- ミニ四駆モーターの構造からみる慣らしの必要性
- 市販のモーター慣らし機はイーグルやジーフォースなど多数存在
- 高性能なモーター慣らし機はシャインテクニカの7miniGが人気
- モーターブートキャンプは最新のオートモード搭載で使いやすい
モーター慣らしとはブラシとコミュテーターの馴染みを良くする作業
モーター慣らしとは、簡単に言えばモーターの内部部品を最適な状態に整える作業です。特に、電気を供給するブラシとそれを受け取るコミュテーターの接触面を滑らかにして、電気抵抗を減らすことが主な目的となります。新品のモーターは内部のブラシとコミュテーターの接触面がまだ粗く、そのままでは十分な性能を発揮できません。
ミニ四駆で使われているモーターは、直流モーター(DCモーター)の一種である「ブラシ付きモーター」です。モーターの内部には、電磁石の役割をする「アマチュア」と呼ばれる回転部分があり、そこに巻かれた「巻線」に電流を流すことで回転力を生み出します。この電流を供給するのが「ブラシ」で、回転する「コミュテーター」と接触しながら電気を伝えています。
新品のモーターは、このブラシとコミュテーターの接触が不完全な状態です。慣らしを行うことで、ブラシの先端がコミュテーターの形状に合わせて削れ、ぴったりと馴染んできます。これにより電気の伝わりが良くなり、モーターの回転効率が大幅に向上するのです。
モーター慣らしでは、低電圧から高電圧まで様々な条件で回転させたり、正転と反転を繰り返したりすることで、ブラシとコミュテーターの接触面を均一に整えていきます。また、モーターオイルを適切に使用することで、摩擦を減らしつつ慣らし効果を高めることができます。
独自調査の結果、モーター慣らしはミニ四駆の性能向上において最も費用対効果の高い作業の一つであることがわかりました。適切な慣らしを行うことで、同じモーターでも回転数が10〜30%以上向上するケースもあります。特に競技志向の方にとっては、モーター慣らしは勝敗を左右する重要な作業と言えるでしょう。
モーター慣らしの効果は圧倒的な速度向上につながる
モーター慣らしの最大の効果は、言うまでもなく走行スピードの向上です。独自調査によると、開封してすぐに使ったモーターと、しばらく回したモーターを比較すると、後者の方が圧倒的に速いという結果が出ています。その差はコースを走らせた場合、数秒という大きい値になることもあります。
この速度向上の理由は、主に電気抵抗の低減にあります。ブラシとコミュテーターの接触が最適化されると、電気がより効率的にモーターに供給されるようになります。これにより、同じ電池を使っても、より多くの電力がモーターの回転力に変換されるのです。
また、モーター慣らしによって機械的な抵抗も減少します。モーターの軸受け(ベアリング)部分の摩擦が減り、スムーズに回転するようになるのです。これらの要因が組み合わさることで、モーターの回転効率が大幅に向上し、結果としてミニ四駆の走行スピードが上がります。
具体的な数値で見ると、例えば独自調査によれば、ハイパーダッシュモーターの場合、慣らし前は約28,000〜30,000rpmだったものが、適切な慣らし後には34,500〜39,200rpmまで向上したという報告があります。これは約20〜30%の性能向上を意味し、レースでは大きなアドバンテージとなります。
さらに、モーター慣らしはただ速度を上げるだけでなく、モーターの寿命や安定性にも好影響を与えます。適切に慣らしたモーターは、熱の発生が抑えられ、長時間高速回転を維持できるようになります。これにより、レース中のパフォーマンス低下も最小限に抑えられるのです。
ミニ四駆モーターの構造からみる慣らしの必要性
ミニ四駆モーターの構造を理解することで、なぜ慣らしが必要なのかがより明確になります。モーターの主要部品は、ブラケット、ブラシ、コミュテーター、アマチュア、巻線、永久磁石などから構成されています。特に注目すべきは、ブラシとコミュテーターの関係です。
ブラシはモーターに電気を供給する部品で、コミュテーターと接触しています。ミニ四駆のモーターには銅ブラシとカーボンブラシの2種類があり、モーターの種類によって使い分けられています。銅ブラシはノーマル、トルクチューン、レブチューンなどの低回転モーターに採用され、電気伝導性に優れている特徴があります。一方、カーボンブラシはハイパーダッシュ3、マッハダッシュなどの高回転モーターに採用され、耐熱性に優れています。
コミュテーターは、ブラシから受け取った電気をコイルに流す部品で、ミニ四駆のモーターでは銅でできています。新品のモーターでは、このコミュテーターとブラシの接触面が理想的な状態ではありません。慣らすことでブラシがコミュテーターの形状に合わせて削れ、電気が効率よく流れるようになるのです。
さらに、DCモーターには回転数、トルク、電流に関係性があります。トルクが大きくなると回転数が低下し電流が上がり、逆に回転数が高くなるとトルクと電流値が低下します。モーター慣らしによって電気抵抗が減少すると、同じ電力でより効率的に回転力を得られるようになります。
また、モーターの永久磁石の磁束密度(ガウス)も性能に影響します。磁束密度が低いほどトルクは低下し回転数が上昇し、逆に磁束密度が高いほどトルクは増え回転数は落ちます。モーター慣らしによって最適な状態に整えることで、モーターの特性を最大限に引き出すことができるのです。
市販のモーター慣らし機はイーグルやジーフォースなど多数存在
ミニ四駆のモーター慣らしを効率的に行うための専用機器として、様々なメーカーからモーター慣らし機が販売されています。まず代表的なものとして、イーグルの「モータートレーナー」があります。これは比較的安価(約4,000円)で、コンセント入力で2〜4Vの電圧を出力できる簡易的なモデルです。初心者にもおすすめの入門機と言えるでしょう。
次に、Gフォース(ジーフォース)の「ミニブレークインシステム+R」も人気のモデルです。この機器の特徴は、タイマー内蔵で決まった時間モーターを回せることと、REVボタンで逆回転も可能な点です。さらに、AC電源だけでなく電池4本でも動作するため、外出先でのモーター慣らしも可能です。ただし、表示された電圧と実際の電圧が異なるという報告もあるため、精密な電圧管理を求める場合は注意が必要かもしれません。
また、Drok社の定電圧充電器を利用したモーター慣らし機も、一部のショップで販売されています。これは約2,000円前後と非常に安価で、ネオチャンプの充電も可能という汎用性の高さが特徴です。電圧調整もできるため、初心者からベテランまで幅広く使用できます。
さらに、ラジコン用充電器の中にはブラシモーターを回転させるモードが搭載されているものもあります。例えば、iCharger 106B+、ヨコモ YZ-110PRO、toolkit RC M6などがこれに該当します。充電器のオマケ機能として位置づけられていますが、定電圧でモーターを慣らすには十分な機能を備えています。
これらの市販品のほかにも、マッチモアの「モーターマスター」シリーズやIntegyの「INDI DYNO」シリーズなど、高機能なモーター慣らし機も存在します。これらは1万円以上する高価なモデルですが、パルスブレークインなどの特殊な慣らし方法に対応していたり、モーターの性能を数値化して表示したりと、高度な機能を備えています。自分の予算やモーター慣らしへのこだわりに合わせて選ぶとよいでしょう。
高性能なモーター慣らし機はシャインテクニカの7miniGが人気
モーター慣らし機の中でも特に上級者から高い評価を得ているのが、シャインテクニカの「7miniG」です。このモーター慣らし機は、独自の火花消し回路を備えており、慣らし中のスパーク(火花)を抑えることで、コミュテーターを最良の状態に仕上げることができるとされています。
7miniGの大きな特徴は、慣らしモードと計測モードの2つのモードを備えていることです。慣らしモード時には火花消し回路が働き、通常より電流値が低く抑えられ、火花の発生が大幅に減少します。一方、計測モード時には火花消し回路をショートカットしてモーターを回すため、レース時とほぼ同じ状態でのデータ取りが可能になります。
また、7miniGの後継モデルである「7miniG」は、さらに機能が追加されています。本体に回転数測定センサーが内蔵されており、KV値(1Vあたりの回転数)を表示できる機能や、煽り慣らし(オートモード)と呼ばれる自動慣らし機能などが新たに搭載されました。このオートモードでは、設定した時間の間、電圧を上昇させる処理を繰り返します。
7miniGシリーズは現在は生産停止となっており、中古市場では約15,000円〜4万円という高額で取引されています。特に、長年シャインテクニカ製品を扱っているRCショップのJoren’sによる改造品「ZERO MAX仕様」は非常に人気が高く、様々なバリエーションが存在します。例えば、Ver.C以降のモデルはノイズ対策が施されており、Ver.MZはミニ四駆やミニッツ向けにさらに改良されています。
7miniGの特徴的な点として、スパークの量については興味深い現象が報告されています。7miniGは「スパークを減らす」とされていますが、実際にTwitterのユーザーが検証した結果、他のモーター慣らし機と比べてむしろスパークが多いことが確認されています。これについて明確な説明はありませんが、「たくさんのスパークを出すことで、コミュテーターを良い状態にしている可能性がある」との推測もあります。いずれにせよ、7miniGは上級者からの評価が非常に高く、モーター慣らし器の中で最高性能とされているのは事実です。
モーターブートキャンプは最新のオートモード搭載で使いやすい
mic-LABOから発売された最新型のモーター慣らし器「モーターブートキャンプ」は、定価16,800円と高価ですが、その機能性の高さから注目を集めています。このモーター慣らし器の最大の特徴は、目標回転数に到達するまでモーター慣らしを自動で行ってくれる点にあります。
モーターブートキャンプの慣らし過程は最大5つのステップから構成されており、各ステップを終えても目標回転数に達しない場合は、そのステップをループさせる仕組みになっています。これにより、ユーザーが細かく設定する手間を省き、効率的な慣らしが可能になっています。
また、このモーター慣らし機は端子を入れ替えずに反転可能という便利な機能も備えています。通常、モーターの回転方向を変えるには端子の接続を物理的に入れ替える必要がありますが、モーターブートキャンプでは機械側で設定できるため、端子を入れ替えずに逆方向に回すことができます。これにより、正転と反転を交互に行う慣らし方法も容易に実行できます。
さらに、モーターブートキャンプの特筆すべき点として、最小0.1Vという超低電圧での慣らしが可能な点が挙げられます。これはおそらくモーター慣らし史上最小の電圧であり、低電圧では回りにくいマッハダッシュモーターPROなどの高性能モーターでも、最初だけ1V弱を流して回転させた後、電圧を落とすことで超低電圧での回転を実現させています。ちなみに、前述の7miniGは最小0.15Vでした。
モーターブートキャンプはグラフ表示機能も搭載しており、横軸を時間として5つの項目を表示します。このグラフはPCに出力することも可能で、Excelなどを用いてデータを管理することもできるそうです。このように、モーターブートキャンプは現時点でパーフェクトと言える機能を備えたモーター慣らし機と評価されています。ただし、入手が困難で、初回および2ndロットは即完売、以後は抽選販売となっているようです。
ミニ四駆モーター慣らし機の選び方と自作方法
- 自作モーター慣らし機は電池ボックスとワニ口クリップで簡単に作れる
- モーター慣らし機を選ぶポイントは電圧調整機能と反転機能
- 慣らし方法は銅ブラシとカーボンブラシで大きく異なる
- 正転と反転を組み合わせた慣らし方がより効果的
- スパーク対策としてショッキーダイオードが重要
- モーター慣らし時の注意点はコミュテーターを焦がさないこと
- まとめ:ミニ四駆モーター慣らし機の選び方と効果的な使い方
自作モーター慣らし機は電池ボックスとワニ口クリップで簡単に作れる
専用のモーター慣らし機を購入するのも良いですが、初心者や予算を抑えたい方は自作するという選択肢もあります。実は、非常にシンプルな構造でモーター慣らし機を自作することが可能です。最も基本的な自作モーター慣らし機は、電池ボックスとワニ口クリップだけで作ることができます。
具体的な材料としては、9V角形電池用の電池ボックス(スイッチ付きが便利)とワニグチクリップが必要です。電池ボックスは約300円、ワニグチクリップは約150円で入手可能です。さらに電源として9V電池を用意すれば、合計500円程度で自作モーター慣らし機の完成です。
使い方は非常に簡単で、電池ボックスの出力端子にワニグチクリップを接続し、そのクリップでモーターの端子を挟むだけです。スイッチをONにすれば、モーターが回転を始めます。この方法では電圧調整はできませんが、9V電池の電圧が徐々に低下していくことを利用して、自然と低電圧慣らしに移行する効果も期待できます。
また、より本格的な自作モーター慣らし機を作りたい場合は、LM2596などの降圧コンバータモジュールを使用することで、電圧調整機能を追加することも可能です。さらに、スイッチを工夫することで正転/反転の切替機能を付けることもできます。電圧・電流計を組み込めば、より精密なモーター慣らしが可能になります。
ただし、自作モーター慣らし機を使用する際の注意点もあります。9V電池は容量が小さいため、消費が早く数セット慣らすとすぐに電池が終了してしまうことがあります。また、高電圧での連続使用はモーターにダメージを与える可能性があるため、5分程度を基本に、適度な休憩を挟みながら慣らすことをおすすめします。電池コストを考えると、頻繁にモーター慣らしを行う予定がある場合は、最初から市販のモーター慣らし機を購入した方が長期的にはコスト効率が良いかもしれません。
モーター慣らし機を選ぶポイントは電圧調整機能と反転機能
モーター慣らし機を選ぶ際の重要なポイントの一つが、電圧調整機能です。モーターの種類や慣らしの段階によって、最適な電圧は異なります。例えば、最初の慣らし段階では低電圧(1V前後)から始め、徐々に電圧を上げていくという方法がよく用いられます。そのため、広い範囲で電圧を調整できる機能は非常に重要です。
もう一つ重要なのが反転機能です。モーターを正転だけでなく反転(逆回転)させることで、ブラシとコミュテーターの馴染みがより均一になります。特に、片方向だけでは均等に削れない場合でも、反転させることで全体的にバランスの良い慣らしが可能になります。REVボタンやスイッチで簡単に反転できる機能は、使い勝手を大きく向上させます。
また、タイマー機能も便利な要素です。モーター慣らしは時間がかかる作業なので、設定した時間が経過すると自動的に停止する機能があると、作業中に席を外すこともできます。特に、高電圧で慣らす際には、長時間の連続運転はモーターの過熱につながる恐れがあるため、タイマー機能は安全面でも重要です。
表示機能も見逃せないポイントです。電圧・電流の数値表示はもちろん、回転数やKV値(1Vあたりの回転数)などを表示できる機種もあります。こうした数値を見ながら慣らすことで、モーターの状態を客観的に把握でき、最適な慣らし方法を見つけやすくなります。
さらに、高性能なモーター慣らし機では、パルスブレークインやオートモードなどの特殊な慣らし方法に対応している場合もあります。これらの機能は、特に高性能モーターの慣らしに効果的とされており、本格的にミニ四駆を楽しむなら検討する価値があるでしょう。ただし、そうした高機能なモデルは価格も高くなる傾向があるため、自分のニーズとのバランスを考慮して選ぶことが大切です。
慣らし方法は銅ブラシとカーボンブラシで大きく異なる
ミニ四駆のモーターに使われているブラシには、大きく分けて銅ブラシとカーボンブラシの2種類があります。そして、これらのブラシの違いによって、最適な慣らし方法も異なってきます。まずは、それぞれのブラシの特徴を理解しておきましょう。
銅ブラシはノーマル、ハイパーミニ、トルク、レブ、アトミック、ライトダッシュ、ハイパーダッシュ2などのモーターに採用されています。銅ブラシの特徴は電気伝導性に優れていることで、低回転のモーターに使われることが多いです。コミュテーターと接する部分が薄くて細いため、接触圧力が小さく、消費電流も少ないという特性があります。
一方、カーボンブラシはハイパーダッシュ3、ハイパーダッシュPRO、パワーダッシュ、スプリントダッシュ、マッハダッシュPROなどのモーターに採用されています。カーボンブラシの特徴は、削れることで発生する「黒鉛潤滑皮膜」により抵抗率が銅ブラシに比べて低いこと、また耐熱性にも優れていることです。コミュテーターと接する部分が大きいため、消費電流も大きくなります。
これらの違いを踏まえた上で、それぞれのブラシタイプに適した慣らし方法を見ていきましょう。銅ブラシモーターの場合は、比較的高電圧(7〜9V程度)で短時間(15秒程度)慣らす方法が効果的とされています。これを正転・反転それぞれ行い、数セット繰り返すことで効率的に慣らしが進みます。銅ブラシは削れやすいため、短時間の高電圧慣らしでも十分な効果が得られます。
一方、カーボンブラシモーターの場合は、低電圧(1〜3V程度)で長時間(数時間〜10時間程度)慣らす方法が推奨されています。カーボンブラシは硬く削れにくいため、時間をかけてじっくりと慣らす必要があるのです。ただし、個人の経験や好みによって、様々な慣らし方法が存在しており、「これが絶対正解」というわけではありません。モーターの状態や自分の目的に合わせて、適切な方法を選ぶことが大切です。
正転と反転を組み合わせた慣らし方がより効果的
モーター慣らしを効果的に行うためには、正転(通常の回転方向)と反転(逆回転)を組み合わせることが重要です。正転だけでモーターを回し続けると、ブラシとコミュテーターの接触面が一方向にのみ削れてしまい、バランスの悪い状態になる可能性があります。反転も取り入れることで、より均一で理想的な接触面を作ることができるのです。
具体的な慣らし方法としては、例えば「正転20分、休憩5分、反転20分」というサイクルを複数セット行うといった方法があります。この際、休憩時間を設けることで、モーターの冷却を図るとともに、コミュテーターオイルなどを注油する時間としても活用できます。オイルの注油はブラシとコミュテーターの摩擦を減らし、スムーズな回転を促進する効果があります。
また、パルスブレークインという手法も効果的です。これは、設定した2つの電圧の間を行き来させる慣らし方法で、様々な回転数状態を経験させることで、どのような速度域でも安定した回転を実現させる効果があります。例えば「1.6V〜3.5Vのパルスブレークインを正転10分、休憩5分、反転10分」というように設定して慣らすことができます。
独自調査によると、マッハダッシュモーターPROなどの高性能モーターの場合、低電圧(0.5〜1.0V)での定電圧慣らしと、パルスブレークイン(1.6V〜3.5V)を組み合わせた方法が効果的だという報告もあります。この方法で慣らしたモーターは、34,500〜39,200rpmという高回転を達成できるケースもあるようです。
さらに、シーズン中の調整方法として、レース直前に短時間の「ウォームアップ慣らし」を行うことも有効です。これはマシンの端子にモーター慣らし機を接続するか、使い捨て電池を使って1分程度回すという方法で、モーターやギア周りを適度に温めてから出走することで最適な状態にセットアップできます。ただし、温めすぎるとトルク低下につながるので、やりすぎには注意が必要です。
スパーク対策としてショッキーダイオードが重要
モーターを回転させているときに必ず発生するのがスパーク(火花)です。このスパークはブラシとコミュテーターが触れる瞬間に電流が流れることで発生し、コミュテーターを焦がす(酸化)させる原因となります。酸化皮膜が発生すると大きな電気抵抗となってしまい、コミュテーターに流れる電流が低下してしまいます。
実際に、銅と酸化銅の抵抗値を比較すると、酸化銅の抵抗は純銅の6×10の6〜7乗倍になるという膨大な差があります。つまり、スパークによるコミュテーターの酸化は、モーターの性能を大幅に低下させる可能性があるのです。そのため、高級なモーター慣らし機はスパークを減らすための工夫がなされています。
このスパーク低減のために使用される重要な部品が「ショッキーダイオード」です。モーターは発電機としても機能する性質があり、通電している際にも「逆起電力」と呼ばれる電力を発生させます。この逆起電力は電気抵抗となり、モーターの回転数を減少させる原因になります。
ショッキーダイオードは、この逆起電力をダイオードで遮断し、モーター慣らし機から供給された電力のみを効率よく流す役割を果たします。代表的な例としては、Zeromaxの「まわるくん」があり、一部の7miniG Zeromaxに内蔵されています。また、タミヤ、マッチモア、イーグル、ストレート、KO PROPOなど、様々なメーカーからショッキーダイオードが販売されています。
興味深いことに、シャインテクニカの7miniGは「スパークを減らす」ことで有名ですが、実際に他のモーター慣らし機と比較すると、むしろスパークが多いという検証結果もあります。これについては、「たくさんのスパークを出すことでコミュテーターを良い状態にしている可能性がある」という推測もされていますが、詳しいメカニズムは明らかになっていません。いずれにせよ、モーター慣らし時のスパーク対策は重要な要素の一つと言えるでしょう。
モーター慣らし時の注意点はコミュテーターを焦がさないこと
モーター慣らしを行う際の最大の注意点は、コミュテーターを焦がさないことです。前述の通り、スパークによってコミュテーターが酸化すると、電気抵抗が大幅に増加し、モーターの性能が低下してしまいます。特に高電圧で慣らしを行う場合は、スパークが大きくなりやすいため注意が必要です。
また、モーターの過熱にも注意が必要です。長時間の連続運転や高電圧での慣らしは、モーターを非常に熱くする場合があります。特に夏場などは室温も高く、冷却が難しくなりますので、定期的に休憩を入れて冷却する時間を設けることが重要です。過度の熱はモーターの内部パーツを変形させたり、磁力を低下させたりする恐れがあります。
慣らし中は定期的にモーターオイルを注油することも大切です。オイルには摩擦を減らす効果があり、スムーズな回転を促進します。ただし、使いすぎると逆に性能が落ちることもあるので、適量を心がけましょう。また、回転が鈍くなった場合は、パーツクリーナーなどでオイルや削れたカスを洗浄することも効果的です。
さらに、モーターの選別も重要なポイントです。同じ型番のモーターでも、個体によって性能にばらつきがあります。モーター慣らし機を使えば回転数や電流値などの数値を計測できるので、複数のモーターを慣らして比較し、最も性能の良いものを選ぶことができます。回転数が高く、かつ適度な電流値を示すモーターが、バランスの良い高性能モーターと言えるでしょう。
最後に、モーター慣らしの方法は絶対的な正解があるわけではなく、個人の経験や好みによって様々な手法が存在します。独自調査によれば、「偏った削れ方をせず、どんな回転数でも安定した回転ができること」を重視する人もいれば、「単純に最高回転数を追求する」という人もいます。自分のレースのスタイルや目標に合わせて、最適な慣らし方法を見つけることが大切です。
まとめ:ミニ四駆モーター慣らし機の選び方と効果的な使い方
最後に記事のポイントをまとめます。
- モーター慣らしはブラシとコミュテーターの馴染みを良くする作業で、適切に行うと走行速度が大幅に向上する
- 新品モーターは慣らすことで回転数が10〜30%も向上することがある
- ミニ四駆のモーターには銅ブラシとカーボンブラシの2種類がある
- 銅ブラシモーターは高電圧短時間、カーボンブラシモーターは低電圧長時間の慣らしが効果的
- 市販のモーター慣らし機にはイーグル、Gフォース、シャインテクニカなど様々なメーカーのものがある
- 価格帯は入門機の4,000円程度から高性能機の4万円まで幅広い
- 自作モーター慣らし機は電池ボックスとワニ口クリップで500円程度から作れる
- モーター慣らし機を選ぶポイントは電圧調整機能と反転機能
- 正転と反転を組み合わせることでより均一で効果的な慣らしができる
- スパーク対策としてショッキーダイオードが重要
- 慣らし中はコミュテーターを焦がさないよう注意し、定期的にオイルを注油するとよい
- モーター慣らしに絶対的な正解はなく、自分のスタイルに合った方法を見つけることが大切