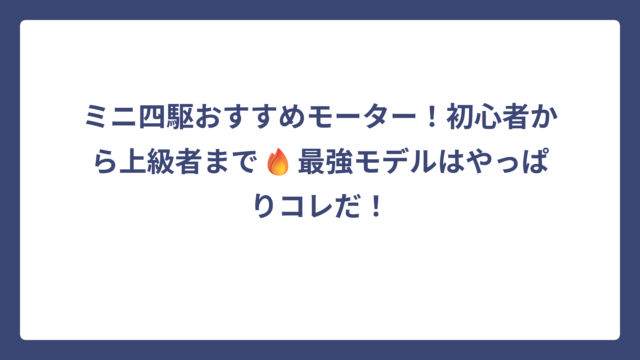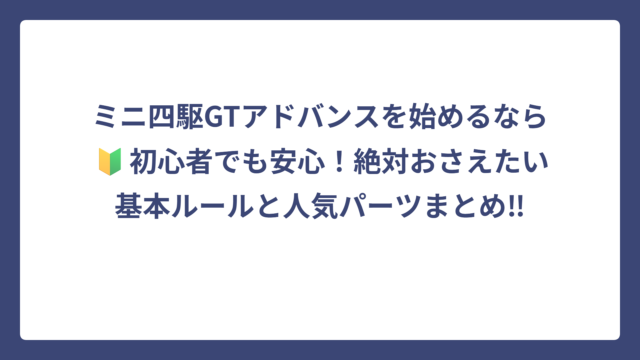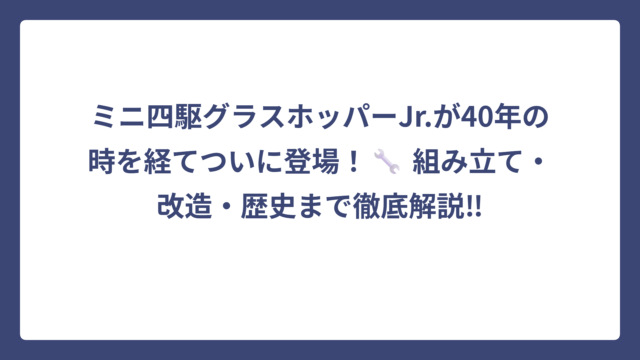ミニ四駆を速く、そして安定して走らせるためには、マスダンパーの配置が非常に重要です。マスダンパーは立体セクションやジャンプでのコースアウトを防ぐ効果がありますが、実は「どこに」「どのように」取り付けるかによって、その効果は大きく変わってきます。間違った位置に取り付けると、せっかくのマスダンパーが全く効果を発揮しないどころか、マシンを不安定にさせてしまうこともあるのです。
独自調査の結果、マスダンパーの配置はフロント・サイド・リアの3か所が基本となり、それぞれの位置で果たす役割が異なることがわかりました。またマスダンパーの形状や重さ、高さもパフォーマンスに大きく影響します。ジャンプ着地後の安定性を高めつつ、マシンのスピードを殺さない絶妙なバランスを見つけることが、ミニ四駆マスターへの近道なのです。
記事のポイント!
- マスダンパーの取り付け位置による効果の違いと最適な配置方法
- マスダンパーの種類ごとの特徴と使い分けのポイント
- 重心を下げるためのマスダンパー高さ調整のテクニック
- 競技会で使える実践的なマスダンパーセッティングの知識
ミニ四駆のマスダンパー位置と基本的な効果について
- マスダンパーとは車体の制振性を高めるための重要なパーツである
- ミニ四駆のマスダンパー位置は前後左右に取り付けるのが基本
- フロントのマスダンパー位置はタイヤの後ろが最適
- サイドのマスダンパー位置は前タイヤ寄りが効果的
- リアのマスダンパー位置はブレーキステー上が一般的
- マスダンパーの高さは低いほど重心が下がり安定する
マスダンパーとは車体の制振性を高めるための重要なパーツである
マスダンパーは、タミヤの公式説明によると「レーンチェンジやテーブルトップなど、マシンが瞬間的に浮き上がるコースでの接地時に威力を発揮。マシンの上下動を抑えてコースアウトを防ぎます」とされています。つまり、ジャンプからの着地時にマシンがバウンドするのを抑制し、安定した走行を実現するためのパーツなのです。
マスダンパーの仕組みは、マシンが着地した際の衝撃をマスダンパー自体が揺れることで吸収するというものです。シャーシに直接固定されず、ビスなどに通して「吊り下げる」形で取り付けることで、この効果を発揮します。
しかし、独自調査によると、マスダンパーは単なる「重り」として機能しているケースも多く見られます。「マスダンパーって本当に効いてる?」という検証記事では、一部のマスダンパーセッティングでは着地直後のバウンドには効果がなく、2回目以降のバウンドで初めて効果を発揮する例も紹介されています。
マスダンパーの価値は、その取り付け位置や使い方によって大きく左右されるため、正しい位置に効果的に配置することが重要です。場合によっては、マスダンパーによって車体が不安定になることもあるため、慎重な調整が必要となります。
マスダンパーは、ブレーキと並んで現代のミニ四駆では欠かせないパーツとなっており、特に立体セクションが多い公式コースでは必須アイテムとなっています。
ミニ四駆のマスダンパー位置は前後左右に取り付けるのが基本
ミニ四駆におけるマスダンパーの取り付け位置は主に3か所あります。フロントバンパー、サイド、リアバンパーです。これらの位置に取り付けたマスダンパーは、それぞれ異なる役割を果たします。
フロントバンパーに取り付けるマスダンパーは、前方からの衝撃や前方向へのバウンドを抑制する効果があります。サイドに取り付ける場合は、左右の安定性を高め、コーナリングやレーンチェンジ時の挙動を安定させます。リアバンパーに取り付ける場合は、後方からの衝撃や後方向へのバウンドを抑制します。
実際の使用においては、コースレイアウトによってどの位置に重点的にマスダンパーを配置するかを決めることが多いです。例えば、大きなジャンプの後にすぐコーナーがあるコースでは、着地後の安定性を確保するためにリアやサイドにマスダンパーを多めに配置することが効果的です。
独自調査によると、現在の主流セッティングでは、フロントタイヤの後ろとリアのブレーキステー付近にマスダンパーを配置するケースが多いようです。この配置は、低重心を保ちつつ効果的に制振性を高めることができるバランスの良いセッティングとされています。
マスダンパーの取り付け位置は、ミニ四駆のレギュレーションにも影響されます。特に、ローラーの中心軸を結んだ線より内側(全幅方向)に設置しなければならないというルールがあるため、ローラーの軸に直接取り付けることはできません。そのため、マスダンパー専用のビスを立てる必要があります。
フロントのマスダンパー位置はタイヤの後ろが最適

フロント部分におけるマスダンパーの位置は、一般的にはフロントタイヤの後ろ側に配置するのが効果的です。この位置にマスダンパーを配置することで、ジャンプ後の着地時に前のめりになるのを防ぎ、安定した着地を実現することができます。
しかし、フロント部分のマスダンパーには注意点もあります。独自調査によると、「フロント側をあまり重くしてしまうとジャンプ中にマシンが前傾し、着地と同時にひっくり返ってしまう」というリスクがあります。そのため、フロントにマスダンパーを配置する場合は、重量と位置のバランスに特に注意が必要です。
実際、多くのミニ四駆レーサーは「特殊なコースでも無い限りフロント側にマスダンパーを装着する人はそんなに見かけない」という状況があります。フロントへのマスダンパー装着は「どうしてもフロントに着けないと攻略出来ない」というような特殊なケースに限られることが多いようです。
フロントマスダンパーを取り付ける場合は、フロントローラーより内側にビスを立てて設置するのが基本となります。このとき、マスダンパーがスムーズに動くことを確認し、シャーシやローラーに当たって動きが制限されないようにすることが重要です。
フロントに適したマスダンパーとしては、比較的軽量なものを選ぶと良いでしょう。タミヤのスリムマスダンパーなどは、フロント部分に取り付けるのに適しています。しかし、背が高くなりがちなスリムタイプは重心が高くなる点にも注意が必要です。
サイドのマスダンパー位置は前タイヤ寄りが効果的
サイドへのマスダンパー取り付けは、おそらく最もスタンダードな方法と言えるでしょう。サイドに翼のようなサイドガードがあるシャーシでは、このパーツを活用してマスダンパーを取り付けることができます。タミヤからはARシャーシサイドマスダンパーセットやMAシャーシサイドマスダンパーセットなど、専用のパーツも販売されています。
独自調査によると、サイドマスダンパーは「なるべく前タイヤ寄りにすると経験上効果が高い」とされています。この位置にマスダンパーを配置することで、コーナリング時の安定性が向上し、特にジャンプ後のコーナーでのコースアウトを防ぐ効果があります。
サイドマスダンパーの取り付け位置には、「ボディに当たらない範囲」という重要な条件があります。ボディとの干渉を避けるために、FRPプレートの穴位置を変更したり、場合によってはFRPプレートを切断して使用することもあります。また、前後のローラーの外側を結んだ線から内側へ5mm程度空けた場所に取り付けることで、ウェーブなどのコース形状でマスダンパーやビスが損傷するリスクを軽減できます。
ARシャーシサイドマスダンパーセットのプレートは、他のシャーシにも応用が効くため、1セット持っておくと様々なシャーシで活用できる便利なパーツです。MAシャーシ用もラインナップされていますが、FRPプレートの形状が異なります。
サイドマスダンパーを効果的に機能させるには、マスダンパーがスムーズに動くことを確認し、シャーシやローラーに当たって動きが制限されないようにすることが重要です。VZシャーシなどでは「VZシャーシのサイドウィングは剛性が低く、折れてしまう可能性がある」ため、通常とは異なる取り付け方法を採用することで剛性を高めるテクニックも存在します。
リアのマスダンパー位置はブレーキステー上が一般的
リア部分のマスダンパー位置には、主に3つの方法があります。1つ目はフロントと同様にバンパーに直接取り付ける方法、2つ目はリアブレーキに設置する方法、そして3つ目はボールリンクマスダンパーを使用する方法です。
リアローラーステーにマスダンパーを取り付ける場合は、注意が必要です。独自調査によると、「リアローラーステーの場合フロントバンパーより高い位置にある」ため、ここにマスダンパーを取り付けると「重心が高くなってしまう」というデメリットがあります。そのため、多くの場合はリアブレーキに取り付ける方法が推奨されています。
リアブレーキの上に取り付ける方法は、「重心を低くできる」というメリットがありますが、「ブレーキの高さを上げるとマスダンパーの高さも上がってしまう」という点がネックになることもあります。この問題に対しては、「ネジなどで高さを調整できる機構にしておく」といった工夫が効果的です。
また、最近のトレンドとしては「リアのマスダンパーはミニ四キャッチャーを加工してその先にウェイトを取り付けるような改造」も見られます。この方法は「東北ダンパー」と呼ばれる特殊なセッティングを再現するものです。
リアマスダンパーを取り付ける際の具体的な方法としては、FRPプレートからビスを通し、スプリングワッシャーとナットで固定した後、ボール型のパーツを挟んでFRPプレートを取り付ける方法などがあります。この際、「マスダンパーがスムーズに動くか確認」し、「シャーシやローラーに当たったりして動かないときは取り付け穴を変更」することが重要です。
リアマスダンパーの選択と配置は、コースレイアウトや他のパーツとの相性も考慮する必要があります。「様々な改造をコースによって使い分ける」ことで、「競技会場での対応力アップにつながる」とされています。
マスダンパーの高さは低いほど重心が下がり安定する
マスダンパーの取り付け高さは、ミニ四駆の安定性に大きく影響する重要な要素です。独自調査によると、「低男産業で最も重視しているのが重心」であり、「ミニ四駆では多くのセクションで重心が低い方が有利に働く場面が多い」とされています。
マスダンパーの高さを低くすることで得られる具体的なメリットとしては、「ジャンプの後にすぐコーナーがあるようなレイアウトでは重心が高いとコースアウトにつながる」のを防いだり、「フェンスに乗り上げた際なども復帰がしやすくなる」といった点が挙げられます。
そのため、マスダンパーは「なるべく低くしたほうが重心を低くできる」とされています。ただし、「ジャンプ着地時に車体が斜めになった時など低い位置のマスダンパーが邪魔になる時もある」ため、「ネジなどで高さを調整できる機構にしておく」と良いでしょう。
マスダンパーの種類によっても、取り付け高さは変わってきます。例えば、「スリムマスダンパーはその名の通りスリムですので狭い所には取り付けしやすい」ですが、「他のマスダンパーに比べ背が高くなって」おり、「背が高いという事はつまり重心が高いという事」になるため、「スペースがある時にはなるべく平べったいマスダンパーを使う」ことが推奨されています。
特にリアのブレーキステーの上に付ける際には、「軸の位置を決める際にマスダンパーの径も考えて穴をあける」ことで、より効果的に配置できます。例えば、「スリムマスダンパーは入るが、シリンダータイプだとスキッドローラーに干渉している」場合は、「軸の位置を少し内側に寄せれば干渉せずに取り付けることが出来る」という工夫が可能です。
マスダンパーの高さ調整において、ビスやナットを使う方法としては、「皿ビス→スプリングワッシャー→ナット→マスダンパー→ゴム管」という順番での組み立てが一般的です。高さを微調整するには、スプリングワッシャーの数や厚さを変えたり、異なる長さのビスを使用したりする方法があります。
ミニ四駆のマスダンパー位置に関する実践テクニックと注意点
マスダンパーの数は増やせば増やすほど効果があるわけではない
マスダンパーは制振効果を高めるために重要なパーツですが、数を増やせば増やすほど効果が高まるわけではありません。独自調査によると、マスダンパーは「付ければつけるほど重量も増え」るため、「付けすぎに注意」する必要があります。
実際、マスダンパーの数と効果の関係について興味深い実験結果があります。「マスダンパーって本当に効いてる?」という検証では、マスダンパーを1個から5個、さらには11個と増やしていった場合の挙動が観察されています。その結果、「5回中3回くらいは横転してしまった」など、マスダンパーを増やすことでむしろ車体が不安定になるケースが報告されています。
この現象について、「着地の衝撃で車体が1度跳ねあがった時、車体が左右のどちらかに傾いていくとマスダンパーもつられて傾いていく方向に動いてしまう」ため、「マスダンパーが傾きを助長させてる」と分析されています。つまり、マスダンパーが多すぎると、制振効果よりも不安定要素が大きくなってしまうのです。
適切なマスダンパーの数については、「自分の中で基準の個数を決め、そこから増減させるやり方がセッティングを決めやすい」とされています。例えば、「前後でシリンダー4つを基準としてコースやコンディションに合わせて増減させている」といったセッティング方法が紹介されています。
また、マスダンパーは「完走出来るギリギリの軽さを目指す」ことが重要です。なぜなら、「軽ければ軽い程マシンは速く走る」からです。特に競技会などでは、安定性とスピードのバランスが勝敗を分けることになるため、必要最小限のマスダンパーで最大の効果を得ることを目指すべきでしょう。
マスダンパーの数は2〜4個程度が理想的とされることが多いようですが、具体的なセッティングはコースレイアウトやマシンの特性、使用するモーターのパワーなどによって変わってきます。自分のマシンに最適なセッティングを見つけるためには、様々な組み合わせを試してみることが大切です。
マスダンパーの形状によって取り付け位置の選択肢が変わる
マスダンパーにはさまざまな形状があり、その形状によって取り付け可能な位置や効果が変わってきます。主な形状としては、円形(シリンダー型)、スリム型、スクエア型などがあります。
円形のマスダンパーは最もオーソドックスなタイプで、幅広い場所に取り付けることができます。独自調査によると、「同じ重量であればなるべく平たいマスダンパーの方が重心が低くなる」ため、円形のマスダンパーは低重心を求める場合に適しています。
スリム型マスダンパーは、その名の通り細長い形状をしており、「狭い所には取り付けしやすい」という特徴があります。ただし、「他のマスダンパーに比べ背が高くなっている」ため、「背が高いという事はつまり重心が高いという事になる」というデメリットも持っています。そのため、「スペースがある時にはなるべく平べったいマスダンパーを使う」ことが推奨されています。
スクエア型マスダンパーは重量が重く、「丸型2個分に相当する重量」を持つことがあります。そのため、少ない個数で高い制振効果を得たい場合に適していますが、その分マシンが重くなるというトレードオフがあります。
マスダンパーの形状に合わせた取り付け位置の選択も重要です。例えば、「リアのブレーキステーの上に付ける時は、軸の位置を決める際にマスダンパーの径も考えて穴をあけると良い」とされています。実際に「スリムマスダンパーは入るが、シリンダータイプだとスキッドローラーに干渉している」といったケースでは、「軸の位置を少し内側に寄せれば干渉せずに取り付けることが出来る」という工夫が可能です。
また、マスダンパーとして使えるパーツは市販のマスダンパーだけではありません。「ローラーをマスダンパーとして使ったり、ファイティングアーマー(六角ウエイト)を付けたりと様々なパーツがマスダンパーとして使える」という柔軟な発想も紹介されています。「削って重量を変えたり、ナットをかわすために座繰りを作ったりする事も可能」など、工夫次第でさまざまなパーツを効果的に活用できるのです。
マスダンパーの形状選びは、取り付け位置の制約やスペースの問題だけでなく、重量配分や重心の高さという観点からも考慮する必要があります。自分のマシンに合った形状を選んで、効果的な位置に配置することが重要です。
マスダンパーの取り付け位置はコースレイアウトに合わせて調整する

ミニ四駆の競技においては、コースレイアウトによってマスダンパーの理想的な配置が変わります。特に公式競技会などでは、コースごとに最適なセッティングを見つけることが勝利への鍵となります。
独自調査によると、「様々な改造をコースによって使い分ける事が競技会場での対応力アップにつながる」とされています。例えば、大きなジャンプやドラゴンバックといった難所がある場合は、より効果的な制振能力が求められます。「ドラゴンバックと言う名前があるそうです」という赤い坂では、通常のマスダンパーセッティングでは「跳ねるわ跳ねるわで余裕でコースアウト」してしまうことがあります。
そのため、特に難しいコースでは「東北ダンパー」と呼ばれる特殊なシステムや、MSフレキ、ペラタイヤなどの改造と組み合わせることで対応力を高めることが有効です。実験では「MSフレキとペラタイヤは凄い!!抜群の安定感」という結果も報告されています。
コースレイアウトに合わせたマスダンパーの調整としては、以下のようなアプローチが考えられます:
- コーナーの多いコース:サイドマスダンパーを充実させて横方向の安定性を高める
- 大きなジャンプがあるコース:リアマスダンパーを効果的に配置して着地の安定性を確保する
- 複雑な立体セクションが続くコース:複数箇所にバランス良くマスダンパーを配置する
コースに合わせた調整の基本的な手順としては、「まずはネジはそのままマスダンパーだけ外して走行し、コースアウトするようなら装着します。それでもダメならリア、さらにサイド+リアなど色々試し、完走出来る状態にして行きます」という方法が推奨されています。
また、競技会場では限られた時間内でセッティングを調整する必要があるため、「これらのパーツを使いサイドに」「FRPプレートにはたくさん穴が空いているので、ボディに干渉しない範囲で色んな位置を試してみて下さい」といった柔軟な対応が求められます。
効率的なセッティング調整のために、「マスダンパーの形や重さのバリエーションがあると様々なセッティングが試せて良い」とされています。コースレイアウトに合わせて素早く最適なセッティングを見つけられるよう、複数のマスダンパーオプションを準備しておくことをおすすめします。
東北ダンパーなどの特殊なマスダンパーシステムも効果的
一般的なマスダンパーの取り付け方以外にも、より効果的な制振システムとして「東北ダンパー」と呼ばれる特殊なセッティングが存在します。この方法は、通常のマスダンパーが持つ制振効果をさらに高めた応用テクニックです。
東北ダンパーとは、タミヤから発売されている「ボールリンクマスダンパー」を使用するか、自作で実現する特殊なダンパーシステムです。独自調査によると、これは「俗に”東北ダンパー”と呼ばれるシステムを再現出来るパーツで、取り付けが簡単な割に高い効果を発揮するのでイチオシ」とされています。
東北ダンパーの特徴は、「通常のマスダンパーはネジに対して垂直に動くのに対し、こちらのボールリンクマスダンパーはボールリンクを軸にブランコのように作用して着地の衝撃を抑える」という点にあります。この動作原理によって、一般的なマスダンパーよりも効果的に衝撃を吸収することができます。
実際の使用例としては、「リアのマスダンパーはミニ四キャッチャーを加工してその先にウェイトを取り付けるような改造」や「東北ダンパーを作ってみた」という記事のように、独自の工夫を加えたセッティングが紹介されています。
ただし、東北ダンパーにも弱点があります。「使っているうちにボールリンクがユルユルになり外れる現象がある」ため、長期的な使用では定期的なメンテナンスや部品交換が必要になることがあります。ただ、「それを見越してなのかスペアが付いているのでしばらく持つ」という対策も取られています。
カーボンプレートを使った自作の東北ダンパーも可能ですが、「カーボン高い」ため、初めは市販のボールリンクマスダンパーを試すことがおすすめされています。タミヤからは「ボールリンクマスダンパー(スクエア)」などの製品が販売されているので、これらを活用するとよいでしょう。
東北ダンパーのような特殊なシステムは、特に難しいコースでの安定性向上に貢献します。「マスダンパーって本当に効いてる?」という実験では、「11個マスダンパーで」通常のセッティングと比較しても「MSフレキとペラタイヤは凄い!!抜群の安定感」という結果が示されていますが、東北ダンパーのような特殊なシステムを導入することで、さらなる安定性の向上が期待できます。
車検規定内で効果的なマスダンパー位置を見つけることが重要
ミニ四駆の公式競技会では、マシンのサイズに関する車検規定があります。独自調査によると、「規定のサイズは幅105mm、全長165mm、高さ70mm以下」とされています。このサイズ制限内で、いかに効果的なマスダンパー配置を実現するかが重要です。
マスダンパーの位置を決める際には、まずこの車検規定を念頭に置く必要があります。例えば、「フロントローラーに19mmローラーを使うと今回の部品の組み合わせだと全長が約2mmオーバーします」というケースでは、「そのような時は13mmや9mmローラーに交換してください」という対応が必要になります。
また、マスダンパーの配置はローラーの位置とも密接に関連しています。「ローラーの取り付け位置を変えるなどして調整します」というように、全体のバランスを考慮したセッティング調整が求められます。
さらに、マスダンパーの位置はミニ四駆のレギュレーションにも影響されます。特に「ローラーの中心軸を結んだ線より内側(全幅方向)に設置しなくてはいけないルールがある」ため、ローラーの軸に直接取り付けることはできません。「マスダンパー用のネジを立てる必要があります」。
車検規定内で効果的なマスダンパー位置を見つけるためには、「FRPプレートの裏表、取り付け穴を変更してボディに当たらない場所を見つけてください」というような細かい調整も必要です。「ちょうど良い場所が無ければブレーキセットに付属しているFRPプレートを使用してマスダンパーを取り付けることもできます」という柔軟な対応も時に必要です。
特にサイド部分では、「前後のローラーの外側を結んだ線から内側へ5mmぐらい空けた場所へマスダンパーを付けるようにして下さい」という具体的なガイドラインも示されています。「あまり外側だとウェーブなどでコースに当たってマスダンパーの取り付けビスが曲がったりします」というリスクを避けるための重要なポイントです。
車検規定内で最大限の効果を発揮するマスダンパー配置を実現するためには、事前のシミュレーションと実際の走行テストを繰り返すことが効果的です。そうして見つけた最適なセッティングを競技会に持ち込むことで、安定した走行と好成績につなげることができるでしょう。
マスダンパーが逆効果になるケースもあるので注意が必要
マスダンパーは適切に配置すれば車体の安定性を高める効果がありますが、場合によっては逆効果になることもあります。独自調査によると、特に数を増やしすぎた場合や配置が不適切な場合に問題が生じやすいようです。
「マスダンパーって本当に効いてる?」という検証では、マスダンパーを5個に増やした際に「嘘だろ….なんで回転するんだーーー??? 全然安定しない!!」という驚きの結果が報告されています。さらに11個に増やすと「さらに横転するようになりました。10回中、8回くらい横転します(マジです)」という状況にまで悪化しています。
この現象が生じる理由として、「着地の衝撃で車体が1度跳ねあがった時、車体が左右のどちらかに傾いていくとマスダンパーもつられて傾いていく方向に動いてしまう」ため、「マスダンパーが傾きを助長させてる」と分析されています。つまり、本来は安定を助けるはずのマスダンパーが、むしろ不安定要素として作用してしまうのです。
また、「マスダンパーは車体に持ち上げられているだけの重量物(挙動が遅く、後から動き出すので意味がない?)」という観察結果もあります。これは、マスダンパーの動きが遅れることで、最初のバウンドには効果がなく、2回目以降のバウンドでようやく効果を発揮するという問題です。「車体を叩いて衝撃を相殺するのかと思っていたのですが、な~~んか違う」と違和感が報告されています。
さらに、マスダンパーの位置によっては別の問題も生じることがあります。例えば、「リアローラーステーの場合フロントバンパーより高い位置にある事がほとんど」なので、「マスダンパーのような重量物を装着すると重心が高くなってしまう」というリスクがあります。
フロント部分についても、「フロント側をあまり重くしてしまうとジャンプ中にマシンが前傾し、着地と同時にひっくり返ってしまいます」という注意点があります。
これらの問題を避けるためには、「マスダンパーを装備する前に一度走行テストをして、必要な場所だけに必要な量のマスダンパーを配置する」というアプローチが効果的です。また、「マスダンパーは、完走出来るギリギリの軽さを目指して」セッティングすることで、不必要なマスダンパーによる悪影響を最小限に抑えることができます。
まとめ:ミニ四駆のマスダンパー位置と効果的な使い方
最後に記事のポイントをまとめます。
- マスダンパーは車体の制振性を高め、ジャンプ後の着地時のバウンドを抑える重要なパーツ
- マスダンパーの基本的な取り付け位置はフロント、サイド、リアの3か所
- フロントのマスダンパー位置は前タイヤの後ろが効果的だが、前傾しやすくなるリスクもある
- サイドのマスダンパー位置は前タイヤ寄りが効果的で、コーナリング時の安定性を高める
- リアのマスダンパー位置はブレーキステー上が一般的で、重心を低く保ちやすい
- マスダンパーの高さは低いほど重心が下がり、マシンが安定する
- マスダンパーは増やせば増やすほど効果があるわけではなく、2〜4個程度が理想的
- マスダンパーの形状によって取り付け可能な位置や効果が変わり、平たいタイプは低重心に有利
- コースレイアウトに合わせてマスダンパーの配置を調整することが競技会での勝利に繋がる
- 東北ダンパーなどの特殊なマスダンパーシステムはより高い制振効果が期待できる
- 車検規定(幅105mm、全長165mm、高さ70mm以下)内で効果的なマスダンパー配置を見つけることが重要
- マスダンパーが多すぎたり位置が不適切だと逆効果になり、マシンが不安定になることもある
- 理想的なマスダンパーセッティングは「完走できるギリギリの軽さ」を目指すこと
- MSフレキやペラタイヤなど他の安定化パーツと組み合わせることでさらに効果を高められる