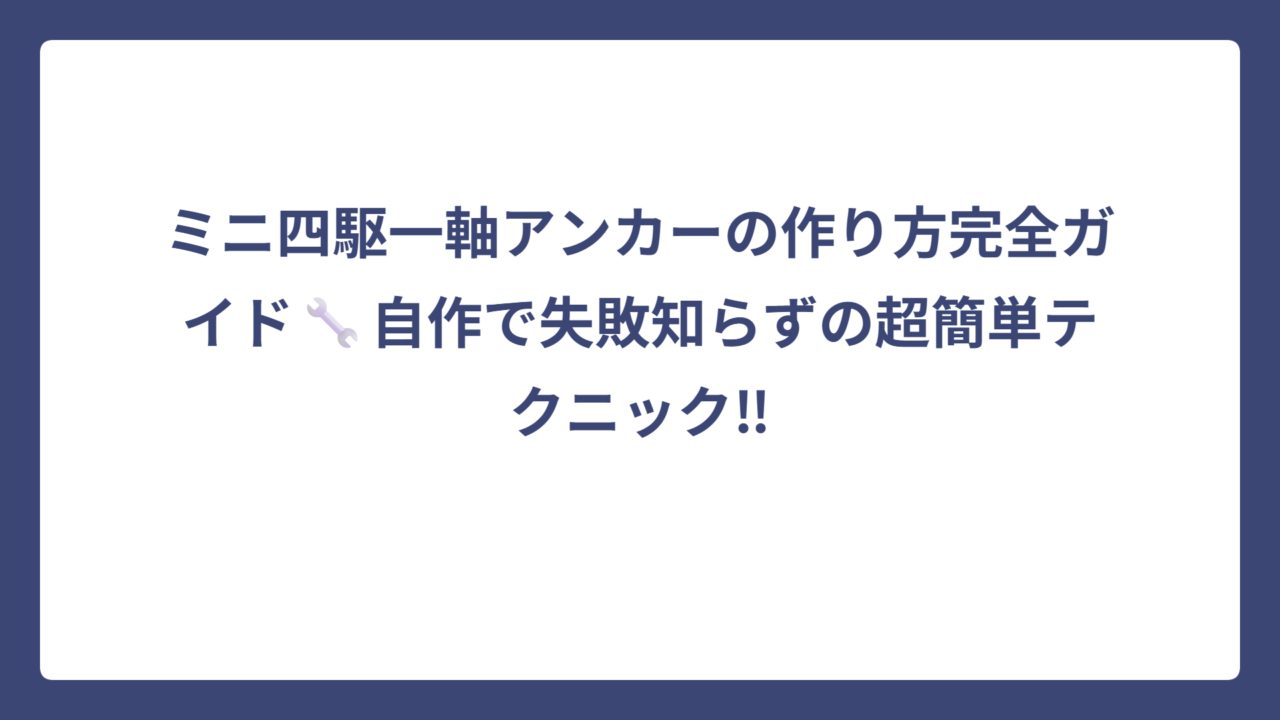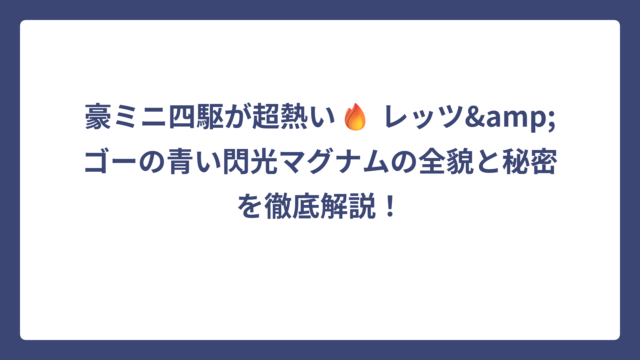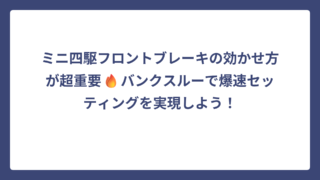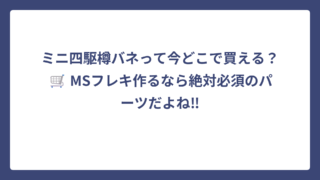ミニ四駆レースの世界で注目を集める「一軸アンカー」。壁に乗り上げた際の復帰率を向上させる重要なギミックとして、多くのレーサーが採用するようになりました。しかし「作り方がわからない」「上手く機能しない」という悩みを抱える方も少なくありません。
この記事では、ミニ四駆一軸アンカーの基本知識から作り方、取り付け方まで、初心者でも失敗せずに自作できるよう詳しく解説します。座繰り加工のコツやキノコヘッドの正しい加工方法など、一軸アンカーの性能を最大限に引き出すポイントを余すことなくお伝えします。
記事のポイント!
- 一軸アンカーの定義と役割について理解できる
- 自作に必要な材料と工具がすべてわかる
- 座繰り加工やキノコヘッドの加工など重要工程のコツがマスターできる
- 効果的な取り付け位置と調整方法で性能を最大化できる
ミニ四駆一軸アンカーとは何かを詳しく解説
- 一軸アンカーの定義はバンパーの一種で壁からの復帰を助ける機構
- ミニ四駆一軸アンカーの主な役割はイレギュラーからの復帰率向上
- 一軸アンカーとATバンパーの違いはスライド機能と構造にある
- ミニ四駆一軸アンカーはMSシャーシとの相性が特に良い理由
- 一軸アンカーの動作原理は支柱を軸にした捻れとスライド
- ミニ四駆一軸アンカーのメリットは回頭性の向上と安定した壁復帰
一軸アンカーの定義はバンパーの一種で壁からの復帰を助ける機構
ミニ四駆一軸アンカーとは、名前の通り1つの軸(支柱)を中心に動くバンパーの一種で、壁からの復帰を助ける機構です。独自の調査によると、一軸アンカーの定義には「1軸のバンパー」「キノコ(アンダースタビヘッド)を使用」「AT的な動き」「スライドもする」という4つの特徴があります。
船の錨(アンカー)のように、マシンが不安定になった時に安定させる役割を持つことから「アンカー」と呼ばれています。コース走行中に壁に乗り上げたり、イレギュラーな動きをした際に、マシンを正常な走行に復帰させるための重要な装置です。
近年のミニ四駆大会では、一軸アンカーを搭載したマシンが多く見られるようになりました。かつては「夢パーツ」などと言われることもありましたが、現在では実用性が認められ、多くのレーサーに採用されています。
コース形状が複雑化し、高速走行が求められる現代のミニ四駆レースにおいて、マシンの安定性を担保する重要なパーツとして確固たる地位を築いています。特に公式大会では、コース壁のギャップなどにも対応できる一軸アンカーの価値が高まっています。
壁からの復帰を助けるだけでなく、左右にスライドする特性により回頭性(曲がりやすさ)も向上するため、総合的なマシンパフォーマンスの向上にも貢献します。
ミニ四駆一軸アンカーの主な役割はイレギュラーからの復帰率向上
ミニ四駆一軸アンカーの主な役割は、イレギュラー(壁乗りあげ時など)からの復帰率を向上させることです。これがアンカーの最も重要な機能と言えるでしょう。
高速で走行するミニ四駆は、カーブや直線でコースの壁に接触することがあります。特に公式大会で使用される5レーンコースは、3レーンとは素材や組み立て方が異なります。5レーンはセクションの自重で固定されているため、設置方法によってはコースの壁にギャップが生まれ、普通のコーナーでも引っ掛かりが発生することがあります。
一軸アンカーは、このような状況でマシンが壁に乗り上げたり、不安定になった際に、独特の構造と動きによってマシンを正常な走行状態に復帰させます。支柱を軸にした捻れる動きにより、壁からの衝撃を効果的に吸収し、マシンの走行を安定させる効果があります。
ただし、一軸アンカーを装着したからといって必ずしも速くなるわけではありません。「壁に引っ掛からない綺麗な着地の方が全体的には速い」という指摘もあります。アンカーは不測の事態に備えるための「保険」的な役割を果たすパーツと考えるべきでしょう。
マシンの速度が上がれば上がるほど、アンカーによる安定性の維持も難しくなります。そのため、一軸アンカーが初めて登場した頃は「3レーンには良いけど…」と評価されることもありましたが、現在では技術的に進化し、様々なコースで効果を発揮するようになっています。
一軸アンカーとATバンパーの違いはスライド機能と構造にある
一軸アンカーとATバンパー(アクティブバンパー)は、どちらもミニ四駆の安定性を高めるパーツですが、その機能と構造には明確な違いがあります。
ATバンパーは主に上下の動きに特化しており、バネの力で上下に動くことで壁からの衝撃を吸収します。一方、一軸アンカーは上下の動きに加えて、左右へのスライド機能を持っています。この左右へのスライド機能により、コーナーでの挙動が安定し、回頭性も向上するという特徴があります。
構造面での違いは以下のとおりです:
| 特徴 | 一軸アンカー | ATバンパー |
|---|---|---|
| 支点 | 1つの軸(支柱)を中心に動く | 複数のポイントで支えられる |
| 動き | 捻れながら斜め上後方にいなす | 主に上下運動 |
| スライド機能 | あり(左右) | なし |
| 調整の難易度 | やや難しい | 比較的簡単 |
| 主な効果 | 復帰率向上+回頭性向上 | 復帰率向上 |
一軸アンカーは支柱を軸にして斜め後方にいなすような動きをします。壁に乗り上げた際は、支柱を中心に捻れながら末端を斜め上後方にいなし、接触している側のユニット後部で支持と復元の補助をします。
使い分けとしては、直線が多いコースではATバンパーの安定性が有利になることもあり、コーナーが多く技術的なコースでは一軸アンカーの柔軟性が活きてくる傾向にあります。自分のマシンの特性やコースの特徴に合わせて選択するのが良いでしょう。
また、両方を組み合わせて使用することで、それぞれの良さを活かした走行が可能になる場合もあります。
ミニ四駆一軸アンカーはMSシャーシとの相性が特に良い理由
ミニ四駆一軸アンカーは元々MSシャーシに特化した構造のギミックだと言われています。MSシャーシとの相性が特に良い理由には、いくつかのポイントがあります。
まず、MSシャーシの形状とバンパーの取り付け位置が一軸アンカーの動作原理に適しています。MSシャーシはフロントとリアにバンパーステーが設けられており、これにアンカーを取り付けることで理想的な動きを実現しやすい構造になっています。
また、MSシャーシのフロント部分の構造は、一軸アンカーを取り付けた際の支柱の固定位置として非常に適しています。特にユニットのバンパーステー穴上部にステーを渡し、基部とステーでアンカーを挟む形でキャップスクリューなどを通して固定するという方法が、MSシャーシでは実装しやすくなっています。
MSシャーシの重心バランスの良さも、一軸アンカーとの相性が良い理由の一つです。アンカーは走行時の挙動に大きく影響するパーツなので、シャーシ自体の挙動が安定していることは重要なポイントです。MSシャーシは重心バランスが良く、一軸アンカーを取り付けた際の挙動の変化が予測しやすいという特徴があります。
もちろん、MSシャーシ以外のシャーシにも一軸アンカーを取り付けることは可能です。その場合は、シャーシごとの特性を考慮した調整が必要になることがありますが、取り付け方法や位置を工夫することで、MSシャーシと同様の効果を得られる可能性があります。
MSシャーシとの相性の良さは、一軸アンカーが広く普及する要因の一つとなっており、多くのレーサーがMSシャーシと一軸アンカーの組み合わせを採用しています。
一軸アンカーの動作原理は支柱を軸にした捻れとスライド
一軸アンカーの動作原理を理解することは、効果的に使用するために非常に重要です。一軸アンカーは主に「支柱を軸にした捻れ」と「スライド機能」の2つの要素で構成されています。
通常走行時、一軸アンカーは支柱を軸に斜め3点で保持されています。この3点とは、支柱、ユニット後部、バンパー押さえ部を指します。この状態でマシンは安定して走行します。
マシンが壁に乗り上げたり、イレギュラーな動きをした場合、一軸アンカーは支柱を軸にして捻れるように動きます。具体的には、支柱を軸に捻れながら末端を斜め上後方にいなし、接触している側のユニット後部で支持と復元の補助をします。
この時、アンカーの後ろにあるバンパー押さえが長すぎると、この捻れる動きを阻害してしまうため、後ろのバンパー押さえは短く、あっても湯呑み程度が適切とされています。
さらに、一軸アンカーはキノコヘッドと座繰りした穴の間に生じる遊びによって、左右にスライドする機能も持っています。このスライド機能により、コーナーでの回頭性が向上します。スライドの範囲はカップリングの強さによって調整可能で、バネの強さと穴の形状も復帰性能に影響を与えます。
ここで重要なポイントとして、一軸アンカーは稼動穴に対して進行方向後ろ側に取り付けることが必須です。進行方向前側に取り付けると、壁に接触した際に支柱を登るような後方に捻れる動きをしてしまい、バンパーの機能が低下する上、コースアウトなどのイレギュラーの原因になり得ます。
この動作原理を理解することで、一軸アンカーの調整や取り付け位置を最適化し、その性能を最大限に引き出すことができます。
ミニ四駆一軸アンカーのメリットは回頭性の向上と安定した壁復帰
ミニ四駆一軸アンカーを使用することで得られるメリットはいくつかありますが、特に「回頭性の向上」と「安定した壁復帰」が大きな魅力です。
まず回頭性の向上について。一軸アンカーはその構造上、左右にスライドする機能を持っています。このスライド機能により、コーナーでのマシンの挙動が安定し、特にタイトなコーナーでの回頭性(曲がりやすさ)が向上します。リジット(固定式)のバンパーと比較すると、この回頭性の向上は顕著に感じられるでしょう。
次に安定した壁復帰について。一軸アンカーの最大の特徴は、壁に乗り上げた際の復帰能力です。支柱を軸にした独特の捻れる動きにより、壁からの衝撃をうまく受け流し、マシンを正常な走行状態に戻す効果があります。これにより、コース上でのマシンの安定性が大幅に向上します。
また、一部のレーサーの経験によると、レーンチェンジ(LC)が楽になったという声もあります。コース上でのレーンの切り替えは、ミニ四駆レースにおいて重要な局面ですが、一軸アンカーの柔軟な動きがこの難所をスムーズに通過するのに役立つようです。
これらのメリットを最大限に活かすためには、適切な調整が必要です。穴の傾斜の緩やかさ、キノコの形状、軸の固定化、グリスの粘度、バネの種類と締め具合など、様々な要素が一軸アンカーの性能に影響を与えます。
一軸アンカーのメリットをまとめると:
- コーナーでの回頭性が向上する
- 壁に乗り上げた際の復帰率が高まる
- レーンチェンジがスムーズになる
- マシン全体の走行安定性が向上する
- イレギュラーからの復元能力が高まる
これらのメリットにより、一軸アンカーは多くのレーサーに支持されています。特に技術的なコースや公式大会などでは、その真価を発揮することが多いようです。
ミニ四駆一軸アンカーを自作するための完全ガイド
- ミニ四駆一軸アンカーの基本材料はFRPパーツとキノコヘッド
- 一軸アンカー作りに必要な工具はリューターや円形ヤスリが基本
- ミニ四駆一軸アンカーの座繰り加工は成功の鍵となる重要工程
- キノコヘッドの正しい加工方法は2.1mmの穴開けから始める
- 支柱の固定方法は複数あり用途に合わせた選択が重要
- フロント用とリア用の一軸アンカーの違いと適切な取り付け位置
- まとめ:ミニ四駆一軸アンカーは工夫次第で走行安定性を大きく向上させる重要パーツ
ミニ四駆一軸アンカーの基本材料はFRPパーツとキノコヘッド
ミニ四駆一軸アンカーを自作する際に必要な基本材料を見ていきましょう。一軸アンカーは比較的シンプルな材料で構成されていますが、それぞれの材料の役割を理解しておくことが重要です。
基本的な材料リストは以下の通りです:
- 弓FRPまたはカーボン(1〜2枚)
- FRPを使用する場合は2枚を貼り合わせることが推奨されています
- カーボンの場合は強度があるため1枚でも可能です
- リアに使う場合、カーボンなら1枚で十分な強度を確保できることが多いです
- ボールリンクFRP(通称「パンツ」)
- ボールリンクマスダンパーのFRPパーツを使用
- 中央に四角穴があり、この穴を加工して使用します
- ボールリンクマスダンパーから取り出すか、ワイドブレーキから削り出すことも可能
- キャッチャー端材
- パンツFRPの形に切り出して使用
- 適当な形でも問題ありませんが、パンツFRPに合わせるとより安定します
- キノコヘッド(アンダースタビヘッド)
- 色は赤、黄色、青などがあります
- タミヤのグレードアップパーツやアンダースタビヘッドセットに含まれています
- 色によって材質や硬さが若干異なる場合があるため、好みで選べます
- バネ(銀バネ推奨、好みで黒なども可能)
- バネの強さによってアンカーの動きが変わります
- 銀バネは標準的な強さで使いやすいとされています
- 黒バネなど強いバネを使うと、より強固な復元力が得られます
- ビス(お好みでキャップスクリューも可)
- キャップスクリューを使用すると、ネジ根元にタップが切られていないため動きが滑らかになり、FRPを削らないメリットがあります
- 25mm程度の長さが使いやすいでしょう
これらの材料は、ミニ四駆専門店やオンラインショップで入手可能です。特に弓FRPとボールリンクFRPは一軸アンカーの基本構造を形成する重要なパーツなので、品質の良いものを選ぶことをおすすめします。
また、一部のパーツはキットに含まれているものを流用することもできますが、専用パーツを使うとより安定した性能を得られる場合が多いです。材料が揃ったら、次は必要な工具を準備して実際の製作に取り掛かりましょう。
一軸アンカー作りに必要な工具はリューターや円形ヤスリが基本
一軸アンカーを自作するには、いくつかの工具が必要になります。これらの工具を揃えることで、加工の精度が上がり、より高品質なアンカーを作ることができます。
基本的に必要となる工具は以下の通りです:
- リューター(または電動ドライバーと三口チャック)
- 穴開けや削り作業に使用します
- 電動ドライバーと三口チャックを使うと、リューターほど回転数が速くないのでヤスリの目が詰まりにくいというメリットがあります
- リューターがない場合は、電動ドライバーで代用することも可能です
- 円形ヤスリ(特に8mmの円柱砥石)
- パンツFRPの中央穴を座繰りする際に使用します
- 新潟精機のダイヤモンドインターナル半丸8×12 #200 R8 φ2.35mmなどが適しています
- ダイソーなどで売っている砲弾形のビットも座繰り作業に適しているという声もあります
- ドリルビット(2mm, 2.1mm, 2.5mm, 3.5mm程度)
- キノコヘッドの穴開けに使用します
- 特に2.1mmのビットがキノコヘッドの穴開けに最適とされています
- 一気に大きなサイズで開けようとすると失敗する可能性があるため、段階的に穴を広げていくと良いでしょう
- ピンバイス
- 細かい穴開け作業に便利です
- WaveのHGワンタッチピンバイスなどが使いやすいとされています
- ニッパーやカッター
- パーツの切断やトリミングに使用します
- キノコヘッドの出っ張り部分を切る際などに使います
- 瞬間接着剤
- パーツの接着に使用します
- FRPの貼り合わせやキャッチャーの固定などに使います
- スパナやドライバー
- ビスの締め付けに使用します
- 細かい調整作業に必要です
- 作業用マスク
- 特に金属を削る際には鉄粉が出るため、マスクの着用が必須です
- また、作業用ケースなどの中で作業することも推奨されています
これらの工具のうち、特に重要なのが8mmの円柱砥石です。アンカー作りの核心となる座繰り作業に使用するため、これがあると作業がかなり楽になります。アンカーを頻繁に作る予定がある方は、この砥石を持っておくと便利でしょう。
また、キノコヘッドの穴開けに使用する2.1mmのドリルビットも、アンカーの動きに大きく影響する重要な工具です。適切なサイズの穴を開けることで、アンカーの動きが滑らかになります。
これらの工具を準備したら、次は実際の製作工程に移りましょう。工具の使い方には慣れが必要な場合もありますが、少しずつ練習しながら進めていくことで、誰でも高品質な一軸アンカーを作ることができるようになります。
ミニ四駆一軸アンカーの座繰り加工は成功の鍵となる重要工程
ミニ四駆一軸アンカーを作る上で、最も重要かつ難しい工程が「座繰り加工」です。この工程の出来栄えによってアンカーの動作品質が大きく左右されるため、じっくりと取り組む価値があります。
座繰り加工の対象となるのは、ボールリンクマスダンパーのFRP(通称「パンツFRP」)の中央にある四角い穴です。この穴を8mmの円柱砥石を使って「すり鉢状」に広げていきます。
座繰り加工の手順は以下の通りです:
- 仮座繰り
- まずパンツFRPの中央の穴を軽く座繰ります
- この時点では、四角の口が丸く見えるくらいまで軽く削るだけで十分です
- 厚さの半分くらいまで座繰るとよいでしょう
- キャッチャーの準備
- キャッチャーをパンツFRPの形に切り出します
- 切り出したキャッチャーをパンツFRPに瞬間接着剤で貼り付けます
- その後、四角穴の真ん中に穴を開けます
- この穴は6mmのビットが貫通するくらいまで開けておきます
- ここを「ド真ん中」に配置できるかどうかがポイントです
- 本座繰り
- 瞬間接着剤が乾いたら、アンカー軸の穴を8mm円柱砥石でさらに座繰ります
- この時、キノコの頭を当てながら微調整することが重要です
- キノコの頭の先が裏側に抜けるとガタガタになるので注意が必要です
- 6mmの貫通穴から8mmで慣らしていき、緩やかな傾斜がつくように「すり鉢加工」を行います
座繰り加工のポイントと注意点:
- 傾斜の角度調整によって滑らかさが変わるため、削りながら好みの塩梅を見つけることが大切です
- 座繰りが深すぎると不安定になり、浅すぎると動きが制限されます
- 傾斜が急すぎると動きがぎこちなくなり、緩やかすぎるとガタつきの原因となります
- 穴の位置を正確に中央に配置することも重要です
- 作業は少しずつ削りながら動きを確認するという慎重なアプローチがおすすめです
初心者が陥りやすい失敗として、一度に深く削りすぎてしまったり、傾斜が不均一になってしまうことがあります。座繰り加工は一度削りすぎると元に戻せないため、常に「少しずつ」が基本です。
また、座繰り加工後には動作確認をしながら調整を重ねていくことが大切です。キノコヘッドとの相性も確認しながら、滑らかな動きになるよう微調整していきましょう。
座繰り加工は一度で完璧にできることは少ないので、何度か作る中で自分なりのコツをつかんでいくことになります。この工程に時間をかけることで、高品質な一軸アンカーが完成します。
キノコヘッドの正しい加工方法は2.1mmの穴開けから始める
一軸アンカーの重要な構成部品であるキノコヘッド(アンダースタビヘッド)の加工方法について詳しく見ていきましょう。キノコヘッドの加工が適切であるかどうかも、アンカーの動きに大きく影響します。
キノコヘッドの加工手順は以下の通りです:
- キノコヘッドの選択
- まず使用するキノコヘッドの色を決めます
- 一般的に販売されているのは赤、黄色、青、黄色の4色程度です
- これらは以下の商品に含まれています:
- 赤・黄色:タミヤ グレードアップパーツ No.408 ロングスタビ低摩擦プラローラーセット
- 青・黄色:ミニ四駆 アンダースタビヘッドセット
- 色によって材質や硬さが若干異なる場合があるので、自分の好みや用途に合わせて選びます
- 穴開け準備
- キノコヘッドの中央の穴は標準では小さいため、拡張する必要があります
- 多くのレーサーが推奨しているのは、2.1mmのドリルビットを使用する方法です
- Waveの2.1mmドリルビットが使いやすいとされています
- 2mmより少し大きいサイズにすることで、支柱との摩擦が適度になり、スムーズな動きが得られます
- 穴開け作業
- ボールスタビ用のゴム管でキノコヘッドを押さえながら作業すると、グリップが効いて穴開けがしやすくなります
- ゴム管で押し付けながらドリルを回すと、簡単に穴を開けることができます
- 一気に2.1mmで開けるのが難しい場合は、2mmで開けてから2.1mmに広げるという方法もあります
- 中には2mmから2.5mmまで段階的に広げる方法を採用している方もいます
- バリ取りと仕上げ
- 穴を開けた後は、キノコヘッドの裏側に出っ張り(バリ)がある場合、それを切り落とします
- この出っ張りがあると、動きの妨げになる可能性があります
- ニッパーやカッターを使って丁寧に切り落としましょう
- 切り落とした後は、軽く紙やすりなどで表面を滑らかにすると良いでしょう
- 穴サイズの確認
- 穴を開けた後は、実際にビスを通してみて、スムーズに動くか確認します
- 穴が小さすぎるとビスに引っかかり、大きすぎるとガタつきの原因になります
- ちょうど良いサイズであれば、ビスとの間に適度な遊びがあり、スムーズに動くはずです
実際の作業では、穴開けの順序に関しても様々な意見があります。一部のレーサーは、まず穴を貫通させてから出っ張りを切るのではなく、出っ張りを切ってから穴を貫通させる方が良いという意見もあります。どちらの順序で行うかは、作業のしやすさによって選ぶとよいでしょう。
キノコヘッドの加工が完了したら、座繰りした穴とキノコヘッドの適合性を確認しながら、アンカーの組み立てを進めていきます。キノコヘッドと穴の相性が良いほど、アンカーの動きは滑らかになります。
支柱の固定方法は複数あり用途に合わせた選択が重要
一軸アンカーの製作において、支柱の固定方法は非常に重要なポイントです。支柱がしっかりと固定されていないと、アンカーの機能が十分に発揮されないだけでなく、耐久性にも問題が生じる可能性があります。
まず、一軸アンカーの支柱は「固定する必要がある」というのが多くのレーサーの共通認識です。支柱が固定されていないと、バンパーが跳ねて戻らない、根元がすぐに壊れる、バンパー後ろ側押さえが長くなければ使えないなどの問題が発生しやすくなります。
支柱の固定方法にはいくつかのアプローチがあり、自分のマシンやパーツの状況に合わせて選択することが大切です。主な固定方法は以下の通りです:
- 両ネジシャフトを利用する方法
- 両ネジシャフトを基部に固定した後、両ネジシャフトのナット部とボールリンクFRPがフラットになるよう、基部またはボールリンクFRP側を厚底にします
- ネジ山がアンダースタビヘッドの動きを阻害する可能性があるため、注意が必要です
- この方法は比較的シンプルで、多くのシャーシに適用できる汎用性の高い方法です
- アンダースタビヘッドの穴を拡張する方法
- アンダースタビヘッドの穴を拡張し、2段アルミローラー用5mmパイプなどを通して上部ナットで締め上げて固定します
- この方法では、キノコヘッドの動きを確保しながらも支柱をしっかりと固定できます
- パイプの長さを調整することで、アンカーの高さも調整できるメリットがあります
- MSシャーシ専用の固定方法
- MSシャーシの場合、ユニットのバンパーステー穴上部にステーを渡し、基部とステーでアンカーを挟む形でキャップスクリューなどを通し上部ナット止めします
- MSシャーシの特性を活かした固定方法で、安定性が高いのが特徴です
- MSシャーシを使用している場合は、この方法がおすすめです
どの固定方法を選ぶにせよ、支柱に負担が集中するという一軸アンカーの特性上、しっかりとした固定が重要です。また、支柱の材質や太さによっても適切な固定方法が変わってくる場合があります。
支柱を固定する際のポイントとしては、キノコヘッドの動きを阻害しないよう注意することと、支柱自体の強度を確保することが挙げられます。支柱が弱いと走行中の衝撃で曲がったり折れたりする可能性があるため、適切な材質と太さを選ぶことも重要です。
また、固定後はバネの強さやナットの締め具合によって、アンカーの動きの特性が変わってきます。自分のマシンの特性やコースの特徴に合わせて、最適な支柱の固定方法と調整を行うことで、アンカーの性能を最大限に引き出すことができるでしょう。
フロント用とリア用の一軸アンカーの違いと適切な取り付け位置
一軸アンカーはフロントとリア、どちらにも取り付け可能ですが、それぞれに適した形状や取り付け方法があります。フロント用とリア用の違い、そして適切な取り付け位置について詳しく見ていきましょう。
まず、フロント用とリア用の一軸アンカーの主な違いは、以下のポイントにあります:
- 形状の違い
- フロント用は比較的コンパクトな形状が多く、マシン前方の限られたスペースに収まるよう設計されています
- リア用はやや大きめの形状でも問題なく、後方の安定性を重視した設計になっていることが多いです
- 材料の違い
- リア用の場合、カーボンなら1枚で十分な強度を確保できますが、FRPを使用する場合は2枚貼り合わせることが推奨されています
- フロント用は衝撃を最初に受けることが多いため、より強度の高い材料や構造が求められることがあります
- 取り付け角度の違い
- フロント用は前方からの衝撃に対応するため、やや上向きの角度がつけられることがあります
- リア用は後方の安定性を重視し、水平に近い角度で取り付けられることが多いです
次に、最も重要なポイントとして、一軸アンカーの適切な取り付け位置があります。アンカーは必ず「稼動穴に対して進行方向後ろ側」に取り付ける必要があります。
稼動穴の前側にバンパーを取り付けると、本来の機能を発揮できません。その理由は、壁に接触した際の力の伝わり方にあります。通常の取り付け位置(後ろ側)では、支柱を軸に後部押さえでその力を受け止め、後方に引かれる(前方から押される)力に耐えます。
しかし、バンパーが支柱より前にある場合、壁からの力により支柱を登るような後方に捻れる動きをしてしまいます。これはフロントATバンパーのスラスト抜けのような状態となり、バンパーの機能が低下するだけでなく、コースアウトなどのイレギュラーの原因にもなり得ます。
また、アンカーの後ろにあるバンパー押さえの長さも重要です。後ろのバンパー押さえが長すぎると、アンカーの捻れる動きを阻害してしまうため、短く、あっても湯呑み程度が適切とされています。
取り付け位置に関する注意点:
- 必ず稼動穴に対して進行方向後ろ側に取り付ける
- 後ろのバンパー押さえは短く設計する
- 取り付け高さはコースの特性に合わせて調整する
- フロントとリアの両方に取り付ける場合は、それぞれの動きが干渉しないよう注意する
フロントとリア、どちらに一軸アンカーを取り付けるかは、マシンの特性やコースの特徴によって決めるとよいでしょう。フロントとリアの両方に取り付けることで、より安定した走行が期待できる場合もあります。
まとめ:ミニ四駆一軸アンカーは工夫次第で走行安定性を大きく向上させる重要パーツ
最後に記事のポイントをまとめます。
- 一軸アンカーはイレギュラーからの復帰率向上を目的としたギミック
- アンカーの定義は「1軸のバンパー」「キノコを使用」「AT的な動き」「スライドもする」の4要素
- MSシャーシとの相性が特に良いが、他のシャーシにも取り付け可能
- アンカーは速さよりも安定性を重視したパーツ
- 座繰り加工の精度がアンカーの性能を左右する重要な工程
- キノコヘッドの穴は2.1mmが推奨され、適切な加工が必要
- 支柱は必ず固定する必要があり、複数の固定方法から選択可能
- アンカーは稼動穴に対して必ず進行方向後ろ側に取り付ける
- バンパー押さえは短く、湯呑み程度が適切
- 左右のスライド機能により回頭性が向上する
- アンカーの調整には穴の傾斜、キノコの形状、バネの強さなど様々な要素が影響
- 一軸アンカーはLCが楽になるという効果も期待できる
- 材料は弓FRP/カーボン、ボールリンクFRP、キャッチャー端材、キノコヘッド、バネ、ビスが基本
- 8mmの円柱砥石があると座繰り作業がかなり楽になる
- フロント用とリア用で最適な形状や材料が異なる