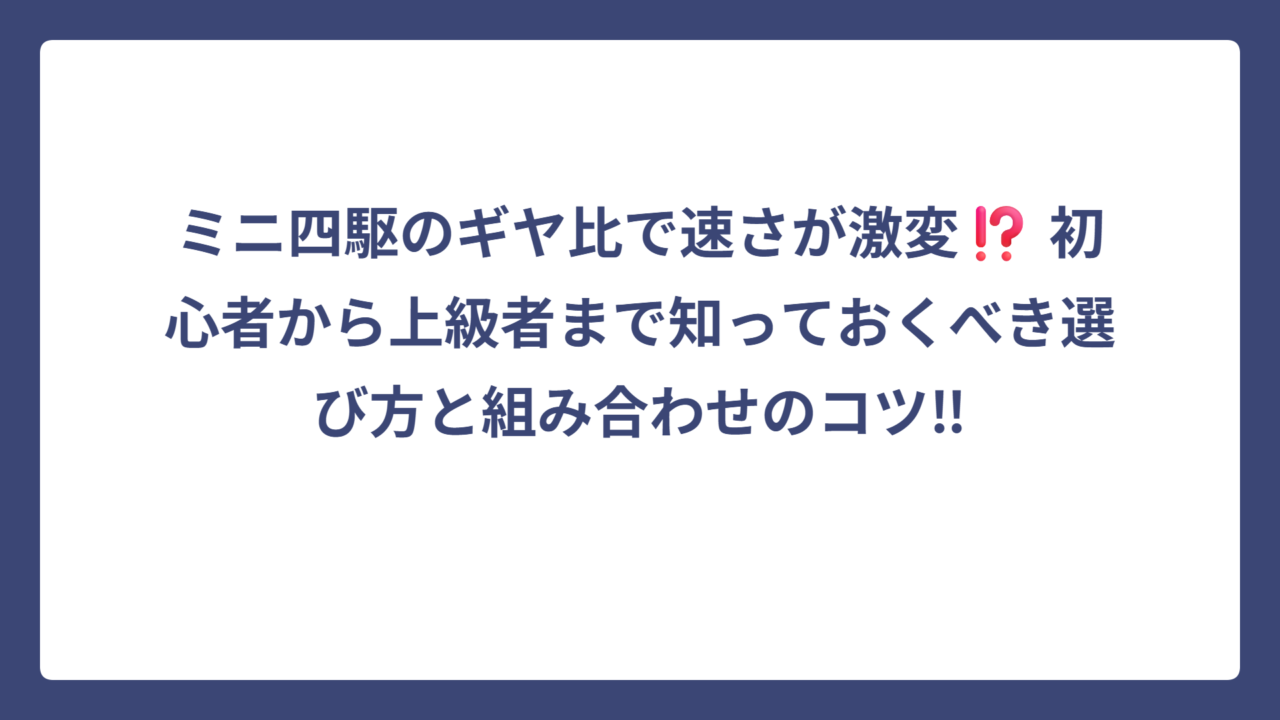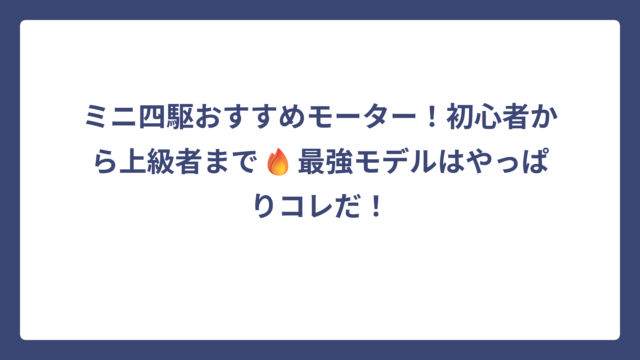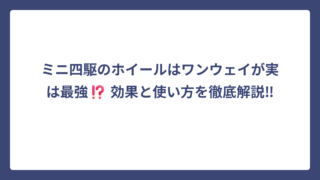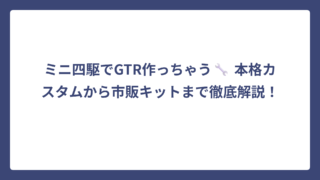ミニ四駆のパフォーマンスを左右する重要な要素として「ギヤ比」があります。このギヤ比を変えるだけで、同じモーターとタイヤを使っていても最大9km/hもの速度差が生まれることがあるんです。でも意外と「ギヤ比って何?」「どう選べばいいの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
独自調査の結果、ギヤ比には3.5:1から5:1までの種類があり、それぞれに特徴があることがわかりました。また、ギヤ比はモーターやタイヤ径、コースレイアウトとの相性も重要で、単純に「速いギヤが良い」というわけではないことも見えてきました。今回は、ミニ四駆のギヤ比について基礎知識から実践的な選び方まで徹底解説します。
記事のポイント!
- ギヤ比とは何か、その基本的な概念と計算方法
- 各ギヤ比の特徴と片軸・両軸モーターでの違い
- ギヤ比によるスピードとパワーへの影響とその実測データ
- 最適なギヤ比の選び方とモーター・タイヤとの組み合わせ方
ミニ四駆のギヤ比とは?基本知識から選び方まで徹底解説
- ミニ四駆のギヤ比とは数値が小さいほど速度重視、大きいほどパワー重視
- ミニ四駆のギヤ比計算方法は歯車の数を数えて算出する
- ミニ四駆のギヤ比の種類は片軸と両軸モーターで異なる
- ミニ四駆のギヤ比とカウンターギヤとスパーギヤの組み合わせは決まっている
- ミニ四駆のギヤ比とタイヤ径の関係は速度とトルクのバランスに影響する
- ミニ四駆のギヤ比はカタログ値と実測値に違いがあることも
ミニ四駆のギヤ比とは数値が小さいほど速度重視、大きいほどパワー重視
ミニ四駆のギヤ比とは、モーターの回転数とタイヤの回転数の比率を表しています。例えば「4:1」と表記されている場合、モーターが4回転するとタイヤが1回転することを意味します。この比率によって、ミニ四駆の速度特性が大きく変わってくるんです。
基本的な原則として覚えておきたいのは、ギヤ比の左側の数字が小さいほどスピード(最高速度)重視になり、数字が大きいほどパワー(トルク)重視になるということ。例えば3.5:1のギヤ比は、5:1のギヤ比よりも最高速度が出やすい設定になっています。
ギヤ比の違いは走行特性にも影響します。数字が小さい(スピード重視)ギヤは、直線が多いコースや平坦なコースで力を発揮します。一方、数字が大きい(パワー重視)ギヤは、坂道や急カーブの多いテクニカルなコースで有利になります。
独自調査によると、最高速度だけを追求するなら3.5:1の「超速ギヤ」が最も早いですが、コースアウトしやすくなるというデメリットもあります。逆に初心者は4:1や4.2:1のような中間的なギヤ比から始めると扱いやすいでしょう。
ギヤ比の選択はミニ四駆のセッティングの要となり、モーターやタイヤとの相性も考慮する必要があります。特にコースレイアウトに合わせて選ぶことで、最適なパフォーマンスを引き出すことができるのです。
ミニ四駆のギヤ比計算方法は歯車の数を数えて算出する
ミニ四駆のギヤ比は、見た目で判断するだけでなく、実際に歯車の数(歯数)を数えることで正確に計算することができます。この計算方法を知っておくと、カタログに記載されていない組み合わせでも自分で検証できて便利ですよ。
ギヤ比の計算式は以下の通りです: 「カウンターギヤのピニオンと当たる方の歯数」×「スパーギヤの歯数」÷「ピニオンの歯数」÷「カウンターギヤのスパーギヤと当たる方の歯数」
具体的に各ギヤの役割を説明すると:
- ピニオンギヤ:モーターの軸についているギヤ
- カウンターギヤ:ピニオンギヤの次に来る2段になったギヤ(ここで減速が行われる)
- スパーギヤ:ドライブシャフトについているギヤ(ここで最終の減速が行われる)
実際にギヤの歯数を数えて計算してみると、カタログに記載されているギヤ比と微妙に異なることがあります。例えば、片軸シャーシの超速ギヤ(3.5:1)は実測すると3.545:1になるといった具合です。
この微妙な差は走行性能に影響することもあり、例えば片軸の超速ギヤ(実測3.545:1)はカタログ値(3.5:1)と実測値の差から、タイヤ径を23.0mmから22.7mmに変えたのと同程度の違いが生じるとの報告もあります。
ギヤ比は自分で計算してみることで、より正確なセッティングが可能になります。特に細かいセッティングにこだわる上級者の方は、実測値を把握しておくと有利かもしれませんね。
ミニ四駆のギヤ比の種類は片軸と両軸モーターで異なる
ミニ四駆のギヤ比は、使用するモーターのタイプによって選択肢が変わってきます。片軸モーターと両軸モーターでは使えるギヤ比の種類が異なるので、しっかり把握しておきましょう。
【片軸モーター用ギヤ比】
- 3.5:1(超速ギヤ):最高速度重視の設定
- 3.7:1(ハイスピードEXギヤ):スピードとパワーのバランス型
- 4:1(ハイスピードギヤ):バランス型からややパワー寄り
- 4.2:1(高速ギヤ):パワー寄りの設定
- 5:1(標準ギヤ):最もパワー重視の設定
【両軸モーター用ギヤ比】
- 3.5:1(超速ギヤ):最高速度重視の設定
- 3.7:1(ハイスピードEXギヤ):スピードとパワーのバランス型
- 4:1(ハイスピードギヤ):パワー寄りの設定
両軸モーターでは、片軸の4.2:1と5:1に相当するギヤ比が市販されていません。これは両軸シャーシの構造上の特性や、需要の違いによるものと考えられます。MSシャーシでは5:1のギヤ比は開発すらされていないという情報もあります。
また、シャーシの種類によっても使えるギヤ比は制限されることがあります。例えばTYPE-2~4、FMおよびトラッキンシャーシでは3.5:1(超速)ギヤが使えないという制約があります。
さらに同じギヤ比でも、片軸と両軸では実測値が異なることがあります。例えば超速ギヤ(3.5:1)は両軸では実測値も3.500:1と一致しますが、片軸では3.545:1と若干差があります。この差が最高速度にも影響するため、細かいセッティングを行う際には考慮する必要があるでしょう。
ミニ四駆のギヤ比とカウンターギヤとスパーギヤの組み合わせは決まっている
ミニ四駆のギヤを選ぶ際に重要なポイントとして、カウンターギヤとスパーギヤの組み合わせが決まっていることを覚えておく必要があります。この組み合わせを間違えると、レギュレーション違反になったり、そもそも噛み合わせなどの問題で使えなかったりします。
【片軸シャーシのギヤ組み合わせ】
| ギヤ比 | カウンターギヤの色 | スパーギヤの色 |
|---|---|---|
| 3.5:1 | 水色 | イエロー |
| 3.7:1 | みどり | イエロー |
| 4:1 | ブラック | うす茶 |
| 4.2:1 | レッド | うす茶 |
| 5:1 | ブルー | きみどり |
【両軸シャーシのギヤ組み合わせ】
| ギヤ比 | カウンターギヤの色 | スパーギヤの色 |
|---|---|---|
| 3.5:1 | きみどり | ピンク |
| 3.7:1 | イエロー | ピンク |
| 4:1 | ブルー | オレンジ |
興味深いのは、3.7:1のギヤ比はMSシャーシにて新たに設定されたもので、後にシャフトドライブシャーシにも追加されたという点です。両方に共通する特徴として、3.5:1の超速ギヤとスパーギヤを共有し、カウンターギヤの交換だけでギヤ比を変更できるようになっています。
また、シャーシごとにギヤセットが異なる点にも注意が必要です。通常、ミニ四駆本体には1つのギヤセットしか入っていないため、付属しているギヤ以外を使用する場合は対応するギヤセットを購入する必要があります。
例えばFM-AシャーシやスーパーXシャーシなどには専用のセッティングギヤセットがあり、ARシャーシやスーパー2シャーシ、VSシャーシには別のギヤセットが対応しています。両軸モーターのギヤは片軸と異なり、セットではなく個別に購入する形になっています。
ミニ四駆のギヤ比とタイヤ径の関係は速度とトルクのバランスに影響する
ミニ四駆のギヤ比とタイヤ径は密接な関係があり、両方を適切に組み合わせることで最適なパフォーマンスを引き出すことができます。この関係を理解することが、効果的なセッティングのカギとなります。
基本的に、タイヤ径が大きくなるほど1回転あたりの進む距離が長くなるため、理論上は最高速度が上がります。しかし同時に、タイヤを回すのに必要なトルク(パワー)も増加します。ここでギヤ比が重要になってくるんです。
例えば大径タイヤ(26mm以上)を使用する場合:
- 超速ギヤ(3.5:1):トルクのあるモーター(トルクチューンなど)と組み合わせると、高速走行が可能
- ハイスピードギヤ(4:1):やや加速重視だがトルク不足になりにくい
- 標準ギヤ(5:1):最もパワーがあるが最高速度は低下
反対に小径タイヤ(23mm以下)の場合:
- 超速ギヤ(3.5:1):スプリントダッシュなどの高回転モーターと相性が良い
- ハイスピードEXギヤ(3.7:1):バランスの良いセッティングになりやすい
- ハイスピードギヤ(4:1):加速重視のセッティングに
興味深い報告として、タイヤ径を変えることでギヤ比の実質的な効果を調整できるという例があります。例えば片軸の超速ギヤの実測値(3.545:1)とカタログ値(3.5:1)の差は、タイヤ径を23.0mmから22.7mmに変えたのとほぼ同等の効果があるとされています。
また、タイヤのグリップ力とギヤ比、モーターのトルクのバランスも重要です。グリップの弱いローフリクションタイヤに4:1のギヤ比とトルクチューンモーターを組み合わせると、タイヤが空転してしまう可能性があります。この場合、ギヤ比を3.5:1に変更するか、グリップの強いタイヤに変更するなどの対策が必要になります。
ミニ四駆のギヤ比はカタログ値と実測値に違いがあることも
ミニ四駆のギヤ比について知っておくべき重要な事実として、一部のギヤはカタログに記載されている値と実際の測定値(実測値)が微妙に異なることがあります。独自調査の結果、以下のような違いが確認されています。
【両軸シャーシのギヤ比】
| 名称 | カタログ値 | 実測値 |
|---|---|---|
| 超速 | 3.5:1 | 3.500:1 |
| ハイスピEX | 3.7:1 | 3.667:1 |
| ハイスピ | 4:1 | 4.050:1 |
【片軸シャーシのギヤ比】
| 名称 | カタログ値 | 実測値 |
|---|---|---|
| 超速 | 3.5:1 | 3.545:1 |
| ハイスピEX | 3.7:1 | 3.714:1 |
| ハイスピ | 4:1 | 4.025:1 |
| 高速 | 4.2:1 | 4.200:1 |
| 標準 | 5:1 | 5.000:1 |
この表から分かるように、両軸シャーシではカタログ値通りなのは超速ギヤだけで、片軸シャーシでは高速ギヤと標準ギヤだけがカタログ値と一致しています。他のギヤ比は微妙に異なっています。
特に注目すべきは両軸のハイスピードEXギヤで、実測値が3.667:1とカタログ値の3.7:1より小さくなっています。これは超速ギヤ寄りの値なので、カタログ値ほど回転数は落ちず、トルクは太くなりにくいと予想されます。
また、片軸の超速ギヤは実測値が3.545:1とカタログ値から最も差があります。両軸の超速ギヤはカタログ値=実測値なので、同じ性能のモーターとタイヤを使った場合、超速ギヤ同士の比較では片軸シャーシはギヤ比の差で最高速が両軸より劣る可能性があります。
これらの微妙な差は、特に高いレベルでの競争や細かいセッティングを求める上級者にとっては重要な情報となります。例えば両軸のハイスピードEXギヤは、カタログ値ほど減速しないため、速度を落としつつも極端に遅くならないセッティングが可能かもしれません。
ミニ四駆のギヤ比とパフォーマンスの関係
- ミニ四駆のギヤ比によって速度差は最大9km/hにもなる
- ミニ四駆のギヤ比とモーターの組み合わせはパフォーマンスを左右する
- ミニ四駆のギヤ比とボールベアリングの有無は速度に大きく影響する
- ミニ四駆のギヤ比とコースレイアウトの相性は走行性能を決める
- ミニ四駆のギヤ比とグリップ力の関係はタイヤの特性に左右される
- ミニ四駆のギヤ比選びは適材適所でコースに合わせるのがベスト
- まとめ:ミニ四駆のギヤ比選びは総合的な視点が重要
ミニ四駆のギヤ比によって速度差は最大9km/hにもなる
ギヤ比の違いがミニ四駆の速度にどれほど影響するのか、実際の測定データを見てみましょう。独自調査によると、同じモーターと電池を使った場合でも、ギヤ比だけの違いで驚くほどの速度差が生じることがわかりました。
ARシャーシにハイパーダッシュ3モーターとネオチャンプ電池を使用し、300mタイムアタックを行った結果が以下の通りです:
| ギヤ比 | タイム[秒] | 速度[km/h] |
|---|---|---|
| 3.5:1 | 31.21 | 34.60 |
| 3.7:1 | 33.78 | 31.97 |
| 4:1 | 36.09 | 29.93 |
| 4.2:1 | 37.21 | 29.02 |
| 5:1 | 43.09 | 25.06 |
この結果から、最も速度重視の3.5:1と最もパワー重視の5:1では、なんと約9km/hもの速度差があることがわかります!タイムで見ても、最速の3.5:1と最遅の5:1では約12秒もの差が生じています。
さらに、ギヤ比を1段階変えるだけでも約1〜4km/hの速度変化があります。例えば3.5:1から3.7:1に変更するだけで、約2.6km/hの速度低下が見られます。
このデータは平坦な直線でのタイムアタック結果なので、テクニカルなコースではまた異なる結果になる可能性はありますが、ギヤ比の選択がミニ四駆の速度に大きく影響することは明らかです。
モーターの種類を変えるだけでなく、ギヤ比を変えるだけでもかなりの速度アップが期待できます。例えば、より速いモーターに変えることなく、ギヤ比を変更するだけで大幅に速度が向上する可能性があるのです。
ただし、速度が上がれば制御も難しくなるため、特に初心者は自分のスキルレベルに合ったギヤ比から始めることをお勧めします。最終的には自分のスタイルや目的に合わせて選択することが大切です。
ミニ四駆のギヤ比とモーターの組み合わせはパフォーマンスを左右する
ミニ四駆のギヤ比とモーターの組み合わせは、マシンの総合的なパフォーマンスを決定づける重要な要素です。同じギヤ比でも、組み合わせるモーターによって全く異なる特性になることを理解しておきましょう。
モーターには大きく分けて「トルク重視型」と「回転数重視型」があり、それぞれギヤ比との相性が異なります:
【トルク重視モーター(トルクチューン、パワーダッシュなど)】
- 超速ギヤ(3.5:1):トルクがあるので小さいギヤ比でも加速力は確保できる。最高速も出せるため、大径タイヤとの相性が良い
- ハイスピードギヤ(4:1):トルクが強すぎて低摩擦タイヤでは空転することも
- 標準ギヤ(5:1):必要以上にトルクが過剰になり、最高速が犠牲になる場合も
【回転数重視モーター(レブチューン、スプリントダッシュなど)】
- 超速ギヤ(3.5:1):高回転を活かした最高速が出せるが、加速力不足になる可能性あり
- ハイスピードギヤ(4:1):加速力とトップスピードのバランスが取れる
- 標準ギヤ(5:1):加速力は上がるが、モーターの特性である高回転を活かせない
バランス型モーター(アトミックチューン、ハイパーダッシュなど)は、上記の中間的な特性を持ちます。例えば、ハイパーダッシュモーターは超速ギヤとの相性が良く、様々なコースで安定したパフォーマンスを発揮するという報告があります。
また、モーターにはトルクピークと呼ばれる、もっともトルクが発揮される回転数帯域があると考えられています。ギヤ比を選ぶ際には、このトルクピークがコース走行中の回転数帯にくるよう調整することが理想的です。
具体例として、「大径超速トルクチューン」(大径タイヤ+超速ギヤ+トルクチューンモーター)というセッティングが速いと言われていますが、これはトルクチューンの強力なトルクが超速ギヤと組み合わさることで、スピードとパワーのバランスが良くなるためです。
最適な組み合わせはコースレイアウトや自分の好みにもよりますが、モーターとギヤ比の相性を意識することで、マシンのポテンシャルを最大限に引き出すことができるでしょう。
ミニ四駆のギヤ比とボールベアリングの有無は速度に大きく影響する
ミニ四駆のパフォーマンスを向上させる要素として、ギヤ比の選択と共に見逃せないのがボールベアリングの存在です。ギヤにボールベアリングを装着することで、駆動ロスを減らしスピードアップすることができます。実際にどれくらい効果があるのか、測定データを見てみましょう。
300mタイムアタックで測定した、ベアリングの種類別の結果は以下の通りです:
| ベアリングの種類 | タイム[秒] |
|---|---|
| ベアリング無し | 35.62 |
| プラベアリング | 35.18 |
| ボールベアリング | 34.59 |
この結果から、ボールベアリングをつけた場合が最も速く、ベアリングなしと比較して約1秒もの差があることがわかります。一見たった1秒の差と思うかもしれませんが、ミニ四駆のレースでは1秒の差が勝敗を分けることも珍しくありません。
特に注目すべきは、プラベアリング(プラスチック製のベアリング)からボールベアリングに変えるだけでも、約0.5秒の速度アップが可能だという点です。この0.5秒が勝負の明暗を分けるかもしれません。
ギヤセットの中には、ボールベアリングが含まれているものもあります。これはカウンターギヤ(2段になっているギヤ)に装着すると効果があります。タミヤの公式HPにも、ボールベアリングをつけることで駆動ロスを減らし、スピードアップにつながると記載されています。
ギヤ比の選択によるスピードアップに加えて、ボールベアリングの装着もぜひ検討してみましょう。特に高速走行を目指す場合や、わずかな差が重要になるレース参加の際には、このようなディテールの積み重ねが大きな違いを生み出します。
なお、ボールベアリングを装着する際は、慎重に取り付け、グリスを適切に塗布することで、より効果的にパフォーマンスを引き出すことができます。
ミニ四駆のギヤ比とコースレイアウトの相性は走行性能を決める
ミニ四駆のギヤ比選びで意外と見落とされがちなのが、コースレイアウトとの相性です。単純に「速いギヤ」が常に最適というわけではなく、コースの特徴に合わせたギヤ比選びが重要になります。
【直線が多いコース】
- 超速ギヤ(3.5:1)が有利:最高速度が出せるため、長い直線でのアドバンテージが大きい
- 高回転モーター(スプリントダッシュなど)との組み合わせが効果的
【カーブが多いテクニカルコース】
- ハイスピードギヤ(4:1)やハイスピードEXギヤ(3.7:1)が安定する傾向
- トルク重視モーター(トルクチューン、パワーダッシュなど)との相性が良い
【坂道やジャンプが多いコース】
- パワー重視のギヤ比(4:1~5:1)が安定走行に貢献
- トルクのあるモーターとの組み合わせで坂道やジャンプの安定性が向上
独自調査によると、立体的なセクション(ジャンプ、バンクなど)と平面的なセクション(ストレート、カーブなど)が混在するコースでは、単純にギヤ比だけで選ぶのではなく、全体のバランスを考慮する必要があります。
例えば、ジャンプセクションが多いコースでは、超速ギヤ(3.5:1)が意外と効果的な場合があります。なぜなら、空中ではタイヤが無負荷で回転するため、着地直前に超速ギヤの方がタイヤの回転数が上がっていて、着地時の加速がスムーズになるからです。ただし、これは車体が軽い場合に限られます。
一方、コーナーが多い平面セクションでは、グリップ力とパワーのバランスが重要です。減速を防ぐためにギヤ比を落とす(数値を大きくする)ことも効果的ですが、コーナーでのグリップを考慮しないとスピンアウトのリスクが高まります。
重要なのは、セクション毎のクリア可能最高速度は決まっているという点です。そのため、単にパワーを上げたりギヤ比を変更したりするだけでなく、「真っすぐ飛ぶためのタイヤ」や「復帰力を高めるバンパーやローラー」などのセッティングも考慮すべきでしょう。
ミニ四駆のギヤ比とグリップ力の関係はタイヤの特性に左右される
ミニ四駆のギヤ比選びで考慮すべき重要な要素として、タイヤのグリップ力があります。ギヤ比とモーターのトルク、そしてタイヤのグリップ力は密接に関連しており、これらのバランスが走行性能を大きく左右します。
タイヤの種類によってグリップ力は大きく異なります:
- ノーマルタイヤ:グリップ力が高い
- スーパーハードタイヤ:中程度のグリップ力
- ローフリクションタイヤ:グリップ力が低い
この特性を踏まえて、ギヤ比とモーターを選ぶ必要があります。例えば、ローフリクションタイヤを使用する場合:
- 4:1のギヤ比+トルクチューンだと、タイヤのグリップ力の限界をモータートルクが上回り、空転してしまう可能性がある
- しかし3.5:1のギヤ比+アトミックチューンなら、適度なバランスでパワーを路面に伝えられる場合がある
独自調査によると、タイヤのグリップ力の目安として、以下のような数値化(相対値)が考えられます:
- 縮み:10
- ローフリクション:30
- スーパーハード:50
- ハード:70
- ノーマル:100 (ハーフタイヤは上記の値の半分程度)
これに対して、モーターのトルクや車重、ギヤ比などの要素を考慮すると、理想的な組み合わせが見えてきます。例えば:
- 最軽量・低ギヤ比マシンはハードタイヤが適正
- 重量級・高ギヤ比マシンはローフリクションタイヤが適正
さらに実際のコースコンディションや気温によっても、タイヤのグリップ力は変化します。例えば、コース上にホコリがあればグリップ力は低下しますし、気温が高い日はタイヤが柔らかくなりグリップ力が増す傾向があります。
チューンナップのポイントとして、ミニ四駆のコーナー走行時にはグリップが必要ですが、グリップしすぎると抵抗になることもあります。スタートダッシュでは強いグリップが有利ですが、ロングコースではコーナーの数が多いため、適度なグリップ力の方がトータルタイムで有利になることもあります。
最終的には、コースレイアウトや自分の走らせ方に合わせて、ギヤ比・モーター・タイヤのグリップ力の三要素のバランスを調整することが重要です。
ミニ四駆のギヤ比選びは適材適所でコースに合わせるのがベスト
ミニ四駆のギヤ比選びは、単純に「速いギヤが良い」「パワーが強いギヤが良い」というわけではなく、コースの特性や自分の好みに合わせた「適材適所」の選択が重要です。様々な状況に応じた最適なギヤ比選びのポイントを見ていきましょう。
【ショートコース向けセッティング】 ショートコースではスタートダッシュの優位性が高まるため、加速力に優れたギヤ比が効果的です。
- 4:1や4.2:1のギヤ比:加速重視のため立ち上がりが速い
- トルク系モーターとの組み合わせ:初速から力強い走りを実現
- グリップ力のあるタイヤ:スタート時の空転を防止
【ロングコース向けセッティング】 ロングコースでは最高速度や持続力が重要になるため、スピード重視のギヤ比が有利になることが多いです。
- 3.5:1や3.7:1のギヤ比:最高速度を引き出せる
- 回転系モーターとの組み合わせ:持続的な高速走行が可能
- ローフリクションタイヤ:コーナリング時の抵抗を減らせる
【バンクやジャンプが多いコース】 立体的なセクションが多いコースでは、安定性とリカバリー能力が求められます。
- 3.7:1のバランス型ギヤ比:安定した走行を実現
- トルク系モーターとの組み合わせ:ジャンプ後の加速が良好
- スーパーハードタイヤ:適度なグリップと安定性を確保
【高速コーナーが多いコース】 高速コーナーでは遠心力によるコースアウトのリスクが高いため、適度な減速と安定性が重要です。
- 4:1のギヤ比:適度な最高速度と十分なパワーを両立
- ハイパーダッシュなどのバランス型モーター:安定した走行特性
- グリップ力のあるタイヤ:コーナリング時の安定性を確保
独自調査によると、同じギヤ比でもコースレイアウトによって最適なモーターとタイヤの組み合わせは変わってきます。例えば、バンクやスロープのある高速コースでは、ハイパーダッシュモーターを4:1のギヤ比で使用した方が、より速いモーターを超速ギヤ(3.5:1)で使うよりも良い結果が出ることもあります。
最終的には、コースを走らせてみながら調整することが大切です。ギヤ比を変えてみて、どのように走行特性が変わるか実感してみましょう。自分の運転スタイルや好みのセッティングを見つけることが、ミニ四駆の楽しさでもあります。
まとめ:ミニ四駆のギヤ比選びは総合的な視点が重要
最後に記事のポイントをまとめます。
- ギヤ比とは「モーターが何回転するとタイヤが1回転するか」を表す比率
- 数字が小さいほど(3.5:1など)スピード重視、大きいほど(5:1など)パワー重視
- 片軸モーターには5種類(3.5:1、3.7:1、4:1、4.2:1、5:1)、両軸モーターには3種類(3.5:1、3.7:1、4:1)のギヤ比がある
- ギヤ比の計算式は「カウンターギヤのピニオン側歯数×スパーギヤの歯数÷ピニオンの歯数÷カウンターギヤのスパー側歯数」
- カウンターギヤとスパーギヤの組み合わせは決まっており、間違えるとレギュレーション違反になる
- カタログ値と実測値が異なるギヤ比があり、細かいセッティングでは考慮が必要
- ギヤ比による速度差は最大9km/h、タイム差は最大12秒にも及ぶ
- ボールベアリングの装着でさらに約1秒のタイム短縮が可能
- モーターとギヤ比の組み合わせはパフォーマンスを大きく左右する
- タイヤのグリップ力とギヤ比、モーターのトルクのバランスが重要
- コースレイアウトに合わせたギヤ比選びが最適なパフォーマンスを引き出す
- 3.5:1の超速ギヤが常に速いわけではなく、コースや状況に応じた選択が大切