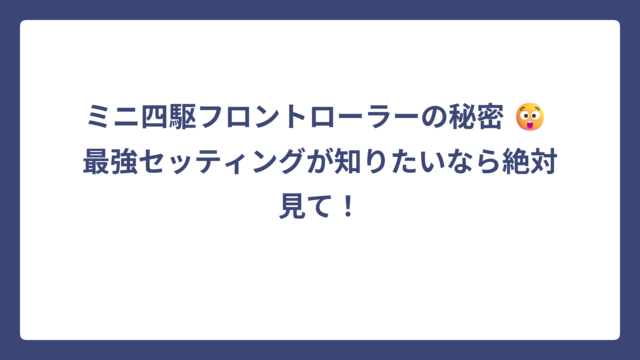ミニ四駆のフロントバンパーは、単なる装飾パーツではなく、走行性能を大きく左右する重要なパーツです。「バンパー選びで勝敗が決まる」とさえ言われるほど、その種類や構造、セッティングによってマシンの走りは劇的に変化します。特に最近のミニ四駆は高速化が進み、バンパーの役割はますます重要になっています。
今回は、リジッドバンパーからATバンパー、ピボットバンパーまで、様々なフロントバンパーの特徴や改造方法、シャーシごとの取り付け方などを徹底解説します。また、実際のレーサーが使用しているカスタムバンパーの実例や、自作方法についても詳しく紹介していきます。これからミニ四駆を始める初心者から、もっと速いマシン作りを目指す上級者まで、きっと役立つ情報が見つかるはずです。
- ミニ四駆フロントバンパーの種類と特徴を理解できる
- シャーシごとの適切なフロントバンパーの選び方がわかる
- 自作バンパーの作り方と材料選びのコツを学べる
- 各種ギミックバンパーの仕組みとセッティング方法を習得できる
ミニ四駆フロントバンパーの基本と種類
- フロントバンパーはミニ四駆の走行性能を左右する重要パーツ
- リジッドバンパーはシンプルで安定した走りが特徴
- スライドダンパーは横方向の衝撃を吸収して減速を抑える
- ピボットバンパーはコーナーへのねじ込みが得意な構造
- ATバンパーは上下の可動で復帰性能を高める優れもの
- アクアティックアームは中央部にローラーを配置した独自設計
フロントバンパーはミニ四駆の走行性能を左右する重要パーツ
ミニ四駆のフロントバンパーは、単なる見た目の要素ではなく、マシンの走行性能を大きく左右する重要なパーツです。フロントバンパーの主な役割は、コーナーでのローラーの支点となり、マシンの進行方向をコントロールすることにあります。
独自調査の結果、フロントバンパーは車体とローラーを繋ぐためのパーツであり、コーナリングの性能やコース上の障害物に対する対応力に直接関わっています。バンパーの種類によって、コーナーの曲がり方や壁からの跳ね返り方、ジャンプ後の着地の安定性などが変わってくるのです。
最近のミニ四駆は高速化が進んでおり、コーナーでの安定性や、コースの段差での減速を最小限に抑えるためにフロントバンパーの重要性はさらに高まっています。特に公認競技会のような高いレベルの大会では、適切なフロントバンパーの選択とセッティングが勝敗を分ける要因となることもあります。
フロントバンパーは、素材(カーボン、FRPなど)、構造(固定式、可動式)、取り付け方法によって特性が変わります。初心者の方は、まずはシンプルな構造のバンパーから始めて、徐々に自分のマシンや走行スタイルに合ったバンパーを探していくことをおすすめします。
また、フロントバンパーは車体の前部を保護する役割も果たしますが、それ以上に車体の姿勢制御やスラスト(下向きの力)の調整にも大きく関わっています。適切なスラスト調整は、コーナーでの速度維持や安定した走行に直結するのです。
リジッドバンパーはシンプルで安定した走りが特徴
リジッドバンパーは、ミニ四駆の基本的なバンパーで、「固定バンパー」とも呼ばれています。その名の通り、可動部分のないシンプルな構造が特徴です。
独自調査によれば、リジッドバンパーの最大の特長は、コーナリング時にローラーが全方向に逃げないため、最もスムーズにコーナーを曲がることができる点にあります。特に連続コーナーやウェーブセクションのような左右に切り返すコーナーを速く走りやすいという特性があります。
また、リジッドバンパーはギミック(可動部分)がないため、部品点数が少なく済み、マシンの重量を抑えられるというメリットもあります。軽量化は加速性能向上にも繋がるため、重要なポイントと言えるでしょう。
一方で、リジッドバンパーの弱点としては、デジタルカーブやロッキングストレートのような横方向に強い衝撃がかかるセクションや、コースの継ぎ目での減速が大きくなる点が挙げられます。特に公認競技会で使用される5レーンコースでは、コース接続部の段差による減速がタイムロスにつながります。
リジッドバンパーは、FRPやカーボンなどの板材を適切な形状に切り出して作ることができます。特にFRPは比較的安価で簡単に製作できるため、ミニ四駆を始めたばかりの初心者の方はまずリジッドバンパーから始めてみることをおすすめします。
なお、リジッドバンパーは基本的にはすべてのシャーシに取り付け可能ですが、シャーシによってはステー取り付け位置の高さが異なるため、調整が必要な場合もあります。初心者でも扱いやすく、セッティングの基準としても重要なバンパー形式です。
スライドダンパーは横方向の衝撃を吸収して減速を抑える

スライドダンパーは、バネの力で横方向にスライドする構造を持ったバンパーです。この横方向へのスライド機能により、コースの壁段差やデジタルカーブでの衝撃を吸収し、減速を最小限に抑えることができます。
独自調査の結果、現在の5レーンコースにおいてはスライドダンパーは「必須パーツ」と言われるほど普及しており、特殊なセクションがある場合を除き、公認競技会ではスライドダンパーを装着するのが定石となっています。スライドダンパーの流行は2012年頃から全国的に広まったようです。
スライドダンパーの最大の特徴は、コースの壁との接触時にバネの力でバンパーがスライドし、その衝撃を吸収することで減速を防ぐ点です。これにより、特に壁との接触が多いコースや、コース接続部の段差が大きいコースで威力を発揮します。
スライドダンパーのセッティングでは、バネの強さやグリスの種類を調整して、スライドの速度やマシンの姿勢を制御します。タミヤからは「ミニ四駆スライドダンパースプリングセット」などが発売されており、バネは全部で4種類あります。バネが弱いと衝撃吸収性能は向上しますが、コーナリング時に深く沈み込み、車体の横方向への動きが大きくなるため、タイヤの横グリップが発生して速度が低下します。
初心者がスライドダンパーを使用する際によくある問題として、スライド可動後にバンパーが元の位置に戻らないことがあります。これは取り付け部分のビスの締めが強すぎることが原因であることが多く、締めを適度に緩めることで改善されます。ただし、緩めすぎるとガタが出るので、バランスが重要です。
スライドダンパーの難点として、バネ受け用のプレートを使用するため、どうしてもローラー位置が高くなりやすい点があります。ローラーが高いと車体が不安定になるため、土台を低くしてローラー位置を下げるなどの工夫が必要になります。
ピボットバンパーはコーナーへのねじ込みが得意な構造
ピボットバンパーは、バンパーの端に支点(ピボット)を作り、そこを中心にローラーステーが後ろ方向に逃げるようにする構造のバンパーです。この独特の動きにより、独自の走行特性を持っています。
独自調査の結果、ピボットバンパーの最大の特徴は、ローラーが後ろに動くことで高速でコーナーギリギリまでジャンプしても衝撃を吸収し、コーナーに入りやすくなる効果があります。いわゆる「ねじ込む」ようにコースに入れることに特化したバンパーで、スピード重視のレーサーがよく使用する傾向があります。
ピボットバンパーは、コーナーへのねじ込みやすさ以外にも、ロッキングセクションでの速さも特徴としています。2018年のジャパンカップではロッキングストレートが使用され、上位入賞マシンのほとんどにピボットバンパーが採用されていました。
また、ピボットバンパーのもう一つのメリットとして、バンパーの支点の下にローラーステーを取り付けることができる点があります。これにより、ローラー位置を下げやすくなり、マシンの安定性向上に寄与します。
現在主流となっている製作方法は、可動部分にローラー用のゴムリングを巻いて固定する方式です。他にも、カーボンを自作してバネ式のピボットにしたり、スライドと併用して「スライドピボット」にする方法もありますが、スライドピボットは稼働箇所が多く、非常に高度な技術を要するため上級者向けと言えます。
ピボットバンパーの難点としては、19mmや17mmのような大径ローラーを使用すると、バンパーが可動した際にタイヤに干渉してしまう問題があります。そのため、多くの場合は小径ローラーしか選択肢がなくなってしまいます。また、ワイドトレッドのタイヤとの相性も悪い傾向があります。
ゴムリングで固定する作り方の場合は、常にテンションがかかっているためゴムが切れやすいという注意点もあります。マシンを長期間使用しない場合でもゴムが切れることがあるため、定期的な点検が必要です。
ATバンパーは上下の可動で復帰性能を高める優れもの
ATバンパー(オートトラックバンパー)は、バンパー自体をバネで支えるように取り付けることで上下に可動する機構を持つバンパーです。この上下方向への可動性が、独特の走行特性をもたらします。
独自調査によると、ATバンパーは近年非常に流行している改造で、従来型の上下可動のないバンパーでは、ジャンプ後にコースフェンスに乗り上げて横転したり、乗り上げ後のコース復帰が間に合わずコースアウトすることが多かった問題を解決します。
ATバンパーの最大の特徴は、バンパー自体が上下に動くことでコースフェンスに乗り上げた際のコース復帰率を向上させる点です。さらに、乗り上げ後の復帰速度も速くなるため、高速化が進んでいる現在の立体ミニ四駆シーンでは必須の改造になりつつあります。
フロントのATバンパーは、基本的にはバネを2点止めにすることで横ブレを防いで設計するのが一般的です。ATバンパーの注意点としては、バネのみでバンパーを支えるため、支える力が弱いとローラーが上を向いてしまいアッパースラスト(上向きの力)になりやすい点が挙げられます。また、軸部分が摩耗しやすいため、こまめにパーツ交換が必要になることもあります。
リア側では「1軸アンカー」と呼ばれる改造もよく使われています。これはバンパー可動軸が中央1点のみで支えられる構造で、可動量を最大限に確保しつつ、部品点数も削減できる合理的な改造です。この1軸アンカーは、現在のミニ四駆シーンで非常に人気のある改造方法の一つです。
ATバンパーの製作には、カーボンやFRPなどの板材、バネ、ビス、ナットなどが必要です。材料選びや加工精度が重要で、特に可動部分の設計には注意が必要です。ATバンパーは提灯(バンパーと連動して上下するローラーステー)と組み合わせることで、より効果的なコース対応力を発揮します。
実際の走行では、ATバンパーは特にジャンプ後の着地や、コースフェンスへの乗り上げから素早く復帰する場面で力を発揮します。これにより、高速走行時のコースアウトリスクを大幅に低減することができます。
アクアティックアームは中央部にローラーを配置した独自設計
アクアティックアーム(アクア)は、一般的なフロントバンパーとは異なり、シャーシの中央部にアームを設置し、そこにローラーを取り付ける独特な設計です。この特殊な構造により、従来のフロントバンパーとは一線を画す走行特性を持っています。
独自調査によると、アクアティックアームの最大の特徴は、フロントバンパーをなくす代わりに、シャーシの中央部にアームを設置してローラーを配置する点です。一見するとこの位置だとコーナーで前輪がコースに当たってしまうのではないかと思われがちですが、実際には当たることなく機能します。
アクアティックアームはピボットではなくスライド機構を持っており、リヤマルチカーボンなどの斜め溝を利用してスライドする構造になっています。この斜め溝を使った巧妙な設計が、アクアティックアームの核心部分です。
アームの製作には、FRPマルチワイドリヤステー(またはカーボン)、FRPワイドプレートセット、ローラー用ゴムリング、各種ローラー、ビス、ロックナットなどが必要です。特に負荷がかかる部分はカーボンを使用すると耐久性が向上します。
アクアティックアームの仕組みとしては、フレキのネジを上に伸ばし、ロックナットで固定することで、標準ギアカバーとの間に適切な傾斜を作り出します。この傾斜によって適度なスラストが付けられますが、アームとギアカバーが干渉するため、一部削り込みが必要になります。
このアームには13mm用のゴムをセットして適切なテンションをかけることで、バランスの取れた可動性を確保します。ゴムの張力調整はアームの性能に直接影響するため、細かな調整が重要です。
アクアティックアームは非常に独創的な設計であり、製作難易度も比較的高いと言えます。しかし、従来のフロントバンパーとは異なる走行感覚を体験できるため、新しい走りを追求するレーサーには魅力的な選択肢となっています。
ミニ四駆フロントバンパーの自作とカスタマイズ
- フロントバンパーの素材選びはカーボンとFRPが主流
- ATバンパーの作り方は提灯連動で走行安定性をアップ
- スライドダンパーの自作ではバネ選びとグリス選びが重要
- シャーシごとのフロントバンパーの取り付け方と注意点
- フロントバンパーのメンテナンス方法でガタつきを防止
- 小径タイヤでもバンクスルーできるブレーキセッティングの秘訣
- まとめ:ミニ四駆フロントバンパーの選び方と改造のポイント
フロントバンパーの素材選びはカーボンとFRPが主流
ミニ四駆のフロントバンパー製作において、素材選びは完成後の性能や耐久性に大きく影響します。現在のミニ四駆シーンでは、カーボンとFRP(ファイバーグラス強化プラスチック)が主流となっています。
独自調査によると、カーボンは強度と軽量性に優れており、剛性が高いため形状変化が少なく、安定したパフォーマンスを発揮します。特に負荷がかかる部分や、精密な動きが求められる可動部分には、カーボン素材が適しています。例えば、アクアティックアームの一部パーツなどは、カーボン製にすることで耐久性が向上します。
一方、FRPはカーボンに比べて若干柔軟性があり、価格も比較的安価です。初心者が最初にバンパーを自作する際は、FRPから始めるケースが多いようです。FRPは加工もしやすく、万が一失敗しても経済的な負担が少ないというメリットがあります。
素材の厚みも重要なファクターです。一般的には1.5mmと3mmの板材が多く使われますが、用途によって適切な厚みが異なります。例えば、ローラーを支えるステー部分には3mm(または1.5mm×2枚の積層)程度の厚みが望ましく、薄すぎるとビスが曲がってしまう可能性があります。
市販品としては、タミヤからHGカーボンフロントワイドステー(1.5mm)やHGカーボンリヤワイドステー(1.5mm)などが発売されており、これらを加工して使用することも可能です。また、ジャパンカップなどの大会に合わせて限定品が発売されることもあり、これらは特殊な穴の配置や形状が特徴となっています。
素材選びでは、予算や技術レベル、求める性能のバランスを考慮することが重要です。初心者の場合は、まずはFRPでの製作に慣れてから、徐々にカーボン素材にステップアップしていくのが一般的なアプローチとなっています。
加工方法としては、ドリルやカッター、ニッパーなどの工具を使用しますが、特にカーボン加工時は粉塵が発生するため、マスクの着用や十分な換気など、安全面への配慮も忘れないようにしましょう。
ATバンパーの作り方は提灯連動で走行安定性をアップ
ATバンパー(オートトラックバンパー)は上下に可動するバンパーですが、これに提灯(ちょうちん)と呼ばれるローラーステーを連動させることで、走行安定性をさらに向上させることができます。ここでは、提灯連動型ATバンパーの作り方を詳しく解説します。
独自調査によると、ATバンパーの基本的な構造は、バンパー基部とそれを支えるバネから成ります。提灯連動型にする場合、バンパーの上下動に合わせて提灯も連動して動くよう設計します。
まず、基部の製作には「カーボンマルチワイドステー」などを使用します。このステーの穴を適切な位置に開け、ハトメなどで補強すると耐久性が向上します。ハトメは表裏があり、差し込む側が表になるよう注意しましょう。ハトメを入れた側が出っ張る形になるため、この部分がローラーステーの動きに影響します。
次に、ピボット部分の製作には「FRPフロントステー」などを使用します。これをカットして形を整え、使用するローラーに合わせて穴を拡張します。例えば13mmローラーを使用する場合は、穴を3.8mm程度まで広げます。急に大きなドリルで穴を開けるとFRPを傷めるため、徐々にサイズを大きくしていく方法が推奨されています。
バンパーの組み上げでは、基部にピボット部分を取り付け、ゴムでテンションをかけます。一般的には19mm用ゴムリングを2重巻きにして2〜3本巻き付けるか、ボールキャップ回しのゴムチューブを切って使用する方法があります。ゴムの幅でテンションを調整でき、幅5mmは柔らかすぎる特殊コース用、10mmは適度な硬さで若干の減速がある設定、15mmは硬めでリジッドに近い特性という目安があります。
提灯連動の仕組みは、ATバンパーが上下動する際に、それに連動して提灯(ローラーステー)も動くようにします。この連動により、バンパーに加わる力を提灯で分散させ、バランスの取れた走行が可能になります。特に重要なのは、提灯の重量がゴムと反対側にかかることで、ゴムの張力と均整が取れ、適切なスラストが得られる点です。
ATバンパーと提灯の連動部分は、シャーシの内側に提灯のアームを伸ばし、ホイールに干渉しないよう設計します。この連動部分の精度によって、バンパーの動きがスムーズかどうかが決まります。
完成したATバンパーは、通常状態ではスラスト0(水平)になり、提灯が上がるとスラストがかかる設計になっています。前側のナットの締め具合でスラストの調整が可能で、閉めるとスラストが付き、緩めるとスラストが減少します。
スライドダンパーの自作ではバネ選びとグリス選びが重要

スライドダンパーは横方向の衝撃を吸収するバンパーですが、自作する際には特にバネとグリスの選択が性能に大きく影響します。ここでは、スライドダンパーの自作におけるポイントを詳しく解説します。
独自調査によると、スライドダンパーのセッティングではバネの強さとグリスの種類を使い分けて、マシンの速度や姿勢を調節するのが基本となります。タミヤからは「ミニ四駆スライドダンパースプリングセット」と「ミニ四駆スライドダンパー2スプリングセット」が発売されており、全部で4種類のバネが用意されています。
バネの選択は、コースの特性やマシンの走行スタイルに合わせて行います。バネが弱いと衝撃吸収性能は良くなりますが、コーナリング時に深く沈み込むため、車体の横方向への動きが大きくなりタイヤの横グリップが発生して速度が落ちます。一方、バネが強すぎると衝撃吸収性能が低下し、壁との接触時の減速が大きくなります。
グリスの選択も重要で、粘度の高いグリスを使うとスライドの動きがゆっくりになり、粘度の低いグリスを使うとスライドが素早くなります。コースの特性やマシンの速度に合わせて、適切なグリスを選ぶことでパフォーマンスを最適化できます。
スライドダンパーを自作する場合、FRPやカーボンのプレートを使用することが多いです。自作の最大のメリットは、自分の好みの形状に製作できることですが、精度良くスムーズに動くよう作るのは難しく、ある程度の経験が必要となります。
スライドダンパーの基本構造は、固定部分と可動部分から成り、その間にバネを配置します。可動部分がスムーズに動くよう、接触面には適切なグリスを塗布します。また、バネの両端がしっかりと固定されるよう、バネ受け部分の設計も重要です。
初心者がスライドダンパー製作で陥りがちな問題として、スライド可動後にバンパーが元の位置に戻らないことがあります。これは取り付け部分の締めが強すぎることが原因であることが多く、締めを適度に緩めることで解決できます。ただし、緩めすぎるとガタが出るので、ガタが出ずにきちんと元の位置に戻るよう、少しずつビスの締めを調節する必要があります。
前後バンパー共にスライドダンパーにする場合、上級者は前後のバネの強さを変えて走行姿勢を調整することもありますが、初心者やスライドを初めて使う方は、まずは前後同じ種類のバネでセッティングを始めることをおすすめします。
シャーシごとのフロントバンパーの取り付け方と注意点
ミニ四駆には様々なシャーシがあり、それぞれフロントバンパーの取り付け方や注意点が異なります。ここでは主要なシャーシごとの特徴を解説します。
S2シャーシ(スーパーII)
独自調査によると、S2シャーシの最大の特徴はフロントステー取付位置の低さです。この低さのため、標準のステーでは25mmタイヤで1mmブレーキを使ってもバンクスルー(バンクコーナーをスムーズに通過すること)が難しい状況があります。
対策として、ステーの付け根を短くし、フロントステー自体をタイヤ側に寄せる方法があります。この場合、シャーシはターンスイッチの手前まで切り取る必要があります。また、上からプレートを出して、そこから下にブレーキプレートを垂らす「つり下げ式」の配置も有効です。
S2シャーシでATバンパーを使用する場合、Aパーツ(シャーシ前部のパーツ)が干渉するため、Aパーツの先端部分とステーの先端部分を削って調整する必要があります。この加工を行うと、Aパーツの固定が弱くなり、走行中にターンスイッチが切れる可能性があるため、Aパーツ抑えを作る必要があります。
MSシャーシ(モーターサイドシャーシ)
MSシャーシはフレキ(フレキシブル)仕様が人気で、フロントユニットの根本が高いためATバンパーのストッパーとして活用できる特徴があります。しかし、フロント・リアともにバンパー基部が低めなので、小径タイヤを使用する場合は底上げが必要です。
MSシャーシの利点は非常に高い走行性能ですが、フレキの駆動知識は他のシャーシには応用が利かないため、一度MSフレキを極めると他のシャーシに戻りづらい傾向があります。また、ギアカバーが折れやすいという欠点もあります。
MAシャーシ(モーターアッパーシャーシ)
MAシャーシはMSと比べるとギアカバーの取り外しが容易で、拡張性が高いという特徴があります。両軸モーターを使用したい場合に特におすすめです。
MAシャーシの注意点として、フロント底部に特殊なテーパー処理があり、バンパーレスのベースプレートがアッパー(上向き)になりやすい点があります。これを解消するには削り込みが必要です。
VZシャーシ
最新シャーシの一つであるVZは、フロントバンパーが高めに取り付けられるため、小径タイヤでも3mmブレーキが無加工で貼れるという大きなメリットがあります。また素の状態でも非常に速く、エアターンも比較的スムーズに回れます。
VZの欠点は、ギアカバーが取れやすい点で、特にプラボディを正規取り付けしない場合は補強が必要です。また、リアステー穴がフロントと比べて低いため、小径タイヤを使用する場合はリアもプレート2枚でブレーキの底上げが必要になることがあります。
ARシャーシ(アンダーギアレブ)
ARシャーシの最大の特徴は、マシンの裏から電池とモーターの両方を交換できる点で、これはレース中の素早いメンテナンスに便利です。GUP(グレードアップパーツ)の適合パーツも豊富で、初心者でもカスタムのバリエーションを楽しめます。
ARの欠点として、フロントが低めなため、23mmタイヤではフロントは1mmブレーキしかバンクスルーできない場合があります。
FM-Aシャーシ(フロントミッドシップAタイプ)
FM-Aシャーシは現代シャーシ唯一のFM(フロントミッドシップ)で、着地姿勢が立体主体のテクニカルコース向きです。不要な部分を切り飛ばすとかなり軽量化できる特徴があります。
FM-Aの注意点として、ボディをかっこよく切るのが難しい点や、タイヤは23mm台前半から使用可能ですが、それ以下だとシャーシの底面が1mmを切ってしまう点があります。最近発売されたアルミギアカバー装備なら、この制限がなくなります。
フロントバンパーのメンテナンス方法でガタつきを防止
ミニ四駆のフロントバンパーは長時間使用していると、様々な問題が生じます。特に可動式バンパーでは、ガタつきや動きの悪化が走行性能に直接影響します。ここでは、バンパーのメンテナンス方法について詳しく解説します。
独自調査の結果、約1年間のレース使用後には、多くの可動式バンパーで以下のような問題が発生することがわかりました:
- ビスで穴が擦れて大きくなる
- バンパーがガタガタと安定しなくなる
- バンパーがスムーズに元の位置に戻らなくなる
- 提灯が上がったままになり、バランスが崩れる
これらの問題に対処するためのメンテナンス方法としては、硬いスペーサー(金属製)を導入する方法が効果的です。具体的な手順は以下の通りです:
まず、カーボンマルチワイドステーの穴を金属スペーサーの大きさに合わせて斜めに削ります。この際、バンパーの動きが硬くなりすぎないよう調整が必要です。提灯を使用している場合は、後ろ側のビスを長くして提灯を取り付けます。
重要なポイントとして、最初から金属スペーサーを入れないほうが良い場合があります。これは、動きが硬くなりすぎるためで、最初は金属スペーサーなしで斜めに削ってビスを付けた方が、走りの調整がしやすいからです。
通常の状態ではスラスト0(水平)を保ち、提灯が上がった時にのみスラストがかかるよう設計するのが基本です。前側のナットの締め具合でスラストの調整ができ、閉めるとスラストが付き、緩めるとスラスト0に近づきます。
カーボンマルチワイドステーのビス穴の形状も重要です。従来のステーはビス穴が長丸だったため、走行中に穴が徐々に大きくなりガタつきの原因となっていました。しかし、2019年ジャパンカップのHGカーボンマルチワイドステーは前部分のビス穴が丸形状になっており、穴が大きくなりにくい設計になっています。
バンパーの調整では、横から見てローラーのスタビライザーの上部を指で押し、アッパースラストから0スラになるまでロックナットを締めて調整します。指を離すと元に戻るよう、ドリルで斜めに削る部分を調整することで、柔らかさを調整できます。この部分が硬すぎると、コースの壁から離れてもスラストがかからない状態になります。
シャーシとバンパーの間に隙間がないように調整することも重要です。カーボンは土台としっかりナットで固定されないため、シャーシとの隙間がないようにしないとガタガタになってしまいます。
メンテナンスを適切に行うことで、バンパーの動きがスムーズになり、特にレーンチェンジ(LC)の左コーナーから右コーナーに入る際に一瞬でスラストがかかり、LCに沿って走るようになります。
小径タイヤでもバンクスルーできるブレーキセッティングの秘訣
ミニ四駆で小径タイヤを使用する際、バンクコーナーをスムーズに通過する(バンクスルー)ためのブレーキセッティングは非常に重要です。特にS2シャーシのような構造上の制約がある場合、工夫が必要になります。
独自調査の結果、小径タイヤでバンクスルーを実現するには、主に以下の方法があることがわかりました:
1. ブレーキプレートの高さ調整
S2シャーシなどでは、シャーシ底面からブレーキプレートを出すと、25mm以下のタイヤでは1mmブレーキでもバンクスルーできなくなる問題があります。この場合、ブレーキプレートを上から吊り下げるように配置する方法が効果的です。
具体的には、上からプレートを出して、そこから下にブレーキプレートをたれ下げるように配置します。このとき、ブレーキプレートが前に傾かないよう、スラストプレートを仕込んでブレーキプレートがアッパー(上向き)になるように調整します。
2. リヤマルチカーボンの活用
ブレーキプレートの製作には、リヤマルチカーボンを二つ使って作る方法があります。この際、下側のブレーキは作らなくても運用可能ですが、上り1着のスロープでも止まれるほどのブレーキ力が必要な場合は、下側にもブレーキを設置すると良いでしょう。
この方法の重要なポイントは、カーボンのアーム部分(本来シャーシ底面の取付穴につける部分)を思い切って切り取ることです。ただし、この加工はシャーシとの現物合わせになるため、他の人の形状はあくまで参考程度にとどめておくべきです。
3. 角度付けプレートの導入
ブレーキが前下がりになってしまう問題を解決するために、角度付けプレートを使用する方法があります。これはリジットマシン用のスラストプレートを流用することもでき、直カーボンを斜めに削り込んで作成します。
このプレートをブレーキプレートとAT基部の間に挟むことで、適切な角度を付けることができます。さらに、ゴムリングが通るための隙間を確保するため、お宝ワッシャーと大ワッシャーを挟むという工夫も効果的です。
4. ブレーキプレートの底上げ
S2シャーシのフロントは、プレート基部の穴からスラストがついているため、適切な角度をつけないとブレーキが前下がりになってしまいます。独自調査によると、普通のプレートよりも約1.5mm底上げされた位置にブレーキプレート最下段を配置し、さらに1.5mm上に通常のブレーキ貼り位置を設定することで、合計で3mmのブレーキの底上げが可能になります。
これにより、25mmでギリギリだったバンクスルーが、1mmブレーキならどんなタイヤ径でも可能になります。つまり、小径タイヤでもレースに出られるようになるわけです。
5. シャーシ加工の注意点
S2シャーシのような特殊な構造のシャーシでは、Aパーツが干渉するため、カーボン側やAパーツ側を削る必要があります。ただし、カーボンのほうが高価なので、なるべくAパーツ側を削ることが推奨されます。ただし、その分保持力が落ちるため、Aパーツ抑えを作成しておくことが重要です。これがないと走行中にスイッチが切れてしまう可能性があります。
これらの工夫により、小径タイヤを使用していても、適切なブレーキセッティングでバンクスルーを実現することが可能になります。
まとめ:ミニ四駆フロントバンパーの選び方と改造のポイント
最後に記事のポイントをまとめます。
ミニ四駆フロントバンパーについて、以下の重要ポイントをおさえておきましょう:
- フロントバンパーはミニ四駆の走行性能を左右する重要パーツである
- リジッドバンパーは連続コーナーやウェーブセクションに強いが横方向の衝撃に弱い
- スライドダンパーはコースの壁段差での減速を抑える効果があり、5レーンコースではほぼ必須
- ピボットバンパーはコーナーへのねじ込みやロッキングセクションで威力を発揮する
- ATバンパーは上下に可動してコースフェンスからの復帰率を高める最新トレンド
- アクアティックアームはシャーシ中央部にローラーを配置する独創的な設計
- フロントバンパーの素材はカーボンかFRPが主流で、用途によって厚みを選ぶ
- ATバンパーと提灯の連動で走行安定性が向上し、特にジャンプ後の着地時に効果的
- スライドダンパーのセッティングではバネとグリスの選択が重要なポイント
- シャーシごとにフロントバンパーの取り付け方や注意点が異なる
- 定期的なバンパーのメンテナンスでガタつきを防止し、走行性能を維持できる
- 小径タイヤでバンクスルーするにはブレーキプレートの位置や角度調整が必要
- S2シャーシの場合、ブレーキプレートを上から吊り下げる構造が有効
- フロントバンパーの改造は走行特性を大きく変えるため、自分のマシンや走りに合ったものを選ぶことが重要