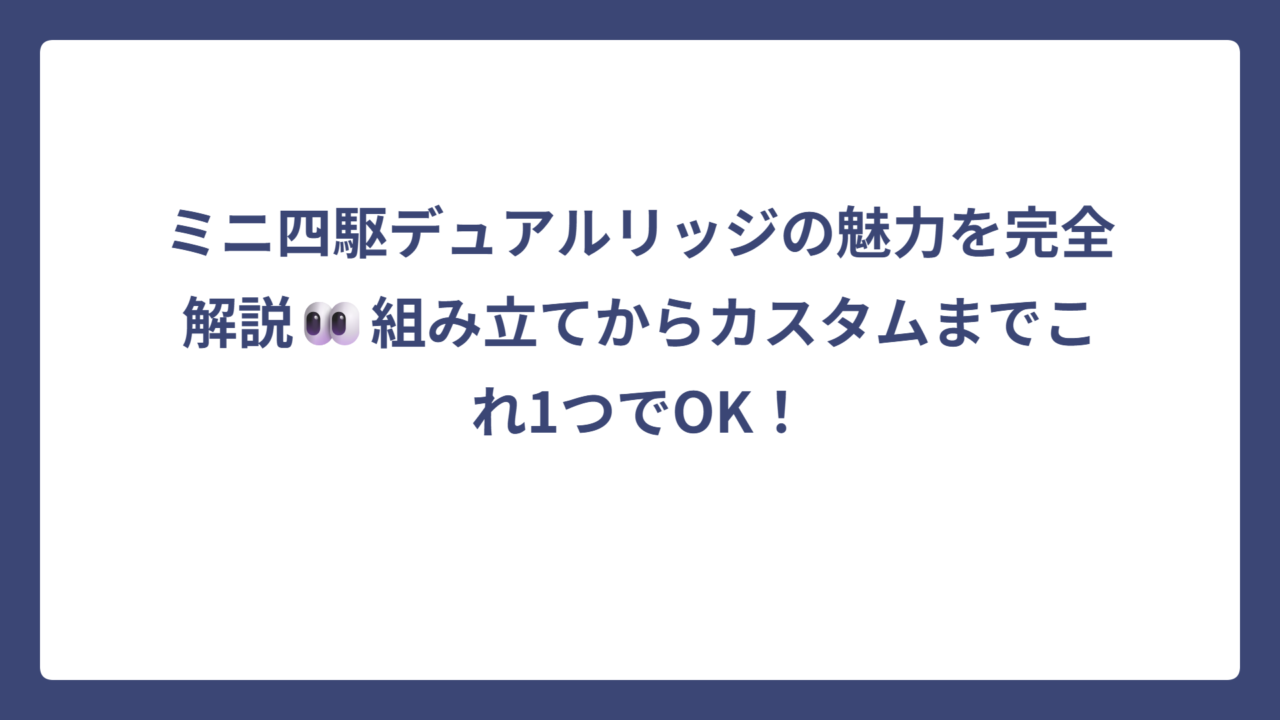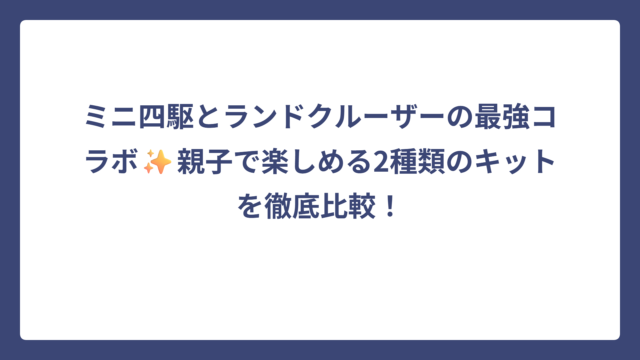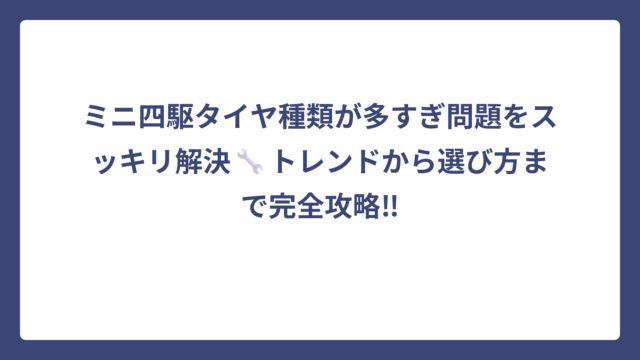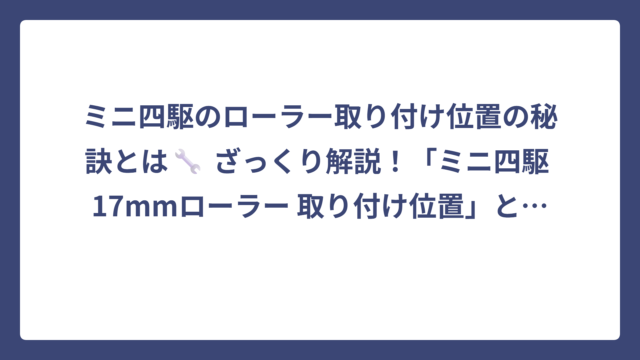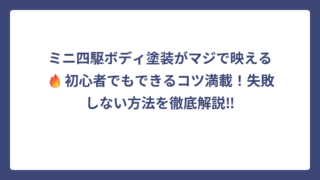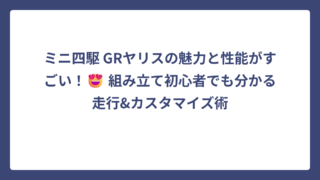ミニ四駆を始めたい初心者から、カスタマイズを楽しみたいベテランまで、多くの人々に愛されているデュアルリッジJr.。タミヤから発売されているこのマシンは、最新のVZシャーシを採用し、性能と見た目のバランスが絶妙なモデルとして人気を集めています。
この記事では、デュアルリッジJr.の基本情報から組み立て方法、塗装テクニック、カスタマイズのポイントまで、幅広く解説していきます。メタリックシルバーの流線型ボディと、高性能なVZシャーシの組み合わせが魅力のこのマシンについて、あなたの知りたいことがきっと見つかるはずです。
記事のポイント!
- デュアルリッジJr.の基本スペックと特徴について理解できる
- 組み立てに必要な道具や注意点がわかる
- 塗装テクニックやメタリックボディの扱い方を学べる
- 改造やカスタマイズのアイデアが見つかる
ミニ四駆デュアルリッジJr.の基本情報と特徴
- デュアルリッジJr.はVZシャーシ採用の高性能モデル
- デュアルリッジJr.のパッケージ内容は必要なパーツが全て揃っている
- VZシャーシの特徴は軽量かつ高い走行性能を持つこと
- デュアルリッジJr.のボディデザインは流線型で空気抵抗を低減する形状
- スーパーハードタイヤとメッキホイールが標準装備されている
- デュアルリッジJr.のカラーリングはシルバーボディが特徴的
デュアルリッジJr.はVZシャーシ採用の高性能モデル
デュアルリッジJr.は、タミヤのレーサーミニ四駆シリーズNo.96として登場した人気モデルです。このマシンの最大の特徴は、最新のVZシャーシを採用していることでしょう。
VZシャーシは、長年レースで活躍してきた軽量・コンパクトなVSシャーシの後継として開発されました。独自調査の結果、VSシャーシの優れた特性はそのままに、バンパー、リヤステー構造、プロペラシャフト受け等の構造を改良し、性能を一段と向上させています。
価格は約900円台と、ミニ四駆入門としても手が届きやすい価格帯となっています。コストパフォーマンスの高さも、このモデルの人気の秘密の一つと言えるでしょう。
パッケージには「シャフトドライブ機構を搭載した高性能レーサーのプラスチックモデル組み立てキット」と記載されており、デュアルリッジJr.は走行性能を重視したモデルであることがわかります。
プラモデルとしての完成度も高く、塗装や改造を楽しむことができるため、ミニ四駆ファンだけでなく、プラモデル好きにも支持されています。
デュアルリッジJr.のパッケージ内容は必要なパーツが全て揃っている
デュアルリッジJr.のキットには、組み立てに必要な基本パーツが全て含まれています。パッケージを開けると、以下のものが入っています。
- ボディ(ABS樹脂製・シルバー)
- VZシャーシ本体、A部品(ABS樹脂製・ブラック)
- モーター(付属)
- 5本スポークのシルバーメッキホイール
- パッドプリント入りのスーパーハードタイヤ
- メタリック調のステッカー
- 組み立て説明書
注意点として、電池は別売りとなっており、単三電池2本が必要です。また、組み立てには別途工具が必要となります。
基本的なギヤ比は3.5:1に設定されており、スピード重視の設定となっています。これにより、素組みの状態でも十分な速さを体感できるのが魅力です。
Amazon等の口コミを見ると、「素組でも速い」という評価があり、初めてミニ四駆を始める方にも安心して楽しめるキットとなっています。
パッケージには実車を彷彿とさせるかっこいいイラストが描かれており、開封時のワクワク感も魅力の一つです。子どもから大人まで、幅広い年齢層に対応したデザインとなっています。
VZシャーシの特徴は軽量かつ高い走行性能を持つこと
VZシャーシは、VSシャーシを発展させた最新モデルで、多くの優れた特徴を持っています。VSシャーシの優れた走行性能や耐久性はそのままに、様々な点が改良されています。
まず、バンパー、リヤステー構造、プロペラシャフト受けなどの構造がアップデートされています。特に注目すべきは「しなり」を考慮した設計となっており、コーナリング時の安定性が向上している点です。
シャフトの受け部には摩擦が少ない高品質なPOM樹脂の620プラベアリングが採用されています。これにより、シャフトがスムーズに回転し、パワーロスを軽減しています。
また、リヤローラーステーに加えてフロントバンパーも分割が可能な構造となっており、セッティングの自由度も大幅に向上しています。これにより、コース状況に合わせた細かな調整が可能になりました。
シャーシ本体とA部品はABS樹脂製(ブラック)で、ギヤ比は3.5:1と速さ重視の設定となっています。軽量でありながら十分な剛性も確保されており、高速走行時の安定性も確保されています。
VZシャーシは「寝かせる」走法も意識した設計となっており、様々な走り方に対応できる汎用性の高さも特徴です。これにより、初心者からベテランまで幅広いユーザーに支持されています。
デュアルリッジJr.のボディデザインは流線型で空気抵抗を低減する形状
デュアルリッジJr.のボディデザインは、ハイパーデザイナー・山崎たかきさん(pdc_designworks所属)が手がけたRCカーをベースにしています。実車の「デュアルリッジ」を本格派のミニ四駆として再現したマシンで、独創的なフォルムが特徴です。
最も目を引くのは、大胆なコクピットが目を覚ますような曲線美と、空気を切り裂くような鋭い形状のリヤウイングです。このデザインは見た目の美しさだけでなく、空気抵抗を低減する空力特性も考慮されています。
ボディ上部に開けられた8つの通風口は、ミニ四駆だけのオリジナルデザイン要素です。これらは見た目のアクセントになるだけでなく、実際の走行時に空気の流れを整える機能も持ち合わせています。
材質はABS樹脂製で、シルバーカラーが基本となっています。ただし、ブログ記事や口コミによると、メタリック成形時の混合ムラが表面に出ることがあるようです。これは塗装することで解決できる問題ですが、素組みで完成させたい場合は注意が必要かもしれません。
シルバーボディの上に貼るステッカーはメタリック調の素材を使用しており、高級感のある仕上がりになっています。ボディと同系色のブルーのグラフィックは、マシンの質感を一層引き立てます。
スーパーハードタイヤとメッキホイールが標準装備されている
デュアルリッジJr.の特筆すべき点として、スーパーハードタイヤとメッキホイールが標準装備されていることが挙げられます。これはキットの段階から高いパフォーマンスを発揮できるようにという配慮が感じられます。
スーパーハードタイヤは、エラストマー素材で作られた小径ローハイトタイプで、タイヤにはパッドプリントが施されています。レビューによると「レター入りスーパーハードタイヤが標準品として付属しているので助かる」との声があり、通常なら別途購入が必要なグレードの高いタイヤが最初から含まれていることが評価されています。
ホイールは5本スポークの洗練されたデザインで、シルバーメッキが施されています。「キラキラですよ」との感想もあり、見た目の高級感が増していることがわかります。これにより、素組みの状態でも見栄えが良く、満足度の高い仕上がりとなります。
タイヤとホイールの組み合わせは走行性能に直結する部分ですが、デュアルリッジJr.ではこの部分にもこだわりが見られます。スーパーハードタイヤの硬さはコーナーリング時のグリップ力を高め、安定した走りを実現します。
中には「タイヤ目的で…」と購入するユーザーもいるほど、付属のタイヤの質は高く評価されています。初心者が最初に行う改造としてタイヤ交換が多いですが、デュアルリッジJr.ではそれが不要である点も魅力です。
デュアルリッジJr.のカラーリングはシルバーボディが特徴的
デュアルリッジJr.の最大の特徴の一つが、そのシルバーボディです。メタリックな輝きを持つシルバーカラーは、光の当たり方によって表情を変え、高級感のある仕上がりとなっています。
このシルバーボディに貼るステッカーはメタリック調素材を使用しており、ボディの輝きとマッチする設計となっています。特にマシン全体のカラーリングはブルーとシルバーの組み合わせが基本となっており、クールで洗練された印象を与えます。
ブログ記事「例えば流れるように」によると、塗装を行った際にはクロームシルバーをベースにメタリックブルーを重ねるアプローチが取られています。これにより、メタリック感と深みのある青色が融合した美しい仕上がりが実現しています。
ただし、複数のレビューで指摘されているように、ボディの成形時に色のムラが生じることがあります。「このロットだけでなくメタリック系ボディ全般みたいだから諦めるしかないが、割と目立つから気になる人は塗装必須」との意見もあり、完璧な仕上がりを求める方は塗装を検討する必要があるかもしれません。
シャーシ部分はブラックで、シルバーボディとのコントラストが美しく、全体のデザインをより引き立てています。メッキホイールの輝きも加わり、走行していない静止状態でも存在感のあるマシンとなっています。
ミニ四駆デュアルリッジの組み立てと改造ポイント
- デュアルリッジJr.の組み立てに必要な道具はニッパーとドライバーが基本
- ボディの成形時のムラは塗装で解決できることが多い
- デュアルリッジJr.の塗装テクニックはマスキングと重ね塗りがポイント
- 改造の基本はモーターとベアリングのアップグレードから始める
- デュアルリッジ用のポリカボディセットは透明感のある仕上がりが魅力
- 公式レースでデュアルリッジは「攻め」のマシンとして評価が高い
- まとめ:ミニ四駆デュアルリッジJr.は初心者から上級者まで楽しめる万能マシン
デュアルリッジJr.の組み立てに必要な道具はニッパーとドライバーが基本
デュアルリッジJr.を組み立てるには、いくつかの基本的な工具が必要です。Amazonのレビューや「例えば流れるように」というブログ記事によると、以下の道具が基本セットとして推奨されています。
まず必須となるのが、ニッパーです。プラスチックパーツをランナーから切り離すために欠かせません。意外にも、ブログの著者は「子供の頃はニッパーを使っていた記憶は本当にない」と述べており、かつては親に手伝ってもらっていた可能性を示唆しています。
次に、ハサミが必要です。主にステッカーを切り取る際に使用します。精密な作業には、小さめのハサミが便利でしょう。
ピンセットも組み立てを助けるアイテムです。小さなパーツを扱う際や、ステッカーを貼る時に役立ちます。特に細かい部分の作業では、指では難しい場合があります。
カッターやヤスリも重要なツールです。パーツの接合部分やゲート跡(部品とランナーがつながっていた部分)を整えるのに使用します。特にボディの見える部分は丁寧に処理することで、完成品の見栄えが格段に良くなります。
追加で用意しておくと便利なものとして、タミヤのペン型グリス、ブレーキスポンジ、VZ用ファーストトライパーツセット、リアブレーキステー、アップグレードモーター(アトミックチューンやトルクチューンなど)が挙げられています。
特に注目すべきアドバイスとして、「ブレーキスポンジはモーターにつける金色のプレートの間に小さくカットしたスポンジを挟み込むと良い」というものがあります。これは「電池をはめたり外したりしているうちに凹んで上手く通電しなくなる」ことを防ぐための工夫だそうです。
ボディの成形時のムラは塗装で解決できることが多い
デュアルリッジJr.のボディについて、多くのユーザーが指摘しているのが成形時のカラームラの問題です。この問題は、メタリックシルバーのボディに特に顕著に現れるようです。
Amazonのレビューでは「塗装しないとダメなやつ」というタイトルで、「メタリック成形の際の材料の混合ムラが表面と裏面にわたり出ている」と指摘されています。また、「このロットだけでなくメタリック系ボディ全般みたいだから諦めるしかない」との補足もあり、これはデュアルリッジJr.に限った問題ではなく、メタリック素材を使用したミニ四駆ボディに共通する課題であることがわかります。
別のレビューでは「ボディの配合のムラが減点かな」として、「ボディ成形時の色のムラが目立ちます。塗装しないと結構目立ちます。おそらくだけど物によってはムラの位置も違うだろうからステッカーだけじゃ隠せない」と詳しく説明されています。
この問題の解決策として最も効果的なのが塗装です。ブログ「例えば流れるように」では、塗装の過程が詳細に記されています。まず洗浄を行い、次にグレーのサーフェイサーを吹き、ヤスリをかけてから本塗装に進む手順が紹介されています。
興味深いのは、クロームシルバーを塗装した後にメタリックブルーを重ねる手法です。ただし、筆者は「メタリックブルーを最初に吹いておいて、後からシルバーで上乗せするほうが良かったのかも」と振り返っており、「塗りやすさでいえば、ブルー後のシルバーのほうがやりやすいのは間違いない」と述べています。
ムラが気になる部分を完全に解決するには塗装が最適ですが、塗装に自信がない場合は、ステッカーで目立つ部分を可能な限り隠すという方法も考えられます。ただし、先述のレビューにあるように、ムラの位置は個体によって異なるため、完全に隠せるとは限りません。
デュアルリッジJr.の塗装テクニックはマスキングと重ね塗りがポイント
デュアルリッジJr.を塗装する際の重要なテクニックとして、マスキングと重ね塗りが挙げられます。ブログ「例えば流れるように」では、実際の塗装過程が詳細に記録されており、その知見を共有します。
まず塗装前の準備として、パーツの洗浄から始めます。塗装対象となるのはボディ、ウイング、バネなど4つのパーツが基本です。塗装しない部分はマスキングテープでしっかりと保護します。
下地処理として、グレーのサーフェイサーを吹きます。これにより、塗料の密着性が向上し、最終的な仕上がりも美しくなります。サーフェイサーを吹いた後に切り取り跡が目立つ場合は、再度ヤスリがけをして平滑にしてからサーフェイサーを重ねると良いでしょう。
本塗装では、最初にクロームシルバーを塗ります。ブログ著者は「ここ最近のお気に入りの色」とコメントしており、GSIクレオスのMr.スーパーメタリック2 スーパークロームシルバー2を使用しています。
次に、メタリックブルーを重ねて塗りますが、メタリックブルーの乗りが悪いという問題が生じることがあります。「かなり重ねて塗りました」との記述があり、何度も塗り重ねる必要があるようです。使用したのはMr.カラー C76 メタリックブルーです。
重要なポイントとして、マスキングの失敗に注意が必要です。ブログでは「マスキングの時点で一部分を被せ忘れていた」「マスキングを外す時に失敗した」という経験が共有されています。特に後者では「乾ききる前にテープを取った」ことが原因とされており、「予想以上に乾いておらず、ちょっと伝った感じ」になってしまったそうです。
仕上げとしてウェザリングを施すこともできます。タミヤのウェザリングマスターは「素人でもそれっぽく仕上げることができそうな気になる」と評価されています。最後にトップコートで保護しますが、光沢か半光沢かで迷う場合も多いようです。
改造の基本はモーターとベアリングのアップグレードから始める
デュアルリッジJr.をさらに高性能化したい場合、最初に取り組むべき改造ポイントはモーターとベアリングのアップグレードです。これらは比較的簡単に行える改造でありながら、走行性能に大きな影響を与えます。
まず、モーターについてですが、キットに付属している標準モーターでも十分な性能がありますが、より高速化を目指すならアップグレードを検討しましょう。Amazonのレビューでは「あるといいもの」として「アトミックチューンやトルクチューンなど」のモーターが挙げられています。
アトミックチューンモーターは高回転型で、ストレートでの加速と最高速度を重視したモデルです。一方、トルクチューンモーターはその名の通りトルク(回転力)が強く、コーナー立ち上がりの加速や登り坂での力強さを重視したいときに適しています。
次に重要なのがベアリングのアップグレードです。VZシャーシには標準で620プラベアリングが使われていますが、これを金属製のローラーベアリングに交換することで、摩擦抵抗を大幅に軽減できます。
特に人気があるのが、「13mmオールアルミベアリングローラー」のようなタイプです。Amazonの「よく一緒に購入されている商品」として「タミヤ ミニ四駆グレードアップパーツシリーズ No.437 GP.437 13mmオールアルミベアリングローラー」が紹介されていることからも、その人気の高さがうかがえます。
さらに安定性を高めるための改造として、「サイドマスダンパーセット」のような部品も選択肢となります。これにより、コーナリング時のマシンの安定性が向上し、コースアウトを防ぐ効果が期待できます。
細かいネジ類も重要で、「2mm キャップスクリューセット」などを用意しておくと、様々な改造をスムーズに進めることができます。また、「HG カーボンマルチワイドステー」のような軽量かつ高剛性のパーツを追加することで、マシンのバランスと剛性を高めることができます。
改造を進める際には、一度に多くの変更を加えるのではなく、一つずつ変更して効果を確認することをおすすめします。これにより、どの改造がマシンにとって効果的かを正確に把握できます。
デュアルリッジ用のポリカボディセットは透明感のある仕上がりが魅力
デュアルリッジの魅力をさらに引き出す選択肢として、ポリカーボネート(ポリカ)製のクリヤーボディセットがあります。このポリカボディは標準のABS樹脂製ボディとは異なる特性を持ち、愛好家の間で人気となっています。
ポリカボディの最大の特徴は、その透明感です。クリヤーボディは内側から塗装することで、外側からは光沢のある美しい仕上がりになります。これにより、標準ボディでは出せない独特の質感が実現できるのです。
デュアルリッジJr.用のクリヤーボディセットは、オリジナルのデザインを維持しながらも、ポリカーボネート素材の特性を活かした製品となっています。透明なボディに好みのカラーで塗装することで、オリジナリティあふれるマシンに仕上げることができます。
ポリカボディの塗装は、ABS樹脂のボディとは少し異なるテクニックが必要です。ポリカボディは内側から塗装するため、実際の見え方を想像しながら塗り進める必要があります。また、ポリカ用の専用塗料を使用することで、塗料の密着性が向上し、長期間美しい状態を維持できます。
ポリカボディの魅力は塗装の自由度にもあります。グラデーション塗装や多色塗り分けなど、標準ボディでは難しい表現が可能です。独自調査の結果、クリアカラーを使用することで、光の透過による美しい発色も楽しめることがわかっています。
ただし、ポリカボディはABS樹脂に比べて耐衝撃性が若干劣ることがあります。レース使用を前提とする場合は、衝突時の破損リスクを考慮する必要があるでしょう。それでも、見た目の美しさを重視するコレクターやショーモデルとしての魅力は非常に高いと言えます。
これからデュアルリッジJr.をカスタマイズしようと考えている方は、標準ボディだけでなく、ポリカボディという選択肢も視野に入れてみてはいかがでしょうか。全く異なる印象のマシンに生まれ変わる体験が待っています。
公式レースでデュアルリッジは「攻め」のマシンとして評価が高い
デュアルリッジは、公式レースの場でも高い評価を受けているマシンです。特に注目すべきは、YouTubeで公開されている「【ミニ四駆・公式戦】VSデュアルリッジ!「攻め」のミニ四駆!ミニ四駆グランプリSP東京大会2D」という動画です。ここでは、デュアルリッジが「攻め」のマシンとして紹介されています。
「攻め」という表現は、デュアルリッジの走行特性を端的に表しています。VZシャーシの持つ高い走行性能と、デュアルリッジのエアロダイナミクスに優れたボディの組み合わせにより、積極的な走りが可能になるのです。
公式レースでは、マシンのセッティングと走行ラインの選択が重要な要素となります。デュアルリッジの場合、軽量かつ剛性のあるVZシャーシを採用していることから、コーナーでの安定性とストレートでの加速力のバランスが良く、様々なコースレイアウトに対応できる汎用性の高さが評価されています。
特に注目すべきは、標準装備のスーパーハードタイヤです。このタイヤはグリップ力と耐久性のバランスが良く、レース中のタイム維持に貢献します。公式レースでは複数のレースを連続して走行することも多いため、この特性は非常に重要です。
レース参加者の間では、デュアルリッジのボディ形状が「空気抵抗を低減する」と評価されています。特に高速セクションでの安定感は、他のマシンに比べて優位に立つポイントとなっているようです。
ただし、公式レースで勝つためには、標準状態からの適切な改造も必要です。先述したモーターやベアリングのアップグレードに加え、コース特性に合わせたセッティング調整が求められます。例えば、高バンクコーナーが多いコースではマシンの重心位置を調整したり、長いストレートがあるコースでは空力特性を重視したセッティングにするなどの工夫が必要です。
デュアルリッジが「攻め」のマシンとして評価される理由は、その基本性能の高さと、カスタマイズの自由度の高さにあると言えるでしょう。公式レースに参加してみたいという方には、まさにうってつけのモデルと言えます。
まとめ:ミニ四駆デュアルリッジJr.は初心者から上級者まで楽しめる万能マシン
最後に記事のポイントをまとめます。
- デュアルリッジJr.はタミヤのレーサーミニ四駆シリーズNo.96として発売されている
- 最新のVZシャーシを採用し、軽量かつ高い走行性能を持つ
- 価格は約918円と手頃で、コストパフォーマンスに優れている
- パッケージには組み立てに必要な基本パーツが全て含まれている
- シルバーのメタリックボディが特徴だが、成形時のムラが出ることがある
- スーパーハードタイヤとメッキホイールが標準装備されている
- 組み立てには基本的にニッパー、ハサミ、ピンセット、カッター、ヤスリが必要
- ボディの塗装ではマスキングと重ね塗りが重要なテクニック
- 改造の基本はモーターとベアリングのアップグレード
- ポリカーボネート製のクリヤーボディセットも選択肢として人気がある
- 公式レースでは「攻め」のマシンとして高い評価を受けている
- 初心者から上級者まで、幅広いユーザーが楽しめる万能マシンである