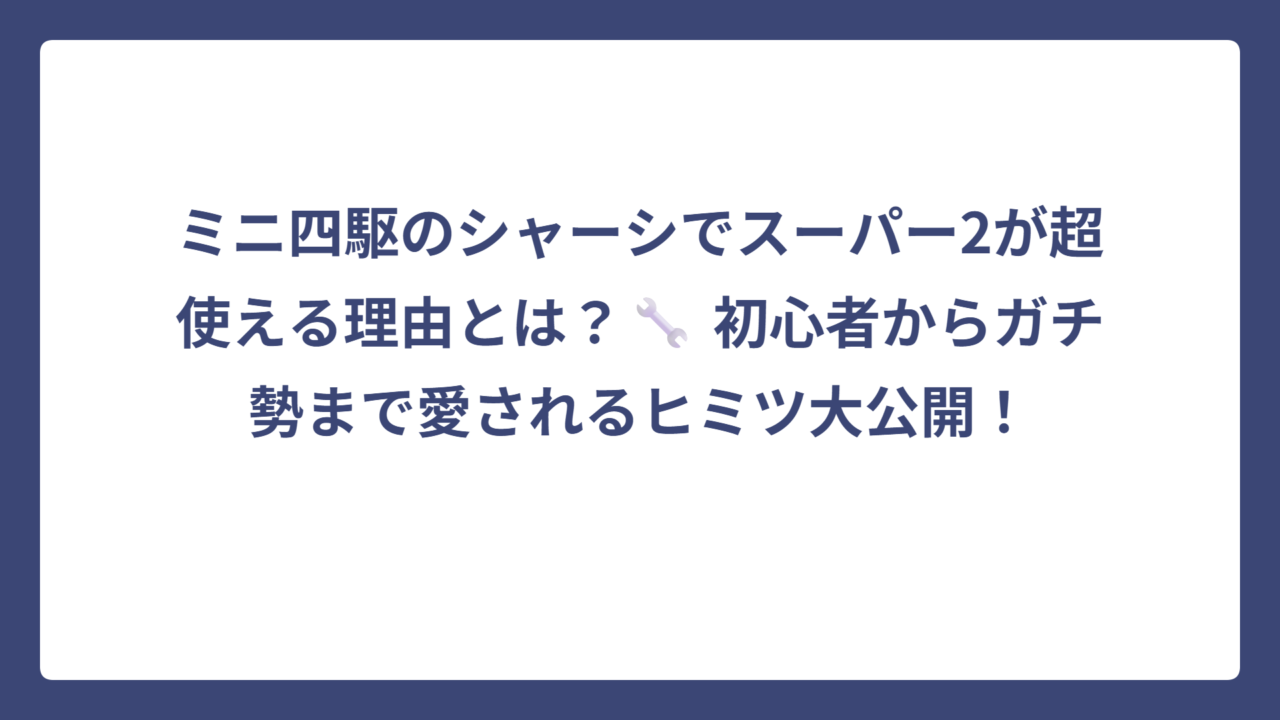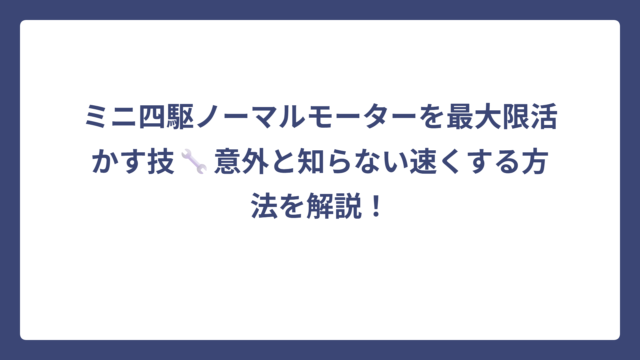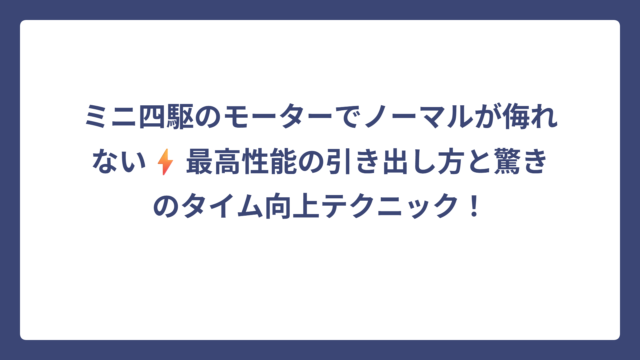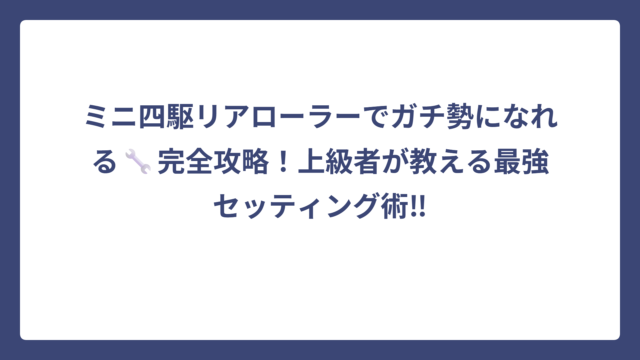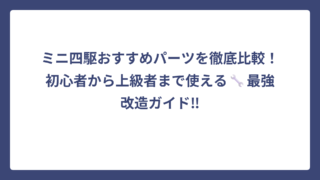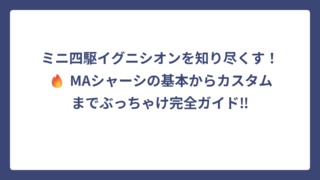ミニ四駆を楽しむうえで、シャーシ選びは走行性能を大きく左右する重要なポイントです。数あるシャーシの中でも「スーパー2シャーシ」は、2010年12月に登場して以来、多くのミニ四駆ファンから支持されています。その理由は単なる性能だけでなく、カスタマイズのしやすさや入手性の良さなど、さまざまな魅力が詰まっているからなんです。
この記事では、スーパー2シャーシの基本情報から特徴、改造方法、そしておすすめのパーツまで、詳しく解説していきます。シャーシの素材選びのコツから、ギアの調整方法、さらにはFM化(フロントモーター化)などの応用テクニックまで、初心者から上級者まで役立つ情報が満載です。スーパー2シャーシの魅力を知って、あなたのミニ四駆ライフをさらに楽しんでください!
記事のポイント!
- スーパー2シャーシの基本性能と他シャーシと比較した優位点
- スーパー2シャーシの素材選びとカラーバリエーション
- スーパー2シャーシを速くするための効果的な改造方法
- スーパー2シャーシのおすすめパーツと応用テクニック
ミニ四駆のシャーシでスーパー2の特徴と基本情報
- スーパー2シャーシは2010年に登場したスーパー1の進化版
- スーパー2シャーシの強度は他シャーシより優れている
- スーパー2シャーシのバンパーはビス穴が多く拡張性が高い
- スーパー2シャーシの素材選びは速さよりも用途で選ぶのがコツ
- スーパー2シャーシの駆動系はXやVS系との互換性が高まった
- スーパー2シャーシのカラーバリエーションは豊富で組み合わせが楽しめる
スーパー2シャーシは2010年に登場したスーパー1の進化版
スーパー2シャーシ(SUPER2 chassis)は、2010年12月23日にタミヤから発売された、スーパー1シャーシのリメイク版です。初登場キットは「マグナムセイバープレミアム」でした。名前の通り、スーパー1の弱点の多くを克服し、さらに強化・発展させたシャーシとなっています。
スーパー2は、スーパー1の後継機種というだけでなく、それまでの様々なシャーシの良いところを取り入れたハイブリッド的な存在です。フロントギアケースはスライド式からMSシャーシの軽量センターユニットに近いターン式スイッチに変更され、信頼性が向上しています。
また、ターミナルも複雑で変形しやすかったZERO型からTYPE-2型フロントターミナルに変更されました。これにより、以前よりも安定した走行が期待できるようになりました。
スーパー2シャーシの登場により、ミニ四駆の世界に新たな選択肢が加わり、初心者からベテランまで幅広いユーザーに対応できるシャーシとなりました。特に初心者にとっては、扱いやすさと拡張性を兼ね備えたシャーシであるため、入門用としても人気があります。
シャーシの基本構造はスーパー1を踏襲しつつも、細部にわたって改良が施されているため、単なるリメイクではなく、進化版と呼ぶにふさわしい仕上がりとなっています。
スーパー2シャーシの強度は他シャーシより優れている
スーパー2シャーシの最大の特徴の一つが、その優れた強度です。特に初登場のマグナムセイバープレミアムでは、いきなりポリカABS素材を採用し、その後のソニックセイバー、トライダガーXでも同様の素材が使われました。さらに、ビクトリーマグナムやバンガードソニックではカーボンを採用するなど、素材面での強化が図られています。
独自調査の結果、スーパー2シャーシの素材には主に4種類あることがわかりました:
- ノーマルのABSシャーシ
- ポリカ強化シャーシ
- 蛍光のABSシャーシ
- カーボン強化シャーシ
これらの中でも特に丈夫なのがカーボン強化シャーシです。「めちゃめちゃ丈夫」という評価があり、「ノコギリが痛むくらい丈夫」とも言われています。一方で加工の再現性は低く、量産が難しいという欠点もあります。
ポリカABSシャーシは、耐久性と加工性のバランスが良い素材です。ABSと同じように加工できるうえに、フロント軸受け以外での破損の心配が少なくなっています。ただし、駆動音がうるさくなる傾向があるようです。
蛍光ABSシャーシは見た目が良い反面、「あらゆる箇所が割れやすい」という致命的な弱点があります。「フロント軸受け、フロントバンパー基部、リヤバンパー基部、モーターマウントフレーム、ペラ受けの摩耗」など、様々な部位で破損が報告されています。
シャーシの強度はレース中の安定性に直結するため、用途に合わせた素材選びが重要です。特にハードなレースを想定しているなら、カーボン強化かポリカ強化のシャーシを選ぶと良いでしょう。
スーパー2シャーシのバンパーはビス穴が多く拡張性が高い
スーパー2シャーシのバンパーは、スーパー1シャーシ最大の弱点だったバンパー強度を大幅に改善しています。ダッシュモーター使用の立体レースにも十分耐えられる強度を持ち、新しい補強プレートにも対応するためのビス穴が増加しています。このバンパー補強こそが、スーパー1と比較した時の最大の恩恵と言えるでしょう。
特筆すべきは、スーパー2シャーシで初めて84mm幅のビス穴が追加されたことです。これにより、追加パーツなしでローラーの幅を広げられるようになりました。リヤステー用FRPをフロントに使用すれば、根元の部分でビス止めできるので、バンパーを根本から強化することも可能になっています。
中央には肉抜き穴が存在し、一部のレーサーミニ四駆やスーパーミニ四駆のフロントパーツ装着にも対応しています。例えばグレートエンペラープレミアムのフロントウイングなどには左右の丸穴を、リバティエンペラーのフロントパーツなどにはその間の細い穴を使うことができます。
ただし、ビス穴が増えた分、ボディによっては取付けが難しくなる場合もあります。例えば、ブレイジングマックス(VSシャーシ)は小径タイヤなら無加工で装着できますが、シャイニングスコーピオン(スーパー1シャーシ)はギリギリで何とか装着できる程度です。また、旧ネオトライダガーZMCなどスーパー1シャーシに特化したボディは装着できないこともあります。
バンパーの強化と拡張性の向上により、スーパー2シャーシはより多様なセッティングが可能になり、ユーザーの創意工夫の幅が広がりました。これは競技での優位性につながる重要なポイントです。
スーパー2シャーシの素材選びは速さよりも用途で選ぶのがコツ
スーパー2シャーシの素材選びでは、「どれが速いか」という観点よりも、用途に合わせた選択をすることが重要です。独自調査によると、シャーシ選びで重視すべきポイントは次の3つだと言われています:
- 丈夫であること
- 加工再現性が容易であること
- 駆動音が良い音であること
速さに関しては、コンディションの要因が多すぎるため、シャーシ選びの段階で優劣を気にしすぎると、ミニ四駆が億劫になってしまう可能性があります。それよりも、自分のスタイルや目的に合った素材を選ぶことが大切です。
例えば、カーボン強化シャーシは最も丈夫で駆動音も静かですが、加工の再現性が低いため、複数マシンを所有したい場合には向いていません。フルパワーのスピードとトルクで走るための1台として使用するのが適しています。
ノーマルABSは耐久性がいまいちですが、加工が容易で再現性も高く、コストも低いため、練習用や実験用のマシンとして適しています。ただし、右フロントの軸受けが弱いのですぐに割れる傾向があります。
ポリカ強化シャーシは、耐久性と加工性のバランスが最も良いとされています。ABSと同じように加工でき、破損の心配もフロント軸受けのみに絞られるため、メインマシンとして使いやすい素材です。ただし、駆動音が他の素材より大きいという欠点があります。
蛍光シャーシは見た目が良いものの、強度面では最低クラスとされており、あらゆる箇所が割れやすいため、展示用や見た目重視のマシンに向いています。
素材選びは走行性能だけでなく、メンテナンス性や長期利用を考慮して行うことで、より満足度の高いミニ四駆ライフを送ることができるでしょう。
スーパー2シャーシの駆動系はXやVS系との互換性が高まった
スーパー2シャーシの駆動系は、基本設計はスーパー1と同じですが、それ以外の部分は大幅に規格が変更されています。これにより、ZEROとS1、XとXXほどの互換性はないものの、現在主流のGUPはXやVS用のものが多く、スーパー2はそちらに対応しているため、パーツ選びの幅が広がっています。
フロント・リヤギヤケースも形を大きく変えており、フロントはスイッチの方式をスライド式からMSシャーシの軽量センターユニットの方式に近いターン式スイッチに変更されました。さらにMS軽量センターのものと違い、スイッチを入れたとき「カチッ」と言う風にクリックを持たせ、確実に固定される仕様になっています。
リヤギヤケースはZERO型ギヤケースからTYPE-2式に変更され、カウンターギヤシャフトはVS等と同じツバ付のものを採用しています。カウンターギヤケースはネジ止めして強度を高められる設計となっており、モーターマウントも形状を工夫することでシャフトドライブシャーシとして唯一モータークーリングシールドを装備できるようになっています。
また、リヤギヤボックス及びリヤギアカバーがTYPE-2式の物に変更されているため、車種限定で同じくTYPE-2式リヤギヤカバーのVSマシンが無改造で装着可能です。
シャーシ中央及びモーター直下の肉抜きはスーパー1のものを継承していますが、電池サイドの肉抜きが埋められているため、僅かながらねじれ剛性が向上しています。
これらの変更により、スーパー2シャーシは従来のシャーシよりも安定した走行が可能になり、また様々なグレードアップパーツとの互換性が向上したことで、カスタマイズの幅が広がっています。特に競技志向のユーザーにとっては、パーツ選択の自由度が高まったことは大きなメリットといえるでしょう。
スーパー2シャーシのカラーバリエーションは豊富で組み合わせが楽しめる
スーパー2シャーシは、スーパー1と同様に、キットにセットされているシャーシ本体とギヤケースの色が全く異なるため、ユーザーのカラーセンスが問われるシャーシとなっています。カラーバリエーションは非常に豊富で、シャーシ本体だけでも20種類以上の色が存在します。
シャーシ本体のカラーには、ブラック、ディープレッド、ホワイト、カーボングレー、ダークガンメタル、ライトガンメタル、レッド、イエローオレンジ、ライトブルー、スカイブルー、シルバー、メタリックグレー、ダークグリーン、ダークグレー、ダークブルー(紺)、蛍光グリーン、蛍光オレンジ、蛍光ピンク、蛍光イエローなどがあります。
Aパーツ(ギヤケース)も同様に豊富なカラーバリエーションがあり、レッド、メタリックグリーン、ガンメタル、ディープブルー、ライトブルー、ホワイト、スカイブルー、ブラック、イエローオレンジ、オレンジ、イエロー、シルバー、ライトガンメタル、蛍光グリーン、蛍光オレンジ、蛍光ピンク、蛍光イエロー、パープル、ピンク、サーモンピンク、ゴールドなどが確認されています。
これらの豊富なカラーバリエーションを組み合わせることで、自分だけのオリジナルマシンを作り上げることができます。特におすすめの組み合わせとしては、以下のような例があります:
- ブラックシャーシ + メタリックグリーンAパーツ:シックで落ち着いた印象
- ブラックシャーシ + レッドAパーツ:スポーティな印象
- カーボングレーシャーシ + ブラックAパーツ:高級感のある実戦志向の仕様
- ダークグレーシャーシ + ディープピンクAパーツ:スーパーシリーズの雰囲気
カラーの選び方は個人の好みによりますが、シャーシの素材や用途に合わせて選ぶと、より一体感のあるマシンに仕上がります。例えば、展示用なら鮮やかな蛍光カラー、レース用なら落ち着いた色合いのシャーシを選ぶなど、目的に応じた色選びも楽しみ方の一つです。
ミニ四駆のシャーシとしてスーパー2を速くするための改造法
- スーパー2シャーシの改造は駆動部分から始めるのが基本
- スーパー2シャーシの弱点は25mm以下のタイヤでブレーキが貼れないこと
- スーパー2シャーシのギアの干渉を減らすことでスピードアップできる
- スーパー2シャーシはFM化(フロントモーター化)も可能
- スーパー2シャーシ用の強化ギアとワンロックギアカバーはおすすめパーツ
- スーパー2シャーシ用のサイドステーは改良型で拡張性が高い
- まとめ:ミニ四駆のシャーシ・スーパー2は入門にも競技にも適した万能シャーシ
スーパー2シャーシの改造は駆動部分から始めるのが基本
スーパー2シャーシを速くするための改造は、まず駆動部分から始めるのが基本です。駆動部分の効率を上げることで、モーターのパワーを無駄なく車輪に伝えることができ、結果としてスピードアップにつながります。
最初に取り組むべきなのは、モーターのブレ防止です。スーパー2シャーシはモーターが左右にブレる傾向があるため、マルチテープを貼ってブレを止めることが効果的です。ブレをなくすことでモーターの力を確実にカウンターギヤへと伝えられるようになります。
次に、ギアの噛み合わせを最適化します。カーボン配合のギアは丈夫である反面、噛み合わせがイマイチな場合があるため、紫とピンクのヘリカルギア(スーパーXX・スーパーIIシャーシ用超速ギヤセット)に交換するのも一つの方法です。ただし、ピンク色のギアは高い性能を誇りながらも強度に問題があったため、現在ではカーボン強化素材のギアも選択肢として考慮できます。
また、ギアやホイールのブレを抑えるために小ワッシャーとアルミスペーサー小を取り付けの際に挟むと効果的です。これによりギアの左右のブレが抑えられ、異音も減少します。
シャフト類も改造の対象になります。強化シャフトの曲がりが気になる場合は、軽量化も兼ねて中空シャフトへの変更が有効です。驚くべきことに、中空になっても普通のシャフトと強度は同等とされており、足回りの軽量化はスピードアップに直結します。同様にプロペラシャフトも中空タイプに変更し、さらにギアの間を少し詰めてプロペラシャフトの上下のブレを抑えると良いでしょう。
こうした駆動部分の改造により、初めはブレがなくなったことによる抵抗で回転が遅く感じることがありますが、走行を重ねるとギアの噛み合わせが安定し、走行音も良くなって最終的にはスピードアップが実感できるようになります。
スーパー2シャーシの弱点は25mm以下のタイヤでブレーキが貼れないこと
スーパー2シャーシの弱点として最も顕著なのは、25mm以下のタイヤでは1mmブレーキも貼れないという点です。これは一見すると大きなデメリットに思えますが、この弱点を逆手に取った戦略的なセッティングも可能です。
独自調査によると、電池抜き重量120g、ローハイトタイヤ真円出しのみ26mmスーパーハード超速という組み合わせが「めっちゃくちゃ速い」とされています。この組み合わせは何百通りもある中から見つけ出された最良の一つであり、タイヤの管理も交換も小径タイヤを使う場合に比べて10倍楽だというメリットがあります。
また、25mm以下のタイヤが使えないという制約があるため、車軸より下にローラーを配置するのが簡単になるという利点もあります。アンダーローラーをつけなくても下り1着が入りやすいという特性があります。
さらに、この弱点があるからこそ、26mmタイヤで1mmブレーキ一択にすれば、小径しかクリアできないようなコース以外に絞ってセッティングを考えることができます。これにより、できることの精度が上がり、より効率的なマシン作りが可能になります。
スーパー2シャーシは、弱点を含めて考えると「意外と弱点がない」シャーシだと評価されています。他のシャーシと比較すると、MAはフロントアッパーを直す必要がある、FM-Aはボディをフリーラインで切る必要がある、ARは重くて摩耗が激しい、VZはフロントが高すぎるなど、それぞれ独自の弱点があります。スーパー2も確かにフロントが低くカウンターの工夫が必要ですが、それ以外は案外優秀なシャーシだと言えるでしょう。
弱点を理解し、それを踏まえたセッティングを行うことで、スーパー2シャーシの真の力を引き出すことができます。
スーパー2シャーシのギアの干渉を減らすことでスピードアップできる
スーパー2シャーシのスピードアップには、ギアの干渉を減らすことが効果的です。ギアとギアの間に存在する様々な干渉を取り除くことで、モーターのパワーをより効率的に伝達することができます。
具体的な改造ポイントとしては、まずクラウンギアとスパーギアの間にある壁がギアの干渉を引き起こしやすいため、この部分を切り取ることが挙げられます。また、前後を繋ぐプロペラシャフトとスパーギアの干渉も問題となるため、こちらも取り除くと良いでしょう。抵抗を少しでも減らすことが、スピードアップにつながります。
ギアの干渉を減らすだけでなく、ギアの噛み合わせを最適化することも重要です。スーパー2シャーシ用の超速ギアセット(スーパーXX・スーパーIIシャーシ用超速ギヤセット)を使用すると、標準のギアよりも効率的にパワーを伝達できます。
さらに、ギアの位置出しも重要なポイントです。小ワッシャーやアルミスペーサーを使って、ギアの位置を微調整すると、ギアのブレを抑えることができます。ギアのブレが少なくなると、パワーロスが減少し、結果的にスピードアップにつながります。
プロペラシャフトについても、上下のブレを抑えるために、ギアの間を少し詰めると効果的です。ペンチでトントンと微調整することで、適切な位置に調整できます。
これらの改造を施した後は、電池を入れて試運転することが大切です。はじめはブレがなくなったことによる抵抗で回転が遅く感じることがありますが、走行を重ねるとギアの噛み合わせが安定し、走行音も良くなって最終的にはスピードアップが実感できるようになります。
ギアの干渉を減らす改造は、見た目の変化は少ないものの、走行性能に大きな影響を与える重要な要素です。特に競技志向の強いユーザーにとっては、必須の改造ポイントと言えるでしょう。
スーパー2シャーシはFM化(フロントモーター化)も可能
スーパー2シャーシは、標準ではリアにモーターが配置されていますが、FM化(フロントモーター化)も可能です。FM化とは、シャーシを前後逆にして使用し、フロント側にモーターを配置する改造方法です。これにより走行特性が変わり、新たな走りを楽しむことができます。
FM化されたスーパー2シャーシは「FMS2」と呼ばれ、マニアの間では人気のある改造方法となっています。FMSXやFMARなどと並び、自作FMシャーシの一つのバリエーションとして楽しまれています。
FMS2へと改造する際に最も大きな問題となるのが、電池のプラスマイナスを逆にしなければならない点です。電池のプラス側は凸になっているため、シャーシの形状と合わなくなります。この問題を解決するためには、ターミナル部分の加工が必要になります。
具体的には、電池プラス側の凸部分が当たる箇所のターミナルの出っ張りをニッパーなどでカットし、さらにターミナルを少し潰す必要があります。逆にマイナス側が当たる部分は、ターミナルを飛び出させて電池との接触を良くします。この際、ビス先の保護などに使うゴムパイプをターミナルの下に仕込んでおくと、飛び出していてもターミナルが潰れにくくなります。
フロントターミナル(FM化するとリヤになる部分)も電池との当たり方が変わるため、少し曲げる必要があるかもしれません。変形しやすい金具なので、しっかりと通電するように調整することが重要です。
FM化の利点としては、フロントにローラーを多く配置できることや、リアの重量バランスが変わることで新たな走行特性が得られる点が挙げられます。特に立体コースではフロントモーターの方が有利な場合もあるため、セカンドマシンとしてFMS2を持っておくのも良い選択肢です。
ただし、FM化の醍醐味はボディのセッティングにもあります。通常のボディをFM化したシャーシに装着するためには、ボディキャッチの位置や形状を工夫する必要があるため、自分だけのオリジナルマシン作りを楽しむことができます。
スーパー2シャーシ用の強化ギアとワンロックギアカバーはおすすめパーツ
スーパー2シャーシを速くするために特におすすめのパーツといえば、強化ギアとワンロックギアカバーです。これらはスーパー2シャーシの性能を大きく向上させる重要なアップグレードパーツとなっています。
まず、強化ギアについてです。タミヤから発売されている「強化ギヤ&ワンロックギヤカバー(スーパーIIシャーシ用)」には、カーボン強化素材のピニオンギアとヘリカルクラウンギアが含まれています。これらは通常のギアに比べて耐久性が高く、効率も良いため、スピードアップと安定性向上の両方に貢献します。
特に注目すべきは、ヘリカルクラウンギアです。従来のピンク色のものは高い性能を誇りながらも強度に問題がありましたが、カーボン強化素材となったことで破損率や摩耗が減少しました。また、形状も見直され、ギア側面部を歯の側へ一段近づけ、側面部からの歯の長さを短くすることで歯を折れにくくしています。言い換えれば、ギアの断面が単純な山型からWW型に近いものになり、より強靭になっています。
次に、ワンロックギアカバーです。スーパー2シャーシのカウンターギアカバーは、ネジ止めで固定する分強度と信頼性は高いものの、メンテナンスの際に毎回ネジを付け外しするのは面倒です。また、ネジ穴の磨耗(ネジ穴が馬鹿になるとギアカバーが固定されない)という欠点もあります。
ワンロックギアカバーはこれらの問題を解決します。専用のロックパーツをネジ穴にネジ止めし、そこでカバーを固定する構造になっています。カバーを開ける際はロックパーツを捻るだけというワンタッチ仕様なので、メンテナンスが大幅に楽になり、ネジの付け外しをしなくて良いためネジ穴の摩耗も防げます。
このパーツは元々はグレードアップパーツ(GUP)として単品販売されていましたが、現在ではエンペラープレミアム以降のスーパー2採用キットでは標準で付属するようになっています。ただし、一部の対応ボディでは干渉する場合があるので注意が必要です。
強化ギアとワンロックギアカバーを導入することで、スーパー2シャーシの弱点を克服し、より高性能かつメンテナンス性の良いマシンに仕上げることができます。競技志向のユーザーにとっては、ほぼ必須のアップグレードと言えるでしょう。
スーパー2シャーシ用のサイドステーは改良型で拡張性が高い
スーパー2シャーシのもう一つの大きな特徴として、サイドステー(サイドガード)の改良が挙げられます。基本的には、サイドガードはシャイニングスコーピオン・プレミアム等のごく一部のキットを除き付属していないため、通常はAOパーツ「AO-1028 ミニ四駆 EXサイドステー」などで入手することになります。
スーパー2用のサイドガードは、スーパー1用のVマシン型サイドガードをベースに改良されたもので、そこそこ頑丈だったVマシン用サイドガードをさらに強化し、ビス穴を追加することで拡張性を増したものになっています。これにより、様々なグレードアップパーツとの組み合わせが可能になり、より柔軟なセッティングが行えるようになりました。
興味深いことに、スーパー1用のサイドガードがスーパー2に流用可能なように、このスーパー2用サイドガードをスーパー1に流用することも可能です。サイドガードのアタッチメント部はスーパー1の物に比べ、多少強化されています。
同ランナーに成型されているのは、元になったVマシン方ではゴムリングローラーでしたが、このスーパー2用ではスタビヘッドとなっており、実用性が向上しています。
シャーシ中央(電池下のセンターライン上)のビス穴は、サイドガード用のもの以外にさらに2つ、前方に追加されています。ホビーショーの展示ではここに直FRPを設置し、そこにマスダンパーを付けている作例があったようで、そういった使い方を想定してのものだと考えられます。
1番前にあるセンターライン上のビス穴は、穴の左右に突起が設けられ、FRPプレートをビス止めした時にずれない様になっています。中央のものも、スーパー1からあったディテールの一部を変更することで、プレートがズレないようになっています(ただしどちらもワッシャーを1枚噛ますと機能しなくなるので注意が必要です)。
ここにFRPを装着する場合、小径タイヤでは(ビス頭が飛び出る分)地上高が規定ギリギリになるため注意が必要です。FRPのビス穴に座繰りを施し、皿ビスを使うと解決しますが、座繰りを施す分FRPの厚みが減り、強度が下がるので瞬着での強化を忘れないようにしましょう。
サイドガードのカラーバリエーションも豊富で、レッド、ゴールド、ライトガンメタル、ディープピンク、ヴァイオレット、ブラック、イエローなどが確認されています。これらを組み合わせることで、見た目のカスタマイズも楽しめます。
まとめ:ミニ四駆のシャーシ・スーパー2は入門にも競技にも適した万能シャーシ
最後に記事のポイントをまとめます。
- スーパー2シャーシは2010年12月に発売されたスーパー1の進化版で、初登場キットはマグナムセイバープレミアム
- スーパー1の弱点を克服し、バンパー強度の向上やビス穴の増加など、様々な改良が施されている
- 素材は主に4種類(ノーマルABS、ポリカ強化、蛍光ABS、カーボン強化)があり、用途に応じて選ぶことが重要
- カーボン強化は最も丈夫で駆動音も静かだが加工性は低く、ポリカ強化は耐久性と加工性のバランスが良い
- 25mm以下のタイヤでは1mmブレーキが貼れないという弱点があるが、これを逆手に取ったセッティングも可能
- 駆動系はXやVS系との互換性が高まり、現在主流のグレードアップパーツの多くに対応している
- モーターのブレ防止やギアの干渉を減らすことで、スピードアップが可能
- FM化(フロントモーター化)して「FMS2」として使用することも可能
- 強化ギアとワンロックギアカバーは特におすすめのグレードアップパーツ
- サイドステーは改良型で拡張性が高く、様々なセッティングに対応可能
- カラーバリエーションが豊富で、シャーシとAパーツの組み合わせを楽しめる
- シンプルな構造ながら高い性能を持ち、初心者から上級者まで幅広く使える万能シャーシである