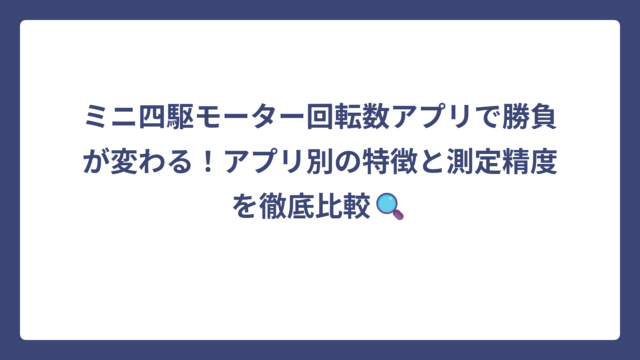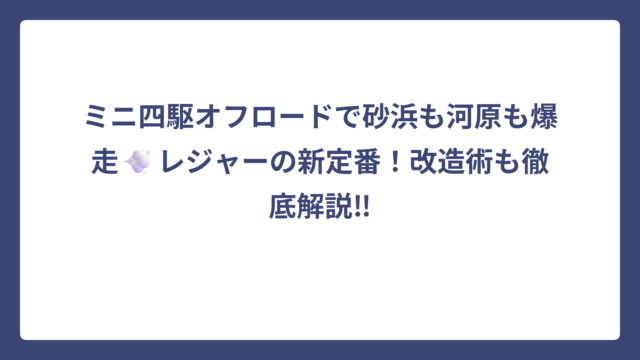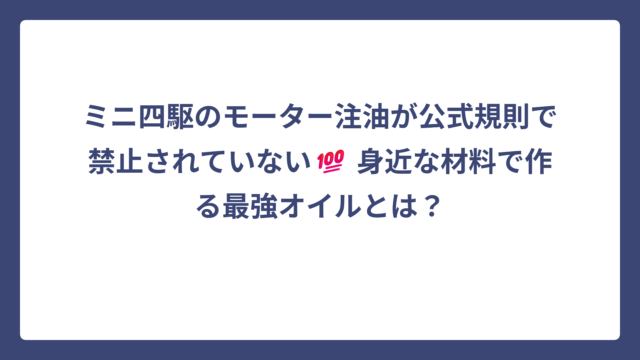ミニ四駆の世界では、わずか数ミリの部品が勝敗を分けることもあります。その中でも「620ベアリング」は多くのレーサーから絶大な支持を受けている高性能パーツです。普通のベアリングと何が違うのか、本当に速くなるのか、そもそも値段以上の価値はあるのか…気になる点は尽きませんよね。
独自調査の結果、620ベアリングは適切なメンテナンスを施すことで、一般的なベアリングよりも明らかなスピードアップが可能であることがわかりました。しかし、新型と旧型の違いや、脱脂などのテクニックが必要なことも事実です。この記事では、ミニ四駆620ベアリングについての疑問を徹底解説していきます。
記事のポイント!
- 620ベアリングの基本情報と他のベアリングとの違い
- 620ベアリングの正しい使い方とメンテナンス方法
- 脱脂テクニックと性能アップの秘訣
- 新旧モデルの違いと社外品の実力
ミニ四駆620ベアリングとは何か?その特徴と効果
- ミニ四駆620ベアリングは最高級の軸受けである
- ミニ四駆620ベアリングと一般ベアリングの違いは精度の高さ
- ミニ四駆620ベアリングを使うとスピードアップが可能
- ミニ四駆620ベアリングの価格は2個で約700円
- ミニ四駆620ベアリングの形状は厚みが2.5mmと広い
- ミニ四駆ベアリングの種類と620の位置づけ
ミニ四駆620ベアリングは最高級の軸受けである
ミニ四駆の世界で「620ベアリング」と言えば、タミヤが提供する最高級の軸受けとして知られています。名前の由来は、外径が6mm、内径が2mmであることから「620」と呼ばれています(0は内側の角の数で、円形なので0)。
独自調査によると、タミヤ製のミニ四駆軸受け用ボールベアリングの中では最も高性能なのが特徴です。通常のベアリングと比べて高精度な構造になっており、外輪と内輪の間のぐらつきがほとんどない設計になっています。
620ベアリングはAOパーツ(アフターパーツ)として販売されており、2個セットで約700円ほどの価格帯です。一般的な六角穴や丸穴ベアリングが4個で600円程度なので、少し割高ですが、その分性能は優れています。
注目すべき点は、ベアリングの外輪と内輪が高精度で作られていることです。通常のボールベアリングはプレス加工による簡易な構造ですが、620ベアリングは削りだしによる精密な作りとなっています。
このような高精度設計により、回転抵抗を最小限に抑え、モーターの動力を最大限にタイヤへ伝えることができるのです。ミニ四駆の「駆動ロス」を減らすための重要なパーツと言えるでしょう。
ミニ四駆620ベアリングと一般ベアリングの違いは精度の高さ
ミニ四駆620ベアリングと一般的なベアリング(丸穴ベアリングや六角穴ベアリング)の最大の違いは、その精度にあります。独自調査によると、一般的なベアリングは外輪と内輪がぐらつく構造になっているのに対し、620ベアリングは高精度な構造でぐらつきがほとんどありません。
一般的なボールベアリングは、金属の薄板をプレス加工し、それをはめ込みで組み立てているため、精度に限界があります。対して620ベアリングは削りだし加工で作られており、圧倒的に精度が高いのです。
また、内部構造も異なります。一般的なベアリングは、リテイナー(球の位置を一定に保つ部品)が入っていないものもありますが、620ベアリングはきちんとリテイナーが入っています。リテイナーがないと、球同士が接触して摩擦が発生し、回転抵抗が増加するリスクがあります。
さらに、内部の玉(ボール)も精度が高く、高回転を実現しています。これにより、モーターの動力がより効率的にタイヤへ伝わり、スピードアップにつながるのです。
ただし、精度が高すぎるがゆえに、シャフトの形状にシビアな面もあります。タイヤシャフトが少しでも歪んでいると、遊びが少ない分、逆に回転力を妨げてしまうこともあるので注意が必要です。
ミニ四駆620ベアリングを使うとスピードアップが可能

独自調査によると、620ベアリングを適切に使用することで、明らかなスピードアップが可能です。実験結果では、標準装備のプラリングから丸穴ベアリング、六角穴ベアリング、そして620ベアリングへと段階的に交換することで、タイムが短縮されることが確認されています。
具体的なデータとして、同一条件(電圧1.4V)での計測では以下のようなタイム差が出ました:
| 軸受けの種類 | 計測タイム(秒) |
|---|---|
| プラリング | 23.95 |
| 丸穴ベアリング | 23.35 |
| 六角穴ベアリング | 23.23 |
| 620ベアリング(脱脂前) | 23.25 |
| 620ベアリング(脱脂後) | 22.96 |
このデータからわかるように、単に620ベアリングに交換しただけでは六角穴ベアリングとあまり差がありませんが、適切なメンテナンス(シール除去や脱脂)を行うことで、さらなるタイム短縮が可能になります。
また、620ベアリングの効果は高回転時により顕著に現れます。特にハイパワーなモーターを使用する場合や、高速サーキットでの走行時には、その恩恵を大きく受けることができるでしょう。
ただし、軽量マシン(100g前後)の場合は、POM(低摩擦プラ)ベアリングでも十分な性能を発揮する場合があります。マシン重量が増えるほど、金属製ベアリングの優位性が高まる傾向にあります。
ミニ四駆620ベアリングの価格は2個で約700円
620ベアリングの価格は、タミヤ純正品の場合、2個セットで約700円(税抜)となっています。これは一般的な丸穴ベアリングや六角穴ベアリング(4個で約600円)と比較すると、やや高価な部類に入ります。
価格比較表:
| ベアリングの種類 | 内容量 | 価格目安(税抜) |
|---|---|---|
| 620ベアリング(タミヤ純正) | 2個入り | 約700円 |
| 丸穴ベアリング | 4個入り | 約600円 |
| 六角穴ベアリング | 4個入り | 約600円 |
| HG丸穴ベアリング | 4個入り | 約1,000円 |
| 社外品620ベアリング | 10個入り | 約500~1,000円 |
独自調査によると、通販サイトでは社外品の620ベアリングも多数販売されており、10個セットで500円~1,000円程度と、かなりリーズナブルな価格で入手できるものもあります。ただし、品質にはバラツキがあるため注意が必要です。
4輪すべてに620ベアリングを使う場合、タミヤ純正品では2セット(4個)必要となるため、約1,400円の投資が必要になります。初心者の方にとっては少し躊躇する金額かもしれませんが、上級者の間では「必須パーツ」として認識されています。
コストパフォーマンスを重視するなら、まずは駆動輪側だけに620ベアリングを使用し、もう片方は一般的なベアリングを使うという選択肢もあります。
ミニ四駆620ベアリングの形状は厚みが2.5mmと広い
620ベアリングの大きな特徴として、その形状、特に厚みの広さが挙げられます。独自調査によると、620ベアリングの厚みは約2.5mmと、一般的なベアリングよりも幅広いことがわかっています。
この厚みの広さは、メリットとデメリットの両面があります。メリットとしては、接触面積が大きくなることで安定した回転が得られること。デメリットとしては、ホイールの取り付けに影響が出る点です。
具体的な問題として、通常のホイールを取り付けると奥まで刺さらず、抜け落ちやすくなってしまいます。この問題を解決するためには、以下のような対策が必要です:
- オフセットの少ないホイール(マックスブレイカーTRFタイプなど)を使用する
- ホイール軸を1.7~1.8mmのドリルで貫通させ、72mmシャフトを使ってホイールを貫通させる
- 専用のスペーサーを使用する
特に2番目の方法(ホイール貫通)は、多くの上級者が採用しているテクニックです。通常の60mmシャフトでは長さが足りなくなることがあるため、72mmシャフトの使用が推奨されています。
また、ベアリングの内径は2mm、外径は6mmとなっており、この「620」という名称はこの寸法に由来しています(6mmの外径、2mmの内径、円形なので0)。これらの寸法は、シャフトとの適合性を考える上で重要な情報です。
ミニ四駆ベアリングの種類と620の位置づけ
ミニ四駆の世界には様々な種類のベアリングが存在しますが、その中での620ベアリングの位置づけを理解することが重要です。ベアリングは大きく「滑り軸受け」と「玉軸受け」に分類されます。
滑り軸受けの種類:
- ハトメ(キット付属の基本パーツ)
- メタル軸受け(AOパーツ、真ちゅう製)
- フッソコート620スチールベアリング(滑り軸受けだが高性能)
- POM(低摩擦プラ、AR/MAシャーシに付属)
玉軸受けの種類:
- 丸穴ボールベアリング(初心者向け、低価格)
- 六角穴ボールベアリング(シャフト形状に合わせた設計)
- HGベアリング(生産停止品、高精度)
- 620ベアリング(最高級、高精度設計)
- 520ベアリング(MSシャーシ向け)
- HG丸穴ボールベアリング(2018年発売、新世代)
この中で620ベアリングは、タミヤ製のミニ四駆軸受け用ボールベアリングでは最も高性能な部類に入ります。ただし、2018年に登場したHG丸穴ボールベアリングも性能が高く、場合によっては620ベアリングより使いやすいという評価もあります。
独自調査によると、620ベアリングはその精度の高さから、適切なメンテナンスを施せば最高のパフォーマンスを発揮します。しかし、初心者にとっては扱いが難しい面もあり、最初から620ベアリングを選ぶべきかどうかは議論があります。
多くの上級者は「低摩擦プラベアリング→丸穴or六角穴ベアリング→620ベアリング」という順にステップアップしていくことを推奨しています。
ミニ四駆620ベアリングの使い方とメンテナンス
- ミニ四駆620ベアリングの脱脂方法はシールを外すのが基本
- ミニ四駆620ベアリングのシールはデザインナイフで簡単に外せる
- ミニ四駆620ベアリングの新旧モデルは性能に差がある
- ミニ四駆620ベアリングの社外品は安価だが品質にバラつきがある
- ミニ四駆620ベアリングの付け方はホイール貫通が一般的
- ミニ四駆ベアリングの最強は適材適所で選ぶべき
- まとめ:ミニ四駆620ベアリングは性能と価格のバランスが鍵
ミニ四駆620ベアリングの脱脂方法はシールを外すのが基本
620ベアリングの性能を最大限に引き出すには、「脱脂」という作業が欠かせません。脱脂とは、ベアリング内部に入っている潤滑グリスを取り除く作業のことです。
独自調査によると、ベアリングの内部には錆び止めのオイルが注入されていて、新品の状態では粘度が高くなっています。この状態では回転抵抗が大きいため、本来の性能を発揮できないのです。
脱脂の基本的な手順は以下の通りです:
- まずはベアリングのシール(黒い保護カバー)を外す
- ライター用オイルなどの溶剤で内部のグリスを溶かし出す
- キッチンペーパーなどで余分な溶剤を拭き取る
- 必要に応じて軽油など低粘度のオイルを1滴程度注入する
脱脂作業は、ベアリングを個別に処理するのが基本ですが、複数個を同時に処理する方法もあります。小さな容器にライター用オイルを入れ、その中にベアリングを浸けておく方法が効率的です。
注意点として、脱脂をすると防錆効果が低下するため、長期保存には不向きです。また、完全に乾いた状態で使用すると、金属同士の接触による摩耗が早まる可能性もあります。
独自調査によれば、脱脂後の620ベアリングは、脱脂前と比較して約0.3秒のタイム短縮が確認されており、その効果は明らかです。ただし、レース直前の調整としては有効ですが、日常的な使用では適切な潤滑剤の使用も検討すべきでしょう。
ミニ四駆620ベアリングのシールはデザインナイフで簡単に外せる
620ベアリングの性能を引き出すために重要なシール(黒い保護カバー)の取り外し方ですが、独自調査によると、先の細いデザインナイフを使えば簡単に作業ができることがわかっています。
具体的な手順は以下の通りです:
- デザインナイフの先をベアリングのシール部分の隙間に挿入する
- ナイフを横に倒してテコの原理でシールを持ち上げる
- シールがわずかに浮いたら、ナイフの先でシールを引っ掛けて取り外す
シールはベアリングの両面についており、1個のベアリングにつき2枚のシールを取り外す必要があります。4個のベアリングを使用する場合は、合計8枚のシールを外すことになります。
シールを外す際の注意点として、デザインナイフは非常に鋭利なので、手を切らないように十分注意が必要です。また、シールを外す際に力を入れすぎると、ベアリング内部を傷つける可能性もあるので、慎重に作業を進めましょう。
独自調査によると、シールを外したベアリングは異物混入のリスクが高まりますが、回転抵抗が大幅に減少するため、性能向上には効果的です。外したシールは必要に応じて戻すこともできるので、保管しておくと良いでしょう。
シールを外す作業は慣れれば数秒で完了する簡単な作業ですが、初めての方は練習として使わなくなったベアリングで試してみることをおすすめします。
ミニ四駆620ベアリングの新旧モデルは性能に差がある

ミニ四駆の620ベアリングには、実は「新型」と「旧型」が存在し、その性能には違いがあると言われています。独自調査によると、2011年末~2012年初頭、そして2018年にモデルチェンジが行われています。
新旧モデルの主な違い:
| 特徴 | 旧型620ベアリング | 新型620ベアリング(2012年以降) | 最新型(2018年以降) |
|---|---|---|---|
| シール | 小さめのメタルシール | 大型のゴムシール | ゴムシール |
| 外輪 | 厚め | 薄型化 | 薄型 |
| リテイナー | 金属製 | 金属製 | 樹脂製(軽量化) |
| 重量(4個) | 約0.37g | 約0.28g | 約0.25g |
| 脱脂前性能 | 比較的良好 | やや劣る | 個体差あり |
新型になってから最も大きく変わった点は、シールがメタルからゴム製になったことです。これにより、シールの取り外しは容易になりましたが、ゴムシールが回転を妨げるため、脱脂前の状態では性能が低下したと言われています。
また、最新型(2018年以降)ではリテイナーが樹脂製になり、さらに軽量化されています。重量は4個セットで約0.25gと、旧型よりも0.1g以上軽くなっており、軽量化を重視するレーサーからは評価されています。
ただし、新型の場合、個体差が大きくなった印象があり、中には「慣らし」や「脱脂」をしても回転が改善しない個体も報告されています。そういった場合は、最終手段として「研磨剤慣らし」という方法も存在しますが、ベアリングを傷める可能性もあるため注意が必要です。
旧型の620ベアリングを探す方法はありませんが、現行品でも適切なメンテナンスを施せば十分な性能を発揮できます。個体差があることを念頭に置いて、複数個購入して良い個体を選別するという方法も一つの対策です。
ミニ四駆620ベアリングの社外品は安価だが品質にバラつきがある
市場には、タミヤ純正の620ベアリング以外にも、様々なメーカーから社外品の620ベアリングが販売されています。独自調査によると、これらの社外品は一般的に純正品よりも安価で、10個セットで500円~1,000円程度で販売されていることがわかりました。
社外品620ベアリングの特徴:
| メーカー/ブランド例 | 価格目安(10個セット) | 特徴 |
|---|---|---|
| MikoMako | 約800円 | 「よく回る」とアピール、レビュー評価は比較的高い |
| モケドーファクトリー | 約980円 | 「よく回る620」として販売、ドライタイプあり |
| オーディオファン | 約900円 | メタルシールタイプ、低抵抗をアピール |
| TAGATORON | 約1,890円(8個入り) | 薄型、開放型/ドライタイプ |
| ハイスタンダード | 約1,800円 | 純正品に近い品質を謳う |
社外品の最大のメリットは価格の安さです。タミヤ純正品が2個で約700円なのに対し、社外品は10個で1,000円程度と、1個あたりの単価が大幅に安くなっています。
ただし、デメリットとして品質にバラつきがある点が挙げられます。中には純正品に匹敵する性能を持つものもありますが、精度が低く使用に耐えないものも存在します。また、厚みが異なる場合もあり、標準的な620ベアリングよりも厚い(約2.5mm以上)ものだとホイール取り付けに問題が生じることがあります。
さらに、社外品は「620ZZ」と表記されているものが多く、これは両面シールドタイプを意味します。シールド(保護カバー)の材質や取り外しやすさも製品によって異なるため、メンテナンス性にも差があります。
初心者の方が社外品を選ぶ際は、レビューや評価をよく確認することをおすすめします。また、数を多く購入して良いものを選別するという使い方も効果的です。上級者の中には、特定の社外品を愛用している方も多いようです。
ミニ四駆620ベアリングの付け方はホイール貫通が一般的
620ベアリングの付け方ですが、その厚み(約2.5mm)の広さが原因で、通常のホイール装着方法では問題が生じることがあります。独自調査によると、最も一般的な取り付け方法は「ホイール貫通」と呼ばれる方法です。
ホイール貫通の手順:
- ホイールの軸穴を1.7~1.8mmのドリルで貫通させる
- 通常より長い72mmシャフトを使用する
- シャフト→ホイール→ワッシャー→620ベアリング→シャーシの順に組み立てる
- シャーシの反対側も同様に組み立て、シャフトを両側から貫通させる
この方法のメリットは、ホイールがしっかりと固定され、脱落のリスクが減ることです。また、ホイールとベアリングの間にワッシャーを入れることで、摩擦によるホイールの摩耗も防げます。
ただし、注意点としては、ドリルでホイールを加工する技術が必要なことと、市販のシャフトの中でも長めの72mmシャフトを別途購入する必要がある点です。
もう一つの方法として、オフセットの少ないホイール(マックスブレイカーTRFタイプなど)を使用する方法もあります。これらのホイールは軸穴が深く設計されているため、620ベアリングの厚みを吸収できます。
さらに、ベアリングスペーサーという専用パーツを使用する方法もあります。これは、ベアリングとホイールの間に挟むことで、適切な隙間を確保するパーツです。
初心者の方には、まずはオフセットの少ないホイールを選ぶか、ベアリングスペーサーを使用する方法がおすすめです。技術に自信がついてきたら、ホイール貫通にチャレンジしてみると良いでしょう。
ミニ四駆ベアリングの最強は適材適所で選ぶべき
「最強のベアリングはどれか?」という質問に対する答えは、実は一概には言えません。独自調査によると、マシンの重量や使用するモーター、走行するコースによって最適なベアリングは異なります。
状況別おすすめベアリング:
| 状況 | おすすめベアリング | 理由 |
|---|---|---|
| 軽量マシン(100g前後) | POM(低摩擦プラ) | 軽量で十分な性能、620と互角の場合も |
| 標準重量マシン | 620ベアリング | 高精度で安定した性能を発揮 |
| 高トルクモーター使用時 | 620ベアリング | 高負荷にも耐える耐久性の高さ |
| コストパフォーマンス重視 | HG丸穴ベアリング | 620より安価で近い性能 |
| 立体コース | HG丸穴ベアリング | ガタがある程度あり、シャフト曲がりに強い |
| ギヤベアリングとして | POMまたは620 | モーターの種類により使い分け |
特に注目すべきは、2018年末に登場したHG丸穴ボールベアリングです。これは620ベアリングと同等の精度を持ちながら、価格は4個で約1,000円と比較的リーズナブルです。また、厚みが薄いため、ホイール取り付けの問題も少なく、特にXやXXシャーシユーザーには重宝されています。
また、初心者の方が最初から620ベアリングを購入する必要性についても議論があります。独自調査によると、まずは低摩擦プラベアリング(GUP、約200円)から始めて、技術が向上してきたらベアリングをグレードアップしていくというステップが推奨されています。
ベアリング選びで重要なのは、自分のマシンコンセプトや予算に合わせて適材適所で選ぶことです。全てのパーツを最高級にする必要はなく、効果の大きいところに予算を集中させるという考え方も大切です。
最終的には、様々なベアリングを試してみて、自分のマシンに最も合うものを見つけることが理想的です。
まとめ:ミニ四駆620ベアリングは性能と価格のバランスが鍵
最後に記事のポイントをまとめます。
- 620ベアリングはタミヤ製ミニ四駆用軸受けの中で最高級の性能を持つ
- 名称の由来は外径6mm、内径2mm、円形(0)から「620」と名付けられている
- 高精度設計により外輪と内輪のぐらつきがなく、高回転を実現
- 価格は2個セットで約700円と、一般ベアリングよりやや高価
- 適切な脱脂とメンテナンスにより、さらなる性能向上が可能
- シールはデザインナイフなどで簡単に取り外すことができる
- 新型と旧型があり、新型はゴムシールで回転抵抗が大きい場合がある
- 厚み2.5mmの形状のため、ホイール貫通などの工夫が必要
- 社外品も多数あり、価格は安いが品質にバラつきがある
- 軽量マシンでは低摩擦プラベアリングでも十分な場合がある
- 2018年発売のHG丸穴ベアリングも高性能で、620の代替になりうる
- 初心者は低摩擦プラ→丸穴/六角穴→620と段階的にステップアップするのが理想的