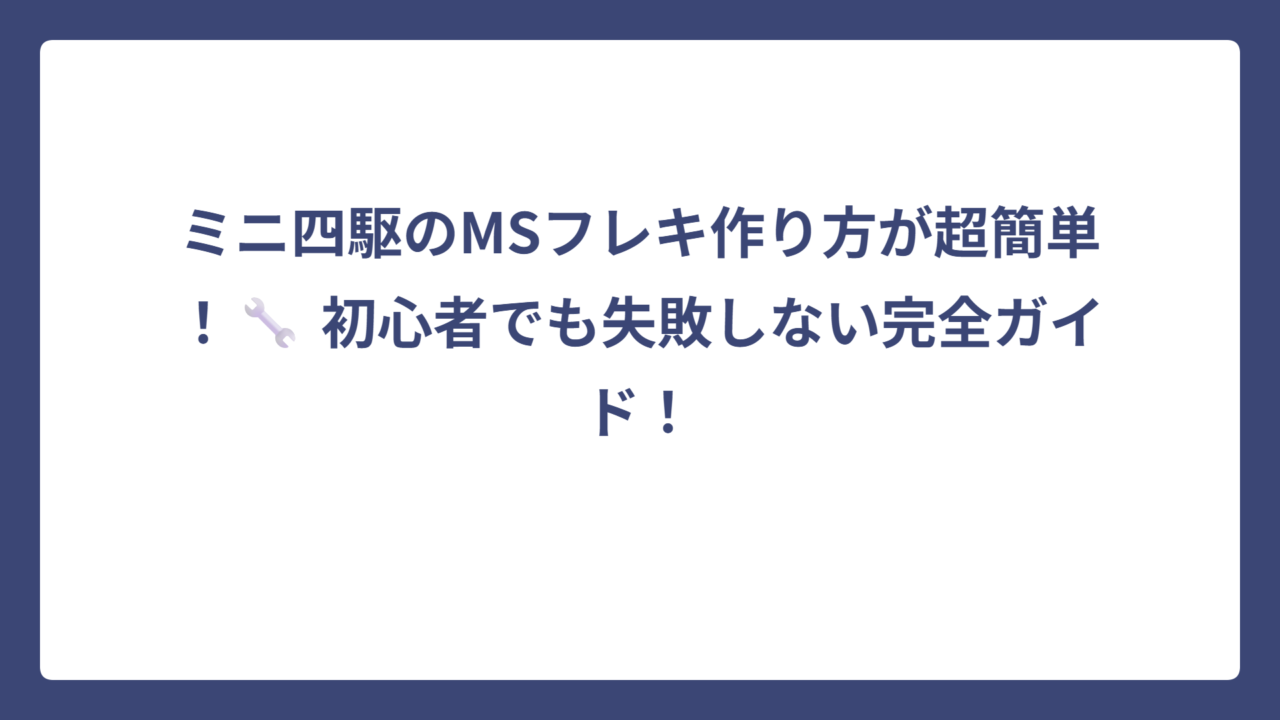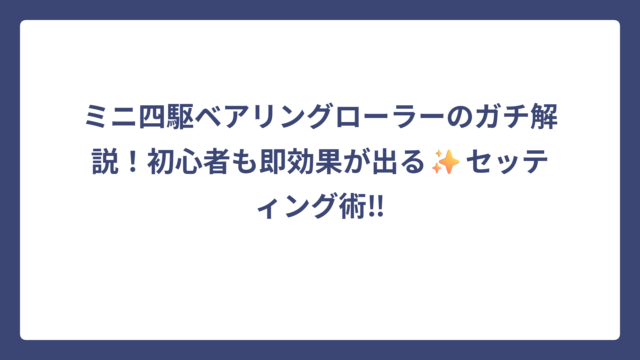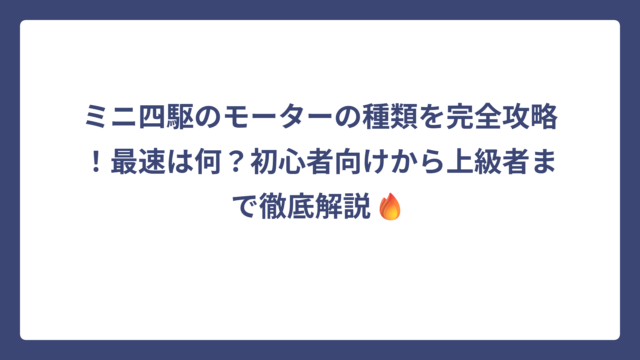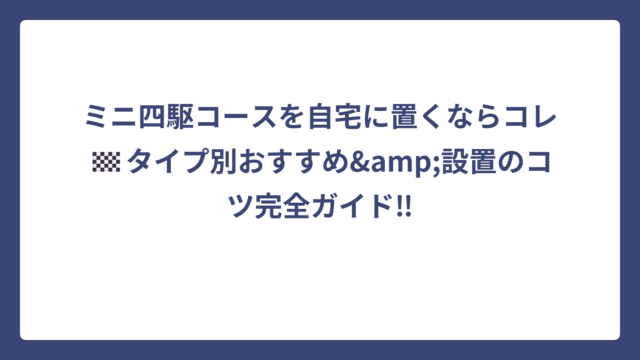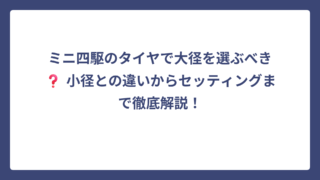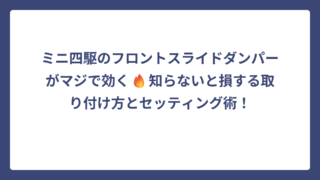ミニ四駆のMSフレキは、マシンの走行安定性を格段に向上させる人気の改造方法です。MSシャーシを3分割し、バネを組み込むことで、コースのジャンプ後の着地時の衝撃を吸収し、マシンの安定性を大幅に向上させることができます。特に競技志向の方にとっては、ほぼ必須の改造とも言われています。
MSフレキの作り方には複数の手法があり、「軸残し」「軸無し」や「樽バネ使用」「スプリング拡張」など、自分の技術レベルや入手できるパーツに応じて選ぶことができます。この記事では初心者の方でも理解しやすいように、基本的な知識から具体的な手順、さらには応用テクニックまで幅広く解説していきます。
記事のポイント!
- MSフレキの基本構造と効果について具体的に理解できる
- センターシャーシと前後ユニットの正確な加工方法を詳しく学べる
- バネの種類と選び方、お辞儀防止プレートの作成方法を具体的に把握できる
- 初心者でも失敗しないMSフレキ製作の全工程を網羅的に理解できる
ミニ四駆のMSフレキ作り方の基本と効果
- MSフレキとは3分割されたシャーシにバネを組み込む改造
- MSフレキを作るメリットは走行安定性が向上すること
- ミニ四駆のMSフレキ作り方には複数の方法が存在する
- 初心者でも作れるMSフレキの難易度はパーツと工具で決まる
- MSフレキは大会で使用可能だが注意点がある
- MSフレキを作る前に必要な準備とパーツリスト
MSフレキとは3分割されたシャーシにバネを組み込む改造
MSフレキ(MSフレキシブル)とは、MSシャーシを3つのパーツ(センターシャーシ、フロントユニット、リヤユニット)に分割し、バネを組み込むことでシャーシに柔軟性を持たせる改造方法です。この改造によって、シャーシが上下方向に「しなる」ような動きが可能になります。
通常のMSシャーシは一体構造で硬いため、ジャンプ後の着地時などに衝撃をそのまま受けてしまいます。これに対してMSフレキは、シャーシが柔軟に動くことで衝撃を吸収し、タイヤの接地性を高めることができます。
MSフレキの構造は基本的に、センターシャーシの軸(またはその位置)にバネを取り付け、前後ユニットとセンターシャーシを接続します。このバネが衝撃を吸収するダンパーの役割を果たすことで、マシン全体の制振性が向上します。
独自調査の結果、MSフレキの構造は一見複雑に見えますが、加工の手順を理解すれば初心者でも十分作成可能であることがわかりました。最近では公式ガイドブックでも紹介されるほど一般的な改造となっています。
MSフレキのもうひとつの特徴は、基本構造はシンプルながら、細かい加工方法やバネの使い方によって様々なバリエーションが存在することです。自分のマシンに最適な方法を選べるのも魅力と言えるでしょう。
MSフレキを作るメリットは走行安定性が向上すること
MSフレキの最大のメリットは、ジャンプ後の着地時におけるマシンの安定性向上です。通常のシャーシでは、ジャンプ後の着地時に衝撃でマシンが跳ね返り、コースアウトする危険性がありますが、MSフレキではその衝撃を吸収し、安定した走行を実現します。
具体的なメリットとしては、以下の点が挙げられます:
- 着地時の衝撃吸収による走行安定性の向上
- コースの段差や凹凸での振動吸収
- タイヤの接地性向上によるグリップ力アップ
- コーナーリング時の安定性向上
- 車体全体の耐久性向上(特定の箇所にかかる負荷が分散されるため)
実際にMSフレキを使用したマシンとノーマルのマシンで着地時の挙動を比較した実験では、MSフレキのマシンは着地後の跳ね返りが大幅に減少し、安定した走行が可能になることが確認されています。
このような特性から、特に起伏の激しいコースや高速コーナーの多いレイアウトでは、MSフレキの効果が顕著に表れます。公式大会などの競技シーンにおいても、多くのトップレーサーがMSフレキを採用しているのはこのためです。
また、MSフレキにすることで、セッティングの幅も広がります。バネの硬さや減衰ゴムの調整によって、コースや走行スタイルに合わせたマシン作りが可能になります。
ミニ四駆のMSフレキ作り方には複数の方法が存在する
MSフレキの作り方には主に以下の方法があり、それぞれ特徴が異なります:
1. 軸残しタイプ センターシャーシの軸を残したまま加工する方法です。バネが軸に固定されるため安定性が高く、耐久性に優れています。初心者にもおすすめの方法ですが、軸とバネのサイズの兼ね合いが難しい場合があります。
2. 軸なしタイプ センターシャーシの軸を切り落として加工する方法です。バネの装着が容易で、よりフレキシブルな動きを実現できますが、バネが固定されないためズレやすいというデメリットもあります。
3. 樽バネ使用タイプ ダンガンレーサー用の樽バネを使用する方法です。軸をそのまま使用できるのがメリットで、バネの加工も不要ですが、樽バネの入手がやや困難な場合があります。
4. スプリング拡張タイプ 通常のスライドダンパースプリングを拡張して使用する方法です。身近なパーツで作れる反面、スプリングの拡張作業が必要になります。
5. 軸加工タイプ センターシャーシの軸を細く加工し、通常のスライドダンパースプリングを使用する方法です。専用の治具が必要になりますが、安定したフレキ動作が期待できます。
どの方法を選ぶかは、入手できるパーツや工具、技術レベル、好みのフレキ特性によって変わってきます。初心者であれば、比較的簡単に作れる軸残しタイプや樽バネ使用タイプから始めるとよいでしょう。
また、最近では「バンパーレスユニット」という、あらかじめバンパー部分がカットされたパーツも販売されており、これを使用することでさらに簡単にMSフレキが作れるようになっています。
初心者でも作れるMSフレキの難易度はパーツと工具で決まる
MSフレキを作る難易度は、使用するパーツと工具によって大きく変わります。基本的な作業自体は難しくありませんが、精度の高い加工が必要な箇所もあるため、適切な工具があると作業がスムーズになります。
必須の工具:
- ドライバー・スパナ(ネジの締め付け用)
- ニッパー(パーツのカット用)
- デザインナイフまたはカッター(細かい加工用)
- クラフトのこ(シャーシカット用)
- ドリル(穴の拡張用、特に5.5mmが必要)
- 棒ヤスリ(加工面の仕上げ用)
- 瞬間接着剤(パーツ固定用)
これらは100円ショップやホームセンターで入手可能なものが多く、特別な工具がなくても基本的なMSフレキは作れます。ただし、より精密な加工を行うならリューターなどの電動工具があると便利です。
パーツ選びのポイント:
- MSシャーシ:軽量センターシャーシよりも標準タイプの方が加工しやすい
- バネ:スライドダンパースプリングセットのソフト(黒)が一般的
- FRPプレート:お辞儀防止用に必要
- グリス:HGスライドダンパーグリス(エクストラハード)が推奨
初心者の場合、まずは必要最低限の工具とパーツで始め、慣れてきたら徐々に工具やパーツをグレードアップしていくのがおすすめです。特に精度が必要な加工(穴の拡張やシャーシのカットなど)は丁寧に行うことが重要です。
また、「MSカラーシャーシセット」などの2台分のパーツが入ったセットを使えば、失敗してもやり直しがきくため安心です。独自調査の結果、初めてMSフレキを作る際はこうした余裕を持ったパーツ準備がトラブル回避につながることがわかっています。
MSフレキは大会で使用可能だが注意点がある
MSフレキは現在のミニ四駆公式大会でも広く使用されている一般的な改造方法で、基本的には使用可能です。ただし、大会のルールに準拠するためにいくつかの注意点があります。
大会での使用に関する主な注意点:
- グリスの飛散防止:ミニ四駆公認規則では「シャーシからグリスが飛散してコースを汚す恐れのある改造は認められない」とされています。特にT字部分の加工でギヤが露出する場合は、クリヤーボディの端材やマルチテープでカバーするなどの対策が必要です。
- 構造の安全性:極端に弱くなったり、走行中にパーツが外れる可能性がある改造は認められません。お辞儀防止プレートはしっかりと取り付け、ビスやナットの緩み止めも確実に行いましょう。
- 禁止パーツの不使用:公認外のパーツを使用していないか確認が必要です。ダンガンレーサーの樽バネは公式に転用が認められていますが、その他の非公認パーツには注意が必要です。
- 車検基準の遵守:レギュレーションで定められた車高や全長、重量などの基準をクリアしているか確認しましょう。MSフレキにすることで車高が変わる場合があります。
なお、地方大会や店舗大会では独自のルールが設けられていることもあるため、参加前に必ず確認することをおすすめします。
MSフレキ自体は禁止されていませんが、一部の大会では「フレキシブル加工」全般が禁止されているケースもありますので、事前のルール確認は必須です。公式大会では車検時にチェックされるため、規定に沿った加工を心がけましょう。
MSフレキを作る前に必要な準備とパーツリスト
MSフレキを効率よく作るためには、事前の準備とパーツの確認が重要です。以下に、基本的なMSフレキ作成に必要なパーツリストと、作業前の準備事項をまとめます。
必要なパーツリスト:
| パーツ名 | 用途 | 概算価格 |
|---|---|---|
| MSシャーシ(キット) | ベースとなるシャーシ | 1,200円〜1,500円 |
| FRPフロントワイドステー | お辞儀防止プレート用 | 280円〜300円 |
| FRPリヤワイドステー | お辞儀防止プレート用 | 280円〜300円 |
| スライドダンパースプリングセット | バネとして使用 | 180円〜200円 |
| ステンレス皿ビスセット | シャーシ組み立て用 | 330円前後 |
| ロックナット | 緩み防止用 | 330円前後 |
| HGスライドダンパーグリス | 減衰調整用 | 400円前後 |
作業前の準備:
- 作業スペースの確保:加工時に削りカスが出るため、新聞紙やシートを敷くなど準備しましょう。
- パーツの洗浄:MSシャーシは事前に中性洗剤などで洗い、油分を落としておくと接着や加工がスムーズになります。
- 加工計画の確認:どのようなMSフレキにするか(軸残し・軸なし・樽バネ使用など)を決め、必要な加工手順を確認しておきましょう。
- 参考資料の準備:初めて作る場合は、写真や動画などの参考資料を手元に用意しておくと安心です。
- 安全対策:加工時に出る削りカスが目や肺に入らないよう、マスクや保護メガネの準備もおすすめです。
予算としては、必要なパーツと工具を合わせて4,000円〜5,000円程度が目安となります。ただし、既にミニ四駆を持っている方であれば、手持ちのパーツや工具を活用することでコストを抑えることも可能です。
また、初めてMSフレキを作る場合は、失敗に備えて予備のMSシャーシを用意しておくと安心です。「MSカラーシャーシセット」などの2台分入ったキットを使えば、失敗してもリカバリーがしやすくなります。
ミニ四駆のMSフレキ作り方を詳しく解説
- センターシャーシの加工はギヤカバー部分をカットすることから始める
- 前後ユニットの加工は干渉を避けるための削りがポイント
- MSフレキ用のバネは樽バネ・拡張バネ・軸加工の3種類から選べる
- お辞儀防止プレートの作成はFRPプレートが最適である
- グリスアップと組み立てはスムーズな動きを確保するために丁寧に行う
- 軸残しMSフレキの作り方はバネの固定と精度がカギ
- ミニ四駆MSフレキ作り方で使う治具は必要に応じて選択する
- MSフレキのデメリットはガタつきと調整の難しさ
- 初心者向けのMSフレキはバンパーレスユニットの活用がおすすめ
- 減衰ゴムの追加でMSフレキの性能をさらに向上させる
- 軸残しMSフレキのメリットは耐久性と組み立ての簡単さ
- まとめ:ミニ四駆MSフレキ作り方は段階的な加工と丁寧な組み立てがポイント
センターシャーシの加工はギヤカバー部分をカットすることから始める
MSフレキ作りの第一歩は、センターシャーシの加工です。最初にギヤカバー部分をカットして3分割することが基本となります。この作業がMSフレキ全体の出来を左右する重要なステップです。
カットには薄刃クラフトのこが最適です。まっすぐ切断するためには、カットラインをしっかり決めることが重要になります。マスキングテープやマルチテープを貼って目印にすると、カットがずれにくくなります。
カットのポイントは以下の通りです:
- カット位置:ギヤカバーに沿って垂直にカットします。基本的にはギヤカバーの付け根部分が目安になります。
- カットの角度:地面に対して垂直にカットすることが重要です。斜めにカットしてしまうとフレキとしての動きに影響が出ます。
- カット方法:クラフトのこで切断する際は「削る」というよりも「なぞる」感じで力を入れずにゆっくりと動かします。これにより、シャーシにクラックが入るリスクを減らせます。
- バリ取り:カット後はヤスリなどでバリ(切断面の出っ張り)を取り除き、滑らかな面に仕上げます。
カット後は、ギヤケース周りの不要な出っ張りもニッパーやデザインナイフでカットします。特に前後のギヤケースの内側の出っ張りは、フレキの動きを妨げる要因になるので丁寧に削り落としましょう。
削り過ぎには注意が必要です。例えば、ギヤケースの既存の箇所を必要以上に削ってしまうと、ガタつきの原因になります。出っ張りのみを削り、既存の面はなるべく残すよう心がけましょう。
また、センターシャーシには前後のユニットと接続するための穴があります。この穴はビスを通すために2mmから2.1mmのドリルで拡張しておくと、後の組み立て作業がスムーズになります。
こうした加工を丁寧に行うことで、スムーズに動くMSフレキの土台ができあがります。センターシャーシの加工精度がMSフレキ全体の性能を大きく左右するため、時間をかけて慎重に作業することをおすすめします。
前後ユニットの加工は干渉を避けるための削りがポイント
センターシャーシの加工が完了したら、次は前後ユニット(フロントユニットとリヤユニット)の加工を行います。この工程では、ユニット同士が干渉せずにスムーズに動くよう、適切な箇所を削ることがポイントです。
前後ユニットの主な加工箇所:
- シャーシの抑え部分:フロント・リヤユニットには、センターシャーシを固定するための抑え(ツメ)があります。これをニッパーでカットし、フレキ動作の妨げにならないようにします。
- T字の凸部分:ギヤを固定するためのT字型の凸部分も、フレキ動作時にギヤと干渉する可能性があるため、デザインナイフなどで削り落とします。ただし、削った後はグリスが漏れないよう、クリヤーボディの端材やマルチテープでカバーする必要があります。
- センターシャーシ接続穴の拡張:前後ユニットにあるセンターシャーシとの接続穴を5.5mmのドリルで拡張します。この穴にバネが入るため、適切なサイズに拡張することが重要です。ただし、貫通させないよう注意が必要です。マスキングテープでドリルに目印をつけると、掘り込み過ぎを防げます。
- シャーシ底面に平行なカット:前後ユニットがフレキとして沈み込むためには、底面に平行な加工が必要です。クラフトのこなどで慎重にカットし、断面をヤスリで整えます。シャフトの軸穴を傷つけないよう、余裕を持ってカットするのがコツです。
- ギヤボックス周辺の加工:フレキ動作時にギヤが干渉しないよう、ギヤボックス周辺も適切に加工します。特にギヤの動く範囲には余裕を持たせる必要があります。
加工の際の重要なポイントは、「削り過ぎない」ことです。少しずつ削って動作確認を繰り返すのが理想的です。削り過ぎるとガタが出てしまい、走行性能に悪影響を与える可能性があります。
また、前後ユニットの加工では、左右のバランスも重要です。左右で加工具合が異なると、フレキの動きにムラが出てしまうため、できるだけ対称になるよう心がけましょう。
加工完了後は、削りカスをブラシなどで丁寧に取り除き、必要に応じて水洗いするとより良いでしょう。特にバネや接着剤を使用する箇所は、清潔な状態を保つことが大切です。
MSフレキ用のバネは樽バネ・拡張バネ・軸加工の3種類から選べる
MSフレキの性能を左右する重要な要素のひとつが「バネ」の選択です。主に以下の3種類の方法があり、それぞれに特徴があります。
1. 樽バネを使用する方法
「樽バネ」は、ダンガンレーサー用として使われていたバネで、樽状の形をしています。
メリット:
- センターシャーシの軸をそのまま使用できる
- バネ自体の加工が不要
- 取り付けが比較的簡単
デメリット:
- 一般的なGUPとして販売されていないため入手しにくい
- タミヤの公式大会の物販などで購入する必要がある
樽バネを使用する場合は、センターシャーシの軸加工は不要で、そのままバネを取り付けることができます。耐久性も高く、初心者にもおすすめの方法です。
2. スライドダンパースプリングを拡張する方法
一般的に販売されているスライドダンパースプリングを拡張して使用する方法です。
メリット:
- 手に入りやすいパーツで作成可能
- 特別な治具なしでも作れる
- スプリングの硬さを選べる(ソフト・ハードなど)
拡張方法:
- 約5mmの太さのドライバーにスプリングを通す
- 24時間ほど放置してスプリングを拡張させる
- 拡張したスプリングをセンターシャーシの軸に取り付ける
スプリングの拡張は手軽にできる方法ですが、拡張のムラが出ると左右で動きに差が出る可能性があります。また、拡張したスプリングは時間が経つと元のサイズに戻る傾向があるため、定期的なメンテナンスが必要になることもあります。
3. 軸を加工してスプリングを使用する方法
センターシャーシの軸を細く加工し、通常のスプリングを取り付ける方法です。
メリット:
- スプリングの拡張が不要
- 安定した動作が期待できる
デメリット:
- 軸加工用の治具が必要
- 加工の精度が重要
- 技術的な難易度が高い
軸加工には専用の治具を使用するのが一般的ですが、一度治具を入手すれば繰り返し使用できるため、長期的にはコスト効率が良いと言えます。軸を均等に削ることで、左右のバランスの良いフレキを作ることができます。
バネ選びのポイント:
- 硬さ:スライドダンパースプリングにはソフト(黒)とハード(銀)がありますが、MSフレキにはソフトの方が適しています。ソフトバネの方が柔軟に動くため、衝撃吸収効果が高くなります。
- 長さの調整:バネは必要に応じて1周半程度切り取ることで、柔らかさを調整できます。切り取る量が多いほど柔らかくなりますが、耐久性は低下します。
- 減衰ゴムの併用:バネだけだと反発が強すぎる場合は、Oリングなどを利用した減衰ゴムを併用することで、より滑らかな動きを実現できます。
実際のレース環境や好みのセッティングに合わせて、これらの方法から最適なものを選択するとよいでしょう。初心者であれば、まずは樽バネかスプリング拡張の方法から始めることをおすすめします。
お辞儀防止プレートの作成はFRPプレートが最適である
MSフレキでは、シャーシが3分割されることによって前後ユニットが不安定になり、「お辞儀」と呼ばれる状態(前後ユニットが下がってしまう現象)が発生します。これを防ぐために必要なのが「お辞儀防止プレート」です。
お辞儀防止プレートの役割:
- 前後ユニットの安定性を確保する
- ギヤ同士の噛み合わせを適切に保つ
- マシン全体の剛性を維持する
お辞儀防止プレートの材質としては、FRP(ファイバーリインフォースドプラスチック)が最も一般的です。その理由は以下の通りです:
FRPプレートの利点:
- 適度な剛性:硬すぎず柔らかすぎない適度な剛性を持ち、フレキの動きを妨げない
- 加工のしやすさ:ニッパーやヤスリでの加工が容易
- コスパの良さ:カーボンプレートと比較して価格が安い
- 重量バランス:軽すぎず重すぎず、マシンのバランスに適している
具体的なお辞儀防止プレートの作成方法は以下の通りです:
1. 材料の選択
以下のFRPパーツがお辞儀防止プレートに適しています:
- FRPマルチワイドステー
- ARシャーシリヤワイドステー
- スーパーXシャーシ用のリヤステー
初心者の場合は、FRPマルチ補強プレートを「=」型にカットして使用する方法もコスト効率が良いです。
2. 形状のカット
プレートをギヤ部分と干渉しないよう「コ」の字型や「=」型にカットします。ニッパーで大まかに切り取った後、ヤスリで丁寧に形を整えます。
3. バリ取りと表面処理
切断面のバリを取り除き、必要に応じて紙ヤスリで表面を磨きます。FRPの断面には瞬間接着剤を薄く染み込ませると強度が増します。
4. 取り付け
お辞儀防止プレートは、前後ユニットとセンターシャーシを繋ぐビスで同時に固定します。通常は12mm~13mmのビスが適しています。
お辞儀防止プレート作成時の注意点:
- ギヤとの干渉を避ける:ギヤの動きを妨げないよう、適切な形状にカットすることが重要です。
- 左右のバランス:左右対称に加工することで、マシンのバランスを保ちます。
- 強度と柔軟性のバランス:プレートが硬すぎるとフレキの動きを妨げ、柔らかすぎるとお辞儀防止の効果が薄れます。
- ザグリ加工の検討:皿ビスを使用する場合は、プレートにザグリ加工を施すとよりスッキリとした仕上がりになります。ただし、ザグリを施すとプレートの強度が落ちるため、バランスを考慮する必要があります。
FRPプレートの代わりにカーボンプレートを使用することもできますが、コストが高くなる上、加工が難しくなります。初心者の方はまずFRPプレートでの作成をマスターしてから、必要に応じてカーボンプレートにステップアップするとよいでしょう。
グリスアップと組み立てはスムーズな動きを確保するために丁寧に行う
MSフレキの性能を最大限に引き出すためには、グリスアップと組み立ての作業が非常に重要です。この工程で動きの滑らかさが決まり、マシン全体の性能に直結します。
グリスアップのポイント:
- 使用するグリス 最適なのは「HGスライドダンパーグリス」のエクストラハードタイプです。硬めのグリスを使用することで、適度な減衰効果が得られます。
- グリスを塗る箇所
- センターシャーシのスプリングが入る部分
- 前後ユニットのセンターシャーシと接触する面
- お辞儀防止プレートの接触面
- 塗布量 多すぎると周囲に漏れ出し、少なすぎると効果が薄いので適量を心がけます。爪楊枝や綿棒を使って細部まで丁寧に塗りましょう。
組み立て手順:
- バネの準備 必要に応じてバネを1周~1周半カットし、減衰ゴムを取り付けます。これにより、バネの反発が抑えられ、より滑らかな動きが実現します。
- バネの取り付け バネをセンターシャーシの軸(または軸の位置)にセットします。軸残しの場合は、バネの位置がずれないよう注意が必要です。
- 前後ユニットの取り付け グリスを塗った前後ユニットをセンターシャーシに合わせます。この時、バネが正しい位置に収まっているか確認しましょう。
- お辞儀防止プレートの設置 前後ユニットとセンターシャーシを合わせた状態で、お辞儀防止プレートを上から被せます。
- ビス・ナットでの固定 適切な長さのビス(通常は10~13mm)で全体を固定します。ロックナットを使用すると、走行中の緩みを防止できます。
組み立て時の確認ポイント:
- 動作の確認 組み立て後は必ず動作確認を行い、前後ユニットがスムーズに上下動するか確認します。引っかかりがある場合は、干渉している箇所を特定して追加の調整を行います。
- ギヤの噛み合わせ フレキが動いた状態でもギヤがしっかり噛み合っているか確認します。お辞儀防止プレートの位置が不適切だと、ギヤの噛み合わせが悪くなり、パワーロスの原因になります。
- バネの動き バネが圧縮・伸長する際にスムーズに動くか確認します。バネの動きが渋い場合は、バネの長さや減衰ゴムの調整、グリスの塗り直しなどで対応します。
仕上げのポイント:
- 隙間のシーリング T字部分などカットした箇所は、グリスの漏れを防ぐためにマルチテープなどでシーリングしておきます。
- ビスの締め付け具合 きつく締めすぎるとフレキの動きが悪くなり、緩すぎるとガタつきの原因になります。適切な締め付け具合を見つけることが重要です。
- 試走と調整 実際に走らせてみて、マシンの挙動を確認します。必要に応じてグリスの量や減衰ゴムの有無、バネの硬さなどを調整していくことで、理想的なMSフレキに仕上げることができます。
適切なグリスアップと丁寧な組み立てを行うことで、MSフレキの性能を最大限に引き出し、安定した走行を実現できます。特に初めてMSフレキを作る場合は、慌てずに各ステップを確実に行うことが成功の鍵となります。
軸残しMSフレキの作り方はバネの固定と精度がカギ
軸残しMSフレキは、センターシャーシの軸を残したまま加工する方法で、初心者から上級者まで幅広く採用されています。この方法の最大の特徴は、バネが軸に固定されるため安定性が高く、耐久性にも優れている点です。ここでは、軸残しMSフレキの具体的な作り方を解説します。
軸残しMSフレキの加工手順:
- センターシャーシの切断 前述の通り、センターシャーシをギヤカバーの付け根でカットします。この際、軸を残す方法では軸部分はそのまま残しておきます。
- 軸の高さ調整 軸をそのままの高さで使用するとバネが入らない、または動きが悪くなる可能性があります。そこで「軸ちょっと残し」と呼ばれる加工を行います。 具体的な方法:
- 1.5mmアルミスペーサーを軸の横に並べる
- アルミスペーサーと同じ高さになるよう軸をニッパーでカットする
- カット面をヤスリで整える
- バネの取り付け スライドダンパースプリングセットの黒いバネ(ソフトタイプ)を使用します。バネをうまく軸に取り付けるには以下の方法があります:
- バネを若干拡張して取り付ける(5mm径のドライバーなどに巻いて24時間放置する)
- バネを1周半程度カットして柔らかくする
- 軸に少し力を加えてバネをはめ込む
- 減衰ゴムの追加(オプション) バネだけだと跳ねる可能性があるため、減衰ゴムを追加するとより滑らかな動きになります。Oリングを6.6mmから約5.4mmに削り、それを半分に切って減衰ゴムとして使用します。
- 前後ユニットの加工 前述の通り、前後ユニットの接続穴を5.5mmのドリルで拡張し、干渉する部分を削ります。軸残しの場合、穴を貫通させないよう特に注意が必要です。
- 組み立て
- 減衰ゴムを6.7mmアルミスペーサーに通してバネの中に入れる
- グリスをバネと接触面に塗る
- 前後ユニット、お辞儀防止プレート、ワッシャー、ビスの順に組み立てる
軸残しMSフレキ作成のポイント:
- 軸の高さ調整の精度 軸の高さが左右で異なると、フレキの動きにムラが出てしまいます。アルミスペーサーなどを基準にすることで、精度の高い加工が可能になります。
- バネの固定性 軸残しの最大のメリットはバネがしっかり固定されることです。バネがズレないよう、適切に軸にはめ込むことが重要です。
- ビスの長さ選び 軸残しの場合、ビスの長さも重要です。理想的には13mmのビスを使用し、ビスの先端が軸の根本内に収まるようにします。これによりビスが上に突き出ることがなく、また軸がビスをしっかり止めてくれるので緩みにくくなります。
- グリスの塗布 軸残しの場合、特に軸とバネの接触部分にグリスをしっかり塗ることで、動きがスムーズになります。
- 減衰調整 軸残しMSフレキでは、バネと減衰ゴムの組み合わせによる減衰調整が可能です。コースや走行スタイルに合わせて調整すると、より高いパフォーマンスが得られます。
軸残しMSフレキは、適切に作れば非常に安定した性能を発揮します。特に耐久性を重視する方や、シンプルな構造を好む初心者の方におすすめの方法です。加工の難易度も比較的低く、一度マスターすれば短時間で作成できるようになります。
ミニ四駆MSフレキ作り方で使う治具は必要に応じて選択する
MSフレキを作る際、より精度の高い加工を行うための「治具」があります。治具を使うことで再現性の高い加工が可能になりますが、初心者の場合は必ずしも必要というわけではありません。ここでは、MSフレキ作成に役立つ治具の種類と、それぞれの必要性について解説します。
主なMSフレキ用治具の種類:
- シャーシカット用治具 センターシャーシをカットする際に使用する治具です。シャーシを固定し、正確な位置でまっすぐカットするのに役立ちます。 メリット:
- 再現性の高いカットが可能
- 左右対称の精度の高いカットができる
- 初心者でも失敗が少ない
- 軸加工用治具 センターシャーシの軸を均等に細くする際に使用する治具です。樽バネを使わず、通常のスライドダンパースプリングを使用する場合に必要になります。 メリット:
- 軸を均等に細くできる
- 左右均等な加工が可能
- スプリングの拡張が不要
- 穴拡張用ガイド 前後ユニットの穴を拡張する際のガイドとなる治具です。穴の位置や深さを一定に保つのに役立ちます。 メリット:
- 穴の位置や深さが均一になる
- 貫通のリスクが減少する
- スプリング拡張用治具 スライドダンパースプリングを拡張するための治具です。ドライバーなどの円柱状のものでも代用可能です。 メリット:
- スプリングを均等に拡張できる
- 作業効率が上がる
- 減衰ゴム作成用治具 Oリングから減衰ゴムを作成するための治具です。モーターとシャーシを利用した簡易的な治具で作ることも可能です。 メリット:
- 均一な大きさの減衰ゴムが作れる
- 作業効率が上がる
治具の選択ポイント:
- 自分の技術レベル 初心者の場合、シャーシカット用治具は精度向上に役立ちますが、他の治具は必ずしも必要ではありません。技術が向上するにつれて、より精密な加工が必要になった場合に追加していくのも良いでしょう。
- 作成頻度 頻繁にMSフレキを作る予定がある場合は、治具への投資も検討する価値があります。一度だけの場合は、必要最低限の治具にとどめるか、代用品を活用するのが効率的です。
- コスト 専用治具は便利ですが、コストがかかります。予算に応じて、必要性の高いものから導入していくとよいでしょう。
- MSフレキの種類 軸残しタイプと軸なしタイプでは必要な治具が異なります。また、樽バネを使用するか通常のスプリングを使用するかによっても、必要な治具は変わってきます。
治具なしでMSフレキを作る場合のポイント:
- 正確な計測 治具がなくても、定規やマスキングテープを使った正確な計測により、精度の高い加工が可能です。
- 丁寧な作業 急がず丁寧に作業することで、治具なしでも高品質なMSフレキを作ることができます。
- 段階的な加工 一度に大きく削るのではなく、少しずつ加工して動作確認を繰り返す方法が、治具なしでも失敗を防ぐコツです。
治具は確かに便利ですが、必ずしも全てが必要というわけではありません。自分の技術レベルやニーズに合わせて、必要な治具を選択することが大切です。初めてMSフレキを作る場合は、まずは基本的な工具で挑戦し、必要に応じて治具を追加していくのがおすすめです。
MSフレキのデメリットはガタつきと調整の難しさ
MSフレキは多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。これらを理解した上で対策を講じることで、より良いマシン作りが可能になります。ここではMSフレキの主なデメリットと、その対策について解説します。
MSフレキの主なデメリット:
- ガタつきの発生 MSフレキは構造上、パーツ間に隙間が生じやすく、これがガタつきの原因となります。特に加工精度が低い場合や使用するうちに摩耗が進むと、ガタつきが顕著になります。 対策:
- 加工時の精度を高める(特にセンターシャーシと前後ユニットの接続部)
- お辞儀防止プレートの材質や厚みを適切に選ぶ
- ビスやナットの締め付け具合を適正に保つ
- 定期的なメンテナンスでグリスの塗り直しや部品の摩耗チェックを行う
- 調整の難しさ MSフレキは様々な要素(バネの硬さ、グリスの種類と量、減衰ゴムの有無など)が複雑に絡み合うため、理想的な動きにするための調整が難しいことがあります。 対策:
- 一度に複数の要素を変更せず、一つずつ調整して効果を確認する
- 走行テストを繰り返し、データを取りながら調整する
- 経験者のアドバイスを参考にする
- コースに合わせた調整方法を学ぶ
- 重量の増加 MSフレキは追加のパーツ(お辞儀防止プレート、スペーサー、ワッシャーなど)が必要なため、ノーマルのMSシャーシと比較すると若干重くなります。 対策:
- 可能な限り軽量なパーツを選択する
- 必要最低限のパーツ構成にする
- カーボン製のお辞儀防止プレートを使用する(予算や技術レベルに余裕がある場合)
- 破損リスクの増加 シャーシが分割されることで、特定の箇所に負荷がかかりやすくなり、破損リスクが高まることがあります。 対策:
- 適切な材質のパーツを使用する
- 走行中の衝撃が大きい箇所を補強する
- 定期的に部品の状態をチェックし、損傷が見られたら交換する
- メンテナンス頻度の増加 可動部分が増えるため、ノーマルシャーシと比較してメンテナンスの頻度が増えます。特にグリスの塗り直しや部品の摩耗チェックが重要になります。 対策:
- 定期的なメンテナンススケジュールを設ける
- 予備パーツを用意しておく
- 走行後のクリーニングを徹底する
- 作成・調整に時間がかかる MSフレキの作成と調整には、ある程度の時間と手間がかかります。特に初めて作る場合は、予想以上に時間がかかることがあります。 対策:
- 十分な時間を確保して作業する
- 焦らず段階を踏んで進める
- 作業の手順を事前に理解しておく
これらのデメリットは、MSフレキを使用する上で完全に避けることは難しいものの、適切な対策を講じることで影響を最小限に抑えることができます。特に初心者の場合は、最初から完璧を目指すのではなく、徐々に改良していく姿勢が大切です。
また、MSフレキのデメリットを認識した上で、自分のレーススタイルやコース条件に本当にMSフレキが必要かどうかを判断することも重要です。場合によっては、ノーマルシャーシやスライドダンパーなど、他の方法の方が適している場合もあります。
初心者向けのMSフレキはバンパーレスユニットの活用がおすすめ
MSフレキ作りに初めて挑戦する方には、「バンパーレスユニット」を活用する方法がおすすめです。バンパーレスユニットとは、あらかじめバンパー部分がカットされたパーツで、MSフレキ作りの手間を大幅に削減できます。
バンパーレスユニットの特徴:
- 加工の手間を省ける 通常のMSフレキ作りでは、バンパーカットという作業が必要になりますが、バンパーレスユニットはこの工程が不要です。特にバンパーカットは精度が求められる作業のため、これを省略できる意義は大きいです。
- ATバンパーやアンカーとの相性が良い バンパーレスユニットは、ATバンパーやリヤアンカーなどのギミックバンパーと組み合わせやすい設計になっています。バンパーの取り付けがスムーズに行えるため、初心者でも高機能なマシンを作りやすくなります。
- 正確さと再現性 工場で精密に加工されているため、自分で加工するよりも正確さと再現性が高いです。左右のバランスも良く、安定したパフォーマンスを期待できます。
バンパーレスユニットを使ったMSフレキの作り方:
- 必要なパーツ
- バンパーレスユニット(前後)
- 軽量センターシャーシ
- スライドダンパースプリングセット
- FRPプレート(お辞儀防止用)
- ビス・ナット類
- 組み立て手順
- センターシャーシはそのまま使用(カット不要)
- バンパーレスユニットの穴を5.5mmドリルで拡張
- 軸加工またはスプリング拡張の準備
- お辞儀防止プレートの作成
- グリスアップと組み立て
- 仕上げのポイント
- ATバンパーやリヤアンカーなどのギミックバンパーを取り付け
- 各部の可動確認と調整
- グリスの漏れ防止のためのテーピング
バンパーレスユニットを使うメリット:
- 時間と労力の節約 バンパーカットや細かい加工が不要なため、MSフレキ作りの時間と労力を大幅に節約できます。特に初心者にとっては、失敗リスクの低減にもつながります。
- 精度の高さ 工場で精密に加工されているため、自分で加工するよりも精度が高く、安定したパフォーマンスを期待できます。
- 拡張性の高さ 標準的なギミックパーツとの互換性が高いため、様々なセッティングを試しやすいです。マシンの進化に合わせて、パーツを追加・変更しやすい構造になっています。
バンパーレスユニットの入手方法:
バンパーレスユニットは、タミヤの公式パーツとして販売されています。オンラインショップやミニ四駆を扱うホビーショップで購入可能です。価格は通常のユニットより若干高めですが、加工の手間を考えると十分コストパフォーマンスが良いと言えます。
なお、バンパーレスユニットを使ったMSフレキは、タミヤの公式ガイドブックでも紹介されている正式な改造方法です。大会でも使用可能ですので、初心者の方は安心して取り組むことができます。
独自調査の結果、バンパーレスユニットを使ったMSフレキは、初心者が短時間で効果的なマシンを作るための最適な選択肢の一つと言えるでしょう。失敗を恐れずにまずは取り組んでみることをおすすめします。
減衰ゴムの追加でMSフレキの性能をさらに向上させる
MSフレキの性能をさらに高めるためのオプション改造として、「減衰ゴム」の追加があります。減衰ゴムはバネの反発を抑え、より滑らかな動きを実現するためのパーツです。ここでは、減衰ゴムの効果と作り方、使い方について解説します。
減衰ゴムの効果:
- バネの反発抑制 バネだけだと、衝撃を受けた後に反発して跳ね返る可能性があります。減衰ゴムはこの反発を抑える役割を果たし、より滑らかな動きを実現します。
- 沈み込みの調整 減衰ゴムの硬さや形状を変えることで、フレキの沈み込み具合を調整できます。コースや走行スタイルに合わせた微調整が可能になります。
- 振動の吸収 コース走行中の細かな振動も効果的に吸収し、マシンの安定性をさらに向上させます。
減衰ゴムの作り方:
- 材料の準備
- Oリング(直径約6.6mm程度)
- ニッパーまたはハサミ
- 「しめ縄君の残骸」または簡易的な旋盤装置(削る際に使用)
- Oリングの加工
- Oリングを約5.4mmの太さに削る
- 削る方法として、モーターにピニオンギアを取り付け、そこにOリングをセットして回転させながらヤスリで削るという方法があります
- または、直径5.4mm程度の円柱状のものにOリングをはめて、そのまま少し伸ばすことでも代用可能です
- Oリングの分割
- 加工したOリングを中央でカットし、2つに分割します
- 1つのOリングから2個の減衰ゴムが作れます
減衰ゴムの使い方:
- 設置場所 減衰ゴムはバネの内側に設置します。具体的には以下の順序で組み込みます:
- センターシャーシの軸(または軸の位置)
- グリス(1回目)
- 減衰ゴム(開いている方を下向きに)
- グリス(2回目)
- バネ(必要に応じて切断したもの)
- 減衰ゴムの向き 減衰ゴムの開いている部分を下に向けて設置するのが一般的です。これにより、バネの動きに合わせて減衰ゴムが自然に変形し、効果的に機能します。
- グリスとの併用 減衰ゴムとグリスを併用することで、より効果的な減衰が得られます。グリスはHGスライドダンパーグリスのエクストラハードがおすすめです。
減衰ゴムのバリエーション:
- 硬さの調整
- 硬めのOリングを使うと減衰効果が強くなり、柔らかいものを使うと弱くなります
- 材質による違いもあるため、複数の種類を試してみるのも良いでしょう
- 厚みの調整
- Oリングの削り加減で厚みを調整できます
- 厚みが増すほど減衰効果も強くなります
- 組み合わせ
- バネの硬さと減衰ゴムの効果を組み合わせることで、様々な走行特性を実現できます
- 例えば、柔らかいバネと硬めの減衰ゴムの組み合わせなど
減衰ゴム使用時の注意点:
- 過剰な減衰に注意 減衰が強すぎると、フレキ本来の効果が失われてしまうことがあります。適度な減衰を心がけましょう。
- 定期的な交換 減衰ゴムは使用していくうちに劣化します。性能低下を感じたら交換することをおすすめします。
- 実走テスト 減衰ゴムの効果は理論だけでは判断しにくい面もあります。実際に走らせてみて、自分のマシンに最適な設定を見つけましょう。
減衰ゴムはMSフレキの性能を一段階向上させる有効な手段です。特に高速コースや起伏の激しいレイアウトでは、その効果が顕著に表れます。自分のマシンとコース条件に合わせて、ぜひ試してみてください。
軸残しMSフレキのメリットは耐久性と組み立ての簡単さ
MSフレキの作り方にはいくつかのバリエーションがありますが、中でも「軸残し」タイプは多くのレーサーに支持されています。ここでは、軸残しMSフレキの具体的なメリットと、他の方法との比較について解説します。
軸残しMSフレキの主なメリット:
- 優れた耐久性 センターシャーシの軸を残すことで、構造的に強度が保たれます。特に激しいコース条件や長時間の走行でも、パーツの破損リスクが低減されます。実際のレース環境では、耐久性の高さが安定した走行につながります。
- バネの固定性が高い 軸にバネを固定できるため、走行中にバネがズレるリスクが少なくなります。これにより、フレキの動作が安定し、一定のパフォーマンスを維持しやすくなります。
- 組み立ての簡単さ 軸を残すことで、バネや減衰ゴムの位置決めが容易になります。特に初心者にとっては、パーツの配置が分かりやすく、組み立てミスを防ぎやすいというメリットがあります。
- メンテナンス性の良さ 分解・組み立てを繰り返す際も、軸がガイドの役割を果たすため、正確に元の状態に戻すことができます。定期的なメンテナンスが必要なMSフレキにとって、これは大きなメリットです。
- ビスの固定力向上 軸残しの場合、ビスの先端が軸の根本に収まるため、ビスがより強固に固定されます。これにより、走行中のビスの緩みが防止され、安定した走行が可能になります。
他の方法との比較:
| 比較項目 | 軸残しタイプ | 軸なしタイプ |
|---|---|---|
| 耐久性 | 高い | やや低い |
| バネの固定性 | 高い | 低い(ズレやすい) |
| 組み立ての簡単さ | 簡単 | やや難しい |
| フレキの柔軟性 | やや制限される | 高い |
| ガタつきの発生 | 少ない | 発生しやすい |
| 加工難易度 | 中程度 | やや簡単 |
| メンテナンス頻度 | 少ない | 多い |
軸残しMSフレキに向いているシチュエーション:
- 初めてMSフレキを作る場合 軸残しタイプは構造がシンプルで理解しやすく、初心者にとって取り組みやすい方法です。
- 耐久性重視の場合 長時間の走行や激しいコース条件で使用する場合、耐久性の高い軸残しタイプが適しています。
- 安定した走行を求める場合 バネの固定性が高く、ガタつきが少ないため、安定した走行特性を求める場合におすすめです。
- メンテナンス頻度を抑えたい場合 頻繁なメンテナンスが難しい場合や、長期間安定した性能を維持したい場合に適しています。
軸残しMSフレキを選ぶ際の注意点:
- バネの選択 軸残しの場合、通常のスライドダンパースプリングをそのまま使用するのは難しいため、樽バネを使用するか、スプリングを拡張する必要があります。
- 軸の高さ調整 完全な軸残しではなく、「軸ちょっと残し」と呼ばれる方法で軸の高さを調整することで、バネの装着と動きのスムーズさを両立できます。
- 加工精度の重要性 軸の高さや形状の精度がフレキの動きに直接影響するため、丁寧な加工が求められます。特に左右のバランスに注意が必要です。
軸残しMSフレキは、その耐久性と組み立ての簡単さから、特に初心者からベテランまで幅広く支持されている方法です。MSフレキ作りに初めて挑戦する方は、まずは軸残しタイプから始めることをおすすめします。経験を積んだ後、必要に応じて他の方法も試してみるとよいでしょう。
まとめ:ミニ四駆MSフレキ作り方は段階的な加工と丁寧な組み立てがポイント
最後に記事のポイントをまとめます。
- MSフレキはMSシャーシを3分割し、バネを組み込むことで走行安定性を向上させる改造
- センターシャーシ加工はギヤカバー部分のカットから始まり、精度が重要
- 前後ユニットの加工は干渉を避けるための削りが必須で、特に接続穴の拡張が重要
- MSフレキ用のバネは樽バネ・拡張バネ・軸加工の3種類があり、状況に応じて選択する
- お辞儀防止プレートはFRPプレートが最適で、ギヤとの干渉を避ける形状に加工する
- グリスアップと組み立ては丁寧に行い、スムーズな動きを確保することが大切
- 軸残しMSフレキはバネの固定性と耐久性に優れ、初心者にもおすすめ
- 治具は必要に応じて選択し、初心者は代用品で十分対応可能
- MSフレキのデメリットはガタつきと調整の難しさだが、適切な対策で解決できる
- 初心者向けのMSフレキはバンパーレスユニットの活用が簡単で効果的
- 減衰ゴムを追加することでMSフレキの性能をさらに向上させられる
- 軸残しMSフレキは耐久性と組み立ての簡単さが最大のメリット
- MSフレキ作りは段階的な加工と丁寧な組み立てが成功の鍵
- コースや走行スタイルに合わせてバネの硬さやグリスの種類を調整するとより効果的
- 大会使用時はグリスの飛散防止など、ルールに沿った加工が必要