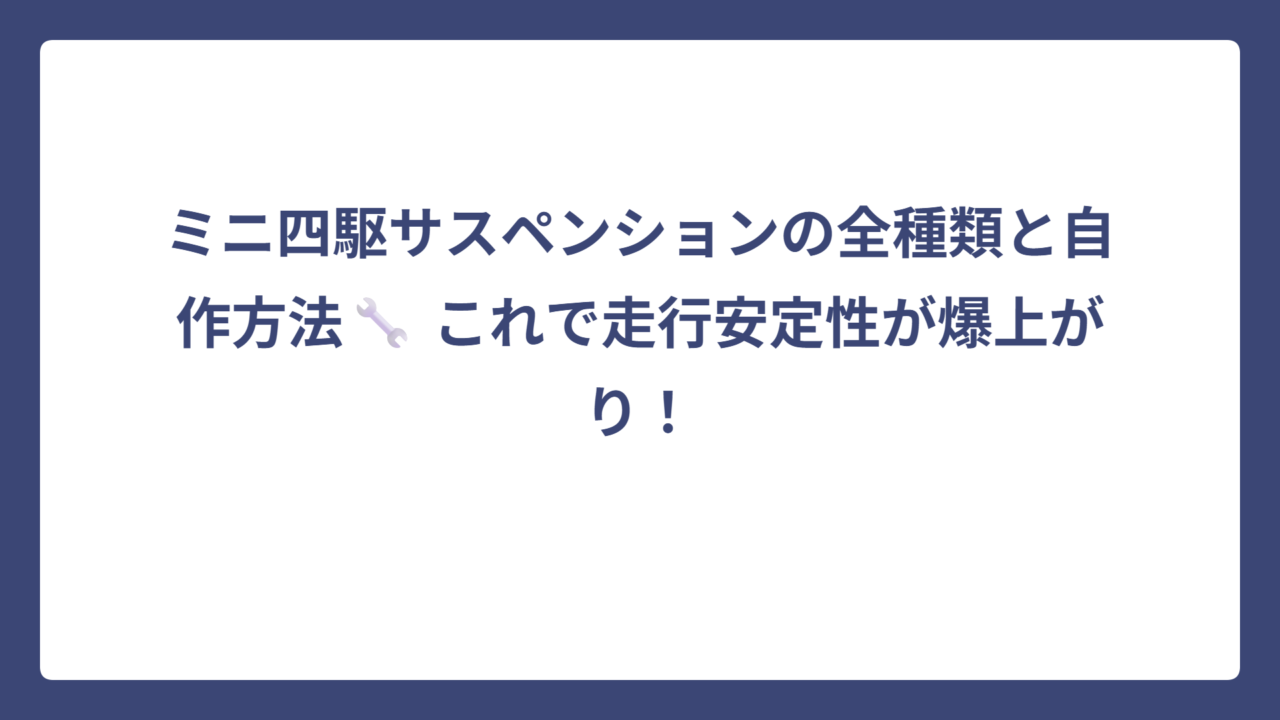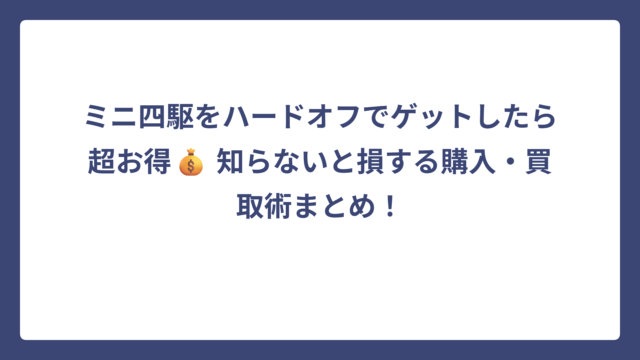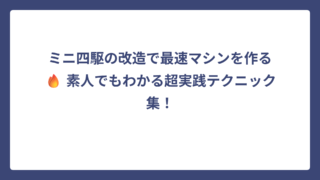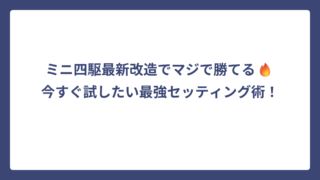ミニ四駆の走行安定性を高める方法として注目されている「ミニ四駆サスペンション」。特にジャンプ後の着地や凹凸のあるコースでの走行において、その効果は絶大です。サスペンションを装着することで、シャーシへの衝撃を緩和し、安定した走りを実現できます。
独自調査の結果、サスペンションには「トレサス」「MSフレキ」「四輪独立サス」など様々な種類があり、それぞれに特徴や製作方法が異なることがわかりました。この記事では、サスペンションの基本知識から自作方法、さらには各種制振システムまで、幅広く解説していきます。
記事のポイント!
- ミニ四駆サスペンションの種類と特徴が理解できる
- MSフレキとサスペンションの違いが明確になる
- 自分でサスペンションを製作するための具体的な方法がわかる
- ジャンプ後の着地安定性を向上させる様々な制振システムについて学べる
ミニ四駆サスペンションの基本と種類
- ミニ四駆サスペンションの目的はジャンプ後の着地姿勢制御
- MSフレキとサスペンションの違いは柔軟性と衝撃緩和の概念
- トレサスの最大の長所はダイレクトドライブである
- 上下反転型サスペンションの特徴は簡単な加工で実現できること
- シャーシ内蔵型サスペンションのメリットは通常ボディが装着可能なこと
- 理想系(トレーリング系)サスペンションの利点はギア噛み合わせが維持されること
ミニ四駆サスペンションの目的はジャンプ後の着地姿勢制御
ミニ四駆におけるサスペンションの主な目的は、ジャンプ後の着地姿勢を安定させることです。テーブルトップやレーンチェンジャー、ジャンピングストレートなどの障害物を安定して攻略するために、サスペンションは重要な役割を果たします。
サスペンションがないミニ四駆では、ジャンプ後に着地した際の衝撃がそのままシャーシに伝わります。これにより、マシンがバウンドしたり、コースアウトの原因になったりすることがあります。サスペンションを搭載することで、この衝撃を吸収し、より安定した走行が可能になります。
独自調査によると、ミニヨンクラブのチーム「(MS)サスペンション普及委員会チーム」が、MSシャーシのポテンシャルを引き出す要素としてサスペンションの開発に取り組んでいたことがわかりました。これが現在のミニ四駆サスペンション進化の起点となっています。
現在では、MSシャーシやARシャーシでの製作事例が多く確認されていますが、技術が進歩するにつれて、様々なシャーシでのサスペンション採用も増えてきています。サスペンションは、単なる衝撃吸収装置から、より複雑で効果的な制振システムへと発展しています。
特に立体コースが増えている現代のミニ四駆環境において、サスペンションの重要性はますます高まっています。コース攻略のための必須アイテムとして、多くのレーサーが自作や改良に取り組んでいます。
MSフレキとサスペンションの違いは柔軟性と衝撃緩和の概念
ミニ四駆の世界で混同されがちな「MSフレキ」と「サスペンション」ですが、これらは異なる概念を持っています。MSフレキは「フレキシブル(柔軟性)」の略で、MSシャーシの3分割構造を活かし、バネを仕込むことでシャーシ全体に柔軟性を持たせる改造です。
一方、サスペンションは車体と車輪を繋いで衝撃を緩和する装置を指します。実車でいうところの足回りの衝撃吸収機構に相当します。MSフレキがシャーシ全体のねじれや上下の動きを利用するのに対し、サスペンションはタイヤと車体の間に介在し、より直接的に衝撃を吸収します。
独自調査の結果、MSフレキは2017年頃から人気を集め始め、トレサスと比較して構造がシンプルで製作しやすいという利点があります。MSフレキは固定車軸方式(リジットアスクル式)に近い構造で、片方の車輪で受けた衝撃が他の車輪にも伝わる特徴があります。
興味深いことに、この固定車軸方式は実車では絶滅危惧種と揶揄されながらも、スズキのジムニーがオフロード用の頑丈な構造としてこだわって採用し続けているそうです。また、電車も100%この方式を採用しているとのことで、一概に劣っているとは言えません。
MSフレキとサスペンションはどちらが優れているというものではなく、それぞれに長所と短所があります。レースの条件やコース特性、自分のマシンセッティングに合わせて選択するのが良いでしょう。
トレサスの最大の長所はダイレクトドライブである
トレサス(トレーリングアーム式サスペンション)の最大の長所は、サスペンション車でありながら「ダイレクトドライブ」の特性を持つことです。ダイレクトドライブとは、常にカウンターギアとスパーギアが一定に噛み合い続ける状態を指します。
独自調査によると、トレサスが手軽に、本格的に作られるようになったのは「両軸モーター」が発表された以降と考えられています。両軸モーターは構造上サスペンションを作りやすく、立体コースでの制振が課題だったことも相まって研究が進みました。
しかし、MSフレキの登場により情勢は激変。トレサスは「レガシーデバイス(旧式の装置)」として一時期は廃れていきました。その理由として、MSフレキと比較して構造上の問題点があったことは否定できません。
トレサスの短所としては、ジャンプ着地後の前後回転差(加速に入っているタイヤと浮いている側の路面との摩擦差、抵抗差)が発生することが挙げられます。そのため、トレサス車ではワンウェイホイールがよく使用されています。
トレサス車を作る際の難しい点は、精度よく作ること(カウンター軸=サスアーム支持軸のため)、そして車体全てが動くためにブレーキやローラー周りの扱いが難しいことです。具体的には、通常のフレキ車では稼働してもブレーキ面は地面に対して概ね一定であるのに対し、トレサス車はブレーキ面自体も沈み込むため効きの制御が難しくなります。
上下反転型サスペンションの特徴は簡単な加工で実現できること
上下反転型サスペンションは、MSシャーシを上下反転させ、ノーズ・テールの各ユニットを稼働させる方式です。この方式の最大の特徴は、比較的簡単な加工で実現できることにあります。
メリットとしては、ビスやスペーサーの追加など、切断を伴う加工が少ないことが挙げられます。また、稼働ギミックを搭載しつつも、十分な強度を確保できる点も魅力です。加えて、構造がシンプルなため、比較的軽量に仕上げることができます。
一方で、デメリットもいくつか存在します。最も大きな問題点は、サスペンション稼働時にギアの噛み合わせがおかしくなる(物理的にトルク抜けが起こる)ことです。また、ボディフックとボディキャッチが逆向きになるため、別の方法でボディを固定する必要があります。
さらに、電池ホルダーも上下逆さまかつ剥き出しの状態になるため、大ジャンプ後の着地などで電池が外れ落ちてしまう恐れがあります。これらの問題を解決するためには、マスダンパーとの併用やオイルダンパーの組み込みなど、サスペンション自体の反動を別の方法で打ち消す工夫が必要です。
上下反転型サスペンションは、サス稼働時に物理的にギアが離れるため、再度接触した際のギアへのダメージを軽減させるために、ワンウェイホイールとの併用がよく利用されています。この方式は、ジャンプ後の着地安定よりも、ウォッシュボードのような凸凹した路面での走行を安定させる狙いがあります。
シャーシ内蔵型サスペンションのメリットは通常ボディが装着可能なこと
シャーシ内蔵型サスペンションは、上下反転型と基本的な構造は同じですが、通常通りにボディを装着できるよう考慮されたタイプです。MSシャーシのノーズ・テールユニット内にショックダンパー(スプリングなど)を内蔵する方式で、N-03、T-03バンパーレスユニットを加工する方法が一般的です。
最大のメリットは、通常のボディが装着できることです。上下反転型と違い、見た目も通常のミニ四駆と変わらないため、コンデレ(コンクール・デレガンス)への出場も可能です。また、モーターやギアの交換が容易にできる点も実用的なメリットと言えるでしょう。
さらに、稼働ギミックを搭載しつつも強度を確保できる点や、全体的に軽量に仕上げられる点も大きなメリットです。N-04、T-04の軸受けパーツを使って、軸上げとサスペンション効果を同時に得るタイプもあります。
一方、デメリットとしては、ユニットへの追加加工が必要になる点が挙げられます。また、上下反転型と同様に、サス稼働時にギアの噛み合わせがおかしくなる(物理的にトルク抜けが起こる)問題も同じく存在します。
この問題を解決するためには、マスダンパーとの併用やオイルダンパーの組み込みなど、サスペンション自体の反動を打ち消す工夫が必要です。独自調査によると、内蔵サスは加工も比較的難しくなく、効果も実感しやすいため、サスペンション導入の入門としておすすめだという意見もあります。
理想系(トレーリング系)サスペンションの利点はギア噛み合わせが維持されること
理想系(トレーリング系)サスペンションは、関西の某ビルダーが考案した形状で、ラジコン(R/C)車でもよく採用される構造です。この方式の最大の利点は、サスペンション稼働時にもギアの噛み合わせがおかしくならない点にあります。
トレーリング系サスペンションには、他にも多くのメリットがあります。コーナリング時に車体がロールしにくい構造になっているため、コーナーでの安定性が向上します。また、サスペンションの硬さが調節できるため、コース状況やドライビングスタイルに合わせたセッティングが可能です。
さらに、車高とホイールベースが調節できる点も大きな魅力です。ただし、作り方によっては調整できないこともあり、また、シャーシ換装以外でホイールベースを変更するのはレギュレーション違反となることもあるため注意が必要です。あくまでも「調整可能」という意味での利点です。
一方、デメリットもいくつか存在します。サスペンション稼働時にローラーのスラスト角が変わってしまう点や、車高とホイールベースを独立して調整できない点が挙げられます。また、フロントバンパーとシャーシ本体との連結部の強度が不足しがちになるという構造上の弱点もあります。
さらに、ユニットへの追加加工が必要で、モーターやギアの交換が容易にできない点、ユニット追加による重量増も気になるポイントです。しかし、ギアの噛み合わせが維持されるという決定的なメリットがあるため、多くのレーサーに支持されています。
ミニ四駆サスペンションの作り方と効果
- 四輪独立サスペンションの優れた点は高いショック吸収性能
- 内蔵サスペンションの作り方は比較的簡単で効果も実感しやすい
- 四輪独立サスペンションの製作には多くの部品と加工技術が必要
- 様々な制振システムの種類と効果はそれぞれ異なる特徴がある
- サスペンション効果を高めるコツはマスダンパーとの併用
- MSフレキが登場した背景には立体コースでの制振課題がある
- まとめ:ミニ四駆サスペンションの選び方と自作のポイント
四輪独立サスペンションの優れた点は高いショック吸収性能
四輪独立サスペンション(ダブルウィッシュボーン系)は、実車のサスペンションに最も近い形式で、各車輪が独立して上下動するシステムです。この方式の最大の優れた点は、路面に対して高いショック吸収性能を発揮することです。
独自調査によると、四輪独立サスペンションは関西の某ビルダーによって作製され、動画サイトに投稿されているものの、ミニヨンクラブには掲載されていないとのことです。それだけ高度な技術を要する改造方法と言えるでしょう。
四輪独立サスペンションの最大のメリットは、不整地や段差のあるコースでの走行安定性です。各車輪が独立して動くため、一つの車輪が受けた衝撃が他の車輪に伝わりにくく、より柔軟にコースの凹凸に対応できます。また、車高が自由に調整できる点も大きな利点です。
一方で、デメリットもいくつか存在します。ドライブシャフトを加工して駆動系を作製するため、駆動ロスが多少発生する点が挙げられます。また、コーナリング時に車体がロールしてしまう傾向があり、高速コーナリングでは不安定になる可能性があります。
さらに、サスペンション稼働時にローラーのスラスト角が変わってしまう問題や、フロントバンパーとシャーシ本体との連結部の強度が不足しがちになるといった課題もあります。しかし、そのショック吸収性能の高さから、凹凸の激しいコースでは絶大な効果を発揮します。
内蔵サスペンションの作り方は比較的簡単で効果も実感しやすい
内蔵サスペンションは、上述したシャーシ内蔵型サスペンションの一種で、独自調査によると比較的簡単に製作でき、効果も実感しやすいとされています。この特徴から、サスペンション入門としておすすめの改造方法と言えるでしょう。
内蔵サスペンションの基本的な作り方は以下の通りです。まず、MSシャーシのN-03、T-03バンパーレスユニットを用意します。次に、これらのユニット内にショックダンパー(スプリングなど)を内蔵できるよう加工します。N-04、T-04の軸受けパーツを使用する方法もあり、この場合は軸上げとサスペンション効果を同時に得ることができます。
具体的な加工方法としては、バンパーレスユニットの内部にスプリングを取り付けるスペースを確保し、スプリングの両端を固定するための部品を取り付けます。スプリングの硬さは、走行特性や好みに合わせて選択することができます。
内蔵サスペンションの大きな利点は、外見上は通常のミニ四駆と変わらない点です。これにより、コンデレへの出場も可能ですし、見た目を損なわずにサスペンション効果を得ることができます。また、モーターやギアの交換も通常通り行えるため、メンテナンス性に優れています。
製作難易度も比較的低く、初めてサスペンションに挑戦する方でも取り組みやすいでしょう。効果も直感的に理解しやすく、ジャンプ後の着地安定性向上を実感できるはずです。ただし、上述した通り、ギアの噛み合わせの問題は残るため、ワンウェイホイールとの併用を検討するとよいでしょう。
四輪独立サスペンションの製作には多くの部品と加工技術が必要
四輪独立サスペンションの製作は、ミニ四駆改造の中でも特に難易度が高く、多くの部品と高度な加工技術が必要です。独自調査によると、製作には以下のような多数の部品が必要になります。
まず、アッパーアームとロアアームが各車輪に必要で、これらはバンパーパーツから切り出して製作します。最低でも8個のアームが必要になるため、複数のバンパーパーツを用意する必要があるでしょう。また、サスペンションの上部受けも同様にバンパーパーツから切り出して製作します。
サスペンション自体は、東北ダンパーのパーツに含まれるボールジョイントの受け側パーツに、二段プラローラーの軸、ワッシャー、スラダンのスプリング、アルミ3mmスペーサーを組み合わせて構成します。これらの部品を適切に組み合わせることで、サスペンションの可動範囲や硬さを調整できます。
さらに、センターシャーシの加工と、軸受けギアにユニバーサルジョイントの代わりとなるゴムチューブの取り付けも必要です。このゴムチューブはMSシャーシ用のブレーキキットに付属しているものを使用します。これがないと、サスペンション稼働時にカウンターギアと軸受けギアが噛み合わなくなってしまいます。
軸受けは、余った強化ユニットから切り出すか、ギアカバー用に削った前後パーツから加工します。620ベアリングを付ける場合は、接着時の精度が特に重要になります。このように、四輪独立サスペンションの製作には多くの部品と精密な加工が必要なため、ある程度の経験と技術を持った方向けの改造と言えるでしょう。
様々な制振システムの種類と効果はそれぞれ異なる特徴がある
ミニ四駆の世界には、サスペンション以外にも様々な制振システムが存在します。これらは着地時の衝撃を吸収し、走行安定性を向上させる目的を持ちますが、それぞれに異なる特徴と効果があります。
「ヒクオ・提灯」は、鳥居のような形状のFRPをマシン後方から取り付け、FRPがパカパカと上下することでシャーシの振動を制御するシステムです。非常に効果的な制振システムとして多くのレーサーに支持されています。
「ギロチン」は、その名の通り刃物が落ちるような動きで制振効果を発揮するシステムです。実戦向きに改良されたバージョンもあり、研究が進められています。
「ノリオ・ザリィ・タザオ」は、ヒクオの進化系と考えられるマスダンパーの搭載方法です。それぞれに特徴があり、ノリオは特にメジャーなシステムとして知られています。
「サイドアーム」は、サイドバンパーにギロチンを搭載したシステムで、様々な形態や作り方が公開されています。基本的な考え方は同じでも、レーサーごとに工夫を凝らした独自のアレンジが見られます。
「ユーロシステム」は、シリコンタイヤの弾力を利用したシステムです。フロントとリアのアンダーガードを地上高1mmに設定し、着地時にシリコンタイヤが押されて変形することでバンパーが直接地面に当たり、結果としてマシンを制振させる仕組みです。弾力がありすぎて着地時に安定しないシリコンタイヤの弱点を逆に利用する、興味深い発想から生まれたシステムです。
サスペンション効果を高めるコツはマスダンパーとの併用
サスペンションの効果を最大限に引き出すためには、マスダンパーとの併用がコツとなります。マスダンパーは、その名の通りマス(質量)を利用してダンピング(制動)効果を得る装置で、サスペンションと組み合わせることで相乗効果を発揮します。
独自調査によると、特に上下反転型や内蔵型のサスペンションでは、「マスダンと併用する・オイルダンパーを組み込むなどサス自体の反動を別の何かで打ち消さないと、逆に跳ねてしまう」という課題があることがわかっています。つまり、サスペンション単体では反動が大きく、かえって不安定になる可能性があるのです。
マスダンパーは、この反動を効果的に抑制する役割を果たします。マスダンパーの重りがサスペンションの動きと逆方向に動くことで、振動を相殺し、より安定した走行を実現します。
具体的な併用方法としては、サスペンションの可動部分の近くにマスダンパーを設置するのが効果的です。また、マスダンパーの重りの重さや可動範囲を調整することで、サスペンションとのバランスを取ることができます。
ただし、「マスダンパーって本当に効いてる?」という疑問を投げかける研究もあります。効果を実感するためには、自分のマシンやコース特性に合わせて、様々な設置位置や重量で試してみることをおすすめします。サスペンションとマスダンパーの相性は、理論だけでなく実際の走行テストで確かめることが重要です。
MSフレキが登場した背景には立体コースでの制振課題がある
MSフレキが登場し、普及した背景には、立体コースでの制振が大きな課題だったという状況があります。独自調査によると、両軸モーターが発表された以降、トレサスが手軽に、本格的に作られるようになったとされています。
両軸モーターは構造上、サスペンションを作りやすい特徴があり、当時増えつつあった立体コースでの制振課題に対応するため、多くのレーサーが研究を重ねていました。しかし、MSフレキの登場により情勢は大きく変わりました。
MSフレキは、MSシャーシの3分割構造を活かし、バネを仕込むことで柔軟性を向上させる改造です。これにより、ジャンプの着地の際の衝撃を緩和させることができます。トレサスと比較して、MSフレキは構造がシンプルで作りやすく、効果も高かったため、多くのレーサーがこちらを採用するようになりました。
また、MSフレキはトレサスが抱えていた構造上の問題点を克服していました。トレサスでは、サス稼働時に物理的にトルク抜けが起こる問題や、ブレーキやローラー周りの扱いに難儀する問題がありましたが、MSフレキではこれらの問題が緩和されていました。
このような背景から、MSフレキは急速に普及し、トレサスは「レガシーデバイス」として一時期は廃れていくことになります。しかし、現在では両者の特性を理解し、コース特性やマシンセッティングに合わせて使い分けるレーサーも増えています。それぞれに長所と短所があり、どちらが優れているというものではなく、シチュエーションによって使い分けるのが理想的です。
まとめ:ミニ四駆サスペンションの選び方と自作のポイント
最後に記事のポイントをまとめます。
- ミニ四駆サスペンションの主な目的はジャンプ後の着地姿勢制御である
- サスペンションには上下反転型、シャーシ内蔵型、理想系(トレーリング系)、四輪独立型の4種類がある
- MSフレキとサスペンションは異なる概念で、MSフレキはシャーシの柔軟性、サスペンションは車体と車輪の間の衝撃緩和装置である
- トレサスの最大の長所はダイレクトドライブ(常にギアが一定に噛み合う状態)である
- 上下反転型サスペンションは簡単な加工で実現できるが、ギアの噛み合わせに問題がある
- シャーシ内蔵型サスペンションは通常ボディが装着可能で、見た目を損なわない
- 理想系(トレーリング系)サスペンションはギア噛み合わせが維持される利点がある
- 四輪独立サスペンションは高いショック吸収性能を誇るが、製作難易度が高い
- 内蔵サスペンションは比較的簡単に製作でき、サスペンション入門におすすめ
- サスペンション効果を高めるにはマスダンパーとの併用がコツである
- MSフレキが登場した背景には立体コースでの制振課題があった
- サスペンション以外にも、ヒクオ、ギロチン、ノリオなど様々な制振システムがある
- 自分のマシンやコース特性に合わせたサスペンションの選択が重要である