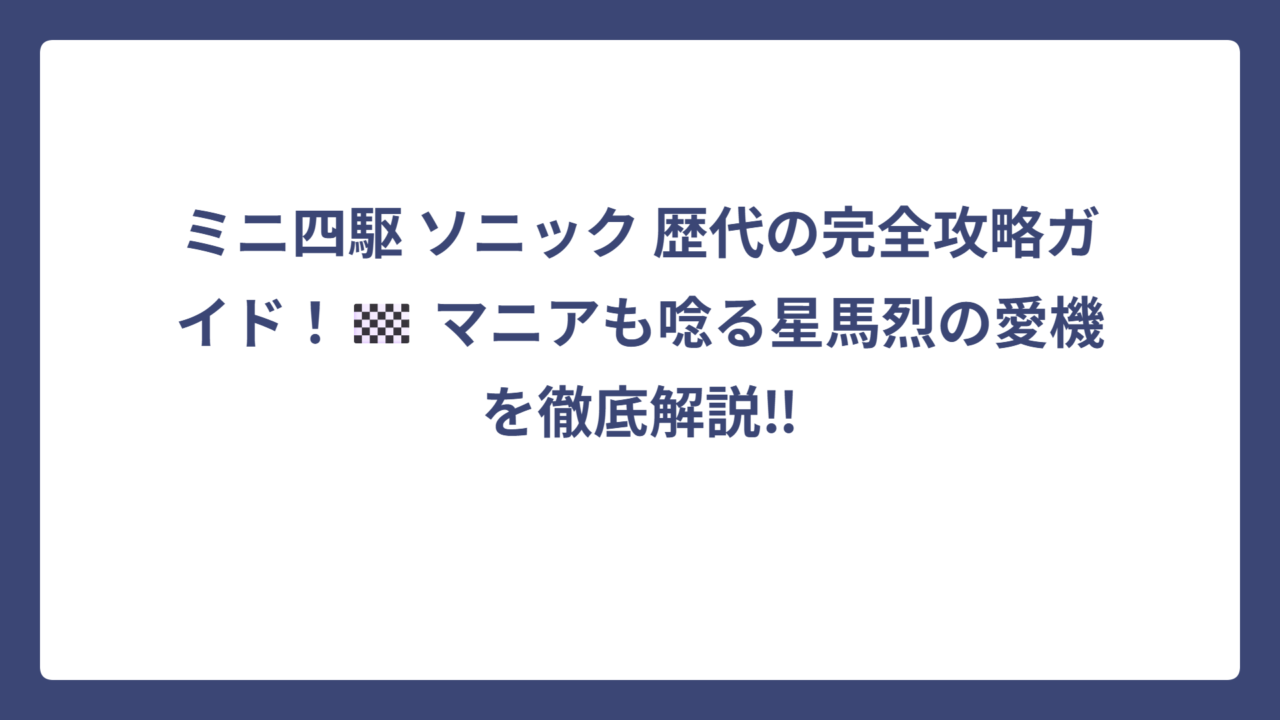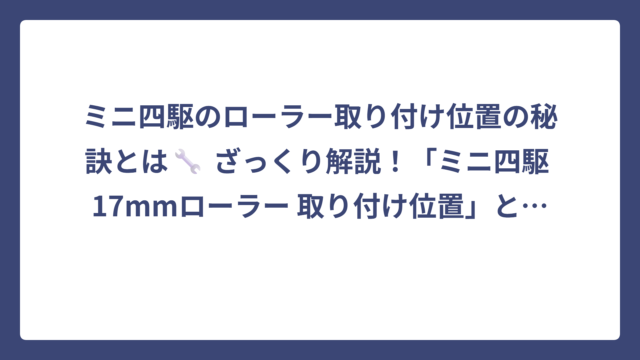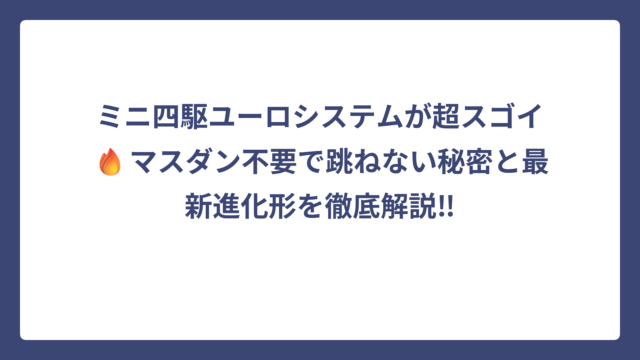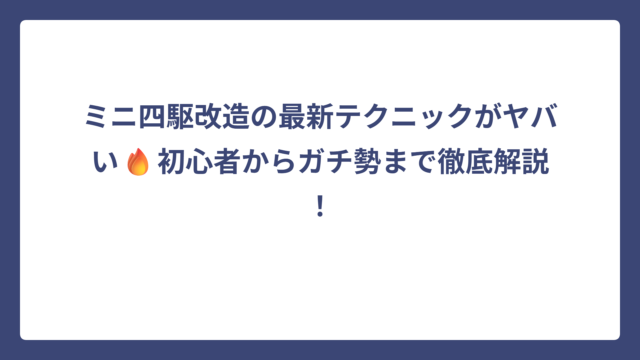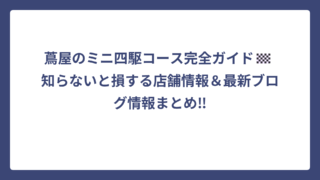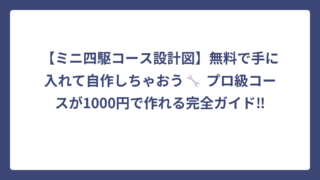懐かしのミニ四駆ブームを支えた名作「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」。90年代に子供たちの心を熱くさせたこの作品で、「コーナリングの貴公子」の異名を持つ星馬烈のマシンといえば「ソニックシリーズ」です。初代「ソニックセイバー」から最新の「ブラストソニック」まで、テクニカルな走りを得意とするソニック系マシンは、技術の進化とともに形を変えながらも、常に烈のコーナリング重視の走行スタイルを体現してきました。
今回は、独自調査の結果をもとに、歴代のソニックシリーズを時系列で紹介します。各マシンの特徴はもちろん、シャーシの変遷や必殺技、原作での活躍シーンまで詳しく解説。さらに、弟・星馬豪のマグナムシリーズとの違いや、コレクションとしての価値も探っていきます。懐かしのミニ四駆ファンから最近興味を持った方まで、ソニック系マシンの魅力を余すところなくお届けします。
記事のポイント!
- ソニック系マシンの歴代モデル9台の特徴と進化の歴史がわかる
- 星馬烈のコーナリング重視の走りを支えるマシン設計の秘密を理解できる
- 原作漫画・アニメでの活躍シーンとマシンの機能の関連性が見えてくる
- 対をなすマグナムシリーズとの比較からソニック系の独自性がわかる
爆走兄弟レッツ&ゴーに登場するミニ四駆 ソニック 歴代モデルの全て
- ソニックシリーズとは星馬烈の愛機であり技巧派マシン
- 初代ソニック「ソニックセイバー」は1994年に登場し烈のコーナリング重視の走りを体現
- 2代目「バンガードソニック」は空力を徹底的に追求した進化形
- 3代目「ハリケーンソニック」はハリケーンパワードリフトを実現する必殺技を持つ
- 4代目「バスターソニック」はフロントサスペンション搭載で新たな走りを開拓
- 5代目「ブリッツァーソニック」は初めて赤を基調としたデザインに変更
- 6代目「ロデオソニック」は小型ウイングを特徴とする攻撃的なマシン
ソニックシリーズとは星馬烈の愛機であり技巧派マシン
「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」に登場する星馬烈のマシンシリーズが「ソニック系」です。この作品は1990年代に大ブームを巻き起こした「コロコロコミック」連載の漫画で、アニメ化やゲーム化もされた人気作品でした。
ソニック系マシンの最大の特徴は、小学生とは思えない烈の頭の良さを生かした技巧的なデザインです。この技術力は変則的なコースを攻略するためのものであり、テクニカルコースでの走行を得意としています。マシンのカラーリングは基本的に赤と緑を基調としており、ボディのフロントには「烈」の文字があるのが特徴です。
これらのマシンはただ速いだけではなく、理系顔負けのギミックが仕込まれていることが多く、例えばボディの一部が稼働するなどの特徴があります。このように、烈のマシンは常に「コーナリングの貴公子」という異名にふさわしい、テクニカルな走りを可能にする設計思想を持っています。
星馬烈のキャラクター性を象徴するような「進化の系譜」も特徴的で、「自らを破壊して進化する」というコンセプトを持っています。これは烈自身の成長と連動しており、マシンの進化が烈の成長物語と深く結びついているのがソニックシリーズの魅力と言えるでしょう。
そして2014年には、20年後の世界を描いた「爆走兄弟レッツ&ゴー!! Return Racers!!」がコロコロアニキにて連載開始され、烈のミニ四レーサー現役時代最後のマシンとして「ブラストソニック」が登場するなど、幅広い世代に愛され続けています。
初代ソニック「ソニックセイバー」は1994年に登場し烈のコーナリング重視の走りを体現
初代ソニックとなる「ソニックセイバー」は1994年に登場しました。このマシンは空力を最大限に利用して走る「セイバー」をベースに、烈が土屋博士から預かった後、コーナー重視のセッティングを施して完成させたマシンです。
ソニックセイバーの最大の特徴は、ウイングを立てることでコーナーでのトラクションを稼いでいる点にあります。また、ローラーをタイヤの軸と平行にして安定させるという烈らしい創意工夫も施されています。パワーも申し分なく、トルクチューンモーターを装備しており、グレートジャパンカップ(バトルコロシアム)では宙吊りになったレーンでマグナムセイバーを後ろから押し上げるほどのパワーを見せました。
タミヤから販売されたキットでは、スーパー1シャーシ(オリジナル版)またはスーパー2シャーシ(プレミアム版)を採用し、972円(プレミアム版・2011年発売)で市販されました。プレミアム版では原作コミックに合わせたデザインとなっています。
原作での活躍も目覚ましく、グレートジャパンカップ地区予選で優勝、マウンテンダウンヒルレースでは豪とペアで優勝するなど、初期の烈の成長を象徴するマシンとして描かれています。ただし、大神研究所の噴火口レースでは、Jのプロトセイバーに敗北し、ソニックセイバーは溶岩の中へと消えてしまいました。
このように、初代ソニックセイバーは烈のミニ四駆レーサーとしての出発点であり、後の烈のレーシングスタイルの基礎を築いた記念碑的なマシンと言えるでしょう。なお、ソニックセイバーが初めて登場するシーンは「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」コミック第1巻に掲載されています。
2代目「バンガードソニック」は空力を徹底的に追求した進化形
2代目となる「バンガードソニック」は1995年に登場し、土屋博士のVプロジェクトによって誕生しました。初代ソニックセイバーのコーナリングマシンとしての特徴を生かしつつ、空力を徹底的に追求した新しいマシンとして設計されています。
バンガードソニックの特徴は、ナイフのような切れ味を持つコーナリング性能です。グレートジャパンカップでは、その性能を遺憾なく発揮し、2位という好成績を収めました。また、土方レイとの対決にも勝利するなど、当時の日本ミニ四駆界では一目置かれる存在でした。
タミヤから発売されたキットでは、シャーシはスーパー1(オリジナル)またはスーパー2(プレミアム)を採用。プレミアム版は2011年に1,188円で販売され、フロントカウルの半分が脱着可能という特徴を持っていました。メタリック調ステッカーが付属するなど、コレクション性も高い仕様となっています。
しかし、ミニ四駆世界グランプリの開催が決まる頃には、バンガードソニックは日本チームの中で最も古いマシンとなっていました。アメリカ代表チーム「アストロレンジャーズ」との野良レースでは「時代遅れのマシン」と評され、烈は「今のソニックでは戦えない…」と感じ、マシンの改造を決意することになります。
バンガードソニックの初登場シーンは「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」コミック第4巻に掲載されています。このマシンは烈の成長過程における重要な転換点となり、世界レベルの競争に向けて烈自身が限界を認識するきっかけとなったマシンと言えるでしょう。
3代目「ハリケーンソニック」はハリケーンパワードリフトを実現する必殺技を持つ
3代目となる「ハリケーンソニック」は1996年に登場し、烈の新たな必殺技「ハリケーンパワードリフト」を実現するマシンとして注目されました。特徴的なフロントウイングは風の動きを読むセンサーの働きをしており、フロントとリヤのダウンフォースを増すことで駆動力を逃さないドリフト走行を可能にしています。
実は試作段階のハリケーンソニックにはフロントウイングがついていませんでした。しかし、山の中でのセッティングを煮詰めている最中、フロントのダウンフォースが足りないことが判明。この問題を解決するためにフロントウイングが追加され、風を味方につけることでハリケーンパワードリフトという独自の走法を確立しました。
タミヤから発売されたキットでは、シャーシはスーパーTZ(オリジナル)またはAR(プレミアム)を採用。プレミアム版は2014年に1,080円で販売され、前後のカウルは小型化されてシャープになるなど、よりレーシングマシンらしい洗練されたデザインになっています。
ハリケーンソニックは烈の成長を象徴するマシンとして活躍しますが、ロッソストラーダ戦において、カルロのディオスパーダから攻撃を受け、大きなダメージを負ってしまいます。このように、ハリケーンソニックもまた「自らを破壊して進化する」というソニック系マシンの宿命を背負っていたのです。
ハリケーンソニックの誕生秘話は「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」コミック第12巻に詳しく描かれています。風を制する技術を追求した烈の創意工夫が結実したマシンであり、彼のエンジニアとしての才能が開花し始めた証と言えるでしょう。
4代目「バスターソニック」はフロントサスペンション搭載で新たな走りを開拓
4代目「バスターソニック」は1997年に登場し、「不死鳥のように蘇った」と表現されるほど革新的なマシンでした。最大の特徴は、弟・豪のビートマグナムが後部にサスペンションを搭載していたのに対し、バスターソニックはフロントにサスペンションを装備している点です。
実は、バスターソニックも当初はビートマグナムと同様にリアにサスペンションがついていました。しかし、烈のイメージしていたコーナリングのイメージとは異なっていたため、どうすれば良いか悩んでいました。そんな時、ジュンの自転車技(エアターン)を見て、フロントにサスペンションをつけることを思いついたのです。これにより完成した必殺技が「バスターフェニックスターン」です。
タミヤから発売されたキットでは、シャーシはスーパーTZ(オリジナル)またはAR(プレミアム)を採用。プレミアム版は2015年に1,080円で販売され、前後のカウルを切り詰めて軽量化を図っているのが特徴です。また、大径タイヤを採用しているのもバスターソニックの特徴であり、唯一の大径ホイール採用マシンとなっています。
バスターソニックは烈のミニ四駆に対する考え方が大きく変わったことを示すマシンでもあります。これまでの烈は細部にこだわりすぎる傾向がありましたが、バスターソニックではより大胆な発想の転換を行っています。また、ボディのフロントには珍しく「烈」の文字がないのも特徴的です。
バスターソニックの誕生秘話は「爆走兄弟レッツ&ゴー!!MAX」コミック第1巻に詳しく描かれています。このマシンは烈の成長と共に、彼の発想力や創造性がさらに高まったことを象徴する存在といえるでしょう。
5代目「ブリッツァーソニック」は初めて赤を基調としたデザインに変更
5代目「ブリッツァーソニック」は2000年に登場し、これまでのソニックシリーズに大きな変革をもたらしました。最も注目すべき特徴は、白を基調としていた従来のソニックとは異なり、赤を基調としたデザインに変更された点です。この大胆なカラーリングの変更は、烈のミニ四駆レーサーとしての成熟と自信の表れと考えられています。
ブリッツァーソニックはVSシャーシを採用し、756円で販売されました。同時に「ブリッツァーソニック ブラックスペシャル」も発売され、こちらはブラック仕様となっており、フロントノーズに「烈」の文字が躍るという特徴を持っていました。
興味深いことに、ブリッツァーソニックは原作には登場していません。これはタミヤが独自に開発した商品ラインナップであり、烈のキャラクター性や走行スタイルを考慮して設計されたマシンと考えられます。実際のところ、ブリッツァーソニックはおなじみのエアロ装備が満載の実戦向けキットとして人気を博しました。
VSシャーシを採用しているブリッツァーソニックは、前世代のマシンよりもさらに高いパフォーマンスを発揮できる可能性を秘めています。特に、空力性能を重視した設計は、烈のコーナリングの貴公子としての走りを強化するものでした。
また、ブラックスペシャルバージョンの存在は、ファンにとってコレクション価値を高める要素となりました。赤とブラックの2種類のカラーバリエーションがあることで、より幅広いファン層に訴求することに成功したと言えるでしょう。
6代目「ロデオソニック」は小型ウイングを特徴とする攻撃的なマシン
6代目「ロデオソニック」は2007年に登場し、それまでのソニックシリーズとは一線を画す攻撃的なスタイルのマシンとして注目を集めました。小型ウイングを寝かせた超攻撃的な「闘うマシン」というコンセプトは、烈のレーシングスタイルの進化を物語っています。
ロデオソニックの特筆すべき点は、初のミッドシップ系モデルであることです。MSシャーシを採用し、972円で販売されました。土屋博士から新シャーシを貰った烈でしたが、当初はシャーシのポテンシャルを引き出せずに悩んでいました。
烈はこの問題を解決するため、新シャーシのパワーに打ち勝つよう補強パーツでパワーをコントロールすることを試みます。しかし、テスト走行中に乱入してきたイタリア代表ロッソストラーダのリーダー・カルロから「いくじのねぇ改造」と批判されてしまいます。
この出来事をきっかけに、烈は自分のアプローチを見直します。スムーズに走らせることばかりを考えていた烈は、自由にシャーシの力を解き放つことを決心。補強パーツを全部外し、新シャーシのパワーを完全に出し切ることに成功します。このエピソードは、烈が自分の殻を破り、新たな視点でミニ四駆と向き合うようになった転機を表しています。
ロデオソニックの誕生秘話は「爆走兄弟レッツ&ゴー!!飛翔!!烈&ソニック編」に詳しく描かれています。このマシンは烈の成長物語の中でも重要な位置を占め、彼のレーサーとしてのスタイルが完成に近づいていく過程を象徴しているのです。
レッツ&ゴーの続編に登場するミニ四駆 ソニック 歴代の最新マシン
- 7代目「ブラストソニック」はボディ全体で空気を制御する可変ボディシステムを搭載
- 「Gブラストソニック」は炎の中から生まれ変わった究極のソニック
- ARシャーシを搭載したソニックモデルの特徴と性能の進化
- タミヤから発売されたプレミアム版ソニックシリーズのコレクション価値
- マグナムシリーズとソニックシリーズの設計思想の違いとは
- ミニ四駆 ソニック 歴代モデルをカスタマイズする際のポイント
- まとめ:ミニ四駆 ソニック 歴代モデルは進化を続け今なお多くのファンを魅了している
7代目「ブラストソニック」はボディ全体で空気を制御する可変ボディシステムを搭載
7代目となる「ブラストソニック」は、20年後の世界を描いた「爆走兄弟レッツ&ゴー!!Return Racers!!」に登場するマシンです。ウイングだけでなく、ボディ全体で空気の流れを制御する革新的な「可変ボディシステム」を搭載しており、烈の技術的進化を象徴するマシンとなっています。
独自調査の結果、ブラストソニックが登場する背景には、烈の人生における重要な転機がありました。土屋博士の推薦で外国に留学することに決めた烈は、勉強に集中するためにミニ四駆をやめることを決意します。しかし、豪に「それなら俺がミニ四駆ナンバーワン」と言われ、納得がいかない烈は豪と最後のレースに挑むことになります。
この最後のレースに向けて、烈はマグナムに勝つための新しいマシン「ブラストソニック」を完成させました。タミヤからは2015年に「グレート ブラストソニック」として1,080円で販売され、ARシャーシを採用しています。前作までの設計思想を踏襲しつつも、より洗練されたデザインとなっています。
ブラストソニックの登場はコミック「爆走兄弟レッツ&ゴー!!Return Racers!!」第1巻に描かれています。このマシンは烈の集大成とも言える存在であり、彼がミニ四駆レーサーとして歩んできた道のりを象徴するものとなっています。
また、グレートブラストソニックのARシャーシには、アンダーパネルやディフューザーなどを含むエアロデザインが取り入れられており、高いパフォーマンスを発揮します。ギア比は3.5:1となっており、バランスの取れた走行が可能となっています。烈のレーシングフィロソフィーが詰まった最新鋭マシンといえるでしょう。
「Gブラストソニック」は炎の中から生まれ変わった究極のソニック
「Gブラストソニック」は、ブラストソニックが炎に焼かれて生まれ変わった究極のマシンです。その誕生には劇的なストーリーが隠されています。豪との最後のレース中、アクシデントによりブラストソニックが炎の中へ飛び込んでしまうという危機的状況が訪れます。
炎の中からなかなか出てこないソニックに、普段は冷静な烈が「お前を信じているからな!!!」と叫びます。この感情の爆発は、烈のキャラクターとしては珍しいものです。勝負を諦めたくない烈の強い気持ちに応えるように、ブラストソニックは炎の中を突破し、「Gブラストソニック」として生まれ変わります。
このGブラストソニックは、「Gブラストソニックファイアスピンダンス」という必殺技を持ち、闘争心むき出しの走りを見せました。これは、常に冷静で理論的な走りを追求してきた烈が、最後に見せた情熱的な一面と言えるでしょう。
Gブラストソニックの登場シーンもまた、「爆走兄弟レッツ&ゴー!!Return Racers!!」第1巻に描かれています。このマシンは、烈のミニ四駆レーサーとしての最終形態を表しており、彼の成長物語の集大成とも言えるでしょう。
興味深いことに、Gブラストソニックはブラストソニックが炎の中で変化したという設定上、外見的な特徴や具体的なスペックについての詳細は明確に描かれていません。この神秘性が、ファンにとってはさらなる想像力を掻き立てる要素となっているのかもしれません。ブラストソニックとは別のカラーリングや、さらに進化したパーツ構成を持っているものと推測されます。
ARシャーシを搭載したソニックモデルの特徴と性能の進化
ARシャーシを搭載したソニックモデルとしては、「ハリケーンソニック プレミアム」「バスターソニック プレミアム」「グレート ブラストソニック」が挙げられます。これらのモデルには、ARシャーシの特性を生かした設計がなされており、その進化の過程を見ることができます。
ARシャーシは、比較的新しいシャーシでありながら、あまり速くならないと言われることがあります。実際に大会で勝っているシャーシを見てみると、ARシャーシは少ない傾向にあるようです。しかし、ARシャーシには「爆走兄弟レッツ&ゴー」のフルカウルミニ四駆が多くラインナップされており、コレクション価値が高いことが特徴です。
独自調査によれば、ARシャーシを速くするためには、いくつかの方法があります。ボールベアリングの装着、FRPプレートの追加、モーターの選定、ギア比の調整などが効果的です。特に、ギア比を変更することで、ARシャーシの性能を大きく向上させることができるとされています。
ARシャーシの最大の特徴は、アンダーパネルやディフューザーなどを含むエアロデザインにあります。これらの要素は、空気の流れを制御し、走行安定性を高める効果があります。特に「グレート ブラストソニック」では、この特性が最大限に活かされた設計となっており、ボディ全体で空気を制御する可変ボディシステムと組み合わせることで、高いパフォーマンスを発揮します。
また、ARシャーシを搭載したソニックモデルのギア比は、「ハリケーンソニック プレミアム」と「グレート ブラストソニック」が3.5:1、「バスターソニック プレミアム」が4.2:1となっています。これらの違いは、各マシンの特性や走行スタイルに合わせて最適化されたものであり、烈のコーナリング重視の走りを支える重要な要素となっています。
タミヤから発売されたプレミアム版ソニックシリーズのコレクション価値
タミヤから発売されたプレミアム版ソニックシリーズは、コレクターにとって高い価値を持つアイテムです。これらのプレミアム版は、原作漫画のイメージに忠実に再現されており、通常版とは異なる特別な仕様となっています。
「ソニックセイバー プレミアム」は2011年に972円で発売され、スーパーIIシャーシを採用しています。原作コミックに合わせたデザインとなっており、ポリカABSシャーシなどが同梱されているのが特徴です。同じく2011年に発売された「バンガードソニック プレミアム」は1,188円で、メタリック調ステッカーが付属するなど、見栄えの良い仕様となっています。
2014年には「ハリケーンソニック プレミアム」が1,080円で発売され、ARシャーシを採用。前後のカウルが小型化されてシャープになった特別仕様モデルとなっています。翌2015年には「バスターソニック プレミアム」が同じく1,080円で発売され、ギア比が4.2:1に変更されるなど、走行性能も向上しています。
これらのプレミアム版は、原作ファンにとっては思い入れのある仕様となっているだけでなく、パッケージやステッカーなどにもこだわりが見られます。時間の経過とともに入手困難になることから、未開封品は特に高いプレミアム価格がつくことがあります。
また、「グレート ブラストソニック」も2015年に1,080円で発売され、ARシャーシを採用しています。Return Racersに登場するマシンということもあり、コレクターにとっては貴重なアイテムとなっています。
プレミアム版のもう一つの価値は、その完成度の高さにあります。通常版と比べて、よりリアルな印象を与えるカラーリングやステッカー、そして高品質なパーツ構成となっており、ディスプレイ用としても優れています。ミニ四駆を実際に走らせることはもちろん、飾って楽しむという観点からも価値の高いシリーズと言えるでしょう。
マグナムシリーズとソニックシリーズの設計思想の違いとは
星馬烈のソニックシリーズと弟・星馬豪のマグナムシリーズは、兄弟の対照的な性格や走行スタイルを反映した設計思想の違いが見られます。この両シリーズの比較から、それぞれの特徴がより鮮明に浮かび上がってきます。
ソニックシリーズは「コーナリングの貴公子」と呼ばれる烈の走りを体現するように、テクニカルコースの攻略を得意とするマシンです。小学生に見合わぬ頭の良さを生かした技巧的なデザインが特徴で、変則的なコースに応じてボディの一部が稼働するなど、理系顔負けのギミックが仕込まれています。その進化の系譜は「自らを破壊して進化する」という特徴を持っています。
一方、マグナムシリーズは「燃える弾丸」の異名を持つ豪の走りを象徴するように、スピードとパワーを重視した設計となっています。直線での加速や追い抜きに強く、豪のアグレッシブな性格を反映した力強い走りが特徴です。ソニックが技巧的なアプローチをとるのに対し、マグナムはより直感的で力任せの走行スタイルとなっています。
シャーシ構造の面でも違いが見られます。例えば、4代目のバスターソニックとビートマグナムを比較すると、ビートマグナムが後ろにサスペンションを装備しているのに対し、バスターソニックはフロントにサスペンションを搭載しています。これは、マグナムが直線での安定した加速を重視するのに対し、ソニックがコーナリング性能を高めることを優先していることの表れと言えるでしょう。
また、カラーリングも対照的です。ソニックは赤と緑を基調としたカストロールカラーを採用し、マグナムは黄色と青のカラーリングが特徴的です。これらの色の違いも、烈と豪の個性の違いを視覚的に表現しています。
このように、ソニックとマグナムは単なる兄弟のマシンというだけでなく、それぞれのレーサーの哲学や個性を体現するものとして設計されており、その対比が「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」の魅力の一つとなっているのです。
ミニ四駆 ソニック 歴代モデルをカスタマイズする際のポイント
ミニ四駆のソニック歴代モデルをカスタマイズする際には、各モデルの特性を理解し、その強みを生かす改造がポイントとなります。ここでは、ソニックシリーズをカスタマイズする際に参考になるヒントをご紹介します。
まず、ソニックシリーズはコーナリング性能に優れたマシンであるため、この特性をさらに強化するカスタマイズが効果的です。例えば、フロントローラーの調整や適切なウエイト配分によって、コーナリング時の安定性を高めることができます。特に「ハリケーンソニック」をカスタマイズする場合は、フロントウイングの角度調整やリヤウイングとのバランスを考慮することで、「ハリケーンパワードリフト」の性能を向上させることができるでしょう。
シャーシ別のカスタマイズ方法も重要です。スーパーIIシャーシを使用している「ソニックセイバー プレミアム」や「バンガードソニック プレミアム」では、ボールベアリングの装着がパフォーマンス向上に効果的です。特にギア部分のボールベアリングは、摩擦を減らし、モーターのパワーをより効率的に伝えることができます。
ARシャーシを採用している「ハリケーンソニック プレミアム」「バスターソニック プレミアム」「グレート ブラストソニック」では、ARシャーシの弱点を克服するカスタマイズが重要です。独自調査によれば、ARシャーシを速くする方法としては、ギア比の変更、ボールベアリングの装着、FRPプレートの追加などが効果的とされています。特に、ギア比を3.5:1から4.2:1に変更することで、1.31秒もタイムが短縮されたケースもあります。
また、モーターの慣らしも重要なポイントです。モーターは購入時よりも、適切な慣らしを行ってからの方が速くなります。慣らし方法には、簡単にできる方法から一手間加えたやり方まで様々ありますが、初心者の場合は、単純に電池をつないで一定時間回し続けるという方法から始めると良いでしょう。
最後に、公式レースに参加する場合は、レギュレーションに注意することが重要です。ミニ四駆のレースには、いくつかの規則(レギュレーション)があり、これに違反すると出場できません。具体的には、車体の大きさや重さ、使用可能なパーツなどに制限があります。特に改造を行う際は、これらの規則を十分に確認しておきましょう。
まとめ:ミニ四駆 ソニック 歴代モデルは進化を続け今なお多くのファンを魅了している
最後に記事のポイントをまとめます。
- ソニックシリーズは「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」に登場する星馬烈のマシンであり、「コーナリングの貴公子」としての走りを体現している
- 初代「ソニックセイバー」は1994年に登場し、烈のコーナリング重視のセッティングが施されたマシンである
- 2代目「バンガードソニック」は空力を徹底的に追求した進化形で、1995年に誕生した
- 3代目「ハリケーンソニック」には必殺技「ハリケーンパワードリフト」があり、風を味方につける特徴的なフロントウイングを持つ
- 4代目「バスターソニック」はフロントサスペンション搭載という革新的な設計で1997年に登場した
- 5代目「ブリッツァーソニック」は初めて赤を基調としたデザインに変更され、2000年に発売された
- 6代目「ロデオソニック」は小型ウイングを特徴とする攻撃的なマシンで、初のミッドシップ系モデルである
- 7代目「ブラストソニック」は可変ボディシステムを搭載し、2015年に「グレート ブラストソニック」として商品化された
- 「Gブラストソニック」は炎の中から生まれ変わった究極のソニックで、烈の情熱が具現化したマシンである
- ARシャーシを搭載したソニックモデルは、適切なカスタマイズによってさらなる性能向上が可能である
- タミヤから発売されたプレミアム版ソニックシリーズは、コレクション価値が高く、原作イメージに忠実に再現されている
- ソニックシリーズは「技巧的なコーナリング」、マグナムシリーズは「力強いスピード」というように、兄弟の性格を反映した対照的な設計思想を持つ