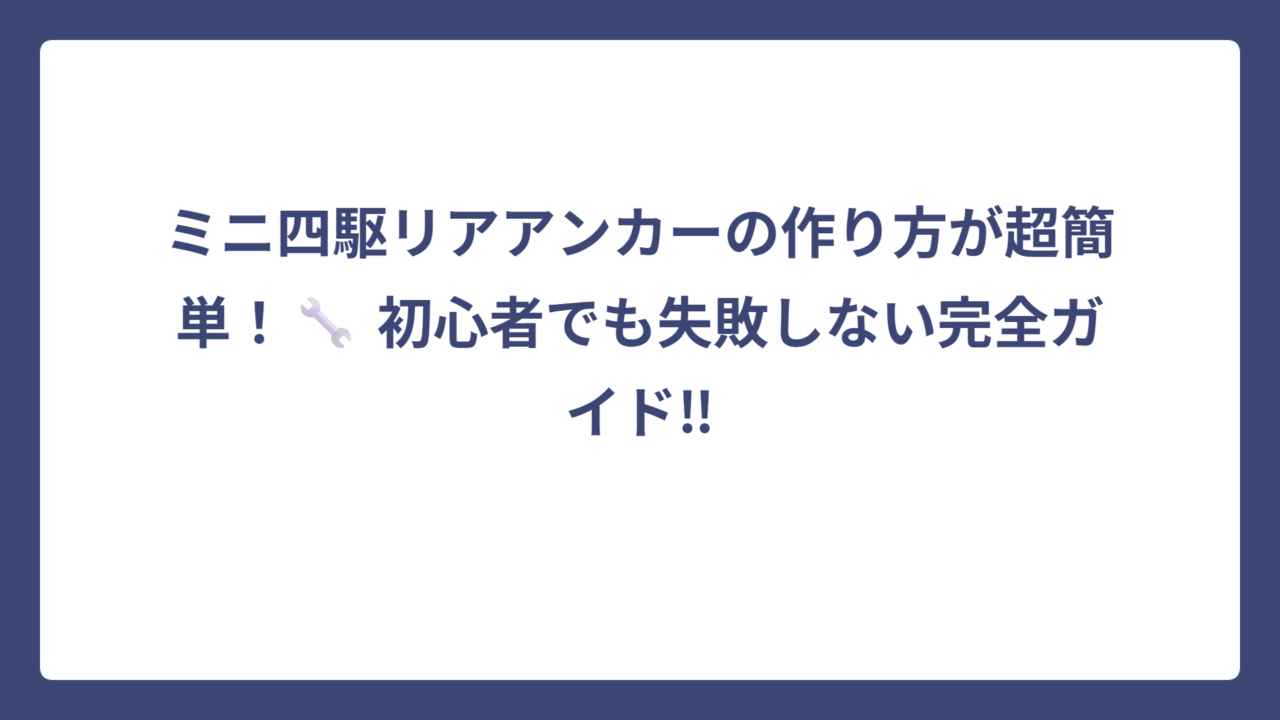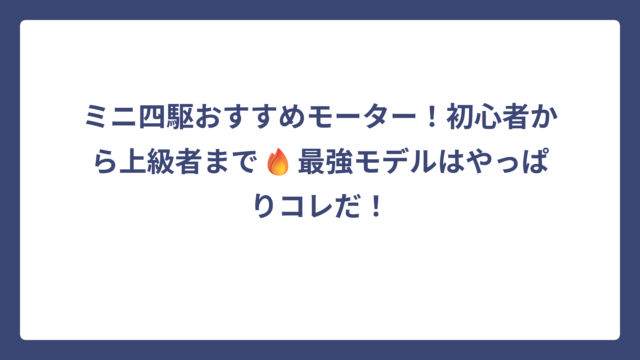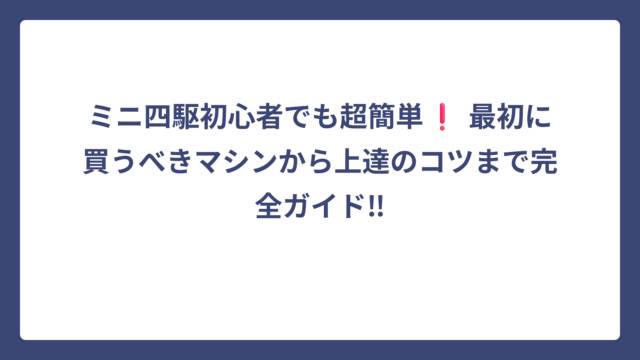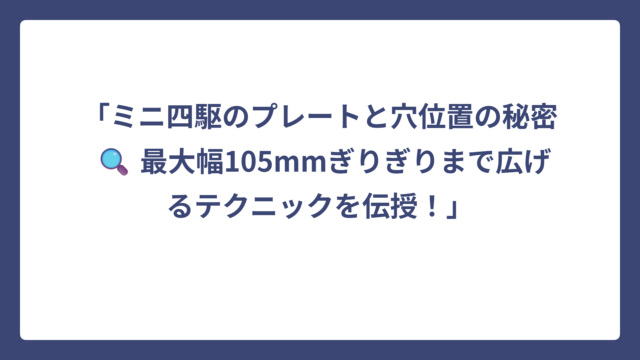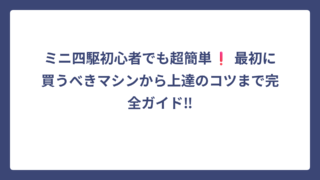ミニ四駆レースの世界では、コース復帰率を高めるためのパーツ選びが勝敗を分けることも少なくありません。その中でも「リアアンカー」は、壁に乗り上げた際の復帰率を大幅に向上させる重要なギミックとして近年注目を集めています。
本記事では、ミニ四駆のリアアンカーについて基本的な構造から製作方法、さらには効果的なセッティング方法まで詳しく解説します。1軸から2軸まで、様々なタイプのアンカー製作に必要な材料や工具、そして製作時のポイントを網羅的に紹介し、初心者の方でも自信を持って製作できるようサポートします。
記事のポイント!
- リアアンカーの基本構造と動作原理について理解できる
- 1軸アンカーと2軸アンカーの違いと製作方法を学べる
- アンカー製作に必要な材料と工具の選び方がわかる
- ATバンパーとの違いや各シャーシへの取り付け方法が理解できる
ミニ四駆リアアンカーの基本と作り方
- リアアンカーの定義はバンパーに可動性を持たせる仕組み
- ミニ四駆リアアンカーの効果はコース復帰率の向上にある
- 1軸アンカーの作り方は基本パーツと加工技術が必要
- リアアンカー製作に必要な材料と工具は手に入りやすいもの
- ミニ四駆リアアンカーの取り付け位置は走行特性に大きく影響する
- ミニ四駆リアアンカー作りで最も重要なのは支柱の固定方法
リアアンカーの定義はバンパーに可動性を持たせる仕組み
ミニ四駆の世界では、アンカーは特定の定義を持つギミックとして認識されています。独自調査の結果、アンカーの基本的な定義には以下の要素が含まれることがわかりました。
アンカーとは、1軸のバンパーでキノコヘッドを使用し、AT(アクティブトルク)的な動きとスライド機能を持つギミックのことを指します。特にリアアンカーは、マシン後部に取り付けるアンカーのことで、コース壁に接触した際の挙動をコントロールする役割を担っています。
基本構造としては、支柱となる軸を中心に、バンパー部分が上下や左右、そして後方へと可動することができる仕組みになっています。この可動性によって、コース壁に乗り上げた際にマシンが受ける衝撃を吸収し、スムーズなコース復帰を可能にします。
最近ではフロント1軸も流行していますが、これはほとんどが完全固定型であり、一般的にはアンカーとは呼ばれていません。アンカーの特徴は、その可動性にあるのです。
多くのレーサーはこの動きを最適化するために、様々な工夫を凝らしています。アンカーがミニ四駆レース界隈で注目されるようになったのは、2016年頃からとされており、当初は「3レーンには良いけど…」と評価されていましたが、現在では技術の進化により5レーンコースでも効果を発揮するようになっています。
ミニ四駆リアアンカーの効果はコース復帰率の向上にある
リアアンカーの主な目的は、イレギュラーな状況(壁乗り上げ時)からの復帰率向上です。これはAT/C-ATバンパーなどと同様の目的を持っていますが、動作機構が異なります。
独自調査によると、リアアンカーの主な効果は以下のとおりです:
- 壁に乗り上げた際、アンカーが上方向に動くことで衝撃を吸収し、マシンが転倒やコースアウトするリスクを低減します。
- 左右への稼働により、コーナーリング中にマシンの進行方向への角度が真っ直ぐに近くなり、コーナーリング性能の向上が期待できます。
- スライド機能によってコースの壁との接触時の衝撃を分散させ、マシンの減速を最小限に抑えることができます。
- コースのギャップ(セクション間の隙間)に対しても効果を発揮し、安定した走行をサポートします。
注意すべき点として、アンカーを付けたからといって単純に速くなるわけではありません。むしろ、綺麗な着地ができれば壁に引っ掛からない方が全体的には速いのです。アンカーは不測の事態に備えるための保険的な役割を持つギミックだと言えるでしょう。
また、マシンのスピードが速ければ速いほど、アンカーによる安定性の維持が構造上難しくなるという点も把握しておく必要があります。そのため、アンカーのセッティングはマシンの特性やコースレイアウトに合わせて調整することが重要です。
1軸アンカーの作り方は基本パーツと加工技術が必要
1軸アンカーの製作は、基本的なパーツと簡単な加工技術があれば比較的容易に行うことができます。独自調査によると、以下の手順で製作していくことが一般的です。
【1軸アンカーの基本的な作り方】
- 材料の準備:
- 弓FRPまたはカーボン(1~2枚)
- ボールリンクFRP(通称「パンツ」)
- キャッチャー端材
- キノコヘッド(アンダースタビヘッド)
- 銀バネ(好みで黒なども可能)
- ビス(お好みでキャップスクリュー)
- FRPの加工:
- FRPを使用する場合は2枚を接着して貼り合わせます。この時、キャップスクリューのネジ頭埋め込みたい場合は、下側の使用するローラー穴を3.5mmくらいまで拡張してから貼り合わせます。
- カーボンを使用する場合は1枚でも十分な強度を持ちます。
- パンツFRPの座繰り:
- ボールリンクのFRP(パンツ部分)の中央穴を8mmの円柱砥石などで座繰ります。
- 厚さの半分くらいまで座繰り、四角の口が丸く見えるまで加工します。この作業は軽めに行うことがポイントです。
- キャッチャーの加工と取り付け:
- パンツFRPの形にキャッチャーを切り出し、瞬間接着剤でパンツFRPに貼り付けます。
- ネジ穴を開け、仮止めします。
- 四角穴の真ん中に6mmビットが貫通するくらいの穴を開けます。この穴の位置精度が製品の出来を左右します。
- キノコヘッドの加工:
- キノコヘッド(スタビヘッド)の中央穴を2.1mmのドリルで貫通させます。
- 貫通後、出っ張りを切り落とします。
個人的な工夫として、キノコヘッドの加工時にボールスタビ用のゴム管で押さえながら穴を開けると、グリップが効いて作業がしやすくなるというテクニックも紹介されています。
これらの工程を丁寧に行うことで、基本的な1軸アンカーが完成します。次の段階では、アンカーの動きを調整するための微調整や取り付け方法について考えていきます。
リアアンカー製作に必要な材料と工具は手に入りやすいもの
リアアンカー製作に必要な材料や工具は、ミニ四駆ショップや一般的な工具店で比較的簡単に入手することができます。独自調査の結果、以下の材料と工具が一般的に使用されています。
【材料リスト】
- 弓FRPまたはカーボン:
- FRPフロントワイドステー(フルカウルミニ四駆タイプ)が一般的
- 強度が必要な場合は2枚重ねて使用
- ボールリンクマスダンパーのFRP:
- 通称「パンツFRP」
- 中央に四角穴が開いており、加工しやすい
- キノコヘッド(アンダースタビヘッド):
- 色は赤、黄色、青、黄色などが一般的
- タミヤのグレードアップパーツNo.408などに含まれている
- その他の材料:
- キャッチャー端材
- 銀バネ(または黒バネなど好みに応じて)
- ビスまたはキャップスクリュー
- Oリング(13mm用):動きの調整用として
【必要な工具】
- 穴開け・加工用工具:
- ドリルまたはピンバイス(2mm, 2.1mm, 2.5mm)
- Wave社の2.1mmドリル刃が使いやすいとされる
- 座繰り用工具:
- 8mmの円柱砥石:ダイヤモンドインターナルなど
- ダイソーで販売されている砲弾形ビットも代用可能
- その他の工具:
- 瞬間接着剤
- ニッパーやカッター
- 電動ドライバーや三口チャック(オプション)
- リューターがあると作業効率が上がる
材料や工具の選択におけるポイントとしては、例えばボールリンクマスダンパーのFRPは、後日発売された同カーボン(フラット)よりも加工が位置ずれしにくく容易なため、初心者には特におすすめです。
また、キノコヘッドの穴開け作業では、Waveの2.1mmドリル刃が使いやすいとされており、アンカーを頻繁に作る方は持っておくと便利です。座繰り作業には8mmの円柱砥石が非常に有効で、これがあると作業がかなり楽になるという声も多いです。
工具については必ずしも高価なものが必要というわけではなく、例えば電動ドライバーと三口チャックを組み合わせることで、リューターほど回転数が速くないため、ヤスリの目が詰まりづらく使いやすいという利点もあります。
ミニ四駆リアアンカーの取り付け位置は走行特性に大きく影響する
リアアンカーの取り付け位置や向きは、マシンの走行特性に大きな影響を与えます。独自調査の結果、以下のような重要なポイントが明らかになりました。
まず、アンカーを取り付ける際の基本的な原則として、バンパーは稼動穴に対して進行方向後ろ側に配置することが重要です。この配置によって、壁に接触した際の力を適切に受け止め、マシンを安定させることができます。
稼動穴に対して前側にバンパーを付けるケースも見かけますが、この場合は本来の機能を果たさないことがあります。それは、前側に配置すると、壁との接触時に支柱を軸に後方に捻れる動きをしてしまい、バンパーの機能が低下して逆にコースアウトなどのイレギュラーの原因となり得るからです。
アンカーの動作原理を図解すると、通常の配置では以下のような力の伝達が行われます:
- マシンが進行して壁にローラーが接触
- 支柱を軸に後部押さえ(およびユニット後部)でその力を受け止める
- 後方に引かれる(前方から押される)力に耐える
一方、バンパーが支柱より前にある場合:
- マシンが進行して壁にローラーが接触
- 矢印の方向から力が掛かる
- 後方に引かれる力により、支柱を登るような後方に捻れる動き
- フロントATバンパーのスラスト抜けのような現象が発生
また、後ろのバンパー押さえ(支えるパーツ)の長さも重要で、長すぎるとアンカーの動きを阻害し、ただ上下するだけのATバンパーと変わらない機能になってしまいます。一般的には、後ろのバンパー押さえは短く、あっても「湯呑み」程度のサイズが適切とされています。
シャーシとの相性も考慮すべき点で、特にMSシャーシに特化した構造のギミックとして開発されましたが、現在では他のシャーシにも応用されています。ただし、シャーシに合わせた調整が必要になることがあります。
リアアンカーをVZシャーシなど特定のシャーシに取り付ける場合は、そのシャーシの特性に合わせた独自の工夫が必要になることもあります。
ミニ四駆リアアンカー作りで最も重要なのは支柱の固定方法
リアアンカーの製作において、最も重要なポイントの一つが支柱の固定方法です。独自調査によると、多くの製作者が「支柱は固定する必要がある」と結論づけています。
支柱が適切に固定されていないと、以下のような問題が発生する可能性があります:
- バンパーが跳ねて戻らない
- 根元がすぐに壊れる
- バンパー後ろ側押さえが長くなければ使えない
これらの問題は、支柱が固定されていないことや正しい取り付け方がされていないことによって起こりやすくなります。1軸アンカーではその構造上、支柱に負担が集中するため、この点は特に注意が必要です。
【支柱の固定方法】
- 両ネジシャフトを利用する方法:
- 両ネジシャフトを基部に固定
- 両ネジシャフトナット部とボールリンクFRPがフラットになるよう基部またはボールリンクFRP側を厚底にする
- アンダースタビヘッドの穴を拡張する方法:
- アンダースタビヘッドの穴を拡張
- 2段アルミローラー用5mmパイプなどを通して上部ナットで締め上げ固定
- MSシャーシの場合の方法:
- ユニットのバンパーステー穴上部にステーを渡す
- 基部とステーでアンカーを挟む形でキャップスクリュー等を通し上部ナット止め
これらの固定方法のうち、どれを選択するかはシャーシの種類やパーツの入手しやすさによって変わってきます。例えば、ネジ山がアンダースタビヘッドの動きを阻害する場合は、両ネジシャフトに変更するといった対応が考えられます。
さらに、動きをスムーズにするための工夫として、Oリングを使用する方法も紹介されています。13mm用のOリングを穴とアンダースタビヘッドに合わせ、FRP上に接着し、砲弾形ビットで内側を慣らしてすり鉢状の延長となるようにします。これにより、ダンパーグリスと併用することで、適度な減衰とアンダースタビヘッドとのカップリングを向上させることができます。
支柱の固定は、アンカーの耐久性だけでなく、その動作特性にも大きく影響します。しっかりと固定することで、アンカーの本来の機能を最大限に発揮させることが可能になるのです。
ミニ四駆リアアンカーの応用とセッティング
- リアアンカーとATバンパーの違いは可動方向と構造にある
- 2軸リアアンカーの特徴は多方向への可動性の向上
- VZシャーシへのリアアンカー搭載方法は独自の工夫が必要
- ミニ四駆リアアンカーのデメリットは安定性とメンテナンス性
- リアアンカーのセッティングはバネの強さと穴の形状が重要
- リアアンカーの性能を最大化するコツはコース特性に合わせること
- まとめ:ミニ四駆リアアンカーは走行の安定性と復帰率を高める重要パーツ
リアアンカーとATバンパーの違いは可動方向と構造にある
ミニ四駆の世界では、リアアンカーとATバンパー(アクティブトルクバンパー)はどちらもコース復帰率を向上させるためのギミックですが、両者には明確な違いがあります。独自調査の結果、以下のような違いが明らかになりました。
【リアアンカーとATバンパーの主な違い】
- 可動方向の違い:
- ATバンパー:主に上下方向への動き
- リアアンカー:上下方向に加え、左右へのスライドや後方への稼働も可能
- 構造の違い:
- ATバンパー:バネによる上下の稼働が基本
- リアアンカー:1軸(または2軸)を中心にした回転運動と、スライド機能を持つ
- 効果の違い:
- ATバンパー:主に垂直方向の衝撃を吸収
- リアアンカー:多方向からの衝撃を吸収し、特にコーナーリング時の回頭性向上も期待できる
- セッティングの柔軟性:
- ATバンパー:バネの強さによる調整が主
- リアアンカー:バネの強さに加え、穴の形状や支柱の固定方法など多彩な調整が可能
ATバンパーは構造がシンプルで、実績から信頼性も高いという利点があります。一方、リアアンカーはより複雑な動きができる反面、セッティングの難易度も高くなる傾向があります。
あるレーサーが述べたように、「上下ならばATバンパーの方が実績から信頼性がある」という意見もあり、単純に上下の動きだけを求めるならATバンパーで十分かもしれません。しかし、コーナーリング性能の向上や多方向からの衝撃吸収を求める場合は、リアアンカーの方が適しているといえるでしょう。
実際、あるレーサーがリアアンカーを使用した際に感じたメリットとして「レーンチェンジ(LC)が楽になった」という報告もあります。これは、リアアンカーのスライド機能によってコースの壁との接触時の衝撃が分散され、レーンチェンジがスムーズになった結果だと考えられます。
アンカーがリジット(完全固定)より回頭性も上がる可能性があるという意見もあり、コーナーリング性能を重視するレーサーにとっては検討の価値があるでしょう。
2軸リアアンカーの特徴は多方向への可動性の向上
ミニ四駆の世界では、1軸アンカーに加えて2軸リアアンカーも使用されています。2軸リアアンカーの最大の特徴は、より多方向への可動性が向上することにあります。独自調査の結果、2軸リアアンカーについて以下のような特徴が明らかになりました。
【2軸リアアンカーの特徴】
- 可動方向の拡張:
- 1軸アンカー:主に支柱を中心とした回転運動と若干のスライド
- 2軸アンカー:2つの軸による自由度の高い動きが可能
- 適応性の向上:
- 様々なコースレイアウトや走行条件に対して、より柔軟に対応できる
- 特に複雑なコース形状や高速域での安定性が向上
- セッティングの多様性:
- 2つの軸それぞれに対して調整が可能
- 戦うコースレイアウトによって、後方、左右に稼働するバランスを柔軟に変更できる
2軸アンカーの構造は1軸アンカーよりも複雑になりますが、その分より高度な機能を実現しています。例えば、一人のレーサーの例では、2018年の公式大会で2軸アンカーを使用した際、「ドラゴンから飛び込みで、車体が左右にブレても上方向へ逃げて収まり、コースギャップに対しても左右のスライドも出来て、少しだけ後ろにも下がるアンカー」で優勝したという実績があります。
また、別のレーサーは2018年5月のバッコブ大会では、「左右後方へ稼働時にかかる力の支えの支点を左右2点ではなく、真ん中1点で取って、後方にはほとんど稼働しない形」にしたアンカーで優勝しています。このように、2軸アンカーはレースの状況やコース特性に合わせて様々なセッティングができる柔軟性を持っています。
2軸アンカーの製作は1軸アンカーよりも複雑になりますが、MA/VZ/FM-Aなどのシャーシに対応した製作方法もYouTubeなどで紹介されており、興味のあるレーサーはそれらを参考にすることができます。
ただし、2軸アンカーは1軸アンカーよりもさらに調整の難易度が高まる傾向があり、セッティングには経験と試行錯誤が必要になることが多いです。その特性を最大限に活かすためには、実際のレースや練習走行を通じて自分のマシンに最適な状態を見つけていくことが重要でしょう。
VZシャーシへのリアアンカー搭載方法は独自の工夫が必要
VZシャーシは、その独特の構造から、リアアンカーを搭載する際に特別な工夫が必要となります。独自調査によると、VZシャーシへのリアアンカー取り付けには以下のようなポイントがあります。
【VZシャーシへのリアアンカー搭載のポイント】
- 取り付け位置の選定:
- VZシャーシの後部構造は他のシャーシとは異なるため、標準的なリアアンカーの取り付け方法では対応できないことがある
- リアユニットの形状に合わせた取り付け方法を考える必要がある
- 支柱の固定方法の工夫:
- VZシャーシの場合、標準的な支柱固定方法が使えないケースがある
- リアユニットの構造に合わせた独自の固定方法を開発する必要がある
- バンパー部分の形状調整:
- VZシャーシのリア部分の形状に合わせて、バンパー部分の形状も調整する必要がある
- 特にローラー配置などとの干渉に注意が必要
VZシャーシ向けのリアアンカー搭載方法については、YouTubeなどの動画サイトで「【ミニ四駆】簡単2軸リヤアンカーを作ろう!【MA/VZ/FM-A】」といったタイトルの解説動画が公開されています。これらの動画では、VZシャーシの特性に合わせたアンカーの製作方法や取り付け方法が詳しく解説されているようです。
VZシャーシは比較的新しいシャーシであり、リアアンカーの搭載方法もまだ発展途上の部分があります。そのため、他のレーサーの事例を参考にしつつも、自分のマシンやパーツ構成に合わせて独自の工夫をすることが重要になってきます。
例えば、アンカーの支柱をVZシャーシのリアユニットにどのように固定するか、バンパー部分の形状をどのように調整するか、といった点は、自分のマシンの特性や目指す走りのスタイルに合わせて検討する必要があります。
また、VZシャーシは高速走行に適した特性を持つシャーシであるため、リアアンカーのセッティングも高速域での安定性を重視したものになる傾向があります。バネの強さや可動範囲の調整にも注意を払うことが、VZシャーシの性能を最大限に引き出すポイントとなるでしょう。
ミニ四駆リアアンカーのデメリットは安定性とメンテナンス性
リアアンカーは多くの利点を持つ一方で、いくつかのデメリットも存在します。独自調査の結果、以下のようなデメリットが明らかになりました。
【リアアンカーの主なデメリット】
- 安定性の課題:
- 「アンカーはマシンが速ければ速い程マシンの安定さを維持するのも構造上難しくなる」という特性がある
- 高速走行時に予期せぬ動きをすることがあり、かえって不安定になるケースも
- 調整の難しさ:
- 適切なセッティングを見つけるには多くの試行錯誤が必要
- 「扱いが難しい」という意見も多く、初心者には敷居が高い場合がある
- メンテナンス上の問題:
- 構造が複雑なため、メンテナンスや修理が難しい
- 支柱に負担が集中するため、「根元がすぐ壊れる」といった耐久性の問題も
- 速度への影響:
- 「コレ付けたから速くなる訳では特にない」という指摘もある
- むしろ「壁に引っ掛からない綺麗な着地の方が全体的には速い」とも言われている
これらのデメリットは、リアアンカーの使用を検討する際に考慮すべき重要な点です。特に、高速域での安定性の問題は無視できない要素で、初期のリアアンカーが「3レーンには良いけど…」と評価されていた背景にも、この問題があったと考えられます。
また、アンカーの調整には多くの時間と労力が必要です。ある熟練レーサーは、「この頃の1番の検証はレースであり、優勝しても次のレースでは同じ形のアンカーセッティングはしていなかった」と述べており、常に改良を重ねる必要があることを示唆しています。
メンテナンス面では、支柱の固定方法やバネの調整、穴の形状など、多くの要素を適切に管理する必要があり、レース中のトラブルにも迅速に対応できる知識と経験が求められます。
これらのデメリットを踏まえた上で、リアアンカーを使用するかどうかは、自分の走りのスタイルやレース環境、技術レベルなどを総合的に判断する必要があるでしょう。例えば、技術的な挑戦を楽しめるレーサーや、イレギュラーな状況での復帰率を特に重視するレーサーにとっては、これらのデメリットを上回るメリットがあると感じるかもしれません。
リアアンカーのセッティングはバネの強さと穴の形状が重要
リアアンカーの性能を最大限に引き出すためには、適切なセッティングが欠かせません。独自調査によると、特にバネの強さと穴の形状が重要な要素となっています。
【リアアンカーのセッティングポイント】
- バネの選択と調整:
- 銀バネ、黒バネなど、強さの異なるバネを選択可能
- バネの締め具合によって可動範囲や復元力が変化
- 締める位置の調整でも可動特性が変わるため、いろいろ調整することが推奨されている
- 穴の形状と加工:
- すり鉢状の穴の角度や深さによって、アンカーの動きが大きく変わる
- 「削りながらいい塩梅をみつけてください」と言われるほど、この加工は重要
- 「この辺りの動きとかは好みがあると思いますので、自分の好みに調整できるように試行錯誤するしかない」という意見もある
- グリスの使用:
- 穴にはダンパーグリスを塗り、動きをスムーズにする
- グリスの粘度によっても動きの特性が変わる
- Oリングとの組み合わせで、適度な減衰とカップリング向上が期待できる
- キノコヘッドの形状調整:
- キノコヘッドを削り込むことで、動きの特性をカスタマイズできる
- 市販のキノコヘッドには色々な色があり、それぞれ若干特性が異なる可能性もある
- 軸の固定度合い:
- 支柱の固定方法や固定の強さも調整ポイント
- 完全に固定するか、若干の遊びを持たせるかで特性が変わる
リアアンカーのセッティングは、レースのコース特性や自分のマシンの走行スタイルに合わせて調整することが重要です。例えば、高速コーナーが多いコースでは、左右のスライド性能を重視したセッティングが有効かもしれません。一方、ジャンプやドラゴンなどの高低差がある場所が多いコースでは、上下の可動性を重視したセッティングが適しているでしょう。
また、ある熟練レーサーは、長年の経験から「上下のいなす動きだけは、絶対に硬くしない事」という結論に達しています。これは、コース壁に乗り上げた際に、上方向への逃げが最も重要だという認識からきていると思われます。
セッティングの多様性こそが、リアアンカーの魅力の一つでもあります。「自分のマシンにあった調整ができるとよい」というアドバイスが示すように、自分だけの最適なセッティングを見つけることが、リアアンカーを使いこなす鍵となるでしょう。
リアアンカーの性能を最大化するコツはコース特性に合わせること
リアアンカーの性能を最大限に引き出すためには、コース特性に合わせたセッティングが非常に重要です。独自調査によると、以下のようなポイントがコース特性に合わせたセッティングの鍵となります。
【コース特性に合わせたリアアンカー調整のポイント】
- コースレイアウトの把握:
- ショートコース vs ロングコース
- 都内のコースは「どこもショートコースなので、すぐに登って、下って、のアップダウンが多く、またコーナーから直下りなどの展開が早いコース」という特徴がある
- より大きめの25秒〜30秒あたりのコースでは、コーナーリング性能が重要になる
- コーナー特性に合わせた調整:
- 「コーナーのキレが今ひとつ良くない」という課題に対しては、「後ろへ下がることも出来るアンカー」を検討
- 「コーナーリング中に少しでもマシンの進行方向への角度が真っ直ぐに近くなる方が速い」という考え方がある
- コース素材への対応:
- 3レーンと5レーンでは素材が異なる点に注意
- 「5レーンはセクションの自重で固定しているらしいです。なので設置方法によってはコースの壁にギャップが生まれ」るという特性を考慮
- アップダウンへの対応:
- 上下動の大きいコースでは、上方向への可動性を特に重視
- 「上下のいなす動きだけは、絶対に硬くしない事」という経験則もある
- レーンチェンジ(LC)対策:
- 「LCが楽になった」というメリットを活かすセッティング
- 左右へのスライド性能を調整する
リアアンカーのセッティングは、一度決めたら終わりというものではなく、継続的な改良が重要です。ある熟練レーサーは、「2016年12月から翌年1年間、色々な場所で走りそれぞれの走りの中で、改良を加えて、2018年初頭に一つの答えの形にたどり着きました」と述べており、長期間にわたる試行錯誤の重要性を示唆しています。
また、同じレーサーは「戦うコースレイアウトによって、後方、左右に稼働するバランスは、支点サポートのゴムも使って柔軟にセッティングを変えていく事」を重視しています。つまり、一つのセッティングをすべてのコースで使うのではなく、コースごとに最適なセッティングを探す姿勢が大切なのです。
さらに、レース当日の状況(気温や湿度、コースの状態など)によっても、アンカーの挙動は変わる可能性があります。そのため、練習走行での様子を見て微調整を行うことも、リアアンカーの性能を最大化するための重要なプロセスとなるでしょう。
まとめ:ミニ四駆リアアンカーは走行の安定性と復帰率を高める重要パーツ
最後に記事のポイントをまとめます。
- リアアンカーは壁に乗り上げた際の復帰率向上が主目的のギミック
- 1軸アンカーは支柱を中心に上下左右に動き、コース復帰をサポートする
- アンカーの基本構造は1軸のバンパーでキノコを使用し、AT的な動きとスライド機能を持つ
- リアアンカー製作には弓FRP/カーボン、ボールリンクFRP、キノコヘッド、バネなどが必要
- 穴の座繰り加工と支柱の固定が製作時の重要ポイント
- 支柱は固定する必要があり、固定方法には複数の選択肢がある
- ATバンパーは上下の動きが主だが、アンカーは左右や後方への動きも可能
- 2軸アンカーはより多方向への可動性を持ち、高度なセッティングが可能
- VZシャーシへの搭載には独自の工夫が必要
- リアアンカーは高速域での安定性の維持が難しいというデメリットもある
- バネの強さ、穴の形状、グリスの粘度などでセッティングを最適化できる
- コース特性に合わせたセッティング調整が性能最大化の鍵
- アンカーは単に付けるだけでは速くなるわけではなく、適切な調整が必要