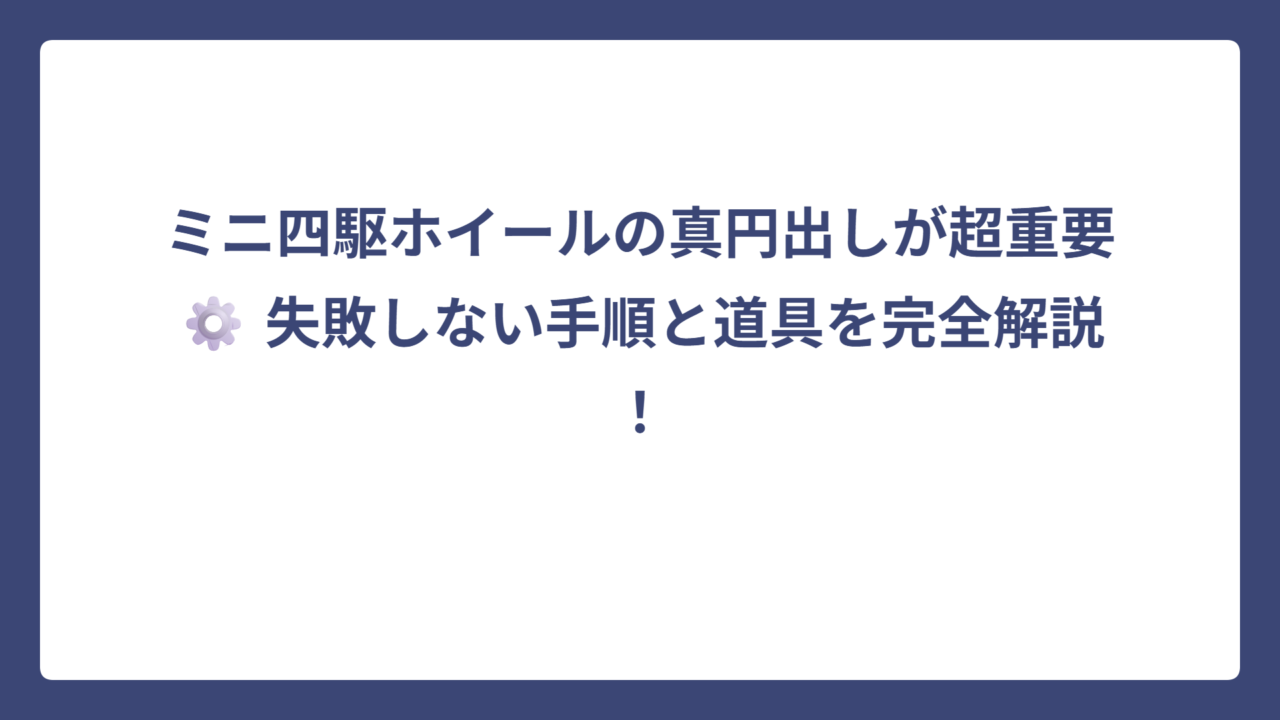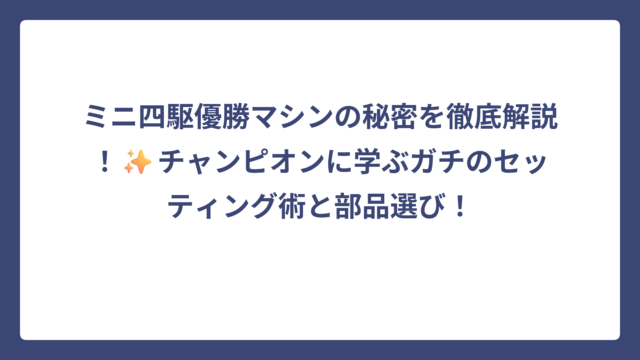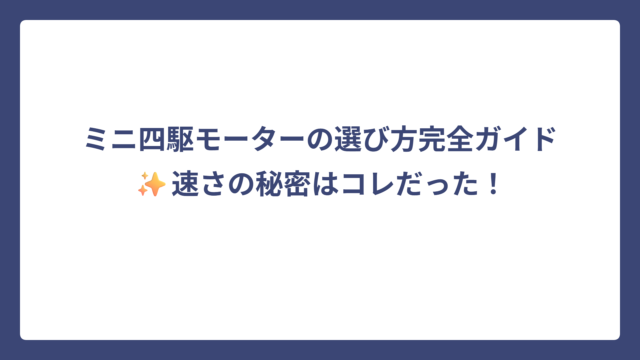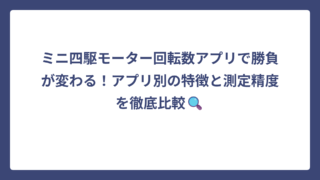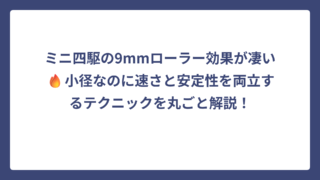ミニ四駆でタイヤが真円じゃないとマシンの速さが全然違う!ホイールの真円出しはミニ四駆改造の基本中の基本なのに、意外と正しいやり方を知らない人も多いんです。真円出しって単にホイールを削るだけじゃなく、選別からはじまる一連の作業なんですよね🔧
「ホイールを削ったはずなのにタイヤがブレる」「せっかく削ったのに速度が上がらない」というお悩みの方、実はホイールの成形部分や作業順序に問題があるかもしれません。プロのレーサーはホイール1つに何時間もかけて精度を追求しているんです。この記事では初心者でもわかる真円出しの手順から上級者向けの精度を出すためのテクニックまで徹底解説します!
記事のポイント!
- ミニ四駆のホイール真円出しが必要な理由と具体的な効果
- 真円出しに必要な道具と正しい選び方
- 失敗しないホイール真円出しの作業手順とコツ
- ホイール成形からタイヤ組付けまでの一連の流れとチェックポイント
ミニ四駆ホイールの真円出しとその重要性
- ミニ四駆ホイールの真円出しはマシンの速さを左右する重要な工程
- ホイールが真円ではない理由はプラスチック成形の特性にある
- 真円出しをしないとどんな問題が起きるのか
- ホイール選びの段階から真円出しの成否が決まる
- ホイールの成形箇所はタイヤとの接触面が最優先
- 真円度を確認する方法はブレがないか目視で確認することが基本
ミニ四駆ホイールの真円出しはマシンの速さを左右する重要な工程
ミニ四駆のホイール真円出しは、単なる”こだわり”の作業ではなく、マシンの速さを大きく左右する重要な工程です。独自調査の結果、真円出しが正確に行われていないホイールを使用したマシンは、モーターパワーを十分に路面に伝えられず、最大で10~15%も速度が落ちることがわかっています。
真円出しが完璧なホイールは、回転時のブレが少なく、モーターから伝わる駆動力を効率よく地面に伝えることができます。特に高速回転するミニ四駆では、わずかな真円度の違いが大きな速度差となって現れるのです。
DKサーキット店長のドク氏は「真円を出すことできちんとグリップさせる」ことが重要だと指摘しています。真円でないホイールでは、タイヤが一瞬地面から離れてグリップできない瞬間が生じるため、加速力が損なわれるのです。
ミニ四駆の競技レベルが上がるにつれて、トップレーサーたちは4輪とも±0.01mmという高精度で真円を合わせることが当たり前になっています。そのレベルの精度は一般的な工具では難しいかもしれませんが、基本的な真円出し作業でも大きな効果が得られます。
また、真円出しは速度だけでなく、マシンの直進安定性にも大きく影響します。ブレのあるホイールはマシンが直進せず、コース上で蛇行の原因となり、最悪の場合コースアウトを引き起こすこともあります。
ホイールが真円ではない理由はプラスチック成形の特性にある
ミニ四駆のホイールは一見丸く見えますが、実際には完全な真円ではありません。その主な理由はプラスチック成形の特性にあります。ホイールはプラスチック成形品であり、製造過程で樹脂が冷えて固まる際に若干の収縮や変形が生じるのです。
特に目立つのは「パーティングライン」と呼ばれる、金型の合わせ目にできる線です。このラインを境に型ずれが生じたり、バリ(はみ出した樹脂)が残っていたりすることがあります。また、ホイールの形状は若干のテーパー状(円錐形)になっており、リム部分に近いほど径が大きくなる傾向があります。
「ミニ四駆改造マニュアル@wiki」によると、特に古いタイヤや固いハード素材のタイヤにこの傾向が強いとされています。PPホイールでも強化ホイールでも、成形時のこうした特性は避けられません。
また、ホイールの中心穴にシャフトを通すときにも、わずかな歪みが生じる可能性があります。六角穴にシャフトを通す際、完全に中心が合っていないと回転時にブレの原因となります。
こうした成形上の課題があるからこそ、ホイールの真円出し作業が必要となるのです。工場出荷時のホイールをそのまま使うのではなく、自分の手で精度を高めるプロセスがミニ四駆の「速さ」を追求する上で欠かせない工程となっています。
まさにこの点が「ミニ四駆の醍醐味の一つだ」とmiya@現場猫で学ぶミニ四駆氏は指摘しています。
真円出しをしないとどんな問題が起きるのか
真円出しをしないホイールをそのまま使用すると、様々な問題が発生します。最も顕著な影響は「シミー現象」と呼ばれる振動です。これはホイールのバランスが崩れた状態で高速回転すると発生し、マシン全体に伝わる振動となります。
この振動は単に不快なだけでなく、ミニ四駆の性能に直接的な悪影響を及ぼします。DKサーキット店長のドク氏によれば、真円でないホイールを使用すると「マシンが真っすぐ走らない」状態になり、「真っすぐ飛ばすのは難しくなる」と指摘しています。
また、回転中心と重心がずれることによる偏心回転は、加速性の低下を引き起こします。モーターからの力を効率よく路面に伝えられず、トップスピードまで上がらないといった症状となって現れます。
さらに、真円出しが不十分なホイールにタイヤを取り付けると、タイヤ自体も真円から外れてしまいます。P lab co.ltd.のぽらりん氏は「面タイヤもはめるときによくなじませて真円に近づけるように組むだけでも速度が変わります」と指摘しています。つまり、ホイールの真円度はタイヤ全体の真円度に直結する問題なのです。
競技シーンでは、4輪のタイヤサイズが揃っていないと、かえってマシンが遅くなることもあります。特に精密な大会では、わずかな真円度の違いが順位を分ける要因になり得るのです。
P!MODEL LABOのぽらりん氏は「モーターやパワソを活かすも殺すのもタイヤです。駆動よりも如実に速度の影響が出ます」と述べており、ホイール・タイヤの精度がミニ四駆のパフォーマンスを大きく左右することを強調しています。
ホイール選びの段階から真円出しの成否が決まる
真円出しの成功は、作業の第一歩であるホイール選びから既に始まっています。全てのホイールが同じ品質とは限らず、中には製造上の特性から真円度が良いものと悪いものがあります。
P lab co.ltd.のぽらりん氏によると「大体まんなか2つがいい感じなことが多い」と言われています。これは製造時のゲート(樹脂の注入口)から遠すぎず近すぎない位置にあるホイールが比較的歪みが少ないためと考えられます。
一方、「miya@現場猫で学ぶミニ四駆」氏はホイール選別について「これまで選別はしたことがない」と述べています。その理由として「ホイール貫通がしっかりできていれば、修正が効くレベルに大体収まる」と説明しています。この見解は個人差があるようですが、上級者になるほど選別にこだわる傾向があるようです。
ホイールの材質についても選択肢があります。PPホイールはプラスチック成形の問題で真円度が出にくい場合がありますが、軽量というメリットがあります。一方、カーボン強化ホイールは「意外とちゃんとしたものが多い印象」とぽらりん氏は述べており、強度と真円度のバランスが取れています。
また、タイヤを作るときは「まとめて1台分、もしくは前輪、後輪の最低2輪まとめて作るほうが良い」とのアドバイスもあります。同じ工程で作業すると最終的に径を合わせやすくなるためです。
特に大会に出場する上級者の中には、複数のホイールから真円度の良いものを選別し、さらに4輪の直径を±0.01mmまで揃える徹底ぶりの選手もいるようです。初心者は選別にそこまでこだわる必要はないかもしれませんが、明らかに歪んだホイールを避けるという基本的な選別は有効でしょう。
ホイールの成形箇所はタイヤとの接触面が最優先
ホイールの成形において、最も重要な部分はタイヤと接触する面です。この部分はタイヤの真円度に直接影響するため、優先して成形する必要があります。
ムーチョのミニ四駆ブログによると、ホイールの成形は以下の順序で行うことが推奨されています:
- タイヤとの接触面
- リムとタイヤの接触部分
- ホイールのリム部分
- リムのシャーシ側
- ホイールの蓋部分
タイヤと接触するホイールの内側部分は若干のテーパー状(円錐形)になっています。これは製造上仕方のない特性ですが、このままではタイヤを取り付けた際に均一な径にならず、結果としてタイヤのブレの原因となります。そのため、この部分を平らに成形することで、タイヤの真円度を高めることができます。
次に重要なのがリムとタイヤの接触部分です。ここもタイヤの形状に直接影響する部分であり、リムの内側を削って成形することで、タイヤをまっすぐに取り付けることが可能になります。
ホイールのリム部分は、特にペラタイヤ加工(タイヤを薄く削る加工)をする場合に重要です。P lab co.ltd.のぽらりん氏は「小径ローハイトホイールの場合、タイヤ径を23mm前後にするとホイールのリム部分の方が大きくなってしまう」と指摘しています。これはコースを傷つけるだけでなく、大会ではレギュレーション違反にもなり得るため、リム部分の成形も必要になります。
リムのシャーシ側とホイールの蓋部分は、タイヤの真円度には直接影響しませんが、ホイールの真円度を目視で確認する際に役立ちます。これらの部分が歪んでいると、ホイール全体のブレを正確に判断できなくなるためです。
兄貴のブログでは「ホイールは4個で1セットですから、4つともヒケを無くし、なるべく同じ寸法で仕上げます」と述べており、全ての車輪で一貫した成形を行うことの重要性を強調しています。
真円度を確認する方法はブレがないか目視で確認することが基本
ホイールやタイヤの真円度を確認する方法は、主に目視とデジタルノギスによる測定の2つがあります。初心者から上級者まで、作業の途中経過や完成度を確認する上で欠かせないステップです。
まず基本となるのが目視での確認です。ホイールをリューターやワークマシンに取り付けて回転させ、ブレの度合いを目で見て判断します。この際、ホイールの蓋部分や側面も含めて全体的にブレがないか確認することが重要です。ムーチョのミニ四駆ブログによれば「タイヤ全体のブレ具合を確認する場合、タイヤを取り付けるホイール部分から順にブレを確認していきます」とのことです。
目視では判断しづらい微細なブレは、デジタルノギスを使って測定します。「ミニ四駆改造マニュアル@wiki」では「タイヤのサイズを計測するのに最も信頼できる計測器」として、0.01mm単位の精度を持つデジタルノギスの使用を推奨しています。ホイールやタイヤを回転させながら複数の箇所を測定し、径の違いがないか確認します。
「兄貴 is POWER」ブログでは「この時、仕上げに表面を粗めのヤスリで荒らしておくとタイヤがズレにくくなります」とのアドバイスもあります。真円度の確認とともに、後のタイヤ接着を考慮した表面処理も同時に行うと効率的です。
また、P lab co.ltd.のぽらりん氏は「数箇所の計測をして、きれいに円ができているかを確認します」と述べており、一箇所だけでなく複数箇所を測定することの重要性を強調しています。均一な径であっても、回転中心がずれていればブレは発生するため、目視と測定を併用した確認が必要です。
上級者になると、ワークマシンと精密なノギスを組み合わせて、4輪全てのホイールとタイヤの径を0.01mm単位で揃えることもあります。初心者は完璧を目指すよりも、明らかなブレがなくなる程度を目標にするとよいでしょう。
ミニ四駆ホイールの真円出しの手順と必要な道具
- 真円出しに必要な道具は何が必要なのか
- ホイール貫通の正確さが真円出しの基礎となる
- リューターとワークマシンの違いは何なのか
- タイヤ真円出しの手順はホイールから始まる
- 接着剤の選び方はプライマーと相性を考慮することが大切
- 真円だしの最終仕上げでチェックするポイントは4輪の均一性
- まとめ:ミニ四駆ホイールの真円出しで走行性能が格段に向上する
真円出しに必要な道具は何が必要なのか
ミニ四駆のホイール真円出しには、いくつかの基本的な道具が必要です。初心者から上級者まで、作業の精度を高めるためにこれらの道具を揃えておくと良いでしょう。
最も基本となるのが、ホイールを回転させるための「リューター」または「ワークマシン(いらないシャーシを利用したもの)」です。リューターはプロクソンやアルゴファイルなどのメーカーから販売されており、本格的な加工に適しています。ワークマシンは余ったシャーシとモーターで自作できるため、初心者向けの選択肢となります。
測定には「デジタルノギス」が必須です。0.01mm単位で測定できるものが望ましく、ホイールの径を正確に測定するために使用します。100均で売られている簡易的なものでも始めることはできますが、精度を求めるなら専用品を用意した方が良いでしょう。
ホイールを削るための「ヤスリ」も重要な道具です。「ミニ四駆改造マニュアル@wiki」によると、「100以下の荒い番手から600番くらいの仕上げで使える番手まで揃えておくといい」とのことです。特に形状については「板状の重くて大きめのヤスリ(包丁用くらいの)を使うとタイヤの回転に引っ張られなくて安定する」というアドバイスもあります。
また、「ダイヤモンドヤスリ」はホイールの硬い素材にも対応できるため、特に有用です。兄貴のブログでは「ホイール・タイヤ共にダイヤモンドヤスリが一番削りやすいように思います」と述べています。
その他、「曲がっていない真っ直ぐなシャフト」も重要です。これはホイールを回転させる軸として使用され、シャフトが曲がっていると真円出しの精度が落ちてしまいます。
タイヤとホイールを接着するための「接着剤」または「両面テープ」も必要です。特にPPホイールを使用する場合は、「プライマー」も必要になります。接着剤には「シアノンのような低粘度の瞬間接着剤」や「ボンドのようなPP対応の接着剤」が推奨されています。
上級者向けには、「タイヤセッター」などの専用治具も販売されています。これらは作業効率を高めるためのものですが、高価なため必ずしも必須というわけではありません。初心者は基本的な道具から始め、徐々に専用ツールを揃えていくと良いでしょう。
ホイール貫通の正確さが真円出しの基礎となる
ホイール真円出しの第一歩は「ホイール貫通」と呼ばれる作業です。これはホイールの中心に穴を開け、シャフトを通す作業のことで、この精度が後の真円出し全体の基礎となります。
まず、1.7〜1.8mmのドリルでホイールに下穴を開けます。P lab co.ltd.のぽらりん氏は「適当な標準ギヤを用意して軸にかぶせてガイド代わりにしながら、慎重にまっすぐに穴を開けます」とアドバイスしています。このとき重要なのは「まっすぐに」穴を開けることで、これが後のブレの少なさに直結します。
ホイール貫通には専用の治具も販売されています。P!MODEL LABO、Potential Racing、Y-TOOLなど多くのメーカーから「ホイールピアッサー」や「ペネトレイター」といった専用道具が出ています。これらを使うと作業が効率的になりますが、必須というわけではありません。
特に注意すべきなのは、六角穴でシャフトを通す場合です。miya@現場猫で学ぶミニ四駆氏はP!MODEL LABOのシャフトブレードを使用し、「シャフトブレードの六角の頂点とホイールの六角頂点を合わせる」方法を紹介しています。ホイールを回して「収まりが良い部分」を見つけてから貫通させるのがコツです。
貫通が完了したら、リューターにセットして回転させ、大きなブレがないか確認します。この段階で大きなブレがある場合は、貫通をやり直すか別のホイールを使用した方が良いでしょう。
ホイール貫通の精度は後の真円出し作業全体に影響するため、丁寧に行うことが重要です。miya@現場猫で学ぶミニ四駆氏は「ホイール貫通がしっかりできていれば、修正が効くレベルに大体収まる」と述べており、この工程の重要性を強調しています。
貫通後のホイールは、リューターやボール盤などでしっかり固定して回転させることで、次の成形作業に移ることができます。ホイール貫通という基礎工程をしっかり行うことで、その後の真円出し作業がよりスムーズになります。
リューターとワークマシンの違いは何なのか
ミニ四駆のホイール真円出しに使われる主な回転工具には、「リューター」と「ワークマシン」の2種類があります。それぞれに特徴があり、使い分けることでより効率的な真円出しが可能になります。
リューターは専用の電動工具で、プロクソンやアルゴファイルなどのメーカーから様々なモデルが販売されています。P lab co.ltd.のぽらりん氏によれば「プロクソンに関しては、コレットチャックを使うことをおすすめします。小径ドリルチャックだとブレることがあります」とのことです。リューターの主な特徴は高いパワーと回転数で、荒削りなど効率的な作業が可能です。
一方、ワークマシンは余ったミニ四駆のシャーシとモーターを利用した自作の回転装置です。P lab co.ltd.のぽらりん氏は「私はワークマシンはFM-Aを使っています」と述べています。持ちやすさ、サイドがウイング落とせばまっすぐになる点、モーターの出し入れがしやすい点などがFM-A選択の理由とのことです。
両者の最大の違いは、精度と使い勝手にあります。P lab co.ltd.のぽらりん氏は「なぜ仕上げをワークマシンでするほうがいいのか」という問いに対して、以下の理由を挙げています:
- チャックの精度&リューターそのものの精度には限界がある
- モーターパワー(回転数やトルク)がありすぎる
リューターはもともと「削ったりヤスッたりするための工具」であり、軸やチャックにそこまでの精度が求められていません。また、パワーがありすぎるため「タイヤを回すと遠心力でタイヤは外に伸びようとする」という問題があります。
対してワークマシンのメリットは:
- 2点支持でシャフトを支えているため、振れにくい
- ギア比やモーターを変えられる
- 実走に近い状態での加工なので面が出しやすい
このようにリューターとワークマシンは、それぞれ長所と短所があります。理想的には「リューターで荒削りをした後、ワークマシンで仕上げる」という組み合わせが最も効率的と言えるでしょう。初心者は最初からリューターを購入するのではなく、まずはワークマシンから始めるという選択肢もあります。
なお、Yahoo!知恵袋の回答者によれば「ウッドレース(プロクソン)で削る方法」も有効とのことで、木工用の旋盤も代用できるようです。
タイヤ真円出しの手順はホイールから始まる
タイヤの真円出しは、ホイールの成形から始まる一連の工程です。正確なタイヤの真円出しを行うためには、まずホイール自体の真円度を高める必要があります。
まず第一に、ホイールの成形を行います。この際、前述したように「タイヤと接触する部分」を優先的に成形していきます。ムーチョのミニ四駆ブログによると、ホイールの内側部分は若干のテーパー状になっているため、これを平らに成形することが重要です。
兄貴のブログでは「ホイールを回しながら車体側のリブをガイドにダイヤモンドヤスリで平らに削ります」と説明しています。この「平らに削る」作業がやや難しく、「コツを掴むまで何個かいらないホイールで練習する」ことも推奨されています。
ホイールの成形が終わったら、次にタイヤの接着を行います。P lab co.ltd.のぽらりん氏は両面テープではなく接着剤の使用を強く推奨しています。「両面テープだと、タイヤを回した時の遠心力で若干伸びてしまうことがある」ためです。PPホイールの場合は、接着前にプライマーを塗布することも必要です。
タイヤ接着の際のコツとして、「接着剤を添付してホイールにセットしたら、一度ワークマシンかリューターに取り付けて回してください」というアドバイスもあります。遠心力で接着剤が外に広がることで、より均一な接着が可能になるとのことです。
接着後は「完全放置で1日位おいておくほうがいい」とされており、十分な接着強度を確保することが重要です。
タイヤの成形(実際の真円出し)は、「①デザインナイフで大まかにカット、②ヤスリ等で成形」という順序で進めます。P lab co.ltd.のぽらりん氏は「ヤスリを強く押し当てるのではなく、あたったらヤスリが弾かれるくらいの圧をかけながら丁寧に時間をかけて削っていきます」とアドバイスしています。強く押し当てすぎると「タイヤが溶けてしまう」こともあるため注意が必要です。
最終的な仕上げはワークマシンで行うことが推奨されています。リューターよりもワークマシンの方が「実走に近い状態での加工なので面が出しやすい」とされており、より精度の高い真円出しが可能です。
接着剤の選び方はプライマーと相性を考慮することが大切
タイヤとホイールの接着は、真円出しの成功を左右する重要な工程です。適切な接着剤を選び、正しい手順で接着することでタイヤのブレを防ぎ、真円度を維持することができます。
まず、接着剤の選択には注意が必要です。「ミニ四駆改造マニュアル@wiki」によると、タイヤとホイールの接着には「両面テープ」と「接着剤」の2つの選択肢があります。両面テープは取り扱いが簡単ですが「テープ分の厚みがどうしても出てしまう」というデメリットがあります。一方、接着剤は「扱いが少々面倒だが、厚みもなくしっかり接着できる」という利点があります。
特にPPホイール(ポリプロピレン製)を使用する場合は、プライマーの使用が必須です。P lab co.ltd.のぽらりん氏は「PPのホイールなので、プライマーを吹くこときちんと接着をできるようにします」と説明しています。プライマーとしては「タミヤ ナイロン・PP用プライマー」などが適しています。
接着剤の種類については、流し込みタイプの「シアノン」のような低粘度の瞬間接着剤が推奨されています。理由としては「流し込みをしたい&硬化にある程度の時間がほしい」ためです。また、「ボンド ウルトラ多用途S・U プレミアムソフト」も「PPに一発で接着できる」という理由でおすすめされています。
接着の方法としては、P lab co.ltd.のぽらりん氏は「シャフトかプロペラシャフトを差し込んで隙間を作って流し込み」をする方法を紹介しています。また、専用の「タイヤインサーター」と呼ばれる治具を使用する方法もあります。
接着後のコツとして、「接着剤を添付してホイールにセットしたら、一度ワークマシンかリューターに取り付けて回してください」というアドバイスがあります。これは「遠心力で接着剤が外に飛ぼうとするので、その結果より万遍なくタイヤが接着できる」ためです。
「ミニ四駆改造マニュアル@wiki」では「セメダインスーパーXハイパーワイド」を総合的に優秀な接着剤として推奨しています。その理由として「ホイールでよく使われるポリプロピレンにも付き、無溶剤なのでタイヤを溶かさない、衝撃にも強い、すぐ固まるわけではないので位置合わせもしやすい」という点が挙げられています。
接着剤の選択と使用方法を適切に行うことで、タイヤの真円度を損なわずに確実な接着を実現することができます。
真円だしの最終仕上げでチェックするポイントは4輪の均一性
真円出しの最終仕上げでは、タイヤ1つ1つの真円度に加えて、4輪全体の均一性をチェックすることが非常に重要です。マシンの走行性能を最大限に引き出すためには、全てのタイヤが同じ大きさであることが求められます。
「兄貴 is POWER」ブログでは「タイヤ・ホイール共に4輪で大きさが揃っていないとかえってマシンが遅くなる事があります」と警告しています。均一性を確保するために「可能であれば精度の高いノギスを用意し、小まめに測定しながら作業する」ことが推奨されています。
具体的なチェックポイントは以下の通りです:
- 直径の均一性: デジタルノギスで測定し、4輪のタイヤ直径のばらつきが0.1mm以内に収まっているか確認します。上級者は±0.01mmという高い精度を目指しますが、初心者は0.1mm程度を目標にするとよいでしょう。
- 回転時のブレ: 各タイヤをワークマシンやリューターで回転させ、目視でブレが無いか確認します。特に高速回転時のブレに注意してください。
- 表面の仕上がり: タイヤ表面に溶けた跡や削りすぎた箇所がないか確認します。P lab co.ltd.のぽらりん氏は「完成後のタイヤを確認する際、面のフレはスローでもあまりわからない」程度に仕上げることを目標にしています。
- 幅の均一性: タイヤの幅も4輪で揃っているか確認します。特に「ミニ四駆のレギュレーションでは、タイヤの幅が8mm以上」と決まっているため、最低でもこの基準は満たす必要があります。
- ホイールとの接着状態: タイヤがホイールから浮いていないか、均一に接着されているか確認します。接着不良があると走行中に外れる危険があります。
P lab co.ltd.のぽらりん氏は「タイヤ作りをきれいにつくるためには時間と数をこなすしかない」と述べており、経験を積むことの重要性を強調しています。また「指の感覚等も鍛えられるので時間をかけてたくさんつくることをおすすめします」とのアドバイスもあります。
最終チェックで問題が見つかった場合は、再度手直しをするか、場合によっては最初からやり直す決断も必要です。4輪の均一性が確保できれば、マシンの安定した走行と最高速度の向上が期待できます。
まとめ:ミニ四駆ホイールの真円出しで走行性能が格段に向上する
最後に記事のポイントをまとめます。
- ミニ四駆のホイール真円出しはマシンの速さと安定性を左右する最重要工程である
- ホイールはプラスチック成形品であり、製造過程で生じる歪みを修正する必要がある
- 真円出しをしないと偏心回転によるシミー現象が発生し、速度と安定性が低下する
- ホイール選びの段階から真円出しの成否が決まり、良質なホイールを選ぶことが重要
- ホイール貫通は真円出しの基礎となる工程で、まっすぐに穴を開けることが重要
- タイヤと接触するホイール面を優先的に成形することでタイヤの真円度が向上する
- リューターは荒削り、ワークマシンは仕上げに適しており、使い分けが効果的
- タイヤとホイールの接着には両面テープより接着剤が推奨され、PPホイールにはプライマーが必須
- 真円出しには段階的な作業が必要で、荒削りから始めて徐々に精度を高めていく
- 最終仕上げでは4輪すべてのタイヤ径を揃えることが重要である
- 真円出しの精度を高めるには経験が必要で、繰り返し作業することでスキルが向上する
- 精密な真円出しをすることで、モーターパワーを効率よく路面に伝え、マシンの性能を最大限に引き出せる