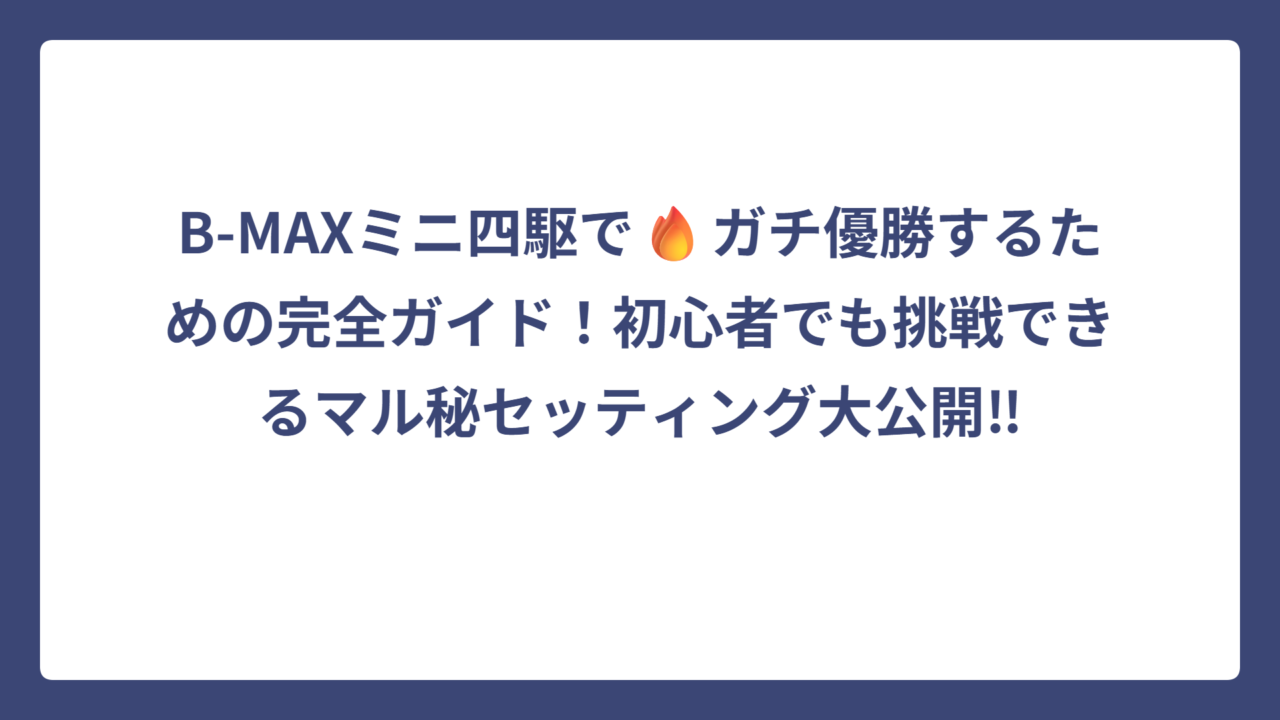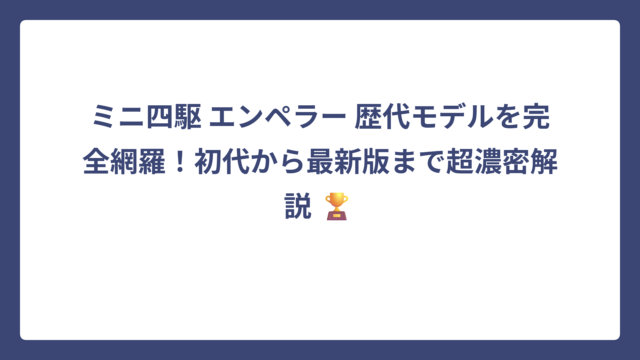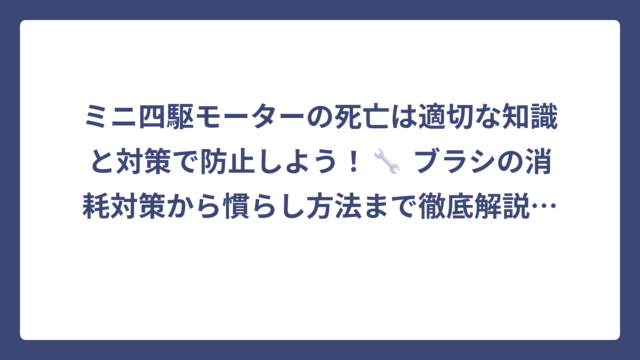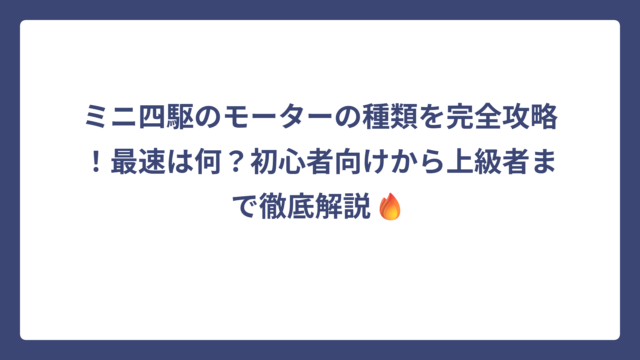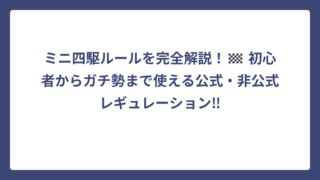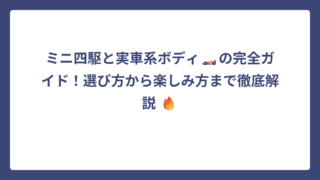B-MAXミニ四駆は、ミニ四駆レースの中でも特に初心者に優しく、かつ上級者も楽しめる人気のレギュレーションとして知られています。タミヤの公認競技会規則をベースとしながら、部品の加工を最小限に抑えた「ポンづけ」と呼ばれる方式を採用しており、誰もが比較的公平な条件で腕前を競い合えるのが大きな魅力です。
この記事では、Basic-MAX GP(B-MAX GP)の競技会規則の内容から、優勝するためのマシンセッティング、初心者におすすめのシャーシ選びまで、独自調査に基づいた実践的な情報をご紹介します。レーンチェンジ攻略の秘訣や人気のローラーセッティングなど、勝利に直結するテクニックも詳しく解説していきます。
記事のポイント!
- B-MAXレギュレーションの基本とオープンクラスとの違い
- 初心者がB-MAXから始めるべき3つの説得力ある理由
- 実際の優勝マシンに学ぶ効果的なセッティング方法
- B-MAXマシンを組み立てるために必要な道具と予算の目安
B-MAXミニ四駆とは?その特徴と基本知識
- B-MAXレギュレーションの基本は「ポンづけ」と「無加工」
- B-MAXとオープンクラスの違いは加工の制限にある
- 初心者にB-MAXがおすすめな理由は簡単さと公平性
- B-MAXレギュレーションで許可される改造と禁止される改造
- B-MAX公式大会の開催情報とレース形式
- B-MAXミニ四駆の予算は初期費用2万円から始められる
B-MAXレギュレーションの基本は「ポンづけ」と「無加工」
Basic-MAX GP(略してB-MAX GP)は、タミヤのミニ四駆公認競技会規則を基本としながら、独自の規則を追加で定めたレギュレーションです。その最大の特徴は「ポンづけ」と呼ばれる、部品をそのまま取り付ける方式を基本としていることです。
B-MAXの基本理念は、「基本無加工のレギュレーションの中で大会が工夫を凝らした競技コースに対して全てのレーサーがフェアプレイ精神のもと頭とテクニックを使って挑戦すること」にあります。つまり、パーツの加工や改造による優位性を排除し、セッティングの工夫やレース戦略によって勝敗を競うことを重視しているのです。
B-MAX GPの実行委員会によると、このレギュレーションの醍醐味は「同じ条件で競い合えるようにする」ことにあります。レース参加者の年齢や性別に関係なく、公平な条件でミニ四駆の速さを競えるようになっています。
B-MAXレギュレーションでは、原則としてタミヤ製のパーツをその形状のまま使用することが求められます。シャーシやボディへの加工は厳しく制限されており、許可される改造は非常に限定的です。例えば、ボディの肉抜きは原型が分かる範囲で認められていますが、過度な加工は禁止されています。
世界中のミニ四駆ファンに共通のルールを提供することで、B-MAXはミニ四駆レースの敷居を下げ、より多くの人が気軽に参加できる環境を作り出しています。これが「ポンづけ」と「無加工」を基本とするB-MAXレギュレーションの本質だと言えるでしょう。
B-MAXとオープンクラスの違いは加工の制限にある
ミニ四駆の競技カテゴリーの中で最も大きな違いを持つのが、B-MAXとオープンクラスです。これらの違いを正確に理解することで、自分に合ったカテゴリーを選ぶ手助けになるでしょう。
オープンクラスはタミヤのミニ四駆公認競技会規則の範囲内であれば、ほぼ何でもOKというレギュレーションです。シャーシの加工はもちろん、FRPやカーボンパーツの自作、ボディの大幅な改造なども認められています。つまり、創意工夫の余地が大きく、カスタマイズの自由度が極めて高いのが特徴です。
一方、B-MAXは「タミヤのミニ四駆公認競技会規則」に加え、「B-MAX独自の規則」が適用されます。この独自規則により、パーツの加工が厳しく制限されており、例えばシャーシの肉抜きや切断は禁止されています。許可されるのは標準ビス穴の2mm拡張や、貫通していないビス穴の貫通加工程度に限られます。
両者の違いを簡潔にまとめると以下のようになります:
| 項目 | B-MAX | オープンクラス |
|---|---|---|
| パーツ加工 | 厳しく制限(基本無加工) | 広範囲に許可 |
| 創意工夫の幅 | セッティングが中心 | 加工も含めて広範囲 |
| 初心者の参入障壁 | 低い | やや高い |
| マシンの製作時間 | 比較的短い | 長い場合が多い |
| 費用 | 比較的抑えられる | 高くなる傾向あり |
B-MAXではマシンの個体差が比較的小さいため、レーサーの技術や知識、セッティングの巧みさがより直接的に結果に反映されます。一方、オープンクラスでは製作技術やパーツ加工の精度も重要な要素となり、より多様なアプローチでマシン開発が可能です。
どちらが優れているというわけではなく、それぞれに異なる魅力があります。自分の好みや技術レベル、投入できる時間や予算に応じて選ぶのがよいでしょう。
初心者にB-MAXがおすすめな理由は簡単さと公平性
ミニ四駆を始めたばかりの方にとって、B-MAXレギュレーションは特におすすめできる理由がいくつかあります。その主な理由を詳しく見ていきましょう。
まず第一に、B-MAXは改造が非常に簡単です。基本的に「ポンづけ」、つまりパーツをそのまま取り付けるだけで競技に参加できるため、複雑な加工技術や特殊な工具は必要ありません。シャーシやボディの加工が厳しく制限されているため、考慮すべきは「既存穴を利用してどうグレードアップパーツを付けるか」という点だけです。現代のミニ四駆で一般的な「シャーシのバンパーカットして、FRP・カーボンをこんな感じで加工して…」といった作業が不要なのは、初心者にとって大きなメリットです。
第二に、B-MAXでは様々なセッティングの効果が試しやすいという特徴があります。例えば「ローラー幅を変えてコーナー速度の変化を見てみたい」と思った場合、オープンクラスマシンでは他のギミックが稼働することで純粋にローラー幅の効果を確認しづらい場合があります。一方、B-MAXマシンではギミックが少ないため、ローラー幅の変更に対するマシンの反応を素直に観察することができます。このように、セッティングの因果関係が分かりやすいのも初心者にとって学習しやすい環境と言えるでしょう。
第三の理由として、B-MAXでは速いレーサーにも勝てる可能性が比較的高いという点が挙げられます。これは「最高速度の上限がオープンより低い所にある」ためです。ミニ四駆の速さには「モーターの性能」も大きく影響しますが、B-MAXではあまりに高性能なモーターを使うと「速さに耐え切れずコースアウト」してしまうことが多いです。そのため、モーターの性能差による優位性が抑えられ、より公平な条件で競争できるのです。
さらに、B-MAXではオープンマシンよりも全体的にコースアウト率が高くなる傾向があるため、上級者のマシンが途中でコースアウトする「ワンチャン」が生まれやすいというのも、初心者にとっては励みになるポイントでしょう。
最後に、B-MAX独自の魅力として「マシンの個体差が小さい」ことが挙げられます。加工の制限により、マシン自体の性能差が比較的小さくなるため、レーサーのセッティング技術やレース戦略がより重要になります。初心者でも正しい知識と適切なセッティングがあれば、十分に勝負になるのがB-MAXの大きな魅力です。
これらの理由から、ミニ四駆初心者はまずB-MAXから始めることで、基本的なセッティング技術や走行のコツを効率よく学ぶことができるでしょう。
B-MAXレギュレーションで許可される改造と禁止される改造
B-MAXレギュレーションでは、加工に関して細かく規定されています。何が許可され、何が禁止されているのかを正確に把握することで、レギュレーション違反を避け、安心して大会に参加できます。ここでは主要なパーツごとに、許可される改造と禁止される改造を詳しく解説します。
【ボディ関連】 許可される改造:
- ボディの塗装
- ステッカーの貼付け
- 異なる種類のボディとボディパーツ(ウィング等)の組合せ
- ボディとボディパーツ(ウィング等)の接着
- シャーシ/プレート/マスダンパー/タイヤに干渉する該当部分の切断(干渉部分から3mm以内の加工)
- アニマル搭載のためのキャノピー部品の切り抜き/取り外し
- ボディの肉抜き、およびメッシュの貼付け(ボディの原型が分かる範囲での肉抜きに限る)
禁止される改造:
- ボディの分割
- ポリカーボネート、PET製のボディの使用
- 原型が分からなくなるような過度な肉抜き
- 肉抜きされたボディの破損部分の接着剤等を使った補修
【シャーシ関連】 許可される改造:
- ステッカーの貼付け
- 標準ビス穴の2mm拡張
- 貫通されていない標準ビス穴の貫通加工
- ビス穴の皿ビス加工
禁止される改造:
- 新規ビス穴の追加
- シャーシの肉抜き、および切断
- シャーシの指定方向以外への電池の設置(シャーシの逆転使用)
【マスダンパー関連】 許可される改造:
- マスダンパーへの着色
- 同一のビス上に配置された複数のマスダンパーのマルチテープによる接合
- 可動するマスダンパーの設置(固定されたビスによる上下運動に限定)
- プレート下方への吊り下げ配置
禁止される改造:
- マスダンパーの形状加工
- マスダンパーの穴拡張(長期使用に伴う削れの場合、穴の最大距離が5mm以上)
- ボールリンクマスダンパーのアーム部が車軸を跨ぐ設置
【タイヤ・ホイール関連】 許可される改造:
- ホイールの車軸用穴の貫通
- タイヤとホイールの接着(両面テープ、接着剤等)
- 同一サイズのタイヤとホイールの組合せ
禁止される改造:
- タイヤの加工(長期使用に伴う削れの場合、直径の変化量が1mm以上)
- 異なるサイズのタイヤとホイールの組合せ(例:中径ローハイトホイールに小径タイヤをはめ込むなど)
特筆すべきは、マスダンパー等重量物を用いたスイング系の制振ギミック(提灯、ヒクオ、ノリオ、東北ダンパー、キャッチャーダンパー等)の使用が禁止されている点です。ただし、グレードアップパーツであるボールリンクマスダンパーの使用は可能です。
これらの規定はB-MAX GPの公平性と安全性を確保するために設けられています。規定内でもセッティングの工夫次第で十分に速いマシンを作ることが可能ですので、創意工夫を楽しみながらレギュレーションを守ることが大切です。
B-MAX公式大会の開催情報とレース形式
B-MAX GP(Basic-MAX GP)は、様々な規模の大会が日本各地で開催されています。特に「B-MAX GP全日本選手権」は、B-MAXレギュレーションの頂点を決める大会として注目を集めています。ここでは、B-MAX公式大会の情報とレース形式について詳しく見ていきましょう。
B-MAX GPの大会は主に「予選大会」と「決勝大会」の二段階で構成されています。まず各地のミニ四駆ショップなどで予選大会が開催され、そこで勝ち上がった選手が全日本選手権などの決勝大会に進出する仕組みとなっています。例えば、第2回B-MAX GP全日本選手権は2022年にニコニコ超会議で開催され、全国から予選を勝ち抜いた選手たちが集まりました。
B-MAX GPのレース形式は、一般的に3レーンのサーキットを使用した対戦形式が採用されています。B-MAX GPレギュレーションでは、「ジャパンカップジュニアサーキット(Item No:69506)」、「ジュニアサーキットスロープセクション(Item No:69570)」、「ジャパンカップJr.サーキットバンクアプローチ20(Item No:69571)」を組み合わせた3レーンサーキットでのレースが推奨されています。
レースの進行は、基本的にタミヤのミニ四駆公認競技会規則に準拠していますが、詳細については各レースイベントを運営する店舗・団体によって多少の違いがあります。一般的には予選と決勝に分かれており、予選ではタイムアタックや周回数を競い、上位者が決勝トーナメントに進出する形式が多いようです。
大会参加に際しては、B-MAX GP実行委員会公認競技会規約への同意が必要となります。この規約には、参加資格や大会進行手順、写真撮影や取材の許可などが含まれており、公正な大会運営を目的としています。
特に車体検査(車検)は厳格に行われ、「ミニ四駆チェックボックス(Item No:95280 / Item No:95548)」および「ミニ四駆クリアランスゲージ(Item No:95613)」を用いた検査が推奨されています。車検でレギュレーション違反が見つかった場合は失格となりますので、事前に十分な確認が必要です。
B-MAX GP実行委員会の公式サイトでは、最新の大会情報や予選会の開催ショップ一覧などが随時更新されています。参加を検討している方は定期的にチェックすることをおすすめします。また、各ショップのSNSアカウントなども情報源として有用です。
B-MAX GP大会は、同じレギュレーションで公平に競い合えることから、初心者から上級者まで幅広い層に人気があります。特に初めて大会に参加する方にとっては、B-MAX GPは敷居が低く、貴重な経験を積む機会となるでしょう。
B-MAXミニ四駆の予算は初期費用2万円から始められる
B-MAXミニ四駆を始める際の気になるポイントの一つが、必要な予算です。ここでは、B-MAXマシンを製作・運用するために必要なコストの目安をご紹介します。
基本的に、B-MAXミニ四駆を始めるための初期費用は、およそ2万円程度からと考えておくとよいでしょう。これには、マシン本体の部品代と基本的な工具の費用が含まれます。ただし、工具はレンタルできる施設もありますので、最初から全てを揃える必要はないかもしれません。
まず、マシン製作に必要なパーツの費用の目安を見てみましょう:
| パーツ | 価格目安 |
|---|---|
| 本体キット | 1,000円 |
| 620ベアリング | 1,400円 |
| 中空シャフト | 540円 |
| カーボンホイール | 320円 |
| スーパーハードタイヤ | 300円 |
| 超速カウンターギア | 264円 |
| 中空プロペラシャフト | 140円 |
| オイルペン | 400円 |
| Fグリス | 400円 |
| ハイパーダッシュモーター | 500円 |
| 合計 | 約5,300円 |
次に、基本的な工具類の費用目安です:
| 工具 | 価格目安 |
|---|---|
| ニッパー | 2,000円 |
| パーツクリーナー | 500円 |
| ベアリングオイル | 1,000円 |
| シャフトチェッカー | 2,420円 |
| ホイールドリリング | 3,630円 |
| マイクロハンマー | 1,200円 |
| ホイールプーラー | 2,750円 |
| ギアプーラー | 1,320円 |
| 合計 | 約14,800円 |
これらを合わせると約2万円程度になりますが、実際には予算や目的に応じて調整が可能です。例えば、最初からすべての工具を揃える必要はなく、徐々に追加していくアプローチも取れます。また、ホビーショップによっては工具のレンタルサービスを提供していることもあります。
注意点としては、上記はあくまでシャーシとタイヤ、基本機構を組み立てるまでの費用であり、ローラーなどの走行安定化パーツはまだ含まれていません。実際にレースに参加するためには、追加で数千円~1万円程度の投資が必要になるでしょう。
また、大会に参加する際の参加費(数百円~千円程度が一般的)や、消耗品の交換費用なども考慮する必要があります。タイヤやシャフトなどは使用していくうちに摩耗するため、定期的な交換が必要です。
B-MAXの魅力の一つは、オープンクラスに比べて比較的コストが抑えられる点にあります。パーツの加工が制限されているため、高価な加工ツールや特殊なカスタムパーツへの投資が少なくて済むのです。
初めてB-MAXを始める方は、まずは基本的なキットと最低限の工具から始め、徐々に拡張していくのが賢明でしょう。レースで経験を積みながら、自分に必要なパーツや工具を見極めていくことをおすすめします。
B-MAXミニ四駆のセッティングと優勝するための実践テクニック
- B-MAXマシンの組み立て手順は10ステップで完成する
- 優勝マシンのフロントローラーセッティングはレーンチェンジ対策がカギ
- B-MAXに最適なシャーシはFM-AとVZの2種類が人気
- B-MAXでのモーター選びは開封そのままでも十分戦える
- マスダンパーとタイヤの組み合わせで安定性を最大化する方法
- レーンチェンジを高速で攻略するB-MAXセッティングの秘訣
- まとめ:B-MAXミニ四駆は初心者から上級者まで楽しめる奥深い世界
B-MAXマシンの組み立て手順は10ステップで完成する
B-MAXマシンを組み立てる際、基本的な手順を押さえておくことで、効率よく高品質なマシンを作ることができます。ここでは、シャーシ組み立ての基本となる10のステップを詳しく解説します。
ステップ1:綺麗にパーツを切り離す 模型作りの基本は丁寧なパーツ処理から始まります。ニッパーでパーツをランナーから切り離したら、軽くやすり掛けして切り口を滑らかにします。特にタイヤは重要なパーツですので、ゴムのつなぎ目を少し引っ張ってからニッパーで切ると綺麗に仕上がります。タイヤはミニ四駆の心臓部の一つなので、丁寧な作業を心がけましょう。
ステップ2:ボールベアリングをセットする ボールベアリングは回転部分の摩擦を減らす重要な部品です。開封したままで使用するか、脱脂してからオイルを差すかは好みによります。初心者の場合は、開封したままでも十分に性能を発揮するので、まずはそのまま使用してみることをおすすめします。
ステップ3:シャフトを選別する シャフトは「結構曲がっている」ことが多いため、真っ直ぐなものを選ぶことが重要です。シャフトチェッカーを使用するか、平らな面に転がして確認する方法もあります。72mm中空ステンレスシャフトを3つ程度購入して、その中から良いものを選ぶとよいでしょう。
ステップ4:ホイールに穴を開けてタイヤを取り付ける ホイールは車体の走行性能に大きく影響します。ホイールに真っ直ぐ穴を開けることが重要で、専用のホイールドリリングツールを使うと垂直に穴を開けられます。貫通したらタイヤを取り付けますが、シャフトが勢いよく通って手を傷つけないよう、必ず保護材(メダルなど)を当てながら作業しましょう。
ステップ5:選別したシャフトをホイールに取り付ける タミヤのマイクロハンマーを使い、シャフトをホイールに慎重に取り付けます。シャフトとホイールの穴は六角形になっているため、少し回しながらハンマーで優しく打ち込みます。この時、ベアリング用スペーサーとギアの入れ忘れに注意してください。
ステップ6:タイヤをシャーシに取り付ける ホイールをシャーシに取り付ける際は、「紙1枚分」の余裕を持たせることが理想ですが、これは難しい作業です。ホイールプーラーなどの専用工具を使うと、タイヤが両サイドに少し動く程度の適切な余裕を持たせることができます。この時点でタイヤが綺麗に回転するかチェックしましょう。
ステップ7:プロペラシャフトを取り付ける プロペラシャフトはデフォルトのまま使うとクラウンギアに当たることが多いので、ハンマーでギアを押し込み、その後プーラーでギアを少しずつ引っ張って調整します。設置した状態で前後に少し動くか動かないかくらいの隙間が理想的です。
ステップ8:各ギアをセットしてグリスを塗る ギアが全てセットできたら、タミヤのFグリスやオイルペンを使って摩擦部分に適量のグリスを塗ります。説明書をよく読んで適切な位置に塗り、はみ出た部分はきれいに拭き取りましょう。
ステップ9:ターミナルを取り付ける ターミナルの汚れは電流の流れを妨げるため、清潔に扱うことが重要です。手袋をして取り付けると良いでしょう。ターミナル、モーターなど全ての電気系統部品を丁寧に取り付けます。
ステップ10:空転させて異音やブレがないかチェックする 全ての部品を取り付けたら、マシンを持ち上げて空転させ、異音やブレがないか確認します。問題があれば、該当する部分を調整して修正しましょう。
これらのステップを丁寧に実施することで、B-MAXレギュレーションに沿った基本的なシャーシの組み立てが完了します。次はローラーやプレートなどを追加してマシンを完成させていきます。基本に忠実な組み立てがその後のセッティングの土台となりますので、焦らず慎重に作業することが大切です。
優勝マシンのフロントローラーセッティングはレーンチェンジ対策がカギ
B-MAX大会で優勝するためには、レーンチェンジ(LC)を安定して攻略できるセッティングが不可欠です。特にフロントローラーのセッティングは勝敗を分ける重要な要素となります。実際の優勝マシンから学ぶ効果的なフロントローラーセッティングを詳しく見ていきましょう。
B-MAX GP全日本選手権の優勝経験者の多くが採用しているのが、右側フロントローラーの特殊セッティングです。具体的には「12-13mm二段アルミローラー(WA)をゴムリング付きで逆に取り付ける」というセッティングが非常に効果的だとされています。
このセッティングがなぜ効果的なのかについては、物理的な原理があります。ミニ四駆がレーンチェンジに侵入して左カーブしながら頂点を抜けようとする時、マシンは右側がリフト(浮き上がる)する傾向にあります。このとき、通常より小さなローラーが下段にあると、傾きによりコース壁面に接触して安定します。さらに重要なのは、この配置によって「下へ向かう強い力(ダウンスラスト)」が発生することです。
このメカニズムを理解するには、紙コップを横に倒してコロコロ転がす様子を想像するとわかりやすいでしょう。紙コップは上底が下底より大きい台形状で、横に倒すと下へ円を描くように転がります。これと同じ原理で、逆さにしたWAローラーは強力なダウンスラストを生み出します。さらに下段ローラーにゴムリングが付いていると、このダウンフォース効果がさらに高まります。
実際の優勝マシン(マッハフレームベース)では、こうしたセッティングにより、レーンチェンジの頂点から下降するときのマシンの姿勢が理想的に保たれ、高速かつ安定した走行が可能になっています。このセッティングを採用した選手は、ショップ予選のレーンチェンジをほぼ高速で抜けて優勝することができたと報告しています。
さらに、フロントローラーの配置も重要です。B-MAX GP全日本選手権の優勝マシンでは、フロントの右側に12-13mmの二段ローラー(ゴムリング付きで逆付け)、左側には通常の二段アルミローラーを配置するというアシンメトリー(非対称)なセッティングが採用されています。これは走行中のマシンの傾向を分析した結果、右側へのリフトが多いことに対応した合理的な配置と言えるでしょう。
こうしたフロントローラーのセッティングは、B-MAXレギュレーションの中でも許可される範囲内の工夫であり、パーツの加工を必要としないため初心者でも比較的容易に真似できます。実際のレースでは、コースレイアウトや自分のマシンの傾向に合わせて微調整することが勝利への近道となるでしょう。
フロントローラーセッティングの重要性は、ミニ四駆のセオリーとして広く認識されていますが、B-MAXレギュレーションではその効果がより顕著に表れるため、優先して取り組むべきポイントだと言えます。
B-MAXに最適なシャーシはFM-AとVZの2種類が人気
B-MAXレギュレーションで勝利を目指すなら、シャーシ選びは非常に重要な要素です。現在のB-MAX競技では、FM-A(エフエムエー)シャーシとVZ(ブイゼット)シャーシの2種類が特に人気を集めています。それぞれの特徴と利点を詳しく見ていきましょう。
FM-Aシャーシの特徴と利点
FM-Aシャーシは、B-MAX競技で最も使用率の高いシャーシと言われています。その人気の理由はいくつかあります:
- バランスの良さ: 重量配分が良く、初心者でも扱いやすい安定した走行特性を持っています。
- モーター位置: モーターが中央に配置されているため、荷重バランスが取りやすいという利点があります。
- カスタマイズの自由度: B-MAXレギュレーション内でも様々なセッティングが可能で、ローラー配置などの調整の自由度が高いです。
- パーツの入手性: 人気シャーシであるため、関連パーツが豊富で入手しやすい点も魅力です。
FM-Aシャーシの注意点としては、プロペラシャフトの問題があります。デフォルトのプロペラシャフトではギアとの干渉が起きやすいため、中空プロペラシャフトへの交換が推奨されています。これはB-MAXでも許可される改造です。
VZシャーシの特徴と利点
VZシャーシも多くのB-MAXレーサーに支持されています:
- 低重心設計: 電池が下部に配置されているため、低重心で安定性に優れています。
- コーナリング性能: 特にコーナーでの安定性が高く、テクニカルなコースで力を発揮します。
- 剛性の高さ: シャーシ自体の剛性が高く、高速走行時の変形が少ないという利点があります。
- レーンチェンジ攻略力: 適切なセッティングを施すと、難所のレーンチェンジも安定して攻略できます。
VZシャーシの課題点としては、初期セッティングが少し難しいことや、重量がやや重くなりがちな点が挙げられます。また、リジッドセッティング(フレキ無し)での調整が主流となります。
シャーシ選びのポイント
B-MAXレギュレーションでは、どちらのシャーシも十分な競争力を持っていますが、自分のレーシングスタイルや好みに合わせて選ぶことが重要です:
- 初心者には比較的セッティングが容易なFM-Aがおすすめ
- テクニカルなコースが多い大会ではVZの安定性が活きる
- 軽量化を重視するならFM-Aが有利な場合が多い
- パワー重視のセッティングではVZの剛性の高さが活きる
実際の優勝マシンのデータを見ると、第2回B-MAX GP全日本選手権の優勝マシンはFM-Aシャーシをベースにしたマッハフレームで、フロントとリアのローラー配置を非対称にした特徴的なセッティングが施されています。一方、店舗大会などではVZシャーシをベースにしたセッティングでの優勝例も数多く報告されています。
重要なのは、シャーシ選びに正解はなく、自分のドライビングスタイルや参加する大会のコース特性に合わせて選ぶことです。また、一度選んだシャーシでじっくりと調整を重ねることで、そのシャーシの特性を最大限に引き出せるようになります。
B-MAXレギュレーションの魅力は、シャーシの選択肢が限られている中でも、様々なセッティングの工夫によって個性を出せる点にあります。自分だけの最適なセッティングを見つける過程も、ミニ四駆の楽しみの一つと言えるでしょう。
B-MAXでのモーター選びは開封そのままでも十分戦える
B-MAX競技における興味深い特徴の一つに、モーター選びが挙げられます。一般的なミニ四駆競技では、モーターの性能差が勝敗を大きく左右することが多いですが、B-MAXでは「開封そのまま(開けポン)」のモーターでも十分に戦えるケースが少なくありません。ここでは、B-MAXにおけるモーター選びのポイントを詳しく解説します。
B-MAXでは高性能モーターが必ずしも有利ではない理由
B-MAXレギュレーションでは、マシンの最高速度よりも安定性とコントロール性が重視されます。その理由としては以下の点が挙げられます:
- コースアウトのリスク: あまりに高出力のモーターを使用すると、B-MAXマシンでは「速さに耐え切れずコースアウト」してしまうケースが多いです。
- 重量とのバランス: B-MAXマシンは一般的に重量が電池抜きで140gを超えることが多く、この重量に対して適切な出力のモーターを選ぶことが重要です。
- レーンチェンジなどの難所: 高速すぎると難所を攻略できないことがあり、適切な速度でコースを完走することが優先されます。
実際、B-MAX GP全日本選手権の予選大会で優勝したマシンのモーターは「開けポン」(開封そのまま)のハイパーダッシュモーター3(HD3)だったという報告もあります。これは極めて興味深い事例で、モーターの厳選よりもマシン全体のバランスとセッティングの方が重要だということを示しています。
B-MAXに適したモーターの選択基準
B-MAXレギュレーションで使用できるモーターはタミヤ製のものに限られますが、その中でもいくつかの選択肢があります:
- ハイパーダッシュモーター系: HD3やHD2などが人気で、バランスの良い出力特性を持ちます。開封そのままでも十分な性能を発揮することが多いです。
- トルクチューン系: 加速性能に優れており、特にコーナーの多いコースで力を発揮します。
- レブチューン系: 最高速度を重視したモーターで、直線の多いコースで有利になります。
モーター選びの際には、参加する大会のコース特性を考慮することが重要です。例えば、レーンチェンジやコーナーが多いテクニカルなコースではトルクチューン系が有利かもしれませんし、長い直線のあるコースではレブチューン系が力を発揮するかもしれません。
モーターの速度計測とセッティング
モーターの性能を把握するために、電圧2.8V程度での速度計測を行うことは有益です。例えば、独自調査によると、HD3モーターを使用したB-MAXマシンは電圧2.8Vの状態で約43km/hを記録しています。これは40km/h以上出るため、B-MAX競技では「まずまず」の速度とされています。
しかし、重要なのは「ミニ四駆は最高速より生き残り」という点です。フラットな速度勝負でない限り、ミニ四駆はコースを完走する安定性の方が最高速度よりも重要です。特にジャンプギミックなどのあるコースでは、制御できないスピードはかえって不利になります。
B-MAX競技の上級者は、専用のガジェットを用いて電池の電圧を調整し、コースに応じた最適な速度でマシンを走らせています。しかし、こうした専用ガジェットがなくても、モーターの基本性能と適切なギア比選択によって十分に競争力のあるマシンを作ることができます。
ギア比については、一般的にB-MAXでは3.5~3.7:1の比率が使われることが多いようです。これはコースの特性や使用するモーターの特性によって調整するべきポイントです。
B-MAXの魅力は、モーターの性能差による優劣が比較的小さく、むしろセッティングの工夫やレース戦略の方が勝敗を左右する点にあります。初心者でも「開けポン」のモーターで十分に楽しめるのがB-MAXレギュレーションの大きな特徴と言えるでしょう。
マスダンパーとタイヤの組み合わせで安定性を最大化する方法
B-MAXレギュレーションでは、マシンの安定性を高めるためのマスダンパーとタイヤの選択・配置が非常に重要です。適切なセッティングによって、コーナリングやレーンチェンジの安定性を大幅に向上させることができます。ここでは、優勝経験者のセッティングを参考に、効果的なマスダンパーとタイヤの組み合わせ方を詳しく解説します。
マスダンパーの効果的な配置
B-MAX GP全日本選手権で活躍したマシンでは、接地型マスダンパーを「リヤ<フロント<中心」の重さの配分で設置する方法が採用されています。この配置の利点は以下の通りです:
- 中央部に最も重いマスダンパー: シャーシの中心に重量を集中させることで、マシンの安定性が向上します。特にレーンチェンジなどでの姿勢の崩れを抑制する効果があります。
- フロント部に中程度の重さ: フロント部のマスダンパーは、コーナー進入時の安定性を高めます。適切な重さのマスダンパーを配置することで、フロントローラーの接地性が向上し、コーナーでのグリップ力が増します。
- リヤ部に軽めのマスダンパー: リヤ部には比較的軽いマスダンパーを配置することで、リヤ部の浮き上がりを抑制しつつ、過度な重量増加を避けることができます。
実際の優勝マシンでは、当初「リヤ=フロント<中心」という重量配分だったものを、「リヤ<フロント<中心」に変更したところ、安定性が向上したという報告があります。この微妙な調整がマシンの挙動に大きな影響を与えることが分かります。
タイヤ選択のポイント
B-MAXでのタイヤ選択も重要なファクターです:
- フロントタイヤ: スーパーハードタイヤが選ばれることが多く、これはグリップ力と耐久性のバランスが良いためです。コーナーでの安定した走行をサポートします。
- リヤタイヤ: ローフリクションローハイトタイヤが人気で、これはジャンプを低くするための工夫です。空気抵抗を減らし、安定した着地を実現します。
優勝経験者のマシンでは、リヤだけローフリクションローハイトタイヤを採用し、フロントはスーパーハードタイヤという組み合わせが採用されています。この非対称なセッティングにより、前後のグリップ特性を最適化しています。
マスダンパーとタイヤのセッティング例
実際の優勝マシンのセッティング例を見てみましょう:
| 部位 | マスダンパー | タイヤ |
|---|---|---|
| フロント | 中程度の重さ | スーパーハードタイヤ |
| 中央 | 最も重い | – |
| リヤ | 軽めの重さ | ローフリクションローハイトタイヤ |
このセッティングにより、マシンの重心が適切に配置され、コーナーでの安定性とレーンチェンジでの挙動が最適化されています。
B-MAXレギュレーションでの注意点
B-MAXレギュレーションでは、マスダンパー等の重量物を用いたスイング系の制振ギミック(提灯、ヒクオ、ノリオ、東北ダンパー、キャッチャーダンパー、ギロチンダンパー等)の使用が禁止されています。ただし、グレードアップパーツであるボールリンクマスダンパーの使用は可能です。
また、マスダンパーの設置に関しては、以下の点が許可されています:
- マスダンパーへの着色
- 同一のビス上に配置された複数のマスダンパーのマルチテープによる接合
- 可動するマスダンパーの設置(固定されたビスによる上下運動に限定)
- プレート下方への吊り下げ配置
これらの規定内で、創意工夫を凝らしたマスダンパーとタイヤのセッティングを行うことが、B-MAX競技で勝利するための重要なポイントとなります。
重要なのは、自分のマシンの走行傾向をよく観察し、その特性に合わせたマスダンパーとタイヤの組み合わせを見つけることです。一度に大きく変更するのではなく、少しずつ調整しながら最適な組み合わせを探っていくアプローチが効果的でしょう。
レーンチェンジを高速で攻略するB-MAXセッティングの秘訣
B-MAX競技での勝敗を大きく分けるのが、レーンチェンジ(LC)の攻略です。特に3レーンコースでは、LCでのコースアウトが敗因となるケースが非常に多くあります。ここでは、LCを高速かつ安定して攻略するための具体的なセッティング方法を、実際の優勝経験者のノウハウを基に詳しく解説します。
LC攻略の重要ポイント1:右フロントローラーのセッティング
LC攻略で最も重要なのが、右フロントローラーのセッティングです。先ほど触れた「12-13mm二段アルミローラー(WA)をゴムリング付きで逆に取り付ける」セッティングは、特にLCに効果を発揮します。
このセッティングが効果を発揮するメカニズムを詳しく見てみましょう:
- ミニ四駆がLCに侵入して左カーブしながら頂点を目指す際、マシンは右側が浮き上がる(リフトする)傾向があります。
- このとき、下段に小さいローラーが来るように逆さに取り付けたWAローラーが、傾いたマシンを支える役割を果たします。
- さらに重要なのは、この配置によって強力なダウンスラスト(下向きの力)が発生することです。これにより、マシンは理想的な姿勢でLCを通過できます。
- 下段ローラーにゴムリングを装着すると、このダウンフォース効果がさらに強化されます。
実際の大会での実績として、このセッティングを採用した選手がショップ予選のLCをほぼ高速で攻略して優勝したという報告があります。
LC攻略の重要ポイント2:左リアローラーの直下にスタビを配置
LC攻略のもう一つの重要なポイントは、左上リアローラーの直下にスタビライザー(スタビ)を配置することです。これはLCから下り始めた時の対策として効果的です:
- LC頂点を通過したマシンは、左カーブから右カーブに移る際に、浮いたまま右壁面から左壁面へ激突します。
- このとき、スラスト角が効いて車体前が下へ向くと、リア左上ローラーはコース壁面を飛び越えてしまう可能性があります。
- スタビが無いと、ローラーを支える支柱にコース壁が激突し、てこの原理でさらに右側がリフトして、最終的に反時計回りに車体が回転してコースアウトする危険性があります。
- 左上ローラーの直下にスタビを配置することで、壁面がローラー支柱に当たる前にスタビに接触して跳ね返り、コースへの復帰率が飛躍的に高まります。
13mmローラーを使用している場合は、リヤブレーキセットのブレーキピースをビスに刺して代用することも可能です。
リアローラーの選択とセッティング
LC攻略の補助的な要素として、リアローラーの選択とセッティングも重要です:
- 左側に厚いローラー: 優勝マシンのセッティングでは、リヤの左側だけ厚い13mmプラスチックリングを装着したローラーを使用しています。これはLCの抜け際に左側が乗り上げる確率が高いため、これを防ぐための工夫です。
- 19mmローラーへの変更: 対振動対策として、リアローラーを13mmから19mmへ変更することも効果的です。ローラーが大きいほどコースのつなぎ目や段差に強くなるため、特に他のマシンと並走する際の振動対策として有効です。
並走時の振動対策
B-MAX GPの決勝トーナメントでは、複数台のマシンが同時に走行する並走レースが行われます。このとき、コースの微細なたわみによる振動が発生し、マシンの挙動に影響を与えることがあります。
特に「テーブルトップから降りる時のジャンプで車体が僅かにブレて着地前にコース壁面にフロントアンダーのプレートが接触する」などのトラブルが報告されています。こうした問題に対応するためにも、前述のローラーセッティングが効果を発揮します。
LC攻略セッティングのまとめ
B-MAXでLCを高速攻略するためのセッティングのポイントをまとめると:
- 右フロントローラーは12-13mm二段アルミローラーを逆さ付け、下段にゴムリングを装着
- 左上リアローラーの直下にスタビを配置
- リア左側に厚めのローラーを配置
- 必要に応じてリアローラーを大径(19mm)に変更して対振動性能を向上
これらのセッティングを組み合わせることで、B-MAX大会の難所となるLCを安定して攻略し、勝率を大幅に向上させることができるでしょう。重要なのは、これらのセッティングがB-MAXレギュレーションの範囲内で実現できる点です。パーツの加工を伴わず、タミヤ純正パーツの組み合わせだけで効果的なLC対策が可能なのがB-MAXの魅力と言えるでしょう。
まとめ:B-MAXミニ四駆は初心者から上級者まで楽しめる奥深い世界
最後に記事のポイントをまとめます。
- B-MAXレギュレーションは「ポンづけ」と「無加工」を基本とし、公平な競争を重視している
- B-MAXはオープンクラスに比べて加工が制限されているため、初心者にも取り組みやすい
- 初心者に特におすすめな理由は改造の簡単さ、セッティングの試しやすさ、勝機の多さの3点
- B-MAXでは細かく規定された許可改造と禁止改造を理解することが重要
- 全日本選手権などの公式大会は定期的に開催され、予選大会から始めることができる
- 初期費用は本体パーツ約5,300円と工具類約14,800円で、合計約2万円からスタート可能
- マシン組み立ては10ステップで完成し、パーツの丁寧な処理が性能を左右する
- 優勝マシンのフロントローラーセッティングは、右側に逆さWAローラーを配置するのがカギ
- B-MAXに最適なシャーシはFM-AとVZの2種類で、それぞれに異なる特徴と長所がある
- モーター選びは開封そのままでも十分戦え、HD3などのバランス型が人気
- マスダンパーは「リヤ<フロント<中心」の重さ配分が効果的で安定性を高める
- レーンチェンジ攻略には右フロントローラーの配置と左リアローラー直下のスタビが決め手
- B-MAXはセッティングの工夫で大きく性能が変わるため、継続的な改善が楽しめる奥深いカテゴリー