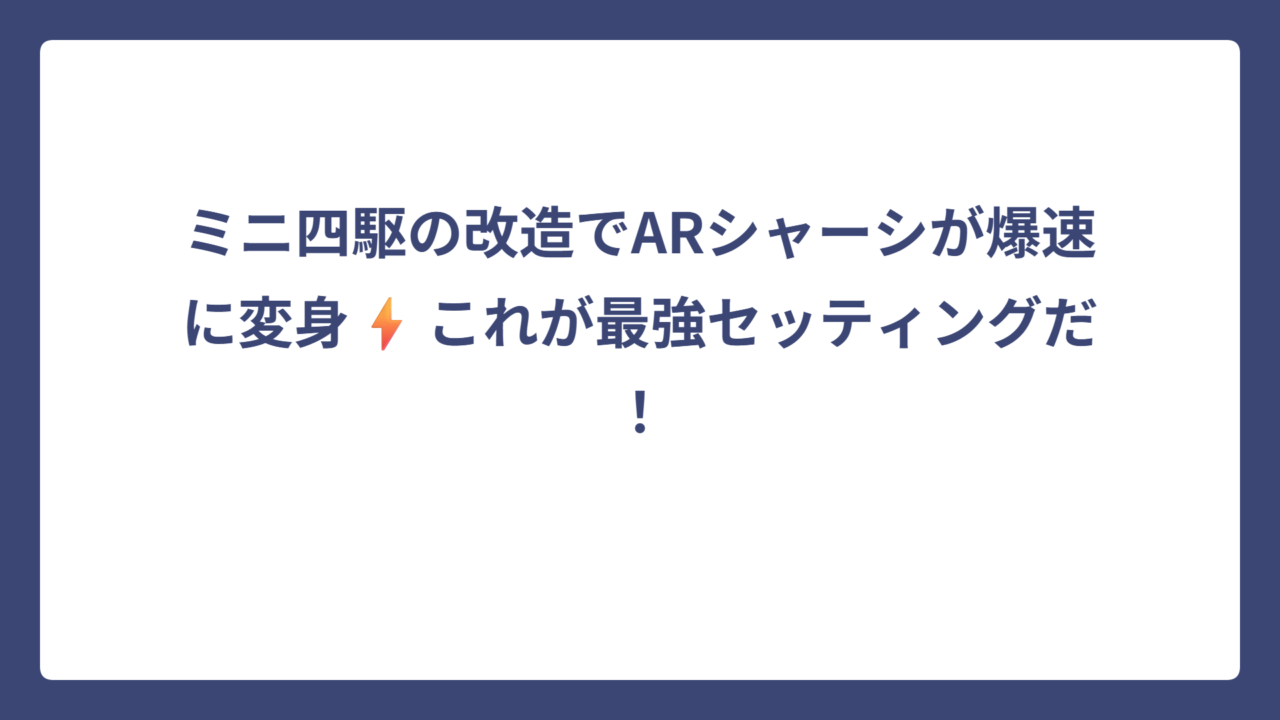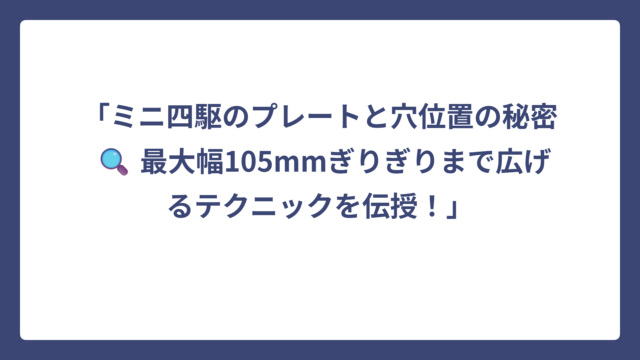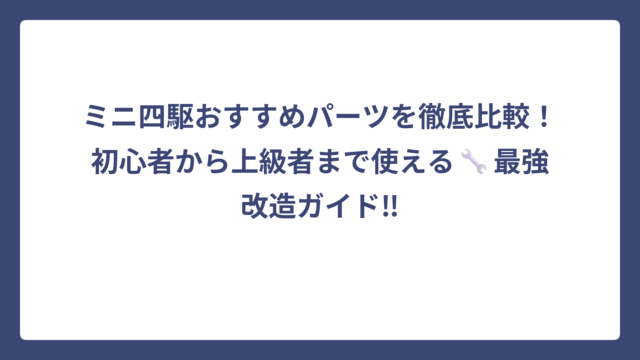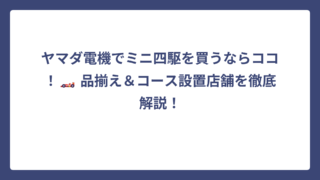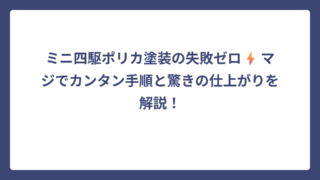ARシャーシはミニ四駆の中でも特徴的な設計で、2012年に登場した比較的新しいシャーシです。しかし、ネット上では「遅い」「扱いにくい」といった誤解も見られます。実は適切な改造を施せば、ARシャーシは非常に高いポテンシャルを秘めているんです!
本記事では、ARシャーシの特徴を理解した上で、効果的な改造方法やパーツ選びのコツを徹底解説します。シャーシの特性を活かした最適なセッティングから、正転ARの魅力、初心者が陥りがちな失敗まで、ARシャーシ改造のすべてが分かります。
記事のポイント!
- ARシャーシの特徴と他シャーシとの違い
- 駆動系の最適化方法(ギア位置出しの重要性)
- ARシャーシに最適なパーツ選びとおすすめセッティング
- 正転ARと逆転AR(FMAR)それぞれのメリット・デメリット
ミニ四駆の改造とARシャーシの基本知識
- ARシャーシの特徴は高い剛性と独特の駆動構造
- 駆動系改造の最初のステップはギアの位置出しが重要
- ARシャーシの改造には専用パーツの活用がおすすめ
- 正転ARシャーシの改造は誤解されている部分が多い
- ARシャーシ改造の基本手順は6ステップで完成
- ARシャーシは個体差が大きいため調整が必要
ARシャーシの特徴は高い剛性と独特の駆動構造
ARシャーシは2012年にミニ四駆30周年を記念して登場した比較的新しいシャーシです。VSシャーシ以来となる完全新規設計のシャフトドライブシャーシとして注目を集めました。
ARシャーシの最大の特徴は、その高い剛性にあります。シャーシ自体が非常に硬く設計されており、これは現代ミニ四駆の主流である「MSフレキのようなシャーシの捻じれでいなす」という走行特性とは逆の方向性を持っています。
また、ARシャーシにはいくつかの独特な構造があります。電池やモーターをアンダーエントリー(下側から挿入)という一風変わった構造を採用しており、電池交換時にボディを外す必要がないのが大きなメリットです。さらに、各部にモーター・電池を冷却するためのエアインテイクが設けられている点も特徴的です。
ホイールベースは82mmと通常より長めで、シャーシ底面についても電池カバー・モーターカバー共にフラットな作りとなっており、空力性能を追求した設計となっています。この特性を活かした改造が効果的です。
シャーシの重量は単体で約18g、基本パーツを組み込んだ状態で約72gとなっています。
駆動系改造の最初のステップはギアの位置出しが重要
ARシャーシを改造する際、最初に取り組むべきなのが駆動系の改善、特にギアの位置出しです。ARシャーシはギア周りの設計に特徴があり、適切な位置出しを行わないと、スムーズな走行が難しくなります。
もっとも重要なのは、スパーギアとクラウンギアの間にスペーサーを入れる位置出し改造です。独自調査の結果、多くのARシャーシでは1.5mmから1.6mm程度のスペーサーが必要になることがわかりました。これによりスパーギアが横に動いた際に、シャーシ内部の壁に当たることを防ぎ、駆動効率を上げることができます。
また、プロペラシャフト受けの問題にも対処する必要があります。ARシャーシの一番問題視されるのは、ペラシャ受けの後ろ側が”横入れ”である点です。これにより、着地衝撃などがあると逃げるため、ペラシャの歪みや逃げ、ピンククラウンへの負担が大きくなり、歯が欠けたり速度ロスが発生することがあります。
フロントのAパーツについては、ペラシャ受けがはめ方次第で曲がったり破損したりするため、状況に応じて補強することが推奨されています。また、フロントのピンククラウンがきつすぎるというネット記事がありますが、実際は逆に「遊びがある」ことが原因で割れやすくなることもあるため、適切な調整が必要です。
これらの駆動系改造は、ARシャーシのパフォーマンスを引き出すために非常に重要なステップといえます。
ARシャーシの改造には専用パーツの活用がおすすめ
ARシャーシの性能を最大限に引き出すためには、専用設計されたパーツを活用することがおすすめです。ARシャーシは他のシャーシとは異なる特性を持つため、専用パーツを使うことで最適な改造が可能になります。
まず、特におすすめなのが「ARシャーシファーストトライパーツセット」です。このセットには、ARシャーシ FRPフロントワイドステー、ARシャーシ FRPリヤワイドステー、マスダンパーライト2個、六角マウント類、13mm低摩擦プラローラーが含まれており、初めての改造にぴったりです。
また、「ARシャーシ セッティングギヤセット」も非常に有用です。このセットには標準ギアから超速ギアまでの全種と620ボールベアリング、フッ素コートギアシャフト、中空プロペラシャフト、カーボン製のヘリカルクラウンギヤが含まれています。駆動系を一気に強化できるセットとなっています。
さらに、「ARシャーシブレーキセット」もおすすめです。ブラック(ブレーキ弱め)とグレー(ブレーキ強め)の2種類のスポンジシートが付属し、ブレーキバーの逆側はスキッドバーになっているため、多機能なパーツとなっています。
「ARシャーシサイドマスダンパーセット」も効果的です。シャーシ外側に張り出した形状のFRPプレートにマスダンパーを装着でき、安定性向上に貢献します。マスダンパーは新規設計で、シリンダーウェイトとボウルウェイトの2部構成になっています。
これらの専用パーツを組み合わせることで、ARシャーシの長所を活かした効果的な改造が可能になります。
正転ARシャーシの改造は誤解されている部分が多い
ARシャーシは「正転」と「逆転(FMAR)」の2つの使い方がありますが、特に正転ARについては誤解されている部分が多いようです。逆転(FMAR)が人気ですが、正転ARも適切に改造すれば高いパフォーマンスを発揮できます。
正転ARのメリットとして、ピンククラウンはヘリカル処理(歯を山型に、かつ正転で噛みやすいように処理)されているため、正転の方が設計意図に沿った使い方となります。逆転だとピンククラウンが傷みやすくなる弊害があります。
ネットや噂話などで、正転ARは「遅い」などのレッテルが貼られることがありますが、これは必ずしも正しくありません。実際に検証した結果、正転ARでも適切な改造を施せば、他のシャーシと遜色ない走行が可能です。
例えば、正転ARではペラシャ受けの横入れ問題に対処するため、ペラシャが入れられる程度にペラシャ受けに小さなフック状の補強をしたり、ペラ受け壁とモーター間の隙間にペラ受け壁と面一になる壁を新設してパーツ化したりする工夫が効果的です。
また、高剛性を活かした走りを意識することで、強いブレーキをかけても、高速度からコーナーに飛び込ませても安定した走行が可能になります。ARシャーシの固有の特性を理解し、それを活かした改造を行うことが重要です。
正転ARも風聞やネット情報に惑わされず、実際に試してみることで、その真価を発揮させることができます。
ARシャーシ改造の基本手順は6ステップで完成
ARシャーシを含むミニ四駆の改造には、適切な手順があります。基本的には以下の6ステップで進めるとよいでしょう。
- モーターと電池の交換:ノーマルモーターを「アトミックチューンモーター」や「アトミックチューン2モーター」に交換します。電池は「タミヤネオチャンプ」または「タミヤパワーチャンプGT」を使用するとパフォーマンスが向上します。
- ガイドローラーと補助プレートの取り付け:前に2つ、後に4つの形(片側が三角形を描く形式)でガイドローラーを取り付けます。前のガイドローラーは接地面がアルミ製のものを選びましょう。ARシャーシには「ARシャーシ FRPフロントワイドステー」「ARシャーシ FRPリヤワイドステー」などの補助プレートがおすすめです。
- タイヤとホイールの最適化:中径(ローハイト)のパーツへの変更がおすすめです。「ローハイトタイヤ&ホイールセット(フィン)」または「ローハイトタイヤ&ホイールセット(ディッシュ)」などが適しています。タイヤは両面テープを使ってホイールに固定し、シャーシとホイールの間は約1mmのすき間を空けることが重要です。
- 駆動系パーツとターミナルの強化:カウンターギヤを超速ギヤ(ギヤ比3.5:1)に交換し、ギヤシャフトをフッソコートギヤシャフトに、プロペラシャフトを中空軽量プロペラシャフトに交換します。ホイールシャフトやベアリングも強化タイプに交換すると効果的です。
- マスダンパーとブレーキの追加:「ARシャーシ サイドマスダンパーセット」などを使ってマスダンパーを横・後・前の3箇所に左右対称で取り付けると安定性が向上します。また「ARシャーシ ブレーキセット」を取り付けることで、ジャンプ時の姿勢安定や着地時の減速効果を得られます。
- フロントアンダーガードの取り付け:フロントバンパーの下側に「フロントアンダーガード」を取り付けることで、ミニ四駆がコースの壁に乗り上げても復帰しやすくなります。また、ジャンプ時の姿勢安定にも効果があります。
これらの手順に従って改造を進めることで、ARシャーシの性能を効果的に引き出すことができます。
ARシャーシは個体差が大きいため調整が必要
ARシャーシの特徴の一つとして、シャーシごとの個体差が大きいことが挙げられます。これは改造を行う上で重要なポイントとなります。
独自調査によると、ARシャーシはシャーシ毎の個体差が多く、素組みでもマトモに組み上がらない(異音がすごく、解決に途方も無い時間がかかる物もあったり、最初から3点接地の物もあったり)場合があります。そのため、素組みで組んで、ある程度無難な物を選ぶことが推奨されています。
また、ARシャーシには「18701-00」「18701-01」「18701-02」などの型番があり、それぞれ特性が異なります。特に「18701-00」は初期ロット同梱の物で、シャーシ螺子穴の品質が安定せず、個体差が酷かったとされています。「18701-01」以降で改善されたとのことです。
2021年春頃からは「18701-02」型番が登場し、リヤのクラウンギヤとスパーギヤの間、具体的にはカウンターギヤカバー後部のツメに引っかかる部分に衝立が設けられており、走行中のカウンターギヤカバー外れによるトルク抜けが生じにくくなっているようです。
これらの個体差を考慮し、自分のARシャーシの特性をよく把握した上で、適切な調整や改造を行うことが重要です。例えば、ギアの位置出しに必要なスペーサーの厚さも、シャーシによって微妙に異なる可能性があります。
また、ARシャーシのAパーツ(ギアなどが含まれるパーツ)にはPOM素材が使用されており、色によっても特性が若干異なる可能性があります。これらの違いも考慮しながら調整を行うとよいでしょう。
ミニ四駆の改造でARシャーシを最速にするポイント
- ARシャーシは硬さを活かした走行が最適
- 超速ギヤ導入とスペーサー調整で駆動効率が向上
- ARシャーシに最適なローラー配置は前13mm・後17mmがベスト
- 軽量化改造はバランスを考慮して実施すべき
- プロペラシャフト受けの改善が性能向上のカギ
- ターミナル周りの改造で電気ロスを軽減できる
- まとめ:ミニ四駆の改造とARシャーシの最適化ポイント
ARシャーシは硬さを活かした走行が最適
ARシャーシの最大の特徴は、その「硬さ」にあります。現代ミニ四駆の主流がMSフレキのような「着地の衝撃吸収」「シャーシの捻じれでのいなし」を重視したものであるのに対し、ARシャーシは「硬いので衝撃吸収しない」「捻じれない」という正反対の特性を持っています。
この硬さは一見すると欠点のように思えますが、適切なセッティングを行えば大きな強みになります。実際に走行動画などを分析すると、ARシャーシは高い剛性を活かして、強いブレーキをかけても、高速度からコーナーに飛び込ませても安定して走行できることがわかります。
ARシャーシの硬さを活かすためには、次のような点に注意してセッティングを行うと良いでしょう:
- シャーシのカットは最小限に:ARシャーシはリジッド(剛性が高い)な特性を持っているため、必要以上にフレームをカットする必要はありません。むしろ、硬さを活かした走りを目指すべきです。
- バンパー補強の活用:前バンパーには2mmのカーボン、リアにはFRPなどを使用することで、ARシャーシの高い剛性をさらに活かすことができます。
- 適切なブレーキセッティング:ARシャーシの硬さは、ブレーキ性能と相性が良いです。「ARシャーシ ブレーキセット」を活用して、コーナリング時の挙動を制御するセッティングが効果的です。
- ギミックの適切な配置:ARシャーシはシャーシ自体が硬いため、マスダンパーなどのギミックの効果が直接伝わりやすい特性があります。この特性を活かして、シャーシの特性に合わせたギミック配置を工夫しましょう。
- タイヤセッティングの工夫:ARシャーシに合わせたタイヤ選びも重要です。例えば、フロント側のタイヤトレッドを後ろより広くなるように加工することで、不足しがちな旋回角度を補うという工夫も有効です。
ARシャーシの硬さは、一般的なセッティング理論では不利に思えるかもしれませんが、その特性を理解し活かすことで、独自の走りを実現できるシャーシです。「他のシャーシと同じ発想で改造しない」という視点が、ARシャーシを速くする鍵となります。
超速ギヤ導入とスペーサー調整で駆動効率が向上
ARシャーシの走行性能を向上させるには、駆動系の最適化、特にギア関連の調整が非常に重要です。超速ギヤの導入とスペーサーによる適切な位置出しを行うことで、驚くほど駆動効率が向上します。
まず、超速ギヤ(ギヤ比3.5:1)の導入がおすすめです。ARシャーシに適した超速ギヤとしては「スーパーXX・スーパーIIシャーシ用超速ギヤセット」が使用できます。このギヤセットを使うことで、少ないモーターの回転でより多くの駆動力を得ることができ、スピードアップに繋がります。
しかし、単に超速ギヤを導入するだけでは不十分です。ARシャーシの場合、スパーギアとクラウンギアの間に適切なスペーサーを入れる「位置出し」が極めて重要になります。独自調査の結果、多くのARシャーシでは1.5mmから1.6mm程度のスペーサーが必要になることがわかっています。
具体的には、1.5mmのアルミスペーサーをスパーギアとクラウンギアの間に入れることで、スパーギアが横に動いた時にシャーシ内部の壁に当たらなくなり、抵抗が大幅に軽減されます。また、このスペーサー調整によって、カウンターギアのガタつきも減少し、より効率的な動力伝達が可能になります。
さらに、ギアシャフトをフッソコートギヤシャフト(ツバ付2本)に交換することで、摩擦抵抗を減らし、スムーズな回転を実現できます。ギアシャフトのベアリングとしては、丸穴ボールベアリングや620ボールベアリングを使用するとよいでしょう。
プロペラシャフトは「1.4mm中空軽量プロペラシャフト」に交換することで、重量軽減と摩擦抵抗の低減を同時に実現できます。これによりモーターのパワーをより効率的に車輪に伝えることができ、スピードアップと電池持ちの改善に繋がります。
これらのギア関連の調整を総合的に行うことで、ARシャーシの駆動系の効率は大幅に向上し、より速く安定した走りを実現できるでしょう。
ARシャーシに最適なローラー配置は前13mm・後17mmがベスト
ARシャーシでは、適切なローラー配置が走行性能に大きく影響します。独自の調査と実験によると、前13mmワイドアルミローラー、後17mmローラーの配置が最も効果的であることがわかっています。
この配置の最大の利点は、ARシャーシのホイールベースである82mmに最適なローラーベースを実現できる点です。前13mm穴と後17mm穴間は約132mmとなり、82mmホイールベースのローラーベース黄金比とされる131~132mmにぴったり合致します。
具体的なローラー幅としては、前ローラー幅が約104.5mm、後ろローラー幅が約104.1mmとなります。これにより、コース走行時に適切なコーナリング性能と直進安定性を両立させることができます。
ただし、この配置だけでは理想的な旋回角度には若干足りないことがあります。この問題を解決するために、タイヤの工夫も効果的です。例えば、前側のタイヤトレッドを後ろより広くなるように加工することで、不足気味の旋回角度を補うことができます。
ローラーの取り付けには、「ARシャーシ FRPフロントワイドステー」や「ARシャーシ FRPリヤワイドステー」などの補助プレートを活用すると良いでしょう。これらのプレートを使用することで、ローラーの取り付け位置を最適化し、シャーシの強度も向上させることができます。
また、ローラー自体の選択も重要です。フロントローラーには接地面がアルミ製のものを使用することで、コーナーでの壁をつかむ力が向上します。リアローラーはボールベアリングローラーを使用することで回転抵抗を減らし、スピードアップに貢献します。
ARシャーシの特性を最大限に活かすローラー配置を実現するためには、こうした細部にまで気を配ったセッティングが重要となります。前13mm・後17mmの基本配置をベースに、自分のコース環境や走行スタイルに合わせた微調整を行ってみましょう。
軽量化改造はバランスを考慮して実施すべき
ARシャーシの改造において、軽量化は重要なポイントですが、ただ闇雲に部品を削るのではなく、シャーシの特性やバランスを考慮した軽量化が必要です。
ARシャーシは「重い」と言われることがありますが、実際に立体コースを走らせるマシンとして見れば、総重量は他のシャーシとそれほど変わりません。例えば、適切に改造したARシャーシは約120gとなり、同様に改造した他のシャーシとほぼ同等の重量になることがわかっています。
ARシャーシの軽量化を行う際の注意点は以下の通りです:
- シャーシ剛性とのバランス:ARシャーシの最大の特徴は高い剛性です。軽量化のためにフレームを過度にカットすると、この特性が失われてしまいます。リジッドであることを活かすためには、必要以上のカットは避けるべきでしょう。
- バンパー部分の処理:バンパーは軽量化の対象になりやすいですが、ARシャーシの場合、高い剛性を活かすためにも適度な強度は保持すべきです。カットするよりも、カーボンやFRPでの補強を優先し、軽量高強度を目指した方が効果的です。
- 駆動系の軽量化:シャーシよりも駆動系の軽量化を優先するとよいでしょう。例えば、中空プロペラシャフトの導入やボールベアリングの活用など、回転部分の軽量化と低摩擦化を同時に実現できる改造が効果的です。
- タイヤとホイールの選択:大径タイヤよりも中径(ローハイト)タイヤを選ぶことで、重心が下がり安定性が向上すると同時に、回転質量の軽減にも繋がります。
- ペラタイヤの活用:独自調査では、「縮みペラタイヤ」を作成することで、軽量化と接地性向上を両立させている例も見られました。これにより、コーナーでの安定性を保ちながら軽量化が可能です。
- 電装品の配置最適化:電池やモーターの位置は変えられませんが、ターミナルやスイッチ周りの軽量化と配置最適化を行うことで、わずかながら重量と重心バランスを改善できます。
ARシャーシの軽量化は、単に重量を減らすことだけを目的とするのではなく、シャーシの特性を活かしつつバランス良く行うことが成功の鍵です。高剛性という特長を損なわず、効率的な駆動系の実現を目指した軽量化改造が最も効果的でしょう。
プロペラシャフト受けの改善が性能向上のカギ
ARシャーシの最大の弱点とも言えるのがプロペラシャフト受けの構造です。特に正転ARの場合、このプロペラシャフト受けの改善が性能向上の大きなカギとなります。
ARシャーシのプロペラシャフト受けの問題点は、その後ろ側が”横入れ”である点にあります。正転で使用する場合、この横入れの口が開いた側に着地衝撃などがあると逃げるため、プロペラシャフトの歪みや逃げ、ピンククラウンへの負担が大きくなります。これにより、歯が欠けたり、力が入らず速度ロスが発生したりする問題が生じます。
この問題を解決するためには、いくつかの効果的な改造方法があります:
- フック状の補強の追加:プロペラシャフトが入れられる程度に、プロペラシャフト受けに小さなフック状の補強を施すことで、プロペラシャフトの逃げを防止できます。ただし、調整が難しい面もあるため、自分のシャーシに合わせた微調整が必要です。
- アタッチメントの作成:より本格的な改造として、プロペラシャフト受けの壁に挟み、モーターカバーで押さえられるアタッチメントをカーボンなどの端材から作成する方法があります。具体的には、プロペラシャフト受け壁とモーター間の隙間にプロペラシャフト受け壁と面一になる壁を新設し、プロペラシャフト受けを「穴」部分だけにする工夫です。
- モーターカバーの押さえ強化:モーターカバーは3点支持ですが、着地衝撃などでモーターが動いてロスが発生する可能性があるため、モーターカバーをしっかりと押さえることも重要です。端材をバンパーと共締めするなどの工夫が効果的です。
- フロントAパーツの補強:フロントのAパーツのプロペラシャフト受けもはめ方次第で曲がったり破損したりします。状況に応じて補強することも、性能向上に繋がります。
- ピンククラウンの位置調整:フロントのピンククラウンが割れやすい問題は、「遊びがある」ことが原因であることが多いです。ピンククラウンと620ベアリングの間に位置合わせのスペーサー(絶縁ワッシャーなど)を挟むことで、この問題を解決できます。
これらの改造を施すことで、ARシャーシの最大の弱点であるプロペラシャフト受けの問題を大幅に改善し、より安定した走りを実現できます。特に正転ARでは、この改善が性能を大きく左右するため、丁寧に調整することをおすすめします。
ターミナル周りの改造で電気ロスを軽減できる
ARシャーシの性能をさらに引き出すためには、ターミナル周りの改造も重要なポイントです。適切な改造を施すことで、電気のロスを軽減し、モーターへの電力供給を最適化できます。
ARシャーシのターミナルはVSシャーシのものに近く、前後ともXシャーシ型のターミナルを使用しています。これを高性能なゴールドターミナルに交換することで、電気の伝導性が向上し、モーターへの電力供給がスムーズになります。ARシャーシには「スーパーXシャーシ・ゴールドターミナル」が適合します。
ゴールドターミナルは、キット付属の銅ターミナルよりも電気をよく通すため、ミニ四駆のスピードがアップします。また、銅と違って劣化しにくいので、高い性能を長期間維持できるメリットもあります。
さらに、ターミナル周りの接触抵抗を減らす工夫も効果的です。例えば、ターミナルとスポンジの間にスポンジを挟むことで、電池の接触が安定し、走行中の電力供給が安定します。ベアリング購入時に付属するスポンジを切って挟むなどの工夫が見られます。
また、ターミナル自体の清掃も重要です。使用前にターミナルを磨くことで、表面の酸化膜を除去し、電気の伝導性を向上させることができます。特に何度か使用したミニ四駆では、このメンテナンスが性能向上に繋がります。
ARシャーシのスイッチは円弧状のレールをスライドする新方式を採用しており、突出するスイッチレバーを保護するフェンスが前方に成形されています。これにより走行中の誤停止を防ぐ工夫がされていますが、スイッチ周りの接触部分も適宜清掃することで、電気ロスを最小限に抑えることができます。
これらのターミナル周りの改造とメンテナンスは、地味な作業に思えるかもしれませんが、ARシャーシの性能を引き出すためには非常に重要です。電気系統の最適化により、モーターのパワーを無駄なく活用できるようになり、より速く安定した走りを実現できるでしょう。
まとめ:ミニ四駆の改造とARシャーシの最適化ポイント
最後に記事のポイントをまとめます。
- ARシャーシは2012年登場の高剛性シャーシで、独特の駆動構造と高い剛性が特徴
- 駆動系改造の基本はスパーギアとクラウンギアの間に1.5mmスペーサーを入れる位置出し
- プロペラシャフト受けの横入れ問題は、フック状の補強やアタッチメント作成で対策可能
- ARシャーシ専用パーツを活用することで効果的な改造が可能
- フロントに13mmワイド、リアに17mmのローラー配置が最適(ローラーベース約132mm)
- 正転ARはピンククラウンのヘリカル処理と相性が良く、適切な改造で高いパフォーマンスを発揮
- モーターと電池の交換、ガイドローラーと補助プレート、タイヤとホイール、駆動系パーツとターミナル、マスダンパーとブレーキ、フロントアンダーガードの順で改造を進めるのが基本
- ARシャーシは個体差が大きいため、シャーシごとの特性を把握して調整することが重要
- ARシャーシの硬さを活かした走行セッティングが効果的
- 超速ギヤの導入とスペーサー調整により駆動効率が大幅に向上
- 軽量化は硬さと強度のバランスを考慮して実施すべき
- ターミナル周りの改造で電気ロスを軽減し、モーターへの電力供給を最適化できる
- ARシャーシは現代ミニ四駆の主流と逆の方向性だが、その特性を理解し活かすことで独自の高いパフォーマンスを発揮できる
- 型番によって特性が異なり、特に「18701-02」は走行中のカウンターギヤカバー外れによるトルク抜けが生じにくく改良されている