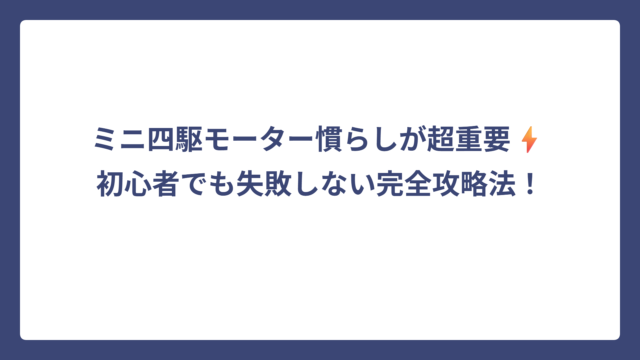ミニ四駆スーパー2シャーシは、2010年12月23日に発売されたスーパー1シャーシのリメイク版で、初登場キットはマグナムセイバープレミアムでした。スーパー1の弱点を克服し、強度やカスタマイズ性が大幅に向上しているため、多くのミニ四駆ファンから支持されている人気シャーシです。
本記事では、スーパー2シャーシの概要から素材の違い、そして改造方法まで詳しく解説します。駆動系の調整やパーツ選びのポイント、さらには速くするためのテクニックなど、初心者から上級者まで役立つ情報を網羅的にお届けします。シャーシ選びで迷っている方や、すでに持っているスーパー2シャーシをもっと速くしたい方は必見です!
記事のポイント!
- スーパー2シャーシの特徴と他シャーシとの違いがわかる
- シャーシの素材による違いと最適な選び方が理解できる
- スーパー2シャーシの改造方法と速くするテクニックがマスターできる
- おすすめのパーツ組み合わせとセッティング方法が学べる
ミニ四駆スーパー2シャーシの特徴と基本情報
- スーパー2シャーシの概要と歴史的背景は発売から進化の歴史
- スーパー2シャーシの素材による違いと選び方のポイント
- スーパー2シャーシの利点は他のシャーシより優れた強度とカスタマイズ性
- スーパー2シャーシの欠点とその対策方法はフロント軸受けの補強が重要
- スーパー2シャーシが初心者におすすめな理由はシンプルさと拡張性の高さ
- スーパー2シャーシに対応するボディの選び方とインストール方法
スーパー2シャーシの概要と歴史的背景は発売から進化の歴史
ミニ四駆スーパー2シャーシは、2010年12月23日に発売された、スーパー1シャーシのリメイクシャーシです。初登場キットはマグナムセイバープレミアムでした。名前の通り、スーパー1の弱点の多くを克服し、さらに強化・発展させたシャーシとなっています。
スーパー2シャーシの基本データを見てみると、全長(キット素組み)は151mm、全幅は97mm、ホイールベースは80mm、地上高は5.3mmとなっています。使用するドライブシャフトは60mmで、対応するギヤ比は5:1、4.2:1、4:1、3.5:1(水色・黄色)、3.7:1と幅広く、様々なセッティングに対応できるようになっています。
発売から数年経過する中で、スーパー2シャーシは細かい改良が加えられてきました。初期のマグナムセイバープレミアムからトライダガープレミアムまで(タイプA)と、Vマグナムプレミアム以降(タイプB)では細かい点が異なります。タイプBでは主に補強などが加えられ、バッテリーホルダーの改良なども行われています。Vマグナムプレミアムから金型改修が加わり、ホルダーの向きがわかるよう取り付け時に前方になる面に三角形の板と、その根元にFRONTの文字が追加されました。
スーパー2シャーシは発売当初、フロントギヤケース及びシャーシの対応部分に構造上の不具合(ギヤカバー爪部分がしっかり固定されない)があることが判明し、任意回収に至ったことがありました。しかし、現在販売されているものはこの問題が解決されており、安心して使用することができます。
スーパー2シャーシの素材による違いと選び方のポイント
スーパー2シャーシには複数の素材バリエーションが存在し、それぞれに特徴があります。主に4つのタイプに分類でき、ノーマルのABSシャーシ、ポリカ強化シャーシ、蛍光のABSシャーシ、カーボン強化シャーシがあります。
ノーマルABSシャーシは、一番ベーシックなタイプで、価格も手頃なのが特徴です。しかし、耐久性はやや劣り、特に右フロントの軸受けがかなり弱いので、使用していると割れやすい傾向があります。音はそこそこ良く、加工も容易なので再現性も高いという利点があります。何より低コストなのが最大のメリットといえるでしょう。
ポリカ強化シャーシは、耐久性と加工性のバランスが最も良いタイプです。ABSと同じように加工できる上に、破損の心配もフロント軸受けのみに絞られます。しかし、致命的な欠点として、無加工だと駆動音が一番うるさいという特徴があります。おそらくポリカーボネートの添加によってシャーシにハリが出すぎているからか、プロペラシャフトがカラカラと弾かれる音がすることがあります。
蛍光シャーシは見た目が派手で目を引きますが、丈夫さに関しては最低クラスです。フロント軸受け、フロントバンパー基部、リヤバンパー基部、モーターマウントフレーム、ペラ受けなど、様々な箇所が割れやすい特徴があります。これは蛍光剤の添加がシャーシの素材強度に悪影響を与えているためと考えられています。
最後にカーボン強化シャーシは、最も丈夫で駆動音も静かなプレミアムタイプです。カーボンファイバー配合ナイロン樹脂を使用しており、ビクトリーマグナムプレミアム、バンガードソニックプレミアム、アゼンテプログレス、ネオトライダガーZMCカーボンSPなどのキットに採用されています。その分、価格は高めですが、耐久性を重視する方におすすめです。
シャーシ選びの際は、使用目的や予算に応じて選択すると良いでしょう。レースで使用することが多い方はカーボン強化かポリカ強化がおすすめですし、見た目重視やコレクション目的なら蛍光シャーシも魅力的な選択肢となります。
スーパー2シャーシの利点は他のシャーシより優れた強度とカスタマイズ性

スーパー2シャーシの最大の利点は、前身であるスーパー1シャーシの弱点を克服し、大幅に強度とカスタマイズ性が向上している点です。特にバンパー部分の強化は注目に値します。スーパー1シャーシ最大の弱点だったバンパーが、ダッシュモーター使用の立体レースにも十分耐えられる強度になりました。
新しい補強プレートにも一通り対応するだけのビス穴増加もあって、このバンパー補強こそがスーパー1と比較した時の最大の恩恵と言っても過言ではありません。そしてこのスーパー2シャーシで初めて、84mm幅のビス穴が追加されました。これにより、初めて追加パーツ無しでローラーの幅を広げられるようになりました。
また、リアステー本体は新形状の2点止めの物が付属します。この2点止めステーは、従来の強度が低くいまいち役に立たない物から、強度も拡張性も高く、ローラーベースも程よくなるように改められています。取り付け基盤は三角形になっている箇所が2つあり、それまでのVSやX系よりも頑丈に作られています。旧来の1点止め用の穴もあるので、1点、3点止めのリアステーにも対応しています。
電気系統も強化されており、バッテリーホルダーがS1用強化バッテリーホルダーを肉抜きしたような形状に変更され、強度が向上しています。ボディキャッチも完全新規設計で、これまでに無かった形状になっています。
駆動系においても、フロント・リヤギヤケースの形状が変更され、信頼性が向上しています。フロントはスイッチの方式をスライド式からMSシャーシの軽量センターユニットの方式に近いターン式スイッチに変更し、スイッチを入れたとき「カチッ」という風にクリックを持たせ、確実に固定される様になっています。
これらの改良点により、スーパー2シャーシは耐久性、拡張性、安定性のすべてにおいてバランスの取れたシャーシとなっており、様々なレーシングスタイルに対応できる汎用性の高さが大きな魅力となっています。
スーパー2シャーシの欠点とその対策方法はフロント軸受けの補強が重要
スーパー2シャーシには多くの利点がある一方で、いくつかの欠点も存在します。最も顕著な欠点はフロント軸受けの脆弱性です。特に右フロントの軸受けがかなり弱く、レース中の衝撃などですぐに割れてしまうことがあります。
この問題に対する対策としては、フロント軸受け部分の補強が効果的です。市販のフロント補強パーツを使用するか、カーボンプレートなどで自作の補強を施すことで、耐久性を高めることができます。また、タイヤのブレとAパーツのゆがみをしっかりケアすることで、フロント軸受けへの負担を減らすこともできます。
もう一つの欠点として、ジャンプからの着地でバッテリーホルダーが外れる可能性があることが挙げられます。最悪の場合、電池が外れて止まってしまうこともあります。この問題に対しては、バッテリーホルダーをしっかりと固定するためのテープや、専用の強化パーツを使用することをおすすめします。
また、蛍光シャーシを使用する場合は特に注意が必要です。蛍光シャーシはあらゆる箇所が割れやすい特性があります。これは成型する段階で蛍光塗料または蛍光剤の添加がシャーシの素材の当接力に悪影響を与えていると考えられています。蛍光シャーシを使用する場合は、カーボンプレートなどでしっかりと補強するか、レブチューン用のマシンなど、激しい走行を想定しないマシンに使用するのが無難です。
ポリカ強化シャーシを使用する場合は、駆動音がうるさくなる可能性があります。これはポリカーボネートの添加によってシャーシに硬さが出すぎていることが原因と考えられています。この問題に対しては、駆動系のパーツをしっかりと調整し、摩擦を減らすことで改善できる場合があります。
最後に、一部のボディとの相性問題があります。ビス穴が増えた分、ボディによっては取付けが難しくなるか、無加工では取り付け不可能な場合があります。ボディを選ぶ際には、スーパー2シャーシとの互換性を確認するか、必要に応じて加工する準備をしておくと良いでしょう。
スーパー2シャーシが初心者におすすめな理由はシンプルさと拡張性の高さ
スーパー2シャーシは、ミニ四駆初心者にとって非常におすすめのシャーシです。その理由はいくつかありますが、最も大きな利点はシンプルさと拡張性のバランスが優れている点にあります。
まず、スーパー2シャーシは基本設計がシンプルで理解しやすいため、初めてミニ四駆に触れる方でも組み立てやすいという特徴があります。シャフトドライブ方式を採用しており、駆動系の構造が直感的に把握できるため、メンテナンスや調整も比較的容易です。また、パーツ数も必要最低限に抑えられているため、パーツの紛失や破損のリスクも低減されています。
さらに、スーパー2シャーシは「意外と弱点がない」というのも大きな利点です。他のシャーシを見てみると、MAはフロントアッパーを直さないといけない、FM-Aはボディをフリーラインで切らないといけない、ARは重いし摩耗が激しい、VZはフロントが高すぎるなど、それぞれに個性と弱点があります。それに比べてS2は、フロントが低いことやカウンター工夫が必要という点を除けば、案外優秀なシャーシとなっています。
また、スーパー2シャーシは拡張性が高く、様々なカスタマイズが可能です。多くのメーカーからスーパー2シャーシ用のパーツが販売されており、自分好みにカスタマイズしやすいという特徴があります。初心者の段階では基本的なセッティングで走らせ、徐々に知識と経験を積みながらカスタマイズを進めていくことができるため、長く楽しむことができるシャーシです。
価格面でも初心者に優しく、ベーシックなキットであれば比較的安価に入手できます。キット付属のパーツだけでも十分走行可能で、追加のパーツは必要に応じて徐々に揃えていくことができるため、初期投資を抑えながらミニ四駆を楽しむことができます。
初心者の方がスーパー2シャーシを選ぶ際は、マグナムセイバープレミアムやソニックセイバープレミアムなど、ベーシックなキットから始めるのがおすすめです。これらのキットは価格も手頃で、基本的なパーツが一通り揃っているため、すぐに走らせることができます。
スーパー2シャーシに対応するボディの選び方とインストール方法
スーパー2シャーシに対応するボディを選ぶ際には、いくつかのポイントに注意する必要があります。スーパー2シャーシはビス穴が増えた関係で、一部のボディでは取り付けが難しくなっている場合があります。
まず、スーパー2シャーシに完全に互換性のあるボディを選ぶことが重要です。基本的にはスーパー2シャーシ用として発売されているキットのボディなら問題なく装着できますが、それ以外のボディを流用する場合は注意が必要です。例えばブレイジングマックス(VSシャーシ)は小径タイヤなら奇跡的に無加工で嵌りますが、シャイニングスコーピオン(スーパー1シャーシ)はギリギリで何とかはまる(コツが必要)程度です。また、旧ネオトライダガーZMCなどスーパー1シャーシに非常にフィットしていたボディは、スーパー2シャーシには嵌らない場合があります。
スーパー2シャーシ対応のボディとしては、マグナムセイバー、ソニックセイバー、トライダガーX、ビクトリーマグナム、バンガードソニック、シャイニングスコーピオン、ベルクカイザー、レイスティンガー、ビークスパイダーなどが挙げられます。これらはすべてスーパー2シャーシ用として発売されているため、互換性に問題はありません。
ボディをインストールする際のポイントとしては、まずボディキャッチの取り付け位置を確認することが重要です。スーパー2シャーシのボディキャッチは完全新規設計で、これまでに無かった形状になっていますが、規格は一緒なので他シャーシに流用が可能です。ただし、取り付け方向には注意が必要で、正しい向きでインストールしないとボディが正確に固定されません。
また、バッテリーホルダーも強化され、形状が変更されているため、取り付けには向きがあることに注意が必要です。S1用Vマシンなど胴体が細いボディでは干渉してしまう可能性があるので、そのような場合は適切な加工が必要になることもあります。
ボディとシャーシのカラーコーディネートも重要なポイントです。スーパー2シャーシとギアケースの色が全く違うので、ユーザーのカラーセンスが問われるシャーシであると言えます。見た目を重視する場合は、シャーシの色とボディの色、そしてAパーツの色のバランスを考えて選択すると良いでしょう。
ミニ四駆スーパー2シャーシの改造方法と速度アップのテクニック
- スーパー2シャーシを速くするための基本的な改造方法はタイヤから始める
- スーパー2シャーシに最適なギア比と選び方は3.7:1や4.2:1が人気
- スーパー2シャーシの駆動系改造でスムーズな走行を実現する方法はクリアランス調整が鍵
- スーパー2シャーシのモーター周りの改造でパワーアップする方法はブレ防止が重要
- スーパー2シャーシの軽量化テクニックと効果は不要部分の削除から
- スーパー2シャーシに使えるおすすめパーツと組み合わせは目的別に選ぶ
- まとめ:ミニ四駆スーパー2シャーシは改造次第で無限の可能性がある走り屋の相棒
スーパー2シャーシを速くするための基本的な改造方法はタイヤから始める
スーパー2シャーシを速くするための改造は、まずタイヤの精度向上から始めることが重要です。どんなに駆動系を改造しても、タイヤの精度が悪ければその効果は半減してしまいます。独自調査の結果、まずはタイヤの真円出しやブレの解消を優先することが推奨されています。
タイヤの精度を向上させるためには、まず適切なサイズのタイヤを選ぶことが重要です。スーパー2シャーシの場合、「電池抜き重量120g、ローハイトタイヤ真円出しのみ26mmスーパーハード超速」という組み合わせが非常に速いことが報告されています。25mm以下のタイヤでは1mmブレーキも貼れないという特性がありますが、26mmタイヤで1mmブレーキ一択にすることで、小径しかクリアできないようなコース以外に絞り、他を考える必要がなくなります。
次に、タイヤの真円度を確認し、必要に応じて修正します。真円ではないタイヤは走行中に振動を発生させ、モーターの力を効率よく地面に伝えることができません。タイヤを水平な台の上で転がし、高さの変化がないか確認し、変化がある場合は研磨やヤスリがけで修正します。
タイヤの外周面の処理も重要です。路面との摩擦を最適化するために、目的に応じて表面を加工します。グリップ力を上げたい場合は表面を粗くし、スピードを重視する場合はツルツルに仕上げます。また、タイヤの側面に適切なブレーキを設置することで、コーナリング時の安定性を向上させることができます。
また、ホイールとタイヤの組み合わせにも注意が必要です。スーパー2シャーシには、キットによって新形状のロープロホイールにロープロタイヤが装備されるものや、強化素材のフルカウル標準型ホイールにリアルミニ四駆とほぼ同じパターンの入ったタイヤを装備するものなど、様々なバリエーションがあります。どの組み合わせを選択するかは、走行するコースの特性や好みに応じて決めるとよいでしょう。
基本的な改造としては、これらのタイヤとホイールの最適化を行った後、ギアの噛み合わせや軸受けの調整、不要部分の軽量化など、各部の調整を進めていくのが効果的です。段階的に改造を進めることで、どの改造がどの程度効果があるかを把握できるようになります。
スーパー2シャーシに最適なギア比と選び方は3.7:1や4.2:1が人気
スーパー2シャーシは様々なギア比に対応しており、セッティングの幅が広いのが特徴です。対応しているギア比は5:1、4.2:1、4:1、3.5:1(水色・黄色)、3.7:1と豊富で、走行環境や目的に応じて最適なものを選ぶことができます。
一般的に、ギア比が小さいほど(例:3.5:1)最高速度が上がり、ギア比が大きいほど(例:5:1)加速力が高まります。しかし、単純にギア比を小さくすれば速くなるというわけではなく、モーターの特性やコースレイアウト、マシンの総重量などを考慮して選ぶ必要があります。
スーパー2シャーシに人気のギア比としては、3.7:1と4.2:1が多く使われています。3.7:1は比較的バランスが良く、直線の多いコースでの最高速度と、コーナーからの立ち上がりの加速のバランスが取れています。4.2:1はコーナーが多いテクニカルなコースや、坂道が含まれるコースでの使用に適しています。
ギアを選ぶ際には、スーパー2シャーシ用の専用ギアセットを使用するのがおすすめです。タミヤからは「スーパーXX・スーパーIIシャーシ用超速ギヤセット」や「強化ギヤ&ワンロックギヤカバー(スーパーIIシャーシ用)」などが発売されており、これらを使用することで性能向上が期待できます。
特に注目すべきは、カーボン強化素材のギアです。「強化ギヤ&ワンロックギヤカバー」ではギアカバー及び付属のピニオンギア・ヘリカルクラウンギアまでがカーボン強化素材仕様となっています。これらのギアは従来のものより強度が高く、摩耗も少ないため、長期間安定した性能を発揮することができます。
また、ヘリカルクラウンギアは単純に強化素材となっただけでなく形状も見直され、ギア側面部を歯の側へ一段近づけ、側面部からの歯の長さを短くすることで歯を折れにくくしています。カーボン素材になったことで滑りも向上しており、性能向上が期待できます。
ギア比の選択と合わせて、ギアの噛み合わせの調整も重要です。ギア同士の間隔が適切でないと、ノイズや抵抗の増加、最悪の場合はギアの破損につながります。ギアを組み立てる際は、適切なクリアランスを確保し、スムーズに回転することを確認しましょう。
スーパー2シャーシの駆動系改造でスムーズな走行を実現する方法はクリアランス調整が鍵

スーパー2シャーシの駆動系を改造してスムーズな走行を実現するためには、各部のクリアランス調整が非常に重要です。駆動系が効率よく動作することで、モーターの力をロスなく車輪に伝えることができ、結果的に速度アップにつながります。
まず最初に取り組むべきなのは、クラウンギアの位置調整です。フロントの軸受け(620ベアリング)とクラウンギアの間にスペーサーやワッシャーを挟むことで、クラウンの歯とプロペラシャフトのギア歯のクリアランスを適切に調整します。この調整を怠ると、クラウンがプロペラシャフトのギアから逃げて先端でとらえてしまい、クラウンの歯先が割れる原因になります。そうなるとプロペラシャフトが暴れ、爆音の異音が発生したり、プロペラシャフトが伸びてしまったり、フロントのトルクが抜けたりといった悪循環に陥ります。
次に、リア側の調整も重要です。3点留め用ビス穴にビスを立てて、クラウンとスパー付近の壁を全部削り取ります。そして620(520でも可)ブッシュ、小ワッシャー、ブッシュ、クラウン、1.5スペーサー、スパー、小ワッシャー×2、620の順番で差し込むことで、リアのクラウンの左右のズレ防止とスパーの左右ずれの防止ができます。これによりカウンターのブレを防ぐことができます。
ただし、これらの改造は必ずしも必要というわけではありません。実はスーパー2シャーシは素組みの状態でもクリアランスが適切に出ていることが多く、タイヤがブレていなければ問題なく使えます。改造を行う目的は、高回転のモーターを使用する場合など、より過酷な条件下でもシャーシの摩耗を抑え、パーツ交換でメンテナンスを完結させるためです。
カウンターシャフトの改造も効果的です。カウンターシャフトの首を切り落として6.4mmくらいの長さにし、520ベアリングブッシュ、カウンター、620の順に入れることで、520がギアカバーの隙間にはまり込んで固定され、カウンターの根本側が浮かないようにすることができます。この改造はVSやARでも効果的です。特にミニ四駆ドッグについてくる白のAパーツのギアカバーが、520がぴったりはまるのでおすすめです。
また、ワンロックギアカバーの使用も検討すべきポイントです。スーパー2シャーシのカウンターギアカバーはネジ止めで固定する分強度と信頼性は高いものの、メンテナンスの度にネジの付け外しをすると、ネジ穴が摩耗してしまうという欠点があります。ワンロックギアカバーを使用すれば、ロックパーツを捻るだけでカバーを開けることができ、メンテナンス性が大幅に向上します。
これらの改造を組み合わせることで、スーパー2シャーシの駆動系はよりスムーズに、そして長期間安定して動作するようになります。改造の目的は速度向上だけでなく、マシンの信頼性や耐久性を高めることも重要な要素です。
スーパー2シャーシのモーター周りの改造でパワーアップする方法はブレ防止が重要
スーパー2シャーシのモーター周りを改造してパワーアップさせるためには、まずモーターのブレを防止することが非常に重要です。モーターがブレると、その力が効率よく伝達されず、パワーロスが生じてしまいます。
モーターのブレを防ぐ基本的な方法として、マルチテープをモーターの周囲に貼る方法があります。スーパー2シャーシはモーターが左右にブレる傾向があるため、マルチテープを貼ることでブレを止めることができます。これによりモーターの力をより確実にカウンターギアへと伝えることができるようになります。
次に注目すべきなのが、モーターマウントの強化です。スーパー2シャーシのモーターマウントは形状を工夫することで、シャフトドライブシャーシとして唯一モータークーリングシールドを装備できるという特徴があります。このクーリングシールドを装着することで、モーターの冷却効率が向上し、連続走行時のパフォーマンス低下を防ぐことができます。
しかし、モータークーリングシールドを装着する際には注意が必要です。3点止めリアステーと同時に使用すると互いに干渉し、モーターの位置がずれてカウンターギアもずれてしまう可能性があります。これらを同時に使用する場合は、干渉する部分を加工するか、どちらかを諦める必要があります。
また、モーターの性能を最大限に引き出すためには、ピニオンギアの選択も重要です。カーボン強化素材のピニオンギアを使用することで、耐久性が向上し、長期間安定した性能を発揮することができます。以前に発売された強化赤ピニオンは問題があったため、現在のカーボン強化ピニオンへの期待は大きいです。
モーター自体の選択も重要で、使用するモーターによってセッティングを変更する必要があります。高回転型のモーターを使用する場合は、より小さいギア比を選び、トルク型のモーターを使用する場合は、より大きいギア比を選ぶのが一般的です。また、モーターの回転数に応じて、駆動系の抵抗を減らすための加工も検討する必要があります。
最後に、モーターの冷却を考慮した改造も効果的です。モーターが熱くなると性能が低下するため、放熱効率を高める工夫が必要です。モータークーリングシールドの使用に加え、スリットを入れたり、エアフローを確保するための加工を施したりすることで、モーターの冷却効率を向上させることができます。
モーター周りの改造は細かい作業が多く、精度が要求されます。しかし、これらの改造を丁寧に行うことで、スーパー2シャーシのポテンシャルを最大限に引き出すことができるでしょう。
スーパー2シャーシの軽量化テクニックと効果は不要部分の削除から
スーパー2シャーシを軽量化することは、加速性能や最高速度の向上に直結します。シャーシの軽量化には様々な方法がありますが、まずは不要な部分を削除または加工することから始めるのが効果的です。
まず取り組むべきなのが、クラウンギアとスパーギアの間にある壁の切り取りです。この壁はギアの干渉を起こしやすいため、切り取ることでギアの抵抗を減らし、スムーズな回転を実現できます。同様に、前後を繋ぐプロペラシャフトとスパーギアの干渉部分も取り除くことで、さらに抵抗を減らすことができます。
次に、シャフト類の軽量化も効果的です。標準のシャフトから中空シャフトに変更することで、軽量化しながらも強度は維持できます。中空になっても通常のシャフトと強度は同等と言われており、足回りの軽量化はスピードに直結します。同様に、プロペラシャフトも中空のものに変更することで、回転部分の慣性モーメントを減らし、加速性能を向上させることができます。
また、モーターマウント部分に付いている、モーター押さえのような部品も実質的には機能していないため、外しても特に問題ありません。特に、スピンバイパーやVマシンなど、一部のボディではこの部品がボディと干渉してしまうので、外しておいた方が良い場合もあります。
シャーシ本体の肉抜きも軽量化の効果的な方法ですが、強度とのバランスを考慮する必要があります。スーパー2シャーシは中央及びモーター直下の肉抜きはスーパー1のものを引き継いでいますが、電池サイドの肉抜きが埋められているため、ねじれ剛性が上がっています。肉抜きを追加する場合は、シャーシの強度を維持できる箇所を選んで行いましょう。
軽量化の効果を最大限に引き出すためには、全体のバランスも重要です。単に軽くするだけでなく、重心位置や前後の重量バランスも考慮する必要があります。例えば、前が軽すぎるとフロントが持ち上がりやすくなり、コーナリング性能が低下する場合があります。そのため、フロント側に適切な重りを配置するなど、バランスの取れた軽量化を心がけましょう。
軽量化によって得られる効果は、特に加速性能の向上に表れます。質量が小さくなることで同じモーターパワーでより大きな加速度を得ることができ、特にコーナー立ち上がりでの差が大きくなります。また、全体の慣性モーメントが小さくなることで、マシンの挙動が素直になり、コーナリング性能も向上します。
ただし、軽量化には限度があり、あまりに軽くしすぎるとマシンが不安定になる場合もあります。特にジャンプや高速コーナリングでは、ある程度の重量が安定性を確保するのに役立ちます。自分の走行スタイルや使用するコースに合わせて、最適な軽量化レベルを見つけることが重要です。
スーパー2シャーシに使えるおすすめパーツと組み合わせは目的別に選ぶ
スーパー2シャーシに使えるパーツは多岐にわたりますが、自分の目的や走行スタイルに合わせて選ぶことが重要です。ここでは、目的別におすすめのパーツと組み合わせを紹介します。
【耐久性重視の組み合わせ】 耐久性を重視する場合は、カーボン強化シャーシをベースに選ぶのがおすすめです。カーボン強化スーパー2シャーシはビクトリーマグナムプレミアム、バンガードソニックプレミアムなどのキットに採用されています。また、「強化ギヤ&ワンロックギヤカバー」のパーツセットに含まれるカーボン強化ピニオンギアとヘリカルクラウンギアを使用することで、ギア部分の耐久性も向上します。さらに、フロント部分の弱点を補強するために、カーボンプレートでの補強も効果的です。
【スピード重視の組み合わせ】 スピードを重視する場合は、軽量化と抵抗の低減がポイントになります。中空のドライブシャフトとプロペラシャフト、「スーパーXX・スーパーII 超速ギヤセット」を使用することで、駆動系の軽量化と効率化を図ることができます。また、タイヤは26mmスーパーハードタイプを選び、真円出しをしっかり行うことで転がり抵抗を減らします。ギア比は直線の多いコースなら3.7:1、技術的なコースなら4.2:1が適しています。
【バランス重視の組み合わせ】 オールラウンドな性能を求める場合は、ポリカ強化シャーシがバランスが良いでしょう。強度と加工性のバランスが取れているため、様々な改造に対応できます。駆動系のパーツは標準的なものを使用し、必要に応じて「ワンロックギヤカバー」を追加することでメンテナンス性を向上させることができます。タイヤは用途に応じて選択し、コースに合わせて1mmブレーキを装着します。
【初心者向けの組み合わせ】 初めてミニ四駆を始める方には、スーパー2シャーシのベーシックなキット(マグナムセイバープレミアムやソニックセイバープレミアムなど)をそのまま使用するのがおすすめです。追加パーツとしては、「EXサイドステー」を装着することで、コースアウトを防ぎ安定した走行が可能になります。また、「2段アルミローラーセット 13-12mm」を使用することで、コーナリング性能を向上させることができます。
【競技志向の組み合わせ】 本格的なレース参加を考えている方には、カーボン強化シャーシと各種強化パーツの組み合わせがおすすめです。「強化ギヤ&ワンロックギヤカバー」、カーボンフロントプレート、3点式リアステーなどを装着し、シャーシの強度を確保します。また、「スーパーIIシャーシ ゴールドターミナル」を使用することで、電気的な接触を安定させ、モーターパワーをロスなく伝えることができます。
【見た目重視の組み合わせ】 コンクール・デレガンスなど見た目を重視する場合は、蛍光カラーシャーシセットや各種カラーバリエーションのシャーシを選ぶと良いでしょう。シャーシ本体のカラーバリエーションは非常に豊富で、ブラック、ホワイト、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、パープルなど様々な色が揃っています。Aパーツも各色が用意されており、ボディのカラーに合わせてコーディネートすることができます。
これらのパーツ選びと組み合わせは、あくまで参考例です。自分のスタイルや好みに合わせて、独自の組み合わせを見つけることも、ミニ四駆の楽しみの一つです。まずは基本的なセッティングから始め、走らせながら少しずつ改良していくことをおすすめします。
まとめ:ミニ四駆スーパー2シャーシは改造次第で無限の可能性がある走り屋の相棒
最後に記事のポイントをまとめます。
- スーパー2シャーシは2010年12月に発売されたスーパー1シャーシのリメイク版で、初登場キットはマグナムセイバープレミアム
- 素材はノーマルABS、ポリカ強化、蛍光ABS、カーボン強化の4種類があり、用途に応じて選ぶことが重要
- カーボン強化シャーシは最も丈夫で駆動音も静かだが、加工再現性は低い
- スーパー2シャーシの最大の利点はバンパー強度の向上と84mm幅のビス穴追加による拡張性の高さ
- 弱点はフロント軸受けの脆弱性とバッテリーホルダーが外れやすい点で、適切な補強が必要
- 初心者におすすめな理由はシンプルさと拡張性のバランスが良く、理解しやすいため
- スーパー2シャーシを速くするには、まずタイヤの精度向上から始めることが重要
- 26mmタイヤと1mmブレーキの組み合わせが速いと報告されている
- ギア比は3.7:1と4.2:1が人気で、コース条件に応じて選択する
- 駆動系改造ではクラウンギアの位置調整やカウンターシャフトの改造が効果的
- モーター周りの改造ではブレ防止が重要で、マルチテープの使用やモーターマウントの強化が有効
- 軽量化は不要部分の削除や中空シャフトの使用から始め、バランスを考慮して行う
- パーツ選びは目的別に行い、耐久性重視、スピード重視、バランス重視など、自分のスタイルに合わせる
- カーボン強化ギアやワンロックギアカバーなど、専用強化パーツの使用で性能と耐久性を向上できる
- スーパー2シャーシはシンプルながらも奥が深く、改造次第で無限の可能性を持つシャーシである