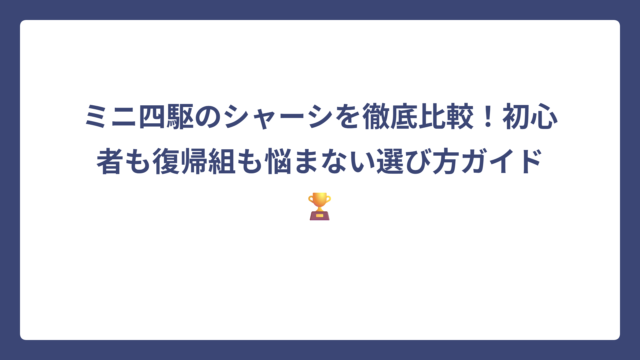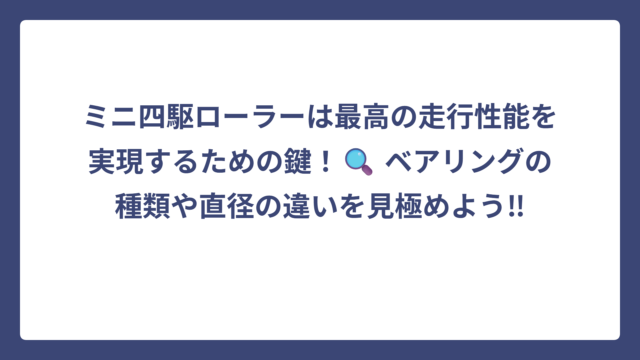ミニ四駆のパフォーマンスを左右する重要な部品であるピニオンギア。この小さなパーツがマシンの走行性能に与える影響は想像以上に大きいんです!モーターの動力をタイヤへと伝える「駆動系の起点」であるピニオンギアは、その種類や素材、取り付け方によって、マシンの速さや安定性が大きく変わってきます。
本記事では、独自調査の結果から分かったピニオンギアの基本知識や種類別の特徴、選び方のコツ、取り付け方のポイントまで、ピニオンギアに関するあらゆる情報を詳しく解説します。プラスチック製、カーボン強化、真鍮製など各素材の特性はもちろん、モーターの回転数との相性や、公式大会のレギュレーションについても触れているので、あなたのマシン設定を最適化するための知識が必ず身につくはずです。
記事のポイント!
- ピニオンギアの役割と素材別の特徴を理解できる
- モーターの回転数に適したピニオンギア選びのコツがわかる
- ピニオンギアのトラブル対処法と正しい取り付け方を学べる
- 公式大会で使用できるピニオンギアの種類とレギュレーションを把握できる
ミニ四駆ピニオンギアの基本と種類
- ピニオンギアとは動力伝達の核となるパーツ
- ピニオンギアの種類は大きく3タイプに分かれる
- プラスチック製ピニオンギアは軽量だが耐久性に注意が必要
- カーボン強化ピニオンギアは強度と軽さのバランスが優れている
- 真鍮製ピニオンギアはパワーロスが少なく頑丈な特性を持つ
- ミニ四駆のピニオンギアは基本的に8T(8歯)で統一されている
ピニオンギアとは動力伝達の核となるパーツ
ミニ四駆におけるピニオンギアは、モーター軸に取り付けられ、カウンターギアに回転を伝えるための重要なパーツです。駆動系の起点となるこのギアは、マシンの走行に欠かせない核となる部品の一つとして位置づけられています。
モーターが生み出すパワーは、まずこのピニオンギアに伝わり、そこからカウンターギア、そしてスパーギアを経由してタイヤへと伝達されます。この動力伝達の最初の部分を担うピニオンギアの状態が悪いと、モーターのパワーをうまく伝えることができず、マシンの性能を十分に発揮できなくなってしまうのです。
ピニオンギア選びは、特にハイパワーなモーターを使用する場合に重要性が増します。モーターが生み出す回転エネルギーを無駄なく伝えるためには、適切な素材と形状のピニオンギアを選ぶ必要があります。
初心者の方がよく見落としがちなのが、ピニオンギアの定期的な点検と交換です。ギアがすり減ったり、ゆるんで抜けやすくなったりした場合は、早めに交換することが高性能を維持するためのポイントとなります。
また、レース中のクラッシュやコースアウト時のタイヤロックなどによって、ピニオンギアに負荷がかかることもあります。こうした状況が繰り返されると、ピニオンギアが損傷したり、モーターピンから抜けたりする原因となるため、レース後の点検も欠かせません。
ピニオンギアの種類は大きく3タイプに分かれる
ミニ四駆のピニオンギアは、大きく分けて3種類あります。プラスチック製、カーボン強化素材、そして金属製(真鍮)の3タイプです。それぞれに特徴があり、使用するシャーシやモーターの種類、レースのスタイルによって最適なものが変わってきます。
プラスチック製ピニオンギアは、さらに白ピニオン、茶ピニオン、紫ピニオン、赤ピニオンなど複数のバリエーションがあります。これらは色だけでなく、形状や材質にも微妙な違いがあり、それぞれ特性が異なります。
カーボン強化ピニオンギアは、通常黒色で炭素繊維を混合して強度を向上させているのが特徴です。ARシャーシやFM-Aシャーシでは、このカーボン強化ピニオンか真鍮ピニオンしか使用できないという制限があるので注意が必要です。
真鍮製ピニオンギアは、耐久性が高く駆動ロスも少ないという利点がありますが、重いのとカウンターギアよりも硬い素材であるため、ギアへのダメージを懸念する声もあります。ただし、立体コースが主流となった2010年代以降は、ジャンプの着地などでピニオンにダメージが入りやすくなったため、真鍮ピニオンを見直すユーザーも増えています。
各種類のピニオンギアは、タミヤの公式製品として販売されているほか、AOパーツとしても提供されています。また、特定のシャーシキットに同梱されているものもあります。自分のマシンの使用環境や目的に合わせて、最適なピニオンギアを選ぶことが重要です。
プラスチック製ピニオンギアは軽量だが耐久性に注意が必要
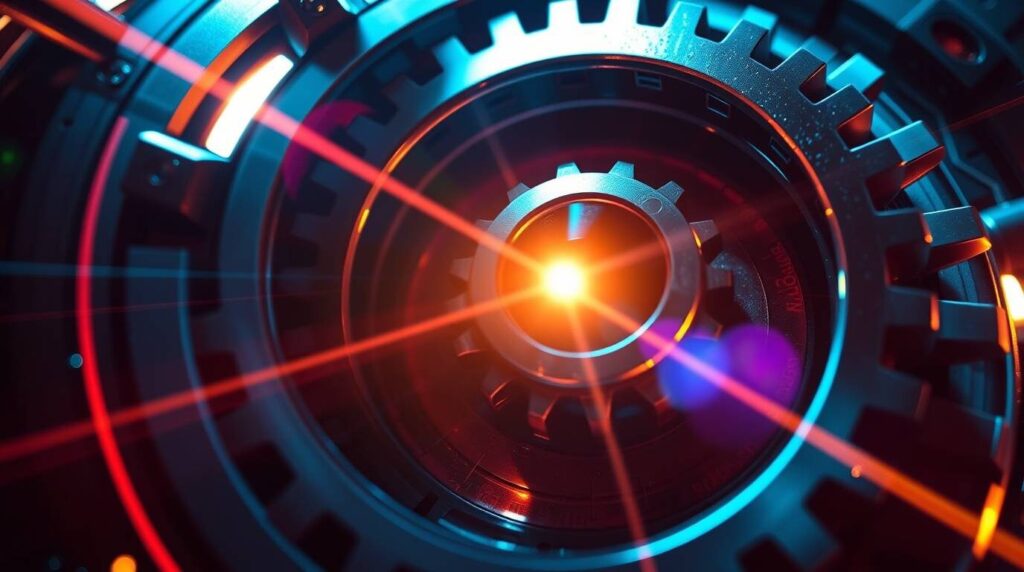
プラスチック製ピニオンギアは、基本的な素材ながらミニ四駆との相性が良く、現在も多くのユーザーに使われています。その最大の特徴は軽量さにあります。小さなパーツなので大差ないと思われるかもしれませんが、駆動系のパーツは他の10倍軽量化に効果があると言われており、パフォーマンスに与える影響は意外と大きいのです。
プラスチック製ピニオンギアの中でも、白ピニオンは比較的強度が高く、ちょっとやそっとのクラッシュでは歯が欠けにくいという特徴があります。スーパーXXシャーシ以前のシャフトドライブシャーシのキットに1個同梱されていたもので、その他にGUPのローハイトワンウェイ以降のワンウェイホイールシリーズにも同梱されています。
紫ピニオンは、元々GUPの中空プロペラシャフトに付属していた製品で、現在はMSシャーシのキットから標準装備(2個同梱)されています。バランスが取れたピニオンギアで愛用者も多いですが、柔らかい材質を使っているためか、取り付け方が悪いと着地やクラッシュであっさり破損してしまうという弱点があります。
赤ピニオン(通称)は、形状は紫ピニオンと同じですが、2009年3月に再販されたGUPの2.0mm中空プロペラシャフトに2個同梱されていました。使用感は紫ピニオンとあまり変わらないとされています。
プラスチック製ピニオンギアの共通の欠点として、樹脂の定めとして経年変化による緩み、そして最終的には割れといった症状が出ることが挙げられます。長時間使用しているとどうしても緩くなるので、その症状が出始めたら交換することをおすすめします。特に紫ピニオンや赤ピニオンを使用している場合は、アップダウンの多いコースを走らせた後やクラッシュ後には、ピニオンの状態をしっかり確認するようにしましょう。
カーボン強化ピニオンギアは強度と軽さのバランスが優れている
カーボン強化ピニオンギア(通称:カーボンピニオン、黒ピニオン)は、炭素繊維を混合して強度を向上させた現代的なピニオンギアです。その特徴は、プラスチック製より高い強度を保ちながらも、真鍮製ほど重くならないというバランスの良さにあります。
全てのシャーシで使用可能であり、特にARシャーシやFM-Aシャーシではカーボン強化ピニオンか真鍮ピニオンしか使用できないという制限があるため、これらのシャーシユーザーにとっては特に重要なパーツと言えます。ARシャーシ用のカーボン強化ピニオンは、紫ピニオンや赤ピニオンと同一形状ですが、強度が大幅に向上しています。
カーボン強化ピニオンギアの形状には複数のタイプがあります。紫ピニオンをベースにした形状のものや、ダンガンレーサーのものに似た形状で片側がリング状になっているものなどがあります。特に後者は、紫ピニオンよりも強度が高く、抜け難い設計になっています。
独自調査の結果、カーボン強化ピニオンギアは基本的に欠点がないと言っていい製品ですが、カーボン配合とはいえ所詮はナイロンなので、マシンのセッティングやコースレイアウトによっては意外とあっさり破損することもあります。特にハイパワーなモーターを使用する場合や、ジャンプなどの衝撃が多いコースでは注意が必要です。
2012年8月には「カーボン強化8Tピニオンギヤ(6個)」として商品化され、現行のARシャーシのキットにも標準装備されています。どうしてもカーボンピニオンでは厳しいと思われる極端なハイパワーモーターを使用する場合は、真鍮ピニオンの使用も視野に入れると良いでしょう。
真鍮製ピニオンギアはパワーロスが少なく頑丈な特性を持つ
真鍮製ピニオンギアは、1次ブーム時のGUPの軽量プロペラシャフトセットに2個付属していたのが初出で、頑丈さと駆動ロスの少なさが特徴です。特にハイパワーモーターを使う場合は、真鍮製ピニオンギアを使えばパワーをロスなく伝えることができるというメリットがあります。
ただし、真鍮製ピニオンには重いという欠点があります。また、カウンターギアより硬い素材であるため、ギアへのダメージを懸念する声もあります。そのため、フラットレースが全盛だった2000年代には一度廃れた時期もありました。
しかし、立体コースが主流になった2010年代では、ダッシュモーター解禁やアップダウン(特にジャンプからの着地)でピニオンにダメージが入りやすくなっていき、少しずつ真鍮ピニオンを見直すユーザーも増えてきています。実際に真鍮ピニオンを使って公式大会優勝したレーサーも存在するそうです。
現在、真鍮ピニオンを入手する方法としては、「紫ピニオン4つと真鍮ピニオン4つのセット」で販売されている製品が主流です。また、以前はチューンモーターPRO3種に標準装備されていましたが、チューン2系モーターへの移行でピニオンギアは別売りになりました。
真鍮ピニオンは基本的にはモーターと一蓮托生という認識でよいでしょう。専用の「ピニオンプーラー」(1,500円程度)で外すことも不可能ではありませんが、壊れたモーターからプーラーで丁寧に外して使いまわすというのも一つの方法です。また、片軸シャーシで使う分には問題ありませんが、両軸シャーシ、特に4:1の青ギアを使う際はピニオンを挿す深さに注意が必要です。シャーシの個体次第ですが、モーター軸と同じ高さまで挿してしまうとカウンターギアとの噛み合わせが半端になり、すぐにギアをダメにしてしまう場合もあります。
ミニ四駆のピニオンギアは基本的に8T(8歯)で統一されている
ミニ四駆に使用されるピニオンギアの歯数は、基本的に8T(8本)に固定されています。これはTYPE-1系列のシャーシを除く全てのシャーシに共通する特徴です。この規格の統一により、互換性が保たれ、ピニオンギアの選択肢が素材や形状に焦点を当てられるようになっています。
例外として、TYPE-1シャーシ、TYPE-3シャーシ、トラッキンシャーシなどには12T(茶色)のピニオンギアが付属しています。これらのシャーシでギア比を6.4:1、5:1、4:1にする際にはこの12Tピニオンが必要となります(11.2:1と8.75:1の場合は8Tを使用)。しかし、これらは比較的古いシャーシであり、現代の主流シャーシでは8Tが標準となっています。
8Tに統一されている理由については明確な公式説明はありませんが、おそらくミニ四駆のバランス設計において最適なギア比を実現するためと考えられます。歯数が少なすぎるとトルクは増すものの速度が出にくくなり、逆に多すぎると速度は出るものの加速性能やコーナリング時の安定性が損なわれる可能性があります。
また、製造や流通の観点からも、パーツを統一することでコスト削減やユーザーの混乱防止になるという側面もあるでしょう。初心者から上級者まで幅広いユーザーが楽しめるミニ四駆において、パーツの標準化は重要な要素と言えます。
8Tのピニオンギアを使用する際は、モーターの種類や回転数、コースレイアウト、マシンの総重量などを考慮して、適切な素材のものを選ぶことが重要です。特に回転数が高いモーターを使用する場合は、より耐久性の高いカーボン強化ピニオンや真鍮ピニオンを選ぶと良いでしょう。モーターの回転数が24,000回転を超えてくると、プラスチック製ピニオンでは耐久性に不安が出てくるという意見もあります。
ミニ四駆ピニオンギアの選び方とメンテナンス
- モーターの回転数に合わせたピニオンギア選びが重要である
- シャーシの種類によって使用できるピニオンギアに制限がある
- ピニオンギアの取り付け方にはコツと注意点がある
- ピニオンギアの外し方には専用ツールが便利である
- ピニオンギアのトラブルと対処法を知っておくことが大切
- 使用済みピニオンギアはワッシャーとして再利用できる
- まとめ:ミニ四駆ピニオンギアの正しい選び方とメンテナンスが走行性能を左右する
モーターの回転数に合わせたピニオンギア選びが重要である
ミニ四駆のモーターの回転数は、使用するピニオンギアの種類選びに大きく影響します。独自調査によると、モーターの回転数が24,000回転を超えてくると、ピニオンに対する考え方が変わってくるとされています。この回転数を一つの区切りとして、ピニオンギアの素材選びを検討する必要があります。
24,000回転以上の高回転モーターを使用する場合、プラスチック製の紫ピニオンではなく、カーボン強化ピニオンを使用することが推奨されています。その理由は、高回転になるとピニオンの抜けが起こりやすくなるからです。ギアの駆動やコースアウト時のタイヤロックでピニオンが滑りやすくなることもありますが、より大きな要因として、モーターの発熱が挙げられます。
高回転のモーターは非常に高温になり、手で持てないほど熱くなることもあります。そうなると、モーターピンに直結しているピニオンも同様に高温になります。プラスチック製ピニオンはモーターピンより膨張係数が大きいため、熱により穴が緩くなってしまうのです。樹脂材料は素材が柔らかければ柔らかいほど膨張係数も大きくなり、熱膨張による歪みも大きくなります。そのため、より硬度が高い(密度が高い)素材を選ぶことで、抜け落ちを防ぐことができます。
ある実験では、ノーマルモーターは無負荷で約18,000回転、ウルトラダッシュモーターは無負荷で約35,000回転を記録したとの報告もあります。こうした高回転モーターを使用する場合は、カーボン強化ピニオンや真鍮ピニオンを選ぶと良いでしょう。
ただし、真鍮ピニオンを使用する場合は、硬すぎるためにモーターピンのわずかな振れによるカウンターギアへのダメージが直接伝わりやすくなるという欠点もあります。そのため、極端にリアの駆動を完璧にしたマシンでなければ、カーボン強化ピニオンがバランスの良い選択肢と言えるでしょう。また、トルクチューンモーターやMSシャーシには真鍮ピニオンが相性が良いという意見もあります。
シャーシの種類によって使用できるピニオンギアに制限がある
ミニ四駆では、使用するシャーシの種類によってピニオンギアの選択肢が制限される場合があります。特に注目すべきなのは、ARシャーシとFM-Aシャーシです。これらのシャーシでは、公認競技会規則(レギュレーション)により、プラスチック製ピニオンの使用が認められていません。
この規制の理由については、駆動の関係からプラスチックピニオンが割れやすいためではないかと推測されています。ARシャーシやFM-Aシャーシを使用する場合は、カーボン強化ピニオンか真鍮製ピニオンを使用する必要があります。規則違反でレースに参加できなくなる可能性もあるため、この点は特に注意が必要です。
また、TYPE-1系列のシャーシは、他のシャーシとは異なるギア比設定が可能で、12Tのピニオンギア(茶色)を使用することもあります。この場合、通常の8Tピニオンとは異なる計算でセッティングを考える必要があります。
シャーシの進化とともに、推奨されるピニオンギアも変わってきています。例えば、エアロアバンテの初期ロットには特殊なカーボン強化ピニオンが付属していましたが、その後のARシャーシキットには現在主流のカーボン強化8Tピニオンギアが付属するようになりました。
シャーシの選択はレースでの戦略に大きく影響するため、そのシャーシに最適なピニオンギアを選ぶことで、マシンのポテンシャルを最大限に引き出すことができます。例えば、MSシャーシは真鍮ピニオンと相性が良いという見解もあります。シャーシの特性を把握した上で、適切なピニオンギアを選択することが、競技での優位性を確保するポイントとなるでしょう。
ピニオンギアの取り付け方にはコツと注意点がある

ピニオンギアの取り付け方は、マシンの性能に直接影響する重要なポイントです。独自調査によると、ベテランレーサーは以下のようなステップでピニオンギアを取り付けています。
まず、モーターピンをペーパーで軽く削ります。表面が傷ついていると接着剤がなじみやすくなるためで、これは塗装前の表面処理と同じ原理です。次に、3Mのネジゆるみ止め嫌気性接着剤(低粘度)をほんの少しだけ(1mm以下の水滴程度)モーターピンに塗布します。ポリカの切れ端などを使ってピンの先全周になじませてから、エンドベルの上からピンを抑えながら、ピニオンギアの穴にモーターピンを突っ込みます。
この方法であれば、かなりの回数コースアウトしてタイヤロックさせても、ピニオンが滑ることはほとんどなくなるでしょう。ただし、接着剤を使用する場合は、ピニオンが外れなくなる可能性もあるため、モーター交換時にはピニオンごと交換する覚悟が必要です。
真鍮ピニオンの場合は、特に取り付け方に注意が必要です。説明書によれば「ハンマーを使ってひと思いに叩け」とありますが、モーターが痛むかピニオンが割れる可能性もあるため、慎重に行うべきです。真鍮ピニオンはプラスチック製に比べて非常に固く、手で押し込むのは困難です。多くの場合、実際にハンマーでの打ち込みが必要になるようです。
両軸モーターを使用する場合は、ピニオンの差し込む角度にも注意が必要です。両サイドで差し込む角度を22.5度ずらすことで、駆動効率が上がるという理論があります。これは自転車のペダルが向かい合っているときに漕ぎやすいのと同じ原理で、両側のバックラッシュ距離を調整することで回転サイクルが安定するとされています。
また、ピニオンの差し込みの深さも重要なポイントです。特に両軸シャーシで4:1の青ギアを使う際は、ピニオンを挿す深さに注意が必要です。モーター軸と同じ高さまで挿してしまうと、カウンターギアとの噛み合わせが半端になり、すぐにギアをダメにしてしまう場合があります。適切な深さに調整するには、専用の治具やツールを使用するとより正確に行えます。
ピニオンギアの外し方には専用ツールが便利である
ピニオンギアをモーターから外す際には、専用の「ピニオンプーラー」や「ピニオン抜き」と呼ばれるツールが非常に便利です。モーターからピニオンを強引に引き抜こうとすると、モーターやピニオン自体を破損する恐れがあるため、正しい道具を使うことが重要です。
ミニ四駆用のピニオン抜きには、主に2種類があります。一つは「ミニ4駆ピニオン抜き(ITEM:15207)」で、本体がプラスチック製であり、ピニオンギアを押し出すネジ部とギアを支える部分のみが金属となっています。これは比較的安価ですが、強度は低く、数回の使用で使い物にならなくなることもあるようです。
もう一つは「ミニ四駆 ピニオンプーラー(ITEM:15422)」で、こちらは全金属製でより頑丈になっています。本体はアルミの削り出しで、平たい部分が市販のレンチ(10mm用)に合うように設計されているため、力が必要なときは組み合わせると楽に抜けます。また、曲面部はモーターの曲面部と同じ直径になるよう成形されていて、モーターケースに収納しやすい工夫もされています。価格は1,500円程度とやや高めですが、頻繁にピニオンを交換する場合は投資する価値があるでしょう。
真鍮ピニオンの場合は特に、通常のプーラーでも外すことは可能ですが、基本的にはモーターと一蓮托生という認識でよいでしょう。どうしても勿体ないと思ったら、壊れたモーターからプーラーで丁寧に外して使いまわすという方法もあります。
TYPE-1シャーシに付属していたピニオン抜きは、少し変わった構造をしています。中央の溝にモーター軸を引っ掛け、テコの原理で引抜くタイプの物で、さらにTYPE-1と3のピニオン用に適正な深さに刺すための穴とくぼみもあり、シャフトの頭が少し出るように調整できる機能も備えています。ただし、これは主にTYPE-1系シャーシ用で、現代の主流シャーシにはあまり必要のない機能です。
ピニオン抜きを使用する際のコツとしては、まっすぐ引き抜くように心がけ、ねじるような動きは避けることが大切です。また、使用前にはモーターとピニオンの接続部にペネトレイトオイルなどを少量垂らしておくと、スムーズに抜けることがあります。
ピニオンギアのトラブルと対処法を知っておくことが大切
ミニ四駆を走らせていると、ピニオンギアに関連するトラブルに遭遇することがあります。代表的なトラブルとその対処法を知っておくことで、レース本番での不測の事態を回避できるでしょう。
最も多いトラブルの一つは「ピニオンギアの空回り」です。これは主に、モーターピンとピニオンギアの間に隙間ができて、モーターが回転してもピニオンギアにその回転が十分に伝わらない状態を指します。モーターの音はするのに車体が動かない、あるいは力が伝わっていない感じがする場合は、このトラブルを疑ってみましょう。対処法としては、ピニオンギアを一度外して、新しいものに交換するか、前述した接着剤を使った取り付け方法を試すとよいでしょう。
次に多いのは「ピニオンギアの歯の欠け」です。特にプラスチック製ピニオンギアでは、強い衝撃や長期間の使用によって歯が欠けることがあります。歯が欠けると、回転の伝達が不安定になり、マシンの動きにムラが出ます。対処法は単純で、新しいピニオンギアに交換するしかありません。予備のピニオンギアを常に持ち歩くことをおすすめします。
「ピニオンギアの割れ」も注意すべきトラブルです。特に紫ピニオンや、過去に一時的に販売された「HG 8Tプラピニオン」では、縦に割れる(歯欠けではなくピニオン自体が割れる「破竹割り状態」)という症状が報告されています。これはギア歯部分を半分なくしたことで支えが弱くなったことや、素材が硬すぎることが原因と考えられています。対処法は新品への交換ですが、再発防止のためにより強度の高いカーボン強化ピニオンや真鍮ピニオンへの変更を検討するとよいでしょう。
「モーター発熱によるピニオンの緩み」も高回転モーターを使用する場合の悩みの種です。前述したように、24,000回転以上の高回転モーターでは、発熱によってプラスチック製ピニオンの穴が緩くなりやすくなります。対処法としては、カーボン強化ピニオンや真鍮ピニオンへの変更が効果的です。また、モーターの冷却対策を施すことで、間接的にピニオンの緩みを防ぐこともできます。
最後に、「ピニオンとカウンターギアの噛み合わせ不良」も見逃せないトラブルです。これはピニオンの差し込み深さが適切でない場合や、両軸モーターの場合に特に発生しやすい問題です。噛み合わせが悪いと異音や振動が発生し、最悪の場合はギアの破損につながります。対処法としては、ピニオンの差し込み深さを調整したり、ベアリングやスペーサーを用いて適切な位置関係を保つことが重要です。
使用済みピニオンギアはワッシャーとして再利用できる
壊れたモーターから取り外したピニオンギアを廃棄する前に、実は再利用できる方法があります。独自調査によると、使用済みのピニオンギアをカットしてワッシャーやスペーサーとして活用できることがわかりました。
具体的な再利用方法としては、まずピニオンギアを適当な長さのネジに通します。次に、カッターでギアの歯車部分と付け根の間のところに切り込みを入れます。一周切り込みを入れれば、簡単に分離できます。この中央の付け根の部分をスペーサーやワッシャーとして使うことができるのです。
紫ピニオンと黒(カーボン強化)ピニオンでこの作業を行うと、それぞれ微妙に厚みの異なるワッシャーができあがります。これらは、ホイールとベアリングの間に入れて抵抗を軽減したり、間隔調整に活用したりすることができます。
重量を測定した結果、ベアリングローラー用スペーサー4個が約0.07g、紫ピニオンで作ったワッシャー4個も約0.07g、黒ピニオンで作ったワッシャー4個が約0.08gとなっています。重量的にはほぼ同等で、純正のスペーサーの代わりに使用しても大きな差はありません。
このピニオン製ワッシャーの利点は、ベアリングとホイールの間を微調整できる点です。抵抗抜きや間隔調整に活用でき、特に貫通ホイールを使用する場合に有効です。ベアリングとホイールの間を狭くしたいときは通常のお宝ワッシャーを、少し離したいときはこのピニオン製ワッシャーを使うことで、選択肢が広がります。
また、ベアリングローラー用スペーサーをベアリングとホイールの間に入れると、回転時に若干の遊びがあるためか、シャフトとスペーサーが震えて擦れるような音が発生することがあります。一方、ピニオン製ワッシャーはシャフトにぴったりとはまるため、ブレによる異音が発生しにくいという利点もあるようです。
このように、一見不要と思われるピニオンギアでも、工夫次第で別のパーツとして再利用できます。ミニ四駆の改造は創意工夫の連続ですので、廃材と思われるものも捨てずに保管しておくと、思わぬ形で役立つことがあるかもしれません。
まとめ:ミニ四駆ピニオンギアの正しい選び方とメンテナンスが走行性能を左右する
最後に記事のポイントをまとめます。
- ピニオンギアはモーターの動力をカウンターギアに伝える駆動系の起点となる重要パーツである
- ミニ四駆のピニオンギアは基本的に8T(8歯)で統一されている(TYPE-1系列シャーシを除く)
- ピニオンギアは主にプラスチック製、カーボン強化素材、真鍮製の3種類がある
- プラスチック製ピニオンは軽量だが耐久性に欠け、長時間使用で緩みや割れが発生しやすい
- カーボン強化ピニオンは強度と軽さのバランスに優れ、ARシャーシやFM-Aシャーシには必須である
- 真鍮ピニオンはパワーロスが少なく頑丈だが、重いことと他のギアへの負担が大きいという欠点がある
- モーターの回転数が24,000回転を超える場合はカーボン強化か真鍮ピニオンの使用が推奨される
- ピニオンギアの取り付けには、モーターピンを軽く削ってから嫌気性接着剤を使用する方法が効果的である
- ピニオンギアの外しには専用の「ピニオンプーラー」を使用すると安全かつ確実に作業できる
- ARシャーシとFM-Aシャーシではプラスチック製ピニオンの使用がレギュレーションで禁止されている
- 使用済みピニオンギアはカットしてワッシャーやスペーサーとして再利用できる
- 両軸モーターを使用する場合は、両側のピニオンの角度を22.5度ずらすことで駆動効率が向上する可能性がある
- ピニオンギアの状態は定期的にチェックし、緩みや歯の欠けなどが見られたら早めに交換することが重要である