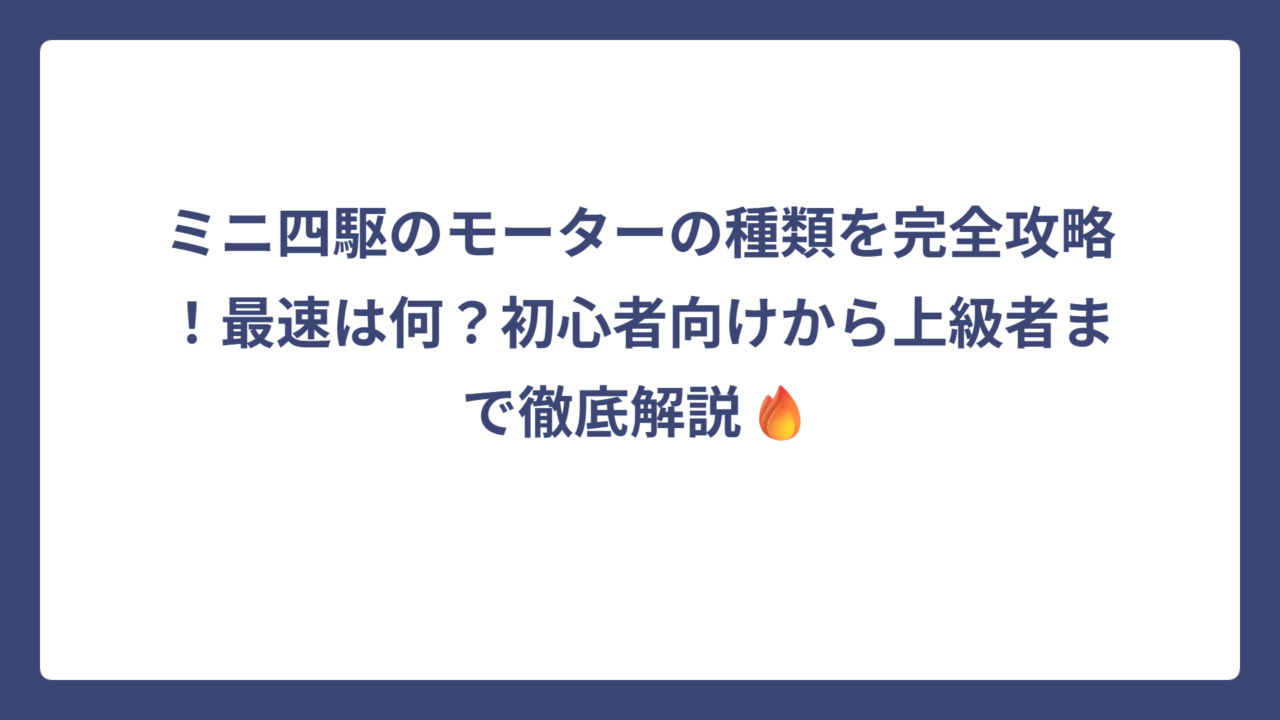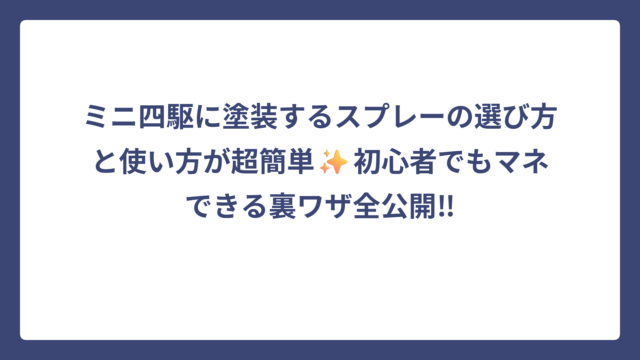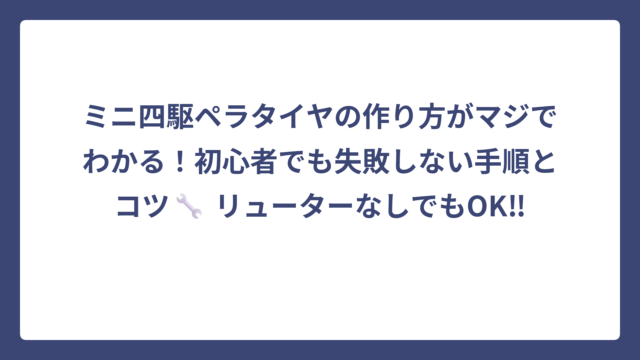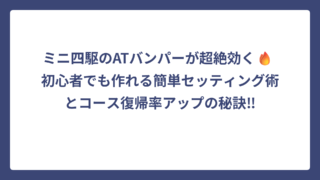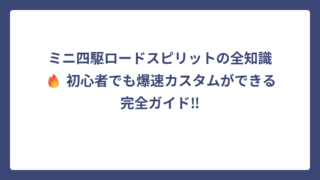ミニ四駆を楽しむ上で避けては通れないのがモーターの選択です。「どのモーターが速いの?」「初心者にはどれがいいの?」と悩んでいる方も多いはず。実はミニ四駆のモーターには片軸と両軸の2種類があり、さらにその中でもスピード型やパワー型など様々な特性を持つモデルが存在します。
本記事では、ミニ四駆のモーター選びに悩む方のために、モーターの種類と特徴を徹底解説します。公式大会で使用可能なモデルから非公式の最速モーターまで、それぞれの特性や選び方のコツをわかりやすく紹介。コースタイプに合わせた選択方法も含め、あなたのミニ四駆ライフをワンランクアップさせる情報が満載です。
記事のポイント!
- ミニ四駆モーターの基本的な種類と互換性について理解できる
- 各モーターの性能比較とおすすめの使用シーンがわかる
- 初心者から上級者まで、レベル別におすすめのモーターが見つかる
- 公式大会で使用できるモーターとNGとなるモーターを把握できる
ミニ四駆のモーターの種類と基本知識
- ミニ四駆のモーターの種類は片軸と両軸の2種類に大別される
- ミニ四駆モーターの性能比較表で速さとパワーの違いを把握すること
- 公式大会で使用可能なモーターとNGとなるモーターの種類を知ること
- ミニ四駆モーターは形状によってシャーシとの互換性が異なる点に注意
- モーターの種類によって電池との相性も変わるポイントを理解する
- ミニ四駆モーターの消費電流の違いは性能に大きく影響する
ミニ四駆のモーターの種類は片軸と両軸の2種類に大別される
ミニ四駆のモーターは、大きく分けて「片軸モーター」と「両軸モーター」の2種類があります。この違いは、モーターシャフト(モーターから伸びている棒)の数によるものです。片軸モーターはモーターシャフトが1つ、両軸モーターはモーターシャフトが2つ付いています。
片軸モーターは通常の「ミニ四駆」シリーズで使用されるもので、プロペラシャフトで4輪へパワーを伝える四輪駆動方式を採用しています。一方、両軸モーターは「ミニ四駆PRO(プロ)」シリーズで使用され、前輪と後輪の両方にダイレクトに回転を伝えられる仕組みになっています。
両者はそれぞれ互換性がないため、使用するシャーシに合わせたモーターを選ぶ必要があります。具体的には、MSシャーシやMAシャーシを使用する場合は両軸モーター、それ以外のシャーシ(VS、ARなど)を使用する場合は片軸モーターを選びましょう。
独自調査の結果、片軸モーターのほうが種類が豊富で、特にハイスペックなモデルが多い傾向にあります。ただし、両軸モーターも駆動効率の良さやダイナミックな走行感が魅力で、多くのレーサーから支持されています。
モーターを選ぶ際は、まず自分の使っているシャーシがどちらのタイプかを確認することが第一歩です。間違ったタイプのモーターを購入してしまうと使用できないので注意しましょう。
ミニ四駆モーターの性能比較表で速さとパワーの違いを把握すること
ミニ四駆のモーターは「スピード型」「パワー型」「バランス型」の3つに大きく分類できます。それぞれのモーターには回転数(RPM)とトルク(パワー)の値があり、これらの数値を比較することで性能の違いを把握できます。
以下に、主要な片軸モーターの性能比較表を示します:
| モーター名 | タイプ | 回転数(r/min) | 推奨負荷トルク(mN・m) | 消費電流(A) | 公式戦使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| FA-130ノーマル | 標準 | 9,900~13,800 | 1.0 | 1.1 | ○ |
| トルクチューン2 | パワー型 | 12,300~14,700 | 1.6~2.0 | 1.7~2.0 | ○ |
| アトミックチューン2 | バランス型 | 12,700~14,900 | 1.5~1.8 | 1.8~2.2 | ○ |
| レブチューン2 | スピード型 | 13,400~15,200 | 1.2~1.5 | 1.6~2.0 | ○ |
| ライトダッシュ | バランス型 | 14,600~17,800 | 1.3~1.9 | 1.5~2.2 | ○ |
| ハイパーダッシュ3 | スピード型 | 17,200~21,200 | 1.4~1.9 | 1.6~3.0 | ○ |
| パワーダッシュ | パワー型 | 19,900~23,600 | 1.5~2.0 | 2.5~3.3 | ○ |
| スプリントダッシュ | スピード型 | 20,700~27,200 | 1.3~1.8 | 2.8~3.8 | ○ |
| ウルトラダッシュ | スピード型 | 24,000~27,500 | 1.4~1.9 | 4.0~5.0 | × |
| プラズマダッシュ | スピード型 | 25,000~28,000 | 1.4~1.9 | 4.1~5.2 | × |
この表から読み取れるように、回転数が高いものほど直線での速度が出やすく、トルクが高いものほど坂道や曲がりなどでの加速力に優れています。例えば、スプリントダッシュモーターは回転数が高くトルクがやや低めなので、直線の多いコースに向いています。一方、トルクチューン2モーターはトルクが高く回転数が控えめなので、カーブや上り坂の多いテクニカルなコースに適しています。
また、消費電流の値も重要で、数値が大きいほど電池の消費が早くなります。特にウルトラダッシュやプラズマダッシュのような高性能モーターは消費電流が非常に大きいため、アルカリ電池では本来の性能を発揮できない点に注意が必要です。
性能比較表を参考にしながら、自分の走らせるコースやバッテリーの種類に合わせて最適なモーターを選びましょう。
公式大会で使用可能なモーターとNGとなるモーターの種類を知ること
タミヤが主催する公式大会(ジャパンカップなど)では、使用できるモーターに制限があります。この規制(レギュレーション)を知っておくことは、大会参加を考えている方にとって非常に重要です。
【公式大会で使用可能な片軸モーター】
- FA-130タイプノーマルモーター
- パワーダッシュモーター
- スプリントダッシュモーター
- ライトダッシュモーター
- ハイパーダッシュ3モーター
- トルクチューン2モーター
- レブチューン2モーター
- アトミックチューン2モーター
- ハイパーミニモーター(絶版品)
- レブチューンモーター(絶版品)
- トルクチューンモーター(絶版品)
- アトミックチューンモーター(絶版品)
- ハイパーダッシュ2モーター(絶版品)
【公式大会で使用NGの片軸モーター】
- ウルトラダッシュモーター
- プラズマダッシュモーター
- ハイパーダッシュモーター(絶版品)
- マッハダッシュモーター(絶版品)
- ジェットダッシュモーター(絶版品)
- タッチダッシュモーター(絶版品)
- ZENチューンモーター(絶版品)
- ターボダッシュモーター(絶版品)
独自調査の結果、公式大会で使用できないモーターは、あまりにもスピードが速すぎるためコースアウトのリスクが高く、また他のレーサーとの公平性を保つために制限されていると考えられます。例えば、プラズマダッシュモーターは最高峰の性能を誇りますが、その分コントロールが難しく初心者には扱いづらいモーターです。
また、タミヤ以外のメーカーが製造したモーターも公式大会では使用できません。そのため、公式大会への参加を目指している方は、必ずタミヤ製の使用可能モーターを選ぶようにしましょう。
公式大会のレギュレーションは変更される可能性もあるため、参加前には必ず最新の公式ルールを確認することをおすすめします。ルールを守ることで、フェアなレース環境が保たれ、より多くの人がミニ四駆レースを楽しめるようになります。
ミニ四駆モーターは形状によってシャーシとの互換性が異なる点に注意
前述したように、ミニ四駆のモーターには片軸と両軸の2種類がありますが、これらはシャーシによって使い分ける必要があります。形状の違いによる互換性について、より詳しく見ていきましょう。
【片軸モーター対応シャーシ】
- VS(ビクトリーソニック)シャーシ
- VZ(ビクトリーマグナム)シャーシ
- AR(エアロ)シャーシ
- TYPE-1〜5シャーシ
- FM系シャーシ
- ZERO系シャーシ
- TZ系シャーシ
- その他、MSとMA以外のほとんどのシャーシ
【両軸モーター対応シャーシ】
- MS(ミッドシップ)シャーシ
- MA(ミッドシップAR)シャーシ
ミニ四駆PROシリーズのマシンは基本的にMS、MAシャーシを採用しているため、これらのマシンには両軸モーターを使用します。両軸モーターはダブルシャフトモーターとも呼ばれ、前輪と後輪にダイレクトに回転を伝えることができる点が特徴です。
片軸モーターを両軸対応シャーシに取り付けたり、その逆を行ったりすることはできません。互換性がないため、シャーシに合ったモーターを選ぶことが重要です。
さらに、モーターによってはシャフトの直径などわずかな差異がある場合もあります。特に旧式のシャーシや絶版のモーターを使用する場合は、きちんと装着できるか事前に確認することをおすすめします。
例えば、MAシャーシを使っている場合は、「レブチューン2モーターPRO」や「トルクチューン2モーターPRO」など、名前に「PRO」と付くモーターを選ぶようにしましょう。これらはすべて両軸モーターです。
モーターを購入する際は、自分のシャーシとの互換性をしっかり確認することで、後悔のない選択ができます。
モーターの種類によって電池との相性も変わるポイントを理解する
ミニ四駆のモーターは種類によって消費電流(必要な電気の量)が異なります。この消費電流の違いによって、どの電池と組み合わせるのが最適かが変わってきます。
【アルカリ電池との相性が良いモーター】
- FA-130タイプノーマルモーター
- トルクチューン2モーター
- レブチューン2モーター
- アトミックチューン2モーター
- ハイパーミニモーター
- ライトダッシュモーター
- ハイパーダッシュ3モーター
【ニッケル水素電池との相性が良いモーター】
- 全てのモーター(特に以下は充電池がおすすめ)
- パワーダッシュモーター
- スプリントダッシュモーター
- ハイパーダッシュPROモーター
- マッハダッシュPROモーター
- ウルトラダッシュモーター
- プラズマダッシュモーター
独自調査の結果、消費電流が2A以下のモーターはアルカリ電池でも十分な性能を発揮できます。しかし、パワーダッシュやスプリントダッシュなど消費電流が大きいモーターは、アルカリ電池では本来の性能を引き出せません。これらのモーターを使用する場合は、放電能力に優れたニッケル水素電池がおすすめです。
例えば、プラズマダッシュモーターの消費電流は4.1〜5.2Aとかなり大きいため、アルカリ電池では電力供給が追いつかず、スピードが出ないばかりか、電池の寿命も極端に短くなってしまいます。
また、ニッケル水素電池は繰り返し使用できるため、長期的にはコスト面でもメリットがあります。特に頻繁にミニ四駆を走らせる方や、高性能モーターを使用する方は、ニッケル水素電池と専用の充電器への投資を検討してみるとよいでしょう。
ただし、ニッケル水素電池には自己放電という弱点があり、使用しないでおくと徐々に電力が失われていきます。レース当日にはしっかり充電してから使用することを忘れないようにしましょう。
ミニ四駆モーターの消費電流の違いは性能に大きく影響する
消費電流は単にバッテリー選びだけでなく、モーター自体の特性にも大きく関わる重要な要素です。消費電流とモーターの性能には密接な関係があり、その理解がミニ四駆の性能向上につながります。
DCモーター(ミニ四駆のモーターもこれに含まれる)には、回転数、トルク、電流の間に一定の関係性があります。一般的に、トルクが大きくなると回転数が低下し、電流値が上がります。逆に、回転数が高くなるとトルクと電流値が低下する傾向があります。
しかし、ミニ四駆の高性能モーターは、この法則を超えて高トルクと高回転を両立させようとしているため、消費電流が大きくなっています。例えば、パワーダッシュモーターは高トルク型ですが消費電流が2.5〜3.3Aと大きく、スプリントダッシュモーターは高回転型ですが消費電流は2.8〜3.8Aとさらに大きくなっています。
消費電流が大きいモーターには以下のような特徴があります:
- 高性能だが電池の消耗が早い
- ニッケル水素電池などの高出力バッテリーが必須
- レース中にパワーダウンする可能性がある
- モーター自体が発熱しやすい
一方、消費電流が小さいモーターには以下のような特徴があります:
- 性能は控えめだがバッテリー持ちが良い
- アルカリ電池でも安定して動作する
- 長時間のレースに向いている
- 発熱が少なく安定性が高い
自分のレーススタイルや参加するレースの特性に合わせて、消費電流を考慮したモーター選びをすることが重要です。例えば、耐久レースを重視するなら消費電流の少ないトルクチューン2モーターが、短距離の速さ勝負なら消費電流は大きくても高性能なスプリントダッシュモーターが適しているかもしれません。
モーターの消費電流は、カタログスペックだけでなく、実際の使用条件(負荷状態)によっても変化します。特に坂道やコーナーなどではモーターに大きな負荷がかかり、消費電流が増加することを理解しておきましょう。
ミニ四駆のモーターの種類別おすすめと選び方
- 初心者におすすめのミニ四駆モーターはアトミックチューン2モーター
- 中級者におすすめのミニ四駆モーターはライトダッシュモーター
- 上級者におすすめのミニ四駆モーターはハイパーダッシュ3モーター
- ミニ四駆の最速モーターはプラズマダッシュだがコースアウトに注意
- コースの特性に合わせたミニ四駆モーターの選び方が勝利のカギ
- モーターの慣らし方でミニ四駆の性能は劇的に向上する
- まとめ:ミニ四駆のモーターの種類を理解して最適な一台を作ろう
初心者におすすめのミニ四駆モーターはアトミックチューン2モーター
ミニ四駆を始めたばかりの初心者の方には、アトミックチューン2モーターがおすすめです。このモーターは黒いエンドベル(モーター後部のプラスチック部分)が特徴で、バランス型のモーターに分類されます。
アトミックチューン2モーターがおすすめの理由は以下の通りです:
- スピードとパワーのバランスが良く、多様なコースに対応できる
- 消費電流が1.8〜2.2Aと比較的控えめで、アルカリ電池でも使いやすい
- ノーマルモーターよりも明らかに性能が高いため、改造の楽しさを体験できる
- 価格が420円前後と比較的リーズナブル
- 公式大会でも使用可能
独自調査の結果、アトミックチューン2モーターの回転数は12,700〜14,900r/min、推奨負荷トルクは1.5〜1.8mN・mとなっています。ノーマルモーターと比べると、回転数で約1.2倍、トルクで約1.5倍の性能向上が見られます。
初心者がいきなり高性能なモーターを使うと、スピードコントロールが難しくコースアウトを頻繁に起こしてしまう可能性があります。アトミックチューン2モーターは適度な性能向上を実現しつつ、扱いやすさも兼ね備えているため、ミニ四駆の基本的な走りを学ぶのに最適です。
両軸モーター(PRO)を使用する場合は、アトミックチューン2モーターPROを選びましょう。こちらも同様にバランス型で初心者に扱いやすい特性を持っています。
まずはこのモーターで基本的なセッティングを学び、ローラーなどのパーツでコースアウト対策を試しながら、自分のマシンに最適なセッティングを見つけていくことが上達への近道です。初心者から中級者へステップアップする過程で、ミニ四駆の奥深さと楽しさを実感できるでしょう。
中級者におすすめのミニ四駆モーターはライトダッシュモーター
アトミックチューン2モーターでの走行に慣れてきて、もう少し速いモーターを試してみたいと思ったら、次のステップとしておすすめなのがライトダッシュモーターです。黄色いエンドベルが特徴的なこのモーターは、中級者にぴったりの性能を持っています。
ライトダッシュモーターがおすすめの理由は以下の通りです:
- アトミックチューン2モーターのスピードとパワーを1段階上げた性能を持つ
- 癖がなく扱いやすいバランス型モーター
- 公式大会でも優勝実績があるほどのポテンシャルの高さ
- 消費電流は1.5〜2.2Aで、アルカリ電池でも比較的性能を発揮できる
- 公式大会で使用可能
独自調査の結果、ライトダッシュモーターの回転数は14,600〜17,800r/min、推奨負荷トルクは1.3〜1.9mN・mとなっており、アトミックチューン2モーターに比べて特に回転数が向上しています。これにより、直線での速度が上がり、より競争力のあるマシンに仕上がります。
ライトダッシュモーターは、珍しく先に両軸版(ライトダッシュモーターPRO)が発売された後に片軸仕様として登場したという経歴を持ちます。性能的な立ち位置としては、トルクチューン2モーターとハイパーダッシュ3モーターの中間に位置し、ハイパーダッシュ3では速すぎるが、トルクチューン2では遅すぎると感じる場面での選択肢として価値があります。
実際に2017年のミニ四駆ジャパンカップではライトダッシュモーターで優勝した人もいるほど、実戦でも十分な性能を発揮します。このモーターを使いこなせるようになると、上級者への道が開けてくるでしょう。
両軸モーター(PRO)を使用する場合は、ライトダッシュモーターPROを選択しましょう。どちらも同様の特性を持ち、中級者にぴったりのモーターです。
ライトダッシュモーターは、適切なセッティングと組み合わせることで、その真価を発揮します。ステイやローラー配置などのセッティングを工夫して、このモーターのポテンシャルを最大限に引き出してみましょう。
上級者におすすめのミニ四駆モーターはハイパーダッシュ3モーター
ライトダッシュモーターの性能にも物足りなさを感じ始めた上級者には、ハイパーダッシュ3モーターがおすすめです。赤いエンドベルが特徴的なこのモーターは、公式大会で使用可能なモーターの中でも高い性能を誇ります。
ハイパーダッシュ3モーターがおすすめの理由は以下の通りです:
- ライトダッシュモーターのスピードとパワーをさらに1段階上げた性能
- ミニ四駆ジャパンカップの優勝者も多数使用している実績あるモーター
- 回転数とトルクのバランスが良く、様々なコースで活躍できる万能性
- カーボンブラシを採用しており、耐久性も向上
- 公式大会で使用可能
独自調査の結果、ハイパーダッシュ3モーターの回転数は17,200〜21,200r/min、推奨負荷トルクは1.4〜1.9mN・mとなっており、特に回転数がライトダッシュモーターから大幅に向上しています。消費電流は1.6〜3.0Aとやや大きめなので、性能を最大限に引き出すためにはニッケル水素電池の使用をおすすめします。
ハイパーダッシュ3モーターは、前作「ハイパーダッシュ2モーター」と公称スペックは同じですが、金属ブラシからカーボンブラシに変更されたことで耐久性が向上し、両軸のハイパーダッシュPROと外見も性能も統一されました。慣らし次第では30,000rpm近くまで回ることもあり、スペック以上の性能を発揮する可能性もあります。
2018年のミニ四駆ジャパンカップでは、チャンピオン決定戦のジュニアクラスや複数の東京大会でハイパーダッシュモーターPRO(両軸版)を使用した選手が優勝しており、その実力は実証済みです。
このモーターの速度でコースアウトしないセッティングができれば、ミニ四駆ジャパンカップでの優勝も視野に入ってくるでしょう。上級者として、モーターだけでなくマシン全体のバランスを考えたセッティングが求められます。
両軸モーター(PRO)を使用する場合は、同等のハイパーダッシュモーターPROを選択しましょう。どちらも上級者向けの高性能モーターとして定評があります。
ミニ四駆の最速モーターはプラズマダッシュだがコースアウトに注意
公式大会の制限を気にせず、純粋に最速のモーターを求めるなら、プラズマダッシュモーターが最高峰の選択肢となります。このモーターは特殊な形状のエンドベルと黒い本体が特徴で、タミヤ製FA-130型モーターの中で最高のスペックを持ちます。
プラズマダッシュモーターの特徴は以下の通りです:
- 回転数25,000〜28,000r/minという驚異的な高回転
- 推奨負荷トルクも1.4〜1.9mN・mと十分な値
- 放熱用のスリットが入ったエンドベルと8個のエアスクープによる冷却機構
- 取り外し可能なブラシホルダーでメンテナンス性も向上
- 発売当時は880円と高価格だったが、その分の価値がある最高峰モデル
ただし、このモーターは公式大会では使用禁止となっているほか、以下のような注意点もあります:
- 消費電流が4.1〜5.2Aと非常に大きく、ニッケル水素電池が必須
- 非常に速いため、セッティングが不十分だとすぐにコースアウトする
- 発熱量が大きいため、連続使用には注意が必要
- 現在は絶版となっており、入手が困難
「コースアウトしてもいいから最速を目指したい」という方にはぴったりのモーターですが、その真の性能を引き出すには高度なセッティング技術が必要です。初心者や中級者には扱いが難しいため、ある程度の経験を積んでからチャレンジすることをおすすめします。
現在はプラズマダッシュモーターが絶版となっているため、最速を目指すなら公式禁止スペックとしては唯一残っているウルトラダッシュモーター(回転数24,000〜27,500r/min、消費電流4.0〜5.0A)が選択肢となります。
また、両軸モーター(PRO)を使用する場合、プラズマダッシュに相当するモデルは残念ながら存在しません。その代わりにマッハダッシュモーターPRO(回転数20,000〜24,500r/min)が両軸モーターの中では最速モデルとなっています。
最速モーターの魅力は圧倒的なスピードにありますが、それを活かすためには総合的なマシンセッティングの知識と経験が必要です。チャレンジする際は、徐々にスピードに慣れていくアプローチをおすすめします。
コースの特性に合わせたミニ四駆モーターの選び方が勝利のカギ
ミニ四駆レースで勝利するためには、単に「最速のモーター」を選ぶだけでは不十分です。コースの特性に合わせた適切なモーター選びが、勝利への重要なカギとなります。
【直線が多いコースに適したモーター】
- スプリントダッシュモーター(回転数が非常に高く、直線での加速力に優れる)
- レブチューン2モーター(小径タイヤとの組み合わせで直線に強い)
- マッハダッシュモーターPRO(両軸モーターで最速)
直線の多いコースでは、とにかくトップスピードを重視するのが基本戦略です。これらのモーターはモーターの回転数(RPM)が高いため、長い直線で差をつけることができます。特に「小径タイヤ + スピード型モーター + 3.5:1などの低めのギア比」という組み合わせは、ハイスピードコースで力を発揮します。
【カーブや坂道が多いコースに適したモーター】
- トルクチューン2モーター(トルクが高く、カーブや上り坂でも安定した走行が可能)
- パワーダッシュモーター(高トルクで坂道に強い)
- トルクチューン2モーターPRO(両軸向けの高トルクモデル)
テクニカルなコースでは、トップスピードよりもトルク(パワー)が重要になります。これらのモーターは推奨負荷トルクが高いため、上り坂でも力強い走りを実現できます。「大径タイヤ + パワー型モーター + 5:1以上の高めのギア比」という組み合わせが、テクニカルコースでは有利になります。
【バランスの取れたコースに適したモーター】
- ライトダッシュモーター(スピードとパワーのバランスが良い)
- ハイパーダッシュ3モーター(高スペックながらバランスが取れている)
- アトミックチューン2モーター(初心者でも扱いやすいバランス型)
直線と曲線、平坦と起伏がバランスよく配置されたコースでは、特定の性能に偏ったモーターよりも、総合力のあるバランス型モーターが適しています。これらのモーターは様々な状況に対応できる柔軟性を持っています。
また、モーター選びだけでなく、ギア比の調整も重要です。高いギア比(例:5:1、8.75:1)はパワーを重視し、低いギア比(例:3.5:1)はトップスピードを重視します。モーターの特性と組み合わせて、コースに最適なギア比を選ぶことも勝利への鍵です。
事前にコースを下見できる場合は、コースレイアウトを確認し、どのような特性(直線が多いか、カーブが多いか、坂道があるかなど)があるかを分析してから、最適なモーターを選びましょう。場合によっては複数のモーターを用意して、コース条件に合わせて使い分けることも戦略の一つです。
モーターの慣らし方でミニ四駆の性能は劇的に向上する
ミニ四駆のモーターは、購入してすぐに使うよりも、しっかりと「慣らし」を行うことで性能が大幅に向上します。モーター慣らしとは、モーターの内部部品を最適な状態に調整する作業で、これによって回転数が上がり、消費電流が安定化します。
【モーター慣らしが必要な理由】
モーターには主に以下の部品があり、これらが慣らしによって最適化されます:
- ブラシ:電気を供給する部品で、コミュテーターと接触する
- コミュテーター:ブラシから電気を受け取り、コイルに流す銅製の部品
- 軸受け:シャフトを支える部分で、回転の滑らかさに影響する
これらの部品は新品時には表面が粗く、接触面積が小さいため、電流の流れが不安定です。慣らしによってブラシとコミュテーターの接触面が馴染み、電流が効率よく流れるようになります。
【ブラシの種類による慣らし方の違い】
ミニ四駆のモーターには、銅ブラシとカーボンブラシの2種類があります:
- 銅ブラシを使用するモーター(ノーマル、トルクチューン2、レブチューン2、アトミックチューン2、ライトダッシュなど) → 慣らし効果が大きく、適切な慣らしでモータースペック以上の性能が出ることも
- カーボンブラシを使用するモーター(ハイパーダッシュ3、パワーダッシュ、スプリントダッシュなど) → 初期性能が高く、慣らし効果はやや小さいが、耐久性に優れている
【基本的なモーター慣らし方法】
- 低電圧での慣らし(0.5〜1.0V)
- 正転20分→休憩5分→反転20分を3セット程度
- 低電圧でブラシとコミュテーターを少しずつ馴染ませる
- 中電圧での慣らし(1.6〜3.5V)
- 正転10分→休憩5分→反転10分を5セット程度
- パルスブレークイン(電圧を変動させる)も効果的
- 慣らし中のメンテナンス
- 休息時間にコミュテーターオイルを注油
- 回転が鈍くなったらパーツクリーナーで洗浄
適切に慣らしを行うことで、マッハダッシュモーターPROなら34,500〜39,200rpm、パワーダッシュモーターなら34,500rpm前後まで回転数が向上することもあります。これはカタログ値を大きく上回る数値です。
モーター慣らし機としては、イーグルのモータートレーナー(約4,000円)やGフォースのミニブレークインシステム+R、シャインテクニカの7miniGなど様々な製品があります。専用の慣らし機がない場合は、安定化電源や可変抵抗器を使った自作キットなども選択肢となりますが、安全面に十分注意しましょう。
モーター慣らしは地道な作業ですが、その効果は絶大です。特に公式大会で使用可能なモーターの性能を最大限に引き出すためには、欠かせない工程と言えるでしょう。
まとめ:ミニ四駆のモーターの種類を理解して最適な一台を作ろう
最後に記事のポイントをまとめます。
- ミニ四駆のモーターは片軸モーターと両軸モーターの2種類に大別される
- 片軸モーターは通常のミニ四駆シャーシ用、両軸モーターはMSやMAシャーシなどのPROシリーズ用
- モーターは性能によってスピード型、パワー型、バランス型の3つに分類できる
- 公式大会で使用可能なモーターとNGになるモーターがあるので事前に確認が必要
- 初心者にはアトミックチューン2モーター、中級者にはライトダッシュモーター、上級者にはハイパーダッシュ3モーターがおすすめ
- 最速のモーターはプラズマダッシュ(絶版)とウルトラダッシュだが、公式大会では使用できない
- 直線の多いコースにはスピード型、カーブや坂道の多いコースにはパワー型のモーターが適している
- バランスの取れたコースにはライトダッシュモーターなどのバランス型が適している
- モーターの消費電流が大きいほど高性能だが、それに見合った電池(ニッケル水素など)が必要
- モーター慣らしを行うことで、モーターの性能は劇的に向上する
- 銅ブラシのモーターは慣らし効果が大きく、カーボンブラシのモーターは初期性能が高い
- モーターだけでなく、ギア比やタイヤサイズなど総合的なセッティングが重要
- 自分の技量や目的に合ったモーターを選び、適切にセッティングすることで最高の走りを実現できる