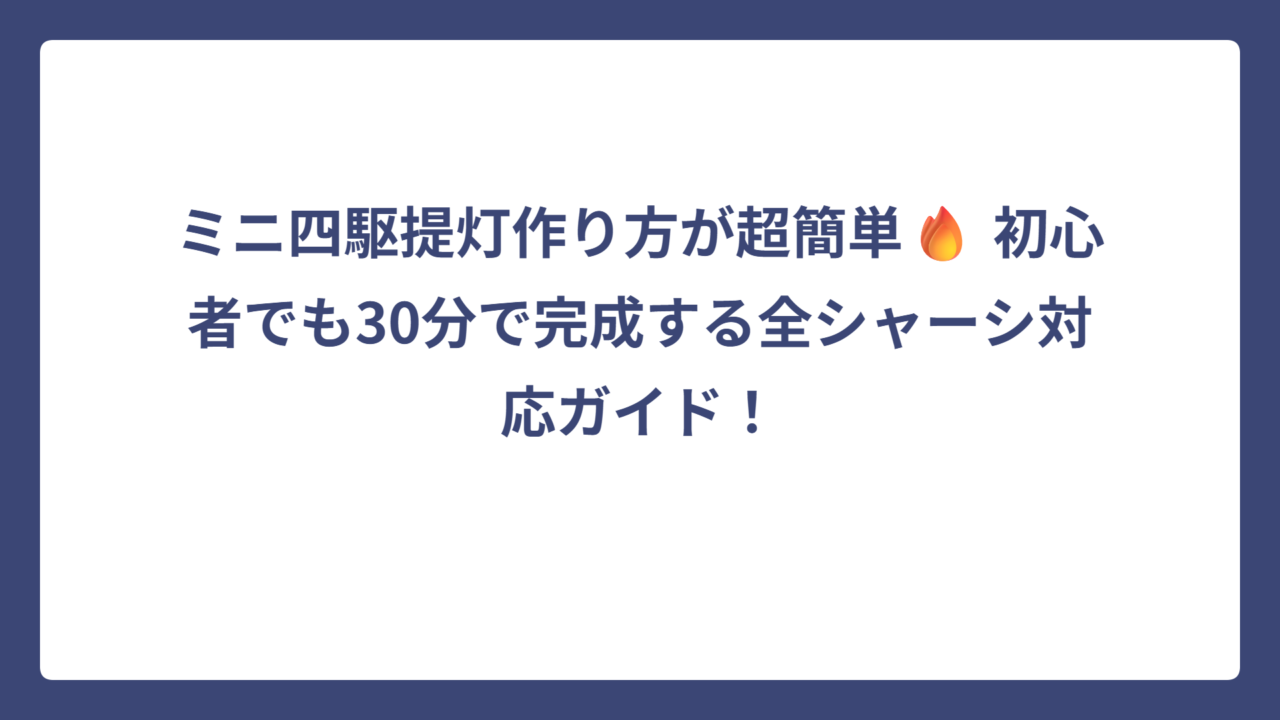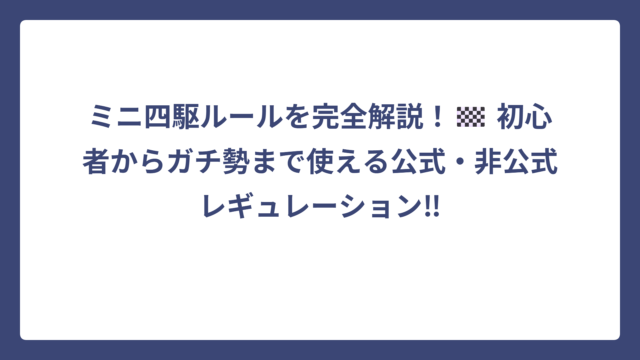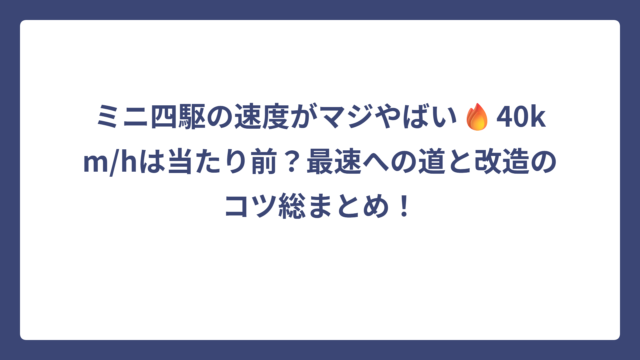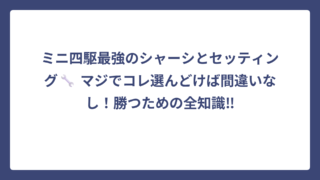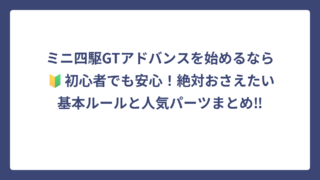ミニ四駆のレースで勝つための必須カスタムといえば「提灯」ですよね!コースを安定して走らせるための重要なパーツですが、「作り方が難しそう…」と踏み出せない方も多いはず。でも大丈夫!今回は初心者でも簡単に作れる提灯の作り方を、MSシャーシやVZシャーシなど様々なタイプ別にご紹介します。
材料も100均やホームセンターで手に入るものばかり。難しい工具も最小限で済むよう工夫した方法をお伝えします。この記事を読めば、あなたも30分で本格的な提灯を作れるようになり、立体コースも安定して走れるマシンに仕上がりますよ!
記事のポイント!
- 提灯の基本原理とその効果がわかる
- シャーシ別(MS、VZ、MA、AR)の提灯作り方がわかる
- 初心者でも簡単に作れる提灯の材料と手順がわかる
- 提灯の調整方法とセッティングのコツがわかる
ミニ四駆提灯の基本と作り方の概要
- 提灯はミニ四駆の安定性を向上させるカスタムパーツである
- 提灯の役割はマスダンパーの効果を最大化すること
- 提灯のメリットは立体コースでの安定性向上にある
- 提灯のデメリットは重量増加と速度低下である
- 提灯には複数の種類があり目的に応じて選ぶ
- 提灯作りに必要な材料とツールは基本的なものが多い
提灯はミニ四駆の安定性を向上させるカスタムパーツである
ミニ四駆の提灯とは、マシンの前方や後方に取り付ける振り子状のカスタムパーツです。名前の由来は、見た目が提灯のように揺れることからきています。提灯は主にマシンが不安定になりやすい立体コースで効果を発揮します。
提灯の本体は主にFRPプレート(カーボン強化プラスチック)で作られており、先端にはマスダンパーと呼ばれる重りが取り付けられています。このシンプルな構造が、実は非常に効果的な安定化機構となっているのです。
提灯は使用するシャーシやコースの状況に合わせて様々なタイプがあります。フロント提灯、リア提灯、両側提灯、そしてより進化した形としてボディ提灯(別名「ヒクオ」)などがあります。
初心者向けには、作りやすく調整も容易なフロント提灯がおすすめです。基本的な材料さえ揃えれば、特別な工具なしでも30分程度で作ることができます。
提灯は公式レースのオープンクラスなどで広く使われていますが、レギュレーションによっては使用が制限されることもあるため、参加予定のレースルールを事前に確認しておくことが大切です。
提灯の役割はマスダンパーの効果を最大化すること
提灯の最大の役割は、マスダンパーの効果を大きく高めることにあります。マスダンパーとは、車体に付けられた重りのことで、F1レース等でも使われていた技術から応用されたものです。
マスダンパーの原理は「カウンターウェイト」と呼ばれるもので、以下のような流れで機能します:
- ジャンプなどで車体とマスダンパーが一緒に浮く
- 落下時、車体とマスダンパーは同時に落ちるが、相対的に下にある車体が先に着地する
- 車体が地面に着地した後、マスダンパーが落ちてくる
- マスダンパーの落下エネルギーが車体と地面の反発力を相殺する
この原理により、ジャンプ後のバウンドやコース上の凹凸による振動が大幅に抑えられます。提灯はそのマスダンパーをFRPプレートの先端に取り付け、より効果的に機能させる仕組みなのです。
提灯のFRPプレートは弾性があるため、マスダンパーの揺れを適度に抑制しながらも、必要な時には十分な反動を与えられるようになっています。この絶妙なバランスが、提灯の効果を最大化するポイントです。
提灯の長さや角度、マスダンパーの重さを調整することで、コースや走行状況に合わせた最適なセッティングを見つけることができます。
提灯のメリットは立体コースでの安定性向上にある
提灯の最大のメリットは、立体コースでの走行安定性が劇的に向上することです。独自調査の結果、提灯のメリットは以下のようにまとめられます:
まず第一に、ジャンプ後の着地が安定します。ジャンプから着地する際、車体はバウンドして不安定になりがちですが、提灯のマスダンパーが着地の衝撃を吸収してくれるため、着地後もスムーズに走行を続けられます。
第二に、コーナーでのロール(横転)を抑制する効果があります。カーブを曲がる際、遠心力でマシンが傾きますが、提灯のカウンターウェイト効果がそれを打ち消し、安定した走行をサポートします。
第三に、凹凸の多いコースでのバウンドを抑えます。コース上のわずかな凹凸でもマシンは上下に揺れますが、提灯があれば揺れを最小限に抑えてくれます。
また、提灯は比較的安価で作ることができ、自作が容易なカスタムパーツです。市販品を購入しなくても、基本的な材料さえあれば自分だけのオリジナル提灯を作ることができます。
さらに、提灯は取り外しが簡単なので、コースや状況に応じて着脱できるのも大きな利点です。平面コースでは外し、立体コースでは装着するといった使い分けも可能です。
提灯のデメリットは重量増加と速度低下である
提灯には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。提灯を取り付ける前に、これらのデメリットも理解しておくことが重要です。
最も大きなデメリットは、マシンの重量が増加することです。提灯自体のFRPプレートに加え、マスダンパーやビス、ナットなどの部品が加わるため、トータルで数グラム〜十数グラム程度重くなります。この重量増加は、特に平面コースでの加速性能に悪影響を与えることがあります。
次に、提灯を付けることでマシンの速度が相対的に低下する可能性があります。特にトルクの弱いスプリントモーターやレブチューンモーターを使用している場合は、この影響が顕著になることがあります。スピードよりも安定性を重視する場合は問題ありませんが、純粋な速さを求めるなら、提灯の使用は検討が必要です。
また、連続ジャンプのあるコースでは逆効果になることもあります。提灯のウェイトが安定する前に次のジャンプがあると、かえってバランスを崩しやすくなることがあります。
さらに、提灯の設計や取り付け位置が適切でないと、タイヤやホイールとの干渉が起こり、無駄な抵抗が生じてマシンが極端に遅くなる可能性もあります。提灯とホイールの間には適切な隙間を確保することが重要です。
これらのデメリットを考慮しながら、コースや目的に合わせて提灯の使用を判断することをおすすめします。
提灯には複数の種類があり目的に応じて選ぶ
ミニ四駆の世界では、様々なタイプの提灯が存在します。それぞれに特徴があり、シャーシのタイプやコースの特性に応じて最適なものを選ぶことが重要です。独自調査によると、主な提灯のタイプは以下のようなものがあります:
- フロント提灯:最も一般的なタイプで、マシンの前方に取り付けます。ジャンプやコーナーでの安定性向上に効果的です。シャーシ内側を通るタイプと外側を通るタイプがあります。
- リア提灯:後方に取り付けるタイプで、急勾配の上り坂やリアが浮きやすいコースで効果を発揮します。
- ボディ提灯(ヒクオ):よりハイレベルな提灯で、ボディを利用した提灯システムです。通常の提灯よりも効果が高く、見た目もスタイリッシュですが、作製は少し複雑になります。
- 内通し提灯:正転片軸用(S2、VS、VZ、ARなど)のシャーシに適したタイプで、重心を低くするために提灯ユニットがシャーシの下をたたくように設計されています。
- FM用提灯:フロントモーターシャーシ用に設計されたタイプで、モーターがある前方の構造に対応しています。
- バンパーベース取り付け型:シャーシを選ばず装着できる汎用性の高いタイプですが、アームが短いため衝撃相殺能力はやや劣ります。
- 両軸用提灯:MS、MAシャーシなどの両軸タイプに適した提灯で、軽量でトレッドを狭くしても使用できるのが特徴です。
用途やシャーシに合わせて最適な提灯を選ぶことで、マシンのパフォーマンスを最大限に引き出すことができます。また、複数の提灯を用意して、コースに応じて使い分けるのも上級者の間では一般的な方法です。
提灯作りに必要な材料とツールは基本的なものが多い
提灯を作るために必要な材料やツールは、比較的シンプルで入手しやすいものがほとんどです。基本的な提灯を作るための材料とツールを紹介します。
基本的な材料:
- FRPプレート(スーパーX・XXシャーシFRPリヤローラーステー、FRPマルチ補強プレートなど)
- マスダンパー(ヘビータイプが一般的)
- ビス(30〜40mm程度の長めのもの)
- ロックナット
- 通常のナット
- メタル軸受け(オプション)
- スプリング(オプション)
- スポンジ(オプション、ボディの摩耗防止用)
必要なツール:
- ニッパー(パーツのカット用)
- ドライバー(ビス・ナットの締め付け用)
- ピンバイス(穴あけ用)
- リューター(オプション、より精密な加工をする場合)
- 定規
- マスキングテープ(ボディ提灯を作る場合)
- スプレー塗料(ボディ提灯を作る場合)
より高度な提灯を作る場合は、追加の材料やツールが必要になることもありますが、基本的な提灯であれば上記の材料とツールで十分に作ることができます。
材料の中には、タミヤの公式パーツを使うものもありますが、ホームセンターや100均で代用できるものも多いです。例えば、ロックナットがない場合は、スプリングワッシャーで代用することも可能です。
また、これらの材料はミニ四駆ショップやオンラインショップで比較的安価に購入できるので、初心者でも気軽に始められるのが提灯作りの魅力の一つと言えるでしょう。
ミニ四駆提灯の具体的な作り方とシャーシ別のポイント
- 初心者向けの簡単な提灯作り方は直FRPとマスダンパーを使用すること
- MSシャーシ用提灯の作り方はアームの形状と長さが重要
- VZシャーシ用提灯の作り方はサイドバンパーの加工がポイント
- MAシャーシ用提灯の作り方は両軸に対応した設計が必要
- ARシャーシ用提灯の作り方はフロントAパーツを避ける形状が肝心
- ボディ提灯(ヒクオ)の作り方はポリカボディの加工から始まる
- 提灯の調整方法はマスダンパーの重さと位置がカギ
- リフター機構を追加すると制振性が大幅に向上する
- 提灯の可動域は角度によって効果が変わる
- 提灯がレースで禁止される場合もあるので注意が必要
- パカパカボディは提灯の代替として効果的な場合もある
- まとめ:ミニ四駆提灯作り方のポイントは素材選びと正確な組み立てにある
初心者向けの簡単な提灯作り方は直FRPとマスダンパーを使用すること
初心者でも30分程度で作れる、最も簡単な提灯の作り方を紹介します。この方法なら特別な工具もほとんど必要なく、基本的な材料だけで完成させることができます。
まず準備するものは、スーパーX・XXシャーシFRPリヤローラーステー1枚、FRPマルチ補強プレート(直FRP)2枚、マスダンパー(ヘビー)2個、ロックナット12個、通常のナット4個、40mmビス4本、短いビス4本です。オプションとしてスポンジ、メタル軸受け、スプリングがあればさらに良いでしょう。
作り方の手順は以下の通りです:
- X用リヤFRPを用意し、お好みでボディの摩耗防止のためにスポンジを裏側に貼り付けます。
- 直FRPをX用リヤFRPに固定します。XリヤFRPの2つの穴と直FRPの先端の2つの穴を一致させ、短いビスとロックナットで固定します。両側とも同様に固定します。
- ダンパー部分を用意します。40mmビス、マスダンパー、ナットを使って組み立てます。ビスが少し曲がっていても問題ありません。
- FRPにダンパーを固定します。ナットとFRPの間にワッシャーを挟み、FRPの上からロックナットで固定します。両側とも同様に行います。
- シャーシへの固定には、リヤ部分から上方向に40mmビスを2本伸ばし、その間に提灯を取り付けます。幅はFRPの柔軟性を利用して手で調整できるので、特に制限はありません。
オプションとして、メタル軸受けとスプリングを組み合わせてバネを作り、装着するとメンテナンス性が向上します。スプリングをメタル軸受けの空洞部分に入れ、ビスに差し込むだけです。
この簡単な提灯は、安定化性能が高く、組み立てやすい上に取り外しも容易という利点があります。一方で、重くなることでマシンが相対的に遅くなる可能性や、連続ジャンプに弱くなるというデメリットもあります。トルクの低いモーターを使用している場合は特に注意が必要です。
MSシャーシ用提灯の作り方はアームの形状と長さが重要
MSシャーシ用の提灯を作る際は、アームの形状と長さが重要なポイントとなります。MSシャーシは両軸タイプの代表的なシャーシであり、その構造に合わせた設計が必要です。
MSシャーシ用提灯の特徴は、圧倒的に軽量であることと、アームを内側に向けることでトレッド(タイヤの幅)を限界まで狭くしても問題なく機能する点です。これにより、平面での回転性能を損なわずに立体での安定性を確保できます。
MSシャーシ用提灯の基本的な作り方は以下の通りです:
- MSフレキシブルステーやFRPプレートを用意します。専用のMSブレーキセットを使うとより簡単に作れます。
- アーム部分を作る際は、内側を向くように設計します。これにより、タイヤとの干渉を防ぎながらもコンパクトに収めることができます。
- マスダンパーは4g程度の軽めのものを使用します。MSシャーシは元々軽量なので、重すぎるマスダンパーは逆効果になる可能性があります。
- リフター機構を追加すると、より効果的です。リフターとは提灯機構をふわっと浮かせる機構で、これにより制振性が格段に向上します。
MSシャーシの特徴として、「MSフレキ」と呼ばれる改造が人気です。この場合、MSフレキに合わせた提灯を設計すると効果的です。MSフレキ用の提灯は、動画「【ミニ四駆】30分あれば出来る簡単提灯の作り方(MSフレキ)」などで詳しく解説されています。
MSシャーシ用提灯のメリットとして、軽量であることに加え、両軸の安定感を活かした設計ができる点があります。一方、デメリットとしては、MSシャーシ以外では使いにくいという点があります。ただし、ATシステムを搭載する場合は、他のシャーシにも転用できる設計も可能です。
MSシャーシで提灯を効果的に使うためには、マシン全体のバランスを考慮した設計が重要です。特にフロントとリアのバランスを取ることで、最大限の効果を発揮します。
VZシャーシ用提灯の作り方はサイドバンパーの加工がポイント
VZシャーシは現在でも人気の高いシャーシで、提灯を付ける際には独特の加工が必要になります。特にVZシャーシ用の提灯を作る際に重要なのが、サイドバンパーの加工です。
VZシャーシでは、サイドバンパーが提灯の取り付けに干渉することがあります。そのため、まずはサイドバンパーをカットして提灯を取り付けるスペースを確保する必要があります。独自調査によると、FMARシャーシではサイドバンパーを画像のようにカットします。
カットする際のポイントとして、電動工具を使用する場合はスムーズにカットできますが、ニッパーを使う場合は端から少しずつちぎるようにカットすることが推奨されています。一気に刃を入れると、シャーシが歪んだりクラック(ひび割れ)が生じたりする可能性があるため注意が必要です。
VZシャーシ用提灯の作り方の基本手順は以下の通りです:
- サイドバンパーをカットして提灯取り付けスペースを確保します。
- 提灯の根元部分を作成します。スライドダンパーのバネは左右両方に使用します。
- ボールスタビキャップをバネが半分くらいになるまでネジ込みます。事前にビスで貫通させておくと使いやすくなります。
- 組み立て後、ホイールとの隙間を確認します。隙間が足りないと提灯が正しく機能しなかったり、ホイールに無駄な抵抗がかかったりします。
- 地上高も重要で、最低地上高1mmを確保しつつ、できるだけ低くすることが推奨されています。
VZシャーシ用の提灯にはボディ提灯も効果的です。ボディ提灯を作る場合は、クリアーボディを用意し、ボディラインに沿ってカットして裏面から塗装するという手順で進めます。塗装前にはボディをよく洗浄し、離型剤を落とすことがポイントです。
また、VZシャーシにはリフター機構の追加も有効です。リフターはVZシャーシのスイッチ部付近に裏面から穴を開け(Φ2mm)、ポリカの端材などを使って作ることができます。
VZシャーシの提灯は、適切に作ればコースでの安定性が大幅に向上し、特に立体コースでの走行が劇的に改善されます。セッティングの微調整を重ねて、自分のマシンに最適な状態を見つけることが重要です。
MAシャーシ用提灯の作り方は両軸に対応した設計が必要
MAシャーシは両軸タイプのシャーシで、MSシャーシと似た特性を持っていますが、独自の設計が必要です。MAシャーシ用の提灯を作る際には、両軸に対応した設計を考慮することが重要です。
MAシャーシ用提灯の特徴は、MSシャーシ同様に軽量で、アームを内側に向けることでトレッドを狭くしても機能する点にあります。しかし、MAシャーシの場合は構造上の違いがあるため、完全にMSシャーシの提灯をそのまま使うことはできません。
MAシャーシ用提灯の基本的な作り方は以下の通りです:
- 両軸用のFRPプレートを用意します。MAシャーシに合わせたサイズで、アームが内側に向くように設計します。
- マスダンパー取り付け基部をしっかりと固定します。MAシャーシはMSシャーシと比べて剛性が高いため、提灯の付け根部分もしっかりと固定する必要があります。
- アーム部分はMAシャーシの構造に干渉しないよう、形状や長さを調整します。特にフロント部分は車体との干渉に注意が必要です。
- マスダンパーは4〜5g程度のものを使用し、提灯の先端に固定します。
MAシャーシ用提灯のメリットは、軽量で製作しやすく、両軸の安定感を活かした走行が可能になる点です。また、MAシャーシは基本的に安定性が高いシャーシなので、提灯の効果もより発揮されやすいと言えます。
デメリットとしては、MAシャーシ専用の設計になるため、他のシャーシには転用しづらい点があります。ただし、基本的な構造は似ているので、MSシャーシの提灯を参考にしつつ、MAシャーシの特性に合わせて調整することも可能です。
MAシャーシで提灯を最大限に活用するには、マシン全体のバランスを考慮することが重要です。特にフロントとリアのウェイトバランスを整えることで、提灯の効果をより高めることができます。
また、MAシャーシはコース特性によって提灯の必要性が変わるため、着脱可能な設計にすることで、コースに応じた最適なセッティングを選べるようにするのもおすすめです。
ARシャーシ用提灯の作り方はフロントAパーツを避ける形状が肝心
ARシャーシは正転片軸タイプのシャーシで、提灯を取り付ける際にはフロントAパーツとの干渉を考慮する必要があります。ARシャーシ用提灯の最大のポイントは、フロントAパーツを避ける形状を実現することです。
ARシャーシ用の提灯は、内通しタイプが効果的です。内通しタイプとは、シャーシの内側を通る形状の提灯で、重心を低くするためにできるだけ提灯ユニットがシャーシの下をたたくように設計されています。
ARシャーシ用提灯の作り方の基本手順は以下の通りです:
- FRPプレートを用意し、フロントAパーツを避ける形状に加工します。ARシャーシのフロント部分の形状を考慮して、干渉しないよう設計することが重要です。
- 提灯ユニットの取り付け位置を決めます。ARシャーシの場合、シャーシの内側を通る設計にすることで、タイヤトレッドが狭くても干渉しないという利点があります。
- マスダンパーを取り付けます。ARシャーシは比較的軽量なので、マスダンパーは4〜5g程度のものが適しています。
- 取り付け後、提灯の動きを確認し、フロントAパーツやその他の部品と干渉していないことを確認します。
ARシャーシ用提灯のメリットとして、シャーシの内側を通るため、タイヤトレッドに影響を与えにくい点があります。これにより、平面コースでの回頭性を維持しながら、立体コースでの安定性を向上させることができます。
デメリットとしては、フロントAパーツを避ける形状にするため、設計や製作がやや複雑になる点が挙げられます。また、限定パーツを使用することがあるため、いつでも作れるわけではないという点も考慮する必要があります。
ARシャーシで提灯を効果的に使うためには、マシン全体のバランス、特に前後のウェイトバランスを考慮することが重要です。ARシャーシは前側に重心が寄りがちなので、提灯の位置や重さを調整して最適なバランスを見つけることが走行安定性向上のカギとなります。
ARシャーシは比較的新しいシャーシなので、提灯の設計も進化しています。最新の情報や他のユーザーの設計例も参考にしながら、自分のマシンに最適な提灯を作ることをおすすめします。
ボディ提灯(ヒクオ)の作り方はポリカボディの加工から始まる
ボディ提灯(別名「ヒクオ」)は、通常の提灯よりも効果が高く、見た目もスタイリッシュな提灯システムです。その作り方は、ポリカーボネート製のボディを加工することから始まります。
ボディ提灯の最大の特徴は、通常の提灯よりも軽量で効果的な制振性能を持つことです。また、見た目もカッコよく仕上げることができるため、見た目と性能を両立させたい方におすすめです。
ボディ提灯の基本的な作り方は以下の通りです:
- ボディの準備:クリアーボディ(例:アバンテMKⅢアズールのクリヤボディなど)を用意します。ボディを切り取る前に、まず中性洗剤でボディをよく洗浄します。これは金型から取り出す際に使用される離型剤を落とすためで、後の塗装の定着をよくします。
- ボディのカット:ボディラインに沿って切り取ります。曲線部分は曲線バサミ(1000円程度で購入可能)を使うとキレイに切れます。切り取ったボディの左右に長いスペースがある場合は、それをリフター用に取っておきます。
- 色入れ:ボディの裏面から塗装します。マスキングテープを使って複数の色で塗り分けることもできます。まずはメインカラーを薄く数回に分けて吹きかけ、マスキングを変えて次の色を入れていきます。窓(キャノピー)部分はマスキングしたままにしておきます。
- ボディの取り付け:ボディを提灯機構に固定します。あらかじめ提灯機構にビスを立てておき、ボディに穴を開けて固定します。左右のズレを防ぐため、まずは片側だけ穴を開け、次にもう片側の穴を開けるとよいでしょう。固定には、ゴム管をカットして使用します。
- リフターの作成:リフターとは、提灯機構をふわっと浮かせる機構で、これにより制振性が格段に向上します。VZシャーシの場合、スイッチ部付近に裏面から穴を開け(Φ2mm)、ポリカの端材にも穴を開けて組み合わせます。シャーシ裏面からトラスビス、表面からはロックナットで固定します。
ボディ提灯のメリットは、見た目の良さに加え、優れた制振性能があります。通常の提灯よりも軽量でありながら、十分な効果を発揮するのが特徴です。
デメリットとしては、作製工程が多く、やや手間がかかる点が挙げられます。また、ボディの塗装技術が必要になるため、初心者にはやや難易度が高いかもしれません。
ボディ提灯は、特にコースを選ばず幅広い状況で効果を発揮するため、一度マスターすれば様々なレースで活用できる技術です。見た目と性能の両方にこだわりたい方は、ぜひチャレンジしてみてください。
提灯の調整方法はマスダンパーの重さと位置がカギ
提灯を作った後の調整方法は、マシンのパフォーマンスを最大化するために非常に重要です。特に重要なのが、マスダンパーの重さと位置の調整です。
マスダンパーの重さは、提灯の効果に直接影響します。一般的には、4〜6g程度のマスダンパーが使われますが、最適な重さはシャーシの種類やコース状況によって変わります。例えば、軽いシャーシ(MSなど)では軽めのマスダンパー、重いシャーシ(VZなど)ではやや重めのマスダンパーが効果的です。
マスダンパーの位置も重要な調整ポイントです。マスダンパーを提灯の先端に近づけるほど効果は大きくなりますが、同時に重心も高くなるため、バランスを考慮する必要があります。また、マスダンパーの高さ(地上からの距離)も調整可能で、「ギリギリ1ミリの高さ」に調整するのが一般的です。これは、公式ルールの「最低地上高1ミリ以上」を守りつつ、できるだけ重心を低くするためです。
提灯の角度や開き具合も調整できます。提灯の開き角度(可動域)によって効果が変わるため、コースに合わせて調整するとよいでしょう。一般的には40〜45度程度の開き角度が推奨されていますが、コースによっては15度程度(あまり開かない)や60〜70度(大きく開く)設定も選択肢となります。
提灯の角度調整には、「提灯の開度リミッタ」という部品が使われることもあります。これは提灯の開きすぎや開きが足りない状態を防ぐための部品で、シャフトと穴の形状を調整することで角度を制限できます。
また、リフター機構の強さも調整可能です。リフターに使うゴムリングの張力を調整することで、「スパッと上がる強めのリフター」や「ふわっとした挙動の弱いリフター」など、走行状況に合わせた調整ができます。
提灯の調整は、実際に走らせながら少しずつ変更していくのが最も効果的です。理論上の最適値だけでなく、自分のマシンとコースの特性に合わせた「感覚的な最適値」を見つけることが重要です。特に、ジャンプのあるコースではジャンプ後の着地の様子を観察し、バウンドが少なく安定して走れるように調整していきましょう。
リフター機構を追加すると制振性が大幅に向上する
提灯の効果をさらに高めるためには、「リフター機構」の追加が非常に効果的です。リフターとは、提灯機構をふわっと浮かせる仕組みのことで、これにより制振性が格段に向上します。
リフター機構の仕組みは比較的シンプルで、提灯の根元部分にゴムやスプリングなどの弾性体を取り付け、提灯全体をわずかに浮かせる状態にするというものです。これにより、提灯がより効果的に振動を吸収できるようになります。
リフター機構の作り方は以下の通りです:
- VZシャーシの場合、スイッチ部付近に裏面から穴を開けます(Φ2mm程度)。
- ポリカーボネートの端材(細長くカットしたもの)にも同様に穴を開けます。
- シャーシ裏面からトラスビス、表面の方はロックナットを使って固定します。
- 提灯を取り付けた後、ゴムリングを引っ掛けてリフター機能を持たせます。
リフターの強さは調整可能で、ゴムリングの張力によって変えることができます。そのままだと強めのリフター(スパッと上がる)になりますが、ゴムリングを大きく伸ばしておくと、弱いリフター(ふわっとした挙動)になります。
リフター機構の最大のメリットは、コース上の凹凸による振動や衝撃をさらに効果的に吸収できる点です。特に連続したジャンプや急なコーナー、凹凸の多いコースでは、リフターの効果が顕著に現れます。
ただし、リフター機構のデメリットとして、調整が難しくなる点や、場合によっては浮き上がりが悪さをすることもあります。そのため、リフター機構は脱着できるように設計するのがおすすめです。例えば、ネジ留め方式にすることで、必要に応じてリフターを取り外せるようにします。
MSシャーシにリフターを搭載した場合の効果は特に顕著で、提灯がふわふわと浮いて制振性が非常に高まります。VZシャーシの場合も、適切に設計すれば同様の効果が得られます。
リフター機構は基本的な提灯の効果を理解し、実際に走らせた経験がある程度ある方におすすめの発展的な改造です。初めて提灯を作る場合は、まずは基本的な提灯を使いこなし、その後リフター機構を追加するという段階的なアプローチが良いでしょう。
提灯の可動域は角度によって効果が変わる
提灯の可動域、つまり提灯が開く角度は、その効果に大きく影響します。適切な可動域を設定することで、コースの特性に合わせた最適な制振効果を得ることができます。
提灯の可動域を決める主な要素は、提灯のアームの長さと取り付け角度、そして「提灯の開度リミッタ」と呼ばれる部品の調整です。一般的には、40〜45度程度の開き角度が多くのコースで効果的ですが、コースによっては15度程度(あまり開かない)や60〜70度(大きく開く)の設定も選択肢となります。
提灯の開き角度が小さい場合(15度程度)のメリットは、急なコーナーや狭いコースでの取り回しが良くなることです。また、提灯が大きく振れないため、安定した走行が可能になります。デメリットとしては、大きなジャンプや激しい凹凸に対する吸収力が弱くなる点が挙げられます。
一方、提灯の開き角度が大きい場合(60〜70度程度)のメリットは、大きなジャンプや激しい凹凸に対する吸収力が高まることです。特に、ジャンプ後の着地の衝撃を効果的に吸収できます。デメリットとしては、提灯が大きく振れるため、急なコーナーでのマシンの挙動が不安定になる可能性がある点です。
最適な提灯の可動域は、コースの特性だけでなく、シャーシの種類やマシンの重量配分、使用するモーターのトルク特性なども考慮して決める必要があります。例えば、トルクの強いモーターを使用している場合は、やや大きめの可動域が効果的な場合があります。
提灯の開度リミッタを調整するには、シャフトが穴の形状に収まった状態から30度程度捻り、瞬間接着剤で固定するという方法があります。シャフトの一番径が広い山が穴の径が狭い角度になるように調整することで、開き角度を制限できます。
実際のレースでは、練習走行の時間を使って異なる可動域の提灯を試し、最も安定して走れる設定を見つけることが重要です。また、複数の提灯を用意して、コースごとに使い分けるというアプローチも上級者の間では一般的です。
提灯の可動域の調整は、マシンのパフォーマンスを最大化するための重要な要素の一つです。自分のマシンとコースの特性に合わせて、最適な可動域を見つけてください。
提灯がレースで禁止される場合もあるので注意が必要
ミニ四駆の提灯は非常に効果的なカスタムパーツですが、レースによっては使用が制限されたり禁止されたりする場合があります。レースに参加する前には必ずレギュレーション(規則)を確認することが重要です。
提灯が禁止される主な理由としては、以下のようなものが考えられます:
- 公平性の確保:初心者クラスなど、基本的な技術を競うレースでは、提灯のような高度なカスタマイズを制限することで、参加者間の公平性を保つ場合があります。
- 安全性への配慮:提灯が大きく突き出していると、他のマシンとの接触時に危険が生じる可能性があります。
- 大会のコンセプト:「無加工マシンのレギュレーション」や「B-MAXグランプリ」などの特定のコンセプトを持つ大会では、提灯のような大きな改造を認めていない場合があります。
- レギュレーションの違い:「エントリークラス」や「完走を楽しむクラス」など、初級者向けのクラスでは、提灯の使用が制限されることが多いです。
提灯が禁止されている大会やクラスでは、代替策として以下のような方法が考えられます:
- 基本的なセッティングの最適化:モーターの選択、タイヤの選定、マシン全体のバランス調整など、基本的なセッティングを最適化することで、提灯がなくても安定した走行を実現できます。
- 軽量化:不要な部品を取り除き、マシン全体を軽量化することで、ジャンプ後のバウンドを軽減できます。
- パカパカボディ:後述しますが、ボディを利用した制振機構も提灯の代替として効果的です。
- 公式パーツの活用:タミヤ公式のスタビライザーやダンパーなど、規則で認められている範囲内のパーツを最大限活用します。
レースに参加する際は、主催者やショップのウェブサイト、SNSなどで最新のレギュレーションを確認することをおすすめします。また、現地での車検時に提灯が認められるかどうか直接確認することも大切です。
提灯が禁止されているレースやクラスでも、その経験はミニ四駆の基本スキルを磨く良い機会になります。提灯に頼らずに安定して走るテクニックを身につけることで、提灯を使用できるレースでもさらに高いパフォーマンスを発揮できるようになるでしょう。
パカパカボディは提灯の代替として効果的な場合もある
パカパカボディとは、ボディを固定せずに浮かせた状態で取り付ける手法で、提灯の代替として効果を発揮することがあります。特に提灯が禁止されているレースやクラスでは、パカパカボディが有効な選択肢となります。
パカパカボディの仕組みは、ボディとシャーシの間に適度な隙間を設け、ボディが上下に動けるようにすることで振動を吸収するというものです。通常のボディマウントではなく、専用のマウントやゴムなどの弾性素材を使って取り付けることが多いです。
パカパカボディの作り方は比較的シンプルです:
- ボディマウントを通常よりも高い位置に取り付けるか、弾性素材(ゴムなど)を使ってボディを浮かせた状態にします。
- ボディとシャーシの間に適度な隙間(数ミリ程度)を設けます。隙間が広すぎるとボディの動きが大きくなりすぎ、狭すぎると効果が薄れます。
- ボディの動きを制限するストッパーを設置することで、ボディの過度な動きを防ぎます。
パカパカボディのメリットとしては、以下のようなものがあります:
- 提灯禁止レースでも使用可能:多くのレースでは、パカパカボディは規則違反にならないため、提灯の代替として使用できます。
- 外観が通常のマシンと変わらない:提灯のように外部に突き出る部分がないため、見た目は通常のマシンと変わりません。
- 軽量:提灯に比べて軽量なため、マシン全体の重量増加を抑えられます。
一方、デメリットとしては以下のようなものがあります:
- 効果は提灯に劣る:振動吸収効果は提灯には及ばないことが多いです。
- 調整の難しさ:適切な隙間や弾性の調整が難しく、効果を最大化するためには試行錯誤が必要です。
- ボディの耐久性:ボディが常に動くため、通常よりも早く摩耗したり破損したりする可能性があります。
パカパカボディは、特にボディ提灯(ヒクオ)の原理を応用したものと考えることができます。ボディ自体が制振機構として機能するという点で共通しています。ただし、ボディ提灯が積極的にボディを振動吸収に利用するのに対し、パカパカボディはやや受動的な効果になります。
提灯が使えないレギュレーションのレースに参加する場合や、まずは簡単な方法から試してみたい初心者の方には、パカパカボディはおすすめの選択肢です。また、提灯との併用も可能で、より高い制振効果を得ることもできます。
まとめ:ミニ四駆提灯作り方のポイントは素材選びと正確な組み立てにある
最後に記事のポイントをまとめます。
- 提灯はFRPプレートとマスダンパーを組み合わせた振動吸収パーツである
- 基本的な提灯は30分程度で作れ、初心者でも取り組みやすい
- 提灯の効果はマスダンパーのカウンターウェイト原理に基づいている
- MSシャーシ用提灯は軽量で、アームを内向きにするのがポイント
- VZシャーシ用提灯はサイドバンパーのカットが必要になる
- MAシャーシ用提灯は両軸に対応した設計が重要
- ARシャーシ用提灯はフロントAパーツを避ける形状に加工する
- ボディ提灯(ヒクオ)はポリカボディの加工から始め、見た目と性能を両立できる
- 提灯の調整ではマスダンパーの重さと位置、開き角度が重要
- リフター機構を追加すると制振性が大幅に向上する
- 提灯はレースによっては禁止される場合があるため、レギュレーション確認が必要
- パカパカボディは提灯の代替として効果的な場合もある
- 最適な提灯はコース特性やシャーシ特性に合わせて選択する
- 提灯の素材選びと正確な組み立てが効果を最大化するカギとなる
- 提灯は着脱可能に設計すると、コースに応じた使い分けができる