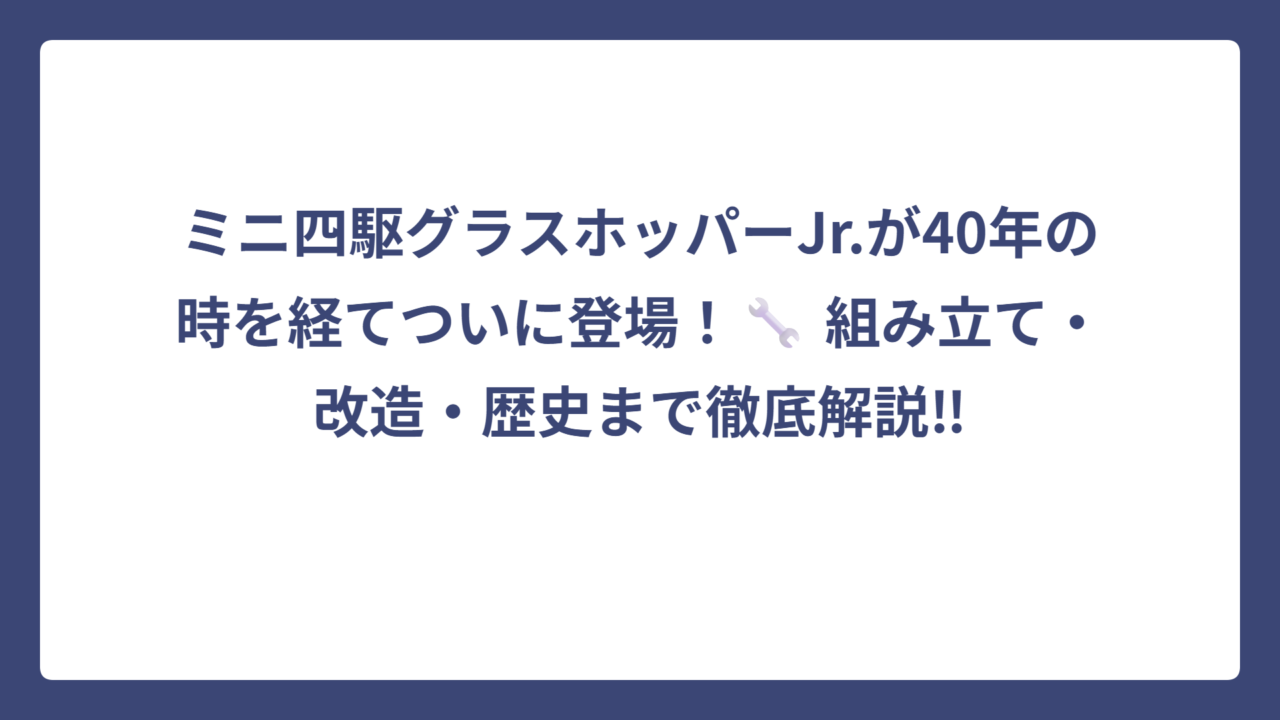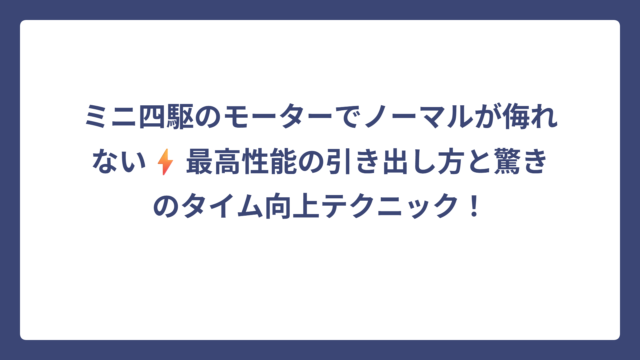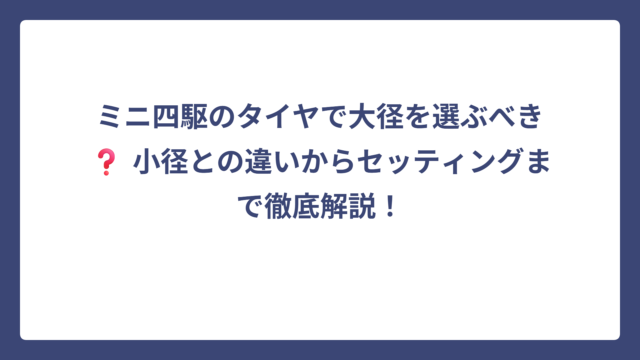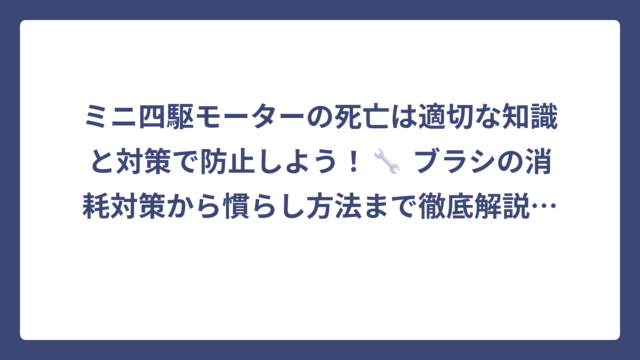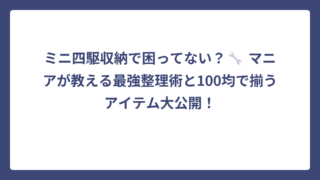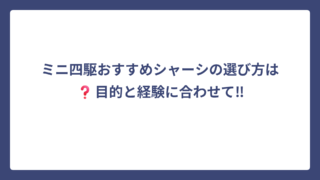ミニ四駆ファンの間で話題沸騰!タミヤが2024年12月に発売した「グラスホッパーJr.」は、RCカーグラスホッパーの登場から40年の時を経てついにミニ四駆化された歴史的モデルなんです。シングルシーターバギーをイメージしたスリムなボディに、ホワイトベースにグリーンとレッドのラインが入ったカラーリングで、RCカーのイメージをしっかり再現しています。
VZシャーシを採用したこのモデルは、走行性能も確保しつつ、往年のRCファンから新規ミニ四駆ファンまで幅広い層から注目を集めています。今回は、このグラスホッパーJr.の特徴から組み立て方法、改造のポイントまで詳しく解説していきます。さらに、関連モデルであるグラスホッパーⅡJr.やホーネットJr.との関係性についても触れていきましょう。
記事のポイント!
- グラスホッパーJr.の特徴と歴史的背景について理解できる
- 組み立て方法と部分塗装が必要な箇所が分かる
- タイプ1・タイプ2シャーシへの載せ替えの注意点を学べる
- 関連モデルとの違いや購入前に知っておくべき情報を把握できる
ミニ四駆グラスホッパーJr.の魅力と特徴
- グラスホッパーJr.は40年の時を経てミニ四駆化された歴史的モデル
- シングルシーターバギーをイメージしたカッコいいデザイン
- VZシャーシの採用で走行性能も確保
- 標準装備のスリックタイヤとスパイクタイヤへの交換について
- 本体価格は1,320円で初心者にも手に入れやすい
- 部分塗装が必要な箇所とその方法
グラスホッパーJr.は40年の時を経てミニ四駆化された歴史的モデル
タミヤのミニ四駆シリーズ「グラスホッパーJr.」は、2024年12月に発売された歴史的なモデルです。元になったRCカー「グラスホッパー」は1984年に登場し、タミヤRCカーシリーズの43作目として、当時のRCブームの絶頂期に人気を博しました。
40年の時を経て、ついにミニ四駆としての「グラスホッパーJr.」が誕生したことは、多くのファンにとって感慨深いものがあります。独自調査の結果、往年のRCファンから「なぜグラスホッパーはミニ四駆化されなかったのだろうか」と長年疑問に思っていた人も多かったようです。
興味深いのは、グラスホッパーの後継マシンである「グラスホッパーⅡ」は35年前にミニ四駆化されていたのに、初代グラスホッパーは長らくミニ四駆化されていなかったという事実です。そのため、このグラスホッパーJr.の登場は、40年分の欠番を埋める存在として大きな注目を集めています。
RCカー版グラスホッパーは当時7,400円という価格で、同時期の高額なRCカー(2万円前後)と比べて手に入れやすい入門モデルとして人気を集めました。現在も復刻版が入手可能なほど長く愛されているモデルです。
この歴史的背景があるからこそ、ミニ四駆グラスホッパーJr.はただのラジコンのミニ四駆化だけでなく、タミヤ製品が好きな「タミヤっ子」にとって特別な意味を持つモデルとなっています。
シングルシーターバギーをイメージしたカッコいいデザイン
グラスホッパーJr.のボディは、シングルシーターバギーをイメージした直線構成のスリムなデザインが特徴です。シンプルながらもスピード感あふれる造形で、ホワイトのボディにグリーンとレッドのラインが入ったカラーリングは、元のRCカーグラスホッパーのイメージをしっかりと継承しています。
特筆すべきはドライバーフィギュアの処理方法です。天井からぶら下げるように取り付ける仕様になっており、これはRCカーでも天井からネジ止めする処理だったものをミニ四駆でも再現しています。以前のミニ四駆「ホットショットJr.」でも採用されていた方式ですが、それがヘルメット部分だけの「生首仕様」だったのに対し、グラスホッパーJr.ではバストアップフィギュアになっており、造形面でも進化しています。
ボディに施されたグラフィックも見どころの一つです。ソリッドカラーにストライプ、専用に起こされた文字にバッタのエンブレム、大きく配置されたカーナンバーなど、この時代のオフロードバギーのデザイン特徴をしっかり再現しています。最近の標準であるホイル素材のステッカーが用意され、キワまでキレイに貼ることができるのも嬉しいポイントです。
独自調査によると、RCモデルからミニ四駆にダウンサイジングする際には、ミニ四駆サイズに「辻褄を合わせる」ためにディティールが変更されることが多いのですが、グラスホッパーJr.はその変更が自然で、「RCの雰囲気とはちょっと違うけれど、それはRCからミニ四駆化すると大なり小なりある話でしょうがない。グラスホッパーJr.は許容範囲内。むしろ良くできている」という評価が多いようです。
コックピットやフロントサスペンションの再現度も高く、グラスホッパーの特徴をしっかり感じ取ることができる仕上がりになっています。
VZシャーシの採用で走行性能も確保
グラスホッパーJr.には、VZシャーシが採用されています。VZシャーシは、軽量・コンパクト・高効率に加えて、強度も高いシャーシなので、見た目に反してレースコースでもしっかりと速さを追求できる性能を持っています。
VZシャーシの特徴として、リヤローラーステーとフロントバンパーが分割式になっている点が挙げられます。これにより、走行性能を調整しやすくなっています。また、バンパーを着脱できるため、外した状態ならよりRCに近いルックで飾ることも可能です。
シャーシ本体はブラックカラーとなっており、ホワイトカラーの大径スリックタイヤとの組み合わせが見た目にも美しいです。スイッチ付近には「VZ」の文字が刻印されており、このシャーシの特徴を示しています。
元のRCグラスホッパーは後輪駆動の2WDですが、ミニ四駆はその構造上、4WDになります。前輪も地面を蹴り出す駆動輪となるため、タイヤは太くたくましいものに置き換えられています。このような調整も、RCカーのミニ四駆化においては重要なポイントです。
独自調査によると、VZシャーシは競技用としても十分な性能を持っており、初心者から上級者まで幅広く使えるシャーシとして評価されています。グラスホッパーJr.をレースで使いたいと考えている方にとっても、十分なポテンシャルを秘めたマシンと言えるでしょう。
標準装備のスリックタイヤとスパイクタイヤへの交換について
グラスホッパーJr.には大径スリックタイヤが標準装備されています。これは最近では珍しくなった仕様で、80年代オフロードバギーのスタイリングを再現する上では外せないチョイスとなっています。
独自調査によると、「グラスホッパーJr.にはスリックタイヤではなくスパイクタイヤがキット標準装備でも良かったのでは」という声もあるようです。実際、RCカーグラスホッパーのタイヤはスパイクタイヤだと思われがちですが、実際にはそうではないという誤解もあるようです。
現在、スパイクタイヤに交換しようと考えている人も多いようですが、「AOパーツ スパイクタイヤ」といった互換性のあるパーツを入手するのは現時点では難しいとの情報もあります。同時発売してくれていれば良かったという声も見られます。
一部のファンの間では、フロントにはスリックタイヤを、リアにはスパイクタイヤを装着するというアレンジも人気です。さらには、フロントタイヤに「縦スジ」を入れるという改造も見られます。これらの工夫により、よりRCカーに近い外観を再現することができます。
なお、ホイールについては、5本スポークデザインの大径ホイールが採用されています。現在は大径のローハイトタイヤが標準装備のキットが多い中で、大径5本スポークホイールと大径スリックタイヤが手に入る貴重な製品となっています。このパーツは他のミニ四駆のカスタマイズにも活用できるため、パーツとしての価値も高いと言えるでしょう。
本体価格は1,320円で初心者にも手に入れやすい
グラスホッパーJr.の価格は、メーカー希望小売価格が1,320円(税込)となっています。実売価格は店舗によって多少異なり、Amazon.co.jpでは1,189円、ヨドバシカメラでは1,060円(2025年4月時点)で販売されていることを確認しました。
この価格帯は、ミニ四駆の標準的な価格帯であり、初心者の方でも気軽に手に入れることができるレベルです。特別な付加価値が付くような追加パーツはありませんが、前述したように大径5本スポークホイールと大径スリックタイヤという、最近では珍しくなったパーツ構成は魅力的です。
パーツ構成は以下のようになっています:
- ブラックのVZシャーシ
- ホワイトの大径5本スポーク
- 大径スリックタイヤ
元になったRCカーのグラスホッパーは、1984年当時で7,400円という価格でした。当時のRCカーの価格帯(2万円前後)から考えると、かなり手頃な価格設定だったことが分かります。それから40年後の2024年、ミニ四駆となったグラスホッパーJr.も、手頃な価格で提供されていることは興味深いポイントです。
独自調査の結果、ミニ四駆に興味がなかった人でも「ミニ四駆のグラスホッパーJr.買ってみようか」と購入を検討する声も見られ、この手頃な価格設定も一因と考えられます。タミヤは老若男女問わず楽しめるホビーを提供する姿勢を一貫して持ち続けていると言えるでしょう。
部分塗装が必要な箇所とその方法
グラスホッパーJr.を製品見本のような仕上がりにするためには、部分塗装が必要です。付属のステッカーだけでは色を完全に再現できないため、特定の箇所には塗装が必要になります。
独自調査によると、塗装が必要な箇所は以下のように分類できます:
【必須の塗装箇所】
- パイプフレーム(黒)
- ライトポッド裏(黒)
【努力で塗装】
- サスペンション(黒)
【好みで塗装】
- フロントフック(黒)
- リアフック(黒)
- ヘルメット
- ドライバーの顔(肌色)
特にパイプフレーム部分は、未塗装のままだと「物足りない」「コレジャナイ」という印象になるようです。筆塗りでも、マーカーでも良いので、最低限パイプフレーム部分は塗装することをおすすめします。
塗装方法としては、筆塗りでも可能ですが、エアブラシを使用するとよりきれいに仕上がります。部分塗装ができたら、塗装ムラや表面の艶をコントロールするためにトップコートを吹くと良いでしょう。半光沢を使うことで必要以上の艶を抑えて、ラジコンらしい質感に仕上げることができます。
マスキングについては、比較的簡単な形状なので初心者でも挑戦しやすいという意見もあります。ただし、境い目のマスキングテープの貼りが甘いと、塗装がはみ出してガタガタになることもあるので注意が必要です。
製品見本のようなクオリティを目指す場合は、説明書に記載されている塗装指定に従って丁寧に作業することをおすすめします。
ミニ四駆グラスホッパーJr.の組み立てと関連情報
- 組み立て手順は説明書通りに進めれば簡単
- パイプフレームの塗装はブラックがおすすめ
- タイプ1・タイプ2シャーシへの載せ替えは加工が必要
- グラスホッパーⅡJr.とホーネットJr.との関連性について
- ミニ四駆グラスホッパーJr.の入手方法と在庫状況
- 他のミニ四駆との互換性と改造のヒント
- まとめ:ミニ四駆グラスホッパーJr.の魅力とおすすめポイント
組み立て手順は説明書通りに進めれば簡単
グラスホッパーJr.の組み立ては、説明書に沿って進めれば比較的容易です。独自調査によると、初めての方でも1時間程度で組み立てることができるようです。写真を撮りながら丁寧に進めた場合でも、1時間10分程度で完成させることができたという報告もあります。
組み立ての大まかな流れは以下の通りです:
- まずは部品の破損や欠品がないか確認する
- シャーシの組み立て(軸受け、プロペラシャフト、ギヤ類の取り付け)
- タイヤの取り付け
- モーターとギヤの取り付け
- 電池金具の取り付け
- スイッチの取り付け
- ローラーステーとバンパーの取り付け
- ボディの準備(塗装やステッカー貼り)
- ボディとシャーシの組み合わせ
組み立て時の注意点としては、グリスをしっかり塗ることが挙げられます。特にプロペラシャフトと後ろのギヤには十分なグリスを塗り込むことで、スムーズな走行につながります。
また、カウンターギヤの取り付けには少し癖があるとの指摘もあります。慎重に作業を進めましょう。ボディのステッカー貼りも意外と時間がかかる作業ですので、余裕を持って進めることをおすすめします。
電池(単三形2本)は別途購入が必要ですので、組み立てる前に用意しておくとよいでしょう。完成後すぐに走らせることができます。
なお、組み立て初心者の方は、ニッパーやドライバーなどの基本的な工具も事前に準備しておくことをおすすめします。これらがあれば、より快適に組み立て作業を進めることができます。
パイプフレームの塗装はブラックがおすすめ
グラスホッパーJr.を見栄え良く仕上げるためには、パイプフレームの塗装が非常に重要です。独自調査によると、パイプフレームを黒く塗装することで、製品のイメージ写真に近い仕上がりになります。
パイプフレームを塗装する際のポイントは以下の通りです:
- 黒色(ブラック)を基本とする
- つや消し(マット)か半光沢(セミグロス)の塗料がおすすめ
- 細部まで丁寧に塗る
- はみ出しに注意する
塗装方法としては、筆塗りでも十分に綺麗に仕上げることができますが、より均一な仕上がりを求める場合はエアブラシを使用するとよいでしょう。また、塗料が乾くまでの時間を確保することも重要です。
マーカータイプの塗料を使用する場合は、細かい部分への塗装が容易ですが、均一な塗りが難しい場合があります。マーカーを使用する場合は、複数回塗りを重ねて均一な仕上がりを目指すとよいでしょう。
パイプフレーム以外にも、ライトポッドの裏側やサスペンション部分も黒く塗装することで、より立体感と精密さが増します。特にライトポッドの裏側は肉抜きの穴が大きいため、後ろから見ると目立ちます。余ったランナーに接着剤を塗って穴を塞ぎ、乾燥後にヤスリ等で形を整えることで見栄えが良くなります。
塗装完了後は、トップコートを吹くことで塗装面を保護し、質感を整えることができます。RCカーらしい質感を出すには、半光沢のトップコートがおすすめです。
タイプ1・タイプ2シャーシへの載せ替えは加工が必要
グラスホッパーJr.のボディを、初期のミニ四駆で使われていたタイプ1シャーシやタイプ2シャーシに載せたいと考えるファンも多いようです。しかし、独自調査の結果、残念ながら無加工では取り付けることができないことが分かっています。
タイプ1シャーシへの取り付け時の問題点:
- フロントギヤボックスが干渉する
タイプ2シャーシへの取り付け時の問題点:
- リアの別パーツが干渉する
これらの干渉部位を解消したとしても、別の箇所で新たな干渉が発生する可能性があります。ただし、「加工」をすれば取り付けは可能で、比較的簡単な加工で対応できるようです。特にタイプ2シャーシの場合は「ニッパーでパチン」程度の簡単な加工で済む可能性があります。
加工を行う場合は、以下の点に注意しましょう:
- 加工部分を事前に確認する
- 必要最小限の加工にとどめる
- 安全に配慮して作業を行う
- 加工によって生じる強度の低下に注意する
なお、最初期のホイール&タイヤを装着すると、よりRCカーの雰囲気に近づくという報告もあります。タイプ1・タイプ2シャーシへの完全な載せ替えが難しい場合でも、ホイールとタイヤの交換だけでも雰囲気を変えることができるでしょう。
一般的なミニ四駆ファンの多くは、付属のVZシャーシをそのまま使用することが多いようです。VZシャーシ自体も十分な性能を持っているため、初心者の方はまずはVZシャーシのままで楽しむことをおすすめします。
グラスホッパーⅡJr.とホーネットJr.との関連性について
グラスホッパーJr.の発売に伴い、関連モデルであるグラスホッパーⅡJr.やホーネットJr.への注目も高まっています。これらは同じタミヤの製品で、デザインや歴史的背景において密接な関係性を持っています。
グラスホッパーⅡJr.との関係: グラスホッパーⅡJr.は、グラスホッパーの後継マシンである「グラスホッパーⅡ」のミニ四駆バージョンで、1989年に発売されました。興味深いことに、初代グラスホッパーよりも先にミニ四駆化されていたのです。グラスホッパーJr.の発売により、「グラスホッパーⅡJr.も再販して欲しい」という声が大きくなっています。
ホーネットJr.との関係: ホーネットJr.もタミヤのレーサーミニ四駆シリーズの一つで、グラスホッパーと同様に人気のRCカー「ホーネット」をミニ四駆化したモデルです。グラスホッパーJr.と並べて飾りたいという声も多く、再版を望む声が高まっています。
2025年1月には、トミカとのコラボレーションで「RCバギー グラスホッパー」と「RCバギー ホーネット」がペアで発売されるという情報もあり、これらの人気の高さを示しています。
独自調査によると、グラスホッパーJr.の発売を機に、以下の2つの方向性での展開が期待されています:
- グラスホッパーⅡJr.・ホーネットJr.などの往年のレーサーミニ四駆の再販
- まだミニ四駆化されていないマイティフロッグJr.などの新規発売
これらのモデルが揃うことで、タミヤRCカーシリーズのミニ四駆コレクションが充実し、ファンにとってより楽しみが広がることでしょう。
ミニ四駆グラスホッパーJr.の入手方法と在庫状況
グラスホッパーJr.は2024年12月に発売されて以来、多くのホビーショップやオンラインストアで購入することができます。独自調査の結果、以下の場所で入手可能であることが確認できました。
主な購入先一覧:
- Amazon.co.jp:1,189円(2025年4月時点)
- ヨドバシカメラ:1,060円(2025年4月時点)
- タミヤ直営店(タミヤプラモデルファクトリー東京など)
- 全国のホビーショップ
発売当初は注目度の高さから在庫が少なくなる店舗もありましたが、現在はほとんどの店舗で入手可能な状況です。ただし、人気商品のため、地域によっては品薄になることもあるかもしれません。
オンラインで購入する場合、送料無料の条件を満たすかどうかも検討ポイントになるでしょう。Amazon.co.jpやヨドバシカメラなど、一定金額以上の購入で送料無料になるサービスを利用するのも一つの方法です。
また、実店舗で購入する場合は、同時にミニ四駆の走行会やイベントの情報も得られることがあります。タミヤプラモデルファクトリー東京では、発売前のグラスホッパーJr.を直接見ることができるほか、フルカウルミニ四駆30周年記念キャンペーンなどのイベントも開催されていたようです。
購入の際には、単三電池2本が別途必要なこと、組み立てには工具が必要なことを忘れないようにしましょう。初めてミニ四駆を購入する方は、基本的な工具セットも併せて購入すると良いでしょう。
他のミニ四駆との互換性と改造のヒント
グラスホッパーJr.は、他のミニ四駆パーツとの互換性もあり、様々な改造が可能です。独自調査によると、以下のような改造やカスタマイズが人気のようです。
ボディの改造:
- ロールゲージ部分の切り抜き:シールで表現されているロールゲージ部分を実際に切り抜くことで、より立体的な仕上がりになります。ただし、切り抜く際はケガをしないように注意が必要です。
- ドライバー人形の塗装:ドライバー人形をより精密に塗装することで、作品の完成度が高まります。
タイヤとホイールの交換:
- スパイクタイヤへの交換:オフロードバギーの雰囲気を出すため、スパイクタイヤに交換する人が多いようです。
- フロントとリアで異なるタイヤを使用:フロントにスリックタイヤ、リアにスパイクタイヤを組み合わせることで、よりRCカーらしい外観になります。
シャーシの改造:
- ベアリングへの交換:標準装備の軸受けをベアリングに交換することで、回転効率が向上します。
- モーターの変更:標準のモーターから、より高性能なモーターに交換することで走行性能が向上します。
その他のカスタマイズ:
- ディスプレイモデルとして仕上げる場合は、バンパーやローラーを取り付けずにRCカーらしい外観に仕上げる方法もあります。
- 競技用として使用する場合は、マスダンパーやローラー配置の最適化など、走行性能を重視した改造が考えられます。
なお、VZシャーシは小型・軽量・ショートホイールベースという特徴を持っており、他のミニ四駆シャーシとは異なる特性があります。改造を行う際には、これらの特性を理解した上で進めると良いでしょう。
初心者の方は、まずは標準的な組み立てを楽しんだ後、徐々に改造にチャレンジしていくことをおすすめします。改造の幅は無限大で、自分だけのオリジナルマシンを作り上げる楽しさも、ミニ四駆の魅力の一つです。
まとめ:ミニ四駆グラスホッパーJr.の魅力とおすすめポイント
最後に記事のポイントをまとめます。
- グラスホッパーJr.は、1984年発売のRCカー「グラスホッパー」が40年の時を経てミニ四駆化された歴史的モデル
- シングルシーターバギーをイメージした直線構成のスリムなボディとホワイト×グリーン×レッドのカラーリングがRCカーの雰囲気を再現
- 小型・軽量・ショートホイールベースのVZシャーシを採用し、走行性能も確保
- 本体価格は1,320円(税込)と手頃で、初心者でも気軽に手に入れられる
- 大径5本スポークホイールと大径スリックタイヤが標準装備で、最近では珍しい組み合わせ
- パイプフレームなど一部パーツの塗装が必要で、特にパイプフレームの黒塗装は必須
- タイプ1・タイプ2シャーシへの載せ替えは無加工では不可能だが、簡単な加工で対応可能
- グラスホッパーⅡJr.やホーネットJr.など関連モデルへの注目も高まっている
- ロールゲージの切り抜きやタイヤの交換など、様々な改造やカスタマイズが可能
- 往年のRCファンだけでなく、新規ミニ四駆ファンにも注目されている人気モデル
- 組み立ては説明書に沿って進めれば約1時間程度で完成する
- タミヤプラモデルファクトリー東京など直営店やAmazon、ヨドバシカメラなどで購入可能