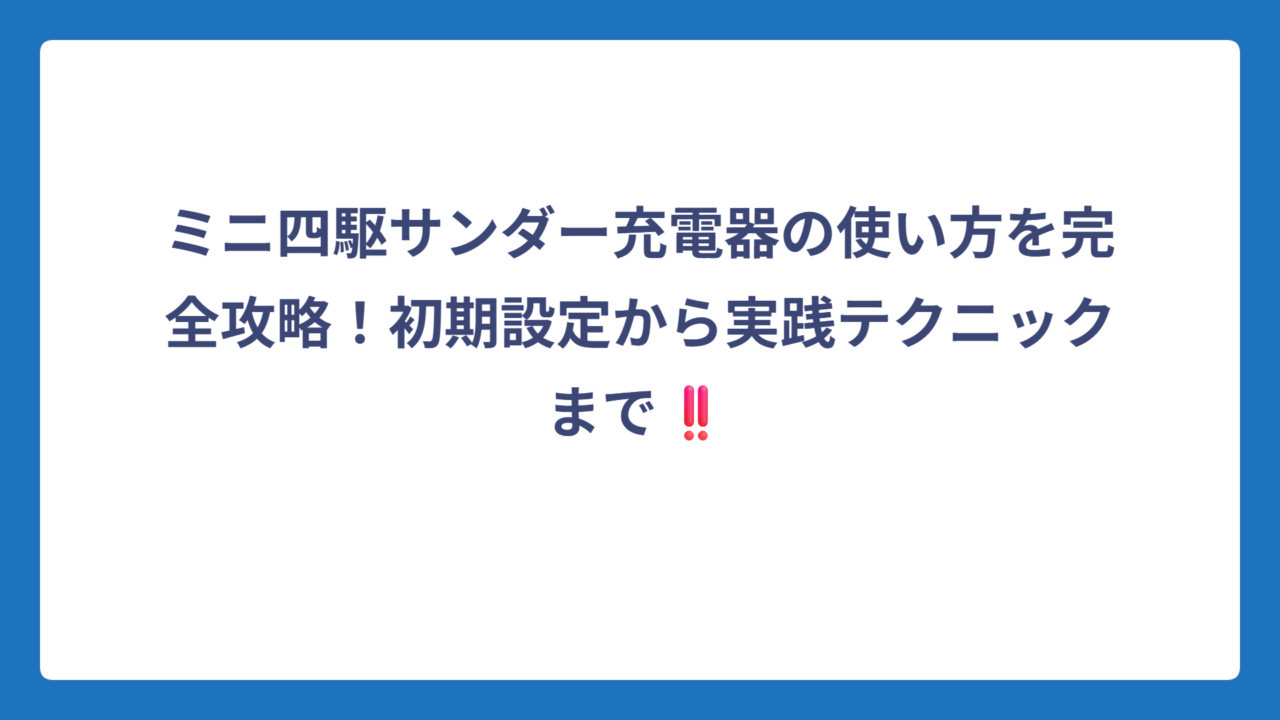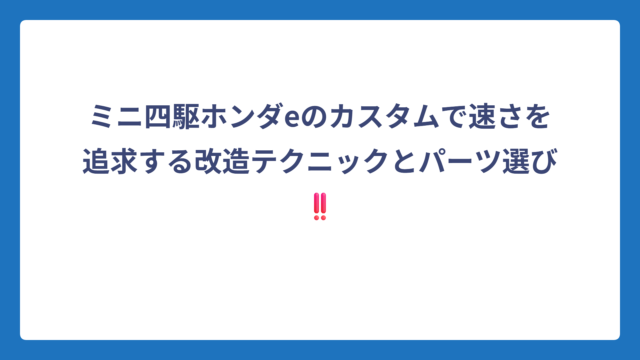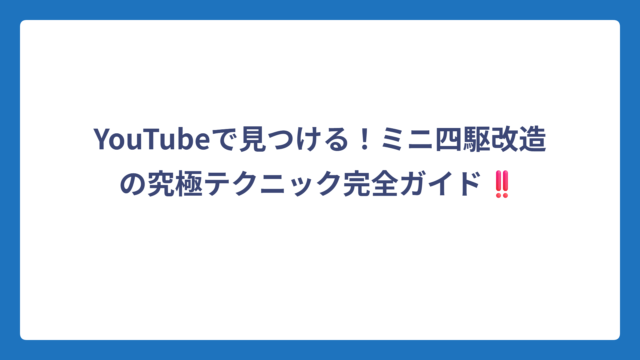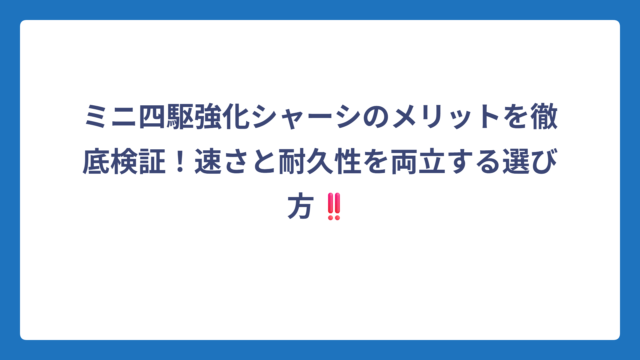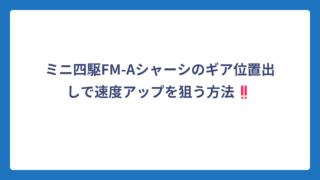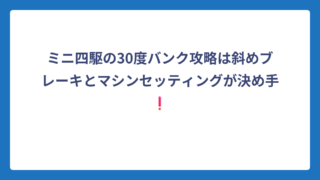ミニ四駆レースで上位を狙うなら、電池管理が重要なポイントになります。そこで注目されているのが「THUNDER(サンダー)」という充電器です。多くのレーサーが使用しているこの機器ですが、日本語マニュアルがなく、使い方に戸惑う方も少なくありません。
この記事では、サンダー充電器の基本的な使い方から、知っておきたい初期設定、実践的な活用テクニックまで、実際のユーザー情報をもとに詳しく解説していきます。購入前に必要な周辺機器や、電池の充放電、モーター慣らしといった具体的な操作方法もカバーしています。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ サンダー充電器の基本操作と初期設定の方法 |
| ✓ 購入前に揃えるべき必須周辺機器 |
| ✓ 電池の充電・放電・サイクルモードの使い分け |
| ✓ モーター慣らしと回転数測定のテクニック |
ミニ四駆サンダー充電器の使い方と基本設定
- サンダー充電器とは何か?アンチマター・リアクターとの違い
- 購入前に必ず揃えるべき周辺機器
- 最初に行うべき重要な初期設定4つ
サンダー充電器とは何か?アンチマター・リアクターとの違い
THUNDER(サンダー)は、ミニ四駆レーサーの間で広く使われている多機能充放電器です。実はこの機器、アンチマター(ANTIMATTER)やリアクター(REAKTOR)と性能面ではほぼ同じものです。
📊 106B+系充電器の系譜
| オリジナル機種 | OEM・互換機 | 特徴 |
|---|---|---|
| iCharger 106B+ | Atlantis AL106b+ | 元祖モデル |
| – | アンチマター | コピー品として流通 |
| – | リアクター | コピー品として流通 |
| – | サンダー | 現在主流の名称 |
| – | ヘマタイト | バリエーション |
これらは見た目や名称が違うだけで、機器としての性能は同等です。一部の上級者は複数台を使い分けているケースもあります。
アンチマター、サンダー、リアクターはほぼ一緒のものらしいです。ハイテックのX4miniとスカイアークのNC1500みたいなもの(製造工場が同じところらしい)
ただし2025年現在、どの機種も入手が困難になっている状況です。見かけたら早めの購入を検討した方がいいかもしれません。
購入前に必ず揃えるべき周辺機器
サンダー充電器は本体だけでは使用できません。一般的な充電器と違い、付属のコンセントもないため、別途周辺機器を揃える必要があります。
🔌 必須アイテム一覧
| 機器名 | 仕様 | 価格目安 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 安定化電源/ACアダプター | DC10-18V、センタープラス5.5/2.5mm | 1,500円〜 | 本体への電力供給 |
| バッテリーホルダー | 単三電池対応、バナナプラグ端子 | 1,200円〜 | 電池の充放電用 |
| ワニ口クリップケーブル | バナナプラグ→ワニ口 | 数百円 | モーター慣らし用 |
電源についての注意点として、サンダーの最大入力電流が6Aであることを考慮すると、6A以上の安定化電源が推奨されます。将来的に複数台運用や他機器も使う予定なら、10A以上の容量があるとより安心です。
バッテリーホルダーは、ホームセンターや家電量販店でも1,200円程度で入手可能ですが、付属ケーブルが細いものが多いです。高性能充電器の性能を最大限引き出すため、1.25sq以上の太めのケーブルのものを選ぶことをおすすめします。
💡 初期費用の目安としては、本体(9,000円前後)+周辺機器(3,000円程度)で、合計12,000円前後を見込んでおくといいでしょう。
最初に行うべき重要な初期設定4つ
サンダー充電器を手に入れたら、使い始める前に必ず行うべき初期設定があります。デフォルト設定のままでは本来の性能を発揮できないため、この設定は必須です。
✅ 設定1:消音設定(Key Beep & Buzzer)
初期状態では操作のたびに大きなビープ音が鳴ります。自宅使用なら問題ないかもしれませんが、コースで使用する際は他のレーサーの迷惑になるため、必ずOFFに設定しましょう。
PROGRAM SELECT → Settings → Key Beep「ON」→「OFF」
→ Buzzer「ON」→「OFF」
✅ 設定2:しぼり放電設定(Discharge Reduce)
サンダーの最大の特徴であるしぼり放電機能は、初期状態では「OFF」になっています。この機能により、電池の容量を極限まで抜くことが可能になります。
PROGRAM SELECT → Settings → Discharge Reduce「OFF」→「ON」
→ 「50%」→「15~20%」
設定値の意味:充電電流がどの値まで絞られた時に充電を終了するかを決定します。あまり大きい値だと過放電の危険があるため、15〜20%が適切とされています。
✅ 設定3:放電終了電圧(カット電圧)
ニッケル水素電池の場合、1セルあたり0.9Vが最低ラインです。ミニ四駆は2本使用するため、2セルで1.80Vに設定します。
| 電池本数 | 設定電圧 | 備考 |
|---|---|---|
| 1本(1セル) | 0.9V | 単セル使用時 |
| 2本(2セル) | 1.8V | ミニ四駆標準 |
| 安全マージン | 2.0V | より安全に運用したい場合 |
⚠️ 0.9V以下まで放電すると「過放電」となり、電池が使い物にならなくなるので注意が必要です。
✅ 設定4:クーリングファンとデルタピーク
その他の推奨設定として:
- クーリングファン:「ON」または「AUTO」に設定(電池やモーターの冷却に使用可能)
- デルタピーク検知:サイクル充電中は「3mV」程度が推奨(電池の寿命を守るため)
- トリクル充電:慣らし中は基本「OFF」推奨
これらの設定を済ませることで、サンダー充電器の性能を最大限に引き出す準備が整います。
ミニ四駆サンダー充電器の実践的な使い方とテクニック
- 電池の充電・放電の基本操作方法
- サイクルモードで電池を管理するコツ
- モーター慣らしと回転数測定の実践テクニック
- まとめ:ミニ四駆サンダー充電器の使い方を習得しよう
電池の充電・放電の基本操作方法
サンダー充電器を使った電池管理の基本は、適切な充電と放電にあります。それぞれの操作方法を見ていきましょう。
📝 充電の基本手順
ミニ四駆でニッケル水素電池を充電する場合、主に**マニュアル充電(定電流充電)**を使用します。
STEP1:PROGRAM SELECT → NiMH battery
STEP2:NiMH CHARGE → Man(マニュアル)を選択
STEP3:充電電流値を設定(例:1.0A)
STEP4:ENTER長押しで充電スタート
💡 充電電流の目安
| 充電方式 | 電流値 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1C充電(基本) | 1.0A | 約1時間で充電完了 |
| 低負荷充電 | 0.5A | 電池に優しい、時間がかかる |
| 慣らし中 | 1.0A | バランスの良い設定 |
充電画面には「電池の種類」「電流」「電池の電圧」「充電中CHG」「充電容量」「経過時間」が表示されます。設定値まで充電完了するか、STOPボタンを押すことで終了します。
📝 放電の基本手順
サンダーの優れた放電性能を活用するための手順です。
STEP1:PROGRAM SELECT → NiMH battery
STEP2:NiMH DISCHARGE
STEP3:放電電流値を設定(例:5.0A)
STEP4:放電終了電圧(カット電圧)を設定(2本で1.80V)
STEP5:ENTER長押しで放電スタート
STEP6:放電完了後、自動的にしぼり放電開始
しぼり放電中の表示:「DSC」と「D>>」が交互に点滅し、電流値が徐々に減少します。Discharge Reduseの設定が「15〜20%」なら、0.15〜0.20Aになった時点で完了し、画面に「DONE」と表示されます。
⚡ 重要なポイント:サンダーで大電流放電(5.0A)を行うと電池がかなり熱くなります。必ず扇風機などで電池を冷やしながら作業してください。
サイクルモードで電池を管理するコツ
サイクルモードは、充放電を自動的に繰り返す機能で、電池のメモリー効果を減らし、性能を維持するために重要です。
🔄 サイクルモードの設定手順
STEP1:PROGRAM SELECT → NiMH battery
STEP2:NiMH CYCLE
STEP3:サイクル回数を設定(画面右上の数字)
STEP4:充電と放電の順番を選択
「C>D」:充電→放電
「D>C」:放電→充電
STEP5:充電の種類を選択(オート or マニュアル)
STEP6:ENTER長押しでスタート
📊 サイクルモードの活用シーン
| 目的 | 設定例 | 効果 |
|---|---|---|
| 新品電池の慣らし | D>C、10〜30サイクル | 眠っていた電池を起こす |
| リフレッシュ | D>C、5〜10サイクル | メモリー効果の除去 |
| レース後の保管 | D>C、10サイクル | 次回使用時の準備 |
INCボタンを押すことで、サイクル中にこれまでの充電容量と放電容量を確認することも可能です。この機能により、電池の状態を数値で把握できます。
サイクルモードで充放電を行うと、電池がめちゃくちゃ熱くなりますので、扇風機などで電池を冷やしながら行ってください。
出典:ミニ四駆作ってみた
一般的には、走行後の電池は必ずアナライズをかけて状態を確認し、ペアを組み直してからサイクルで充放電を行って保管することが推奨されています。
モーター慣らしと回転数測定の実践テクニック
サンダー充電器の大きな魅力の一つが、モーター慣らしにも使えるという点です。モータードライブモード機能を活用することで、安定した電圧でのモーター管理が可能になります。
⚙️ モータードライブモードの設定
STEP1:PROGRAM SELECT → Special modes
STEP2:MOTOR DRV
STEP3:時間を設定(1min〜240min)
STEP4:最大出力電流を2.0Aに設定
STEP5:モーターを回す電圧を設定(測定時は3.0V)
STEP6:ENTER長押しでスタート
🎯 電流と電圧の推奨設定
| 項目 | 設定値 | 理由 |
|---|---|---|
| 電流(A) | 2.0A | モーターショート時の過電流から保護 |
| 電圧(V) | 3.0V | 回転数測定の業界標準 |
| 慣らし時間 | 用途により変動 | モーターやブラシの種類に応じて調整 |
電圧を3.0Vに設定しておくことで、他のサンダーユーザーと同じ条件での回転数測定が可能になります。これにより、モーターの性能を客観的に比較できます。
🔍 モーター慣らしのポイント
サンダーの利点は、出力電圧が安定していること。他のモーター慣らし機のように電圧が変動することがないため、長時間のモーター慣らしでも一定の条件を維持できます。
モーター慣らしのやり方は、使用するモーターや個人によって変わってくる部分です。おそらく一般的には:
- 銅ブラシモーター:高電圧・短時間での慣らし
- カーボンブラシモーター:低電圧・長時間での慣らし
画面にはモーターの消費電流なども表示されるため、モーターの状態や性能を簡易的に把握することもできます。
⚠️ 安全上の注意:モーター慣らし中は必ず監視し、煙が出たり異常な熱を持った場合はすぐに中止してください。
まとめ:ミニ四駆サンダー充電器の使い方を習得しよう
最後に記事のポイントをまとめます。
- サンダー充電器はアンチマターやリアクターと性能面で同等の機器である
- 使用には別途安定化電源やバッテリーホルダーなどの周辺機器が必須
- 初期設定として消音・しぼり放電・カット電圧・デルタピークの調整が重要
- しぼり放電機能により電池の容量を極限まで抜くことが可能
- マニュアル充電は1.0Aが基本、放電は5.0Aで大電流放電ができる
- サイクルモードで自動的に充放電を繰り返し電池を管理できる
- モータードライブモードで安定した電圧でのモーター慣らしが可能
- 3.0V設定で回転数測定を行うことが業界標準となっている
- 充放電時は電池が高温になるため冷却しながらの作業が必須
- 初期費用は本体と周辺機器合わせて12,000円前後を見込む必要がある
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- 【ミニ四駆】充放電器「THUNDER」購入!使い方・操作方法 : サブカル”ダディ”ガッテム日記
- 【解説】THUNDER(サンダー)の使い方|電池の充放電からモーターの慣らしや測定まで | ムーチョのミニ四駆ブログ
- 【ミニ四駆】HOTA THUNDER をもう少し説明する 【動画連結記事】 : “やき=う始めました”がミニ四=駆始めました
- ミニ四駆作ってみた〜その455「電池管理 〜ThunderとC4を使って〜」 – ミニ四駆作ってみた
- P!的充電器レビュー 「106B+系」|P lab co.ltd.,ウチダケイ/ポラ
- 充電器廃人学生によるミニ四駆の充電器についての考察|Shoya H.
- Amazon.co.jp: THUNDER 250W DCバランス充電器ディスチャージャー
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当ブログをご覧いただきありがとうございます。
このたび、当ブログの記事内容について無断転載とのご指摘を受けました。
事実確認が十分でない部分もありますが、著作権に関わるご迷惑をおかけする可能性を重く受け止め、記事をすべて非公開とし、今後の再確認を進めてまいります。
ご心配・ご不快の念をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後は再発防止に努め、安心してご覧いただけるブログ運営を行ってまいります。