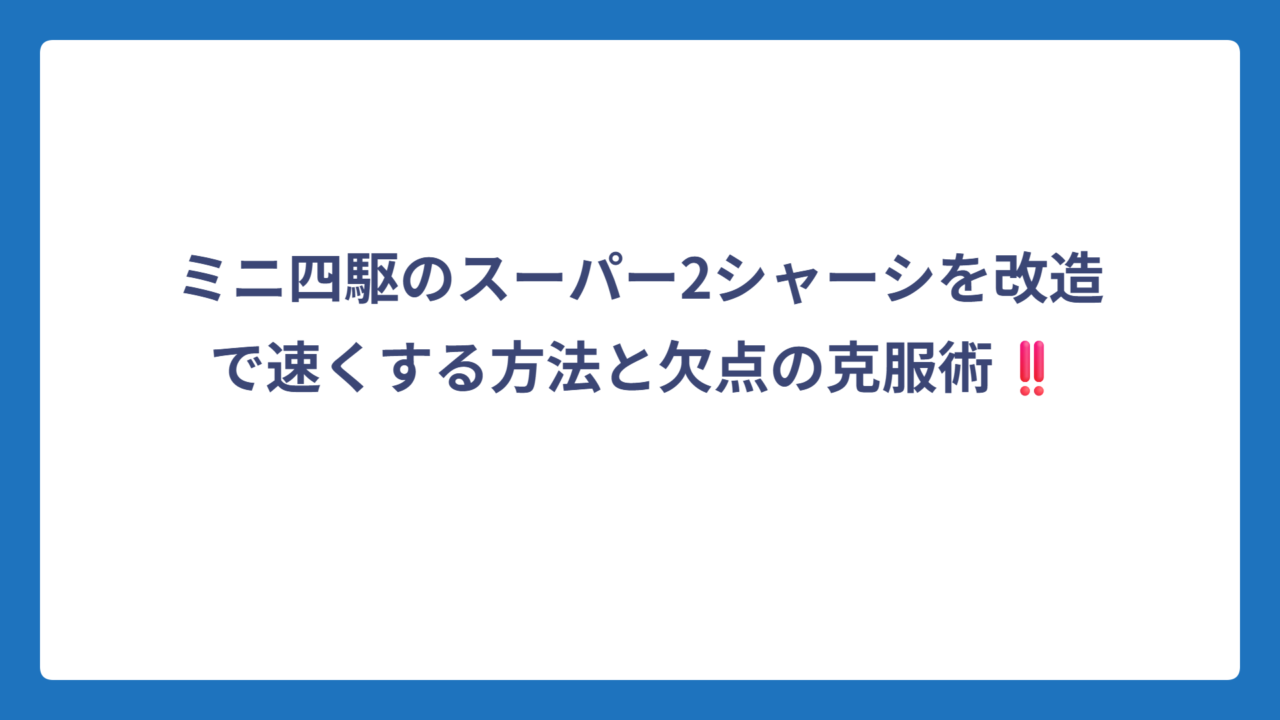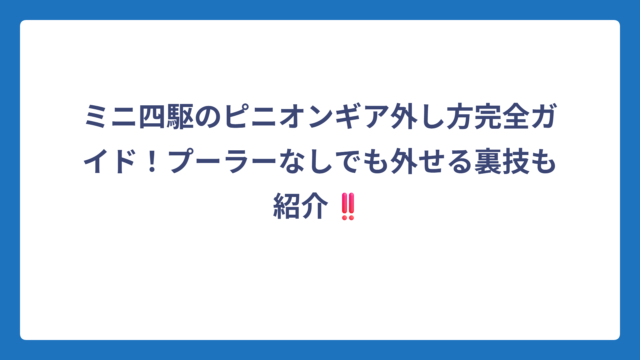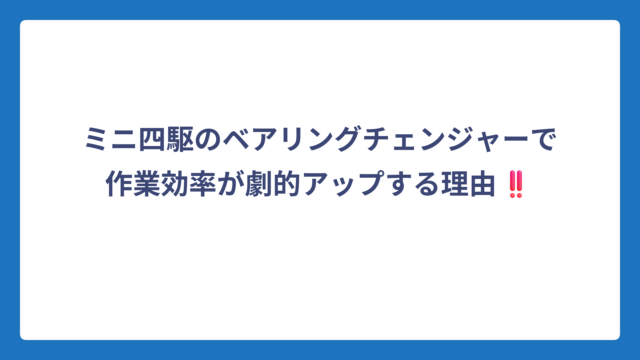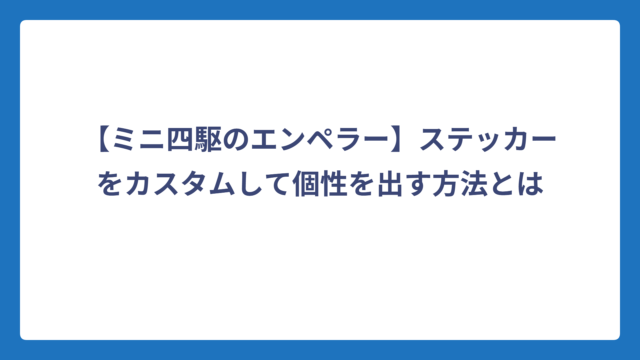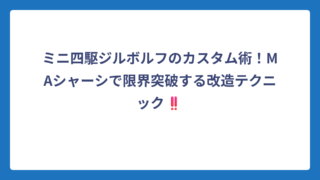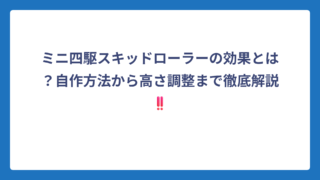ミニ四駆の改造を始めるとき、シャーシ選びは非常に重要な要素です。その中でも「スーパー2シャーシ(スーパーIIシャーシ)」は、2010年に登場した片軸シャーシの進化形として、今でも多くのレーサーに支持されています。特にフルカウルミニ四駆のプレミアム版に採用されることが多く、カーボン強化シャーシが通常キットで手に入るという特徴もあります。
しかし、初めてスーパー2シャーシを手にした方は、「駆動音がうるさい」「改造のポイントがわからない」「フロントバンパーが弱い」といった悩みにぶつかることも少なくありません。この記事では、インターネット上に散らばる改造ノウハウや実践情報を収集し、スーパー2シャーシの特徴から具体的な速くする方法、欠点を克服する改造テクニックまで、幅広く解説していきます。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ スーパー2シャーシの基本的な特徴とメリット・デメリット |
| ✓ 駆動調整や騒音対策など速くするための具体的な改造方法 |
| ✓ 初心者向けの無加工改造とB-MAX仕様の作り方 |
| ✓ カーボン強化シャーシと通常シャーシの使い分け |
スーパー2シャーシの基本特性とミニ四駆改造における位置づけ
- スーパー2シャーシは軽量性が最大の強み
- 豊富なカラーバリエーションと強化シャーシの存在
- 駆動調整の必要性とフロント周りの課題
- 無加工改造とガチマシンの両立が可能
スーパー2シャーシは軽量性が最大の強み
スーパー2シャーシの最も注目すべき特徴は、現行シャーシの中で最軽量クラスの約115gという重量です。ミニ四駆の速度は車体重量に大きく影響されるため、この軽さは非常に大きなアドバンテージとなります。
📊 主要シャーシの重量比較
| シャーシ名 | 重量 | 特徴 |
|---|---|---|
| スーパー2 | 約115g | 最軽量クラス、片軸駆動 |
| MA | 約120g~ | 軽量で改造しやすい |
| MS | 約130g~ | 剛性が高く安定性に優れる |
| VZ | 約125g~ | バランス型、拡張性高い |
さらに、スーパー2シャーシはスーパー1シャーシの後継機として開発されており、前身の弱点だったバンパー強度や拡張性が大幅に改善されています。初期のスーパー1で問題となっていた強度不足が解消され、ダッシュモーター使用時の立体コースにも十分耐えられる設計になりました。
素材についても、初期のマグナムセイバープレミアムやソニックセイバープレミアムではポリカABS樹脂を採用し、さらにビクトリーマグナムプレミアムやバンガードソニックプレミアムではカーボン配合ナイロン樹脂のシャーシが通常品番で手に入るという大きな特徴があります。
豊富なカラーバリエーションと強化シャーシの存在
スーパー2シャーシは、他のシャーシと比較して圧倒的にカラーバリエーションが豊富です。これは動物系のミニ四駆(パンダ、しろくまっこ、ドッグ、ホークなど)に多く採用されていることも理由の一つです。
🎨 入手可能なシャーシカラー例
| カラー | 素材 | 主な採用車種 |
|---|---|---|
| カーボングレー | カーボン強化 | ビクトリーマグナム、バンガードソニック |
| ブラック | ABS/ポリカABS | 多数の車種 |
| ホワイト | ABS | スピンコブラ、自由皇帝など |
| ライトグリーン | ABS | ミニ四駆ドッグ |
| メタリックグリーン | ABS | 地平プレミアムなど |
特筆すべきは、カーボン強化シャーシが限定品ではなく通常キットとして入手できる点です。一般的に、カーボン強化シャーシは特別企画商品やプレミアムアイテムとして高価になりがちですが、スーパー2シャーシの場合は比較的手に入れやすい価格帯で提供されています。
ビクトリーマグナムプレミアムとバンガードソニックプレミアムに付属するカーボンシャーシは非常に丈夫で、駆動音も静かという特徴があります。
駆動調整の必要性とフロント周りの課題
スーパー2シャーシの最大の欠点は駆動周りの調整が必要という点です。片軸シャーシの宿命として、プロペラシャフトやカウンターギヤの位置調整をしっかり行わないと、本来の性能を発揮できません。
⚠️ 調整が必要な主な箇所
- ✓ カウンターギヤの固定と位置出し
- ✓ プロペラシャフトの長さ調整と上下のブレ対策
- ✓ クラウン・スパーギヤの噛み合わせ調整
- ✓ モーターの固定とブレ防止
- ✓ ペラシャの頭部加工による干渉回避
特にプロペラシャフトについては、VZシャーシよりも長く設定する必要があるものの、クラウンとの噛み合い位置が非常に奥に入っているため、実質的には片軸シャーシの中で最も短いペラシャ位置になるという特徴があります。
リアのペラシャ浮きを抑えるため、ギアカバー裏へポリカ片を貼り付けて押さえることで「ティンティンティン」という金属音を大幅に軽減できます。
また、フロントバンパーについては改良されたとはいえ、バンパーレス加工後の強度低下やブレーキ調整の難しさという課題が残っています。フロント部分の高さが限られているため、思うようなブレーキセッティングができないケースもあります。
無加工改造とガチマシンの両立が可能
スーパー2シャーシの魅力の一つは、初心者向けの無加工改造からガチマシンまで幅広く対応できるという柔軟性です。
無加工改造の場合、AOパーツの「EXサイドステー」を使用することで、本来スーパー2シャーシにはないサイドステーを追加でき、サイドマスダンパーの取り付けも可能になります。さらに、ファーストトライパーツセットのパーツとの相性も良く、B-MAX仕様としても活用できます。
一方、ガチマシンを目指す場合は、駆動周りの徹底的な調整が必要になります。しかし、その手間をかけた分、軽量性を活かした高速マシンを構築できるという大きなメリットがあります。
📌 改造レベル別の特徴
| 改造レベル | 必要な加工 | 向いている用途 |
|---|---|---|
| 無加工・初心者向け | GUPのポン付けのみ | B-MAX、ストッククラス |
| 中級者向け | 駆動調整、軽量化 | チューン系モーター使用 |
| 上級者向け | 徹底的な駆動調整、補強 | ハイパワーモーター使用 |
スーパー2シャーシを速くする改造テクニックと欠点克服法
- 駆動周りの調整で静音化と速度向上を実現する方法
- カーボン強化シャーシとポリカABSの使い分けと特性理解
- フロントバンパーの強度アップとブレーキ調整のコツ
- まとめ:ミニ四駆のスーパー2シャーシを使いこなすポイント
駆動周りの調整で静音化と速度向上を実現する方法
スーパー2シャーシを速くするために最も重要なのは、駆動ロスを最小限に抑える調整です。特にポリカABSシャーシの場合、無加工だと「カラカラ」とペラシャが弾かれるような音が出やすく、これが駆動ロスの原因になっています。
🔧 具体的な駆動調整の手順
1. プロペラシャフトの上下ブレ対策
- ギヤカバー裏にポリカ片やFRP端材を貼り付けて、ペラシャの浮きを押さえる
- 特にリア側のペラシャ浮きが騒音の主原因となるため、重点的に対策
2. カウンターギヤの固定
- カウンターギヤカバーをしっかり押さえつけて固定
- ワンロックギヤカバー(GP.438)の使用で、メンテナンス性と固定力を両立
3. モーターの固定
- モーターホルダーの爪部分とモーター背面が当たる小さい壁にマルチテープを貼る
- 左右のブレを抑えることで、モーターの力を確実にカウンターギヤへ伝達
4. ギヤの位置出し
- 小ワッシャーとアルミスペーサー小を使用してギヤとホイールのブレを抑制
- クラウンギヤとスパーギヤの間にある壁を切り取り、干渉を防ぐ
5. ペラシャの長さ調整と頭部加工
- S2用の適切な長さに新造(VZ用より長めに設定)
- クラウンのヘソに近づきすぎる場合は、ペラシャ頭部を削って干渉を回避
ギヤの噛み合わせが安定したことで、走行音が良くなり、馴染んできてスピードが上がってきました。
これらの調整を行うことで、おそらく駆動効率が大幅に向上し、同時に騒音も軽減されるでしょう。特にカーボン強化シャーシの場合は、最初から駆動音が静かな傾向にありますが、通常のABSやポリカABSの場合は上記の対策が効果的です。
カーボン強化シャーシとポリカABSの使い分けと特性理解
スーパー2シャーシには複数の素材バリエーションがあり、それぞれに特徴があります。改造の目的や使用するモーターによって、最適な素材を選ぶことが重要です。
📊 素材別の特性比較
| 素材タイプ | 耐久性 | 加工性 | 駆動音 | 入手性 | おすすめ用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| カーボン強化 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | 静か | 普通 | ハイパワーモーター使用時 |
| ポリカABS | ★★★★☆ | ★★★★☆ | やや大きめ | 良好 | バランス重視、中級者向け |
| 通常ABS | ★★★☆☆ | ★★★★★ | 普通 | 良好 | 初心者、コスト重視 |
| 蛍光カラー | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ | 普通 | 特別企画 | 見た目重視(改造は慎重に) |
カーボン強化シャーシの特徴
最も丈夫で最も駆動音が静かですが、ノコギリが痛むくらい丈夫なシャーシなので加工再現性が低く、大量所有は難しいです。フルパワーのスピードとトルクで走るマシンに使用するのが適しています。
カーボン強化シャーシは、タミヤのGUP「強化ギヤ&ワンロックギヤカバー(スーパーIIシャーシ用)」にも採用されており、滑りも向上しているため性能面では優れています。ただし、加工の手間がかかるため、メインマシンとして1台を徹底的に仕上げる場合に適しているでしょう。
ポリカABSの特徴
耐久性と加工性のバランスが最も良いのがポリカABSです。フロント軸受けの破損リスクはあるものの、タイヤのブレとAパーツの歪みのケアをしっかり行えばほぼ割れません。ただし、無加工だと駆動音がうるさいという欠点があります。
蛍光シャーシの注意点
蛍光カラーシャーシ(ピンク・イエロー、オレンジ・グリーンなど)は見た目が魅力的ですが、丈夫さに関しては最低クラスです。蛍光塗料や蛍光剤の添加がシャーシ素材の結合力に悪影響を与えている可能性が高く、フロント軸受け、バンパー基部、モーターマウントフレームなど多くの箇所で破損リスクが高まります。使用する場合は、カーボンプレートでガチガチに補強するか、ノーマルやレブチューン用のマシンとして使用することをおすすめします。
フロントバンパーの強度アップとブレーキ調整のコツ
スーパー2シャーシの課題の一つが、バンパーレス加工後のフロント周りの強度とブレーキ調整です。バンパーカット自体は簡単ですが、その後の対策が重要になります。
🛡️ フロントバンパー強化の方法
1. フロントアンダーガードの活用
- ローラー用ビスの引っかかり防止だけでなく、バンパー強度の補強にも効果的
- スーパー2シャーシのバンパーの弱点をカバーできる
2. リヤステー用FRPのフロント転用
- バンパーの根元部分でビス止めすることで、バンパーを根本から強化
- スーパー2シャーシは84mm幅のビス穴が追加されており、追加パーツなしでローラー幅を広げられる利点も
3. カーボンプレートでの補強
- 特に蛍光シャーシやノーマルABSを使用する場合は、カーボン補強が効果的
- フロントバンパー全体をカーボンプレートで覆うような補強も検討の余地あり
📏 ブレーキ調整の工夫
スーパー2シャーシはフロント部分の高さが無いため、通常のブレーキセッティングが難しいという課題があります。
25mm以下のタイヤでは1mmブレーキも貼れないという弱点がありますが、だからこそ「電池抜き重量120g、ローハイトタイヤ真円出しのみ26mm、スーパーハード超速」という組み合わせを発見できました。
この課題への対応として、以下のアプローチが考えられます:
✅ ブレーキ調整のポイント
- 26mm径のペラタイヤを使用することで、フロントブレーキの調整幅を確保
- 小径タイヤを使用する場合は、スプリントダッシュに特化した割り切った設定に
- チューン系モーターの速度域であれば、強度をそこまで求めなくても対応可能
まとめ:ミニ四駆のスーパー2シャーシを使いこなすポイント
最後に記事のポイントをまとめます。
- スーパー2シャーシは現行シャーシの中で最軽量クラスの約115gという大きなメリットがある
- カーボン強化シャーシが通常キットで手に入るのはスーパー2シャーシの大きな特徴である
- 豊富なカラーバリエーションにより、マシンデザインに合わせたシャーシ選びが可能
- 駆動周りの調整が必須であり、特にプロペラシャフトの上下ブレ対策が重要
- ポリカABSシャーシは耐久性と加工性のバランスが良いが、無加工では駆動音が大きい
- カーボン強化シャーシは最も丈夫だが加工が難しく、ハイパワーマシン向き
- 蛍光カラーシャーシは破損リスクが高いため、使用には注意が必要
- バンパーレス加工後はフロントアンダーガードなどで強度補強が効果的
- 26mm径タイヤの使用でブレーキ調整の自由度が高まる
- 無加工改造からガチマシンまで幅広く対応できる柔軟性がスーパー2シャーシの魅力
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- じおんくんのミニ四駆のぶろぐ – S2の良いところを独自の目線で紹介
- ミニ四駆改造マニュアル@wiki – SUPER 2
- じおんくんのミニ四駆のぶろぐ – めちゃくちゃ深堀りS2シャーシ
- サブカル”ダディ”ガッテム日記 – S2シャーシ駆動チェック
- みそじで復活!!ミニ四駆改造奮闘記 – スーパーⅡシャーシを速くする
- タミヤ公式オンラインストア – ソニックセイバー プレミアム
- ムーチョのミニ四駆ブログ – スーパー2シャーシの改造
- みそじで復活!!ミニ四駆改造奮闘記 – FMS2バッテリー加工編
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当ブログをご覧いただきありがとうございます。
このたび、当ブログの記事内容について無断転載とのご指摘を受けました。
事実確認が十分でない部分もありますが、著作権に関わるご迷惑をおかけする可能性を重く受け止め、記事をすべて非公開とし、今後の再確認を進めてまいります。
ご心配・ご不快の念をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後は再発防止に努め、安心してご覧いただけるブログ運営を行ってまいります。