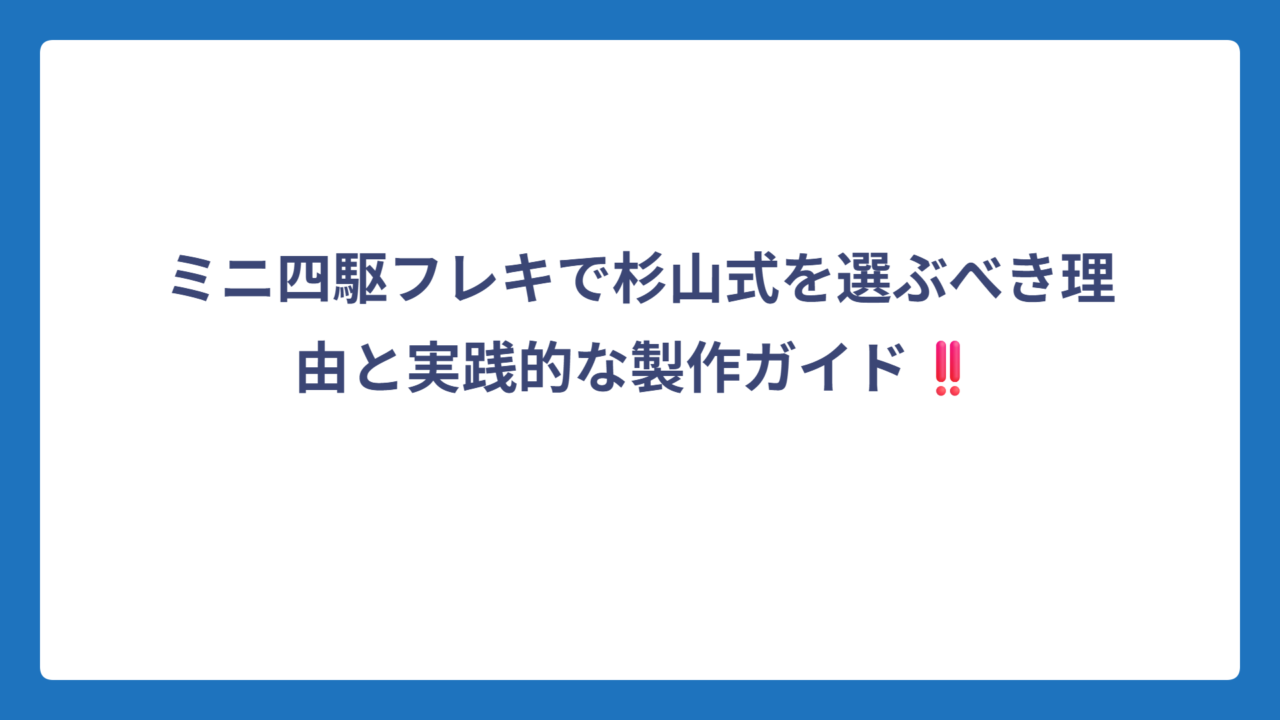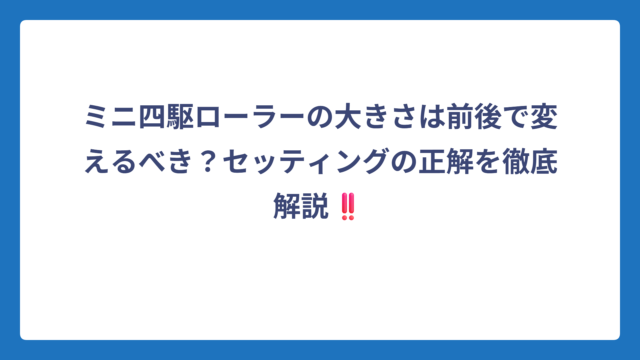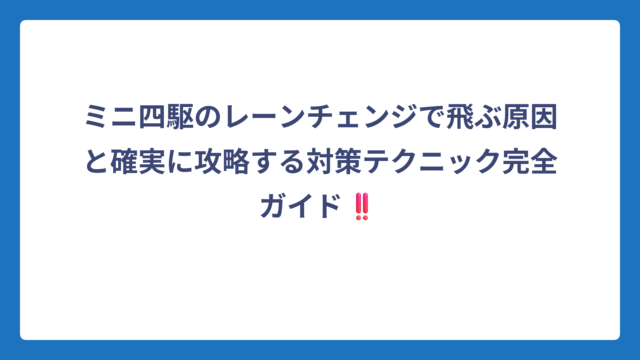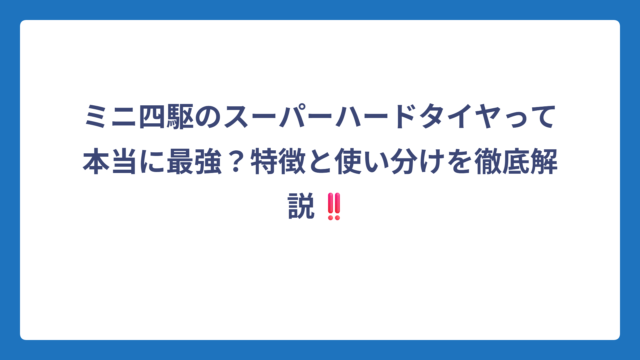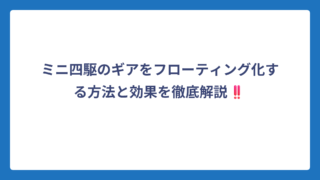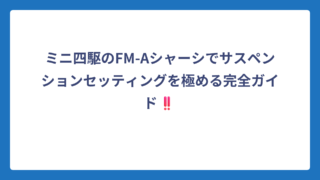ミニ四駆の改造の中でも「フレキ」は上級者向けの手法として知られていますが、その中でも「杉山式フレキ」という製作方法があるのをご存じでしょうか。インターネット上を調査してみると、フレキには複数の種類があり、それぞれに特徴や製作難易度の違いがあることがわかりました。杉山式フレキは軸を残すタイプの加工法で、バネの加工にはニッパーとデザインナイフといった身近な工具で対応でき、センターシャーシの加工では軸の高さを基準にしてサスペンションの沈み込み深さを調整するという特性を持っています。
今回は、杉山式フレキについて基本的な特徴から製作時のポイント、さらにMSフレキの軽量化や提灯製作といった関連する改造テクニックまで、幅広く情報を整理してお届けします。フレキ製作に興味があるけれど何から始めればいいかわからない方、すでにフレキを作っているけれど杉山式の詳細を知りたい方にとって、参考になる内容をまとめました。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ 杉山式フレキは軸を残すタイプの加工法でサス調整がしやすい |
| ✓ バネ加工にはニッパーとデザインナイフという身近な工具で対応可能 |
| ✓ MSフレキを含むフレキ製作には多様な方式があり自分に合った方法選びが重要 |
| ✓ 提灯製作や軽量化など周辺の改造知識も速さ向上に直結する |
ミニ四駆フレキにおける杉山式の基本と特徴
- 杉山式フレキとは何か?軸を残す加工方法の基本を理解する
- 杉山式フレキのバネ加工はニッパーとデザインナイフで簡単にできる
- 杉山式フレキのセンターシャーシ加工は軸の高さを基準にする
杉山式フレキとは何か?軸を残す加工方法の基本を理解する
杉山式フレキは、フレキシブルマシン(通称フレキ)の製作方法の一つです。ネット上の情報を整理すると、フレキの種類には軸残しタイプと軸無しタイプがあり、杉山式は軸を残すタイプに分類されることがわかりました。
軸を残すことで、サスペンションの沈み込みをコントロールしやすくなり、マシンの挙動を安定させやすいという特徴があります。一方で軸無しタイプ(おじゃ式フレキなど)は別の調整方法を用いるため、同じフレキでも走り方が大きく変わってくるようです。
📊 フレキの主な種類と分類
| フレキの種類 | 特徴 | 代表的な方式 |
|---|---|---|
| 軸残しタイプ | 軸を残してサスの基準点を作る | 杉山式フレキ |
| 軸無しタイプ | 軸を完全に取り除き自由度を高める | おじゃ式フレキ |
| その他 | DKフレキなど独自の構造を持つ | DKフレキ |
一般的には、フレキ初心者には軸残しタイプの方が調整の基準が明確で取り組みやすいとされているようですが、最終的には自分のマシンの特性や走らせ方に合った方式を選ぶことが重要です。
杉山式フレキのバネ加工はニッパーとデザインナイフで簡単にできる
バネの加工というと専用工具が必要なイメージがありますが、杉山式フレキの場合はニッパーとデザインナイフという身近な工具で加工が可能です。
杉山式フレキのバネ加工には特殊な工具は不要で、ニッパーとデザインナイフで対応できる
出典:杉山式フレキのバネはニッパーとデザインナイフで簡単に加工できます!
この手軽さが杉山式フレキの魅力の一つといえるでしょう。ただし、バネの種類によって硬さや特性が変わるため、スラダンバネ、樽バネ、あるいはバネなしといった選択肢の中から、自分のマシンセッティングに合ったものを選ぶ必要があります。
🔧 バネ加工に必要な工具リスト
| 工具名 | 用途 | 注意点 |
|---|---|---|
| ニッパー | バネの切断・調整 | 強度のあるものを使用すること |
| デザインナイフ | 細かい削り作業 | 刃の角度を意識して使用 |
| リューター(任意) | より精密な加工 | なくても製作可能 |
薄刃ニッパーなど刃こぼれしやすい工具は避け、強度のあるニッパーを選ぶことが推奨されます。また、バネの硬さや穴の深さ、カットラインなどは個人の加工によって細分化されるため、自分なりの最適解を見つけることが大切です。
杉山式フレキのセンターシャーシ加工は軸の高さを基準にする
杉山式フレキの最大の特徴は、軸を残してセンターシャーシを加工し、サスペンションの沈み込み深さを軸の高さを基準に調整する点にあります。
センターシャーシ加工では軸を残し、サスの沈み込み深さも軸の高さが基準となる
出典:杉山式フレキのセンターシャーシ加工は軸を残して
この加工方法により、サスペンションの動きを視覚的に把握しやすく、調整もしやすくなると考えられます。軸の高さという明確な基準点があることで、再現性の高いマシン製作が可能になるのです。
センターシャーシのカットラインは個人差が大きい部分ですが、軸の高さを基準にすることで調整の指標が得られるのが杉山式の利点です。フレキ製作では調子の良かった作り方を自分で記憶し、同じ性質のものを再現できることが非常に重要になってきます。
MSフレキの実践的な製作テクニックと周辺知識
- MSフレキの軽量化は速さに直結する重要なポイント
- MSフレキでギア干渉を防ぐための構造理解
- MSシャーシのスイッチが固い場合の対処法を知っておく
- 簡単な提灯製作方法で手間を省きながら精度を確保する
- まとめ:ミニ四駆フレキで杉山式を活用するために
MSフレキの軽量化は速さに直結する重要なポイント
フレキ製作において、軽量化は速さに直結する基本的かつ重要な要素です。MSフレキに限らず、シャーシ全体の軽量化を意識することでマシンのポテンシャルを引き出すことができます。
一般的に、ミニ四駆の改造は「引き算」の考え方が基本だとされています。純粋に足し算になるのはモーターなどのパワーソースくらいで、それ以外は基本的にロスを減らし、不要な重量を削っていく作業になります。
✅ 軽量化のための基本的なアプローチ
- 不要なネジの削減:1本のネジにも意味を持たせ、無駄なものは省く
- FRP素材の活用:軽量かつ十分な強度を持つFRP製パーツを選択
- ワッシャーの見直し:必要最小限の使用にとどめる
- パーツ配置の最適化:重心バランスを考慮しながら軽量化
おそらく上級者ほど、ネジ1本の長さや配置にまで意味を持たせているはずです。「なぜそのネジを使っているのか」「なぜその長さなのか」と自問自答しながら組み立てることで、無意識に作るのと比べて大きな差が生まれます。
MSフレキでギア干渉を防ぐための構造理解
MSフレキを製作する際、ギアの干渉問題は避けて通れない課題の一つです。フレキ化によってシャーシの構造が変わるため、ギアとの干渉を防ぐための構造理解が不可欠になります。
📋 ギア干渉を防ぐためのチェックポイント
| チェック項目 | 確認内容 | 対処法 |
|---|---|---|
| センターシャーシの加工精度 | カットラインが適切か | 軸の高さを基準に再調整 |
| パーツ同士の隙間 | 動作時に干渉しないか | テスト走行で確認 |
| ギアの位置関係 | フレキの可動域とギアが干渉しないか | 必要に応じてスペーサーで調整 |
MSシャーシ特有の構造を理解し、フレキ化したときにどの部分が可動するのかを把握しておくことが重要です。加工前に構造をよく観察し、干渉しそうな箇所を事前に確認しておくことで、トラブルを未然に防げる可能性が高まります。
MSシャーシのスイッチが固い場合の対処法を知っておく
MSシャーシを使用していると、スイッチが固くて操作しづらいという問題に直面することがあります。これは新品のシャーシでも起こりうる現象で、スイッチ周辺の構造や組み付け精度が原因と考えられます。
🔧 スイッチが固い場合の対処法(一般的な方法)
- スイッチ周辺のバリや不要な突起を削る
- 接点部分にわずかなグリスを塗布して滑りを改善
- スイッチの可動部分を何度も動かして馴染ませる
- 組み付け時のビスの締めすぎに注意
ただし、これらは一般的な対処法であり、シャーシの状態によって効果は異なるかもしれません。無理に力を入れて破損させないよう、慎重に作業を進めることが大切です。
簡単な提灯製作方法で手間を省きながら精度を確保する
フレキと並んで重要な改造が提灯(ちょうちん)の製作です。提灯はリアの跳ね上がりを抑え、マシンの安定性を高める役割を果たします。しかし、提灯製作は手間がかかる作業というイメージがあるかもしれません。
簡単な提灯製作には「スーパーXシャーシFRPリアローラーステー」と「FRPマルチワイドリアステー」の2つのパーツを組み合わせる方法があり、所要時間は30分未満で精度も良い
出典:簡単!手間いらずで新シャーシに提灯製作!
この方法の利点は以下の通りです:
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 簡単 | カットして組み合わせるだけ |
| 精度が良い | パーツの形状が決まっているため再現性が高い |
| 価格が安い | FRP製で入手しやすい |
| 短時間で完成 | 30分程度で製作可能 |
カットにはリューターがあれば綺麗に仕上がりますが、なければニッパーでも対応できます。ただし、薄刃ニッパーは刃こぼれしやすいため、強度のあるものを使用するよう注意が必要です。
提灯の根元部分の取付穴を斜めに削ることで開度を調整でき、耐久性を高めたい場合は2.5mm穴にハトメを固定したり、3mm穴に真鍮スペーサーを使用したりする方法もあります。
まとめ:ミニ四駆フレキで杉山式を活用するために
最後に記事のポイントをまとめます。
- 杉山式フレキは軸を残すタイプの加工法で、サスの基準点が明確なため調整しやすい
- バネ加工にはニッパーとデザインナイフという身近な工具で対応でき、特殊な工具は不要である
- センターシャーシの加工では軸の高さを基準にすることで再現性の高いマシン製作が可能になる
- フレキには軸残し・軸無し・DKフレキなど複数の方式が存在し、それぞれ走りが異なる
- MSフレキの軽量化は速さに直結し、ネジ1本にも意味を持たせることが重要である
- ギア干渉を防ぐには構造理解が不可欠で、加工前の観察が重要である
- 提灯製作は簡単な方法を使えば30分未満で精度の良いものが作れる
- フレキ製作では調子の良かった作り方を記憶し再現することが大切である
- ミニ四駆の改造は基本的に「引き算」の考え方であり、無駄を省くことがポテンシャル向上につながる
- 同じフレキでも作り手の個性や癖が走りに現れるため、自分のスタイルを確立することが重要である
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- 杉山式フレキのバネはニッパーとデザインナイフで簡単に加工できます!【簡単ホエイル講座 Returns#7】
- 【ミニ四駆】簡単!手間いらずで新シャーシに提灯製作! : サブカル”ダディ”ガッテム日記
- 杉山式フレキのセンターシャーシ加工は軸を残して、サスの沈み込み深さも軸の高さが基準になる。【ホエイル講座Returns#4】
- 走らせ方を考える|紅蓮の太陽
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当ブログをご覧いただきありがとうございます。
このたび、当ブログの記事内容について無断転載とのご指摘を受けました。
事実確認が十分でない部分もありますが、著作権に関わるご迷惑をおかけする可能性を重く受け止め、記事をすべて非公開とし、今後の再確認を進めてまいります。
ご心配・ご不快の念をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後は再発防止に努め、安心してご覧いただけるブログ運営を行ってまいります。