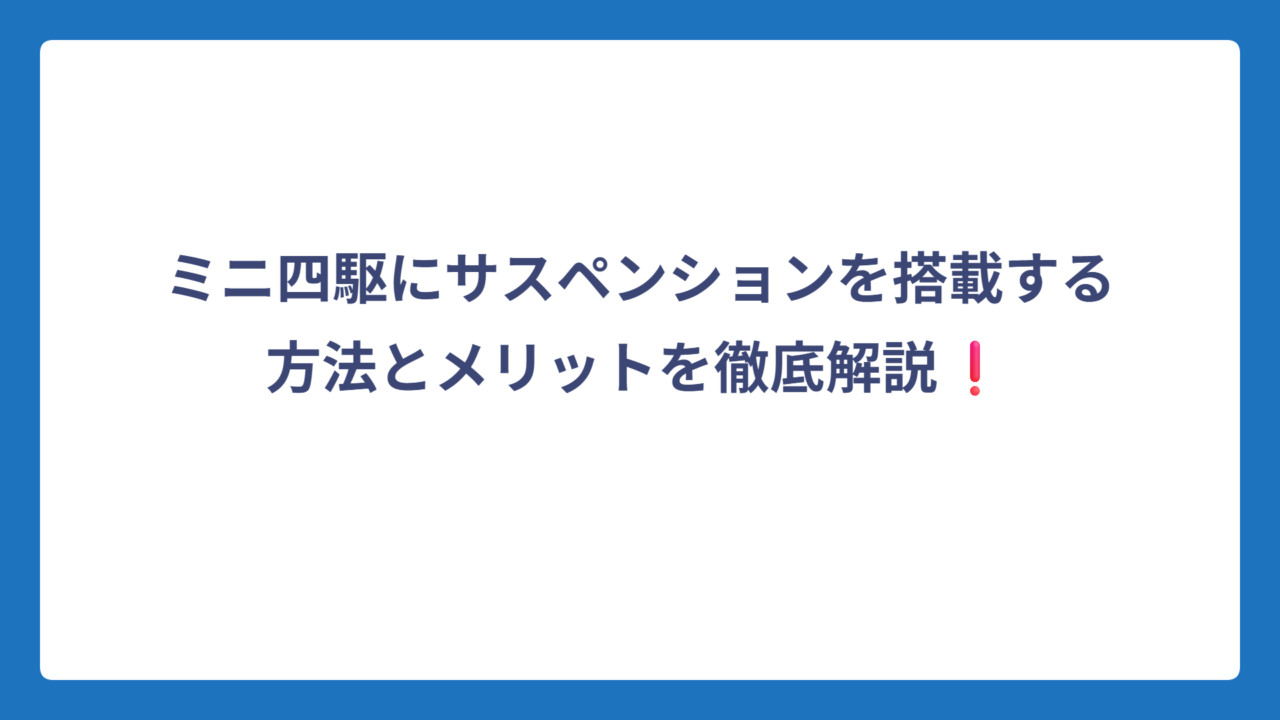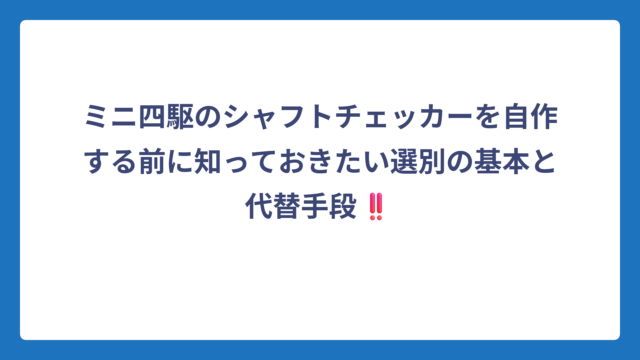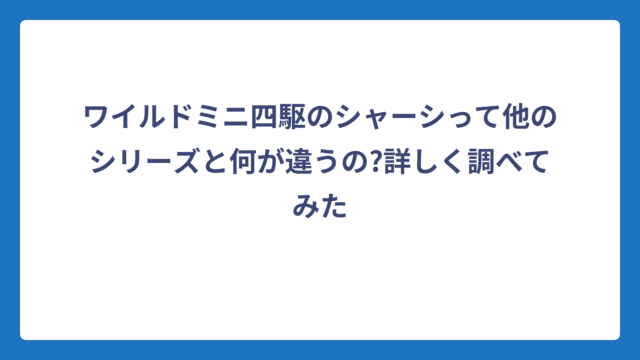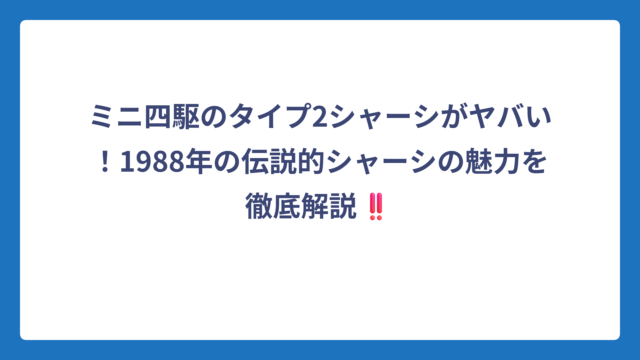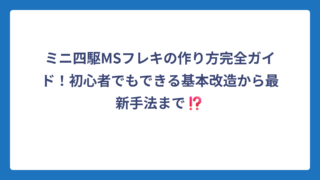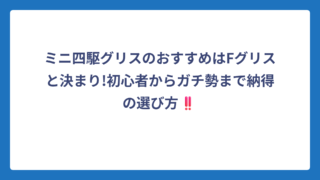ミニ四駆にサスペンションを搭載する改造は、ジャンプ後の着地姿勢を安定させ、コースアウトのリスクを減らす上級者向けのカスタマイズです。MSシャーシやMAシャーシを使った「トレサス(トレーリングサスペンション)」や「MSフレキ」など、さまざまな方式が存在し、それぞれに特徴があります。
この記事では、ミニ四駆のサスペンション改造の基本から、具体的な作り方、各方式のメリット・デメリット、そしてレギュレーションとの兼ね合いまで、網羅的に解説します。サスペンション搭載マシンの可能性と課題を理解することで、あなたのミニ四駆カスタマイズの幅が広がるでしょう。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ ミニ四駆サスペンションの主要な種類と仕組みが理解できる |
| ✓ MSフレキ、トレサス、四輪独立サスなど各方式の特徴がわかる |
| ✓ サスペンション搭載のメリットとデメリットが把握できる |
| ✓ 公式レースでの使用可否やレギュレーションの注意点がわかる |
ミニ四駆サスペンションの基本と種類を理解する
- ミニ四駆サスペンションは着地姿勢の安定化が主目的
- 主要なサスペンション方式は4種類に分類される
- MSシャーシとMAシャーシが改造のベースに最適
- トレサスとMSフレキの違いを理解することが重要
ミニ四駆サスペンションは着地姿勢の安定化が主目的
ミニ四駆におけるサスペンションの役割は、実車とは若干異なります。主な目的はジャンプ後の着地姿勢を制御し、バウンドを抑えて安定した走行を維持することです。
📊 ミニ四駆サスペンションの主な効果
| 効果 | 詳細 |
|---|---|
| 着地姿勢の安定 | ジャンプ後の姿勢を素早く元に戻す |
| バウンド抑制 | 跳ねを抑えてコースアウトを防ぐ |
| 路面追従性向上 | 凹凸のある路面での走行安定性が増す |
| 制振効果 | ウォッシュボード区間での揺れを軽減 |
ミニ四駆へのサスペンション話はその頃からあったと思います。(子供ながらにトライはしてましたw)トレサスが手軽に、本格的に作られるようになったのは両軸が発表された以降と記憶しています。
レーサーミニ四駆の時代から、サスペンションの搭載は多くのレーサーの夢でした。特に立体コースの登場以降、制振技術の必要性が高まり、研究が進められてきた歴史があります。
主要なサスペンション方式は4種類に分類される
ミニ四駆のサスペンション改造は、構造によって大きく4つのタイプに分類されます。
🔧 ミニ四駆サスペンション4大方式
| 方式名 | 特徴 | 難易度 |
|---|---|---|
| 上下反転型系 | シャーシを反転させノーズ・テールユニットを可動 | ★★☆☆☆ |
| シャーシ内蔵系 | ユニット内にショックダンパーを内蔵 | ★★★☆☆ |
| 理想系(トレーリング系) | ギアの噛み合わせを維持したまま可動 | ★★★★☆ |
| 四輪独立系 | 各車輪が独立して可動する本格派 | ★★★★★ |
それぞれの方式には一長一短があり、製作難易度や必要なパーツ、走行特性が大きく異なります。初心者であれば上下反転型系から始めるのが一般的ですが、本格的な性能を求めるならトレーリング系や四輪独立系への挑戦が必要になるでしょう。
MSフレキの登場により情勢が激変、トレサスは「レガシーデバイス」として廃れていきました。理由はMSフレキと比べ、構造上の問題点があった事は否定出来ません。
MSフレキの登場は、ミニ四駆改造シーンに大きな変革をもたらしました。製作の手軽さと効果のバランスが優れていたため、一時期は主流となったのです。
MSシャーシとMAシャーシが改造のベースに最適
サスペンション改造に適したシャーシは限られています。MSシャーシとMAシャーシが最も適しており、特にMSシャーシは3分割構造を活かした改造がしやすい設計です。
📋 サスペンション改造に適したシャーシ比較
| シャーシ | 適性 | 特徴 |
|---|---|---|
| MSシャーシ | ◎ | 3分割構造で改造の自由度が高い |
| MAシャーシ | ◎ | ミッドシップで重量バランスが良い |
| ARシャーシ | ○ | リア駆動で改造事例あり |
| VZシャーシ | △ | 改造事例が限定的 |
| 旧シャーシ | △ | 構造上の制約が多い |
現在はMS シャーシ とAR シャーシ での製作が確認されています。果たして、旧 シャーシ で作製する猛者は現れるのだろうか?
MSシャーシの3分割構造は、センターシャーシを軸にフロント・リアユニットが独立して動く仕組みを作りやすく、サスペンション改造の理想的な土台となっています。
トレサスとMSフレキの違いを理解することが重要
「トレサス」と「MSフレキ」は、どちらもミニ四駆のサスペンション改造を指す言葉ですが、厳密には構造と効果が異なります。
⚙️ トレサスとMSフレキの比較
| 項目 | トレサス | MSフレキ |
|---|---|---|
| 正式名称 | トレーリングサスペンション | MSフレキシブル |
| 構造 | ダイレクトドライブ維持型 | バネで柔軟性を付与 |
| ギアの噛み合い | 常に一定 | 可動時に変化 |
| 製作難易度 | 高い | 中程度 |
| 部品点数 | 多い | 比較的少ない |
トレサスの最大の特徴は、サスペンションが稼働してもギアの噛み合わせが維持される点です。これによりダイレクトドライブの利点を保ちながら、制振効果を得られます。
一方、MSフレキはシャーシの3分割構造を活かし、バネで柔軟性を持たせる方式です。製作がトレサスよりも容易で、一時期は主流となりました。ただし、サス稼働時にギアの噛み合わせが物理的に変化するため、トルク抜けが発生する可能性があります。
このタイプのトレサスの長所は、サス車でありながらダイレクトドライブ(常にカウンターとスパーが一定に噛み続ける事)です。
どちらの方式を選ぶかは、求める性能と製作スキル、投入できる時間によって判断すべきでしょう。
ミニ四駆サスペンション改造の実践と注意点
- 上下反転型MSフレキの作り方と課題
- トレーリングサスペンション(トレサス)の製作ポイント
- 四輪独立サスペンションは最高難度の改造
- サスペンション改造で生じるデメリットへの対策
- まとめ:ミニ四駆サスペンションは技術とロマンの結晶
上下反転型MSフレキの作り方と課題
上下反転型のMSフレキは、MSシャーシを上下逆さまにして使用する最もシンプルなサスペンション改造の一つです。
🔨 上下反転型MSフレキの基本工程
| 工程 | 作業内容 |
|---|---|
| ①シャーシ反転 | MSシャーシを上下逆に配置 |
| ②バネの設置 | ノーズ・テールユニットにバネを仕込む |
| ③ワンウェイホイール | ギア離脱時のダメージ軽減 |
| ④ボディ固定方法の変更 | フック・キャッチが逆になるため工夫が必要 |
| ⑤電池落下防止策 | 電池ホルダーが露出するため対策必須 |
✅ 上下反転型のメリット
- 切断などの大規模加工が少ない
- 強度を確保しやすい
- 比較的軽量に仕上がる
❌ 上下反転型のデメリット
- ギアの噛み合わせがおかしくなる(トルク抜け)
- ボディの固定方法を別途考える必要がある
- 電池が外れ落ちるリスクがある
- マスダンパーやオイルダンパーとの併用が必須
サス稼動時にギアの噛み合わせがおかしくなる。(物理的にトルク抜けが起こる)ボディ フックと ボディ キャッチが逆向きの為、別の方法で ボディ を固定しなくてはいけない。
上下反転型は入門には適していますが、本格的な性能を求めるには限界があると言えるでしょう。
トレーリングサスペンション(トレサス)の製作ポイント
トレーリングサスペンション(トレサス)は、ギアの噛み合わせを維持したまま制振効果を得られる理想的な方式です。
🛠️ トレサス製作の重要ポイント
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 精度が命 | カウンター軸=サスアーム支持軸のため高精度が必須 |
| ブレーキ調整 | ブレーキ面自体も沈み込むため効きの制御が難しい |
| ローラー設定 | 稼働時にローラー高さ・角度が変化する |
| 重量増 | 部品点数が多く重くなりがち |
トレサス車の難しい部分は、一番に精度よく作ること(カウンター軸=サスアーム支持軸の為)、車体全てが動く為にブレーキやローラー周りの扱いに難儀する事です。
トレサスの最大の利点は、サス稼働時にギアの噛み合わせが変わらない点にあります。これによりダイレクトドライブの利点(常にカウンターとスパーが一定に噛み続ける)を維持しながら、着地後の姿勢制御が可能になります。
ただし、車体全体が動くため、ブレーキやローラーのセッティングが非常に難しいのが課題です。フレキはブレーキ面が地面に対して概ね一定ですが、トレサスはブレーキ面自体も沈み込むため、効きの制御に高度な技術が求められます。
📌 トレサス製作に必要なパーツ例
- U-工房のミニ四駆サスペンション講座が参考になる
- MS3架、MA2架などシャーシに応じた設計
- ワンウェイホイールの併用が推奨される
- オイルダンパーやマスダンパーで反動を抑制
おそらく、トレサス改造は中級者以上向けの改造と考えるべきでしょう。
四輪独立サスペンションは最高難度の改造
四輪独立サスペンション(ダブルウィッシュボーン系)は、各車輪が独立して上下動する本格的なサスペンションです。
🚗 四輪独立サスの特徴
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 路面に対する高いショック吸収性能 | ドライブシャフト加工で駆動ロス発生 |
| 車高の自由な調整が可能 | コーナリング時に車体がロールする |
| 凹凸路面での走行安定性が最高レベル | ローラーのスラスト角が変化 |
| – | フロントバンパーの強度不足 |
ミニヨンクラブには掲載されていないが、某動画サイトに動画が投稿されている。こちらも関西の某ビルダーによって作製されたもの。
四輪独立サスの製作には、各種パーツの精密な加工と組み立て技術が必要です。
4輪独立サス ミニ四駆で一番面倒な改造と思われる4輪独立サスペンション化をしてみました。ベースキットは、MSシャーシのTRFワークスjrです。
製作事例によると、以下のような部品が必要になります:
📦 四輪独立サス製作に必要な主要パーツ
- アッパーアーム・ロアアーム(バンパーパーツから切り出し)
- サスペンションユニット(東北ダンパーのボールジョイント等)
- センターシャーシの軸受け加工
- ゴムチューブ(ユニバーサルジョイント代わり)
- ギアカバー加工品
- 各種スペーサーとベアリング
一般的には、四輪独立サスは最も製作難易度が高く、上級者向けの改造と言えるでしょう。
サスペンション改造で生じるデメリットへの対策
サスペンション改造には多くのメリットがある一方で、いくつかの課題も存在します。
⚠️ サスペンション改造の主な課題と対策
| 課題 | 対策 |
|---|---|
| 重量増加 | 軽量パーツの採用、不要部分の削減 |
| トルク抜け | ワンウェイホイールの使用 |
| 跳ね返り | マスダンパー、オイルダンパーとの併用 |
| ブレーキ調整難 | 可変スラストブレーキなどの工夫 |
| ローラー制御 | セッティングの試行錯誤 |
| モーター交換の困難さ | 構造を工夫して作業性を確保 |
短所としてジャンプ着地後の前後回転差(加速に入ってるタイヤと浮いてる側の路面との摩擦差、抵抗差と言うべきか)がありますが、それ故にワンウェイホイールがよく使用されます。
特に重要なのが、サスの反動を抑える仕組みです。マスダンパーと併用する、オイルダンパーを組み込むなど、サス自体の反動を別の何かで打ち消さないと、逆に跳ねてしまう可能性があります。
🔍 振り子式サイドマスダンパー/サスペンションの例
市販パーツとして、左右独立型のマスダンパーが上下に振り子のように稼働する「振り子式サイドマスダンパー/サスペンション」も存在します。これはジャンプ後のバウンドを抑える効果があり、スプリングを組み込んだサスペンション機能を備えています。
推測の域を出ませんが、サスペンション改造の成功には、各パーツの精度と全体のバランス調整が鍵になるでしょう。
まとめ:ミニ四駆サスペンションは技術とロマンの結晶
最後に記事のポイントをまとめます。
- ミニ四駆のサスペンションは着地姿勢の安定とバウンド抑制が主目的である
- 主要な方式は上下反転型、シャーシ内蔵型、トレーリング型、四輪独立型の4種類に分類される
- MSシャーシとMAシャーシがサスペンション改造に最適なベースとなる
- トレサスはギアの噛み合わせを維持する理想的な方式だが製作難易度が高い
- MSフレキは製作が比較的容易だがギアの噛み合わせに課題がある
- 上下反転型は入門に適しているがボディ固定や電池落下に注意が必要である
- 四輪独立サスは最高難度の改造で高いショック吸収性能を持つ
- サスペンション改造には重量増加やトルク抜けなどの課題が伴う
- ワンウェイホイールやマスダンパーとの併用で欠点を補う工夫が重要である
- 公式レースではタミヤ純正パーツのみ使用可能なため改造範囲に注意が必要である
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- トレサスはいいぞ(。-∀-)|紅蓮の太陽
- 69 MSフレキについて調べてみたよ – ミニ四駆、もう一度始めてみたよ
- サスペンション – ミニ四駆改造マニュアル@wiki
- 4輪独立サス ミニ四駆|ふじんじのブログ
- ミニ四駆MAシャーシフロント・リアサスペンションマシン製作 : 子育て&ミニ四駆のブログ/Morinokuma
- 【ミニ四駆パーツ】振り子式サイドマスダンパー/サスペンション【レッドVer】
- 【ミニ四駆パーツ】振り子式サイドマスダンパー/サスペンション【ブルーVer】
- TAMIYA – MAサス MAフレキ ミニ四駆 TAMIYA Wサスペンション MS
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当ブログをご覧いただきありがとうございます。
このたび、当ブログの記事内容について無断転載とのご指摘を受けました。
事実確認が十分でない部分もありますが、著作権に関わるご迷惑をおかけする可能性を重く受け止め、記事をすべて非公開とし、今後の再確認を進めてまいります。
ご心配・ご不快の念をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後は再発防止に努め、安心してご覧いただけるブログ運営を行ってまいります。