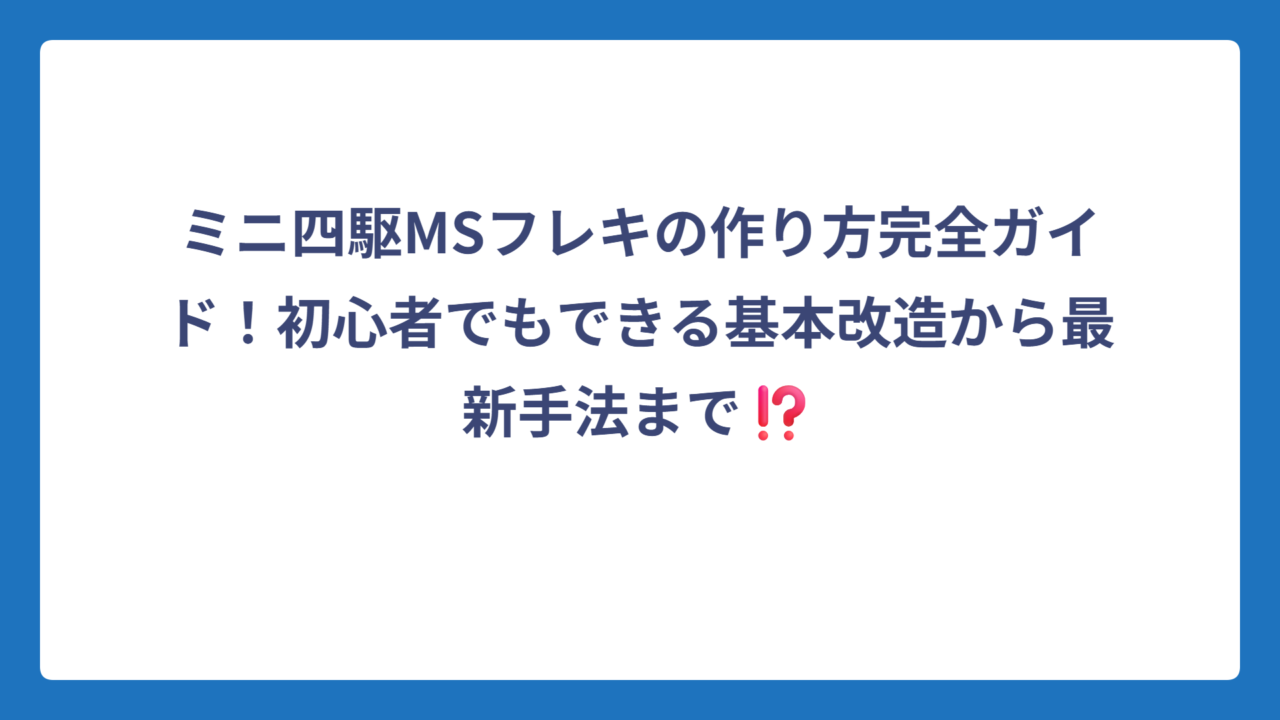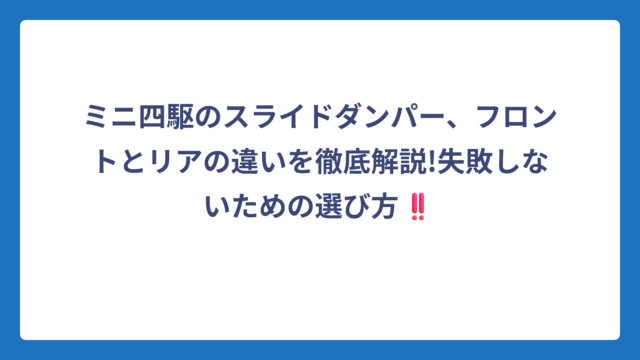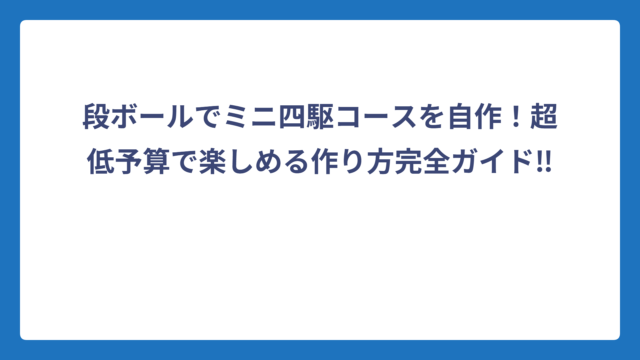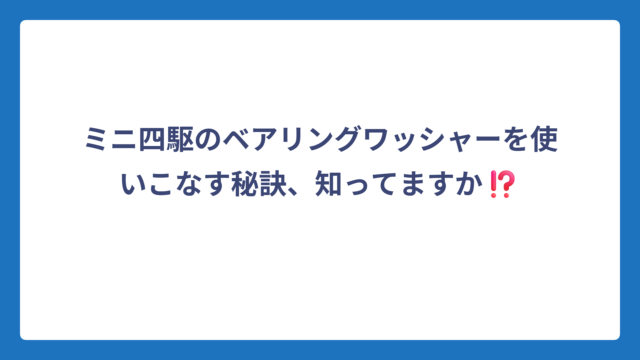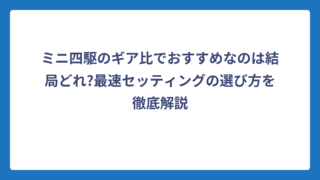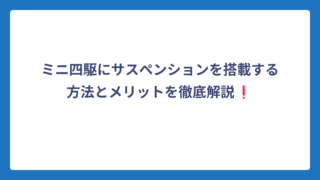ミニ四駆レースで勝ちたいなら、MSフレキという改造は避けて通れません。着地時の衝撃を吸収し、コースアウトを防ぐこの技術は、現在のレースシーンで圧倒的な支持を集めています。しかし「難しそう」「失敗したらどうしよう」と二の足を踏んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、MSフレキの基本的な作り方から最新の加工テクニック、必要な工具やパーツ、さらには陥りがちな失敗例まで、インターネット上の情報を徹底的に調査・分析してまとめました。初心者でも手が届く予算内での製作方法や、治具を使った精度の高い加工方法など、実践的な情報を網�羅的にお届けします。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ MSフレキの基本構造と動作原理が理解できる |
| ✓ 軸残しフレキの具体的な製作手順がわかる |
| ✓ 必要な工具・パーツと予算感が把握できる |
| ✓ よくある失敗例と対処法が学べる |
ミニ四駆MSフレキの基本知識と製作準備
- MSフレキとは衝撃吸収システムを搭載した改造シャーシのこと
- 軸残しフレキが初心者には作りやすくおすすめ
- 基本的な工具とパーツで5,000円以内での製作が可能
MSフレキとは衝撃吸収システムを搭載した改造シャーシのこと
MSフレキとは、MSシャーシを3分割してスプリングを仕込み、サスペンション機能を持たせた改造のことです。
この改造により、ジャンプ後の着地時に発生する衝撃を吸収し、車体の跳ね返りを最小限に抑えることができます。一般的には「フレキシブル加工」とも呼ばれ、現在のミニ四駆レースシーンでは上位入賞マシンのほとんどがこの改造を施しています。
📊 MSフレキの基本構造
| 部位 | 役割 | 特徴 |
|---|---|---|
| センターユニット | 中央の固定部分 | モーターやギヤを搭載 |
| フロントユニット | 前部の可動部分 | スプリングで上下に動く |
| リヤユニット | 後部の可動部分 | スプリングで上下に動く |
| スプリング(バネ) | 衝撃吸収装置 | 前後4箇所に設置 |
MSフレキの最大の特徴は、着地時の「おつり」と呼ばれる跳ね返りを抑制できる点です。通常のリジッド(固定)シャーシでは、着地の衝撃がそのまま車体に伝わり、コースアウトのリスクが高まります。一方、フレキシブルシャーシは衝撃をバネが吸収するため、より高速での走行が可能になります。
ミニ四駆のMSフレキは「速い」というより「安定性が高く、より速い速度でコースを攻略できる」改造
出典:リオンチャンネル
ただし、MSフレキにもデメリットは存在します。バネの動きによるギヤの噛み合わせロスや、シャーシ全体の重量増加などがその代表例です。それでも安定性というメリットが大きく上回るため、レースシーンではMSフレキが主流となっています。
軸残しフレキが初心者には作りやすくおすすめ
MSフレキには「軸残し」と「軸無し」の2つの主流があり、初心者には軸残しフレキがおすすめです。
軸残しフレキは、センターシャーシにある支柱(軸)を残してバネを固定する方法で、バネの位置がズレにくく安定性が高いのが特徴です。一方、軸無しフレキは軸を完全に切り落とす方法で、よりフレキシブルな動きが期待できますが、バネの固定が難しく上級者向けとされています。
🔧 軸残しと軸無しの比較
| 項目 | 軸残しフレキ | 軸無しフレキ |
|---|---|---|
| 加工難易度 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| バネの固定 | 軸で固定(安定) | 接着剤等で固定(不安定) |
| 可動域 | やや制限あり | より広い |
| 初心者向け | ◎ | △ |
軸残しフレキを選ぶ最大の理由は、バネの位置が左右対称に保ちやすいという点にあります。軸無しの場合、車体が動き続けるとバネの位置が徐々にズレる可能性があり、左右で動きが異なると着地時に致命的な影響が出る恐れがあります。
軸無しの場合、バネの両端がどちらもシャーシに固定されていないため、車体がフレキシブルに可動し続けるとバネの位置が少しズレる時がある
軸残しフレキでの課題は、標準のスライドダンパースプリングが軸より内径が小さいという点です。これには主に3つの解決策があります。
✅ 軸残しフレキのバネ問題解決法
- 樽バネ(ダンガンレーサー用)を使用する → 入手困難・高価
- バネを拡張する → 拡張の均一性に注意が必要
- 軸を細く加工する → 専用治具があると便利
一般的には、5mm程度の太さのドライバーにスプリングを差し込んで24時間放置し、バネを拡張する方法が手軽です。あるいは、市販のシャフトスリマー(軸削り治具)を使って軸を細く加工する方法も効果的です。
基本的な工具とパーツで5,000円以内での製作が可能
MSフレキの製作には、基本的な工具とグレードアップパーツがあれば5,000円以内で十分に対応できます。
高価な専用工具や特殊なパーツは必須ではなく、100円ショップで入手できる工具でも製作は可能です。ただし、精度や作業効率を考えると、一部のプラモデル用工具への投資は長期的に見て有効でしょう。
💰 MSフレキ製作に必要な予算内訳
| カテゴリ | 主な内容 | 概算費用 |
|---|---|---|
| キット本体 | MSシャーシマシン | 1,000〜1,500円 |
| グレードアップパーツ | FRPプレート各種、スプリング等 | 2,500〜3,500円 |
| 工具類 | ニッパー、ドリル、のこぎり等 | 0〜2,000円 |
| 合計 | – | 3,500〜7,000円 |
すでに工具を持っている方なら、パーツ代のみで4,000円程度に抑えることも可能です。
🛠️ 最低限必要な工具リスト
- ✓ ニッパー(100均可、タミヤ薄刃推奨)
- ✓ クラフトのこぎり(薄刃タイプ推奨)
- ✓ デザインナイフ(100均可)
- ✓ ドリル刃(2mm、4mm、5.5mm)
- ✓ ドリル用持ち手
- ✓ 棒ヤスリ(100均可)
- ✓ 瞬間接着剤(低粘度タイプ)
- ✓ ドライバー・スパナ
タミヤのドライバーとボックスレンチのセットが1,000円ちょっとで購入でき、普段のミニ四駆でも使用頻度が高く便利
出典:note 3710
📦 必要なグレードアップパーツ例
- ✓ FRPフロントワイドステー×2
- ✓ FRPリヤブレーキセット×2
- ✓ FRPマルチワイドリヤステー×2
- ✓ FRPマルチ補強プレート×3
- ✓ スライドダンパースプリングセット
- ✓ ステンレス皿ビスセット
- ✓ ロックナット
これらのパーツは、Amazonや家電量販店の割引価格を利用すれば定価より安く揃えられることが多いです。特にセール時期を狙えば、さらにコストを抑えられるでしょう。
加工治具については、必須ではありませんが精度向上と時間短縮に大きく貢献します。市販のMSフレキ専用治具は2,500円前後で購入でき、「真っすぐ切れる」「再現性が高い」と高評価を得ています。予算に余裕があれば検討する価値はあるかもしれません。
ミニ四駆MSフレキの具体的な製作手順と注意点
- センターシャーシを3分割してバネを仕込む準備をする
- 前後ユニットの穴拡張と可動域調整が最も重要な工程
- お辞儀防止プレートとグリスアップで完成度を高める
センターシャーシを3分割してバネを仕込む準備をする
MSフレキ製作の第一段階は、センターシャーシを前後ユニットとセンター部分の3つに分割することです。
この工程では、ギヤカバーの少し内側をクラフトのこぎりで切断します。切断位置の精度がフレキの性能を左右するため、マスキングテープで目印をつけてから慎重に作業するのがポイントです。
📐 センターシャーシ分割の手順
| ステップ | 作業内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1 | 切断位置にマスキングテープで印 | ギヤカバーの内側を目安に |
| 2 | クラフトのこで前後を切断 | 地面に対して垂直に切る |
| 3 | 切断時のバリをニッパーで除去 | 細い凸部分も丁寧に処理 |
| 4 | ギヤケース周辺の不要部分をカット | フレキ可動の妨げになる箇所 |
切断の際は、のこ刃をギヤカバーにガイドとして当てながら進めると真っすぐ切りやすくなります。ただし、ギヤカバーは若干斜めに傾いているため、のこ刃全体を当てたまま切ると斜めになってしまう可能性があります。のこ刃の天井部分を少し離して垂直を確認しながら切断しましょう。
切断後は、センターシャーシの軸部分にバネを仕込む準備をします。軸残しフレキの場合、軸を1.5mmアルミスペーサーと同じ高さに切り揃えるのが一般的な方法です。
🔩 軸の加工方法(軸ちょっと残し)
- ✓ 1.5mmアルミスペーサーを軸の横に並べる
- ✓ スペーサーと同じ高さでニッパーで切断
- ✓ 左右の高さを揃えることが重要
- ✓ 切断面を軽くヤスリで整える
この「軸ちょっと残し」の方法は、樽バネを用意しなくても、バネや軸を複雑に加工しなくても、ニッパーで切除するだけで済むため初心者にも優しい手法です。残した軸の根元に力を入れてバネをしっかりはめ込めば、バネがズレることなく左右対称の正確な配置が可能になります。
軸の横に1.5mmアルミスペーサーを並べ、アルミスペーサーと同じ高さに切り揃えて軸の根元だけ残す
センターシャーシのビス穴は、後でビスを通しやすくするために2mmドリル刃で拡張しておきます。余裕があれば2.1mmドリル刃で拡張すると、メンテナンス時のビスの着脱がさらにスムーズになります。
前後ユニットの穴拡張と可動域調整が最も重要な工程
MSフレキ製作で最も精度が求められるのが、前後ユニットの穴拡張と可動域の調整作業です。
フロントユニット(N-02)とリヤユニット(T-01)の両方で、センターシャーシ側の穴を5.5mmドリル刃で拡張します。この際、貫通させず1〜2mm程度は残すことが絶対条件です。貫通させてしまうとバネが抜けてしまい、作り直しになってしまいます。
⚙️ 前後ユニット加工の重要ポイント
| 加工箇所 | 目的 | 加工方法 |
|---|---|---|
| センターシャーシ接続穴 | バネを入れるスペース確保 | 5.5mmドリルで1〜2mm残して拡張 |
| ギヤボックス周辺 | 可動域の確保 | ニッパーとヤスリで段階的に削る |
| ツメ・Tモールド | 干渉防止 | ニッパーでカット |
| センターシャーシ接触面 | 可動をスムーズに | ヤスリで平らに削る |
穴を拡張する際は、ドリル刃に目印(マスキングテープなど)をつけておくと、深さを統一しやすく貫通事故を防げます。拡張後は、穴の中に残ったバリを棒ヤスリで丁寧に取り除きましょう。
次に重要なのが可動域の調整です。ギヤボックスの高さに合わせて不要な部分をカットし、スペーサーやスプリングを置くスペースを確保します。一般的には3mmスペーサーを使用することが多いですが、可動域を広くしたい場合は調整が必要です。
✂️ 可動域調整の作業フロー
- ✓ ギヤボックスの高さまで水平方向にカット
- ✓ センターシャーシ接続穴の一部をニッパーでカット
- ✓ 棒ヤスリで平らに整える
- ✓ スペーサー設置箇所を確保
センターシャーシ接続穴の高さはスペーサーよりも低くする必要がある
出典:ミニ四ファン
可動をスムーズにするための微調整も欠かせません。センターシャーシとの接触面を棒ヤスリで削り、摩擦を減らします。ただし、削りすぎるとガタが出てしまうため、「少し削っては確認」を繰り返す慎重な作業が求められます。
センターシャーシ接続穴の側面を2〜3mm削る程度が目安ですが、個体差もあるため最終的には実際に組み合わせて動きを確認しながら調整するのがベストです。番手#1000以上のヤスリで仕上げると、接触面がツルツルになり可動がさらにスムーズになります。
お辞儀防止プレートとグリスアップで完成度を高める
MSフレキ完成の仕上げとして、お辞儀防止プレートの取り付けとグリスアップが必須です。
お辞儀防止プレートとは、前後ユニットが下に沈み込む「お辞儀」を防ぎ、ギヤの噛み合わせを正常に保つためのパーツです。お辞儀が発生すると、ギヤ同士がしっかり噛み合わなくなり(トルク抜け)、パワーダウンしてしまいます。
🛡️ お辞儀防止プレートの役割
| 問題 | 原因 | 解決策 |
|---|---|---|
| トルク抜け | ギヤの噛み合わせ不良 | お辞儀防止プレートで支える |
| パワーダウン | ギヤの空転 | 前後ユニットを正しい高さに保つ |
| 駆動不安定 | ローラー等の重さ | プレートで水平を維持 |
お辞儀防止プレートは、FRPマルチワイドステーやFRPマルチ補強プレートを使って製作します。予算を抑えたい場合は、マルチ補強プレートを「=型」にカットする方法がコストパフォーマンスに優れています(220円×2個で440円)。
プレートの材質は、カーボンが軽量で剛性が高く理想的ですが、FRPでも十分に機能します。FRPの強度を高めるには、断面に瞬間接着剤を染み込ませるという裏技があります。FRPは繊維層になっているため、そこに接着剤を染み込ませるとカチカチのプレートに変わります。
FRPの断面が繊維層になっているので、そこに薄く瞬間接着剤を染み込ませると、カッチカチのプレートに生まれ変わる
最後の工程がグリスアップと本組みです。グリスを塗る箇所は、前後ユニットのセンターシャーシと接触する面と、センターシャーシのスプリング周辺の2箇所が基本です。
💧 グリスアップの手順
- ✓ スライドダンパー用グリス(またはキット付属グリス)を用意
- ✓ 前後ユニットの接触面に爪楊枝や綿棒で薄く塗る
- ✓ センターシャーシのバネ設置部分に塗る
- ✓ 10mmビスで前後を組み付ける
グリスの種類は、HGスライドダンパーグリスのエクストラハードが一般的です。グリスの硬さで減衰(バネの動きの抑制)を調整できます。硬いグリスほど動きが緩やかになり、柔らかいグリスほど素早い動きになります。
組み付けには10mmまたは13mmのビスを使用しますが、13mmビスの場合はビスの先が軸の根元内で収まるため、ナットが不要で軽量化できるというメリットがあります。また、軸残しの軸がビスをしっかり止めてくれるため、ビスが緩む心配も少なくなります。
全ての組み付けが完了したら、手で前後ユニットを押して動きを確認します。スムーズに動き、グリスの効果で「ぬるっ」とした感触で戻ってくれば成功です。バネのクイックイッ感ではなく、減衰が効いた滑らかな動きが理想的な状態です。
まとめ:ミニ四駆MSフレキ製作で押さえるべきポイント
最後に記事のポイントをまとめます。
- MSフレキはスプリングで衝撃を吸収するサスペンション機能を持つ改造である
- 軸残しフレキは初心者に適しており、バネの固定が安定している
- 製作費用は工具込みでも5,000〜7,000円程度に抑えられる
- センターシャーシの切断は垂直性が重要で、マスキングテープでガイドを作ると良い
- 前後ユニットの穴拡張は貫通させないよう注意が必要である
- 可動域調整は削りすぎるとガタが出るため慎重に行う
- お辞儀防止プレートはトルク抜けを防ぐために必須である
- FRPの断面に瞬間接着剤を染み込ませると強度が上がる
- グリスアップは接触面とバネ周辺に行い、滑らかな動きを実現する
- 専用治具を使えば精度と再現性が向上するが必須ではない
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- ミニ四駆、もう一度始めてみたよ – 70 MSフレキを作ってみたよ
- ミニ四ファン – MSフレキ 作り方・作成方法
- note ユリノキ – MSフレキは最強か?
- リオンチャンネル – MSフレキってどう作るの??基本的な加工をマスターしよう☆
- note 3710 – 5,000円の予算でつくる支柱残しフレキ
- Yahoo!ショッピング – MSシャーシ用 フレキ製作カット治具セットのレビュー
- YouTube しろっこチャンネル – 跳ねない!強い!MSフレキを作ってみよう!
- YouTube ミニヨンクマスター – MSフレキ入門!強化ユニットを使った簡単改造!
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当ブログをご覧いただきありがとうございます。
このたび、当ブログの記事内容について無断転載とのご指摘を受けました。
事実確認が十分でない部分もありますが、著作権に関わるご迷惑をおかけする可能性を重く受け止め、記事をすべて非公開とし、今後の再確認を進めてまいります。
ご心配・ご不快の念をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後は再発防止に努め、安心してご覧いただけるブログ運営を行ってまいります。