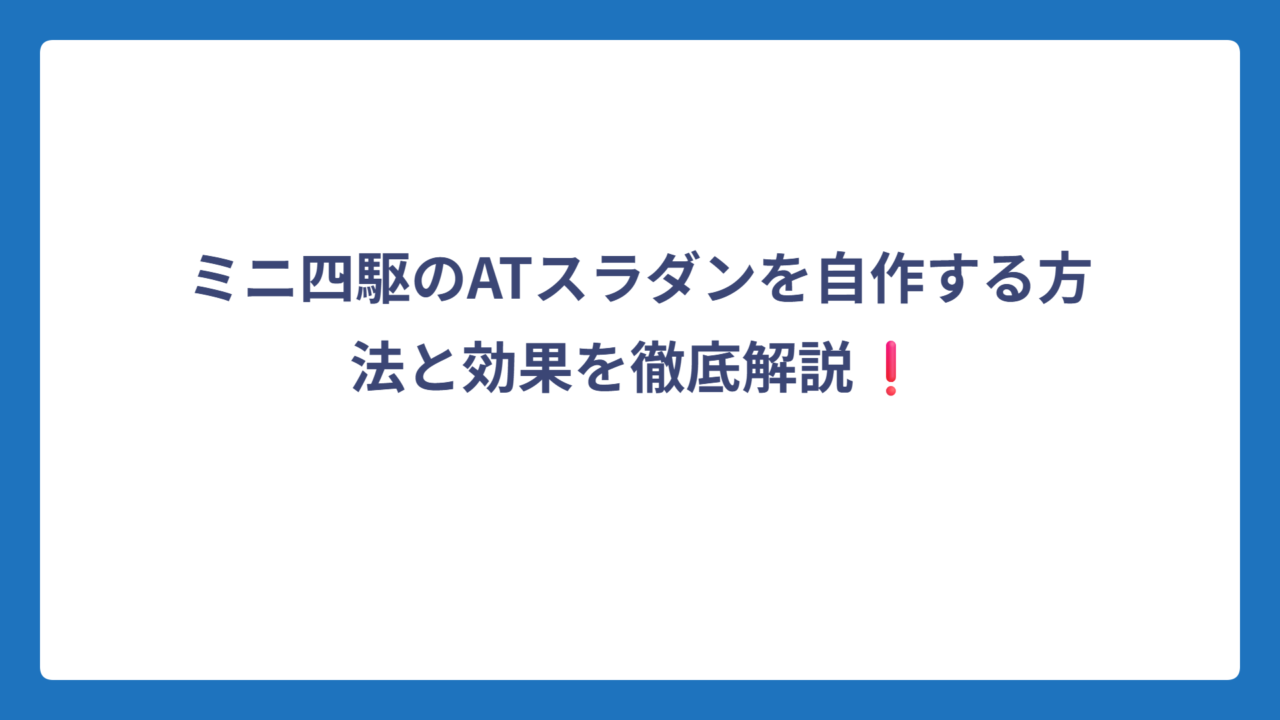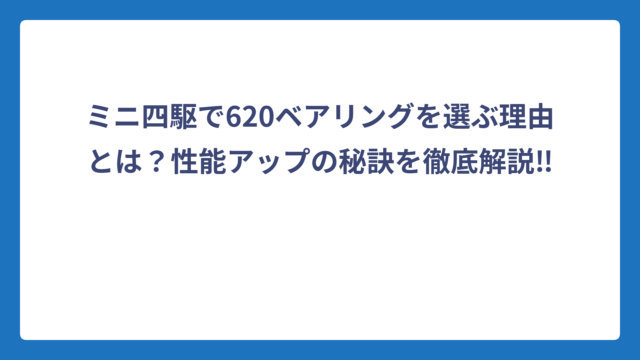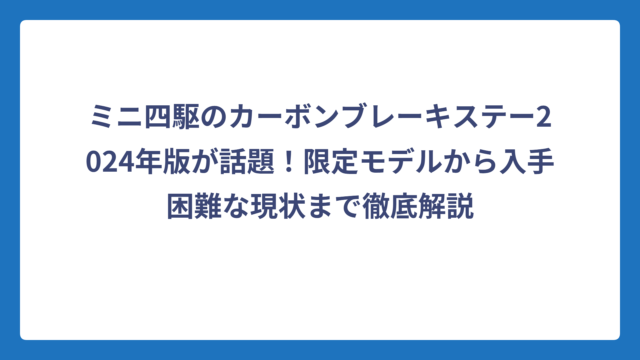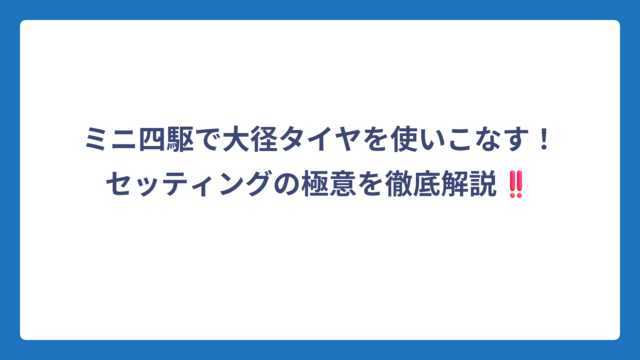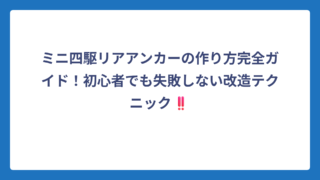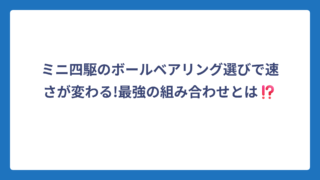ミニ四駆のカスタマイズで注目を集めている「ATスラダン」。ATバンパーとスライドダンパーの機能を併せ持つこのギミックは、現代のミニ四駆コースを攻略するうえで欠かせない改造として定着しつつあります。コーナーでの安定性を高めながら、壁への乗り上げ時にも復帰しやすいという二つの利点を同時に得られるのが最大の魅力です。
しかし、ATスラダンの自作には一定の加工技術が必要で、初心者にはハードルが高く感じられるかもしれません。本記事では、ネット上で公開されている製作ガイドを参考に、ATスラダンの基本構造から具体的な作り方、調整のコツまでを網羅的に解説します。対応シャーシやパーツ選びのポイント、スラスト抜け対策といった実践的な情報も織り交ぜていますので、これからチャレンジする方の参考になれば幸いです。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ ATスラダンの効果とメリットが理解できる |
| ✓ 必要なパーツと工具のリストがわかる |
| ✓ 具体的な加工手順と組み立て方法を学べる |
| ✓ スムーズな可動のための調整テクニックを習得できる |
ミニ四駆のATスラダンがもたらす効果と必要パーツ
- ATスラダンが発揮する二つの機能とは
- 作成に必要な基本パーツと代用品の選択肢
- まとめ:ミニ四駆のATスラダンを理解して準備を整えよう
ATスラダンが発揮する二つの機能とは
ATスラダンは、スライドダンパーとATバンパーという二種類のギミックを一つにまとめたバンパー改造です。それぞれの機能を簡単に整理すると、以下のようになります。
📊 ATスラダンの二大機能比較
| 機能 | 効果 | 主な利点 |
|---|---|---|
| スライドダンパー | コースからの横方向の衝撃を吸収 | コーナーでの走行ラインが安定し、マシンの挙動が穏やかになる |
| ATバンパー | バンパーが持ち上がった際にコース内へ復帰しやすくなる | ジャンプ後の壁乗り上げ時などにコースアウトを防ぐ |
近年のミニ四駆コースは複雑なセクションが増えており、3レーン用マシンでもスライドダンパーの採用が一般的になってきました。ATスラダンを搭載することで、コーナー直後のセクションでもマシンが安定し、なおかつ壁への乗り上げ時の復帰力も高まるため、完走率の向上が期待できます。
ATスラダンは「スライドダンパーの機能」と「ATバンパーの機能」の両方の動きを兼ね備えたバンパーになります。
出典:ムーチョのミニ四駆ブログ
デメリットとしては、パーツ点数が増えて重量がかさむ点が挙げられます。それでも現代のコース環境においては、安定性とコースアウト対策を両立できるATスラダンの価値は非常に高いと言えるでしょう。
作成に必要な基本パーツと代用品の選択肢
ATスラダンを自作する際には、いくつかの専用パーツと汎用パーツを組み合わせる必要があります。主な必要パーツを以下の表にまとめました。
🛠️ ATスラダン作成に必要なパーツリスト
| パーツ名 | 用途 | 代用品・補足 |
|---|---|---|
| フロントワイドスライドダンパー | 上蓋、スプリング、アルミプレート(型枠用) | タミヤ純正。上蓋とスプリングを主に使用 |
| カーボンマルチワイドリヤステー | バンパー本体の素材(2枚推奨) | 限定品。入手困難な場合はFRPマルチワイドリヤステーで代用可 |
| FRPマルチワイドリヤステー | カーボンステーの補強・代用 | カーボン1枚+FRP1枚の組み合わせも可能 |
| リヤブレーキステー | ATバンパー用プレート | 2枚使用する作例もあり |
| 2段アルミローラー用5mmパイプ | ATとして可動させるための軸 | 直径3mm程度に穴を拡張して使用 |
| スプリング各種 | スライド硬さ・AT可動の調整 | ソフト/ミディアム/ハード/スーパーハードなど |
フロントワイドスライドダンパー用カーボンステーを用意できない場合はこのパーツ(カーボンマルチワイドリヤステー)が必要になります。
出典:ミニ四ファン
カーボンマルチワイドリヤステーは限定品のため入手しづらいことがあります。その場合、Amazonなどで定期的に在庫が復活することがあるため、こまめにチェックするのがおすすめです。また、夏頃にロゴを変えた新製品が発売されることもあるため、事前予約を狙うのも一つの手でしょう。
✅ 工具面での準備
- 電動リューターと円筒形ビット(細め・太め)
- 2mm・3mmドリル(ビス穴拡張用)
- 小さめの棒ヤスリ(角ばった形状の加工用)
- ニッパー、紙ヤスリ、接着剤など
リューターは細かな穴拡張やスライドレール加工に必須級となりますので、まだお持ちでない方はこの機会に揃えておくと他の改造にも役立ちます。
まとめ:ミニ四駆のATスラダンを理解して準備を整えよう
最後に記事のポイントをまとめます。
- ATスラダンはスライドダンパーとATバンパーの機能を併せ持つギミックである
- コーナーでの安定性向上と壁乗り上げ時の復帰力強化を同時に実現できる
- 必要パーツは主にフロントワイドスライドダンパー、カーボンまたはFRPマルチステー、リヤブレーキステーなど
- カーボンマルチワイドリヤステーは限定品で入手困難な場合があるため、代用品としてFRPステーを活用する
- 電動リューターと各種ドリルは加工に必須となる工具である
- パーツ点数が増えて重量がかさむが、現代コースでは安定性のメリットが大きい
ミニ四駆のATスラダン作成手順と調整のコツ
- バンパー部分の加工ステップ
- 上蓋の加工とスライド可動域の拡張
- 組み立てとスラスト角調整の実践
- スムーズに可動させるための調整テクニック
- まとめ:ミニ四駆のATスラダンを完成させて走らせよう
バンパー部分の加工ステップ
ATスラダンの心臓部とも言えるバンパー部分は、既存ビス穴の拡張とステーの結合が主な作業になります。具体的な手順は以下の通りです。
🔧 バンパー加工の基本ステップ
| ステップ | 作業内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 型枠の結合 | スライドアルミプレートとカーボンマルチステーをビスで固定 | 4箇所以上で固定してズレを防ぐ |
| 2. スライドレール作成 | 既存ビス穴をリューターの円筒形ビットで拡張 | 横幅は少し狭めに留めると可動域を後から調整しやすい |
| 3. スプリングスペース作成 | 同じく円筒形ビットで拡張後、棒ヤスリで角を整える | スプリングが綺麗に収まるよう四隅を角ばった状態にする |
| 4. ステーの結合 | カーボンステーとFRPステーを接着剤で接合 | 引っ掛かり防止加工は結合前に実施すること |
| 5. 干渉箇所のカット | 支柱・タイヤ・シャーシとの干渉部分を削る | シャーシに仮組みしながら確認すると失敗が少ない |
⚠️ 削りすぎに注意
スライドレールの外側を削りすぎるとステーの強度が低下します。裏面を確認しながら慎重に作業を進めましょう。また、スライドアルミプレートも一緒に削れてしまうことがあるため、リュータービットをプレートに当てすぎないよう注意が必要です。
スライドレールの外側をスライドアルミプレートとまったく同じところまで削ってしまうとカーボンマルチステーの強度が落ちてしまうので、強度が落ちない程度のところで止めておきましょう。
出典:ミニ四ファン
加工は1枚ずつ行うことで、仮に1枚を削りすぎてももう1枚でカバーできるため、初心者の方にはこの方法がおすすめです。
上蓋の加工とスライド可動域の拡張
上蓋はバンパーの上に載せるパーツで、スライドダンパーの動きを制御する重要な役割を果たします。干渉箇所のカットとスライド可動域の調整が主な作業です。
📐 上蓋加工のポイント
| 加工内容 | 目的 | 方法 |
|---|---|---|
| 干渉箇所のカット | 支柱・タイヤ・シャーシとの干渉を防ぐ | ニッパーやリューターで不要部分を除去 |
| 可動域の拡張 | スライドダンパーがより広く動けるようにする | 裏面のビス穴周りの出っ張りをカット |
| スプリングスペースの底上げ | スプリングの力を効率的に伝える | 厚さ1mm程度の端材を底に接着 |
💡 可動域は広ければ良いわけではない
近年のトレンドでは、スライド可動域は比較的狭めに設定するのが主流になっています。そのため、可動域の拡張加工は一旦保留にしておき、実際に走らせてから必要に応じて調整するのも良いでしょう。後から可動域を狭くすることも可能なので、加工してしまったからといって取り返しがつかないわけではありません。
底上げに使う端材は、ミニ四駆キャッチャーの端材や上蓋をカットした際の切れ端が利用できます。サイズは横7mm×縦3mm未満が目安です。
組み立てとスラスト角調整の実践
加工が終わったら、いよいよパーツを結合してATスラダンを組み立てます。スラスト角の調整も忘れずに行いましょう。
🔩 組み立ての基本手順
- カーボンマルチ強化プレートの上にバンパーを乗せ、ビスを通す
- スプリングをスプリングスペースに設置
- 上蓋をかぶせ、大ワッシャーを取り付ける
- ロックナットで固定(締めすぎるとスライドしなくなるので注意)
組み立て時にスプリングが外れやすい場合は、マルチテープなどで一時的に全体を固定すると作業が楽になります。
🎯 スラスト角調整の方法
| 調整方法 | 使用パーツ | 特徴 |
|---|---|---|
| 上蓋のビス穴利用 | トラスビス、ワッシャー、スペーサー | 上蓋に取り付けたビスがシャーシに接触してスラストが付く |
| シャーシ側で高さ調整 | スラスト調整プレート、ブレーキスポンジなど | バンパー下に挟むことでスラストを調整 |
スラスト角は5°程度が一般的ですが、シャーシによって適切なワッシャー・スペーサーの組み合わせが変わります。仮組みしながら微調整を重ねるのがコツです。
スムーズに可動させるための調整テクニック
ATスラダンを組み立てても、スムーズに可動しないことがあります。特に「押した時は問題ないが戻りが悪い」という症状は多くのレーサーが経験する課題です。以下の調整テクニックを試してみてください。
✅ スムーズ可動のための3つのアプローチ
- ロックナットの締め具合を調整
最も手軽な方法。ただし非常にシビアで、少し変えるだけで挙動が変わる。緩めすぎるとガタつくので注意。 - グリスを塗る
カーボンマルチステーの両面、または上蓋裏面とマルチプレート表面に少量塗布。ミニ四駆オイルペンを使うとピンポイントで塗りやすい。 - スキッドシールを貼る
カーボンマルチステーの接触面にスキッドシールを貼ることで摩擦を減らす。2.5cm×1cmサイズを4枚用意するのが目安。
ATスライドダンパーのバンパーの上に載せる上蓋の加工について解説していきます。干渉箇所のカット、スライド可動域の拡張、スプリングスペースの底上げなどが主な作業です。
出典:ミニ四ファン
また、ブレーキステーのビス穴を拡張しておくと、ATバンパーを装着したままロックナットの調整ができるようになり、作業効率が上がります。この加工はスラスト抜け対策としても有効です。
まとめ:ミニ四駆のATスラダンを完成させて走らせよう
最後に記事のポイントをまとめます。
- バンパー加工は既存ビス穴の拡張とステー結合が中心である
- スライドレールは削りすぎると強度が落ちるため慎重に作業する
- 上蓋の可動域拡張は必須ではなく、実走後に必要なら調整する
- スプリングスペースの底上げはスプリングの力を効率的に伝える工夫である
- 組み立て時はロックナットの締め具合がスライド可動を左右する
- スラスト角は上蓋のビス穴やシャーシ側の高さ調整で設定できる
- スムーズな可動のためにはロックナット調整、グリス塗布、スキッドシール貼付が有効である
- ブレーキステーのビス穴拡張で調整作業が効率化できる
- スプリングの種類を変えることでスライドの硬さを調整可能である
- スペーサーを使えばスライド可動域を制限できる
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- ATスライドダンパー(ATスラダン) 作り方・作成方法【ミニ四駆 改造】 | ミニ四ファン
- 【ATスラダン】効果とメリット|かんたんな作り方とスラスト抜け対策も紹介 | ムーチョのミニ四駆ブログ
- ATスラダンをつくろう#5「組立」【ミニ四駆】 – YouTube
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当ブログをご覧いただきありがとうございます。
このたび、当ブログの記事内容について無断転載とのご指摘を受けました。
事実確認が十分でない部分もありますが、著作権に関わるご迷惑をおかけする可能性を重く受け止め、記事をすべて非公開とし、今後の再確認を進めてまいります。
ご心配・ご不快の念をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後は再発防止に努め、安心してご覧いただけるブログ運営を行ってまいります。