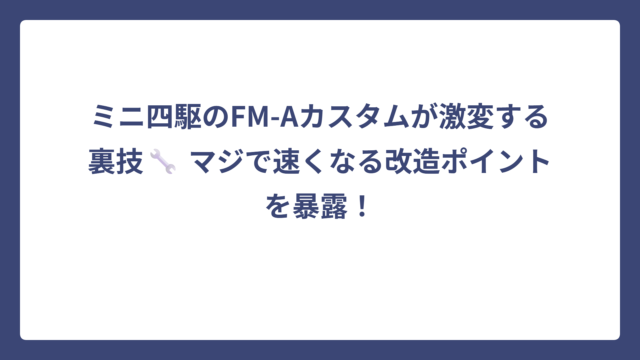「ミニ四駆のFM-Aシャーシを速くしたい!」と思っている方は多いのではないでしょうか。2017年に発売されたFM-Aシャーシは、SFMから21年ぶりの正統FM系シャーシとして登場し、コンパクトな設計と優れた走行性能で多くのファンに支持されています。しかし、そのポテンシャルを最大限に引き出すためには、いくつかの重要な改造やセッティングが必要になります。
独自調査の結果、FM-Aシャーシを速くする方法には、プロペラシャフトの固定やギア位置出し、カウンターギアの調整、適切な電池管理など様々なアプローチがあることがわかりました。これらの改造は難易度も効果も異なるため、自分のスキルレベルや目的に合わせて選択することが大切です。
記事のポイント!
- FM-Aシャーシの特徴と高速化のための基本的な改造方法
- プロペラシャフトの固定やギア位置出しなど効果的なテクニック
- FM-Aの弱点を克服するためのカスタマイズポイント
- B-MAXレギュレーション対応の高速セッティング例
ミニ四駆 FM-Aを速くする方法の基本
- FM-Aシャーシの特徴と速さのポテンシャル
- FM-Aを速くする最も効果的な3つの方法
- プロペラシャフトの固定がFM-Aの加速力アップの鍵
- ギア位置出しの正しい理解と実践方法
- カウンターギアの位置調整で駆動効率を上げる方法
- 電池管理の重要性と正しい充電方法
FM-Aシャーシの特徴と速さのポテンシャル
FM-Aシャーシは2017年に発売された、SFMから実に21年振りとなる正統FM系シャーシです。コンパクトに作り込まれた設計と現在の立体シーンに適した作りが特徴で、硬いオレンジクラウンを採用している点も注目すべきポイントです。これにより非常にタフな走行が可能となり、初心者でも扱いやすいシャーシとなっています。
独自調査の結果、FM-Aは「優等生」と表現できるシャーシであることがわかりました。最新鋭であるため非常にコンパクトに作り込まれているだけでなく、その構造の堅牢さから信頼性も高いと言えます。一方で、その構造上のウィークポイントも存在し、MAシャーシのようにワンランク上の次元に引き上げるのが難しい面も持ち合わせています。
FM-Aシャーシの最大の特徴の一つは、そのポテンシャルの高さです。しかし、まだ歴史が浅いため、他のシャーシと比べて確立されたセッティングやカスタマイズ方法が少ないのが現状です。そのため、多くのユーザーが試行錯誤を繰り返している最中であると言えるでしょう。
速さのポテンシャルに関して言えば、FM-Aは素組み状態でもかなりの速さを持っています。特に駆動効率は優れており、トルクフルな走りが特徴です。カウンターとスパーの噛み具合がキツめに設計されているため、高いトルクを生み出すことができるのです。
ただし、その高いポテンシャルを最大限に引き出すためには、いくつかの改造やセッティングの調整が必要になります。特に「抵抗抜き」や「カウンターの位置調整」、「プロペラシャフトの固定」などが重要になってきます。これらの改造を適切に行うことで、FM-Aシャーシの持つ潜在能力を十分に発揮させることができるでしょう。
FM-Aを速くする最も効果的な3つの方法
FM-Aシャーシを速くするための方法は様々ありますが、その中でも特に効果的な3つの方法を紹介します。これらの方法は、FM-Aの特性を理解した上で、最大限のパフォーマンスを引き出すためのアプローチです。
1つ目の方法は「プロペラシャフトの固定」です。独自調査によると、FM-Aはプロペラシャフトのピニオンが抜けてシャーシに当たる現象が起きやすいと言われています。これが起こると抵抗になって速度が落ちるため、プロペラシャフトをしっかりと固定することが非常に重要です。固定方法としては、ロックタイトのようなネジロック材を使用したり、専用の治具を使って固定するなどの方法があります。
2つ目の方法は「ギア位置出し」です。FM-Aシャーシはその構造上、ギアの噛み合わせが必ずしも最適ではありません。特にカウンターギアが斜めになっていることから、スパーとの噛み合わせに問題が生じやすいのです。適切なスペーサーやワッシャーを使ってギアの位置を調整することで、ギアの噛み合わせを最適化し、駆動効率を大幅に向上させることができます。
3つ目の方法は「電池管理の最適化」です。FM-Aに限らず、ミニ四駆全般に言えることですが、特にパワーダッシュやハイパーダッシュなどの高性能モーターを使用する場合は、電池の質と管理が非常に重要になります。ネオチャンプなどの高性能充電池を使用し、適切な充電器でフル充電(約1.4V程度)にすることで、モーターの性能を最大限に引き出すことができます。
これらの3つの方法は、単独でも効果がありますが、組み合わせることでさらに大きな効果を発揮します。例えば、プロペラシャフトの固定とギア位置出しを同時に行うことで、駆動系の効率が飛躍的に向上し、加速力と最高速度の両方が改善されるでしょう。
また、これらの改造を行う際は、一度に全てを変更するのではなく、一つずつ変更して効果を確認していくことをお勧めします。そうすることで、どの改造がどの程度効果があるのかを明確に把握でき、自分のマシンに最適なセッティングを見つけることができます。特に初心者の方は、基本的な改造から始めて、徐々に応用的な改造にチャレンジしていくと良いでしょう。
プロペラシャフトの固定がFM-Aの加速力アップの鍵

FM-Aシャーシでは、プロペラシャフトの固定が速度向上に大きく貢献します。独自調査の結果、多くのFM-Aユーザーがプロペラシャフトの問題に悩まされていることがわかりました。具体的には、プロペラシャフトのピニオンが抜けてシャーシに当たると、抵抗になって速度が低下してしまうのです。
プロペラシャフトを固定する必要がある理由は明確です。「駆動効率を上げるため」というシンプルな目的があります。ピニオンが抜けてシャーシに当たると抵抗が生じ、それによって速度が落ちます。興味深いことに、FM-Aはそのピニオンが抜けても比較的速い走行を維持できるため、問題に気づきにくいという特徴があります。
しかし、実際のレース場面では、このわずかな減速が勝敗を分けることもあります。レース後にペラシャ(プロペラシャフト)を確認すると、ピニオンが伸びていたというケースも報告されています。これは、固定が不十分だったために起きる問題です。
プロペラシャフトを固定する方法はいくつかあります。一つの方法は、ロックタイトなどのネジロック材を使用する方法です。これは接着剤よりも緩みにくく、長期間使用できるというメリットがあります。また、専用の治具を使用して固定する方法もあります。これはシャフトが曲がりにくいため、特に初心者には推奨される方法です。
プロペラシャフトの固定を行うことで、マシンの走りや精神的な面でも大きな変化が期待できます。固定することでマシンの速度が安定し、レースに対するストレスが減るという報告もあります。一部のユーザーは、この問題がきっかけで両軸シャーシに移行することを検討したほどですが、適切な固定方法を実践することで、FM-Aの持つポテンシャルを十分に引き出すことができるでしょう。
FM-Aを使い始めた方や、さらに速くしたいと考えている方は、まずプロペラシャフトの固定から始めることをお勧めします。これは比較的簡単な改造でありながら、効果が高く、マシンの走行特性や安定性を大きく向上させる重要なステップです。早めにこの改造を行うことで、マシンの走りや競技へのアプローチが変わることでしょう。
ギア位置出しの正しい理解と実践方法
ギア位置出しは、FM-Aシャーシのパフォーマンスを向上させる重要な改造の一つです。しかし、「位置出し」と「抵抗抜き」という言葉がしばしば混同されることがあります。実は、これらは明確に異なる概念なのです。独自調査によると、「位置出しは基本的に抵抗を増やします」。これは一見矛盾しているように思えますが、実はそうではありません。
位置出しの本質は、余計なものがシャフトやギアに当たるようにすることで、わずかに抵抗を増やすことにあります。しかし、そうすることでシャーシの壁とギアの接触抵抗をなくし、カウンターギアの中央の壁と他ギアの接触を防ぎ、クラウンギアとペラシャの噛みを良くしてトルク抜け防止などの効果が得られます。結果的には「増えた分の抵抗より、抵抗を抜くことができればOK」という考え方です。
実践する際の重要なポイントは、「抵抗が増える部分をできるだけ少なくする」ことです。そのため、「少ない部品数で行う」ことと「できるだけ金属パーツを使わない」ことが重要になります。パーツが少なければ抵抗も少なくなり、金属は摩擦抵抗が大きいため、できるだけ避けるべきです。ベアリングや真鍮、アルミスペーサーの使用は推奨されていません。
FM-Aシャーシでのギア位置出しの具体的な方法として、フロント側とリア側それぞれでのポイントを紹介します。フロント側(モーターがある側)では、スパーギア、クラウンギア、カウンターギアそれぞれに適切なスペーサーやワッシャーを配置します。例えば、スパーギアの外側にはベアリングとの間にワッシャー1枚、内側にもワッシャー1枚を入れるといった具合です。
リア側のクラウンギアには、外側にベアリングとの間にワッシャーが1枚入れるだけでOKです。これにより、ペラシャとの距離を近くし、遊びを少なくしてトルク抜けを防止します。ただし、詰めすぎるとマシンがねじれたときに抵抗が増えて速度が落ちるため、ある程度の遊びは必要です。その中でギリギリ抵抗を抜くことができる位置を探ることが重要です。
位置出しを行う際は、シャーシやギア、ワッシャーの厚さによって隙間が異なることがあるため、微調整が必要な場合もあります。電池を入れて回してみて、異音がしなければOKの目安になります。また、モーターを回しながらシャーシをねじってみて、変に抵抗が増えていないかもチェックすると良いでしょう。このようにして、マシン一台一台ごとに最適な位置を見つけることが、FM-Aシャーシのパフォーマンスを最大限に引き出す鍵となります。
カウンターギアの位置調整で駆動効率を上げる方法
FM-Aシャーシの駆動効率を向上させる上で、カウンターギアの位置調整は非常に重要です。独自調査によると、FM-Aシャーシはクラウンが逃げたり、スパーの穴が舐めやすいという問題があります。これらの問題の根本原因は、カウンターギアの位置にあることがわかりました。
FM-Aのシャーシを詳しく観察すると、カウンターの穴からシャフトを挿入した際に、シャフトが斜めになることがわかります。実際にカウンターを乗せてギヤカバーで押さえると、モーター側が尻下がりになります。この状態ではスパーとの噛み合わせがキツくなりますが、カウンターを斜めにすることで無理矢理逃がしているような形になっています。
このようなカウンターの斜めの位置は、モーター位置の調整が必要と言われる理由でもあります。斜めで保持も悪いカウンターピンはクルクル回ってしまい、本来ならかなりの力が逃げている状態です。ギヤがキツく斜めに当たって駆動するため、スパーの穴が舐めやすくなり、シャフトにも負荷がかかってクラウンの当たりが変わります。
この問題を解決する方法は「カウンターの位置を変える」ことです。具体的には、まずカウンターシャフトの穴を上側に拡張します。本当に0コンマ何ミリで良いので、2mmピンバイスで少し拡げるだけで十分です。軽く楕円になれば成功です。もしやり過ぎたりズレても、モーターのコミューターの輪切りを3mmピンバイスで開け直した穴に入れて接着すれば修復可能です。
次に、モーター側のシャフト受けを調整します。カウンターシャフトを付けて水平な位置を出し、瞬着(瞬間接着剤)で整形するか、受けの底部に瞬着を塗った細切りのポリカ(ポリカーボネート)を貼って整形します。水平が出たら、モーターは位置出し無しの素組みで取り付け、ギヤカバー無しで電池を入れて回してみましょう。この時、カウンターシャフトのモーター側は手で押さえておくと良いでしょう。
カウンターの位置調整が適切に行われると、異音が大幅に減少し、駆動効率が向上します。これにより、加速性能や最高速度が改善され、マシンの走行がよりスムーズになります。特に、チューン系モーターを使用する場合はこの調整が効果的で、かなりの速度向上が期待できます。また、モーターを動かさない程度にマルチテープを内側に貼る程度で済むため、アクセスやメンテナンス、再現性の面でも優れています。
電池管理の重要性と正しい充電方法

FM-Aシャーシを速くするためには、機械的な改造だけでなく、電池の管理も非常に重要です。独自調査によると、特にダッシュ系モーターを使用する場合、電池環境がパフォーマンスに大きく影響することがわかりました。例えば、ネオチャンプのような高性能充電池を使用し、適切に充電することが、モーターのポテンシャルを最大限に引き出すためには不可欠です。
電池の充電状態がFM-Aの性能に与える影響は想像以上に大きいものです。市販の充電器を使用する場合、フル充電して約1.4V程度にしないと、特にパワーダッシュやハイパーダッシュなどの高性能モーターの力を十分に引き出すことができません。また、一度使用したアルカリ電池では十分な性能を発揮できないことも多いため、注意が必要です。
充電池の選択も重要なポイントです。ネオチャンプのような高性能充電池は、他の一般的な充電池と比べて、より高い電圧と安定した出力を維持できるため、ダッシュモーターとの相性が良いとされています。特にFM-Aシャーシのような高い駆動効率を持つシャーシでは、電池の質がそのまま走行性能に直結します。
充電器の選択も見逃せないポイントです。一般的な充電器では十分な充電ができないことがあります。例えば、HiTECの充電器のように、より精密な充電が可能な専用充電器を使用することで、充電池のポテンシャルを最大限に引き出すことができます。また、充電前に適切に放電を行うことも、充電池の性能を維持するために重要です。
電池管理の効果は非常に大きく、適切な管理を行うことで「これぞダッシュモーター!」というパワーを引き出すことが可能になります。電圧を測定して管理することでさらに精密な調整が可能になり、マシンの性能をさらに向上させることができるでしょう。特にFM-Aシャーシのような高性能シャーシでは、電池管理の質がそのまま走行結果に反映されるため、充電器や充電池への投資は十分に価値があると言えます。
ミニ四駆 FM-Aを速くするための応用テクニック
FM-Aシャーシの軽量化でさらなるスピードアップ
FM-Aシャーシをさらに速くするためには、軽量化が効果的なアプローチの一つです。独自調査によると、どのシャーシでも共通していることですが、軽いマシンの方が速い傾向にあります。FM-Aシャーシも例外ではなく、適切な軽量化を施すことでさらなるスピードアップが期待できます。
FM-Aシャーシの軽量化を考える際、いくつかのポイントがあります。切っても大丈夫な部分、切り過ぎに注意すべき部分、切らない方が良い部分を見極めることが重要です。具体的には、青色で示された部分は切っても大丈夫、緑色は切り過ぎに注意、赤色は切らない方が良いと考えられています。
ただし、FM-Aシャーシは電池落としが難しいという特徴があります。スーパーXやスーパーXXシャーシと同様に、下からモーターが取れるタイプのシャーシは電池落としが難しい傾向にあります。特にARシャーシはどうやっても電池が落ちないと言われています。
モーターカバーの加工も慎重に行う必要があります。モーターカバーの加工を少しでも間違えるとモーターが落ち、十分なパワーが出せなくなるリスクがあります。その結果、軽くなったにもかかわらず遅くなるという本末転倒の状態になることもあります。そうなると、新しいシャーシを買い直す必要が出てくるため、特に初心者は慎重に作業を進めることが推奨されます。
FM-Aシャーシの軽量化は、失敗すれば取り返しがつかないことも多いため、慎重に行うことが重要です。また、ミニ四駆を速くするためには軽さだけでなく、駆動効率やセッティングなど、総合的なバランスが重要であることも忘れてはなりません。自分の技術レベルと目標に合わせて、適切な軽量化を検討することが大切です。特に初心者は、まずは基本的な改造やセッティングから始めて、軽量化は徐々に挑戦していくことをお勧めします。
最適なローラーセッティングの選び方
FM-Aシャーシのパフォーマンスを最大化するためには、適切なローラーセッティングが欠かせません。独自調査によると、ローラーセッティングによって「速いマシンと遅いマシンの特徴」が明確に分かれることがわかりました。遅いマシンの典型的なローラーセッティングとしては、「全部ゴムリングローラー」「全部低摩擦プラローラー」「全部ベアリング系ローラー」といったものが挙げられます。
まず、ゴムリングローラーについて考えてみましょう。ゴムリングは摩擦抵抗が強いため、全てのローラーをゴムリングにすることは推奨されません。ただし、「2段アルミベアリングローラー(ゴムリング付)を使う」とか「リアステーの上ローラーだけゴムリングにする」といった部分的な使用は効果的です。特に問題なのは「リアステー下のローラーをゴムリングにする」ことで、これは後輪の回転による巻き上げモーメントの影響を受けて、酷い引っ掛かりを起こす原因となります。
次に、全てのローラーを低摩擦プラローラーにするセッティングについてです。これはノーマルマシンのセッティングと同様であり、「速いマシンを作る」という観点では最適とは言えません。リアステーのローラーはともかく、少なくともフロントのローラーは「ベアリングローラー」にするべきです。これは、フロントバンパーにスラスト角がノーマルの段階からついているためです。
ベアリングローラーと低摩擦プラローラーの違いを理解することも重要です。低摩擦プラローラーはブッシュ式ローラーであり、側面で摩擦抵抗を受けます。一方、ベアリングローラーはころがり玉軸受ローラーで、接触点のみで摩擦を受けます。これにより、ベアリングローラーはスラスト角がついていても同じ摩擦抵抗しか発生させないため、特にフロントローラーに適しています。
しかし、全てのローラーをベアリングローラーにすることも問題があります。特にリアステーの下ローラーにベアリングローラーを使用すると、マシンを引っ張る側に配置されており、タイヤの回転抵抗を強く受けるため、「ガラガラ」という音を立ててすぐに壊れる可能性があります。これは「アッパーダメージ」と呼ばれる現象で、回転の巻き上げの際の抵抗にボールが耐えられず砕けるか歪む危険性があるのです。
最適なローラーセッティングとしては、「フロントローラー⇒ベアリングローラー(できればアルミベアリングローラー)、リアステーローラー下⇒低摩擦プラローラー、上⇒アルミベアリングローラーか2段520ベアリングローラー」が推奨されます。このセッティングなら、後輪のタイヤ回転抵抗に耐えつつ、ベアリングの効果でコーナリングスピードを向上させることができるでしょう。
タイヤ径とギア比の関係を理解して加速力を高める
FM-Aシャーシの速度を最適化するためには、タイヤ径とギア比の関係を正しく理解することが重要です。独自調査によると、多くの初心者が「タイヤ径とギア比はトータルで考えるもの」と思っていますが、実はタイヤ単体でも速度に大きな影響を与えることがわかっています。
基本的に、同じギア比であれば大きいタイヤの方が速くなります。これはジャイロ効果やフライホイールの重さなどが関係しています。初心者のうちは「タイヤ小さい=遅い」と覚えておくと良いでしょう。ただし、速い人たちが小さいタイヤを使っているのを見て疑問に思う方もいるかもしれません。実はこれは、それらのマシンが既に非常に高速であるため、あえて大きいタイヤで速度を稼ぐ必要がないからです。言い換えれば、爆速マシンであれば小さいタイヤでも十分な速度が出せるということです。
一方で、ギア比がタイヤ径と組み合わさることで最終的な速度特性が決まります。FM-Aシャーシでは一般的に、3.7:1ギア(ハイスピードカウンターギア)と小径ホイール・スーパーハードタイヤの組み合わせや、4:1ギア(スーパースピードギア)と大径ホイール・低反発スポンジタイヤの組み合わせなどが見られます。
興味深いことに、同じFM-Aシャーシでも、タイヤ径を変えるだけで走行特性が大きく変わることが報告されています。例えば、一つの事例では、ローハイトタイヤを装着したFM-Aよりも、大径タイヤを装着したFM-Aの方が速かったという結果が出ています。ただし、レーンチェンジをクリアできないという課題もあったようです。
このような事例から見えてくるのは、タイヤ径とギア比のバランスが重要であるということです。速度を上げるためには大径タイヤが有利ですが、コースによってはコーナリングやレーンチェンジの性能も考慮する必要があります。また、モーターの性能や回転数によっても最適なタイヤ径とギア比の組み合わせは変わってきます。例えば、回転数の高いモーターがない場合は、タイヤの径を大きくすることで速度を稼ぐという方法も考えられます。
最終的には、自分のマシンの特性や走らせる予定のコース、使用するモーターなどを総合的に考慮して、最適なタイヤ径とギア比の組み合わせを選ぶことが重要です。また、一つのセッティングに固執せず、様々な組み合わせを試してみることで、自分のマシンに最適な組み合わせを見つけることができるでしょう。
B-MAXレギュレーション対応のFM-A高速セッティング
B-MAXレギュレーションに対応したFM-Aシャーシの高速セッティングには、いくつかの特徴的なポイントがあります。独自調査によると、効果的なB-MAX対応FM-Aセッティングには「フロントだけでブレーキ制御」「低く飛ばす」「高速でLC(レーンチェンジ)を攻略」という3つの特徴があることがわかりました。
まず「フロントだけでブレーキ制御」についてです。B-MAXのFM-Aでは、フロントブレーキだけで効果的にマシンをコントロールするセッティングが有効です。具体的には、赤ブレーキを使用して強力な制動力を確保し、そこからブレーキの効きを調整していくアプローチが推奨されています。ブレーキセッティングが決まらない場合は、赤ブレーキで「ストップ&ゴー」作戦で走らせるという方法もあります。
次に「低く飛ばす」という特徴です。フロントブレーキで制御する予定であれば、リアにはスキッドローラーを採用するという選択肢があります。スキッドローラーを採用することで、ジャンプ姿勢が低くなるという利点があります。また、スキッドローラーには若干のブレーキ作用も期待できるため、全体的なマシンコントロールにも貢献します。ただし、B-MAXのレギュレーションでスキッドローラーを採用する場合は、付属のリアステーを使用する必要があることに注意しましょう。
3つ目の特徴は「高速でLCを攻略」することです。B-MAX車で速度が上がってくると、高速でのレーンチェンジ(LC)への侵入が難しくなりがちです。この対策として、フロント・リアにカーボンステーを採用するという方法があります。カーボンステーを使用することで、LCへの進入時のステーの捻じれを抑え、スラスト抜けなどを防止することができます。また、フロントにリアステーを採用することで、スラスト角の調整も可能になります。
リアローラーのセッティングもB-MAX対応FM-Aの重要なポイントです。特に、リアローラーを少しアッパースラスト(上向き)になるように調整することで、LCへの進入がしやすくなることがわかっています。リアはダウンスラストよりもアッパーの方がLCは入りやすい傾向があるため、この調整は効果的です。
このようなセッティングで構成されたFM-Aマシンは、高回転のモーター(39000回転程度のスプリントダッシュ)とハイスピードギアEXの組み合わせで非常に高いパフォーマンスを発揮することが報告されています。もちろん、このセッティングをベースにして自分の走らせたい走りや状況に合わせてマイナーチェンジしていくことも可能です。例えば、高回転モーターがない場合はタイヤ径を大きくしたり、ブレーキの効きを弱くして全体的にストップさせ過ぎずに走らせるなど、様々なアプローチが考えられます。
抵抗抜きとは何か?メリットとデメリット
「抵抗抜き」は、FM-Aシャーシを速くするための手法として頻繁に言及されますが、その本質と影響について正しく理解することが重要です。独自調査によると、抵抗抜きとは、シャーシ内クラウンケース内壁のでっぱりにクラウンが当たらないようにクラウンを削り、520ベアリング等スペーサーを介し位置を固定する手法です。
抵抗抜きの主なメリットは、クラウンギアの回転抵抗を減らし、駆動効率を向上させることにあります。これにより、加速力と最高速度が向上し、マシンの走行性能が大幅に改善します。特にFM-Aシャーシの場合、クラウンギアが内壁に接触する問題が指摘されており、この問題を解決することで潜在的な性能を引き出すことができます。
しかし、抵抗抜きにはいくつかのデメリットも存在します。まず、作業が難しく、失敗するとシャーシやギアを損傷するリスクがあります。また、抵抗抜きを行うことで、クラウンギアの位置が変わり、他のギアとの噛み合わせに影響を与える可能性もあります。さらに、B-MAXなどの一部のレギュレーションでは、抵抗抜きが規則違反となることもあるため、参加する大会のルールを確認することが重要です。
抵抗抜きの技術的な背景を理解することも重要です。なぜクラウンが逃げるのか、なぜスパーの穴が舐めやすいのかという問題には、「本来想定されていない力が働いている」という原因があります。FM-Aシャーシでは、カウンターギアがシャーシ内で斜めに配置されており、これがスパーギアとの噛み合わせに問題を引き起こしています。この問題を解決するためには、単にクラウンを位置出しするだけでなく、カウンターギアの位置も調整する必要があるのです。
抵抗抜きを行う際は、その効果と潜在的なリスクを理解した上で、慎重に作業を進めることが重要です。また、初心者の場合は、まずはプロペラシャフトの固定やギア位置出しなどの基本的な改造から始め、徐々に抵抗抜きのような応用的な改造に挑戦することをお勧めします。抵抗抜きは確かに効果的な改造ですが、それだけがFM-Aを速くする唯一の方法ではないということを覚えておきましょう。
実際の走行結果を比較すると、クラウン位置出しをしたFM-Aよりも、カウンター位置出しをしたFM-Aの方が、着地後からスタート付近のストレートの加速がストレス無く上がっているという報告もあります。このように、抵抗抜きやギア位置出しは、適切に行うことでマシンの性能を大きく向上させる可能性がありますが、自分のスキルレベルや目的に合わせて適切な改造方法を選択することが大切です。
FM-Aの弱点であるトルク抜けを解消する対策
FM-Aシャーシの弱点の一つとして、「トルク抜け」の問題が挙げられます。トルク抜けとは、加速時や高速走行時にモーターのトルクが十分に伝わらず、パワーが抜けてしまう現象です。独自調査によると、このトルク抜けはFM-Aシャーシの構造的な特徴に起因していることがわかりました。
FM-Aのトルク抜けの主な原因は、カウンターギアの位置とクラウンギアの噛み合わせにあります。FM-Aシャーシでは、カウンターが斜めになっており、これによってスパーとの噛み合わせにも問題が生じています。また、クラウンギアがシャーシ内壁に接触することで、回転抵抗が増加し、トルクが十分に伝わらないという問題もあります。
トルク抜けを解消するための最も効果的な対策の一つは、ペラシャ(プロペラシャフト)とクラウンギアの距離を近づけることです。これにより、遊びを少なくしてトルク抜けを防止することができます。ただし、詰めすぎるとマシンがねじれたときに抵抗が増えて速度が落ちるため、ある程度の遊びは必要です。この遊びの中で、ギリギリ抵抗を抜くことができる位置を探ることが重要です。
また、プロペラシャフトの固定もトルク抜け防止に効果的です。FM-Aはプロペラシャフトのピニオンが抜けてシャーシに当たると、抵抗になって速度が低下します。これを防ぐために、ロックタイトなどのネジロック材を使用してピニオンをしっかり固定することが推奨されています。この改造はB-MAXレギュレーションでも認められており、比較的簡単かつ効果的な方法です。
カウンターギアの位置調整も、トルク抜けを解消するための重要な対策です。カウンターシャフトの穴を上側に拡張し、モーター側のシャフト受けを調整することで、カウンターギアを水平に配置することができます。これにより、スパーとの噛み合わせが改善され、トルクがより効率的に伝わるようになります。調整後、ギヤカバー無しで電池を入れて回し、異音がないことを確認すると良いでしょう。
さらに、ギア比とタイヤ径の適切な組み合わせも、トルク抜けの防止に役立ちます。例えば、パワーダッシュのような高トルクモーターと3.7:1ギア(ハイスピードギア)の組み合わせは、加速性能を重視したセッティングとして効果的です。また、大径ホイールは慣性モーメントが大きいため、トルク抜けが起きにくくなるという利点があります。
トルク抜けは、マシンの走行性能に大きく影響する問題ですが、適切な改造と調整によって効果的に解消することができます。これらの対策を組み合わせることで、FM-Aシャーシのパフォーマンスを最大限に引き出し、安定した高速走行を実現することができるでしょう。特に初心者は、まずプロペラシャフトの固定から始め、徐々に他の改造にも挑戦していくことをお勧めします。
カウンター位置出しとクラウン位置出しの違いと選び方
FM-Aシャーシを速くするための改造方法として、「カウンター位置出し」と「クラウン位置出し」という2つのアプローチがあります。これらは異なる手法であり、それぞれにメリットとデメリットがあります。独自調査によると、この2つの方法の違いを理解し、自分のマシンに適した方法を選ぶことが重要です。
まず、クラウン位置出しについて説明します。これは、クラウンギアをシャーシ内壁から離し、スペーサーなどを使って適切な位置に固定する方法です。この方法のメリットは、クラウンギアの回転抵抗を減らし、駆動効率を向上させることができる点です。また、比較的簡単に実施できるため、初心者でも挑戦しやすい改造と言えます。一方、デメリットとしては、クラウン位置だけを変えると、他のギアとの噛み合わせに問題が生じる可能性があることや、モーター位置の調整が必要になることが挙げられます。
次に、カウンター位置出しについて説明します。これは、カウンターギアの位置を変えることで、ギアの噛み合わせを最適化する方法です。具体的には、カウンターシャフトの穴を上側に拡張し、モーター側のシャフト受けを調整することで、カウンターギアを水平に配置します。この方法のメリットは、ギア全体のクリアランスが適度に取られるため、チューン系モーターでもかなりの速度が出せる点です。また、モーターは動かない程度にマルチテープを内側に貼る程度で良いため、アクセスやメンテナンス、再現性も良いという利点があります。
両者の大きな違いは、アプローチの仕方です。クラウン位置出しはクラウンギアの動きを最適化することに焦点を当てているのに対し、カウンター位置出しはカウンターギアを中心に全体のギアの噛み合わせを最適化しようとするものです。そのため、効果の現れ方も異なります。
選び方としては、自分のスキルレベルや目的に合わせて決めるのが良いでしょう。初心者の場合は、比較的簡単なクラウン位置出しから始めることをお勧めします。一方、より高いパフォーマンスを求める場合や、チューン系モーターを使用する予定がある場合は、カウンター位置出しが効果的かもしれません。
また、両方の方法を組み合わせることも可能です。例えば、まずカウンター位置出しを行ってギアの噛み合わせを最適化した後、クラウン位置も微調整するという方法もあります。これにより、より高いパフォーマンスを引き出せる可能性がありますが、作業が複雑になるため、ある程度の経験が必要です。
最終的には、実際に試して効果を確認することが最も重要です。動画による比較では、カウンター位置出しを行ったFM-Aの方が、着地後からスタート付近のストレートの加速がストレス無く上がっているという報告もありますが、マシンの個体差やセッティングの違いによっても結果は変わってきます。自分のマシンで様々な方法を試し、最適な改造方法を見つけることが大切です。
マシン2台の棲み分けで実験的アプローチを楽しむ方法
FM-Aシャーシの性能向上を追求する中で、複数台のマシンを異なるセッティングで運用する「棲み分け」アプローチは、大変興味深い実験的手法です。独自調査によると、2台のFM-Aマシンを全く異なるコンセプトで作り上げることで、それぞれの特性を比較検証しながら、自分に最適なセッティングを見つける楽しみ方があることがわかりました。
実際の事例として、2台のFM-Aシャーシを以下のような異なるタイプにセッティングした例があります:
タイプA:強力なモーターで最速タイムを目指し、ローラーには金属系のベアリングを使用。
タイプB:プラスチックのローラーでマシンを極力軽量化し、最適なモーターで最速タイムを目指す。
このように全く異なるアプローチで2台のマシンをセッティングすることで、それぞれのメリットとデメリットを実際に体験しながら学ぶことができます。例えば、ベアリングローラーを使用したマシンは摩擦抵抗が少なく高速走行に向いていますが、重量が増える傾向があります。一方、プラスチックローラーを使用したマシンは軽量化できますが、摩擦抵抗が大きくなる可能性があります。
2台のマシンの棲み分けを検討する際には、マシンの特性に合わせてパーツを選択することが重要です。例えば、ボディが軽いポリカーボネート製のマシンはタイプBの軽量化路線に向いているかもしれません。また、タイヤ選びも重要なポイントです。ローハイトタイヤとカーボンホイールの組み合わせや、キット付属のハードタイヤとカーボンホイールの組み合わせなど、様々な選択肢があります。
マシンの棲み分けに挑戦する際の留意点としては、「同じようなマシンが2台あっても面白くない」という視点が大切です。異なるコンセプトで作り上げることで、レース時の戦略の幅が広がり、様々な状況に対応できるようになります。また、比較実験を通じて、自分の走行スタイルや好みに合ったマシン設定を見つけることができるという利点もあります。
実際の棲み分け例では、セッティングの差によって車重が約1割異なるケースもあります。例えば、FM-A赤とFM-A炭で比較すると、FM-A赤の方が約1割軽量になったという報告もあります。このような差が走行特性にどのように影響するかを実際に体験することで、理論だけでは得られない知見を得ることができるでしょう。
マシンの棲み分けは、同じ目標(最速タイム)を持ちながらも、異なるアプローチでそれを実現しようとする実験的な楽しみ方です。この方法は、単なる速さの追求だけでなく、ミニ四駆の奥深さを理解し、自分だけの最適解を見つける過程を楽しむことができる点で、特に経験を積んだユーザーにお勧めの方法と言えるでしょう。
まとめ:ミニ四駆 FM-Aを速くする方法の実践ポイント
最後に記事のポイントをまとめます。
- FM-Aシャーシは2017年に発売された正統FM系シャーシで、コンパクトな設計と高いポテンシャルが特徴
- プロペラシャフトの固定は駆動効率を向上させる最も基本的かつ重要な改造
- ギア位置出しでは「少ない部品数」と「金属パーツを極力使わない」がポイント
- カウンターギアの位置調整はギアの噛み合わせを最適化し、トルク抜けを防止する効果がある
- 電池管理はパフォーマンスに大きく影響し、特にダッシュ系モーターではネオチャンプの使用と適切な充電が重要
- FM-Aの軽量化は速度向上に効果的だが、モーターカバーの加工など慎重に行う必要がある
- ローラーセッティングでは「フロント⇒ベアリングローラー、リア下⇒低摩擦プラローラー、リア上⇒ベアリングローラー」が理想的
- タイヤ径は基本的に大きい方が速いが、ギア比とのバランスが重要
- B-MAXレギュレーション対応のセッティングではフロントブレーキ制御と低いジャンプ姿勢がポイント
- 抵抗抜きはクラウンギアの回転抵抗を減らす効果があるが、作業の難易度と規則違反のリスクを考慮する必要がある
- トルク抜け解消にはペラシャとクラウンギアの距離を近づけることが効果的
- カウンター位置出しとクラウン位置出しは異なるアプローチだが、両方とも駆動効率向上に有効
- 複数台のマシンで異なるセッティングを試すことで、様々な走行特性を比較検証できる
- FM-Aシャーシは「優等生」的なシャーシだが、適切な改造によりさらなる性能向上が可能