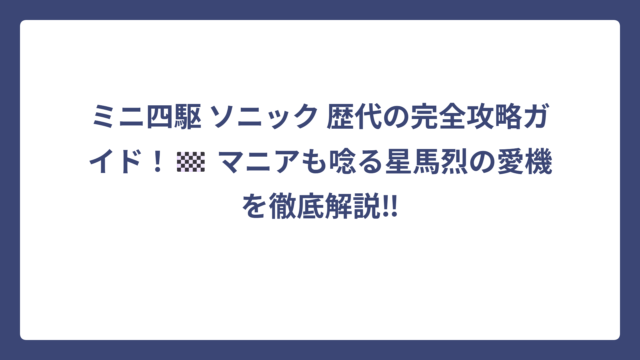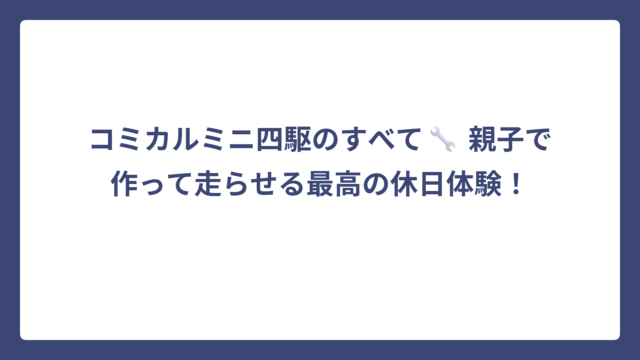ミニ四駆で勝つためには「バンクスルー」というテクニックが欠かせません。これは、速度を維持するためにバンクではブレーキを効かせず、スロープやレーンチェンジなどの必要な場所だけでブレーキが効くようにするセッティングのこと。実はこの微妙な調整がレースの勝敗を分ける重要なポイントなんです。
現代のミニ四駆レースでは、立体コース(3レーン、5レーン)が主流となっており、バンクやスロープなどの異なる角度のセクションをどう攻略するかが課題になっています。バンクとスロープではRの角度(曲がりの丸み)が違うため、その差を利用して必要な場所だけで減速できるセッティングが「バンクスルー」なのです。初心者から上級者まで知っておくべき重要なテクニックを徹底解説します。
記事のポイント!
- バンクスルーとは何か、なぜ必要なのかが理解できる
- バンクとスロープの違い、各シャーシ別の対策方法が分かる
- バンクスルーのセッティング方法とチェック方法が習得できる
- 小径タイヤでもバンクスルーを実現するテクニックが身につく
ミニ四駆バンクスルーとは何か?基本的な考え方と重要性
- バンクスルーとはバンクを減速せずにスロープで減速するテクニック
- バンク・スロープ・レーンチェンジの角度の違いが重要
- バンクスルーが必要な理由は速さと安定性の両立のため
- バンクスルーができるマシンの特徴は底面クリアランスの確保
- バンクスルーの確認方法はチェッカーや実走行テストが基本
- ダイソーのコレクションボックスは20度バンクチェッカーの代用に
バンクスルーとはバンクを減速せずにスロープで減速するテクニック
バンクスルーとは、その名の通り「バンク(傾斜のカーブ)を通過(スルー)する」技術のことです。具体的には、バンクセクションではブレーキを効かせずに通過し、スロープやドラゴンバックなどのセクションでのみブレーキを効かせる調整方法を指します。
独自調査の結果、バンクスルーはミニ四駆の速度を維持しながら安定走行を実現するために欠かせないテクニックであることがわかりました。特に3レーンや5レーンなどの立体コースでは、バンクとスロープの切り替わりが頻繁に発生するため、どこでブレーキを効かせるかが重要になってきます。
バンクスルーができていないマシンは、バンクセクションでも減速してしまうため、タイムロスにつながります。一方、適切にバンクスルーができていれば、必要なセクションだけで減速するので効率的な走行が可能になります。
プロのレーサーたちもレースでの勝敗を分けるポイントとしてバンクスルーを重視しています。「バンクはスルーして、スロープで効く」という基本的な考え方が、優れたマシン設計の土台となっているのです。
初心者の方は最初は難しく感じるかもしれませんが、バンクスルーの考え方を理解し、適切なセッティングができるようになれば、ミニ四駆の性能を飛躍的に向上させることができるでしょう。
バンク・スロープ・レーンチェンジの角度の違いが重要
ミニ四駆のコースには様々な角度のセクションがあり、それぞれの「R(角の丸み)」が異なります。この角度の違いを理解することがバンクスルーの肝となります。
一般的な3レーンコースでは、バンクの角度は20度が標準とされています。場合によっては40度バンクや60度バンクが組み合わされることもありますが、これらは基本的に20度バンクを組み合わせたものなので、Rの角度自体は同じです。
一方、スロープセクションはバンクよりも「R」がきつくなっています。つまり、曲がりの角度が急で、同じブレーキ設定ではマシンへの影響が大きく変わってくるのです。
これらの違いを利用してバンクスルーを設定します。具体的には、バンクではブレーキが当たらず、スロープでは当たるようにセッティングするのです。バンクの緩やかなRに合わせてブレーキを設定すれば、より急なRを持つスロープでは自然とブレーキが当たるようになります。
5レーンコースの場合は、さらに複雑な角度設定があり、45度バンクなどより高度な調整が必要になることもあります。これらすべての違いを考慮してマシン設計することが、バンクスルーの技術なのです。
角度の違いを把握するためには、バンクチェッカーなどのツールを使うことも効果的です。実際のコースのRを測定して、それに合わせたセッティングを行うことで、より精密なバンクスルーが可能になります。
バンクスルーが必要な理由は速さと安定性の両立のため

なぜバンクスルーは重要なのでしょうか?その理由は「速さ」と「安定性」という、ともすれば相反する要素を両立させるためです。
高速で走るミニ四駆は、コーナリングやジャンプなどの激しい動きに対応するためにブレーキが必要です。しかし、すべてのセクションでブレーキを効かせてしまうと、不必要な減速が生じてタイムロスになってしまいます。
バンクセクションはコースアウトのリスクが低く、減速せずに通過したい部分です。一方、スロープやドラゴンバック、レーンチェンジなどはマシンが浮き上がりやすく、コースアウトしやすいセクションなので、ブレーキによる減速と姿勢制御が必要になります。
バンクスルーのセッティングは、この「減速させたくない場所」と「減速が必要な場所」を見極め、適切にブレーキを効かせる技術です。これにより、必要最小限の減速で最大限の安定性を確保することができます。
レースの勝敗を分けるのは、しばしばわずか数ミリ秒の差です。バンクスルーの調整が適切であれば、バンクでの不要な減速を避けながらも、危険なセクションではしっかりとコントロールできるため、総合的なタイムアップにつながります。
また、バンクスルーは単にブレーキの効きを調整するだけでなく、マシンの姿勢制御にも関わっています。適切なセッティングにより、スロープからの着地時の姿勢を安定させ、次のセクションへのスムーズな移行を可能にします。
バンクスルーができるマシンの特徴は底面クリアランスの確保
バンクスルーを実現するマシンには、いくつかの共通する特徴があります。その中でも最も重要なのが「底面クリアランス(地上高)」の確保です。
理想的なバンクスルーができるマシンは、バンクを通過する際にブレーキが当たらないよう、適切な地上高が確保されています。一般的には、シャーシの底面と地面との間に1mm以上の隙間が必要とされています。
同時に、フロントとリアのバンパーの高さも重要です。バンパーが低すぎると、バンクの角度によってはバンパー自体がコースに接触してしまい、減速の原因になります。特にフロントバンパーは、バンクの入り口でコースに接触しやすいため、調整が必要です。
小径タイヤを使用する場合は特に注意が必要です。タイヤ径が小さくなると全体の地上高が下がるため、バンクスルーが難しくなります。そのため、小径タイヤを使用する場合は、ブレーキプレートの高さ調整や段上げなどの対策が必要になってきます。
また、マシンの重心位置も重要なファクターです。重心が低く、安定したマシンほどバンクでの挙動が安定し、バンクスルーがしやすくなります。反対に、重心が高すぎると、バンクでマシンが傾き、意図せずブレーキが当たってしまうことがあります。
バンクスルーを目指す際は、マシン全体のバランスを考えながら、どのセクションでどのようにブレーキを効かせるかを総合的に検討することが大切です。
バンクスルーの確認方法はチェッカーや実走行テストが基本
バンクスルーができているかどうかを確認するには、主に二つの方法があります。一つは「バンクチェッカー」などのツールを使用する方法、もう一つは実際のコースで走行テストを行う方法です。
バンクチェッカーは、コースのバンクやスロープの角度を再現した治具で、マシンのセッティングを事前に確認することができます。マシンをチェッカーに乗せ、タイヤが浮かずに接地しているか、ブレーキがバンク面に接触しないかを確認します。
市販のバンクチェッカーは様々な種類があり、3レーン用や5レーン用、さらには特定の角度専用のものまであります。価格帯も1,000円台から6,000円台まで幅広く、精度も様々です。
実走行テストは、実際のコースでマシンを走らせて確認する方法です。バンクセクションでの速度維持とスロープなどでの減速が適切に行われているかを実際に確認します。この方法はリアルな状況での挙動を確認できる利点がありますが、店舗のコースを利用する場合は他のレーサーへの配慮も必要です。
理想的には、まずバンクチェッカーでセッティングの基本を確認し、その後実走行テストで微調整を行うという手順が効果的です。チェッカーで「バンクスルーできている」と確認できても、実際のコースでは想定外の挙動を示すことがあるため、両方の確認方法を組み合わせるのがベストです。
バンクスルーのセッティングは、気温や湿度、コースのコンディションによっても変化するため、定期的に確認と調整を行うことをおすすめします。
ダイソーのコレクションボックスは20度バンクチェッカーの代用に
バンクチェッカーを購入するのは初心者にとって負担が大きいと感じる方もいるでしょう。そんな方に朗報です。実は100円ショップのダイソーで販売されている「コレクションボックス」が、20度バンクチェッカーの代用品として使えるという情報があります。
特に「アーチワイドL型」というコレクションボックスのフタの部分が、ミニ四駆のバンクセクションと似た角度を持っているとされています。このボックスは400円程度で購入できるため、専用のバンクチェッカーよりもかなり安価です。
ただし、このダイソー製品はあくまで代用品であり、正確な角度を持つ専用チェッカーではありません。実際に使用した方の報告によると、3レーンの20度バンクとはやや異なり、5レーンの45度バンクに近い角度だという意見もあります。そのため、参考程度に使用し、過信しないことが重要です。
もし本格的にミニ四駆を続けるなら、一般に3レーン用のバンクセクションを購入して自作チェッカーを作る方法も検討の価値があります。バンクセクション1セットで約5,000円ですが、左右2レーンずつ計4個のチェッカーを作ることができるため、友人と分ければ一人当たり1,500円弱で済みます。
初心者の方はまずダイソーのコレクションボックスで大まかな調整を行い、上達してきたらより精度の高いチェッカーに移行するという段階的なアプローチも一つの選択肢です。どのような方法であれ、バンクスルーの確認作業は必ず行い、マシンの性能を最大限に引き出しましょう。
ミニ四駆バンクスルーのためのセッティングと各シャーシ別対策法
- ブレーキプレートを斜めに削る方法がバンクスルーの基本
- ブレーキスポンジを斜めにカットするテクニックも効果的
- MSシャーシのバンクスルー方法は段上げ治具が有効
- MAシャーシのバンクスルー対策はリヤバンパー調整が重要
- VZ・FM-A・ARシャーシなど各シャーシ別のバンクスルー調整法
- 小径タイヤでもバンクスルーは可能だがセッティングが重要
- まとめ:ミニ四駆バンクスルーのポイントはマシンタイプに応じた適切な調整
ブレーキプレートを斜めに削る方法がバンクスルーの基本
バンクスルーを実現するための基本的な方法は、ブレーキプレートを斜めに削ることです。この方法は多くのベテランレーサーが採用している定番テクニックです。
ブレーキプレートを斜めに削ることで、バンクのRに合わせた角度を作り出します。これにより、バンクセクションではブレーキが当たらず、スロープなどの角度がきついセクションでのみブレーキが効くようになります。
プレートの斜め加工は、ヤスリやリューターなどの工具を使用して行います。加工の際は、バンクチェッカーを使いながら少しずつ削り、定期的に確認することが重要です。一度削りすぎると元に戻せないので、慎重に作業を進めましょう。
また、フロントとリアで異なる角度設定が必要になることもあります。一般的には、フロントのブレーキプレートはマシンの先端部分に配置されるため、よりシャープな角度にする必要があります。一方、リアのブレーキプレートはやや緩やかな角度設定でも問題ないことが多いです。
プレートの斜め加工と併せて、ブレーキプレートの高さ調整も重要です。プレートが高すぎるとブレーキが全く効かず、低すぎるとバンクでも減速してしまいます。ワッシャーなどを使って1mm単位での微調整を行うことで、理想的なバンクスルーが実現できます。
プレート加工の際は、加工後のブレーキスポンジの貼り付け位置や面積も考慮することが大切です。プレートを斜めに削っても、ブレーキスポンジの貼り方次第で効果が変わってくるためです。
ブレーキスポンジを斜めにカットするテクニックも効果的
プレートを加工する以外にも、ブレーキスポンジ自体を斜めにカットする方法もバンクスルーの有効な手段です。この方法は特に、B-MAXやGTアドバンスのように無加工がベースのマシンにおすすめです。
ブレーキスポンジを斜めにカットすることで、バンクの角度に合わせた形状にすることができます。これにより、プレートを加工しなくても、バンクではブレーキが当たらず、スロープでは当たるという理想的な状態を作り出せます。
斜めカットの方法には、カッターナイフなどを使って手作業で行う方法と、専用の「ブレーキスライサー」などの治具を使う方法があります。初心者の方は治具を使用することをおすすめします。治具を使えば、均一な角度でカットができ、再現性も高くなります。
斜めカットの角度は、使用するコースのバンク角度に合わせて決めます。3レーンの20度バンクであれば10度程度の斜めカット、5レーンの45度バンクであればより急な角度でのカットが必要になることも。
ブレーキスポンジのカットは、一度失敗すると新しいスポンジが必要になるため、最初は少し角度を付けた程度から始め、走行テストを繰り返しながら徐々に角度を調整していくのが安全です。
また、スポンジの種類によってもカットのしやすさや効果が変わってきます。一般的に柔らかいスポンジほどカットしやすく、硬いスポンジほど形状を維持しやすい傾向があります。ブレーキの種類と斜めカットの組み合わせを工夫して、理想的なバンクスルーを実現しましょう。
斜めカットの最大のメリットは、シャーシやプレートを加工せずに済むことです。マシンの構造を変えずにバンクスルーを実現できるため、初心者の方や無加工マシンを使用する方におすすめのテクニックと言えます。
MSシャーシのバンクスルー方法は段上げ治具が有効

MSシャーシでバンクスルーを実現するには、「段上げ治具」を使用する方法が効果的です。MSシャーシは前後バンパーがバンクスルーできない傾向があるため、この対策が必要になります。
段上げ治具とは、ブレーキプレートの取り付け位置を通常よりも高い位置に移動させるための部品です。市販品も多く、1.5mm、2.0mm、3.0mmなど様々な高さがあり、マシンの状態に合わせて選ぶことができます。
MSシャーシの場合、特にフロントバンパーのブレーキプレートが低く、バンクスルーが難しいという特徴があります。そこで、フロント用の段上げ治具を使用することで、プレートの位置を上げ、バンクでの接触を避けることができます。
リアバンパーについても同様に、段上げ治具によってプレートの位置を上げることで、バンクスルーを実現できます。ただし、リアは後ろに下げる傾向があるので、リヤバンパーステーの工夫でも解決可能な場合もあります。
段上げ治具の選択は、使用するタイヤ径によっても変わってきます。小径タイヤを使用する場合は、より高い段上げ治具が必要になることが多いです。反対に、大径タイヤであれば、段上げの必要性は低くなる傾向があります。
段上げ治具を使用する際の注意点として、高さを上げすぎるとスロープなどでもブレーキが効かなくなる可能性があります。そのため、バンクチェッカーなどで確認しながら、適切な高さを見つけることが重要です。
MSシャーシのバンクスルーは、他のシャーシに比べて調整が難しい面もありますが、段上げ治具と適切なブレーキ設定の組み合わせで、高いパフォーマンスを発揮することができます。
MAシャーシのバンクスルー対策はリヤバンパー調整が重要
MAシャーシでバンクスルーを実現する場合、特にリヤバンパーの調整が重要になってきます。MAシャーシの特徴として、リヤバンパーがバンクスルーできない傾向があるため、この部分に対策が必要です。
MAシャーシのリヤバンパー対策としては、「掘り込み治具でプレート基部を上げる」という方法が効果的です。これにより、ブレーキプレートの取り付け位置が上がり、バンクでの接触を避けることができます。
もう一つの方法として、「プレートを2枚使ってブレーキプレートをかさ上げする」という技もあります。これは、通常のブレーキプレートの下に別のプレートを挟むことで、全体の高さを調整する方法です。
MAシャーシはリアバンパーの構造上、単純に高さを調整するだけでなく、角度も重要になってきます。バンパーの根元からプレートが出ている形状のため、プレート基部の角度調整も必要になることがあります。
また、MAシャーシはフロントバンパーの調整も重要です。フロントは比較的調整しやすいですが、リアとのバランスを考慮しながら設定することがポイントです。
MAシャーシのバンクスルー調整では、リアブレーキステーの役割も重要です。リアブレーキステーは単にブレーキを貼るだけでなく、「タイヤを浮かせて駆動力を抜く」という重要な機能も持っています。特にスロープなどでの姿勢制御に大きく関わるため、高さや角度の調整が重要になります。
MAシャーシはその構造上、バンクスルーの調整が少し難しいシャーシですが、適切な対策を施すことで高いポテンシャルを発揮します。リヤバンパーを中心とした調整を丁寧に行い、理想的なバンクスルーを目指しましょう。
VZ・FM-A・ARシャーシなど各シャーシ別のバンクスルー調整法
各シャーシにはそれぞれ特徴があり、バンクスルーの調整方法も異なります。ここでは、VZ、FM-A、ARシャーシなどのバンクスルー調整法を紹介します。
【VZシャーシ】 VZシャーシは比較的バンクスルー調整がしやすいシャーシです。主な対策は「リヤバンパーのバンクスルー対策」で、「プレート基部をカットして上げる」「プレートを2枚使ってブレーキプレートをかさ上げする」などの方法が効果的です。VZシャーシはシャーシ底面の地上高も確保しやすいため、初心者の方にもおすすめのシャーシと言えるでしょう。
【FM-Aシャーシ】 FM-Aシャーシは「リヤバンパーがバンクスルーできない」「シャーシ底面が地上高を稼げない」という2つの課題があります。対策としては「プレート基部をカットして上げる」「プレートを加工したギヤカバーを装着してシャーシ底面を上げる」「シャーシ底面を削り込む」などの方法があります。FM-Aシャーシはコンパクトな設計のため、調整の自由度が低い面もありますが、工夫次第で高いパフォーマンスを発揮できます。
【ARシャーシ】 ARシャーシは「前後バンパーがバンクスルーできない」「シャーシ底面が地上高を稼げない」という2つの課題があります。対策としては「掘り込み治具でプレート基部を上げる」「シャーシ底面は削り込むか電池カバー・モーターカバーを自作する」などの方法があります。ARシャーシは調整の難易度が高めですが、適切な対策を施せば安定した走りを実現できます。
【S2シャーシ】 S2シャーシは「フロントバンパーがバンクスルーできない」という課題があります。対策としては「掘り込み治具でプレート基部を上げる」が効果的です。S2シャーシはリアの調整がしやすい反面、フロントの調整が難しいという特徴があります。
各シャーシによって課題と対策は異なりますが、基本的な考え方は「ブレーキプレートの位置を上げる」「シャーシの地上高を確保する」という2点に集約されます。自分のシャーシの特徴を理解し、適切な対策を施すことでバンクスルーを実現しましょう。
小径タイヤでもバンクスルーは可能だがセッティングが重要
現在のレースシーンでは小径タイヤ(概ね22〜23mm径)が主流ですが、小径タイヤでもバンクスルーは可能です。ただし、より精密なセッティングが必要になります。
小径タイヤを使用すると、マシン全体の地上高が下がるため、バンクスルーの実現が難しくなります。小径タイヤでバンクスルーを行う場合、以下の3つの問題のうちどれかが発生する可能性があります。
- シャーシ底面が地上高1mmを下回る
- フロントバンパーがバンクスルー不可能になる
- リヤブレーキプレートがバンクスルー不可能になる
これらの問題を解決するためには、シャーシの種類に応じた対策が必要です。例えば、プレート基部の掘り込みや治具の使用、ブレーキプレートのかさ上げなどが効果的です。
特に小径タイヤでは、ブレーキプレートの高さ調整が極めて重要になります。わずか1mmの違いでバンクスルーの成否が分かれることもあるため、綿密な調整が必要です。
一つの対策として、ブレーキを貼る位置を車輪に近づけることで、比較的簡単にバンクスルーが実現できる場合もあります。ただし、この方法ではスロープなどでの効きが弱くなる可能性もあるため、バランスを考慮することが重要です。
小径タイヤでバンクスルーを実現するには、シャーシの底面への加工や、ブレーキステーを斜めに削るなどの工夫も有効です。自分のマシンの特性を理解し、どのような対策が最適かを見極めることが大切です。
小径タイヤでのバンクスルーは難しい面もありますが、適切なセッティングを行えば十分に実現可能です。むしろ、この調整の難しさを克服することで、より高度な走りが可能になるとも言えるでしょう。
まとめ:ミニ四駆バンクスルーのポイントはマシンタイプに応じた適切な調整
最後に記事のポイントをまとめます。
- バンクスルーとは、バンクで減速せずにスロープで減速するセッティング技術
- バンクとスロープではRの角度(曲がりの丸み)が異なることを利用している
- 3レーンコースでは20度バンクが基本、スロープはバンクよりRがきつい
- バンクスルーは速さと安定性を両立させるために必須のテクニック
- バンクチェッカーは必要な装備で、ダイソーのコレクションボックスで代用も可能
- ブレーキプレートを斜めに削る方法がバンクスルーの基本テクニック
- ブレーキスポンジを斜めにカットする方法は無加工マシンに効果的
- MSシャーシは段上げ治具を使ったバンクスルー対策が有効
- MAシャーシはリヤバンパーの調整が特に重要
- 各シャーシによって課題と対策方法が異なるため、自分のマシンに合わせた調整が必要
- 小径タイヤでもバンクスルーは可能だが、より精密なセッティングが必要
- ワッシャー1枚の違いでバンクスルーの成否が分かれることもある
- バンクスルーはレースの勝敗を分ける重要な要素のひとつ