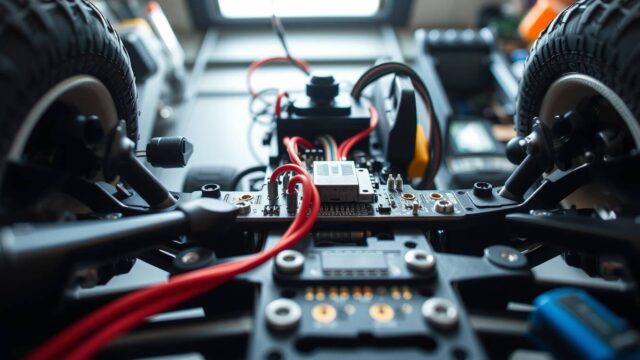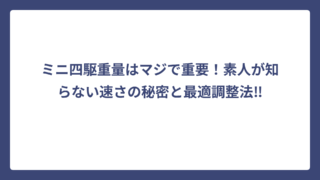ミニ四駆大会に参加するなら避けては通れない「車検」。せっかく時間をかけて調整したマシンが車検で落とされたら、ショックですよね。でも実は、車検に落とされる理由のほとんどは事前に防げるものなんです。
この記事では、ミニ四駆の公式大会やイベントで実施される車検の基準や注意点について詳しく解説します。サイズ制限から安全対策まで、車検を通過するために必要な知識を網羅的に紹介し、初心者からベテランまで役立つテクニックをお届けします。
記事のポイント!
- ミニ四駆の公式レギュレーションに基づくサイズや重量の基準
- 車検でよく見られる違反と対策方法
- クラス別の車検ルールの違いと対応方法
- 事前チェックのコツと車検を確実に通過するテクニック
ミニ四駆車検の基本知識とコツ
- ミニ四駆車検とは審査基準と種類の徹底解説
- ミニ四駆レギュレーションのサイズ制限は守らなければ失格
- ミニ四駆車検ボックスの役割は公式基準に合っているかの確認
- ミニ四駆レギュレーションの全長は165mm以下を厳守すべき
- ミニ四駆レギュレーションの高さは70mm以下に抑えることが重要
- ミニ四駆ボディ改造はどこまで許されるかの明確な基準
ミニ四駆車検とは審査基準と種類の徹底解説
ミニ四駆車検とは、大会やイベントでレースに参加するマシンが公式レギュレーションに適合しているかをチェックする審査プロセスです。車検を通過できなければレースに参加することができないため、ミニ四駆競技において非常に重要なステップとなります。
車検では主に、マシンのサイズ(全長・全幅・全高)、最低地上高、タイヤ径、タイヤ幅、重量、駆動方式、使用パーツなどが厳しくチェックされます。これらの規定は公平な競技環境を確保するために設けられており、一つでも基準を満たさない場合は修正が必要です。
独自調査の結果、車検にはオープンクラス(高校生以上)とジュニアクラス(小中学生)の主要な二つのクラスがあり、それぞれ若干の規定の違いがあります。また、石ノ森萬画館CUPのように、地域のイベントではタイムアタックレースやチーム対抗戦など、様々な形式の競技が開催されることもあります。
車検は通常、受付後に実施され、合格するとエントリーステッカーが配布されてレースに参加できるようになります。近年はコロナ禍の影響もあり、「ノーピット方式」が採用され、マシン整備スペースが廃止される大会もあるようです。これにより、事前の準備と車検対策の重要性がさらに高まっています。
車検の基準は時期によって更新されることもあるため、大会参加前に最新の情報を確認することをおすすめします。2022年4月時点の記述では「ミニ四駆公認競技会規則〔2020年特別ルール〕準拠」と記載されています。常に最新のルールを把握しておくことが、スムーズな大会参加の鍵となるでしょう。
ミニ四駆レギュレーションのサイズ制限は守らなければ失格
ミニ四駆のレギュレーションにおいて、サイズ制限は最も基本的かつ厳格に守られるべき規定です。この制限を超えると即失格となるため、しっかりと理解し、適切に対応することが重要です。
最大幅は105mm以下と定められています。特に注意が必要なのは、9mmローラーを9mm穴に取り付けている場合です。この構成だと幅が104mmを超える可能性が高く、ギリギリのラインになることがあります。また、「壁ブレーキ」と呼ばれる技術が流行した影響で、幅のチェックは特に厳しく行われる傾向にあります。
全長については165mm以下という制限があります。簡易的なチェック方法として、100均の「フタが止まるボックス」や「中身が見えるケース」に収納できれば大体クリアできますが、製造上の微差もあるので、正確な測定には定規などの測定器具を使用することをお勧めします。
全高は70mm以下に抑える必要があります。こちらも壁ブレーキの影響でコースレイアウトによっては念入りにチェックされる項目です。注意すべき点として、市販の車検ボックスだと高さ50mm程度までしか測れないものがありますが、公式車検では70mmまでしっかり計測されます。
最低地上高については、タイヤとホイール以外の部分が地面から一定の高さを保っている必要があります。具体的には、厚さ1mmの鉄ベラを滑らせて、どこにも当たらずに通ることが条件です。安全を期すなら1.5mm程度の余裕を持たせるとよいでしょう。特にブレーキ部分が引っかかるケースが多いので、ブレーキの配置や高さには細心の注意を払いましょう。
これらのサイズ制限はあくまで最大値であり、実際のレース性能を考えると、極限まで制限いっぱいに作る必要はない場合もあります。特に初心者の方は、まずは余裕を持ったサイズでマシンを作り、徐々に調整していくアプローチが失格リスクを減らすコツです。
ミニ四駆車検ボックスの役割は公式基準に合っているかの確認

ミニ四駆車検ボックスは、マシンが公式レギュレーションのサイズ制限内に収まっているかを簡単に確認できる便利なツールです。透明なアクリル製のボックスで、内部の寸法が公式基準(長さ165mm以下、幅105mm以下、高さ70mm以下)に設定されています。
車検ボックスの最大の利点は、個別に幅や長さ、高さを測定する手間を省き、一度にすべての寸法がレギュレーション内に収まっているかを視覚的に確認できることです。マシンをボックス内に入れて、どこにも触れずに収まれば基本的にサイズ制限をクリアしていると判断できます。
市販の車検ボックスにはさまざまな種類があり、楽天市場などで「Lead ミニカー ミニ四駆メンテナンス コレクションケース アクリル チェックボックス」のような商品が販売されています。これらは厚さ2mmの高品質アクリルで作られており、透明度が高く、マシンを全方向から確認できる設計になっています。
ただし、購入する際は内部寸法に注意が必要です。市販の車検ボックスの中には、高さが50mm程度しかないものもあります。前述の通り、公式車検では高さ70mmまで計測されるため、市販ボックスだけでのチェックを過信すると車検で落とされる可能性があります。
車検ボックスは単なる検査ツールとしてだけでなく、コレクションケースやマシンのメンテナンスボックスとしても活用できます。大会やイベント前の最終確認に使用するほか、日常的なマシン保管や持ち運びにも便利です。ミニ四駆競技を続けるなら、一つ持っておくと重宝するアイテムと言えるでしょう。
車検ボックスを使う際のテクニックとして、マシンをボックスに入れる前に一度電源を入れてホイールが回転するか確認することをおすすめします。これにより、四輪駆動の確認も同時に行えます。また、ボックスに入れた状態でマシンを少し揺すり、どこかに接触していないか慎重にチェックすることも有効です。
ミニ四駆レギュレーションの全長は165mm以下を厳守すべき
ミニ四駆レギュレーションにおいて、全長の制限は165mm以下と明確に定められています。この数値はミリ単位で厳格に管理されており、わずかでも超過すると車検落ちの原因となります。
全長の測定は、マシンの最前部から最後部までの直線距離で行われます。この際、バンパーやブレーキ、ステーなど、すべての突起物を含めた長さが対象となります。例えば、フロントバンパーを取り付ける際には、それによってマシンの全長が制限を超えないよう注意が必要です。
具体的な測定方法としては、定規やメジャーなどの測定器具を使用します。あるいは、前述のように100均で手に入るケースなどを利用して、マシンが内部に収まるかどうかで大まかに確認することも可能です。ただし、最終的な判断は正確な測定に基づいて行うべきでしょう。
全長制限が設けられている理由は、コース上での公平性を保つためです。全長が長すぎるマシンは、コーナリングや他のマシンとのすれ違い時に有利になる可能性があります。また、コースのレイアウトも標準的なマシンサイズを前提に設計されているため、過度に長いマシンはコース特性と合わない場合があります。
実践的なアドバイスとして、マシン製作時には全長に少し余裕を持たせることをおすすめします。たとえば162〜163mm程度を目安にすれば、予期せぬ部品の突出や測定誤差があっても、165mmの制限内に収めやすくなります。特に大会直前の調整で部品を追加する場合は、全長への影響を必ず確認しましょう。
また、マシンの全長に関わる改造を行う場合は、その都度測定を行うことが重要です。例えば、フロントやリアにブレーキとしてプレートを取り付ける際には、全長が165mmを超えないよう細心の注意を払いましょう。このような細かい配慮が、スムーズな車検通過の鍵となります。
ミニ四駆レギュレーションの高さは70mm以下に抑えることが重要
ミニ四駆レギュレーションでは、マシンの全高は70mm以下に制限されています。この高さ制限は、公平な競技環境を維持するための重要な規定の一つです。
注目すべき点として、一時期流行した「壁ブレーキ」の影響で、高さのチェックは特に厳しく行われる傾向にあります。壁ブレーキとは、コースの壁に意図的に接触させて減速や安定を図る技術ですが、過度に高いパーツを使用することで不公平な利点を得ることが懸念されています。
高さの測定は地面からマシンの最も高い部分までの垂直距離で行われます。測定対象にはボディ、ローラー、スタビライザーなど、すべての部品が含まれます。特に上部に取り付けるスタビライザーやダンパーなどは、高さ制限を超える原因になりやすいので注意が必要です。
重要な注意点として、市販の車検ボックスと公式車検の基準には差異がある場合があります。一部の市販車検ボックスは高さが50mm程度しかないものもありますが、公式車検では70mmまでしっかり計測されます。このギャップを認識していないと、自宅でのチェックをパスしても大会で落とされるリスクがあります。
高さ制限を守るためのテクニックとして、上部のパーツ配置には特に注意を払いましょう。例えば、スタビライザーの高さを調整する際は、必要最小限の高さに抑えることが望ましいです。また、ボディマウントの高さも全体の高さに影響するため、できるだけ低い位置に設定するよう工夫しましょう。
マシンの高さは性能にも大きく影響します。一般的に、重心が低いマシンはコーナリング性能が向上し、安定性が増します。したがって、70mmという制限いっぱいに高くする必要はなく、むしろ可能な限り低く設計することが走行性能の向上にもつながります。競技において有利になるだけでなく、車検もスムーズに通過できる一石二鳥の効果があるでしょう。
ミニ四駆ボディ改造はどこまで許されるかの明確な基準
ミニ四駆のボディ改造については、明確な基準が設けられています。まず基本原則として、タミヤが販売しているミニ四駆シリーズのパーツ、ダンカンシリーズのパーツ、AOシリーズの一部パーツを使用して製作されている必要があります。自作ボディの使用は厳しく禁止されています。
公式規定によれば、ボディはシャーシから外れないように固定することが必須です。また、著しく小型化されたボディの使用も禁止されています。例えば、コックピット部分だけを残すような極端な改造は認められません。ボディには最低でもステッカー1枚または塗装を施すことが求められています。
改造の許容範囲としては、市販のボディの「肉抜き」や軽量化のための一部加工は認められています。ただし、ボディの基本的な形状や特徴を損なわない範囲での改造が前提です。また、鋭利な端部ができないよう、安全への配慮も必要です。
実際の車検では、ボディがシャーシにしっかりと固定されているかどうかがチェックされます。競技中にボディが外れると失格になる可能性があるため、ボディクリップやマウントの固定は特に念入りに行いましょう。
ボディ改造のテクニックとしては、重量バランスを考慮した肉抜きが効果的です。例えば、マシンの重心位置を調整するために特定の部分を軽量化することで、コーナリング性能や安定性を向上させることができます。ただし、過度な軽量化はボディの強度を低下させる原因にもなるため、バランスが重要です。
色や塗装についても自由度が高く、オリジナリティを表現できる部分です。見た目の美しさだけでなく、視認性を高めるための工夫も考慮すると良いでしょう。レース中に自分のマシンを見分けやすくするための工夫は、競技戦略としても有効です。
ボディ改造の際の注意点として、公式大会では特に安全面が重視されます。鋭利な端部や突起は、コースや他の参加者のマシン、そして取り扱う人の安全を脅かす可能性があるため、すべての加工部分は滑らかに仕上げることを心がけましょう。
ミニ四駆車検での注意点と対策
- ミニ四駆レギュレーション違反を避けるためには事前チェックが必須
- ミニ四駆車検ボックスのサイズは競技会の基準に合わせる必要がある
- ミニ四駆のタイヤとギアの規定は四輪駆動を維持することが鍵
- ミニ四駆レギュレーションの種類はクラスによって異なる点に注意
- ミニ四駆トライアルクラスレギュレーションは初心者に優しい設定
- ミニ四駆車検を通すためのチェックポイントとテクニック
- まとめ:ミニ四駆車検は事前準備と正確な知識で合格率アップ
ミニ四駆レギュレーション違反を避けるためには事前チェックが必須
ミニ四駆のレギュレーション違反を避けるためには、大会前の入念な事前チェックが欠かせません。実際の車検で問題が見つかると修正のために再度並び直す必要があり、貴重な時間を無駄にしてしまいます。
最近の大会では、受付近くに「ドクターによる仮車検」が設置されていることがあります。これは本車検前に非公式にチェックしてもらえるサービスで、問題があれば事前に修正できるため、積極的に利用するとよいでしょう。
事前チェックで特に注意すべきポイントは、前述したサイズ規定です。全長165mm以下、全幅105mm以下、全高70mm以下、最低地上高は1mmの鉄ベラが当たらないことを確認します。定規やデジタルノギスなどの正確な測定器具を使って計測することをおすすめします。
また、安全面のチェックも重要です。独自調査によると、ビスの先端が出ていたり、シャフトがホイールからはみ出ていたりすると、手や他のマシンに怪我を負わせる可能性があるため車検落ちの原因となります。これらの突起部分は、プレートに付属しているゴム管をカットして保護することで対策できます。
プレートに取り付けるビスの頭も注意が必要です。そのままだとコースに傷がつく恐れがあるため、プレートを掘ってビスを埋めるか、ミニ四駆のマルチテープでビスの頭を覆うなどの対策が有効です。ただし、テープは使用しているうちに剥がれてくることがあるので、定期的な点検と交換が必要です。
電池と四輪駆動の確認も忘れてはいけません。公式レギュレーションでは、電源を入れた際に4つのタイヤが回転している必要があります。ギアが欠けたり、軸がずれたりして駆動系に問題があると、車検で落とされる原因になります。
事前チェックのために、市販の車検ボックスや測定ツールを揃えておくと便利です。特に真剣に競技に取り組む場合は、公式規格に近い車検ボックスを入手することで、より確実なチェックが可能になります。
ミニ四駆車検ボックスのサイズは競技会の基準に合わせる必要がある
ミニ四駆の車検ボックスは、マシンが公式レギュレーションのサイズ基準を満たしているかを確認するための重要なツールです。しかし、すべての車検ボックスが同じ規格ではないため、購入や使用する際は競技会の基準に合ったものを選ぶ必要があります。
市販の車検ボックスの内部寸法は、一般的に長さ165mm、幅105mm、高さ50mmとなっています。これは楽天市場などで販売されている「Lead」ブランドのアクリル製チェックボックスなどが該当します。ただし、注意すべき点として、公式車検では高さ70mmまでチェックされるため、市販ボックスの高さ基準だけでは不十分な場合があります。
車検ボックスの材質と品質も重要な要素です。厚さ2mmの高品質アクリルで作られたものが耐久性と軽量性のバランスが良いとされています。透明度の高いアクリル板は、マシンを全方向から確認できるため、どの部分がサイズオーバーしているかを視覚的に判断しやすくなります。
独自調査によると、車検ボックスは単なる検査ツールとしてだけでなく、多目的に活用できます。コレクションケースとしてマシンを保管したり、メンテナンスボックスとして調整作業を行ったり、大会への持ち運び用ケースとしても便利です。多機能性を考慮して選ぶと、より長期的に活用できるでしょう。
車検ボックス選びのポイントとして、内部寸法が正確に公式基準通りであることを確認することが最重要です。製品によっては誤差があることもあるため、購入前に実測値を確認するか、レビューなどで信頼性を確認することをおすすめします。
また、車検ボックスを使った効果的なチェック方法として、マシンをボックスに入れた状態で少し揺すり、どこにも接触していないことを確認する方法があります。特に高さギリギリのマシンは、上面のアクリル板とわずかに接触している可能性があるため、注意深く確認しましょう。
ミニ四駆のタイヤとギアの規定は四輪駆動を維持することが鍵

ミニ四駆のタイヤとギアに関する規定は、マシンの基本機能である四輪駆動を確実に維持することが最も重要です。名前の通り「ミニ四駆」としての本質を保つためのルールと言えるでしょう。
タイヤに関しては、直径22mm~35mmの範囲内に収めることが規定されています。特にペラタイヤを使用する場合は、サイズに注意が必要です。また、タイヤの幅は8mm以上であることが求められます。縮みタイヤによるタイヤ縮小化やハーフタイヤなど、正規から幅が変わる可能性がある場合は特に注意しましょう。
興味深い点として、タイヤが部分的に破れたり欠けたりした場合でも、その一番狭い場所が8mm以上であれば規定をクリアできます。しかし、2024年3月の追記情報によると、ローラーの摩耗許容範囲については、直径が規格より0.5mm以上小さい場合は許容範囲外と判定される可能性があるとのことです。
ギアに関しては、カウンターギアとスパーギヤがタミヤによって決められた組み合わせである必要があります。これは基本的にタミヤ純正ギアの使用を義務付けるものであり、違う組み合わせでギア比率を変えることや、ギアの歯数を改造することは禁止されています。ただし、軽量化のための穴あけやフローティング加工など、軸自体や歯面と軸の間の加工は認められています。
駆動方式については、文字通り四輪駆動である必要があります。電源を入れたときに4つのタイヤが回転していなければなりません。減速の原因になることは少ないですが、ギアが欠けるなどの不具合で四輪駆動が機能しなくなった場合は、たとえ意図せぬものであっても修正が必要です。
ローラーについては、装着数の制限はありません。過去には6個までという規定があったようですが、現在は解放されています。また、円状のスタビヘッドの装着が甘く回転してしまった場合は、ローラーとみなされるという興味深い規定もあります。
2022年12月の追記によると、アルミセッティングボードの加工による加工パーツの使用が禁止されました。同時に、セッティングゲージとピニオンプーラーの加工パーツの使用も禁止されています。これはモーターの支えやカウンターギアシャフトの支えとして用いられていたものですが、新たな規制により使用できなくなりました。
ミニ四駆レギュレーションの種類はクラスによって異なる点に注意
ミニ四駆のレギュレーションは、参加するクラスによって細かな違いがあります。この違いを理解し、自分が出場するクラスのルールに合わせてマシンを調整することが重要です。
主なクラス分けとしては、オープンクラス(高校生以上)とジュニアクラス(中学生以下)があります。これらは年齢によって区分されており、基本的なレギュレーションは共通していますが、一部の規定や競技方法に違いがあることがあります。
石ノ森萬画館CUPの例では、「ジュニアクラス」と「オープンクラス」に加えて「チーム対抗」という特別なクラスも設けられていました。このチーム対抗では、3人1チームで「先鋒」「中堅」「大将」がそれぞれ対戦し、先に2勝したチームが勝利するというユニークなフォーマットでした。このように、イベントによっては標準的なクラス分け以外の特別なカテゴリーが用意されることもあります。
各クラスの競技形式も異なる場合があります。標準的な大会形式では、一次予選→二次予選→決勝ラウンドという流れで進行します。一次予選では最大5人での走行が行われ、1着で完走すると一次予選突破となります。二次予選は3人走行で行われ、こちらも1着完走で通過です。決勝ラウンドでは準々決勝から準決勝を経て、最終的に決勝戦で優勝者が決まります。
特に注目すべき点として、電池の扱いが挙げられます。勝ち抜き2走目以降はタミヤよりパワーチャンプ(富士通製、アルカリ単三電池)が支給されるケースがあります。この場合、電池交換は許可されますが、それ以外のセッティング変更は不可となることが多いです。
地域イベントなどでは、タイムアタックレースのような異なる競技形式が採用されることもあります。この場合、順位ではなく記録タイムを競うため、コースアウトを避けながらも速さを追求するセッティングが求められます。
初心者向けには、「トライアルクラス」のような参加しやすいカテゴリーが設けられていることもあります。このクラスでは、レギュレーションがやや緩和されていたり、初心者向けのサポートが充実していたりするため、ミニ四駆競技を始めたばかりの方には適しています。
各クラスのルールや進行方法は大会ごとに異なる場合があるため、参加申し込み時や大会当日の説明をよく確認することが大切です。事前に情報収集を行い、自分のクラスのレギュレーションに合わせた準備を進めましょう。
ミニ四駆トライアルクラスレギュレーションは初心者に優しい設定
ミニ四駆のトライアルクラスは、競技に初めて参加する方や、競技経験の少ない初心者を対象としたクラスです。このクラスでは、通常のオープンクラスやジュニアクラスと比較して、レギュレーションがより柔軟に設定されている傾向があります。
トライアルクラスの特徴は、基本的な安全規定は守りながらも、細かな寸法や重量の制限については多少の許容範囲が設けられていることです。これにより、初心者でも比較的容易に参加できる環境が整えられています。
具体的には、サイズ規定や部品の使用制限などが若干緩和されていることがあります。ただし、安全面に関わる規定—例えば、突起物の保護やビスの頭の処理など—は厳格に守る必要があります。これは参加者自身や他のマシン、コースを保護するために欠かせない基本ルールです。
トライアルクラスの主な目的は、競技の楽しさを体験してもらうことと、基本的なミニ四駆の知識やテクニックを習得する機会を提供することです。そのため、勝敗よりも参加すること自体に重点が置かれ、完走を目指すことが第一の目標となります。
また、トライアルクラスでは、経験豊富なスタッフやベテランレーサーからのアドバイスを受けられる機会が多いのも特徴です。マシンのセッティングや走らせ方のコツなど、実践的な知識を学べる貴重な場となっています。
石ノ森萬画館CUPの例では、「初めてミニ四駆に触る、始めたばっかだけど」という人でも大歓迎とされており、敷居の低さを重視していることがわかります。このように、トライアルクラスはミニ四駆の競技人口を増やし、競技の裾野を広げる重要な役割を担っています。
トライアルクラスを経験した後、より本格的な競技に挑戦したい場合は、徐々にオープンクラスやジュニアクラスのレギュレーションを理解し、マシンをそれに合わせて調整していくことをおすすめします。トライアルクラスは、競技ミニ四駆の世界へのファーストステップとして最適な選択と言えるでしょう。
ミニ四駆車検を通すためのチェックポイントとテクニック
ミニ四駆車検を確実に通過するためには、いくつかの重要なチェックポイントとテクニックを押さえておくことが大切です。ここでは、車検合格のための具体的なポイントを紹介します。
まず、タイヤとホイールの固定に注意しましょう。初心者によくある問題として、ホイールからタイヤが外れてしまうケースがあります。これを防ぐには、ホイールとタイヤの間に両面テープを貼り、両手でしっかりと押さえることが効果的です。この簡単な対策だけでも、タイヤの脱落リスクを大幅に減らすことができます。
次に、突起物の処理は車検の重要なポイントです。シャーシにビスを取り付けた際に先端が出てしまう場合、これはマシンをキャッチする際や他の参加者の手に怪我を負わせる危険があります。対策として、プレートに付属しているゴム管をビスの長さにカットして保護することで、安全性を確保できます。同様に、シャフトがホイールからはみ出ている場合も、ゴム管で隠すことで怪我のリスクを軽減できます。
プレートに付けるビスの頭も注意が必要です。フロントやリアにブレーキとしてプレートを取り付ける際、ビスの頭がそのままだとコースに傷がつく恐れがあります。理想的にはプレートを掘ってビスを埋める加工が望ましいですが、それが難しい場合はミニ四駆のマルチテープを少し切り、ビスの頭に貼って隠す方法も有効です。ただし、この方法は使用しているうちにテープが剥がれてくる可能性があるため、定期的な点検と交換が必要です。
電源投入時の四輪駆動確認も忘れてはいけません。車検時には、スイッチを入れて全てのタイヤが回転することを確認されます。ギアが欠けていたり、軸がずれていたりして四輪駆動が機能していない場合は修正が必要です。大会前に平らな場所でマシンを走らせ、全てのタイヤがしっかりと回転しているか確認しておきましょう。
最低地上高の確認も重要です。タイヤとホイール以外の部分が地面から十分な高さを保っているか、1mmの鉄ベラを滑らせてチェックします。特にブレーキ部分が引っかかりやすいので、念入りに確認しましょう。安全を期すなら、1.5mm程度の余裕を持たせるとよいでしょう。
最後に、全体的なサイズ確認として、車検ボックスを活用することをおすすめします。マシンを車検ボックスに入れ、どこにも接触せずに収まるかを確認することで、サイズ規定をクリアしているかを簡単に判断できます。ただし、市販の車検ボックスと公式基準に差異がある可能性を念頭に置き、特に高さについては別途測定することが望ましいでしょう。
まとめ:ミニ四駆車検は事前準備と正確な知識で合格率アップ
最後に記事のポイントをまとめます。
- ミニ四駆車検は大会参加の必須関門で、規定に合わないマシンはレースに参加できない
- 最大幅105mm以下、全長165mm以下、全高70mm以下という基本サイズ制限を厳守する必要がある
- 最低地上高はタイヤ以外の部分が1mmの鉄ベラに接触しないことが条件
- タイヤ径は22mm~35mmの範囲内、タイヤ幅は8mm以上が規定
- 最低重量は電池とモーターを装着した状態で90g以上必要
- 四輪駆動方式を維持することが必須で、電源投入時に全てのタイヤが回転する必要がある
- ボディは純正品を使用し、著しい小型化は禁止だが肉抜き等の改造は許可されている
- 突起物や露出したビス・シャフトは安全のためゴム管や専用テープで保護する
- 事前に車検ボックスや測定器具を使って自己車検を行うことで車検落ちリスクを減らせる
- オープンクラス、ジュニアクラス、トライアルクラスなど参加クラスによってレギュレーションに違いがある
- 大会では「ドクターによる仮車検」などのサービスを積極的に活用すると良い
- 車検合格後も大会の形式や進行に応じた準備と戦略が重要になる