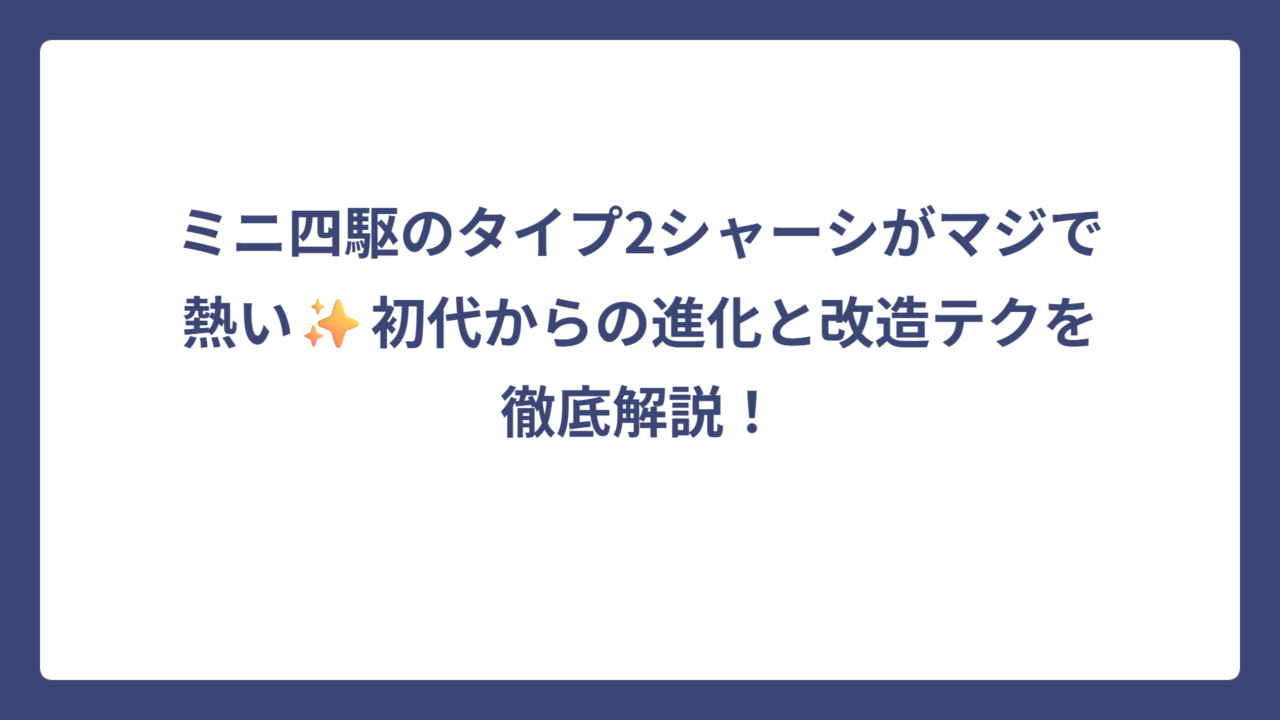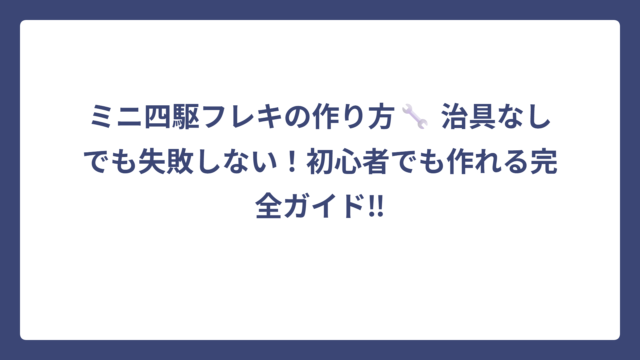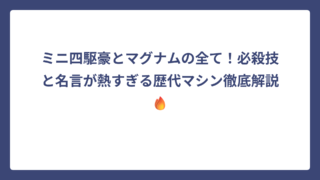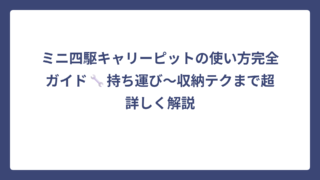ミニ四駆の歴史において重要な転換点となった「タイプ2シャーシ」。1988年にアバンテJr.と共に登場したこのシャーシは、それまでのタイプ1とは一線を画す性能と精度で、多くのミニ四駆ファンを魅了しました。公式コースでの走行を前提に設計されたタイプ2シャーシは、その革新的な構造と高い走行性能で、今なお多くの愛好家から支持されています。
本記事では、タイプ2シャーシの特徴や歴史だけでなく、現代のレースでも活用できる改造テクニックや互換性のあるパーツ情報まで徹底解説します。初代タイプ2シャーシからVS、ARシャーシまで受け継がれた設計思想や、各種カラーバリエーションについても詳しく紹介していきますので、ぜひ最後までお読みください。
記事のポイント!
- タイプ2シャーシの基本スペックと革新的な特徴について理解できる
- タイプ2シャーシを強化するための効果的な改造方法が分かる
- 互換性のあるパーツと使用可能なギヤ比について詳しく知ることができる
- タイプ2シャーシと他のシャーシとの性能比較で優位点と弱点が分かる
ミニ四駆のタイプ2シャーシとは何か?歴史と特徴
- タイプ2シャーシは1988年にアバンテJr.と共に登場した革新的オンロード専用シャーシである
- タイプ2シャーシの基本スペックは82mmホイールベースと8mm地上高によるバランスの良さが特徴
- タイプ2シャーシの革新点は6mmベアリング対応と高精度駆動系による圧倒的な性能向上
- タイプ1シャーシとの違いは精度と冷却性がさらに向上し直進安定性が大幅に改善された点
- タイプ2シャーシ採用車種はアバンテJr.、グラスホッパーⅡJr.、バンキッシュJr.、スコーチャーJr.の4種のみ
- タイプ2シャーシの入手難易度は2012年の再販以降は比較的容易になっている
タイプ2シャーシは1988年にアバンテJr.と共に登場した革新的オンロード専用シャーシである
1988年、ミニ四駆の世界に革命をもたらしたタイプ2シャーシが「アバンテJr.」と共にデビューしました。当時は特にネーミングもなく「ニューシャーシ」と呼ばれていましたが、のちに「タイプ2」という名前が定着していきました。
このシャーシの最大の特徴は、ミニ四駆初の本格的オンロード仕様として開発されたことです。それまでのタイプ1がオフロード走行を前提としていたのに対し、タイプ2は公式コースでの走行を前提に設計されました。
RCカーの世界ではアバンテがレースシーンを席巻し「アバンテじゃないと勝てない」と言われるほどの存在でしたが、その技術と情熱はミニ四駆のタイプ2シャーシにも受け継がれています。
実際、タイプ2シャーシは登場当時、それまでのレーサーミニ四駆のマシンを無改造で追い抜くという衝撃的な性能を持っていました。これは「アバンテ・ショック」と呼ばれる現象をミニ四駆界にももたらしました。
タイプ2シャーシの登場により、ミニ四駆はより高性能で精密なレース指向のトイへと進化し、第1次ブーム期を通じて広く使われることになったのです。
タイプ2シャーシの基本スペックは82mmホイールベースと8mm地上高によるバランスの良さが特徴
タイプ2シャーシの基本スペックを詳しく見てみましょう。このシャーシはホイールベース82mm、地上高8mmというバランスの取れた設計となっています。使用するドライブシャフトは60mmで、対応するギヤ比は4:1、4.2:1、5:1の3種類です。
カウンターギヤシャフトはストレートタイプを採用し、ターミナルはB型を使用しています。重量はシャーシのみで12.9g、ボディやボディキャッチ、電池を除いたノーマル状態の全重量は66gと、当時としては軽量化が図られていました。
見た目は現代のシャーシと比べるとシンプルですが、大径タイヤとの組み合わせでコンパクトに見えるのが特徴です。底面には肉抜き穴が設けられ、軽量化も図られています。
駆動系は全て右側にまとめられ、モーターからカウンターギヤ、スパーギヤへと繋がり、クラウンギヤが前輪へと駆動を伝達する構成になっています。この基本レイアウトは、その後10年間ほとんど変更されることがなく、1998年発売のスーパーXシャーシまで受け継がれました。
タイプ2シャーシはタイプ1よりも2mmホイールベースが長くなったため、直進安定性が向上し、オンロードコースで真価を発揮するシャーシとなりました。
タイプ2シャーシの革新点は6mmベアリング対応と高精度駆動系による圧倒的な性能向上
タイプ2シャーシが革新的だった点は数多くありますが、特に注目すべきは軸受けに直径6mmのベアリングが無加工で取り付けられるようになったことです。これによりコーナリング性能と走行抵抗の低減に大きく貢献しました。
また、駆動系の精度がタイプ1から大幅に向上したことも重要なポイントです。新設計のカウンターギヤ2種と新設計のスパーギヤ1種を採用し、ピニオンギヤも8Tのものに統合されました。クラウンギヤは前後とも共通(オレンジクラウン)とすることで互換性と整備性を高めています。
ローラーが標準で付属するようになったことも大きな変更点です。フロントバンパーのビス穴がタイプ1の倍に増えたほか、サイドガードにもローラー取り付け穴が付き、セッティングの幅が広がりました。
モーターを縦置き型のターミナルと一体となる固定パーツの採用タイプに変更し、ホルダーがモーターをむき出しにするような形になったため冷却性が向上しました。これによりモーターの熱暴走を防ぎ、長時間の走行でも安定したパフォーマンスを維持できるようになりました。
ターミナルの形状も変更され、リヤを中心に整備性と信頼性が向上しました。スイッチも大型化され、使いやすくなりました。これらの改良により、タイプ2シャーシはノーマル状態でもタイプ1に改造を施したマシンを圧倒するほどの性能を持つシャーシへと進化したのです。
タイプ1シャーシとの違いは精度と冷却性がさらに向上し直進安定性が大幅に改善された点
タイプ2シャーシとタイプ1シャーシの違いを詳しく見ていきましょう。最も大きな違いは駆動系全体の精度向上です。タイプ1と基本レイアウトこそ同じものの、半分以上のギヤが一新され、ほぼ別物と言えるほど進化しました。
タイプ2シャーシで初採用された5:1、4.2:1のギヤは、後の2次ブーム最終型のVSシャーシや最新シャフトドライブシャーシのARにも使える互換性の高さを持っており、いかにこのシャーシの設計が優れていたかがうかがえます。
モーターマウントとリヤギヤケース周りの構造も改良され、メンテナンス性は若干悪いものの精度を高めやすい方式となりました。この構造はX系、VS、S2、ARなどに継承された優れた設計です。
また、タイプ1と比較して車高が低くなり、重心位置も下がったことで安定性が向上しました。ホイールベースも2mm伸びたことで旋回性は若干落ちましたが、直進安定性は大幅に向上しています。
オフロード走行性能はタイプ1に比べ低下しましたが、コースでの走行性能は圧倒的に向上しました。各部の精度がよくなったため速度性能は確実に向上し、ノーマル状態でも改造を施したタイプ1を圧倒することもザラだったと言われています。
このようにタイプ2シャーシは、タイプ1の欠点を克服し、より高い性能と精度を持つシャーシとして設計され、ミニ四駆の進化に大きく貢献したのです。
タイプ2シャーシ採用車種はアバンテJr.、グラスホッパーⅡJr.、バンキッシュJr.、スコーチャーJr.の4種のみ
タイプ2シャーシは、その画期的な性能にもかかわらず、限られた車種にしか採用されませんでした。具体的には、アバンテJr.、グラスホッパーⅡJr.、バンキッシュJr.、スコーチャーJr.の4車種のみです。
特にアバンテJr.はタミヤのミニ四駆史上最も売れたボディと言われており、漫画化作品の主人公機を差し置いて歴代1位を記録したほどの人気モデルでした。そのスタイルは現代の目で見ても美しく、無駄のない生粋のレーシングバギーとしての佇まいを感じさせます。
後のシリーズでもアバンテJr.のモデルチェンジ版が数多く発売され、タミヤにとっても特別なモデルであることは間違いありません。その人気ゆえか、現代でもボディだけなら比較的入手が容易なモデルとなっています。
タイプ2シャーシ採用車種が少ない理由としては、その後のメインラインナップがタイプ3シャーシ採用車に移ったことが挙げられます。タイプ3は2次ブーム時もダッシュ軍団のラインナップが定期的に再生産されていましたが、タイプ1・タイプ2・タイプ4のラインナップは軒並み生産停止処分を受け、長らく入手が困難な時期がありました。
しかし、2012年にアバンテJr.および同ブラックスペシャルが再販されたことで、メモリアルBOXに頼らずともシャーシ自体は比較的入手しやすくなっています。また、キット販売が行われていない現在でも、新橋タミヤプラモデルファクトリーでシャーシ単品が販売されているほか、部品請求でも入手可能となっています。
タイプ2シャーシの入手難易度は2012年の再販以降は比較的容易になっている
かつてはプレミア価格がついていたタイプ2シャーシですが、2012年の再販以降は入手のハードルが下がっています。特にアバンテJr.の30周年記念モデルとして復刻されたこともあり、以前よりも手に入れやすくなりました。
タイプ2シャーシには、標準的なグレーの他にも、アバンテJr.ブラックスペシャルで採用されたブラック、アバンテJr.スペシャル、バンキッシュJr.スペシャル、スコーチャーJr.スペシャルで採用されたクリアなど、いくつかのカラーバリエーションが存在します。
クリアタイプには、それぞれ黄(アバンテ)、赤(バンキッシュ)、青(スコーチャー)のカラースリックタイヤが付属していました。また、青色のシャーシも存在し、かつてモデラーズギャラリーで販売されたり、抽選などで配布されたりした非常に希少なバリエーションもあります。
ミニ四駆ステーションなどでは、シャーシ単品でバラ売りされている店舗もあるので、新しいキットを購入せずとも入手できる可能性があります。また、新橋タミヤプラモデルファクトリーでもシャーシ単品が販売されているため、探してみる価値はあるでしょう。
ただし、世に出てから30年以上経過していることもあり、保存状態の良いものを見つけるのは難しい場合もあります。また、昔のシャーシを知らない若い世代には「何これ?」と言われる扱いになることもあるため、ミニ四駆の歴史を知る上での貴重な資料としての価値も持っています。
ミニ四駆のタイプ2シャーシの改造とカスタマイズポイント
- タイプ2シャーシのフロント改造はFRPによる補強が強度と剛性向上に最も効果的
- タイプ2シャーシへのリヤステー取り付けはリヤースキッドローラーセットのアタッチメントを活用すべき
- タイプ2シャーシの互換ギヤは4:1、4.2:1、5:1で超速ギヤは公式的にはアウト
- タイプ2シャーシのベアリング組み込みは無加工で可能で走行性能が大幅に向上する
- タイプ3シャーシとの比較ではタイプ2の方が基本性能で優れている点が多い
- タイプ2シャーシとVSシャーシの共通点は多く、VSはタイプ2の設計思想を継承している
- まとめ:ミニ四駆のタイプ2シャーシは改造次第で現代でも十分に戦える名シャーシである
タイプ2シャーシのフロント改造はFRPによる補強が強度と剛性向上に最も効果的
タイプ2シャーシを現代のレースで使用するにあたって、最も重要な改造ポイントはフロントバンパーの補強です。このシャーシは登場当時から強度面での課題があり、特にフロント部分は弱いとされていました。
フロントバンパーを補強する方法としては、FRPやカーボンなどの素材を使用するのが最も効果的です。フニャフニャなフロントバンパーをそのまま使うよりも、根元の水平な部分までカットし、そこに新たにFRPやカーボン製のバンパーを装着する方法が一般的です。
具体的な手順としては、まずフロントバンパーの根元部分をスパッとカットします。次に、FRPリヤブレーキステーセットなどを活用して新しいバンパーを作成します。その際、シャーシの腹側からも加工が必要で、出っ張っている部分を平らにするとスムーズに取り付けられます。
フロントバンパーだけでなく、フロントギアカバーの抑えもFRPで補強することで、クラッシュやロッキング時にカバーが開かないようにすることができます。これには皿ビスとロックナットを使用するとしっかりと固定できます。
最終的にはスラストをつけるFRPとバンパーを装着し、ローラーをつけることで、かなり強固なフロント部分が完成します。こうした補強を施すことで、タイプ2シャーシの弱点を克服し、現代のレースでも十分に戦えるマシンへと進化させることができるのです。
タイプ2シャーシへのリヤステー取り付けはリヤースキッドローラーセットのアタッチメントを活用すべき
タイプ2シャーシの走行安定性をさらに向上させるには、リヤステーの取り付けが効果的です。しかし、タイプ2シャーシにリヤステーを取り付けるには専用のパーツが必要となります。
リヤステーを取り付ける際に最も活用すべきなのが、「リヤースキッドローラーセット」に含まれるアタッチメント(H5パーツ)です。このパーツを使うことで、1点止めステーをタイプ2シャーシに取り付けることが可能になります。
具体的な取り付け手順としては、まずナットを六角の穴にはめ、シャーシ側から6mmビスで止めます。次に1点止めステーを取り付けますが、後ろから見ると右側がシャーシと干渉する場合があるので、必要に応じてステー側をカットして調整します。
リヤーステーの選択肢としては、「リヤローラースタビセット」と「リヤースキッドローラーセット」の2種類がありますが、どちらも現在のレースで使うには強度が不足しています(特に前者)。そのため、リヤースキッドローラーセットのアタッチメントを利用して、他の強度の高いリヤステーを取り付けることをお勧めします。
ただし、現在入手可能な一点止めリヤステーで、無加工のままアタッチメントに取り付けられるものはないので注意が必要です。リヤースキッドローラーセットは「ミニ四駆グレードアップパーツセット クラシックVol.3」で入手可能ですので、チェックしてみてください。
タイプ2シャーシの互換ギヤは4:1、4.2:1、5:1で超速ギヤは公式的にはアウト
タイプ2シャーシで使用できるギヤ比については、公式には4:1、4.2:1、5:1の3種類となっています。これらのギヤ比は走行スタイルや路面状況に応じて選択することで、マシンの性能を最適化することができます。
興味深いことに、タイプ2シャーシで初採用された5:1、4.2:1のギヤは、後の2次ブーム最終型のVSシャーシや最新シャフトドライブシャーシのARにも使える互換性の高さを持っています。これは、タイプ2シャーシの設計がいかに優れていたかを示す証拠でもあります。
超速ギヤ(3.5:1など)については、ギヤボックスを改造すれば装着可能ですが、タミヤの公式見解としてはアウトとされているので注意が必要です。そのため、公式レースなどで使用する場合は、4:1のハイスピードギヤセットが使える最高速のギヤとなります。
ギヤ比の選択は、コースレイアウトや電池の種類、モーターのタイプなどによって最適なものが変わってきます。一般的に、直線が多いコースでは4:1のようなギヤ比の低いものが有利ですが、コーナーが多いテクニカルなコースでは5:1のようなギヤ比の高いものが安定した走りを実現します。
なお、ギヤは駆動系の中核を担う重要なパーツですので、定期的なメンテナンスを行い、摩耗や損傷がないか確認することをお勧めします。特にタイプ2シャーシは発売から30年以上経過しているため、中古品を使用する場合はギヤの状態にも注意を払いましょう。
タイプ2シャーシのベアリング組み込みは無加工で可能で走行性能が大幅に向上する
タイプ2シャーシの大きな特徴の一つに、軸受けに直径6mmのベアリングが無加工で取り付けられる点があります。これはタイプ1からの主だった変更点の一つであり、走行性能を大幅に向上させる重要な要素です。
ベアリングを組み込むことの最大のメリットは、車軸の回転抵抗を減らすことができる点です。これにより、駆動ロスが減少し、モーターパワーをより効率的にタイヤに伝えることができます。結果として、スピードアップだけでなく、バッテリーの消費効率も向上します。
タイプ2シャーシにベアリングを組み込む際は、6mmのボールベアリングを使用します。フロントとリヤの両方に装着することで、マシン全体のバランスが取れた走行性能が得られます。特に、ローラー用ベアリングよりも精度の高い軸受け専用ベアリングを使用することで、より一層の性能向上が期待できます。
ベアリングのメンテナンスも重要です。定期的に脱脂・洗浄し、適切な潤滑油を注すことで、ベアリングの性能を維持できます。特に、長期間使用していないベアリングは内部に埃やゴミが溜まっている可能性があるので、使用前にメンテナンスを行うことをお勧めします。
このようにタイプ2シャーシはベアリングの組み込みが容易で、これによる性能向上効果も大きいため、改造の第一歩としてぜひ取り入れてみてください。コストパフォーマンスも高く、比較的簡単な改造でありながら効果は絶大です。
タイプ3シャーシとの比較ではタイプ2の方が基本性能で優れている点が多い
タイプ2シャーシとタイプ3シャーシを比較すると、興味深いことに多くの面でタイプ2の方が基本性能で優れています。タイプ3はタイプ1のオンロード用改良型として位置づけられていましたが、タイプ2と比較すると性能面での優位性を保っていました。
タイプ2シャーシの優位点としては、まず駆動系の精度の高さが挙げられます。タイプ3と比較しても、ギヤの精度や噛み合わせの良さは明らかで、これが直接スピードとスムーズな走行性に繋がっています。
また、モーターの冷却性もタイプ2の方が優れています。タイプ2はモーターホルダーがモーターをむき出しにするような形状になっているため、走行中の熱がこもりにくく、長時間走行してもモーターの性能低下が少ないという利点があります。
整備性や信頼性についても、タイプ2で改良されたターミナルやスイッチのおかげで、タイプ3より優れています。特にスイッチの大型化は使いやすさを大幅に向上させました。
一方で、タイプ3の方が優れている点としては、ボディマウントの種類の多さや、一部パーツの入手のしやすさなどが挙げられます。タイプ3はダッシュ軍団のラインナップが定期的に再生産されていたため、パーツの流通量が多いという利点があります。
しかし、総合的な性能や走行フィーリングを考えると、タイプ2の方が「純粋なレースマシン」としての資質が高いと言えるでしょう。ただし、現代のレースで使用するには、どちらのシャーシも適切な補強や改造が必要となります。
タイプ2シャーシとVSシャーシの共通点は多く、VSはタイプ2の設計思想を継承している
タイプ2シャーシとVSシャーシには多くの共通点があり、VSはタイプ2の設計思想を色濃く継承していることが分かります。これは、VSシャーシが2次ブーム最終型のシャフトドライブシャーシとして、それまでの優れた設計を集大成したものだからです。
まず、駆動系の構造に着目すると、VSシャーシではタイプ2方式を再び採用し、カウンターギヤ(正確にはカウンターギヤシャフト)をモーターマウントではなくシャーシ本体に固定する方式を取り入れています。これにより駆動系の精度が向上しましたが、モーター交換の際にカウンターギヤを外す必要があるという欠点も同様に継承されています。
VSシャーシで使用されるギヤも、タイプ2で初採用された5:1、4.2:1のギヤが使用可能であり、基本設計は同じと言えます。また、リヤのモーターマウントおよびギヤケースの構造やパーツ構成もVSと良く似ています。
さらに、VSに採用されているX型ターミナルも、タイプ2のB型ターミナルの改良型と考えることができます。このB型ターミナルは(ZERO系シャーシを除き)TZ-Xまで同形状のものが使われ、さらにX系、VS、ARに使われているターミナルもこの改良型です。
これらの共通点から、タイプ2シャーシがいかに先進的で優れた設計だったかがうかがえます。VSシャーシはタイプ2の設計思想を受け継ぎながら、さらなる精度向上や使いやすさを追求したシャーシと言えるでしょう。タイプ2はまさに、VSまで続く本格オンロード用シャーシの直接の祖型なのです。
まとめ:ミニ四駆のタイプ2シャーシは改造次第で現代でも十分に戦える名シャーシである
最後に記事のポイントをまとめます。
- タイプ2シャーシは1988年にアバンテJr.と共に登場した革新的なオンロード専用シャーシ
- 基本スペックは82mmホイールベース、8mm地上高で、駆動効率と精度が大幅に向上
- 6mmベアリングが無加工で取り付け可能になり、ローラーも標準装備された最初のシャーシ
- タイプ1と比較して車高が低くなり、冷却性や直進安定性が大幅に改善された
- アバンテJr.、グラスホッパーⅡJr.、バンキッシュJr.、スコーチャーJr.の4種のみに採用
- 2012年の再販以降は入手難易度が下がり、比較的容易に手に入るようになった
- フロント改造はFRPによる補強が最も効果的で、強度と剛性が大幅に向上する
- リヤステー取り付けにはリヤースキッドローラーセットのアタッチメントが活用できる
- 使用可能なギヤ比は4:1、4.2:1、5:1で、超速ギヤは公式には非対応
- ベアリング組み込みは無加工で可能で、走行性能が大幅に向上する重要な改造ポイント
- タイプ3と比較してもタイプ2の方が基本性能で優れている点が多い
- VSシャーシはタイプ2の設計思想を色濃く継承しており、多くの共通点がある
- 適切な改造とメンテナンスを施せば、現代のレースでも十分に戦える名シャーシである