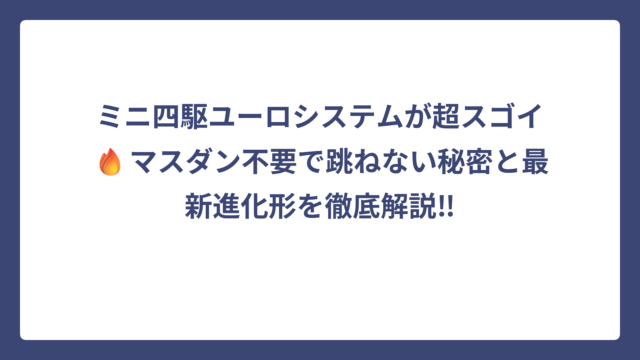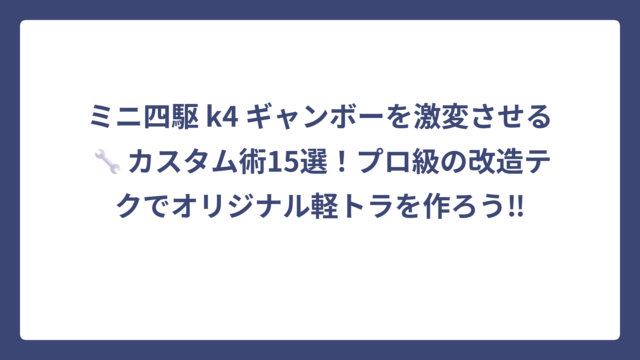ミニ四駆のレースには様々なレギュレーションがありますが、近年特に人気を集めているのが「B-MAX」です。B-MAX(Basic-MAX)とは、タミヤのミニ四駆公認競技会規則をベースにしながら、パーツの無加工を基本としたレギュレーションのこと。「ポン付け」と呼ばれるパーツの組み付けを中心に、誰でも気軽に楽しめるように設計されています。
このレギュレーションの最大の特徴は、高度な工作技術がなくても参加できる点です。複雑な加工や特殊なパーツを使わず、シンプルな構成でレースを楽しむことができるため、初心者や子供にも優しい仕様になっています。本記事ではB-MAXの基本ルールからおすすめのシャーシ、セッティングのコツまで徹底解説していきます。
記事のポイント!
- B-MAXとは何か、そのルールと特徴を理解できる
- B-MAXマシンの作り方とおすすめパーツについて学べる
- 初心者がB-MAXで勝つためのセッティングのコツがわかる
- B-MAX大会の特徴と参加方法について知ることができる
ミニ四駆のB-MAXとは何かを徹底解説
- ミニ四駆のB-MAXとはポン付けで作るレギュレーション
- B-MAXとオープンクラスの違いはシンプルさと無加工が基本
- B-MAXレギュレーションが生まれた経緯はフェアプレイ精神を重視
- B-MAX GPレギュレーションのポイントは無加工での組み立て
- B-MAXレギュレーションの許可されている加工は皿ビス加工とホイール貫通
- B-MAXレギュレーションの禁止事項はボディの分割や肉抜きなど
ミニ四駆のB-MAXとはポン付けで作るレギュレーション
B-MAX(Basic-MAX)は、タミヤのミニ四駆公認競技会規則をベースに、Basic-MAX GP実行委員会が独自に定めたレギュレーションです。最大の特徴は、グレードアップパーツを「無加工」で取り付ける「ポン付け」が基本となっていることです。
このレギュレーションは、横浜にあるフォースラボが制定したとも言われていますが、現在はB-MAX GP実行委員会が運営・管理を行っています。彼らが定めたルールに従い、全国各地でB-MAX GPの予選大会や決勝大会が開催されています。
B-MAXの魅力は、専門的な工具や技術がなくても誰でも参加できる点にあります。パーツの加工をしないため、初めてミニ四駆を組み立てる子供や、久しぶりにミニ四駆を再開する大人でも気軽に始められます。
また、B-MAXはシンプルなルールながらも奥が深く、パーツの選択やセッティングにこだわることで走行性能を高めることができます。無加工のレギュレーションの中で、いかに知恵と工夫を凝らせるかが勝負の鍵となります。
B-MAX GP実行委員会の公式サイトによると、B-MAXの醍醐味は「基本無加工のレギュレーションの中で大会が工夫を凝らした競技コースに対して全てのレーサーがフェアプレイ精神のもと頭とテクニックを使って挑戦すること」とされています。
B-MAXとオープンクラスの違いはシンプルさと無加工が基本
ミニ四駆の主要なレギュレーションとして「B-MAX」と「オープン」が挙げられますが、両者には明確な違いがあります。オープンクラスは、タミヤのミニ四駆公認競技会規則の範囲内であれば、パーツの加工など何でもOKとされています。一方、B-MAXはタミヤのミニ四駆公認競技会規則を適用した上で、基本的に加工無しという制限が加わります。
この違いがマシン作りにどう影響するのか、具体的に見ていきましょう。オープンクラスでは、シャーシのバンパーを切断したり、FRPやカーボンプレートを加工したりと、様々な改造が可能です。これにより、高い次元でマシンのカスタマイズができる反面、専門的な知識や技術、工具が必要となります。
対して、B-MAXでは既存の穴を利用してグレードアップパーツを取り付けることが基本となります。「どうグレードアップパーツを付けるか」という点に焦点を当て、複雑な加工は必要としません。このシンプルさが、初心者にとっての大きなメリットになっています。
また、実験的な観点からも違いがあります。独自調査の結果、B-MAXはギミックが少ないため、例えばローラー幅を変えた際のコーナー速度の変化など、特定の要素がマシンに与える影響を直接観察しやすい特徴があります。オープンマシンでは他のギミックの影響で単一要素の効果を判断しづらい場合があるのに対し、B-MAXはマシンの挙動変化が見やすいのです。
さらに興味深いのは、B-MAXでは「最高速度の上限がオープンよりも低い」という特性上、速いモーターを使いこなすのが難しく、モーターの性能差が結果に与える影響が小さくなる傾向があることです。これにより、技術的に優れたレーサーであっても、コースアウト率が上がり、結果的に初心者でも勝つチャンスが生まれやすくなっています。
B-MAXレギュレーションが生まれた経緯はフェアプレイ精神を重視
B-MAXレギュレーションが誕生した背景には、ミニ四駆を通じてフェアな競争環境を作りたいという思いがありました。ミニ四駆のレース競技は、技術力や経験の差が大きく結果に影響することがあり、初心者や子供たちが参加しづらい状況が生まれていました。
B-MAX GP実行委員会は、その公式サイトの前文で次のように述べています。「B-MAX GPの醍醐味は基本無加工のレギュレーションの中で大会が工夫を凝らした競技コースに対して全てのレーサーがフェアプレイ精神のもと頭とテクニックを使って挑戦することにあります。」
このような理念のもと、加工技術の差ではなく、パーツ選びやセッティングのセンス、レース戦略などの「頭脳戦」を重視したレギュレーションとして、B-MAXは確立されました。加工無しという制限により、参加者の技術的なハードルを下げ、誰でも気軽に参加できる環境を作り出したのです。
また、B-MAXでは「ミニ四レーサーとして正々堂々と戦い、レースを通じてお互いの交流とミニ四駆技術向上を希望」すると明記されています。これは単に勝敗を競うだけでなく、参加者同士の交流や技術の共有も大切にしたいという願いが込められています。
B-MAXレギュレーションは時代とともに進化しており、現在はver3.0まで更新されています。初期のルールから改良を重ね、より多くの人が楽しめるレギュレーションとして成長し続けているのです。
B-MAX GPレギュレーションのポイントは無加工での組み立て

B-MAX GPレギュレーションの最も重要なポイントは、「無加工での組み立て」にあります。この基本理念が、B-MAXの全てのルールの土台となっています。
具体的には、タミヤが発売しているミニ四駆のパーツを、基本的に加工せずに組み立てることが求められます。例えば、シャーシやFRP、カーボンなどのプレート類は、皿ビス加工やエッジのテーパー加工以外の改造は禁止されています。
また、ローラーやギア、ビス、シャフトなどの金属パーツの加工も基本的に禁止されています。これらのルールにより、高価な工具や専門的な加工技術がなくても、誰でも同じスタートラインに立てるのです。
加工が禁止されている一方で、パーツの選択や組み合わせ、セッティングなどの「知恵」の部分は自由度が高く設定されています。同じパーツを使っても、どのように組み合わせるか、どのようなセッティングにするかで、マシンの性能は大きく変わります。
B-MAXでは、マスダンパーなどの重量物を用いたスイング系の制振ギミック(提灯、ヒクオ、ノリオ、東北ダンパー、キャッチャーダンパー、ギロチンダンパー、ドラえもん提灯など)の使用が禁止されています。これにより、複雑なギミックに頼ることなく、基本的なセッティングでいかに速く安定して走らせるかが問われるのです。
独自調査の結果、B-MAXの「無加工」というルールは、逆に参加者の創意工夫を引き出す効果があることがわかりました。制限があるからこそ、その中でいかに効率的にマシンをセットアップするか、知恵を絞ることになるのです。
B-MAXレギュレーションの許可されている加工は皿ビス加工とホイール貫通
B-MAXレギュレーションでは基本的に加工は禁止されていますが、いくつかの例外的な加工が許可されています。主なものとして「皿ビス加工」と「ホイール貫通」が挙げられます。
皿ビス加工とは、ビスの頭をフラットに収めるための加工です。通常のビスを使用すると頭が出っ張ってしまい、マシンの走行に悪影響を及ぼすことがあります。B-MAXレギュレーションでは、既存のビス穴に対して皿ビス加工を施すことが許可されています。シャーシや各種プレート類の既存穴に皿ビス加工を行うことで、ビスの頭を埋め込み、マシンの走行抵抗を減らすことができます。
もう一つの許可されている加工が「ホイール貫通」です。これはホイールにシャフトが通る穴を貫通させる加工のことで、タイヤの固定を強化する目的で行われます。B-MAXでは走行中のタイヤやホイールの脱落は失格となるため、この加工は重要です。ホイール貫通をすることで、シャフトがホイールを貫通して固定され、走行中のタイヤ外れを防止できます。
また、ボディに関しては、シャーシやプレート、マスダンパー、タイヤに干渉する部分を切断することが許可されています。ただし、切断できるのは干渉部分から3mm以内と規定されており、過度な加工は認められていません。
さらに、ボディの肉抜きやメッシュの貼付けも、ボディの原型が分かる範囲内であれば許可されています。ただし、原型が分からなくなるような過度な肉抜きや、肉抜きされたボディの破損部分を接着剤で補修することは禁止されています。
これらの許可されている加工は、あくまでマシンの安全性や基本性能を確保するための最低限のものであり、過度な加工によるアドバンテージを得ることを防ぐ目的があります。
B-MAXレギュレーションの禁止事項はボディの分割や肉抜きなど
B-MAXレギュレーションでは、マシンの公平性を保つために多くの禁止事項が設定されています。これらを理解することは、B-MAXマシンを作る上で非常に重要です。
まず、ボディに関する禁止事項として「ボディの分割」が挙げられます。ボディを切り分けて再構成することは認められていません。また、ポリカーボネートやPET製のボディの使用も禁止されており、プラスチック製のボディのみが使用可能です。原型が分からなくなるような過度な肉抜きや、肉抜きされた箇所が破損したボディの使用も禁止されています。これは、折れて飛び出たり尖った部分がレーサーやマーシャルの怪我に繋がる可能性があるためです。
タイヤとホイールに関しては、異なるサイズの組み合わせが禁止されています。例えば、ローハイトタイヤを大径ホイールに装着するような組み合わせはできません。また、タイヤの加工も禁止されており、長期使用に伴う削れの場合でも、直径の変化量が1mm以上の場合は加工とみなされます。
シャーシに関しては、新規ビス穴の追加やシャーシの肉抜き、切断などが禁止されています。電池の設置も、各種シャーシの指定方向以外への設置は禁止されており、シャーシの逆転使用はできません。
マスダンパーについても、形状加工や穴拡張は禁止されています。特筆すべきは、マスダンパー等重量物を用いたスイング系の制振ギミック(提灯、ヒクオ、ノリオ、東北ダンパー、キャッチャーダンパー、ギロチンダンパー、ドラえもん提灯等)の使用が明確に禁止されている点です。ただし、グレードアップパーツであるボールリンクマスダンパーの使用は可能とされています。
その他にも、ローラーの加工、プレート類のグラつき取り付け、パーツの加工、ビス・シャフト・ローラー等金属パーツの加工、モーターを分解することで取得できるパーツの使用なども禁止されています。
これらの禁止事項は、B-MAXの基本理念である「無加工でのフェアな競争」を実現するために設けられています。
ミニ四駆のB-MAXをはじめるための基礎知識
- B-MAXにおすすめのシャーシはMA、FM-A、VZなど複数ある
- B-MAXで選ぶべきボディの特徴はプラスチック製であること
- B-MAXのセッティングのコツは複雑なギミックに頼らないこと
- B-MAX大会の特徴は全国規模で開催されていること
- B-MAXがオープンより初心者に向いている理由は3つある
- B-MAXマシンの実例から学ぶ効果的なセッティング方法
- まとめ:ミニ四駆のB-MAXとは初心者から上級者まで楽しめるレギュレーション
B-MAXにおすすめのシャーシはMA、FM-A、VZなど複数ある
B-MAXマシンを作る際、どのシャーシを選ぶかはとても重要です。各シャーシには特徴があり、コースや自分の走らせ方に合わせて選ぶことがポイントになります。
MAシャーシは、B-MAXでも人気のあるシャーシの一つです。フロント部分が広く、比較的安定した走りが特徴で、様々なセッティングに対応できる汎用性の高さが魅力です。独自調査によると、MAシャーシはB-MAXレギュレーションの中でもバランスが良く、初心者から上級者まで幅広く使われています。
FM-Aシャーシも、B-MAXでよく使われるシャーシです。軽量かつコンパクトな設計で、MAシャーシよりも若干軽い特徴があります。ただし、プロペラシャフトの問題(走行中に曲がりやすい)があるため、その対策が必要になることがあります。B-MAXの公式大会でも、FM-Aを使用した優勝マシンは多く見られます。
VZシャーシは、近年注目を集めているシャーシです。リヤが低く設計されており、重心の低さが特徴です。高速コーナリングに強い一方で、セッティングが難しいという側面もあります。B-MAXレギュレーションでは、VZシャーシの特性を生かしたセッティングが可能です。
その他にも、スーパー2シャーシやARシャーシ、MSシャーシなども、B-MAXで使用可能です。スーパー2シャーシは古いタイプですが、シンプルな構造で調整がしやすく、初心者にも扱いやすい特徴があります。ARシャーシはフロントとリヤのモーター配置が特徴で、独特なバランス感覚が楽しめます。MSシャーシは軽量かつコンパクトで、特にMSフレキと呼ばれるセッティングが人気です。
シャーシ選びのポイントは、自分の走らせ方やコースとの相性です。例えば、ジャンプセクションが多いコースではMAシャーシが、高速コーナーが多いコースではVZシャーシが活躍する傾向があります。初心者であれば、セッティングが比較的簡単なMA、FM-A、スーパー2シャーシから始めることをおすすめします。
各シャーシの特性を理解し、自分の走らせ方に合わせてシャーシを選ぶことで、B-MAXの魅力をさらに深く味わうことができるでしょう。
B-MAXで選ぶべきボディの特徴はプラスチック製であること
B-MAXレギュレーションでは、使用できるボディに明確な制限があります。最も重要なポイントは、「プラスチック製のボディのみが使用可能」ということです。ポリカーボネートやPET製のボディは使用禁止とされています。
プラスチック製ボディの固定方法も規定されており、フロント、リヤ共にタミヤ製のボディキャッチパーツで固定する必要があります。ボディとシャーシの組み合わせは自由なので、好きなボディと好きなシャーシを組み合わせることができます。また、ウィングパーツの未装着も許可されています。
ボディの加工に関しては、いくつかの許可事項と禁止事項があります。許可されている加工としては、ボディの塗装、ステッカーの貼付け、異なる種類のボディとボディパーツ(ウィング等)の組合せ、ボディとボディパーツの接着などがあります。また、ボディを搭載する際にシャーシやプレート、マスダンパー、タイヤに干渉する該当部分の切断も許可されていますが、干渉部分から3mm以内での加工に限定されています。
一方、禁止されている加工としては、ボディの分割が挙げられます。また、走行中のボディやボディパーツの脱落は失格となるため、しっかりと固定することが重要です。さらに、原型が分からなくなるような過度な肉抜きや、肉抜きされたボディの破損部分を接着剤で補修すること、肉抜きされた箇所が破損したボディでの走行も禁止されています。
B-MAXでボディを選ぶ際のポイントは、まず自分のシャーシに合うボディを選ぶことです。ボディの形状によって空気抵抗や重心位置が変わり、マシンの挙動に影響します。例えば、流線型のボディは空気抵抗が少なく、高速走行に向いています。また、ボディの重さも考慮すべき点で、軽いボディはマシン全体の重量を軽減できます。
さらに、ボディのデザインや色なども、自分の好みで選ぶことができます。B-MAXではボディの塗装やステッカーの貼付けが許可されているので、オリジナリティのあるマシン作りを楽しむこともできます。
いずれにせよ、B-MAXでボディを選ぶ際は、プラスチック製であることを確認し、レギュレーションに沿った使用方法を守ることが大切です。
B-MAXのセッティングのコツは複雑なギミックに頼らないこと

B-MAXレギュレーションでは、複雑なギミックが禁止されているため、基本に忠実なセッティングが重要になります。ここでは、B-MAXでのセッティングのコツについて解説します。
まず、ローラーのセッティングがB-MAXでは特に重要です。マスダンパー等を用いたスイング系の制振ギミックが使用できないため、ローラーの配置や角度調整がマシンの安定性に大きく影響します。フロントローラーとリヤローラーの幅を適切に設定し、スラスト角(ローラーの傾き)を調整することで、コーナリング性能を向上させることができます。
例えば、フロントローラーの幅をリヤより少し短めにすると、コーナーでの安定性が増すという実験結果もあります。具体的には、フロントローラー幅を102mm、リヤローラー幅を104mmにするなどの調整が効果的とされています。
また、マスダンパーの配置も重要なポイントです。B-MAXでは固定されたマスダンパーの使用が許可されていますので、フロント、センター、リヤに適切に配置することで、マシン全体のバランスを取ることができます。例えば、フロントにはFRPの角マスダンパー、リヤにはスリムタイプのマスダンパーを配置するなど、マシンの特性に合わせた調整が可能です。
タイヤ選びも重要な要素です。B-MAXでは同一サイズのタイヤとホイールの組み合わせのみが許可されており、異なるサイズの組み合わせは禁止されています。コースの特性に合わせて、ハードタイヤやスーパーハードタイヤなどを選ぶことで、グリップ力や耐久性を調整できます。
モーターと電池の選択も、B-MAXでのセッティングに大きく影響します。特に電池の「育成」と呼ばれる、電池の電圧を調整する作業は上級者がよく行っていますが、これはB-MAXでも非常に重要な要素です。適切な電圧に調整された電池を使用することで、マシンの速度を制御し、コースアウトを防ぐことができます。
ブレーキのセッティングも忘れてはいけません。B-MAXではタミヤ製グレードアップパーツのブレーキのみが使用可能です。ブレーキの位置や強さを調整することで、下り坂やコーナーでの減速効果を高めることができます。例えば、フロントブレーキを斜めに取り付けることで、効果的な制動力を得られるケースもあります。
このように、B-MAXのセッティングでは複雑なギミックに頼らず、基本的なパーツの選択と配置、調整を丁寧に行うことがコツとなります。シンプルなレギュレーションだからこそ、細部へのこだわりが重要なのです。
B-MAX大会の特徴は全国規模で開催されていること
B-MAX GPは、単なるローカルな大会ではなく、全国規模で開催されている大規模な競技会です。B-MAX GP実行委員会が主催する「B-MAX GP全日本選手権」をはじめ、各地のホビーショップや団体が主催する予選大会が日本全国で開催されています。
B-MAX GP大会の最大の特徴は、その規模と組織力です。B-MAX GP実行委員会が定めた競技会規則に則って大会が運営されるため、どの地域の大会に参加しても同じルールで競技を楽しむことができます。これにより、地域間の交流も盛んになり、日本全国のミニ四駆ファンがつながる場となっています。
また、B-MAX大会では参加資格についても明確に定められています。B-MAX GP実行委員会の競技会規約によると、参加者は規約に同意し、大会運営スタッフや他の参加者と円滑にコミュニケーションが取れること、大会進行手順を理解し遵守することなどが求められています。さらに、必要に応じて個人情報の提供や写真撮影、取材の許可も条件となっています。
B-MAX大会のレース運営についても、タミヤのミニ四駆公認競技会規則に準拠しつつ、詳細についてはレースイベントを運営する店舗・団体に委ねられる形になっています。これにより、地域の特性や参加者の特徴に合わせた柔軟な大会運営が可能となっています。
B-MAX GPのレースコースは、ジャパンカップジュニアサーキット(Item No:69506)、ジュニアサーキットスロープセクション(Item No:69570)、ジャパンカップJr.サーキットバンクアプローチ20(Item No:69571)を組み合わせた3レーンサーキットが推奨されています。このような標準化されたコース設定により、どの地域の大会でも同様の条件でレースを楽しむことができます。
B-MAX大会への参加方法は、各レースイベントを運営する店舗・団体によって異なりますが、大会の開催情報はB-MAX GP実行委員会の公式サイトやSNSで確認することができます。大会によっては事前エントリー制を採用しているケースもあるので、参加を希望する場合は早めに情報をチェックしておくことをおすすめします。
B-MAX大会に参加することで、同じルールでマシンを作る全国のレーサーと競い合い、交流することができます。これはB-MAXの大きな魅力の一つであり、初心者から上級者まで幅広いレーサーが一堂に会する貴重な機会となっています。
B-MAXがオープンより初心者に向いている理由は3つある
B-MAXレギュレーションが初心者にとって特に魅力的な理由は、大きく分けて3つあります。これらの特徴が、多くの初心者がB-MAXからミニ四駆を始める理由となっています。
1つ目の理由は「改造が簡単」であることです。B-MAXは基本的に無加工でのポン付けが原則となっています。つまり、シャーシやプレートを切ったり削ったりする必要がなく、既存の穴を利用してパーツを取り付けるだけでマシンを作ることができます。現代のミニ四駆でよく見られる「シャーシのバンパーカットして、FRP・カーボンをこんな感じで加工して…」などの複雑な作業が不要なため、工具や技術に自信がない初心者でも気軽に取り組めます。
2つ目の理由は「色々な事が試しやすい」点にあります。ミニ四駆は速さと安定性のバランスを取りながらより速いマシンを作っていく競技ですが、B-MAXはギミックが少ないシンプルな構造のため、特定のパーツやセッティングの変更がマシンの挙動に与える影響を直接観察しやすいという特徴があります。例えば「ローラー幅を変えてコーナー速度の変化を見てみたい」と思った場合、オープンマシンでは他のギミックの影響で結果が分かりにくいことがありますが、B-MAXマシンではローラー幅の変更による影響をより純粋に観察することができます。これにより、原因と結果の関係を理解しやすく、ミニ四駆の基本を学ぶのに最適な環境となります。
3つ目の理由は「速い人にも勝てる可能性がある」ことです。B-MAXでは最高速度の上限がオープンクラスよりも低い水準にあるため、速いモーターを使いこなすことが難しく、単純なスピードだけでは勝負が決まりません。「速いレーサー」と「普通のレーサー」の差を生む一つの要因であるモーターの性能差が、B-MAXでは生かしきれないケースが多いのです。シンプルに言えば、速すぎるとマシンがコースアウトしてしまうため、モーターの性能が「そこそこ」でも安定して走らせることができれば勝てる可能性があります。また、B-MAXはオープンマシンよりも全体的にコースアウト率が高くなる傾向があるため、運の要素も絡んできます。これにより、技術的に優れたレーサーであっても常に勝てるとは限らず、初心者にも「ワンチャン」があるのです。
これらの理由から、ミニ四駆を始めたばかりの人や、久しぶりにミニ四駆を再開する人にとって、B-MAXは最適なレギュレーションだと言えるでしょう。シンプルながらも奥が深く、初心者から上級者まで楽しめる懐の広さがB-MAXの魅力です。
B-MAXマシンの実例から学ぶ効果的なセッティング方法
B-MAXマシンを効果的にセッティングするためには、実際に走らせて調整を重ねることが大切ですが、成功している実例から学ぶことも非常に有効です。ここでは、実際のB-MAXマシンのセッティング例を紹介し、そこから学べるポイントを解説します。
MAシャーシを使ったB-MAXマシンの例を見てみましょう。あるレーサーはアバンテMK3 NEROをボディに使用し、サイドには角マスダンパー、リヤにはスリムマスダンパーを搭載しています。フロントブレーキは斜めに取り付けることで効果を高めています。このセッティングの特徴は、重量バランスを考慮したマスダンパーの配置と、効果的なブレーキ位置にあります。MAシャーシは比較的安定感があるため、マスダンパーの配置を工夫することで、さらに安定した走りを実現しています。
FM-Aシャーシのセッティング例では、フロントローラーの幅と角度が重要なポイントになっています。ある優勝マシンでは、フロントローラー幅を104mm、フロントローラースラスト角を5度(ダウンスラスト)に設定し、リヤローラー幅を104mm、リヤローラースラスト角を0度(水平)にしています。このセッティングにより、コーナリング時の安定性を確保しています。また、FM-Aシャーシ特有のプロペラシャフト問題を解決するために、中空プロペラシャフトを使用し、適切な位置に調整することも重要です。
VZシャーシのB-MAXマシンでは、低重心を活かしたセッティングが効果的です。例えば、リヤに13mmオールアルミベアリングローラーを使用し、タイヤは前後ともに26mmのローフリクション小径ローハイトタイヤを装着することで、安定した走りを実現しています。また、マスダンパーをフロント、センター、リヤに設置型で配置することで、全体のバランスを取っています。
どのシャーシでも共通して言えるのは、ローラーのセッティングが非常に重要だということです。B-MAXでは複雑なギミックが使えないため、ローラーの位置や角度、サイズがマシンの安定性を左右します。例えば、フロントローラーは軽量2段アルミローラーセット(13-12mm)を使用し、リヤローラーは13mmオールアルミベアリングローラーを使用するというセッティングが人気です。
また、タイヤの選択も重要なポイントです。B-MAXでは同一サイズのタイヤとホイールの組み合わせが必要ですが、タイヤの硬さや径によってマシンの挙動が変わります。コースによって適したタイヤを選ぶことで、最適なパフォーマンスを引き出すことができます。例えば、ハードなタイヤはスピードが出やすく、ソフトなタイヤはグリップ力が高いという特性があります。
ギア比も重要な要素で、コースの特性に合わせて調整することが効果的です。多くのB-MAXマシンでは、3.5~3.7:1の比率が使われており、これはバランスの取れたギア比と言えます。
これらのセッティング例から学べるのは、B-MAXでは基本に忠実なセッティングがカギであるということです。複雑なギミックに頼るのではなく、基本的なパーツの選択と配置を丁寧に行うことで、効果的なマシンを作ることができます。
まとめ:ミニ四駆のB-MAXとは初心者から上級者まで楽しめるレギュレーション
最後に記事のポイントをまとめます。
- ミニ四駆のB-MAX(Basic-MAX)とは、タミヤのミニ四駆公認競技会規則をベースに、無加工でのポン付けを基本としたレギュレーション
- B-MAXはフォースラボが制定し、現在はB-MAX GP実行委員会が運営・管理している
- B-MAXの醍醐味は無加工のレギュレーションの中で頭とテクニックを使って挑戦すること
- オープンクラスとの違いは、B-MAXでは加工が基本的に禁止されている点
- B-MAXでは皿ビス加工とホイール貫通などの一部の加工のみが許可されている
- B-MAXではボディの分割や異なるサイズのタイヤとホイールの組み合わせなどが禁止されている
- B-MAXにおすすめのシャーシには、MA、FM-A、VZ、スーパー2、AR、MSなどがある
- B-MAXで使用できるボディはプラスチック製のみで、ポリカーボネートやPET製は禁止されている
- B-MAXのセッティングでは、ローラーの配置や角度、マスダンパーの位置が重要
- B-MAX大会は全国規模で開催されており、B-MAX GP全日本選手権などの大きな大会もある
- B-MAXが初心者に向いている理由は、改造が簡単、色々な事が試しやすい、速い人にも勝てる可能性があることの3つ
- B-MAXマシンの効果的なセッティングには、実例から学ぶことが有効で、基本に忠実なセッティングがカギとなる
- B-MAXは無加工のシンプルなレギュレーションながらも奥が深く、初心者から上級者まで楽しめる懐の広さが魅力