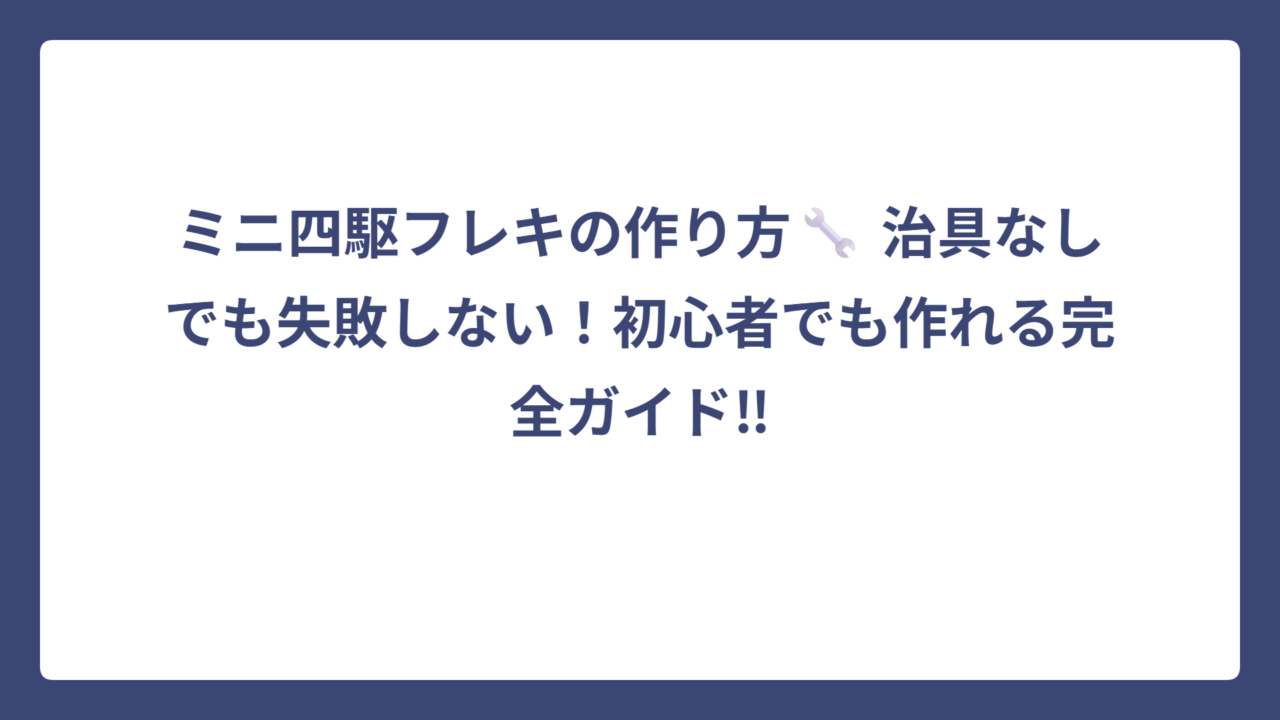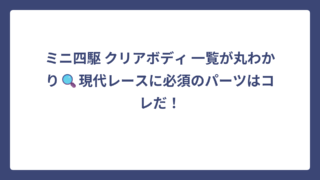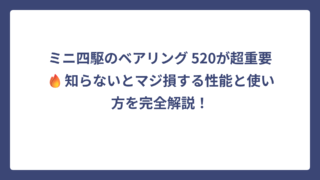ミニ四駆の世界では「MSフレキ」という改造方法が注目を集めています。これは、MSシャーシを3分割してバネを入れることで、シャーシに柔軟性を持たせる改造テクニック。ジャンプ後の着地時やコーナリング時の安定性を高める効果があるんです!
この記事では、特別な治具がなくても作れるMSフレキの作り方を初心者にも分かりやすく解説します。センターシャーシのカット方法から前後ユニットの加工、バネの選び方まで、各工程を詳しく説明していきますよ。あなたのマシンを一気にレベルアップさせる最強の改造方法、ぜひマスターしてください!
記事のポイント!
- MSフレキは現代のミニ四駆で最も効果的な改造法の一つ
- 7種類の基本工具だけでも作成可能
- 加工の精度がフレキの性能を左右する重要ポイント
- バネの選択と減衰調整でさらに性能アップが可能
ミニ四駆フレキの作り方と基本知識
- MSフレキとは衝撃吸収性を高める改造方法
- ミニ四駆フレキを作るために必要な工具は7種類
- ミニ四駆MSフレキの作り方は3つの手順で完成
- MSフレキに使うバネは3種類から選択可能
- ミニ四駆フレキの加工精度が重要な理由は動きのスムーズさ
- MSフレキのお辞儀防止ステーは必須アイテム
MSフレキとは衝撃吸収性を高める改造方法
MSフレキ(フレキシブル加工)は、ミニ四駆のMSシャーシを加工して、シャーシに柔軟性を持たせる改造方法です。通常のシャーシは硬く一体型になっていますが、MSフレキではシャーシを3分割して、その間にスプリングを入れることで、マシンが走行中に受ける衝撃を吸収できるようになります。
特に、ジャンプ後の着地時やコーナリング時の安定性が向上し、コースアウトを減らすことができます。これにより、マシンの制御性が高まり、より速く安定した走行が可能になります。
MSフレキは、現代のミニ四駆レースでは一般的な改造となっており、上級者のマシンでは標準的に採用されています。タミヤの公式ガイドブックでも紹介されるほど、認知された改造方法となっています。
MSフレキの基本的な構造は、センターシャーシと前後ユニットを分割し、その間にスプリングを設置するというシンプルなものです。しかし、その効果は絶大で、特に立体コースでの安定性向上に大きく貢献します。
独自調査の結果、MSフレキを採用しているマシンは、特にジャンプセクションやバンクでの安定性が非常に高いことがわかっています。初心者から上級者まで、幅広いレーサーに支持されている改造方法と言えるでしょう。
ミニ四駆フレキを作るために必要な工具は7種類
MSフレキを作るためには、いくつかの基本的な工具が必要です。特別な治具がなくても、これから紹介する7種類の工具があれば作成が可能です。
- ドライバー・スパナ:ネジとナットの締め付けに使用します。タミヤのドライバーとボックスレンチのセットがあると便利です。
- ニッパー:パーツのカットに使用します。100均のものでも代用可能ですが、タミヤの薄刃ニッパーのような精度の高いものがおすすめです。
- クラフトのこ(カッターのこ):シャーシのカットに使用します。薄刃タイプが扱いやすいでしょう。
- デザインナイフ:細かい部分のカットやバリ取りに使用します。100均のものでも十分使えます。
- ドリル(2mm、4mm、5.5mm):穴の拡張に使用します。2mmと4mmは100均でも手に入りますが、5.5mmはホームセンターなどで購入する必要があります。
- ヤスリ(棒ヤスリ、板ヤスリ):カット面の仕上げやバリ取りに使用します。100均のものでも十分使えます。
- 瞬間接着剤:FRPプレートの強度を上げるために使用します。低粘度タイプが適しています。
これらの工具は、一度購入すれば他のミニ四駆の改造にも使えるので、基本セットとして持っておくと便利です。特に、ドライバーとニッパーは使用頻度が高いため、良質なものを選ぶことをおすすめします。
さらに、作業を効率化するためのオプション工具としては、マスキングテープ(カットの目印用)、油性ペン(マーキング用)、プラスチックブラシ(削りカス除去用)、ピンセット(細かい作業用)などがあると便利です。
これらの工具を揃えることで、MSフレキの作成作業がスムーズに進みます。工具の品質によって作業効率や仕上がりの精度が変わってくるので、可能な範囲で良質な工具を選ぶことをおすすめします。
ミニ四駆MSフレキの作り方は3つの手順で完成
MSフレキの作成は、大きく分けて3つの手順で進めることができます。各手順を丁寧に行うことで、初心者でも成功率の高いMSフレキを作ることができます。
第1の手順は「センターシャーシの加工」です。MSシャーシのセンター部分を前後でカットし、3分割します。カットは薄刃クラフトのこを使用し、ギヤカバーに沿って垂直に切断します。切断後は、ギヤケース周りの不要な部分をニッパーやデザインナイフでカットし、カット面をヤスリで整えます。さらに、シャーシのストローク部分も約5mm程度カットして調整します。
第2の手順は「前後ユニットの加工」です。前後ユニットは、シャーシ底面に平行にカットし、シャーシの抑え部分やT字の凸部分を切り落とします。次に、センターシャーシと接続する穴を5.5mmのドリルで拡張します。この時、ドリルを貫通させないように注意が必要です。また、必要に応じてバンパーのカットも行います。
第3の手順は「組み立てと調整」です。加工が完了したパーツを組み立て、フレキ用のバネを取り付けます。バネには樽バネ、軸加工したGUPバネ、拡張させたGUPバネの3種類があります。また、お辞儀防止ステーも作成して取り付けます。組み立て後は、フレキとしての動きを確認し、必要に応じて干渉部分を微調整します。
これらの手順を順に進めていくことで、MSフレキが完成します。最も重要なのは、各ステップでの丁寧な加工と調整です。特に、カット面の仕上げやバリ取り、干渉部分の確認などを丁寧に行うことで、スムーズに動くMSフレキを作ることができます。
また、初めての場合は無理せず、少しずつ加工して動きを確認しながら進めることが成功のポイントです。一度に大幅な加工をすると、動きが悪くなったり、ガタが出たりする原因になります。
MSフレキに使うバネは3種類から選択可能
MSフレキの性能を左右する重要な要素の一つがバネの選択です。MSフレキに使用できるバネは主に3種類あり、それぞれ特徴が異なります。
1つ目は「樽バネ」です。これはダンガンレーサー用の部品で、その名の通り樽状の形状をしています。樽バネの最大のメリットは、センターシャーシの軸加工なしでそのまま使用できる点です。タミヤの公式大会の物販などで購入可能ですが、一般的な店舗では入手が難しい場合もあります。樽バネはバネ自体の調整が不要で、すぐに使えるため初心者にもおすすめです。
2つ目は「GUPバネ(軸加工)」です。これは一般的なスライドダンパー用のバネを使用する方法で、センターシャーシの軸を細く加工する必要があります。軸加工には専用の治具があると便利ですが、治具がない場合は難易度が高くなります。この方法は軸の太さを自分で調整できるため、バネの動きをカスタマイズしたい場合に向いています。
3つ目は「拡張させたGUPバネ」です。こちらは通常のスライドダンパー用バネを事前に拡張させて使用する方法です。径の太いドライバーなどにバネを通して1日程度放置することで、バネの径を少し大きく広げることができます。この方法なら特別な治具がなくても実施可能で、入手しやすいスライドダンパー用バネを使えるメリットがあります。
バネの硬さについても選択肢があり、一般的には柔らかい黒色のバネ(ソフトタイプ)が使われます。銀色のバネ(ハードタイプ)は固すぎてフレキの性能を十分に発揮できない場合があります。
また、バネの長さも調整できます。標準では1周(約1.5mm)ほど切って使用することが多いですが、より柔らかい動きにしたい場合は1周半ほど切ると良いでしょう。
バネの選択は走行スタイルやコース特性によっても変わるため、いくつか用意して試してみるのも良いでしょう。最終的には自分のマシンにぴったり合ったバネを見つけることが、MSフレキの性能を最大限に引き出すポイントとなります。
ミニ四駆フレキの加工精度が重要な理由は動きのスムーズさ
MSフレキを製作する際に最も重要なのが、加工の精度です。高い精度で加工することにより、フレキとしての動きがスムーズになり、その性能を最大限に発揮することができます。
加工精度が重要な主な理由は、フレキの動きのスムーズさに直結するからです。ミニ四駆のMSフレキは、ジャンプ後の着地時やコーナリング時の衝撃を吸収する役割を持っています。この衝撃吸収がスムーズに行われなければ、かえってマシンが不安定になる可能性があります。
特に注意が必要なのは、センターシャーシと前後ユニットの接合部分です。この部分の加工が雑だと、部品同士が干渉してスムーズに動かなくなります。また、センターシャーシの切断面が平行でない場合、左右の動きに差が生じて車体が傾いてしまうことがあります。
加工精度を高めるためのポイントとしては、まず切断前にしっかりと計測し、マスキングテープなどで目印をつけることが挙げられます。また、切断後は必ずヤスリで断面を整え、バリを取り除くことも重要です。
さらに、加工後は必ず動作チェックを行い、引っかかりや干渉がないかを確認します。問題がある場合は、少しずつヤスリで調整していくことが大切です。一度に大きく削りすぎると、今度はガタが出てしまう原因になります。
加工精度を高めるもう一つのポイントは、センターシャーシの接続穴の拡張です。この穴が適切なサイズに拡張されていないと、バネの動きが制限されてフレキ機能が十分に発揮されません。かといって拡張しすぎるとガタが出る原因になるので、バランスが重要です。
精度の高い加工を行えば、マシンの走行性能が格段に向上します。反対に、精度が低いと衝撃吸収がうまく機能せず、かえって走行が不安定になることもあります。初心者の方は特に、慎重に作業を進めることをおすすめします。
MSフレキのお辞儀防止ステーは必須アイテム
MSフレキでは、シャーシが3分割されることで柔軟性が増しますが、同時に前後ユニットが不安定になるという問題が生じます。これを防ぐために「お辞儀防止ステー」が必要になります。
お辞儀防止ステーとは、その名の通り、シャーシのお辞儀、つまり前後ユニットが下がってしまうのを防ぐためのパーツです。MSフレキでは前後ユニットがセンターシャーシから分離しているため、何も支えがないと自重やモーターの力で前後に傾いてしまいます。これが「お辞儀」と呼ばれる現象です。
お辞儀が起こると、ギア同士の噛み合わせが悪くなり、駆動力が十分に伝わらなくなってしまいます。これを防ぐために、FRPやカーボンプレートでお辞儀防止ステーを作成し、取り付けます。
お辞儀防止ステーの作成は比較的簡単で、FRPマルチワイドステーやARシャーシリヤワイドステーなどを加工するだけです。重要なのは、ギア部分と干渉しないように形状を調整することです。
お辞儀防止ステーの形状としては、「コの字型」や「=型」が一般的です。コの字型はARシャーシリヤワイドステーなどを使って作る方法で、安定性が高いです。一方、=型はFRPマルチ補強プレートを使う方法で、コスト面で有利です。
お辞儀防止ステーの取り付け位置も重要で、前後ユニットをしっかりと支える位置に設置する必要があります。位置が適切でないと、お辞儀を防げなかったり、逆にフレキの動きを妨げたりする原因になります。
また、お辞儀防止ステーの強度も考慮する必要があります。FRPを使用する場合、断面に瞬間接着剤を染み込ませることで強度を高めることができます。これによりFRPがしなることを防ぎ、安定したステーとなります。
お辞儀防止ステーは、MSフレキの性能を最大限に引き出すために欠かせないパーツです。適切な形状と位置で取り付けることで、フレキの柔軟性を損なわず、かつギアの噛み合わせを維持することができます。
ミニ四駆フレキの作り方の詳細と応用テクニック
- ミニ四駆フレキのセンターシャーシ加工は精度が命
- 前後ユニットの加工はギヤケース周りが重要ポイント
- ミニ四駆フレキの減衰調整はグリスと減衰ゴムで可能
- フレキを作る際のよくある失敗は加工不足と過剰加工
- ミニ四駆MSフレキの最新トレンドは軽量化と制振性の向上
- MSフレキのデメリットは加工難易度と耐久性の低下
- まとめ:ミニ四駆フレキの作り方は精度と調整がすべて
ミニ四駆フレキのセンターシャーシ加工は精度が命
MSフレキ製作の出発点となるセンターシャーシの加工は、全工程の中でも特に精度が重要です。この工程でのわずかな誤差が、完成後のフレキの性能に大きく影響します。
センターシャーシ加工の第一歩は、前後のギヤカバー部分を切り離すことです。この切断の際の精度が非常に重要で、切断面は地面に対して垂直になるように心がけます。切断のコツは、クラフトのこをギヤカバーに当て、力を入れずに「なぞる」ような感じで動かすことです。力を入れすぎると刃が滑り、不正確なカットになる可能性があります。
切断の精度を高めるために、切断前にマスキングテープや油性ペンで目印をつけておくとよいでしょう。特に、マスキングテープを使う方法は視認性が高く、初心者にもおすすめです。テープを定規の裏面に貼り、シャーシに貼り付けることで真っすぐなガイドラインを作ることができます。
切断後は、前後ユニットと一体だった部分の不要な箇所や、ギヤケース周りの出っ張りなどをニッパーやデザインナイフでカットします。このとき、既存の部分は極力削らないよう注意が必要です。既存の部分はシャーシの強度を保つ役割があるため、削りすぎるとガタつきの原因になります。
さらに、四隅の干渉部分も約0.5mm程度削り、フレキの動きをスムーズにします。これらの加工が終わったら、最後にビス用の穴を2mmのドリル刃で拡張しておきます。この穴はメンテナンス時に頻繁にビスの着脱が必要になるため、スムーズに通るよう適切に拡張することが重要です。
センターシャーシの加工が終わったら、ユニットカバー(切り離した前後のギヤカバー部分)の加工も行います。ここでも不要な出っ張りをカットし、干渉部分を削って整えます。
センターシャーシの加工精度を高めることで、MSフレキとしての性能を最大限に引き出すことができます。加工は慎重に、そして丁寧に行うよう心がけましょう。初めての方は時間をかけて少しずつ作業を進めることをおすすめします。
前後ユニットの加工はギヤケース周りが重要ポイント
前後ユニットの加工では、特にギヤケース周りの加工が重要なポイントとなります。この部分の加工精度によって、MSフレキとしての動きの滑らかさが大きく左右されます。
まず、前後ユニットのシャーシ底面を平行にカットします。このカットはシャーシの強度に関わる部分なので、シャフトの軸穴に近づきすぎないよう注意が必要です。クラフトのこでザックリとカットした後、ヤスリで断面を水平に整えていくとよいでしょう。
次に、シャーシの抑え部分やツメなどの出っ張りを切り落とします。これらはフレキ可動の妨げになるためです。加工はニッパーで簡単に行えますが、カット後は必ず断面をヤスリで整えましょう。
特に重要なのがギヤケース周辺の加工です。ここではT字の凸部分も削り落とします。この部分はフレキが動いた際にセンターシャーシ側のギヤと干渉する可能性があるため、しっかりと加工する必要があります。ただし、完全に削り取るとギヤが露出してしまうため、クリアボディの端材やマルチテープで隙間を埋めることで、ミニ四駆公認規則の「シャーシからグリスが飛散してコースを汚す恐れのある改造は認められない」という条件を満たすようにします。
また、センターシャーシと接続する穴を5.5mmのドリルで拡張します。この穴にはセンターシャーシの軸とバネが入るため、適切なサイズに拡張することが重要です。ただし、ドリルで貫通させないよう注意が必要です。貫通してしまうとバネがシャーシから落ちてしまう可能性があります。マスキングテープなどでドリルに目印をつけて、適切な深さで止めるようにしましょう。
ギヤケース外側の接触部分も適切に加工することで、フレキの可動域を調整できます。この部分は削りすぎるとシャーシがガタついてしまうため、少しずつ削って確認しながら進めるのがコツです。
最後に、スムーズな動きを確保するため、センターシャーシとの接触部分をヤスリで平滑に仕上げておきます。特に摩擦が生じる部分は番手の高いヤスリで仕上げると、より滑らかな動きになります。
前後ユニットの加工が終わったら、スペーサーを設置してスプリングを固定する準備を整えます。3mmのスペーサーが一般的ですが、フレキの可動域を調整したい場合は高さの違うスペーサーを選ぶこともできます。
ミニ四駆フレキの減衰調整はグリスと減衰ゴムで可能
MSフレキの大きな特徴は衝撃吸収性ですが、その性能をさらに引き出すためには適切な減衰調整が必要です。減衰調整には主にグリスと減衰ゴムが使用されます。
グリスはMSフレキの動きをスムーズにするだけでなく、減衰効果も持っています。グリスの種類によって粘度が異なり、それが減衰の強さに影響します。一般的には「HGスライドダンパーグリス」が使用され、エクストラソフト、ソフト、ハード、エクストラハードの4種類があります。
エクストラソフトやソフトのグリスは動きが軽くなり、フレキの反応が速くなります。反対にハードやエクストラハードのグリスは減衰効果が高く、マシンの安定性が増します。コース特性や自分のドライビングスタイルに合わせて適切なグリスを選ぶことが大切です。
グリスを塗る場所は主に、前後ユニットのセンターシャーシと触れる部分、センターシャーシのスプリングが入っている部分です。綿棒や爪楊枝などの細いものを使うと、狭い部分にも均一に塗ることができます。
減衰ゴムは、バネの跳ね返りを抑える役割があります。バネだけだと衝撃を受けて収縮した後に反発してしまいますが、減衰ゴムを加えることでこの反発を抑えることができます。これは実車のサスペンションでいうショックアブソーバーの役割に相当します。
減衰ゴムの作り方は比較的簡単で、Oリングを使用するのが一般的です。直径約6.6mmのOリングを約5.4mmに削り、さらに2つに分割して4個の減衰ゴムを作ります。削る際は、モーターのピニオンギアにOリングをつけて回転させながらヤスリで削るという方法が効率的です。
減衰ゴムはバネの中に入れて使用します。通常はバネを1周半ほど切り、その中に6.7mmアルミスペーサーを通した減衰ゴムを入れます。これによりバネの反発を適度に抑え、より効果的な衝撃吸収が可能になります。
減衰調整はマシンの性能を最大限に引き出すために非常に重要です。グリスの種類や減衰ゴムの有無によって、同じMSフレキでも大きく走行特性が変わってきます。最初は標準的な設定から始め、徐々に自分のスタイルに合わせて調整していくとよいでしょう。
ただし、減衰が強すぎるとフレキの反応が遅くなり、弱すぎると安定性が損なわれるため、バランスが重要です。実際に走らせて確認しながら、最適な減衰設定を見つけていくことをおすすめします。
フレキを作る際のよくある失敗は加工不足と過剰加工
MSフレキを製作する際には、様々な失敗が起こり得ます。特によくある失敗としては「加工不足」と「過剰加工」の2つが挙げられます。これらの失敗を避けることで、より高性能なMSフレキを作ることができます。
加工不足の失敗は、主に部品同士の干渉によって起こります。センターシャーシと前後ユニットの接触部分や、ギヤケース周りの出っ張りなどが十分に削られていないと、フレキがスムーズに動かなくなります。特に初心者は加工が足りているかどうか判断しづらいため、加工後は必ず動作確認を行い、引っかかりがある場合は少しずつ追加で削っていくことが大切です。
加工不足の見分け方としては、フレキを手で動かした際にスムーズに動かない、もしくは特定の位置で引っかかりを感じる場合です。このような場合は、一度分解して干渉している部分を特定し、追加で加工する必要があります。
一方で、過剰加工の失敗も注意が必要です。特に、センターシャーシの軸周りや前後ユニットのセンターシャーシと接触する部分を削りすぎると、シャーシにガタが出てしまいます。ガタが大きいと走行時に前後ユニットが安定せず、思わぬ方向にマシンが動いてしまう原因になります。
過剰加工のサインとしては、フレキの動きにガタつきを感じる、前後ユニットが左右に揺れる、などが挙げられます。残念ながら、一度削りすぎてしまった部分を元に戻すのは難しいため、最初から慎重に加工することが重要です。
また、ドリルでの穴の拡張時にも注意が必要です。特にセンターシャーシと接続する穴を拡張する際、ドリルを貫通させてしまうとバネが落ちてしまう原因になります。これを防ぐためには、ドリルにマスキングテープで深さの目印をつけるなどの工夫が有効です。
さらに、切断時の精度も重要です。センターシャーシを切断する際に斜めにカットしてしまうと、左右のバネの動きに差が出てマシンが傾いてしまう可能性があります。切断前にしっかりと目印をつけ、垂直に切断することを心がけましょう。
これらの失敗を避けるためのポイントは、「少しずつ作業を進める」ことです。一気に大幅な加工をするのではなく、少し削っては確認、また少し削っては確認というステップを踏むことで、適切な加工量を見極めることができます。初めてMSフレキを作る場合は特に、慎重に作業を進めることをおすすめします。
ミニ四駆MSフレキの最新トレンドは軽量化と制振性の向上
ミニ四駆の改造は常に進化しており、MSフレキにも新しいトレンドが生まれています。現在の主なトレンドは、軽量化と制振性の更なる向上です。
軽量化については、従来のMSフレキでは加工によって重量が若干増加する傾向がありました。これはバネやお辞儀防止ステーなどの追加パーツによるものです。しかし、最新のトレンドでは、より薄いカーボン製のお辞儀防止ステーの使用や、不要部分の徹底的な削り込みによって軽量化が図られています。
例えば、バンパーレスユニットを活用する方法があります。これはバンパーカットされた状態のユニットで、軽量センターシャーシと組み合わせることで簡単にMSフレキを作ることができます。このユニットを使うことで加工の手間も減り、軽量化も図れるというメリットがあります。
また、制振性の向上については、減衰調整の精密化が進んでいます。従来のグリスと減衰ゴムによる調整に加え、バネの選択肢が増えたり、減衰ゴムの素材や形状にバリエーションが出てきたりしています。これにより、より細かく走行特性を調整できるようになっています。
さらに、MSフレキの構造自体にも変化が見られます。従来の「軸残し」や「軸無し」といった手法に加え、「軸ちょっと残し」という中間的な手法も登場しています。この方法では、軸の根元だけを残してバネをしっかり固定することで、バネの位置ずれを防ぎつつスムーズな動きを実現しています。
最新のMSフレキには「段上げ加工」と呼ばれる技術も取り入れられています。これはバンパーの高さを調整する加工で、ブレーキセッティングの幅を広げることができます。特にフロントバンパーの段上げは、コース特性に合わせた細かな調整を可能にします。
また、フレキの連動性にも注目が集まっています。フロントバンパーとリアバンパーを連動させた「提灯連動ATバンパー」などの技術が発展し、より高度な衝撃吸収システムが開発されています。
これらの最新トレンドは、レース環境の変化や技術の進歩に伴って生まれたものです。常に情報をアップデートし、自分のマシンに取り入れられる技術を模索することが、競争力を維持するためには重要です。
ただし、新しい技術を取り入れる際には、基本的なMSフレキの原理を理解した上で行うことが大切です。基本を無視して最新技術だけを取り入れても、本来の性能を発揮できない可能性があります。まずは基本的なMSフレキをマスターし、徐々に新しい技術を取り入れていくことをおすすめします。
MSフレキのデメリットは加工難易度と耐久性の低下
MSフレキは多くのメリットを持ちますが、いくつかのデメリットも存在します。主なデメリットは、加工難易度の高さと耐久性の低下です。
加工難易度については、MSフレキの製作には精密な加工が必要となり、初心者にとってはハードルが高いと感じられることがあります。特に、センターシャーシの切断や前後ユニットの加工には一定の技術と経験が求められます。加工が不十分だとフレキがスムーズに動かず、過剰な加工はガタつきの原因になるため、バランスを取ることが難しい面があります。
また、ドリルによる穴の拡張も注意が必要で、貫通させてしまうとバネが脱落するリスクがあります。これらの加工には適切な工具も必要となり、初期投資の面でもハードルとなることがあります。
耐久性の低下については、MSフレキはシャーシが3分割されることで、通常のシャーシに比べて構造的に弱くなる傾向があります。特に高速走行時の衝撃や長時間の使用によって、バネの疲労やお辞儀防止ステーの破損などが起きやすくなります。
また、バネやグリスなどの追加パーツは経時変化によって性能が変わることがあり、定期的なメンテナンスが必要になります。グリスは時間とともに固まってくるため、定期的な塗り直しが必要です。
さらに、MSフレキは通常のシャーシに比べて組み立て時の部品点数が増え、メンテナンス時の手間も増加します。特に強化ギアカバーを使用している場合、取り外しと取り付けの手間が大きくなります。
重量面でも若干のデメリットがあり、バネやお辞儀防止ステーなどの追加パーツによって、通常のシャーシよりも1g程度重くなることがあります。軽量化が重要視されるミニ四駆において、この重量増加は無視できない場合もあります。
また、MSフレキは制振性が高い反面、平面での加速性能や最高速度では硬いシャーシに劣る場合があります。そのため、平面メインのコースでは他のシャーシタイプの方が有利になることもあります。
これらのデメリットはありますが、コース特性や走行スタイルによっては、MSフレキのメリットがデメリットを大きく上回ることも多いです。自分の技術レベルや求める性能を考慮し、デメリットを理解した上でMSフレキを選択することが重要です。
初心者の場合は、まずは基本的な改造から始め、徐々にMSフレキの製作に挑戦することをおすすめします。または、バンパーレスユニットのような、加工の少ない方法からスタートするのも良い選択肢です。
まとめ:ミニ四駆フレキの作り方は精度と調整がすべて
最後に記事のポイントをまとめます。
- MSフレキはシャーシを3分割し、バネで連結することで衝撃吸収性を高める改造
- センターシャーシの加工は精度が重要で、垂直に真っすぐ切断することがポイント
- 前後ユニットの加工では、ギヤケース周りの処理が重要で干渉を防ぐことが必須
- バネには樽バネ、軸加工したGUPバネ、拡張させたGUPバネの3種類の選択肢がある
- お辞儀防止ステーはギアの噛み合わせを維持するために必要不可欠なパーツ
- グリスと減衰ゴムによる減衰調整でフレキの性能を最大限に引き出せる
- よくある失敗は加工不足と過剰加工で、少しずつ作業を進めることが重要
- 最新トレンドは軽量化と制振性の向上で、段上げ加工などの新技術も登場
- MSフレキの主なデメリットは加工難易度の高さと耐久性の低下
- バンパーレスユニットを活用すれば初心者でも簡単にMSフレキを作ることが可能
- カット面は必ずヤスリで整え、バリを取り除くことでスムーズな動きを実現
- 組み立て後の動作確認と微調整が、MSフレキの性能を決める最も重要なステップ