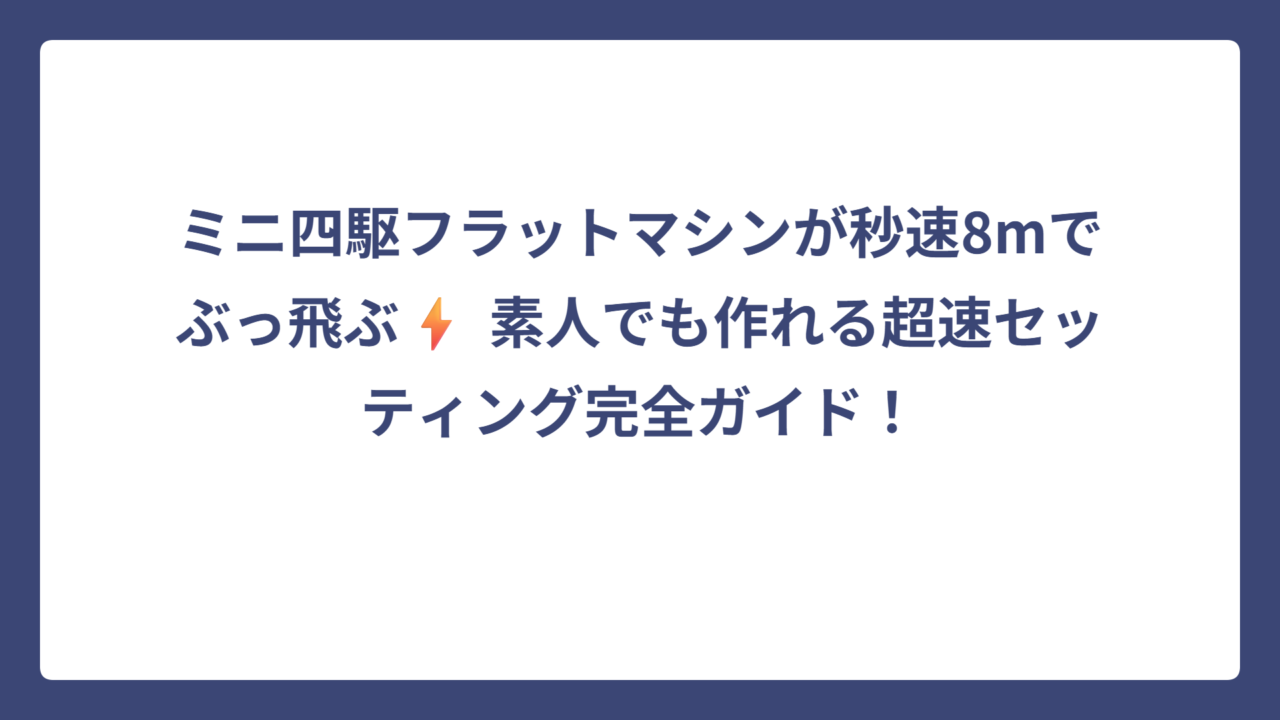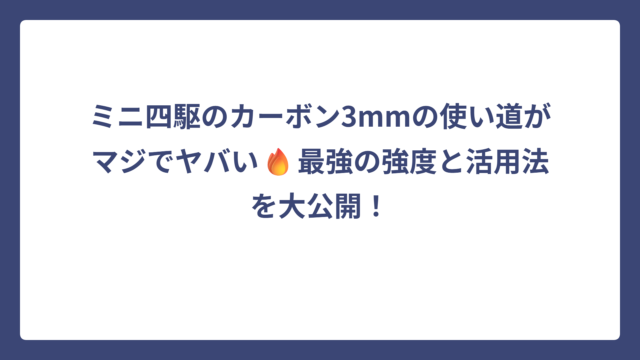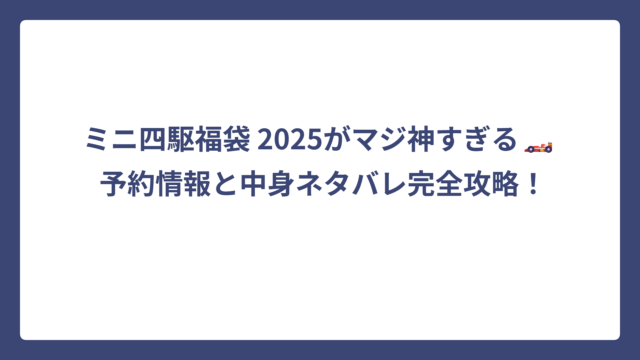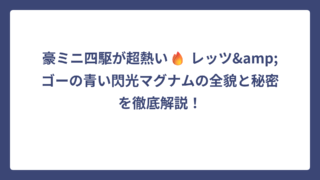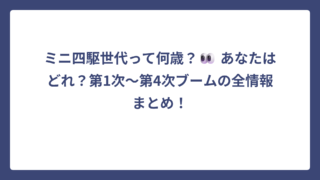ミニ四駆といえば立体コースを駆け抜ける姿を想像する人が多いかもしれませんが、実はもう一つの楽しみ方があります。それが「フラットマシン」です。単純な速さを競う「フラットレース」で活躍するマシンで、驚くべきことに秒速7〜8m(時速25〜29km)という原付バイク並みの速度で走行します!
フラットマシンは通常のミニ四駆と比べてセッティングや製作方法が大きく異なり、独自の世界観を持っています。井桁と呼ばれる特殊なバンパー構造や超大径タイヤなど、一見すると難しそうに感じるかもしれませんが、実は初心者でも取り組みやすいクラスも存在します。この記事では、フラットマシンの基礎知識から作り方、セッティングのコツまで詳しく解説します。
記事のポイント!
- フラットマシンの基本と種類(カツフラ・ダッシュフラットなど)を理解できる
- フラットマシン製作に必要なパーツ選びとセッティングのコツが分かる
- 超大径タイヤや井桁バンパーなどフラット特有の改造テクニックを学べる
- 初心者から上級者まで楽しめるフラットレースの魅力と参加方法が分かる
ミニ四駆フラットマシンとは何か?その特徴と魅力
- フラットマシンはスピード特化の最速マシンである
- ミニ四駆フラットマシンと立体マシンの違いは走行スタイルにある
- フラットレースは平均秒速7〜8mという驚異的なスピードが魅力
- ミニ四駆フラットマシンの主な種類はチューンフラットとダッシュフラット
- チューンフラット(カツフラ)はモーター制限で純粋な技術勝負
- ダッシュフラットはハイパワーで初心者にも挑戦しやすい
フラットマシンはスピード特化の最速マシンである
ミニ四駆フラットマシンとは、その名の通り「フラット」なコースを走るために特化したマシンのことです。フラットコースとは、立体コースのような飛んだり跳ねたりする箇所がほぼないレイアウトを指します。つまり、障害物や起伏がほとんどない平坦なコースで速さを競うために開発されたマシンなのです。
フラットマシンの最大の特徴は「速さ」です。立体コースのように複雑なセクションを乗り越える必要がないため、純粋にスピードを追求することができます。その結果、驚くような速度を実現しています。独自調査によると、フラットマシンは秒速7〜8mという速度(時速約25〜29km)で走行することもあり、これは原付バイクに匹敵するスピードです。
フラットマシンは見た目も特徴的です。超大径と呼ばれる大きなタイヤや、「井桁」と呼ばれる特殊な形状のバンパーを装備していることが多く、無駄を削ぎ落とした機能美を追求したデザインとなっています。これはただの見た目の問題ではなく、最高速度を実現するための合理的な設計なのです。
フラットマシンは「タイムアタック」形式のレースで使われることが多く、各選手のベストラップタイムを競います。そのため、ミニ四駆の世界では「秒○」という独特の表現が使われます。これは平均秒速何メートルで走れたかを表し、例えば「秒8」ならば秒速8メートルで走ったことを意味します。
フラットマシンは一見ハードルが高そうに見えますが、実はミニ四駆の奥深さや速さの追求という醍醐味を純粋に味わえる分野なのです。無駄を削ぎ落とし、速さのみを極限まで追求する世界は、多くのミニ四駆ファンを魅了しています。
ミニ四駆フラットマシンと立体マシンの違いは走行スタイルにある
ミニ四駆フラットマシンと一般的な立体コース用マシンには、明確な違いがあります。最も大きな違いは、それぞれが走るコースの特性に適応するためのセッティングの違いです。
立体マシンは、ジャンプセクションやバンクカーブ、上り下りなど複雑なレイアウトを安定して走行することが求められます。そのため、姿勢制御のためのマスダンパーやブレーキ、強力な防振装置などが必要になります。一方、フラットマシンは基本的に平坦なコースを走るため、これらの装置はほとんど不要で、むしろ余計な重量として切り捨てられます。
パーツ数にも大きな違いがあります。フラットマシンは「無駄なパーツは付けない」という思想が徹底されており、最小限のパーツだけで構成されています。これは単に軽量化のためだけでなく、不要な抵抗を減らし、モーターの力を最大限に活かすためでもあります。
タイヤにも明確な違いがあります。フラットマシンでは「超大径」と呼ばれる大きなタイヤが使われることが多く、これは一回転あたりの進む距離を増やすことでスピードを向上させる目的があります。立体マシンではグリップ性能やジャンプの安定性が重視されますが、フラットマシンでは純粋に速度を上げることが最優先されます。
興味深いことに、フラットマシンで培った知識や技術は立体マシンにも応用できる部分があります。例えば、駆動効率の改善や抵抗の少ないローラー配置などは、立体マシンでも役立ちます。「紅蓮の太陽」氏の記事によれば、「フラットは、自分のポテンシャルを測る意味でも、可能であれば経験しておいて損はない」とのことです。
フラットと立体、どちらが優れているというわけではなく、それぞれに異なる魅力と楽しさがあります。両方を経験することで、ミニ四駆の理解がさらに深まり、新たな発見があるかもしれません。
フラットレースは平均秒速7〜8mという驚異的なスピードが魅力
フラットレースの最大の魅力は、何と言ってもその圧倒的なスピードにあります。チューンフラットでは秒速7〜8m、ダッシュフラットになると秒速8〜9m以上という驚異的な速度で走行します。これを時速に換算すると、チューンフラットで約25〜29km/h、ダッシュフラットで約29〜32km/h以上になります。
この速度感を体感するのは非常に興奮する体験です。特に長いストレートセクションでは、マシンがほとんど見えないほどの速さで駆け抜けていきます。第5回山茶花高原杯ミニ四駆大会では、25mのホームストレートを一瞬で駆け抜けるマシンの描写がありましたが、それほどの速さなので「マシンが見えない」という表現が使われているほどです。
フラットレースでは、各選手のベストタイムを記録し、順位を競うタイムアタック形式が主流です。予選では3〜4回の走行チャンスがあり、各選手のベストタイムによって順位が決定します。このシステムにより、単に速いマシンを作るだけでなく、予選通過ラインを計算しながら、どのタイミングでベストを出すかという戦略も重要になってきます。
また、フラットレースの醍醐味として、「心理戦」の側面も見逃せません。予選通過ラインを考えたり、決勝においてはどのタイミングでベストタイムを狙うかなど、各選手の駆け引きも重要な要素です。「一撃を狙う」という選択肢もあれば、安定して確実に予選通過を狙うという選択肢もあり、その判断が結果を大きく左右します。
フラットレースは単純なスピード勝負に見えて、実は奥が深いのです。マシンの性能だけでなく、コンディションの読み、タイミングの判断、そして精神的な強さも必要とされます。秒速7〜8mという数字だけでなく、そこに至るまでの過程や戦略が、フラットレースをより魅力的なものにしているのです。
ミニ四駆フラットマシンの主な種類はチューンフラットとダッシュフラット
ミニ四駆のフラットマシンには、主に2つの種類があります。「チューンフラット」と「ダッシュフラット」です。これらは使用するモーターの種類によって区別されており、それぞれに特徴があります。
チューンフラットは、レブチューン、トルクチューン、アトミックチューンなどの「チューン系モーター」を使用するカテゴリです。特に「カツフラ」と呼ばれるチューンフラットは、当日支給されたチューンモーターを当日慣らして競うという、非常に公平な条件でレースが行われます。片軸マシンならアトミックチューン2、両軸ならトルクチューンPRO2が主流となっています。
一方、ダッシュフラットは文字通り「ダッシュモーター」を使用したフラットレースです。ダッシュモーターはチューンモーターよりもパワーがあるため、より高速な走行が可能になります。そのため、超大径タイヤやフルカスタムの井桁バンパーなどの高度な改造が必ずしも必要ではなく、市販パーツの組み合わせでも十分に競争力のあるマシンを作ることができます。
また、フラットのレイアウトにも違いがあります。「セミフラット」と呼ばれる立体レーンチェンジ(LC)を使用したコースと、「フルフラット」と呼ばれるバーニングLCを使用した完全に平坦なコースの2種類があります。特に「MINI4WD Grand Champion Series」(MINI4GCS)では、セミフラットのレースによるポイント制のシリーズ戦が行われています。
その他にも、各ショップや大会独自のクラス分けがあります。「エキスパート」(ポン付けクラス)、「小径レブ」(小径タイヤ+レブチューンモーター)、「ゆるフラ」(ライトダッシュモーター限定、タイヤ径制限あり)など多彩なクラスがあり、それぞれにレギュレーションが設けられています。
これらの多様なクラス分けにより、ビギナーからエキスパートまで、様々なレベルの参加者が楽しめる環境が整っています。自分の技術レベルや予算、好みに合わせて、参加するクラスを選ぶことができるのも、フラットレースの魅力の一つです。
チューンフラット(カツフラ)はモーター制限で純粋な技術勝負
チューンフラット、特に「カツフラ」と呼ばれるレースは、ミニ四駆の世界でも特に技術勝負の側面が強く、多くのコアなファンを魅了しています。「カツフラ」という名称は「カツカツしたフラット」という意味で、歴史も古く、フラットレースの主流と言えるジャンルです。
カツフラの最大の特徴は、モーターの制限です。チューン系モーター(片軸ならアトミックチューン2、両軸ならトルクチューンPRO2など)に限定され、しかも当日支給された同一ロットのモーターを当日慣らして使用するという厳しい条件が設けられています。これにより、モーターの個体差による有利不利がなくなり、純粋にマシンの完成度とセッティングの技術で勝負することになります。
また、電池についても規制があり、地域によってアルカリ電池限定の大会や、ニッカド・ニッケル水素電池使用可能な大会があります。関西・西日本ではアルカリ限定の大会が多いようです。これもまた、公平な条件での勝負を重視する姿勢の表れと言えるでしょう。
カツフラマシンの特徴的な外観として、「超大径タイヤ」と「井桁バンパー」が挙げられます。超大径タイヤは非力なチューンモーターでも高速を出すために必要な改造で、1回転あたりの進む距離を増やす役割があります。井桁バンパーはFRPやカーボンプレートで自作され、軽量さと剛性を両立させる構造になっています。
カツフラは「敷居が高い」と思われがちですが、実際には細かい工夫や丁寧な作り込みが重要で、特別な工具や治具がなくても取り組むことができます。「丁寧に、ゆっくり、きれいに」作ることが、良い結果につながる傾向があります。
また、カツフラの大会の雰囲気は、一般的なイメージと違って非常に友好的です。選手同士でリスペクトし合い、応援しあうような和やかな雰囲気があり、初心者にも優しい環境です。技術的な相談にも応じてくれるベテランレーサーも多く、学びの場としても最適です。
ダッシュフラットはハイパワーで初心者にも挑戦しやすい
ダッシュフラットは、その名の通りダッシュモーターを使用したフラットレースのことで、近年人気が高まっているカテゴリです。カツフラと比較した際の最大の違いは、使用するモーターのパワーが格段に上がるため、より高い速度を出しやすいという点にあります。
ダッシュモーターのパワーにより、カツフラでは必須とされる超大径タイヤや井桁バンパーなどの高度な改造をしなくても、比較的簡単に高速走行が可能です。タイヤの大きさも様々なサイズが選択可能で、シャーシも軽量なVSやS1だけでなく、重めの両軸シャーシでも十分な速度を出すことができます。これにより製作の自由度が高く、初心者でも取り組みやすい環境となっています。
ダッシュフラットの速度域はカツフラよりも上がり、秒8以上、場合によっては秒9以上(時速32.4km以上)の速度が出ることもあります。これはモーターのパワーが大きいことによるものですが、逆に言えばそれだけの高速でも安定して走行できるセッティング技術が求められます。
また、ダッシュフラットの大きな魅力として、コースアウトの可能性やマシンの負担が比較的少なく、部品の破損リスクが低いという点が挙げられます。高速走行でも安定性が高いため、初心者や子供でも楽しめる要素があります。実際に、R263三瀬高原サーキットのレースでは、子供たちが丁寧に作り上げたマシンで大人のマシンを上回る好タイムを出すこともあるそうです。
ダッシュフラットには「ゆるフラ」というクラスもあり、これはライトダッシュモーター限定、タイヤ径31mm以下、重量制限あり、プラボディ限定などのレギュレーションが設けられています。このクラスでは走行性能だけでなく、コンデレ(コンクールデレガンス)も重視され、見た目の美しさも競われます。レース前に参加者による投票が行われ、その結果がトーナメント表に反映されるという独特のシステムもあります。
ダッシュフラットは「速さ」だけでなく「楽しさ」「個性」も重視されており、ミニ四駆の多様な魅力を味わえるカテゴリと言えるでしょう。初めてフラットに挑戦する方には、ダッシュフラットからスタートするのがおすすめです。
ミニ四駆フラットマシンの作り方とセッティングのポイント
- フラットマシン作りに最適なシャーシはVSやS1など軽量シャーシ
- ミニ四駆フラットマシンのローラー配置は減速効果を考慮して決める
- 井桁バンパーの役割は軽量化と剛性確保の両立
- 超大径タイヤの作り方とポイントは精度と軽さのバランス
- フラットマシンの駆動調整は抵抗を減らすことが最重要
- フラット初心者におすすめのエントリーモデルはポン付けダッシュフラット
- まとめ:ミニ四駆フラットマシンは工夫と改良の楽しさがある最高の趣味
フラットマシン作りに最適なシャーシはVSやS1など軽量シャーシ
ミニ四駆フラットマシンを作る際、シャーシ選びは非常に重要なポイントです。特にチューンフラット(カツフラ)では、チューンモーターのパワーを最大限に活かすために、できるだけ軽量なシャーシを選ぶことが定石となっています。
最も一般的に使用されているのは、VSシャーシとS1シャーシです。これらは軽量でありながら、必要な剛性も確保されているため、フラットマシンに最適とされています。特にチューンフラットの世界では比較的軽量なVSやS1シャーシを使用するケースが多く見られます。これらのシャーシは基本的な軽さがあるため、さらなる改造による軽量化がしやすいという利点もあります。
一方、ダッシュフラットの場合は、モーターのパワーが大きいため、シャーシ選びの幅が広がります。VS、S1だけでなく、MAシャーシやARシャーシなど、比較的重めの両軸シャーシでも十分な速度を出すことができます。このため、手持ちのシャーシや慣れているシャーシを活用できる点もダッシュフラットの魅力と言えるでしょう。
また、シャーシ選びの際には、改造のしやすさも考慮すると良いでしょう。例えば井桁バンパーを製作する場合、取り付けやすいシャーシか、肉抜き加工がしやすいシャーシかなども重要なポイントになります。VSシャーシは構造がシンプルで改造しやすく、初心者にもおすすめです。
各シャーシにはそれぞれ特徴があり、「これが絶対に最適」というものはありません。フラットレースのクラスやレギュレーション、自分の技術レベル、好みなどを総合的に考慮して選ぶことが大切です。例えば「ゆるフラ」クラスではMSシャーシが使われている例もあり、様々な選択肢があります。
最終的には、「速さを追求する」というフラットマシンの基本コンセプトに立ち返り、いかに軽量かつ高効率なシャーシセッティングができるかが鍵となります。自分なりのこだわりを持ちながら、理想のフラットマシンに合ったシャーシを選びましょう。
ミニ四駆フラットマシンのローラー配置は減速効果を考慮して決める
ミニ四駆フラットマシンにおけるローラーセッティングは、安定走行と高速維持のバランスを取る上で非常に重要なポイントです。特にフラットコースでは、立体コースと異なりコースアウトのリスクが限られた場所(主にレーンチェンジャー)にあるため、それを考慮したローラーセッティングが求められます。
フロントローラーのセッティングでは、特に右前のローラーが重要です。フラットコースではレーンチェンジャーの壁に最初に当たるのが右前のローラーであることが多いため、ここに減速効果を持つローラーを使用するのが効果的です。具体的には、WAローラーや9mmボールベアリングローラーなどが適しています。
左前のローラーには830ローラーなど通常のローラーを使うことが多いですが、コースレイアウトや走行スタイルによって調整が必要です。また、フロントローラーの上だけでなく下にもスタビ(スタビライザー)を取り付けることで、さらに安定した走行が可能になります。
リアローラーについては、立体マシンと比較して大きな違いはありません。ただし、フラットマシンではマスダンパーやブレーキなどを省略することが多いため、ローラー自体の配置や性能がより重要になります。多くの場合、4つとも830ローラーを使用しますが、コースアウトが心配な場合は、ネジを通常の30mmではなく40mmのものを使用して、より安定性を高める工夫もあります。
ローラーの調整においては、脱脂も重要なポイントです。ローラーの回転抵抗を減らすことで、マシンの走行効率が向上します。BC-9などの専用クリーナーを使用して、ローラーを外さずに脱脂する方法も効果的です。
フラットマシンのローラーセッティングの基本は「コースアウトしない程度に最小限のセッティング」と言えるでしょう。過剰なブレーキやスタビは不要な抵抗になるため、必要最小限のパーツで最大限の効果を得ることを目指します。「無駄なパーツは付けない」という考え方がフラットマシンの基本理念であり、ローラーセッティングにもそれが表れています。
井桁バンパーの役割は軽量化と剛性確保の両立
ミニ四駆フラットマシンの特徴的な部分の一つが「井桁バンパー」です。井桁バンパーとは、FRPやカーボンプレートなどを使って自作されるバンパー構造のことで、その形状が日本の漢字の「井」に似ていることからこの名前が付けられています。
井桁バンパーの最大の役割は、軽量化と剛性確保の両立です。通常のプラスチック製バンパーと比較して大幅に軽量化できる上に、格子状の構造により高い剛性も維持できます。これにより、フラットマシンに求められる「軽さ」と「安定性」を同時に達成することができるのです。
井桁の製作には、主にFRPプレートやカーボンプレートが使用されます。これらの素材は軽くて強く、加工性も良いため、自作バンパーの材料として最適です。作り方は複雑そうに見えますが、基本的には素材を切り出して組み合わせ、接着するという流れになります。初心者には難しく感じるかもしれませんが、慣れれば比較的簡単に作れるようになります。
井桁バンパーの製作には、専用の治具(ジグ)があると便利です。正確な寸法や角度を出すために、アクリル製の型などを自作している愛好家も多いようです。ただし、特別な治具がなくても、丁寧に作業すれば十分実用的な井桁バンパーを作ることは可能です。「丁寧に、ゆっくり、きれいに」という姿勢が何よりも重要です。
また、井桁バンパーのフロント部分には、モーターピンにスラスト角(角度)を付けることがあります。これにより、走行中のマシンの姿勢を安定させる効果があります。リアは垂直、フロントは2度程度のスラストを付けるといった調整が一般的です。
井桁バンパーは見た目にも美しく、職人技が光る部分です。特にカツフラの世界では「速さを追求するための独特のフォルム」「機能美の塊」と表現されるほど、洗練されたデザインになっています。技術的な側面だけでなく、芸術性も兼ね備えた井桁バンパーは、フラットマシンの魅力を大いに高めています。
超大径タイヤの作り方とポイントは精度と軽さのバランス
ミニ四駆フラットマシンの重要な構成要素の一つが「超大径タイヤ」です。通常のミニ四駆タイヤよりも大きな直径を持つこのタイヤは、一回転当たりの進む距離を増やすことでスピードアップを図る重要なパーツです。フラットマシン、特にカツフラでは必須とも言えるカスタムパーツです。
超大径タイヤの最大のメリットは、モーターの回転数に対して進む距離を増やせることです。チューンモーターのような比較的非力なモーターでも、タイヤの直径を大きくすることで効率よく速度を出すことができます。これはギヤ比を上げるのとは異なり、トルクを犠牲にせずにスピードを上げられるという利点があります。
超大径タイヤの作り方ですが、基本的には既製品のタイヤを重ねたり、加工したりして大きくします。具体的な方法としては、ペラ抜き(タイヤの中央部分を抜く加工)したタイヤを複数枚重ねたり、多層タイヤとダミーを組み合わせたりする方法があります。接地面は全てノーマルタイヤにするなど、グリップ性能にも考慮が必要です。
超大径タイヤ製作のポイントは、精度と軽さのバランスです。直径を大きくすることは重要ですが、あまりに重くなっては加速性能が落ちてしまいます。また、タイヤの精度(真円度)が悪いとブレの原因になり、最高速度に悪影響を与えます。そのため、丁寧な加工と組み立てが求められます。
タイヤの直径はレギュレーションによって制限されることもあります。例えば「ゆるフラ」クラスではタイヤ径31mmまで、「小径レブ」クラスでは26mm以下といった制限があります。自分が参加するレースのレギュレーションを確認した上で、適切なサイズのタイヤを製作することが重要です。
また、タイヤの硬さや種類もパフォーマンスに大きく影響します。一般的には、フロントにはローフリクションやスーパーハードなどの硬めのタイヤ、リアにはノーマルなど適度なグリップを持つタイヤを使用するセッティングが多いようです。コース状況や走行スタイルに合わせて調整すると良いでしょう。
超大径タイヤは見た目のインパクトも大きく、フラットマシンの象徴的な要素となっています。職人の技術が光る部分でもあり、フラットマシンの魅力を大いに高めています。
フラットマシンの駆動調整は抵抗を減らすことが最重要
ミニ四駆フラットマシンの性能を最大限に引き出すためには、駆動系の調整が非常に重要です。特にフラットでは加減速を繰り返す立体コースと異なり、高速を維持することが求められるため、駆動系の効率が直接タイムに影響します。
駆動調整の最大のポイントは「抵抗を減らすこと」です。具体的には、モーター、ギア、軸受け、ピニオンギアとクラウンギアの噛み合わせなど、動力が伝達される全ての部分での抵抗を最小限にすることを目指します。これにより、モーターの力を無駄なく車輪に伝え、最高速度と加速性能を向上させることができます。
まず重要なのがギア比の選択です。フラットでは超速ギア(3.5:1)一択と考えて良いでしょう。これはスピード重視のセッティングで、モーターの回転を効率よくスピードに変換します。ただし、「ゆるフラ」などのクラスでは、タイヤサイズによってギア比に制限がある場合もあるので注意が必要です(例:26mmまでは3.5:1、それ以上は4:1まで)。
次に重要なのが駆動部分の位置調整です。特にピニオンギアとクラウンギアの噛み合わせは慎重に行う必要があります。噛み合いが深すぎると抵抗が増え、浅すぎるとスリップの原因になります。適切なクリアランスを確保することで、スムーズな動力伝達が可能になります。特にチューンフラットのような繊細なセッティングが求められるクラスでは、この調整が勝敗を分けることもあります。
また、620ボールベアリングなどの軸受けの状態も重要です。回転の滑らかさが足りないものがあれば交換し、適切な潤滑剤で処理することで抵抗を減らします。同様に、ローラーの脱脂も重要な作業です。BC-9などの専用クリーナーを使用して、ローラーの回転抵抗を減らしましょう。
フロントクラウンの遊びも調整ポイントの一つです。遊びが大きすぎると駆動ロスの原因になるため、絶縁ワッシャーなどを使って適切に調整することが効果的です。
最後に重要なのが、グリスアップです。適切な部分に適量のグリスを塗布することで、駆動系の効率と耐久性を向上させることができます。ただし、使いすぎると逆に抵抗になるので注意が必要です。
これらの調整は一度で完璧にできるものではなく、走行と調整を繰り返しながら少しずつ改善していくプロセスが重要です。「0.1秒縮まりそう!」という感覚を大切にしながら、地道に調整を続けることがフラットマシンの醍醐味と言えるでしょう。
フラット初心者におすすめのエントリーモデルはポン付けダッシュフラット
フラットマシンの世界に初めて足を踏み入れる方にとって、「どのマシンから始めればいいのか」という疑問は大きいものです。結論から言うと、初心者にはダッシュモーターを使用したポン付けマシンがおすすめです。特に「ダッシュフラット」のカテゴリーは、比較的簡単に作れて速度も出やすく、初心者にとって理想的なスタートポイントとなります。
「ポン付け」とは、市販のパーツをそのまま使用して、複雑な加工をせずに組み立てるスタイルのことを指します。フラットの世界では「エキスパート」クラスと呼ばれることもあり、シャーシ、タイヤ、プレートなどのパーツの加工が禁止されているため、フラットのお約束とも言える超大径タイヤや井桁バンパーは使用できません。
ポン付けダッシュフラットの最大のメリットは、モーターのパワーが大きいため、複雑な改造をしなくても十分な速度が出せることです。また、部品の選別や繊細なセッティングの重要性を学ぶことができるため、フラットマシンの基本を理解するのに適しています。
初心者向けのフラットマシンを作る際のポイントは以下の通りです:
- シャーシ:VSシャーシやMAシャーシなど、自分が扱いやすいものを選びましょう。初めての場合はVSシャーシが比較的軽量で扱いやすいです。
- モーター:ダッシュモーター(ライトダッシュやスプリントダッシュなど)を使用します。これにより、加工なしでも高速走行が可能になります。
- ギア比:3.5:1または4:1の超速ギアを使用します。これはスピード重視のセッティングです。
- タイヤ:大径ローハイトホイールにオフセットトレッドタイヤを取り付けるなど、できるだけ直径を大きくしたセッティングを目指します。フロントはハードまたはローフリクション、リアはノーマルといった組み合わせが一般的です。
- ローラー:右前にWAローラーなど減速効果のあるローラーを使い、他は830ローラーを使用するといったセッティングが基本です。
初心者がフラットマシンを作る際は、まず基本的なセッティングでスタートし、少しずつ調整を加えていくことが大切です。走行と調整を繰り返しながら、マシンの挙動を理解し、自分なりの最適なセッティングを見つけていきましょう。
また、地域のショップや走行会に参加して、経験者からアドバイスをもらうことも大変有効です。フラットの世界では、経験者が親切に技術を教えてくれることも多く、コミュニティの一員となることで学びを深めることができます。
初めは完璧を目指さず、楽しみながら少しずつ上達していく姿勢が大切です。フラットマシンの奥深さと面白さを体感しながら、自分だけの速いマシンを作り上げていきましょう。
まとめ:ミニ四駆フラットマシンは工夫と改良の楽しさがある最高の趣味
最後に記事のポイントをまとめます。
ミニ四駆フラットマシンで紹介したことの振り返りまとめ:
- フラットマシンとは飛んだり跳ねたりする箇所がほぼないレイアウトで走る、スピードに特化したミニ四駆である
- 平均秒速7〜8m(時速25〜29km)という原付バイク並みの驚異的なスピードが最大の魅力である
- チューンフラット(カツフラ)とダッシュフラットの2種類が主流で、使用するモーターの種類で区別される
- カツフラは当日支給チューンモーターで技術勝負、ダッシュフラットはパワーで初心者も楽しめる
- フラットマシンに最適なシャーシはVSやS1などの軽量シャーシだが、ダッシュフラットではMAなども使える
- ローラーセッティングでは右前に減速効果のあるローラーを配置し、コースアウト防止を図る
- 井桁バンパーはFRPやカーボンプレートで自作し、軽量化と剛性確保を両立させる
- 超大径タイヤは一回転あたりの進む距離を増やし、非力なモーターでも高速走行を可能にする
- 駆動調整では抵抗を減らすことが最重要で、ギア比やピニオンとクラウンの噛み合わせが重要
- フラット初心者はポン付けダッシュフラットから始めると、比較的簡単に速いマシンを作れる
- 「ゆるフラ」などの多様なクラス分けにより、様々なレベルや好みに合わせた楽しみ方ができる
- フラットマシンづくりは速さを追求する過程で得られる知識や技術が立体マシンにも役立つ
- フラットレースのコミュニティは和やかで友好的であり、技術交流の場としても価値がある
- フラットマシンは「無駄なパーツは付けない」という思想のもと、機能美を追求した芸術性も持つ
- 0.1秒を縮めるための試行錯誤の過程こそがフラットマシンの真の魅力である