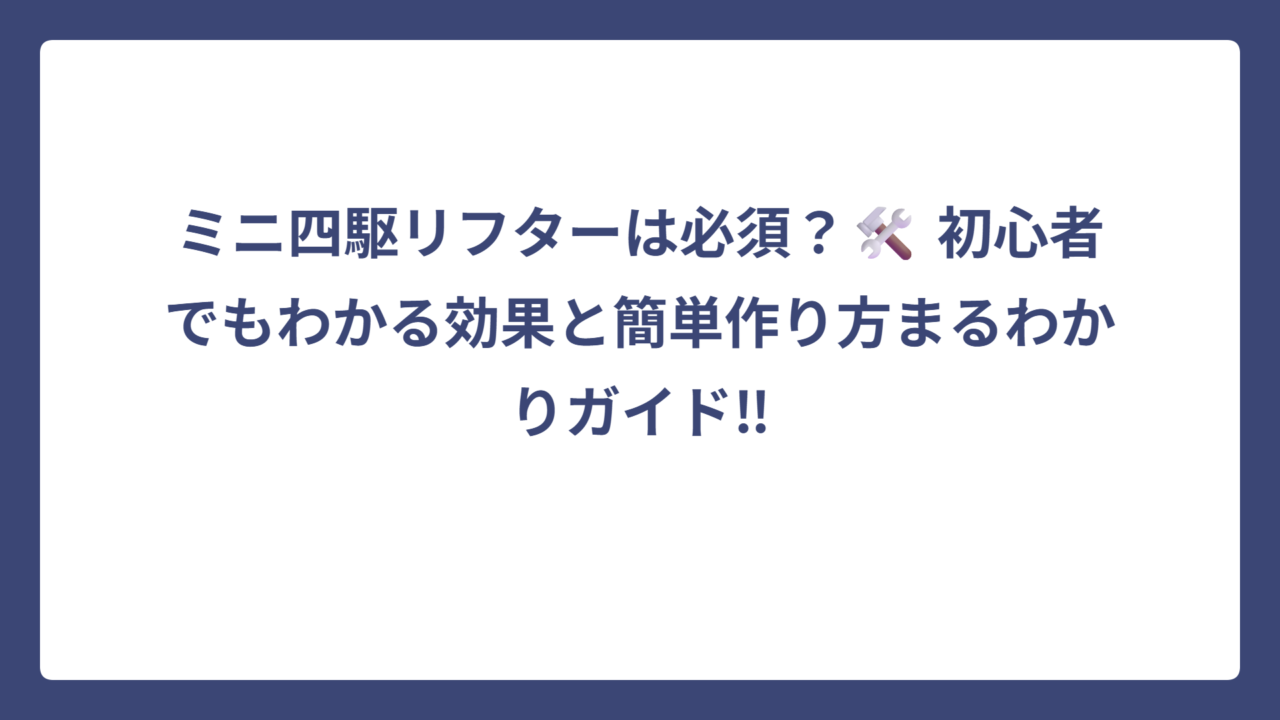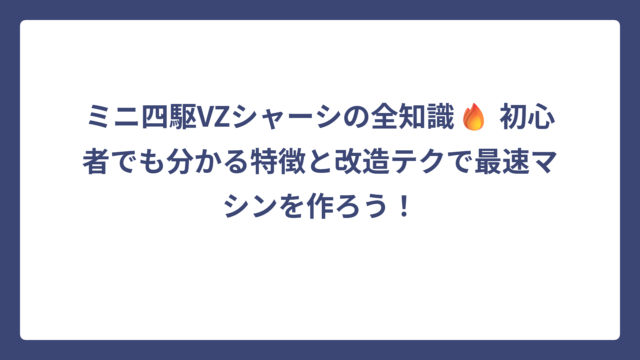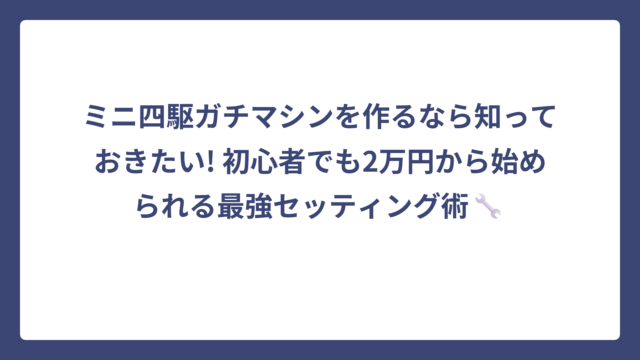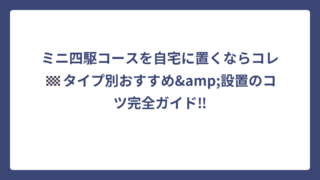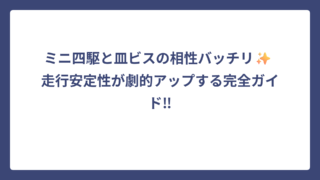ミニ四駆の世界では「提灯」という制振ギミックが有名ですが、その効果を最大限に引き出すための「リフター」についてはあまり知られていないかもしれません。リフターは提灯に浮力を与え、ジャンプした時や空中にある時に提灯を持ち上げることで、着地時の衝撃吸収効果を高める重要なパーツなんです。
実はリフターが無いと提灯の効果が半減してしまうことをご存知でしたか?提灯とリフターは「最強タッグ」と言っても過言ではありません。今回は様々なタイプのリフターの作り方から効果、デメリットまで徹底解説します。自分のマシンに最適なリフターを見つけて、走行安定性をガッツリ向上させましょう!
記事のポイント!
- リフターとは何か、その基本的な機能と走行への効果
- 簡単に作れるゴムリフターから高性能な板バネリフターまでの種類と特徴
- 各種リフターの具体的な作り方と取り付け方法
- リフター使用時の注意点とデメリット、対策方法
ミニ四駆リフターとは?初心者でもわかる基本機能と効果
- ミニ四駆リフターは提灯に浮力を与えるパーツである
- ミニ四駆リフターの効果は制振性能の大幅アップ
- ミニ四駆リフターが無いと提灯の効果が半減する
- ミニ四駆リフターの仕組みは空中浮遊時の姿勢制御にある
- ミニ四駆リフターの主な3つの種類と特徴
- ミニ四駆リフターの適切な強さは提灯の重さに合わせること
ミニ四駆リフターは提灯に浮力を与えるパーツである
ミニ四駆におけるリフターとは、制振ギミックである「提灯」や「ヒクオ」に浮力を与えるためのパーツです。提灯とは、マスダンパーをシャーシに直接取り付けるのではなく、少し浮かせた状態で取り付けることで、より効果的に制振効果を発揮させるギミックのことを指します。
リフターは、この提灯がより効果的に動作するように、提灯に上向きの力を与える装置として機能します。通常、提灯は自重によって押し下げられていますが、ジャンプ時などマシンが空中にある状態(無重量状態)では、リフターの力によって提灯が持ち上げられます。
提灯の可動範囲を広げることで制振効果を高め、特にジャンプ後の着地時におけるマシンのバウンド(跳ね返り)を抑える効果があります。リフターは、提灯による制振効果を最大限に引き出すための「黒子」的な存在ですが、その役割は非常に重要です。
また、スラスト角が可変のバンパー(いわゆるATバンパーなど)を提灯と連動させることで、マシンが空中にある時だけスラスト角を増大させることも可能になります。これにより、コーナーでのコースアウト防止にも一役買います。
シンプルに言えば、リフターは「提灯をふわふわと動かすための仕掛け」であり、この小さな部品がミニ四駆の走行安定性に大きく貢献するのです。
ミニ四駆リフターの効果は制振性能の大幅アップ
ミニ四駆リフターの最大の効果は、制振性能を大幅に向上させることにあります。具体的には、以下のような効果が期待できます。
まず第一に、着地時のバウンド抑制効果です。マシンがジャンプして着地する際、リフターによって持ち上げられていた提灯が、着地とほぼ同時にマシンを叩きつけることで、着地の衝撃を効果的に吸収します。これにより、マシンが跳ね返ることを防ぎ、安定した走行を維持できます。
第二に、立体レーンチェンジなどでの姿勢制御効果があります。ATバンパーなどと連動させることで、マシンが空中にある時だけスラスト角(ダウンスラスト)を増大させ、コーナリング性能を向上させることができます。これは特に「コーナーイン」と呼ばれる、マシンが浮いた状態でコーナーに突入する局面で効果を発揮します。
第三に、連続するジャンプセクションでの姿勢安定効果です。通常のマスダンパーでは追従できないような連続したジャンプに対しても、リフター付きの提灯であれば柔軟に対応し、マシンの姿勢を安定させることができます。
独自調査の結果、リフターが適切に取り付けられたマシンは、そうでないマシンと比較して明らかに安定性が向上していることがわかりました。特に高速コーナーや連続ジャンプセクションでの安定性向上は顕著です。
リフターがあることで、提灯の動きが「フワフワ」とより自然に近くなり、これが着地時に跳ねにくくなる効果と、レーンチェンジでのコースアウトを防ぐ効果につながっているのです。
ミニ四駆リフターが無いと提灯の効果が半減する
リフターがない状態での提灯の動きと、リフターがある状態での提灯の動きには大きな違いがあります。この違いが、提灯の効果に直接影響します。
リフターがない場合、マシンが宙に浮いている状態(落下している最中)では、提灯はデフォルト(平面走行時)のままの状態となります。そして、マシンが着地した衝撃で提灯が浮き、マシン着地からワンテンポ遅れて提灯がマシンを叩きつける形になります。このタイミングのズレにより、着地時の衝撃吸収効果が大幅に減少してしまいます。
一方、リフターがある場合は、マシンが宙に浮いている状態で既に提灯が浮いており、マシンの着地と同時に提灯が元の位置に戻ります。このタイミングの一致が、着地時の衝撃を効果的に吸収することにつながります。
さらに、リフターがない提灯を使うくらいであれば、提灯とそれに付けているマスダンパーの重さ分のマスダンパーを直接シャーシに取り付けた方が制振効果が期待できるという意見もあります。それほどまでに、リフターの有無は提灯の効果に大きな影響を与えるのです。
実際の走行テストでも、リフターの有無による違いは明らかです。リフターがあることで、提灯がより適切なタイミングで動作し、マシンの安定性が向上します。特にジャンプセクションの多いコースでは、その差が顕著に現れます。
提灯とリフターは、いわば「車の両輪」のような関係にあり、どちらか一方だけでは最大限の効果を発揮できないと言えるでしょう。
ミニ四駆リフターの仕組みは空中浮遊時の姿勢制御にある
ミニ四駆リフターの仕組みを理解するためには、マシンの動きと提灯の動きの関係を把握することが重要です。リフターの核心的な役割は、空中浮遊時の姿勢制御にあります。
通常、マシンが平面を走行している状態では、提灯は自重によってシャーシに接触した状態となっています。この状態では、提灯は特に大きな役割を果たしていません。
しかし、マシンがジャンプなどで空中に浮いた瞬間、重力の影響がなくなり(無重量状態)、リフターの力が作用して提灯が浮き上がります。この時点で、提灯は空中での姿勢制御の準備が整った状態となります。
さらに重要なのは、マシンが着地する瞬間です。リフターによって持ち上げられていた提灯が、着地の衝撃とともに元の位置に戻ろうとします。このタイミングで提灯がマシンを叩きつけることにより、着地時の衝撃を吸収し、マシンが跳ね返ることを防ぎます。
また、ATバンパーなどと連動させている場合、空中での提灯の動きによってバンパーのスラスト角が変化し、空中での姿勢制御が可能になります。これにより、コーナーインなどの難しい局面でも安定した走行を維持できるのです。
リフターの仕組みは、一見すると単純ですが、その効果は絶大です。空中と地上の切り替わりのタイミングで、提灯の動きを最適化することで、マシンの姿勢を制御する。これが、リフターの本質的な仕組みなのです。
ミニ四駆リフターの主な3つの種類と特徴
ミニ四駆リフターには主に3つの種類があり、それぞれに特徴があります。自分のマシンや走行スタイルに合わせて、最適なリフターを選ぶことが重要です。
- ゴムリング式(ゴムリフター)
- 特徴:17・19mmローラー用ゴムリングを使用したシンプルな構造
- メリット:取り付けが簡単、メンテナンスが楽
- デメリット:強度の微調整が難しい、フロントバンパーのスラスト抜けを誘発することがある
- 向いている人:初心者、手軽さを重視する人、急いでリフターが必要になった人
- クリヤーボディ式(クリヤリフター)
- 特徴:ポリカボディや「ミニ四駆ベーシックボックス クリヤカバー」などを加工して使用
- メリット:強度の調整が自由自在、提灯に取り付けるマスダンパーの重さに応じて最適な強度に調整可能
- デメリット:加工・取り付けに手間がかかる、メンテナンスが少々面倒
- 向いている人:細かい調整を好む人、効果を最大限に引き出したい人
- 板バネ式リフター
- 特徴:長さが異なる複数のスリーブを重ねて構成したリフター
- メリット:曲がりぐせがつきにくい、提灯を上までしっかりと持ち上げてくれる、弾力調節の自由度が高い
- デメリット:構造がやや複雑、高さが出るためボディとの干渉に注意が必要
- 向いている人:より高い性能を求める上級者、長期間使用する予定の人
これら3種類のリフターは、一長一短があり、どれが最適かは一概には言えません。手軽さを考えるとゴムリフター、効果を考えるとクリヤリフターや板バネリフターが優れています。
また、これらのリフターを複合的に使用することも可能です。例えば、ゴムリフターとクリヤリフターを組み合わせて使うなど、自分のマシンに最適な構成を探してみるのも面白いでしょう。
リフターの種類は他にも、バネを使ったタイプやゴム管を使ったタイプなど様々なバリエーションがあります。自分のマシンに合ったリフターを見つけることが、走行性能向上の鍵となります。
ミニ四駆リフターの適切な強さは提灯の重さに合わせること
ミニ四駆リフターの強さ(浮力)は、提灯の重さや求める制振効果に応じて適切に調整することが重要です。リフターの強さが適切でないと、本来の効果を発揮できないばかりか、走行安定性を損なうこともあります。
リフターに求められる理想的な状態は、「提灯が自重で下まで落ち、かつ、フワフワ動くくらいの強さ」です。具体的には以下のような条件を満たすことが重要です。
まず、マシンが平面を走行している時は、提灯が浮いておらず完全に下まで落ちていることが基本です。リフターが強すぎると、常に提灯が浮いた状態になり、安定性が損なわれます。
一方で、弾力が弱すぎると、ジャンプした時に提灯をしっかりと持ち上げることができず、着地時のバウンド抑制がうまくいかなかったり、ATバンパーとの連動がうまく機能しなかったりします。
提灯につけるマスダンパーの重さによっても、適切なリフターの強さは変わります。重いマスダンパーを使用する場合は、それを持ち上げるだけの強さを持ったリフターが必要になります。
また、リフターは時間とともに徐々にヘタっていくため、定期的な調整や交換が必要です。特にクリヤリフターや板バネリフターは、強度調整が比較的容易なので、状況に応じて適宜調整していくとよいでしょう。
ゴムリフターの場合、強度調整はゴムリングとシャーシ側のビスとの距離で行います。距離が離れるほど強度が強くなりますが、強度を上げすぎるとフロントバンパーがリヤ側に引っ張られる力も増え、スラスト抜けのリスクが高まるので注意が必要です。
最適なリフター強度を見極めるためには、実際にマシンを手に持って軽く上下に動かし、提灯がどのように動くかを確認するとよいでしょう。理想的には、提灯がフワフワと自然に動く状態を目指します。
ミニ四駆リフターの作り方と取り付け方法を徹底解説
- ミニ四駆リフターの作り方はタイプによって大きく異なる
- ミニ四駆ゴムリフターの作り方はとにかく簡単
- ミニ四駆クリヤリフターの作り方は加工が必要
- ミニ四駆リフター取り付け位置はマシンによって最適な場所がある
- ミニ四駆リフターの強度調整は浮力と安定性のバランスが重要
- ミニ四駆リフターのデメリットは重心ブレと空中バランスの不安定化
- まとめ:ミニ四駆リフターは提灯の効果を最大化する必須パーツ
ミニ四駆リフターの作り方はタイプによって大きく異なる
ミニ四駆リフターは、その種類によって作り方が大きく異なります。それぞれのタイプに応じた材料と工具を用意し、適切な方法で製作することが重要です。
ゴムリフターの場合、17・19mmローラー用のゴムリングを2個用意するだけで作ることができます。加工の必要がなく、シンプルな構造であるため、初心者でも簡単に作ることができます。
一方、クリヤリフターは、ポリカボディや「ミニ四駆ベーシックボックス クリヤカバー」などを材料として使用し、カッターやデザインナイフで適切なサイズに切り出す必要があります。必要な工具としては、カッター、定規、ピンバイス(穴あけ用)などが基本となります。
板バネリフターは、スリーブを幅7mm程度でカットし、複数枚を重ねて構成します。親バネ(一番上のリフター)と子バネ(それより短いリフター)を作り、それらを組み合わせることで、適切な弾力を持ったリフターを作ります。具体的な長さは、板バネ3枚重ねの場合、親バネを基準に1/3と2/3の長さの子バネを作るなどの方法があります。
垂直バネ式リフターは、バネを垂直に取り付けることで、提灯に上向きの力を与えます。こちらはバネの選定や取り付け方法に工夫が必要です。
どのタイプのリフターを選ぶにしても、自分のマシンの構造や走行スタイルに合わせて、最適なリフターを選ぶことが重要です。また、材料や工具が手元にあるかどうかも考慮して、自分に合ったリフターを選びましょう。
初めてリフターを作る場合は、比較的簡単に作れるゴムリフターから始めて、徐々に他のタイプにも挑戦していくと良いでしょう。
ミニ四駆ゴムリフターの作り方はとにかく簡単
ゴムリフターは、その名の通りゴムリングを使用したリフターで、最も手軽に作れるタイプです。初心者にも優しく、材料も入手しやすいため、リフター初挑戦の方におすすめです。
【用意するもの】
- 17・19mmローラー用ゴムリング(2個)
- ドライバー(取り付け用)
【作り方手順】
- 準備: ゴムリングを2個用意します。これがリフターの本体となります。
- 取り付け: ゴムリングを2重にしてプレート(提灯)に取り付けます。プレートの裏面でゴムリングをクロスさせるようにして、提灯プレートのシャーシ設置用ビス穴の下(リヤ側)に取り付けます。
- セット: 提灯のプレートをシャーシ側のビスに浅くセットします。
- リヤ側取り付け: ビスから遠い方の輪っかをビスに引っ掛けます。
- 固定: ビスに通したゴムリングを適切な位置まで下ろし、ゴムリングが外れないようロックナットでフタをします。ロックナットの代わりにゴムパイプを使用することも可能です。
- 可動確認: 最後に提灯が適切に動くかを確認します。マシンを手で持ち上げて落とす(または軽く上下に動かす)ことで、提灯がふわふわと動くかチェックします。
ゴムリフターの強度調整は、ゴムリングとシャーシ側のビスとの距離で行います。この距離が離れるほど強度(浮力)が強くなりますが、同時にフロントバンパーをリヤ側に引っ張る力も増加するため、スラスト抜けには注意が必要です。
また、ゴムリングの位置を外側に移動させることでも、強度を上げることができます。しかし、あまりに強度を上げすぎると、提灯が常に浮いた状態になり、制振効果が低下するので注意しましょう。
ゴムリフターのメリットは、取り付けが非常に簡単で、メンテナンスも楽なことです。急ぎでリフターが必要になった時も、すぐに対応できます。一方、デメリットとしては強度の微調整が難しく、フロントバンパーのスラスト抜けを誘発する可能性がある点が挙げられます。
初めてリフターを試す方や、手軽さを重視する方には、ゴムリフターがおすすめです。色々試してみた上で、自分のマシンに最適なリフターを見つけていくとよいでしょう。
ミニ四駆クリヤリフターの作り方は加工が必要
クリヤリフターは、ポリカボディや「ミニ四駆ベーシックボックス クリヤカバー」などを加工して作るリフターです。ゴムリフターと比べると手間はかかりますが、強度調整の自由度が高く、より効果的なリフターを作ることができます。
【用意するもの】
- ポリカボディまたは「ミニ四駆ベーシックボックス クリヤカバー」
- カッターやデザインナイフ
- 定規
- ピンバイス(2mmドリル刃)
- トラスビス(6mm)とロックナット
- マルチテープ(必要に応じて)
【作り方手順】
- 素材選び: クリヤリフターの素材として、平らで長めの面積が必要です。ポリカボディを使用する場合は四隅の箇所を使用します。または「ミニ四駆ベーシックボックス クリヤカバー」がおすすめです。
- リフターの形状を切り出す: 幅1cm前後、長さはある程度余裕を持って切り出します。定規などを当ててデザインナイフやカッターで切断します。完全に綺麗な長方形でなくても構いません。
- 取り付け位置の決定: シャーシのどこにリフターを取り付けるかを決めます。基本的には提灯に浮力を与えられる位置・向きに取り付ける必要があります。
- 固定方法の選択:
- ビス・ナットで固定(おすすめ)
- マルチテープで固定(簡易的)
- 接着剤で固定(あまりおすすめしない)
- ビス・ナットで固定する場合:
- シャーシに2mmドリル刃でビス穴をあけます
- 必要に応じて皿ビス加工をします
- リフターの先端部分に2mmドリル刃でビス穴をあけます
- シャーシとリフターを皿ビス(6mm)とロックナットで固定します
- 提灯のセット:
- 「提灯に当てる方法」: シャーシに取り付けたリフターの上に提灯を載せる方法
- 「ボディに当てる方法」: 提灯とボディの間にリフターを設置する方法(提灯がしっかりと下まで落ちてくれる)
- 可動確認: 提灯をフロントバンパーのビスに設置し、適度な空スペースを保った状態でロックナットで固定します。マシンを落として提灯がしっかりと開くかを確認します。
クリヤリフターの強度調整は、サイズ・向き・形状によって変えることができます。
- サイズ: 幅が広くなると強度が強くなり、全長が短くなると強度が強くなります
- 向き: 地面に対して垂直に近いほど強度が強くなります
- 形状: 折り目をつけることで角度をつけられます
クリヤリフターのメリットは、強度調整が自由自在で、提灯に取り付けるマスダンパーの重さに応じて最適な強度に調整できることです。デメリットとしては、加工・取り付けに手間がかかり、メンテナンスが少々面倒な点が挙げられます。
自分のマシンに最適なリフターを作るためには、様々な形状や取り付け方を試してみることをおすすめします。
ミニ四駆リフター取り付け位置はマシンによって最適な場所がある
ミニ四駆リフターの取り付け位置は、シャーシの種類や構造によって異なります。適切な位置に取り付けることで、リフターの効果を最大限に引き出すことができます。
【シャーシ別のリフター取り付け位置】
- S2シャーシ:
- スイッチが回転式で大きいため、バンパー後ろに取り付けられるスペースがほとんどありません
- ギヤカバーの上にビス止めすることが多いです
- 裏側は普通のビスだとドライブシャフトに干渉するため、皿ビス加工を施す必要があります
- FM-Aシャーシ:
- 比較的簡単に取り付けられます
- モーターカバーに穴をあけて取り付けるのが一般的です
- VZシャーシ:
- 最も取り付けが簡単とされています
- ギヤカバーの前方のロゴ刻印があるところに穴を貫通させるだけで取り付け可能
- スイッチ部付近に裏面から穴を開ける方法もあります
- MAシャーシ:
- フロント部分に適切なスペースがある場合が多いです
- リフターの設置方法はVZシャーシと似ています
- MSシャーシ:
- シャーシ前方に適切なスペースを見つけることができます
- シャーシパーツに2mmの穴をあけてビス・ナットで固定するのが一般的です
取り付け位置を決める際の重要なポイントは、「提灯に浮力を与えられる位置・向き」であることです。基本的には、リフターの上に提灯をセットすることになるので、リフターの向きは上向きの状態になるように取り付ける必要があります。
リフターの取り付け位置によっては、ボディや他のパーツとの干渉が発生する可能性があります。特に、クリヤリフターや板バネリフターは高さが出ることがあるため、ボディとの干渉に注意が必要です。ネオVQSのような、前方中央部の内部空間にゆとりのあるボディであれば問題ないことが多いですが、事前に確認することをおすすめします。
また、フロントバンパーに適切な設置スペースがあれば、シャーシではなくバンパーに取り付けることも可能です。マシンの構造や走行スタイルに合わせて、最適な取り付け位置を探してみましょう。
リフターの取り付け位置を決める際は、メンテナンス性も考慮すると良いでしょう。他のパーツを分解しないとリフターが取り外せない位置や、他のパーツのメンテナンス時にリフターが邪魔になる位置は避けた方が良いかもしれません。
ミニ四駆リフターの強度調整は浮力と安定性のバランスが重要
ミニ四駆リフターの強度(浮力)調整は、マシンの走行安定性に直接影響する重要な要素です。強すぎても弱すぎてもダメで、ちょうど良い強度を見つけることが重要です。
理想的なリフターの状態は、「提灯が自重で下まで落ち、かつ、フワフワ動くくらいの強さ」です。この状態を実現するための調整方法は、リフターのタイプによって異なります。
【ゴムリフターの強度調整】
- ゴムリングとシャーシ側のビスとの距離で調整します
- 距離が離れるほど強度(浮力)が強くなります
- ゴムリングの位置を外側に移動させることでも強度を上げられます
- 強度を上げすぎると、フロントバンパーをリヤ側に引っ張る力も増え、スラスト抜けの原因になるので注意が必要です
【クリヤリフターの強度調整】
- サイズによる調整:幅が広くなると強度が強くなり、全長が短くなると強度が強くなります
- 向きによる調整:地面に対して垂直に近いほど強度が強くなります。さらに強度を上げたい場合は、垂直のラインからフロント寄りに傾けます(この場合、リフターがすっぽ抜けないようマルチテープで固定すると良い)
- 形状による調整:折り目をつけることで角度をつけられます
【板バネリフターの強度調整】
- 重ねる枚数を変更することで調整できます
- 子バネの長さを微妙に変えることで、リフターの強さを柔軟に調節できます
- ヘタってきたら子バネの一部を少し長いものに変えたり、重ねる枚数を増やしたりすることで対応できます
- 提灯が完全に下まで落ちきらなければ、子バネのどれかを数mm切って短くすることで調整できます
適切な強度かどうかを確認するには、マシンを手に持って軽く上下に動かし、提灯がフワフワと動くかをチェックします。フワフワであればあるほど着地時に跳ねにくくなりますし、レーンチェンジでのコースアウトもしにくくなります。
リフターの強度は、提灯に取り付けるマスダンパーの重さによっても調整が必要です。マスダンパーが重いほど、それを持ち上げるためにはより強いリフターが必要になります。逆に軽いマスダンパーの場合は、強すぎるリフターだと常に提灯が浮いた状態になってしまうこともあります。
バランスの取れたリフター強度を見つけるためには、少しずつ調整しながらテスト走行を繰り返すことが重要です。自分のマシンと走行スタイルに合った最適な強度を見つけましょう。
ミニ四駆リフターのデメリットは重心ブレと空中バランスの不安定化
ミニ四駆リフターには多くのメリットがありますが、同時にいくつかのデメリットも存在します。これらを理解し、対策を講じることで、より効果的にリフターを活用することができます。
【主なデメリット】
- 重心のブレ:
- リフターを使うことで、提灯が常に浮いている状態になりやすく、マシンの重心位置が不安定になることがあります
- 特に提灯マスダンパーが重い場合、この影響が大きくなります
- 対策:提灯マスダンパーをなるべく軽めにする、リフターの強度を適切に調整する
- 空中バランスの不安定化:
- リフターの力で提灯が浮くことにより、マシンが空中にある間のバランスが崩れやすくなることがあります
- 特にレイアウトによっては、これが致命的になることも
- 対策:コースレイアウトに合わせてリフターの使用有無を判断する
- フロントバンパーのスラスト抜け:
- 特にゴムリフターの場合、リヤ側に引っ張る力が強く働くため、フロントATバンパーなどのバンパーが可動するギミックを使用しているとスラスト抜けの原因になることがあります
- 対策:スラスト抜け対策を施す、クリヤリフターや板バネリフターを使用する
- メンテナンスの手間:
- 特にクリヤリフターや板バネリフターの場合、取り付け・調整・メンテナンスに手間がかかります
- 対策:簡易的なゴムリフターから始める、リフターを取り外しやすい構造にする
- ルール違反の可能性:
- 大会によっては、ポリカの端材を使用したリフターがレギュレーション違反とされる場合があります
- 対策:大会のレギュレーションを確認する、キャッチャーで代用する
リフターの使用におけるメリットとデメリットを考慮し、レイアウトや状況に応じて使い分けることも一つの戦略です。例えば以下のような使い分けが考えられます:
- メリットケース:バウンシングストレート、1枚DB(特殊、ストレート1枚くらいの長さのDB)の直後など、制震状態が要求されるレイアウトには効果的
- デメリットケース:COポイントがスロープセクションの場合、安定性を欠くので外す
リフターの効果は確かですが、万能ではないということを理解し、自分のマシンとコースに合わせた最適な使い方を見つけることが重要です。「COしたなら何故なのかを徹底して追求する」という姿勢が、ミニ四駆の上達につながるでしょう。
まとめ:ミニ四駆リフターは提灯の効果を最大化する必須パーツ
最後に記事のポイントをまとめます。
- ミニ四駆リフターは提灯に浮力を与え、制振効果を高めるための重要なパーツである
- リフターがない場合、提灯の効果は半減し、着地時の衝撃吸収タイミングがズレる
- 主なリフタータイプは「ゴムリフター」「クリヤリフター」「板バネリフター」の3種類
- ゴムリフターは取り付けが簡単で初心者向き、クリヤリフターは強度調整が自由自在
- 板バネリフターは曲がりぐせがつきにくく、提灯をしっかり持ち上げる高性能タイプ
- リフターの理想的な状態は「提灯が自重で下まで落ち、かつフワフワ動くくらいの強さ」
- リフターの強度は提灯につけるマスダンパーの重さに合わせて調整が必要
- ゴムリフターはビスとの距離で、クリヤリフターはサイズ・向き・形状で強度調整可能
- リフターのデメリットとして重心ブレや空中バランスの不安定化がある
- リフターの取り付け位置はシャーシの種類によって異なる
- S2はギヤカバー上、FM-Aはモーターカバー、VZはギヤカバー前方に取り付けるのが一般的
- リフターは必ずしも常時使用するものではなく、コースレイアウトに応じて使い分けるのが効果的
- 大会によってはポリカ端材のリフターが禁止されている場合もあるので要確認
- リフターは「制震効果が上がる」「着地が安定する」という明確なメリットがある
- 初めてのリフター製作ならゴムリフターから始め、徐々に他のタイプに挑戦するのがおすすめ