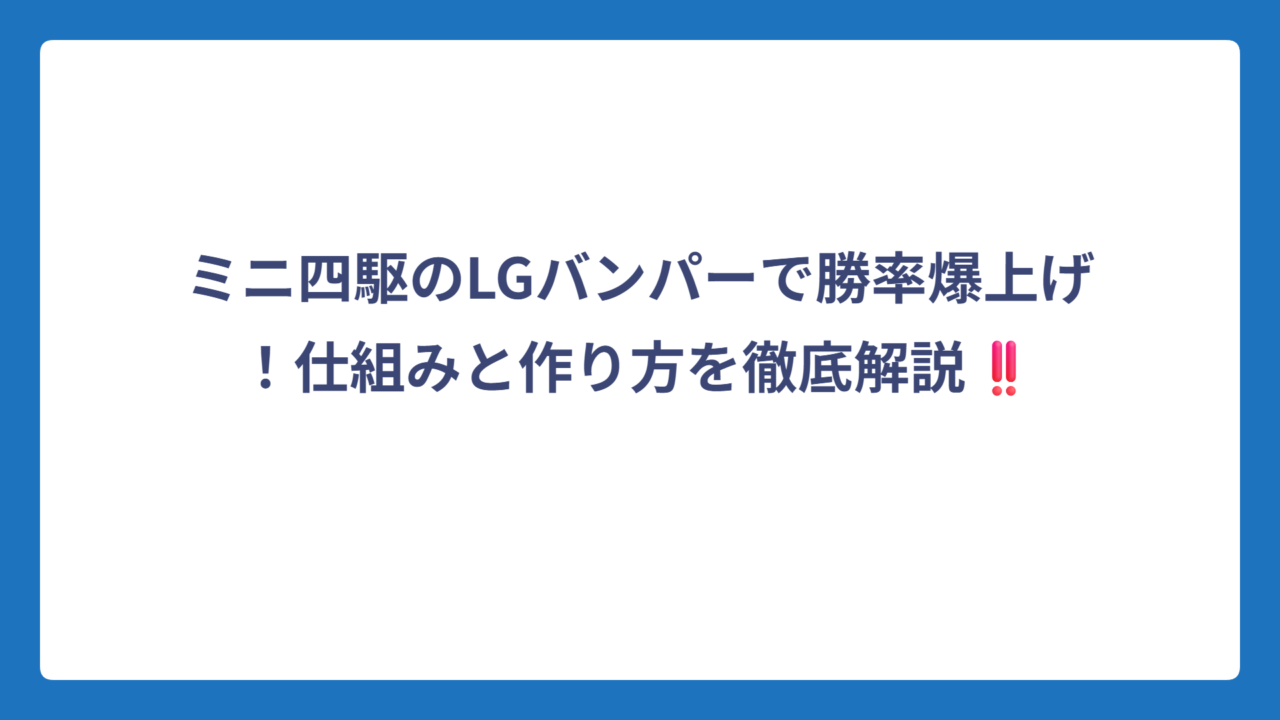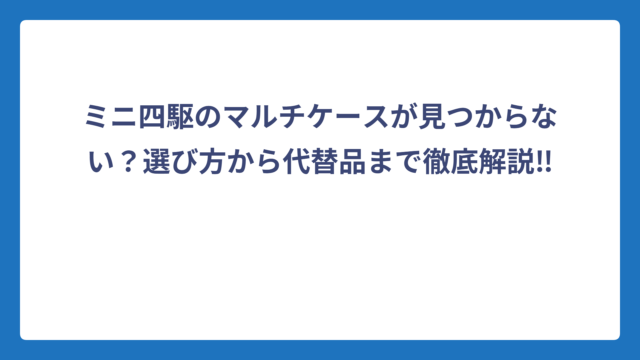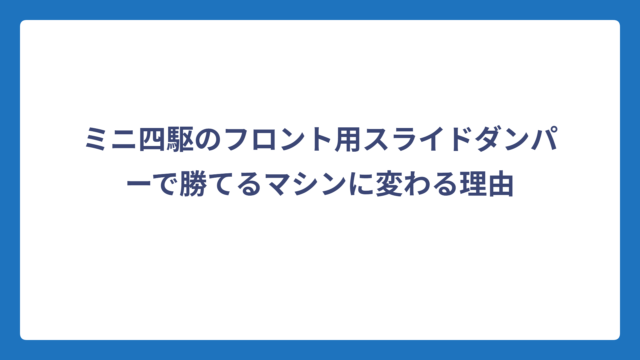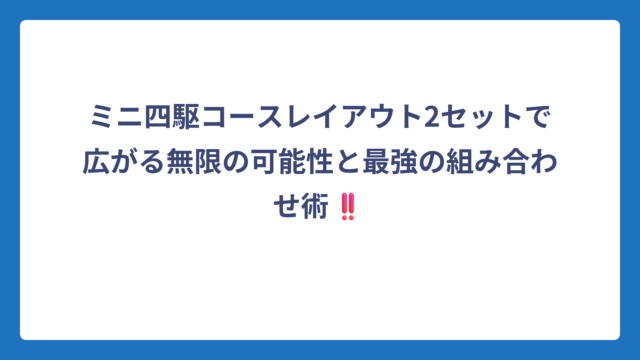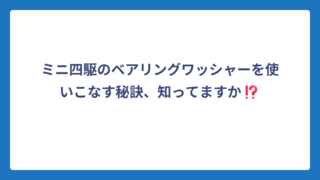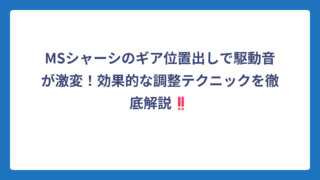ミニ四駆のレースで完走率を上げたいなら、LGバンパーは要チェックのギミックです。コースアウトを防ぎながらマシンを復帰させる機能は、多くのレーサーが注目している改造テクニックの一つといえるでしょう。
この記事では、インターネット上に散らばるLGバンパーに関する情報を収集し、その仕組みや製作方法、実際の効果について詳しく解説していきます。初心者でも挑戦しやすい低コストなギミックとして、またベテランレーサーの戦略的な選択肢として、LGバンパーの魅力を多角的にお届けします。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ LGバンパーの基本構造と動作原理が理解できる |
| ✓ 必要なパーツと具体的な製作手順がわかる |
| ✓ シャーシ別の搭載方法と注意点を把握できる |
| ✓ 実際の使用感や改良のヒントが得られる |
ミニ四駆のLGバンパーとは何か?基礎知識
- LGバンパーは軽量かつ簡単に作れる復帰システム
- 従来のアンカーシステムとの違いと特徴
- LGバンパーがコースアウト防止に効果的な理由
LGバンパーは軽量かつ簡単に作れる復帰システム
LGバンパーは「Light ゴムリング」の略称で、るどらがさんによって発案された革新的なバンパーシステムです。このシステムの最大の特徴は、特殊な工具や高度な加工技術が不要で、入手しやすいパーツのみで構成されている点にあります。
LGアンカーとは Light ゴムリング (lightは軽量、容易等の意味を込めて)
出典: サブカル”ダディ”ガッテム日記
📊 LGバンパーの主な構成要素
| パーツ分類 | 具体的なパーツ | 役割 |
|---|---|---|
| 基板部分 | FRPプレート、ブレーキステー | バンパー全体を支える土台 |
| 支柱部分 | ビス、ナット、ワッシャー、スペーサー | ゴムリングを固定する柱 |
| 可動部分 | FRP弓プレート | ローラーを保持し復帰動作を担う |
| テンション材 | 19mmゴムリング | 可動部に復帰力を与える |
一般的なミニ四駆レーサーが既に所持している、あるいは手軽に入手できるパーツで製作可能なため、初心者からベテランまで幅広く挑戦できる改造といえるでしょう。
従来のアンカーシステムとの違いと特徴
LGバンパーは従来のアンカーシステムと比較して、いくつかの明確な違いがあります。最も大きな相違点は軸の有無です。
従来のアンカーシステムでは、キノコやポールといった軸を中心に可動部が動く構造でした。一方、LGバンパーはその名の通り「0軸アンカー」や「Non-Pole(軸無し)アンカー」とも呼ばれ、中心軸を持たない構造になっています。
✅ LGバンパーと従来型アンカーの比較ポイント
- パーツ点数: LGバンパーの方が少なく済む
- 製作難易度: キノコの位置出しなど細かい調整が不要
- 重量: 軽量化しやすい設計
- 可動の自由度: ゴムリングによる柔軟な動きが特徴
- コスト: 安価なパーツで構成可能
作業工程自体もアンカーより少なく、軽量で簡単。アンカーはキノコの位置出しが何気に難しいですよね…
出典: ミニ四駆作ってみた
この構造により、MAシャーシなどリア接続部分が狭いシャーシでも前に詰めた配置が可能になり、スペース効率の良い設計が実現できます。
LGバンパーがコースアウト防止に効果的な理由
LGバンパーの最大の目的はコースアウトの確率を極力抑え、完走を確実にすることです。その効果を生み出す仕組みには、いくつかの要素が関係しています。
🎯 コースアウト防止のメカニズム
- ゴムリングによる復帰力: マシンが傾いたりコースアウトしかけた際、ゴムリングのテンションが元の位置に戻そうとする
- 前後左右の柔軟な可動: 力がかかった方向に対して柔軟に動き、衝撃を吸収しながら復帰
- 平面でのスライド動作: 平面上ではスライドのみを行い、不要な動きを制限
- 調整可能なテンション: ゴムリングの本数や巻き方で、硬さを自由に調整できる
LGバンパー搭載により、確かにコース復帰率が高くなりました。
実際の使用例では、360度コーナーなど大きく遠心力がかかる場面でもローラーステーが負けることなく機能したという報告もあります。特にFM-Aシャーシのような安全性重視のマシンをレース仕様に仕上げる際、LGバンパーの搭載は有効な選択肢といえるでしょう。
ミニ四駆LGバンパーの実践的な製作方法と改良テクニック
- 必要なパーツリストと入手方法
- 基板部分の製作手順とシャーシ別の注意点
- バンパー本体の加工とゴムリング取り付けのコツ
- シャーシへの組み付けと調整方法
- まとめ:ミニ四駆のLGバンパーで完走率アップを目指そう
必要なパーツリストと入手方法
LGバンパーを製作するにあたり、必要なパーツは比較的シンプルです。ここでは標準的な構成でのパーツリストを紹介します。
📝 LGバンパー製作に必要なパーツ一覧
| カテゴリ | パーツ名 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プレート類 | FRP弓プレート(フロントステー) | 2枚 | 貼り合わせて使用 |
| リアブレーキステーセット | 1セット | 皿ビス加工が必要 | |
| マルチワイドリアステー(カーボン) | 1枚 | MAシャーシの場合は必須 | |
| マルチ補強プレート(直プレート) | 1枚 | 中央3つ穴部分を使用 | |
| ゴム類 | 19mmゴムリング | 1〜3本 | テンション調整用 |
| 固定部品 | 各種ビス、ナット、ワッシャー、スペーサー | 適量 | 在庫パーツで対応可能 |
| ローラー | 19mmAAローラー、プラリングローラー | 適量 | 使用するレイアウトによる |
これらのパーツは、タミヤのグレードアップパーツとして模型店やオンラインショップで入手可能です。おそらく、多くのミニ四駆レーサーは既にいくつかのパーツを所持している可能性が高いでしょう。
💡 コスト面でのメリット
- 特別な専用パーツが不要
- ビスやナットなど汎用品を活用可能
- 余剰パーツの有効活用ができる
基板部分の製作手順とシャーシ別の注意点
基板部分はLGバンパー全体を支える重要な土台です。シャーシによって取り付け方法が異なるため、注意が必要です。
⚙️ MAシャーシの場合の製作手順
MAシャーシでは、リア接続部分の幅が狭いため、カーボン製のリアマルチプレートが必須となります。FRP1枚だと簡単に折れてしまうためです。
MAのリア接続部分は幅が狭く、プレートを支えにくいんです。(中略)なので、FRP1枚だと簡単に折れます。ここだけはカーボン必須です。
出典: ミニ四駆作ってみた
✨ 基板加工の具体的な手順
- リアマルチのサイドを切り落とす
- ボールリンクFRPをワイドブレーキの幅に合わせてカット(できるだけキッチリと)
- 直プレートは中央の3つ穴部分のみ切り出し(穴から外に1.5mm程度余白を残す)
- 面取りを行い、可動が丸くなるように削る
- 3枚のプレートを組み上げ、1.5mmスペーサーで高さ調整
- ゴムリングを通す(1.5mmと狭いため、爪楊枝などで通す)
🔧 VZシャーシの場合の注意点
VZシャーシに搭載する際は、独自の工夫が必要になります。
VZロゴのあるシャーシ部分。これちょっと複雑な気持ちw
出典: サブカル”ダディ”ガッテム日記
VZシャーシの場合、以下の対応が必要です:
- シャーシ裏のロゴマークによる凹凸を削り取る
- FRP端材などで補強を追加
- フロントギアカバーの出っ張りがゴム抜け防止になるため、支柱位置を調整
- バンパーとシャーシの接続部が弱いため、補強策を検討
バンパー本体の加工とゴムリング取り付けのコツ
バンパー本体の製作では、面取り作業が非常に重要です。これを怠るとゴムリングがすぐに切れてしまう原因になります。
🛠️ バンパー本体の製作ステップ
| 工程 | 作業内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ① プレート貼り合わせ | 2枚のFRP弓プレートを接着 | 強度確保のため確実に |
| ② 整形 | 9mm部分を切り落とし、全体を細く | スライド抵抗を減らす |
| ③ 面取り | 角を丸く削る | 最重要作業 |
| ④ 穴あけ | 中央付近に2つ穴を開ける | ワイドブレーキを治具に使用 |
| ⑤ ビス取り付け | 皿ビスを裏から、表に1.5mmスペーサー | 完全に埋めて抵抗を減らす |
面取りしっかりやっておかないと、この時点でゴムリング切れます。
出典: ミニ四駆作ってみた
💪 ゴムリング取り付けのテクニック
ゴムリングの取り付けには複数のパターンがあり、それぞれ特性が異なります:
✓ 1本のみ: 緩めの動きで使いたい場合。ただし切れた時のリスクあり ✓ 2本(基板部分): 最大で入れられる本数。保険になるが可動が硬くなる ✓ 追加1本(バンパー上部): 直プレートの前後に引っ掛け、バンパー上を通す ✓ ネジったゴムリング: 左右の動きを制限し、調整の幅を広げる
シャーシへの組み付けと調整方法
組み付け作業では、シャーシへの負荷分散を考慮した取り付けが重要です。
🔩 シャーシ側の加工と取り付け
[加工手順]
1. リアの穴を2mmで貫通拡張
2. 大ワッシャーを入れてネジを通す
3. ロックナットで締める
4. 前側のロックナットがシャーシに干渉する場合、シャーシ側を0.5mm程度削る
貫通させて締め付けることで、負荷が分散されて壊れにくくなり、メンテ性も上がります。また皿ビスでなくワッシャー使うのも丈夫に作るためです。
出典: ミニ四駆作ってみた
⚡ 調整と改良のポイント
LGバンパーは基本構造を維持しながら、様々な調整が可能です:
| 調整項目 | 方法 | 効果 |
|---|---|---|
| 可動域制限 | FRPでストッパーを追加 | デメリット改善 |
| テンション調整 | ゴムリングの本数変更 | 硬さの最適化 |
| 高さ調整 | スペーサーの厚み変更 | バンパー位置の微調整 |
| 補強 | コの字型ステー追加 | 耐久性向上 |
さらには可動域の制限もかけられるという優れもの。LGバンパーの良くないところとしては、テンションを下げて可動を軽く、さらにフレキシブルに動くようにすると可動域も広がってしまうところだと思うのですが、これで制限かけるとデメリットも改善できますね。
出典: サブカル”ダディ”ガッテム日記
推測の域を出ませんが、レースコースの特性や使用するモーターの出力に応じて、これらの調整を組み合わせることで、マシンに最適なセッティングを見つけられるでしょう。
まとめ:ミニ四駆のLGバンパーで完走率アップを目指そう
最後に記事のポイントをまとめます。
- LGバンパーは「Light ゴムリング」の略で、るどらがさんが発案した軽量で簡単な復帰システムである
- 従来のアンカーシステムと異なり、中心軸を持たない「0軸アンカー」構造が特徴である
- 特殊な工具や高度な加工技術が不要で、入手しやすいパーツのみで構成される
- MAシャーシではカーボン製リアマルチプレートが必須、VZシャーシでは独自の補強が必要である
- 面取り作業を丁寧に行わないと、ゴムリングがすぐに切れる原因となる
- ゴムリングの本数や巻き方でテンションを調整でき、マシン特性に合わせたセッティングが可能である
- 実際の使用例では、コース復帰率が高くなり、完走率向上に貢献したという報告がある
- 可動域制限やストッパー追加など、様々な派生形や改良が可能である
- 製作コストが安価で、初心者からベテランまで幅広く挑戦できる改造である
- シャーシへの取り付けは、負荷分散を考慮した方法で行うと耐久性が向上する
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- 【mini4wd】高機能バンパー!LGバンパーの作り方紹介!【ミニ四駆】 – YouTube
- ミニ四駆作ってみた〜その427 「簡単高速MA製作その3」 – ミニ四駆作ってみた
- ミニ四駆ブログ LGバンパーの作り方 : 子育て&ミニ四駆のブログ/Morinokuma
- 【ミニ四駆】ボディ取り付け、LGバンパー改良。 : サブカル”ダディ”ガッテム日記
- 【ミニ四駆】FMVZ+LGバンパー! : サブカル”ダディ”ガッテム日記
- 【ミニ四駆】新戦力LGバンパー VZシャーシ改造計画16 | 見たいモノを造る企画【mitaimonowotsucool.com】
- concours d’Elegance/SEARCH TAG
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当ブログをご覧いただきありがとうございます。
このたび、当ブログの記事内容について無断転載とのご指摘を受けました。
事実確認が十分でない部分もありますが、著作権に関わるご迷惑をおかけする可能性を重く受け止め、記事をすべて非公開とし、今後の再確認を進めてまいります。
ご心配・ご不快の念をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後は再発防止に努め、安心してご覧いただけるブログ運営を行ってまいります。