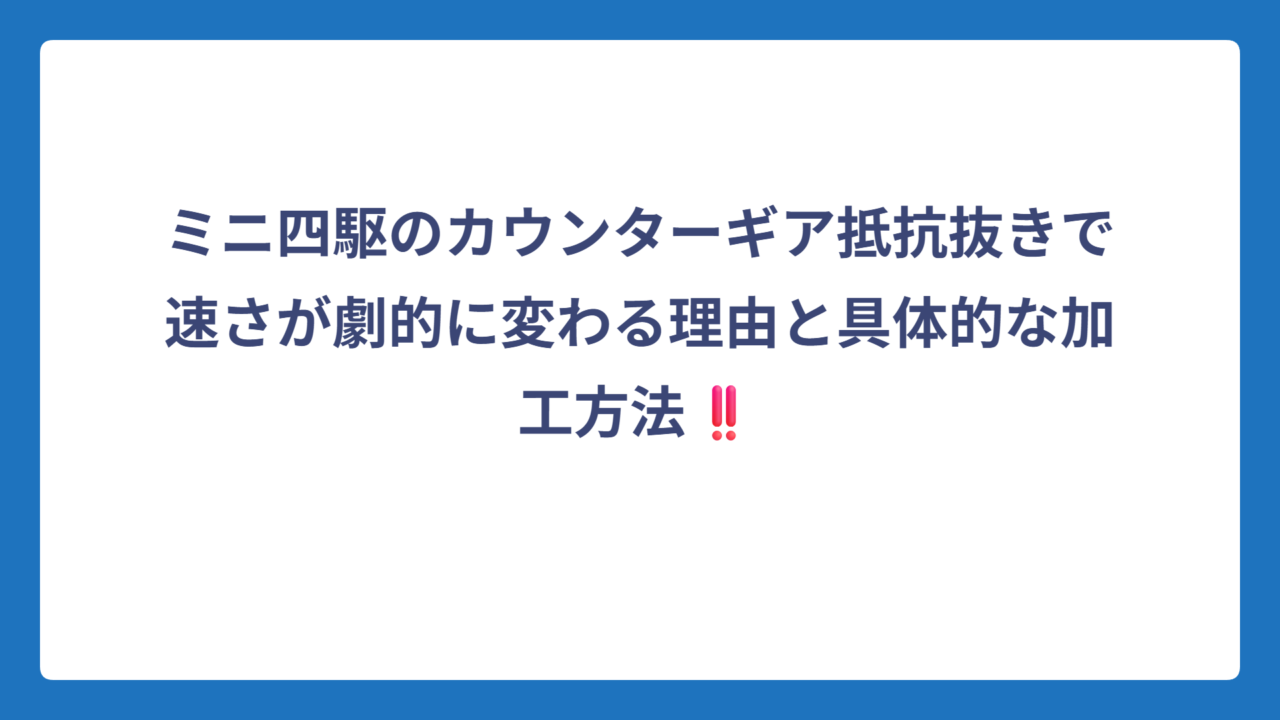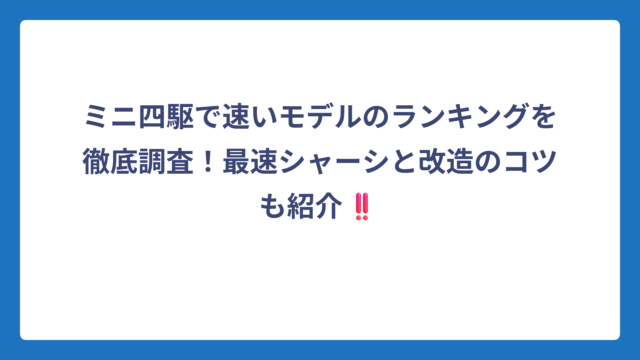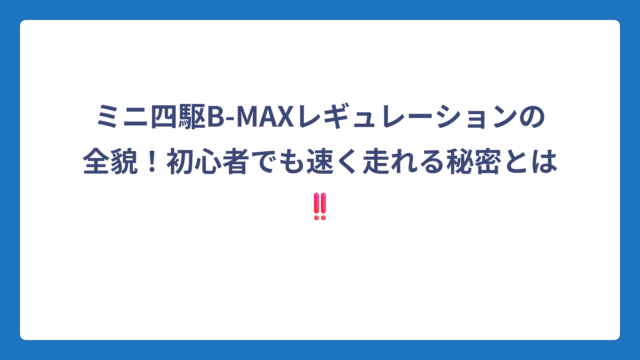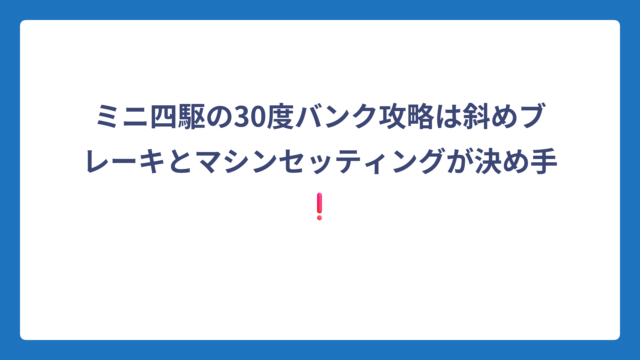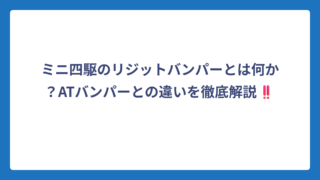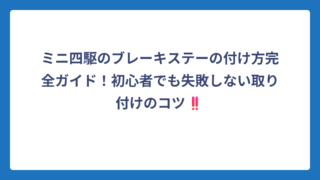ミニ四駆のスピードアップを目指すなら、カウンターギアの抵抗抜き加工は避けて通れない改造テクニックです。多くのレーサーがこの加工に取り組んでいますが、実は正しい方法を知らないと効果が出ないどころか、逆にタイムが落ちることもあります。
この記事では、インターネット上に散らばるカウンターギア抵抗抜きの情報を徹底的に収集・分析し、効果的な加工方法から失敗しないコツまで、独自の視点で解説していきます。初心者から上級者まで、すぐに実践できる具体的なテクニックが満載です。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ カウンターギアの抵抗が発生する仕組みと抵抗抜きの効果 |
| ✓ 片軸・両軸モーター別の具体的な加工手順 |
| ✓ フローティング化との違いと使い分け方 |
| ✓ 失敗しないための治具の作り方と注意点 |
ミニ四駆カウンターギアの抵抗抜きが速度向上に直結する理由
- カウンターギアの構造が生み出す摩擦抵抗の正体
- 抵抗抜き加工で実際にどれくらいタイムが変わるのか
- ベアリング化との併用で最大効果を引き出す方法
カウンターギアの構造が生み出す摩擦抵抗の正体
ミニ四駆のカウンターギアは、シャフトとの接触面積が意外と大きいことをご存知でしょうか。
一般的なカウンターギアの場合、ベアリング部分を除いてシャフトに接触する部分が約4mmも存在します。この部分では、プラスチック製のギア内部とシャフトが直接触れ合い、回転するたびに摩擦抵抗が発生しているのです。
🔧 カウンターギアの接触部分の詳細
| 部位 | 接触長さ | 材質 |
|---|---|---|
| ギア本体の円筒部 | 約7mm | プラスチック |
| POMベアリング | 約2mm | 低摩擦樹脂 |
| シャフト接触面 | 約4mm(ギア7mm+POM2mm-ベアリング部) | – |
カウンターギアの内部はこのようになっていまして、シャフトの接触面が斜線部分です
抵抗抜き加工の基本的な考え方は、このシャフトとの接触面積を減らすことにあります。外側の必要最小限の部分だけを残してギア内部の穴を拡張することで、摩擦抵抗を大幅に低減できるというわけです。
抵抗抜き加工で実際にどれくらいタイムが変わるのか
抵抗抜き加工の効果について、複数の検証データを分析すると興味深い結果が見えてきます。
📊 抵抗抜き前後のタイム比較データ
| 加工内容 | 100m走タイム | 改善幅 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 未加工(標準) | 21.75秒 | – | 基準値 |
| 背面削り+絶縁ワッシャー | 21.45秒 | -0.3秒 | カウンターギア背面の出っ張り除去 |
| 抵抗抜き加工 | 21.28秒 | -0.47秒 | 内部穴拡張+位置出し調整 |
このデータから分かる通り、適切な抵抗抜き加工を行うことで0.5秒近いタイム短縮が期待できます。100mで0.5秒は非常に大きな差であり、レースの勝敗を分ける重要な要素となるでしょう。
ただし、注目すべきは「ただドリルで穴を広げるだけでは効果が出ない」という点です。
加工後に手回ししてみましたが『うん。なんとなく回りが良くなった気がする。。。』というのが正直な感想です
この体験談が示すように、抵抗抜きの効果を最大化するには、ギアの位置出しやワッシャーの配置など、総合的なセッティングが不可欠なのです。
ベアリング化との併用で最大効果を引き出す方法
抵抗抜き加工とベアリング化を組み合わせることで、さらなる効果が期待できます。
一般的には、POM(低摩擦樹脂)ベアリングを使用している場合でも内部の抵抗抜きは有効ですが、おそらく最も効果的なのはボールベアリングと抵抗抜きの併用でしょう。
⚙️ ベアリングタイプ別の特性
| ベアリングタイプ | 摩擦係数 | 抵抗抜きとの相性 | コスト |
|---|---|---|---|
| プラベアリング(標準) | 高 | ◎ 効果大 | 低 |
| POM低摩擦ベアリング | 中 | ○ 効果あり | 中 |
| 620ボールベアリング | 低 | ◎ 最大効果 | 高 |
ただし、ある検証では興味深い結果が報告されています。
結論はベアリングが無ければ…、抵抗抜きしても良いかもね?…。1/10は僅差で回数をこなすと電池消耗で正確ではなくなります
この報告によれば、ボールベアリング使用時と抵抗抜き加工では、ボールベアリングの方がやや優位という結果でした。しかし、これは加工精度や方法によって結果が変わる可能性があるため、「絶対にどちらが優れている」とは言い切れません。
理想的なセッティングとしては、ボールベアリング+適切な抵抗抜き加工の組み合わせが、最も高い駆動効率を実現できると推測されます。
ミニ四駆カウンターギアの抵抗抜き加工を成功させる実践テクニック
- 片軸モーター用カウンターギアの基本的な抵抗抜き手順
- 両軸モーター(MA・MS)のフローティング化との違い
- 加工精度を高める治具の自作方法
- 失敗しないための位置出しとワッシャー配置のコツ
- まとめ:ミニ四駆のカウンターギア抵抗抜きで押さえるべきポイント
片軸モーター用カウンターギアの基本的な抵抗抜き手順
片軸モーター用カウンターギアの抵抗抜き加工は、比較的シンプルな手順で実施できます。
🛠️ 基本的な加工手順
- ドリル径の選定:2.5mm径のドリルを使用(シャフト径2mm+余裕0.5mm)
- 外側の残し幅の決定:外側2mm程度を残して加工(強度とのバランス)
- ドリル加工:慎重に少しずつ穴を拡張(一気に削らない)
- バリ取り:丁寧に内部のバリを除去
- POM部分の加工(オプション):約1mm程度を加工
穴径について、複数の情報を総合すると以下のような傾向が見られます。
📏 ドリル径と残し幅の関係
| ドリル径 | 外側残し幅 | 強度 | 抵抗低減効果 | 推奨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5mm | 2.0mm | ◎ | ○ | 初心者向け |
| 3.0mm | 1.5mm | ○ | ◎ | 中級者向け |
| 4.0mm | 0.5mm | △ | ◎◎ | 上級者・リスク大 |
外側2㎜ぐらいを残して加工しました。ギヤの強度を選ぶか抵抗抜きを優先するか悩むところですね
重要な注意点として、削りすぎはギアの強度低下につながります。レース中にギアが割れてしまっては元も子もありません。特に初めて加工する場合は、保守的に2mm残しから始めることをおすすめします。
両軸モーター(MA・MS)のフローティング化との違い
両軸モーター搭載のMAシャーシやMSシャーシでは、単純な抵抗抜きとは異なる「フローティング化」という手法が存在します。
この二つは似て非なるものです。それぞれの特徴を理解して使い分けることが重要でしょう。
🔄 抵抗抜きとフローティング化の比較
| 項目 | 抵抗抜き | フローティング化 |
|---|---|---|
| 加工難易度 | 低〜中 | 高 |
| 必要な部品 | ドリルのみ | ベアリング(620/730など) |
| コスト | 低 | 中〜高 |
| 効果 | 中 | 高 |
| ギア強度 | やや低下 | 低下(パイプ切断時) |
| 加工精度の要求 | 中 | 非常に高 |
フローティング化は、カウンターギアの内部をベアリングのみで支持し、プラスチック部分とシャフトの接触を完全になくす手法です。
ベアリングが噛む部分は良いとして、内部の4mm程度のプラスチックの筒部分が大きく干渉しています。絶対ここロスしてる感ある
理論上は最も抵抗が少ない理想的な状態ですが、加工精度が非常に重要で、わずかなズレでもギアが正常に回転しなくなるリスクがあります。
複数の情報源で「フローティング化は失敗した」という報告も見られることから、推測の域を出ませんが、手作業での加工には限界があると考えられます。
加工精度を高める治具の自作方法
抵抗抜き加工で最も難しいのが「真っ直ぐに穴を拡張する」ことです。手で押さえながらドリルで削ろうとすると、ギアが揺れて穴が斜めになったり、最悪の場合割れてしまったりします。
そこで役立つのが自作治具です。
🔧 MSシャーシのピニオンギア取り付け治具を活用した方法
MS・MAシャーシに付属するピニオンギア取り付け治具は、実は抵抗抜き加工に最適な厚みを持っています。
| 治具の特徴 | 寸法 | 利点 |
|---|---|---|
| 厚み | 5mm | トラスビス(6mm)を差すと1mm飛び出る |
| 穴の開けやすさ | – | プラスチックで加工容易 |
| 入手性 | ◎ | MSシャーシに付属 |
具体的な治具作成手順:
- ピニオン治具に1.5〜1.8mmの穴を開ける
- トラスビス(6mm)をねじ込む
- ビス頭が治具と面一になるまで固定
- カウンターギアをかぶせて3mmドリルで加工
この状態でビスの先端が1mmだけ飛び出していることになります。カウンターギヤをかぶせ、押し付けながら3mmのドリルで穴を広げていきます
出典:SiSO-LAB
この方法なら、ドリル刃先がビス先端に当たった時点で自動的に停止するため、外側約1.6mmを残した精密な加工が可能です。
別の方法として、4:1ギアを固定用の治具として使う方法も報告されています。
普段は使うことのない、4:1ギアを抑えに使ってみました。木の板にネジ釘で打ち付け、同じものを3つ揃えて均等に並べます
どちらの方法も、ギアをしっかり固定して正確に加工するという基本原理は同じです。自分の持っているパーツや工具に合わせて選択すると良いでしょう。
失敗しないための位置出しとワッシャー配置のコツ
抵抗抜き加工で穴を広げた後、多くの人が直面するのが「ギアの位置出し」の問題です。
穴が広がった分、カウンターギアが左右にガタつくようになります。このガタを放置すると、せっかく抵抗を減らしても別の抵抗や異音が発生してしまいます。
✅ 効果的なワッシャー配置の原則
- 基本ルール:ギアとシャーシの接触を避けつつ、ガタを最小限に抑える
- 絶縁ワッシャーの活用:摩擦抵抗が少ない絶縁ワッシャーを優先的に使用
- 左右のバランス:均等ではなく、構造に応じて最適な配置を見つける
実際の配置例として、以下のような報告があります。
フロント ベアリング側:小ワッシャー1 絶縁ワッシャー1 フロント 背面側:絶縁ワッシャー1 リア ベアリング側:絶縁ワッシャー1 リア 背面側:絶縁ワッシャー1
この配置により、電圧1.4Vで100m走21.45秒という良好なタイムを記録したとのことです。
⚠️ よくある失敗パターン
| 失敗例 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| ギューという異音 | ワッシャーの配置でギアが圧迫 | ベアリング側にまとめる |
| カラカラという音 | スパーギアのグラつき | スパーギア側も位置出しが必要 |
| タイムが逆に遅くなる | 過度な締め付けによる抵抗増 | クリアランスを見直す |
また、カウンターギアの背面にある出っ張りも抵抗源になっているという興味深い発見があります。
カウンターギアの背面はシャーシに接触している?これひょっとして…摩擦抵抗になってないかな
背面の出っ張りを削り取り、絶縁ワッシャーを挟むことで、さらなるタイム短縮が報告されています。抵抗抜きは単なる穴拡張だけでなく、ギア周辺の総合的な最適化が重要なのです。
まとめ:ミニ四駆のカウンターギア抵抗抜きで押さえるべきポイント
最後に記事のポイントをまとめます。
- カウンターギアは約4mmの接触面があり、摩擦抵抗の主要な発生源である
- 適切な抵抗抜き加工により0.5秒程度のタイム短縮が期待できる
- ドリル径は2.5〜3.0mm、外側2mm程度を残す加工が強度とのバランスが良い
- フローティング化は理論上最高だが加工精度が非常に高く、失敗リスクも大きい
- MSシャーシのピニオン治具を活用すると精密な加工が可能になる
- 抵抗抜き後はワッシャーによる位置出しが効果を左右する重要な要素
- 絶縁ワッシャーを活用することで摩擦抵抗をさらに低減できる
- カウンターギアの背面の出っ張りも抵抗源となるため削ることが有効
- ボールベアリングと抵抗抜きの併用が最も高い効果を発揮する可能性がある
- 加工は少しずつ進め、都度テストしながら最適点を見つけることが成功の鍵である
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- カウンターギヤを抵抗抜きしてみよう!!(片軸用)- みそじで復活!!ミニ四駆改造奮闘記。
- MAカウンターギヤの抵抗抜き! – ジジイのミニ四駆Part17!
- カウンターギヤの抵抗抜き2 – あに。のブログ
- 【ミニ四駆】MA・簡易的な両軸フローティングカウンターギア – サブカル”ダディ”ガッテム日記
- 88 ギア駆動を見直してみたよ【後編】 – ミニ四駆、もう一度始めてみたよ
- ミニ四駆カウンターギヤの抵抗抜き、簡単に精度よく加工できる方法を考案 – SiSO-LAB
- 87 ギア駆動を見直してみたよ【中編】 – ミニ四駆、もう一度始めてみたよ
- カウンターギヤ – ミニ四駆改造マニュアル@wiki
- ミニ四駆作ってみた〜その290「JC2018対策:MAのギア周り」
- concours d’Elegance/SEARCH TAG カウンターギア
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当ブログをご覧いただきありがとうございます。
このたび、当ブログの記事内容について無断転載とのご指摘を受けました。
事実確認が十分でない部分もありますが、著作権に関わるご迷惑をおかけする可能性を重く受け止め、記事をすべて非公開とし、今後の再確認を進めてまいります。
ご心配・ご不快の念をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後は再発防止に努め、安心してご覧いただけるブログ運営を行ってまいります。