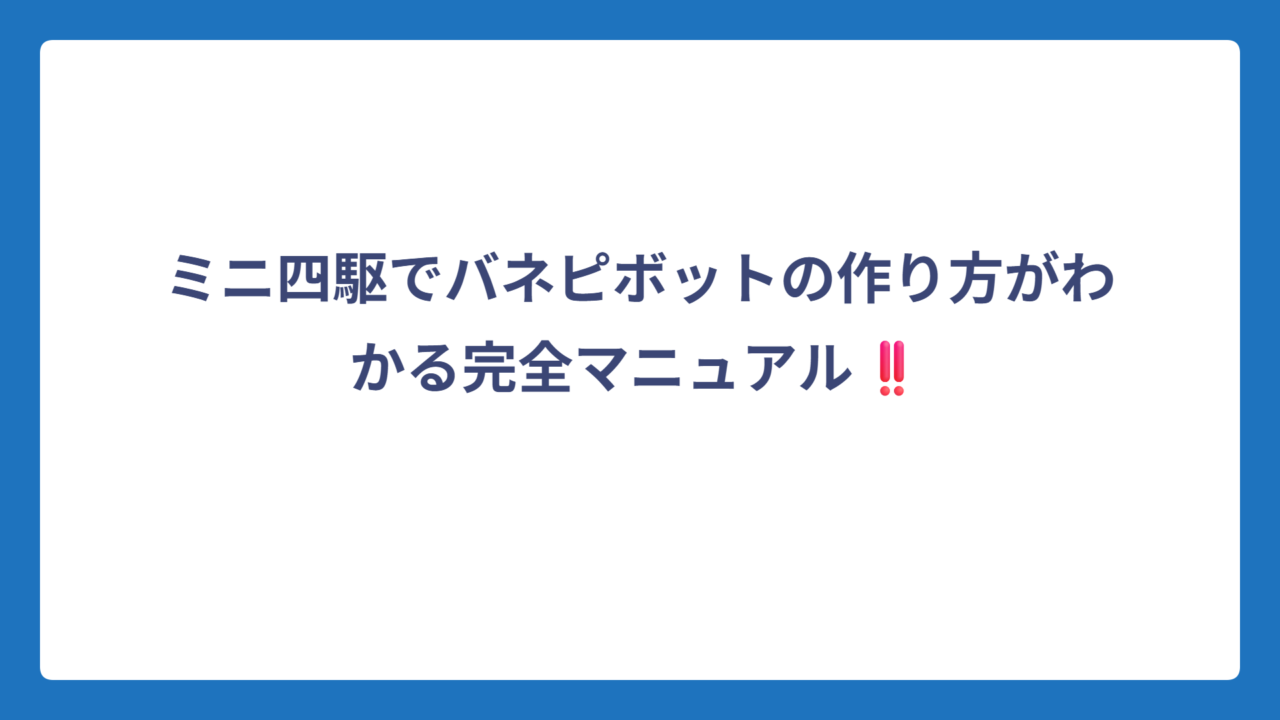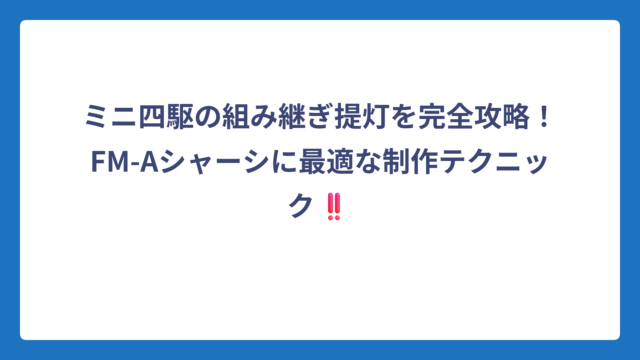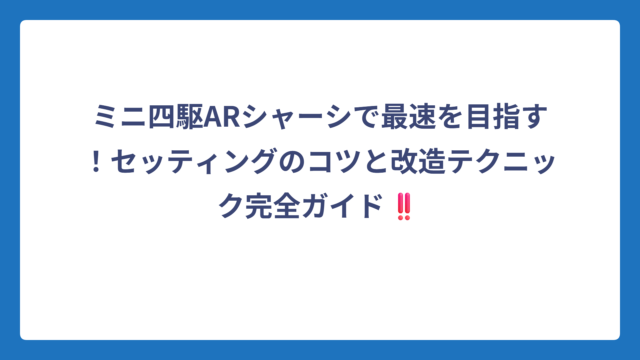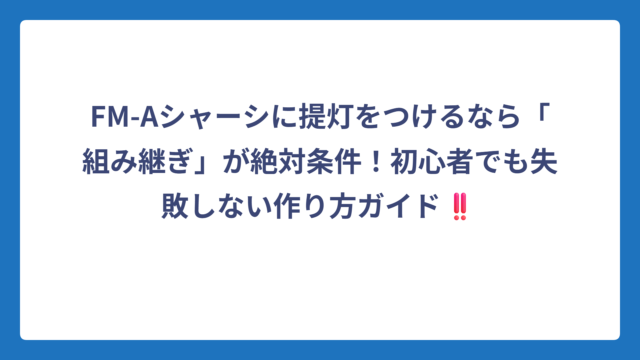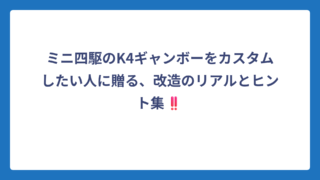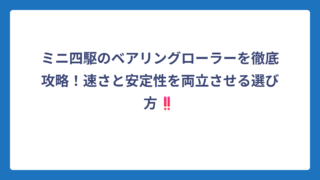ミニ四駆の改造を突き詰めていくと、ピボットバンパーのゴム劣化や切れに悩まされていませんか?従来のゴム式ピボットバンパーは衝撃を吸収してくれる一方で、経年劣化や走行中の摩擦で頻繁にゴムが切れてしまうという弱点があります。そこで登場するのが「バネピボット」です。バネピボットとは、ゴムの代わりにスプリングを使用したピボットバンパーのこと。耐久性が高く、ほぼ半永久的に使えるという大きなメリットがあります。
この記事では、バネピボットの基本的な作り方から、必要な材料や治具の選び方、無加工での作成方法、さらにはピボットスラダンとの組み合わせまで、幅広い情報をお届けします。カーボンプレートを使った本格的な作り方から、初心者でも挑戦できるFRP加工まで、実際の製作者たちの工夫を参考にしながら詳しく解説していきます。
| この記事のポイント |
|---|
| ✓ バネピボットはゴムを使わずスプリングで稼働させる耐久性の高い改造パーツ |
| ✓ FRPやカーボンプレートを使った作り方と必要な工具・材料 |
| ✓ スプリングの固定方法とH型加工のコツで脱落を防ぐテクニック |
| ✓ ピボットスラダンとの組み合わせや無加工での製作アイデア |
ミニ四駆のバネピボットとは何か
- バネピボットはスプリングを使った次世代型ピボットバンパー
- ゴム式との違いと耐久性のメリット
- バネピボットの作り方における基本構造
バネピボットはスプリングを使った次世代型ピボットバンパー
バネピボットとは、従来のピボットバンパーで使用していたゴムをスプリング(バネ)に置き換えた改造パーツです。ピボットバンパーは、コースの壁に当たった際に可動部が動くことで衝撃を吸収し、マシンの挙動を安定させる重要な役割を担っています。
通常のピボットバンパーでは、可動部の復元力にローラー用のゴムが使われることが多いのですが、このゴムが頻繁に切れてしまうという問題がありました。特に硬めのセッティングにするために2重3重にゴムを重ねると、放置しているだけでも劣化して切れてしまうケースが報告されています。
ローラー用のゴムが擦れて頻繁に切れる。硬めにしたくて2重3重にしてバンパーへ取り付けるのですが、そのまま放置していると切れてしまいます。
この問題を解決するために考案されたのがバネピボットです。スプリングはゴムと違って劣化しにくく、理論上は半永久的に使用できるため、メンテナンス頻度を大幅に減らすことができます。
ゴム式との違いと耐久性のメリット
バネピボットとゴム式ピボットバンパーの最大の違いは、耐久性と安定性にあります。以下の表で両者の特徴を比較してみましょう。
📊 バネピボットとゴム式の比較表
| 項目 | ゴム式ピボット | バネピボット |
|---|---|---|
| 耐久性 | 低い(劣化・切れやすい) | 高い(半永久的) |
| メンテナンス頻度 | 高い(頻繁な交換が必要) | 低い(ほぼ不要) |
| 反発力の調整 | ゴムの本数や種類で調整 | スプリングの硬さで調整 |
| 加工難易度 | 比較的簡単 | やや高度(穴あけ加工が必要) |
| 見た目 | ゴムが見える | スプリングが見える(スタイリッシュ) |
バネピボットの大きなメリットは、ゴムと違って永久に使えるという点です。走行中にスプリングが外れにくいように適切な加工を施せば、コースからの衝撃を安定して吸収し続けることができます。
また、スプリングの硬さを変えることで反発力を調整できるため、コースの特性やマシンのセッティングに合わせて細かなチューニングが可能です。一般的には、スライドダンパーに使われる銀色のスプリング(硬いタイプ)を使用すると、素早い復元が期待できるようです。
デメリットとしては、FRPやカーボンプレートに正確な穴加工が必要という点が挙げられます。スプリングを固定するためのH型の穴を開ける作業には、ある程度の工作技術とツールが必要になります。
バネピボットの作り方における基本構造
バネピボットの基本構造は、大きく分けて3つの層から構成されています。
🔧 バネピボットの構造図
| パーツ名 | 役割 | 使用する材料の例 |
|---|---|---|
| 土台プレート(下層) | シャーシに固定する基盤 | FRPマルチワイドステー、カーボンマルチ補強プレート |
| 可動プレート(中層) | スプリングを保持し実際に動く部分 | HGカーボンフロントワイドステー、ARシャーシFRPリヤワイドステー |
| 蓋プレート(上層) | スプリングの脱落を防ぐカバー | 土台プレートと同じ材料 |
これら3層を重ね、中央のビスを軸にして可動プレートが左右に動く構造になっています。可動プレートにはH型の穴を開けてスプリングを固定し、そのスプリングが土台プレートと蓋プレートの間に挟まれることで、復元力を生み出します。
可動域はおそらく両側で約4mm、片側で約2mm程度になることが多いようです。この限られた可動域でも、コースからの衝撃を和らげる効果は十分に得られると考えられます。
制作の際の重要なポイントは以下の通りです:
- ✅ スプリングの穴はH型に加工し、中央の突起を大きめに残すことで脱落を防ぐ
- ✅ 左右対称に穴を開けることで、均等な動きを実現する
- ✅ 土台と可動部の間にはスペーサーを入れ、スプリングが土台に当たらないようにする
この基本構造を理解しておけば、様々な材料でバネピボットを作成することができます。次のセクションでは、具体的な材料選びと作り方の手順について詳しく見ていきましょう。
ミニ四駆のバネピボットを実際に作ってみよう
- 必要な材料と工具の準備(治具やプレート選び)
- FRPやカーボンを使ったバネピボットの作り方
- スプリングの固定方法と脱落防止のコツ
- まとめ:ミニ四駆でバネピボットを成功させるポイント
必要な材料と工具の準備(治具やプレート選び)
バネピボットを作るには、適切な材料と工具を揃えることが成功への第一歩です。ここでは実際の製作者が使用している材料を参考に、必要なアイテムをご紹介します。
📦 バネピボット製作に必要な基本材料
| カテゴリ | 具体的なアイテム | 価格目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プレート(土台・蓋) | HG 13・19mmカーボンマルチ補強プレート | 2枚で約1,000円 | FRPマルチワイドステーでも代用可 |
| プレート(可動部) | HGカーボンフロントワイドステー1.5mm | 1枚1,000円 | ARシャーシFRPリヤワイドステーでも可 |
| スプリング | ミニ四駆PROスライドダンパースプリング | 約200円 | 銀色(硬め)が復元力が高い |
| ビス・ナット類 | 9-10mm皿ビス/トラスビス、真鍮スペーサー、ロックナット | – | 2mm穴用が標準 |
| スペーサー | 1.5-3.0mmアルミスペーサー | – | スプリングと土台の接触防止 |
カーボンプレートは2020年頃は需要が逼迫し、定価の倍程度で取引されていたこともあったようですが、HGカーボンフロントワイドステー1.5mmなどは比較的入手しやすい材料とされています。一方で、フルカウル用の品番95から始まる限定商品は高値取引されやすいので注意が必要です。
品番が95から始まる商品は限定商品なので高値で取引されます。対して今回使ったカーボンは15から始まる通常商品なので定価で普通に出回ってます。
🛠️ 必要な工具類
- ✓ ドリル(2mm、5.5mm程度)
- ✓ 6mm面取りカッター(ザグリ加工用)
- ✓ デザインナイフ
- ✓ 棒ヤスリ/小さいダイヤモンドヤスリ
- ✓ リューター(あれば便利)
- ✓ スライドダンパー(寸法の目安として)
治具については、専用の加工治具があると便利ですが、カーボンプレートの模様を利用して目印をつける方法もあります。カーボンプレートはプリズム調の正方形が並んだ模様をしているため、これを1マスとして数えながら目印をつけていけば、比較的正確に左右対称の加工ができるようです。
FRPやカーボンを使ったバネピボットの作り方
ここでは、実際の製作手順を段階的に解説していきます。今回はカーボンプレートを使った方法を基本としますが、FRPでも同様の手順で作成可能です。
🔨 製作手順
ステップ1:プレートのカット
まず、土台用(A)、蓋用(B)、可動部用(C)のプレートを必要なサイズにカットします。タミヤのロゴである2つの☆マークの真ん中あたりを目安にすると良いでしょう。カットする際は、なるべく真っすぐに切ることを心がけてください。
ステップ2:土台と蓋に穴を開ける
土台(A)と蓋(B)を可動部(C)と重ね合わせ、中央の2つの穴を目印にしてビスとナットで仮固定します。そして、可動部の一番外側の穴(2mm)を土台と蓋にも開けていきます。
ステップ3:可動部にスプリング用の穴を加工
これが最も重要な工程です。可動部プレートにH型の長方形の穴を開けます。
📏 スプリング穴の寸法目安
- 縦:約5mm
- 横:約8mm(3マス分が理想、削りすぎると隙間ができる)
- 位置:中央の3つ並んだ穴の隣のラインから外側へ
加工方法としては、5.5mmドリルで長方形の中央に穴を開け、残った四隅を棒ヤスリで少しずつ丁寧に削っていく方法が推奨されています。FRPの強度を残すために大きさを最小限にし、真ん中の突起を大きめに残すことが重要です。
穴加工が終わったら、実際にスプリングが入るかどうか確認してください。ちょうど穴に引っかかるか引っかからないかくらいの絶妙なフィットが理想的です。
ステップ4:蓋プレートの加工
蓋プレート(D)がある場合は、左右対称に切り抜きます。片方を切り取り、それをもう片方に重ね合わせて切り取っていけば左右対称に仕上がります。
ステップ5:組み立て
- 土台プレートの穴にザグリ加工を施す(6mm面取りカッター使用)
- 10mm皿ビスを通し、1.5mmアルミスペーサーを装着
- 可動プレートを重ね、9mmトラスビスを下から差し込む
- 大ワッシャーを重ねる(スプリングが潰れないための高さ調整)
- スプリングを仕込む
- 蓋プレートを重ね、小ワッシャー、ロックナットで固定
完成したバネピボットは、中央のビスを軸に左右に可動するようになります。動きを確認し、スムーズにピボット動作が行えれば成功です。
スプリングの固定方法と脱落防止のコツ
バネピボット製作で最も心配なのが、走行中にスプリングが脱落してしまうことです。ここでは、スプリングをしっかり固定し、脱落を防ぐためのコツをまとめます。
⚠️ スプリング脱落を防ぐ重要ポイント
1. H型の穴加工を正確に
スプリングの固定で最も重要なのは、H型の穴の中央部分の突起を大きめに残すことです。この突起がスプリングのコイルに引っかかり、脱落を防ぐ役割を果たします。
実際の製作者の中には、突起を小さくしすぎて失敗したケースも報告されています。ヤスリで削る際は慎重に、少しずつ削っていくことが大切です。
2. プレートで挟み込む構造
バネピボットは基本的に3層構造(土台・可動部・蓋)になっており、スプリングがカーボンプレートやFRPに挟まれる設計になっています。
隙間からバネが見えてますが、ご覧の通りカーボンプレートに挟まれていますのでナットが緩んで分解でも起こらない限り、バネが抜けることは絶対にありません。
ロックナットでしっかり固定し、分解が起こらないようにすることで、スプリングの脱落リスクを最小限に抑えられます。
3. ワッシャーで高さ調整
大ワッシャーを使用することで、蓋をするときにスプリングが潰れすぎないように高さを調整できます。これはピボットの動きには直接関係しませんが、スプリングに適度な余裕を持たせることで、長期的な耐久性が向上する可能性があります。
4. スプリングの入れ方
FRPを2枚重ねた状態でスプリングを入れようとすると非常に入りにくいため、1枚ずつ入れる方法が推奨されています。細いマイナスドライバーなどを使いながら慎重に入れていきましょう。
入らないからといって穴を大きくしすぎると、スプリングが効かなくなったり脱落しやすくなるため、注意が必要です。
5. 走行後の確認
実際にコースで走らせた後は、スプリングが外れていないか、可動部がスムーズに動いているかを必ず確認してください。初回走行時は特に注意深くチェックすることをおすすめします。
まとめ:ミニ四駆でバネピボットを成功させるポイント
最後に記事のポイントをまとめます。
- バネピボットは、ゴムの代わりにスプリングを使用した耐久性の高いピボットバンパーである
- 主な材料は、カーボンプレートまたはFRPプレート、スライドダンパー用スプリング、各種ビス・ナット類
- 可動部プレートにH型の穴を開け、中央の突起を大きめに残すことが脱落防止の鍵
- スプリングは1枚ずつ慎重に入れ、3層構造(土台・可動部・蓋)で挟み込む
- 2mm穴加工、ザグリ加工、スペーサーの使用など、細かな工作技術が求められる
- カーボンプレートの模様を利用すれば、治具なしでも左右対称の加工が可能
- スプリングの硬さ(銀色が硬め、黒が柔らかめ)で反発力を調整できる
- 可動域は片側約2mm程度だが、衝撃吸収には十分な効果がある
- ゴム式と比べてメンテナンス頻度が大幅に減り、半永久的に使用可能
- 完成後は必ずコースで動作確認し、スプリングの脱落や可動部の動きをチェックする
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- 76 ATバンパーを作ってみたよ【後編】 – ミニ四駆、もう一度始めてみたよ
- バネピボを作ってみよう!!(バネ式ピボットバンパー)【奮闘記・第103走】 – みそじで復活!!ミニ四駆改造奮闘記。
- バネピボ!!構造公開!! | 【DKサーキット】ミニ四駆関連商品販売 オレが最強!
- ミニ四駆!スプリング式ピボット完成です!: だーいのミニ四駆研究室!
- concours d’Elegance/PARTS
各サイト運営者様へ
有益な情報をご公開いただき、誠にありがとうございます。
感謝の意を込め、このリンクはSEO効果がある形で設置させていただいております。
※リンクには nofollow 属性を付与しておりませんので、一定のSEO効果が見込まれるなど、サイト運営者様にとってもメリットとなれば幸いです。
当サイトは、インターネット上に散在する有益な情報を収集し、要約・編集してわかりやすくお届けすることを目的としたメディアです。
私たちは、情報の収集や整理を通じて「情報をまとめてわかりやすく伝える」という形で新たな価値を提供できるのではないかと考え、運営しております。
なお、引用や参照の方法には不備、あるいはご不快に感じられる点がございましたら、迅速に対応いたしますので、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
当ブログをご覧いただきありがとうございます。
このたび、当ブログの記事内容について無断転載とのご指摘を受けました。
事実確認が十分でない部分もありますが、著作権に関わるご迷惑をおかけする可能性を重く受け止め、記事をすべて非公開とし、今後の再確認を進めてまいります。
ご心配・ご不快の念をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後は再発防止に努め、安心してご覧いただけるブログ運営を行ってまいります。